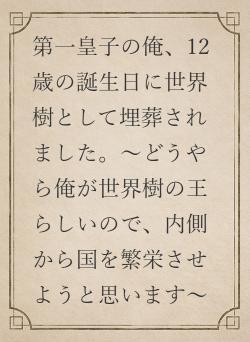「もう、戦ったりはしないのか?」
風呂から上がり、宿へ向かいながらも俺たちの会話は止まらなかった。
「食材調達くらいはするつもりだけど、ダンジョン潜ったりとかそういう予定はないな」
「そうか……。せっかくだからここのダンジョンにでも一緒にと思ったんだが……」
「ああ、そういう話か。そういうのなら問題ないぞ。明日行くか?」
そういえば、ここにきてからもうしばらく経っているが、まだ一度もシローテダンジョンに入ったことがなかった。
まあ、最初はユーリたちに続いて、そこそこの数の探索者が来るかもと思っていたから、魔物の数は減らさない方がいいと考えてのことだったのだが――蓋を開けてみれば、俺の考えは全くの杞憂だった。
「いや、数日後だな。しばらくはこの辺りを詳しく調査してみる予定だ」
「そうか。じゃあ、ダンジョン行く時は誘ってくれよ。ここのダンジョンには十年くらい前に入って以来、まだ入ってないんだ」
「そうなのか……って、十年? ここがお前の旅の始まりというか、原点なのか?」
「いや、そういうわけでもないんだが……まあ、似たようなものかもな」
強さだけを求めていた俺が、人や仲間、そして自分という存在の影響力をよく認識させてくれた大事な場所だ。
原点と言っても、差し支えないだろう。
そんな話をしながら宿に戻ってきた。
「随分と打ち解けられたようですね。憂いは晴れましたか?」
そう言いながら、目線で「良かったな」と語りかけてくるネイロス。
最近までは仇敵だったと言うのに、今となってはもう、大恩人になってしまったな……。
「ああ、ありがとな。背中、押してくれて」
「そうだよ……結局ネイロスさんとお前はどういう関係なんだ? さっきは何か微妙に誤魔化してたみたいだけどよ?」
「おい、ケイル。その話はもういいだろう」
「良くは無いな。ことの次第ではミア王女への報告の仕方まで変わってくる」
ケイルがミアの名前を出すと、ネイロスの表情が少し変わった。
「ケイルさん。よろしければその方のお話をお聞かせいただけないでしょうか?」
「もちろんいいですよ! ファレスとミア王女の昔の話ならいくらでもお聞かせしましょう!」
テーブル席にどっかりと腰を下ろすと、なんでも聞いてくれと言わんばかりに腕をまくってみせるケイル。
ネイロスの言葉は王国民であるにも関わらず、まるでミア王女のことを全く知らないように聞こえたが、ファレスとの再開で気分が高揚していたケイルはその事に気が付かない様子だった。
「おい、ネイロスまで……」
止めようとするも時すでに遅し。
ケイルの正面に腰を下ろしたネイロスはもう質問を始めていた。
「その方、ミア王女とはどんな方なのですか?」
「そうですね、まずミア王女はとてもお綺麗な方です。ネイロスさんもとても美人だと思いますが、ミア王女はまるで女神みたいな方でして……」
「ほう……女神ですか。ますます気になってきました。容姿や性格を詳しく聞いても?」
「ええ、もちろん。最近までは美しく長いホワイトブロンドを靡かせていたのですが……何やら心機一転されたようで今はショートボブ程の長さにされましたね。あの日は王城中に激震が走りましたよ」
ミア、ショートヘアにしたのか……。
一瞬、目付きを険しくしたケイルが俺の事を睨んできたが、なおもケイルは話を続ける。
「性格に関しても素晴らしい、この一言に尽きますね。一度挨拶した騎士の名前は全員覚えていてくださいますし、最近は王政にも積極的に関わられて、今回のこの視察もミア王女の提案で行われたんですよ」
どんどん饒舌になっていくケイル……心なしか顔も赤くなっているような?
「ふむふむなるほど。それで……ファレスさんとの関係は?」
「それはですね〜何とも言えないところではありますが、付かず離れずの距離のままの幼馴染といった感じでしょうか。まあ、六歳の頃から二人を知っている私からすれば、ミア王女の気持ちは確かだと思いますね」
「ほぉう、それでお主はどうなんだファレス?」
「そこで俺に振るのかよ……」
というかネイロス、素の口調が出てるぞ。
あと、酒をよく回るようにする魔法使ってるだろ……ケイルのやつが急にハイテンションすぎるわ。
と、思ったが、ネイロスの正体をばらす訳にもいかないため何とか心の内に留めた。
「さぁ、ファレス答えてみろ!」
あーあーもう、顔真っ赤ですよケイルさん……。
風呂と魔法のダブルパンチで相当キてるみたいだな。
「さぁな……それよりケイル水飲んでさっさと寝た方がいいぞ。相当酒が回ってるみたいだし。あと、ダンカンさんにはくれぐれも俺の正体がバレないように頼むぞ?」
「ちっ。またはぐらかしやがって……。ダンカンのことは気にするな。いくら酔ってもそんなヘマはしねーよ」
「ならいいんだ。うちのベッドは幻妖の羊の羊毛で作ってるからな。滞在期間中に存分に味わっておけよ!」
それを聞いた途端ケイルの顔色が途端に青くなっていく。
ネイロスが魔法の調整を間違えたのかとも思ったが、これは違うか。
「……幻妖の羊だと? それってあの王家御用達とか言う?」
「ああ、それだよ。よかったな王族体験だぞ?」
やはり、幻妖の羊に対しての顔色だったようだ。
さっきのお返しにちょっといじってやろう。
「……お前の金銭感覚どうなってんだよ! 幻妖の羊のベッドなんて俺の給料半年分で買えるかどうかってもんだぞ!?」
「そりゃ買えばそうだろうけど、俺の場合は幻妖の羊を狩って作ってもらうだけだからそこまではしない」
「くっ……そういえばこいつ勇者だった……」
淡々と言い放つ俺に悔しげな顔を浮かべながら、ケイルは背を向けた。
「じゃあ、寝るわ。また明日な」
「おう」
「おやすみなさいませ」
いつの間にか口調を戻したネイロスと共にケイルを見送り、騒がしい夜は幕を閉じた。
◇◇◇
諸々の後片付けは俺が風呂に行っている間にネイロスが済ませておいてくれたようで、あとはもう寝るだけだった。
「ネイロス、ほんとに色々とありがとう。お前が来てくれて良かったと心から思うよ」
酒のおかげか、ケイルとの再会で俺も饒舌になっていたのか、そんな言葉が軽々と口を出た。
「唐突になんだ? さすがの妾もそこまでまっすぐ来られると照れるのだがな……」
珍しく頬を薄く染めながら呟くネイロス。
ネイロスとの生活を始めてそれなりの時間が経っていると言うのに、まだまだ全然彼女のことを知らないと、この表情を見て思った。
まぁそれはお互い様な部分もあるだろうし、どうせ長い付き合いになりそうだから追々知って行けばいいか。
そんなことを考えながらネイロスのことを見ていると、髪の艶がいつもより褪せているような気がした。
「あ、そうだ。ネイロスお前も風呂入ってこいよ。初の接客で疲れただろうに気が回らなくてすまんな」
あまりにも自然な溶け込みで失念していたが、ネイロスは今日が初めての接客だったのだ。
どんなことであれ、初めてというのは疲れるものだ。
せっかくゆっくり出来る風呂もある事だし、今日は十分に休んで欲しい。
「うむ、ならばファレスに背中を流してもらうとするか」
「いや、それはちょっと……」
そう思っての提案だったが、好機訪れたり! と言わんばかりに、にやりと音が聞こえそうな顔でそう言うネイロス。
「妾、初めての仕事を終えた従業員を労うのも店主の役割ではないのか?」
まあ、確かに世話になりっぱなしではあるのだが……さすがになぁ。
でも、なるべくネイロスの頼みは叶えてやりたいという気持ちも同時に確かだった。
「……今日はケイルたちもいるから勘弁してくれ。また、宿泊客が来なくなったらその時は背中を流すくらいはいいぞ、やってやろう」
悩んだ末、別に背中を流してやるくらいは俺が折れるべきだろうと判断してそう答えた。
「なんと! まさか許可が出るとは思わなかったぞ!」
するとネイロスは驚き七割喜び三割と言ったような、またも見たことのない顔をしてそう言ってきた。
「ダメ元だったのかよ……」
「ファレス、お主が言ったのだからな? 発言の責任はとってもらうぞ?」
「わかったよ。男に二言はない」
「うむ! 今日のところはそれで満足するとしよう。では風呂に行ってくるが、先に寝るでないぞ? 今日はまだ話し足りないからな!」
なんだ? 急に。寝ていたら顔を踏んで起こしてくる猫みたいなことを言って……。
いや、これもネイロスの新しい一面ってことか。
「わかったよ。でも、明日も早いんだからあんまり長風呂するなよ?」
「むろん、分かっているぞ!」
ドタバタと騒々しい足音を立てて風呂へ走っていくネイロス。
「最近は猫ってより犬っぽい気がしてきたな、あいつ」
黒猫の姿でネイロスがここを訪れた日を懐かしく感じながら、そんなことを思う俺だった。
◇◇◇
就寝の準備を終え、布団に入って待とうと思っていたところに丁度ネイロスが戻って来た。
「ファレス! まだ寝ておらぬな?」
「寝てないよ……ってネイロス、髪くらい乾かしてこいよ。俺たちの魔法なら一瞬だろ?」
「ぬ、忘れておったわ! お主が寝てしまうかもしれぬと思ってな」
「いやいや、約束したからには守るぞ? まあ、良いや」
魔法で温風と冷風を順番に生み出し、ネイロスの髪にそれぞれを当てる。
「うむ、気が利くではないか!」
気分の良さそうな顔でネイロスはご満悦の様子だ。
「それで、何か話したいことでもあったのか?」
「いや? 別にそういう訳ではないぞ?」
「ただいつも通り、駄弁りたかったってことか」
「うむ、妾の接客姿の感想も聞きたかったしな」
まあ、確かにここにネイロスが来てからは基本ずっと二人だったからな。
今日は口調も態度も完全に別人な接客モードだったし、喋り足りないという気持ちは分からなくはない。
「接客姿については正直、想像以上だった。ケイルたちもどこかのご令嬢かと勘違いしていたぞ」
「そうだろう、そうだろう! 魔族には人間のような身分の階級などはないが、その代わりに力がものを言う。妾も最初から魔王であったわけではないからな。昔はああして物腰を低くしていたものよ!」
なるほど……経験があったのか。
道理で妙に堂に入っているように見えたわけだ。
「そう言えばネイロスはいつごろから魔王だったんだ?」
ふとそんなことが気になった。
人類から見た魔王の情報はどれも不確かなものばかり、今となってはあまり関係ないが、興味はあることだ。
「む? それは妾に年齢を聞いているのか?」
「あ、いや、そういう訳ではないけど……」
言われてみればそういうネイロスのプライベートもあまり知らないな……とも思ったが、女性の前で年齢の話は避けるべきと思い言葉を濁した。
「ふふっ、冗談だ。そうだな……ファレス、前に魔王の記憶の話をしたことを覚えているか?」
「ああ、確かネイロスは〈存在しない記憶〉を乗り越えて前魔王の記憶を持っていたんだよな?」
「うむ、その通りだ。だが、記憶を持つ者が必ず魔王になるという訳でもない。周りは覚えていないのだから、はっきりとした記憶でも、いつの間にか何かの思い込みや勘違いだと思うようになる者もいるのだ。だから実質的な魔王でなくとも、力の強い魔族が魔王のように振舞うこともあるのだ」
「ほう……でも、それとネイロスの魔王歴とに何の関係が?」
「そう結論を急ぐな。この話が面白いのはここからなのだ! そして、そんな魔王ではないが力の強い魔族が王のように振舞っていた時代、それがちょうど十一年ほど前までだ」
「十一年前?」
「うむ、そして妾がそれを打倒し、本物の魔王として君臨したという訳だ! つまり魔王歴は十年だな! 奇しくもお主の勇者歴と同じだな」
「なるほど……それは確かに奇妙な縁だな。まあ、俺とお前が今一緒に居るのもそういう不思議な縁の繋がりなのかもな」
「ふふっ、そうかもしれぬな。だが、他に一つとない希少な縁だ。この縁の相手がお主で良かったと思うぞ」
「なんだよ急に」
「先ほど妾を照れさせたお返しだ」
どうやら意外と本気で照れさせてしまっていたようだ。
でもまあ、素直に感情を示すことは悪いことじゃない。
ケイルの涙にしろ、本心をさらけ出すというのはそれだけの信用がなければできないことだ。
「……ま、それについてはさっきも言ったが俺も同じように思っているからな」
とは言え、この妙に気恥しくなる空気間はどうにかならないものだろうか。
………………
………………
………………
「……んんっ、魔王でなくとも、力の強い魔族が王のように君臨するなら魔王を倒してもあまり意味がなくないか?」
微妙な空気間に耐え切れなくなり、強引に話を変えた。
魔王討伐は人類に語り継がれる伝説であり、悲願でもあるわけだが、そう言えばどうして魔王を倒せば良いという考えになっているのだろうか?
「それはまあ、その通りだな。人間だって王が殺されたところで次の王を擁立するであろう? とはいえ、話した通り魔族の社会構造は人とは違うからな。立て直しにかかる時間は人間の比ではない。だから意味がないことはないな」
「言われてみればそうだよな……まあ、俺たちにはもう、関係のない話か」
気になって聞いてみたが、もう俺は勇者ではない。
少し気になる自分もいるが、積極的に気にしていては引退した意味がないだろう。
「うむ、今お主が考えるべきことは、妾とここで少しでも長い時を生きるために魔族と同じくらい長生きをする方法だ!」
「それは……。まあ、俺は魔王討伐をした史上二人目の人間だからな。魔族と同じだけ長生きをした史上一人目の人間になるのを次の目標にするのも悪くないか」
いつもより少し長めの夜更かしをして、いつの間にか俺たちは眠りに落ちていた。
また一つ、心残りの減った今日はいつもよりさらに寝心地の良い夜だった。
風呂から上がり、宿へ向かいながらも俺たちの会話は止まらなかった。
「食材調達くらいはするつもりだけど、ダンジョン潜ったりとかそういう予定はないな」
「そうか……。せっかくだからここのダンジョンにでも一緒にと思ったんだが……」
「ああ、そういう話か。そういうのなら問題ないぞ。明日行くか?」
そういえば、ここにきてからもうしばらく経っているが、まだ一度もシローテダンジョンに入ったことがなかった。
まあ、最初はユーリたちに続いて、そこそこの数の探索者が来るかもと思っていたから、魔物の数は減らさない方がいいと考えてのことだったのだが――蓋を開けてみれば、俺の考えは全くの杞憂だった。
「いや、数日後だな。しばらくはこの辺りを詳しく調査してみる予定だ」
「そうか。じゃあ、ダンジョン行く時は誘ってくれよ。ここのダンジョンには十年くらい前に入って以来、まだ入ってないんだ」
「そうなのか……って、十年? ここがお前の旅の始まりというか、原点なのか?」
「いや、そういうわけでもないんだが……まあ、似たようなものかもな」
強さだけを求めていた俺が、人や仲間、そして自分という存在の影響力をよく認識させてくれた大事な場所だ。
原点と言っても、差し支えないだろう。
そんな話をしながら宿に戻ってきた。
「随分と打ち解けられたようですね。憂いは晴れましたか?」
そう言いながら、目線で「良かったな」と語りかけてくるネイロス。
最近までは仇敵だったと言うのに、今となってはもう、大恩人になってしまったな……。
「ああ、ありがとな。背中、押してくれて」
「そうだよ……結局ネイロスさんとお前はどういう関係なんだ? さっきは何か微妙に誤魔化してたみたいだけどよ?」
「おい、ケイル。その話はもういいだろう」
「良くは無いな。ことの次第ではミア王女への報告の仕方まで変わってくる」
ケイルがミアの名前を出すと、ネイロスの表情が少し変わった。
「ケイルさん。よろしければその方のお話をお聞かせいただけないでしょうか?」
「もちろんいいですよ! ファレスとミア王女の昔の話ならいくらでもお聞かせしましょう!」
テーブル席にどっかりと腰を下ろすと、なんでも聞いてくれと言わんばかりに腕をまくってみせるケイル。
ネイロスの言葉は王国民であるにも関わらず、まるでミア王女のことを全く知らないように聞こえたが、ファレスとの再開で気分が高揚していたケイルはその事に気が付かない様子だった。
「おい、ネイロスまで……」
止めようとするも時すでに遅し。
ケイルの正面に腰を下ろしたネイロスはもう質問を始めていた。
「その方、ミア王女とはどんな方なのですか?」
「そうですね、まずミア王女はとてもお綺麗な方です。ネイロスさんもとても美人だと思いますが、ミア王女はまるで女神みたいな方でして……」
「ほう……女神ですか。ますます気になってきました。容姿や性格を詳しく聞いても?」
「ええ、もちろん。最近までは美しく長いホワイトブロンドを靡かせていたのですが……何やら心機一転されたようで今はショートボブ程の長さにされましたね。あの日は王城中に激震が走りましたよ」
ミア、ショートヘアにしたのか……。
一瞬、目付きを険しくしたケイルが俺の事を睨んできたが、なおもケイルは話を続ける。
「性格に関しても素晴らしい、この一言に尽きますね。一度挨拶した騎士の名前は全員覚えていてくださいますし、最近は王政にも積極的に関わられて、今回のこの視察もミア王女の提案で行われたんですよ」
どんどん饒舌になっていくケイル……心なしか顔も赤くなっているような?
「ふむふむなるほど。それで……ファレスさんとの関係は?」
「それはですね〜何とも言えないところではありますが、付かず離れずの距離のままの幼馴染といった感じでしょうか。まあ、六歳の頃から二人を知っている私からすれば、ミア王女の気持ちは確かだと思いますね」
「ほぉう、それでお主はどうなんだファレス?」
「そこで俺に振るのかよ……」
というかネイロス、素の口調が出てるぞ。
あと、酒をよく回るようにする魔法使ってるだろ……ケイルのやつが急にハイテンションすぎるわ。
と、思ったが、ネイロスの正体をばらす訳にもいかないため何とか心の内に留めた。
「さぁ、ファレス答えてみろ!」
あーあーもう、顔真っ赤ですよケイルさん……。
風呂と魔法のダブルパンチで相当キてるみたいだな。
「さぁな……それよりケイル水飲んでさっさと寝た方がいいぞ。相当酒が回ってるみたいだし。あと、ダンカンさんにはくれぐれも俺の正体がバレないように頼むぞ?」
「ちっ。またはぐらかしやがって……。ダンカンのことは気にするな。いくら酔ってもそんなヘマはしねーよ」
「ならいいんだ。うちのベッドは幻妖の羊の羊毛で作ってるからな。滞在期間中に存分に味わっておけよ!」
それを聞いた途端ケイルの顔色が途端に青くなっていく。
ネイロスが魔法の調整を間違えたのかとも思ったが、これは違うか。
「……幻妖の羊だと? それってあの王家御用達とか言う?」
「ああ、それだよ。よかったな王族体験だぞ?」
やはり、幻妖の羊に対しての顔色だったようだ。
さっきのお返しにちょっといじってやろう。
「……お前の金銭感覚どうなってんだよ! 幻妖の羊のベッドなんて俺の給料半年分で買えるかどうかってもんだぞ!?」
「そりゃ買えばそうだろうけど、俺の場合は幻妖の羊を狩って作ってもらうだけだからそこまではしない」
「くっ……そういえばこいつ勇者だった……」
淡々と言い放つ俺に悔しげな顔を浮かべながら、ケイルは背を向けた。
「じゃあ、寝るわ。また明日な」
「おう」
「おやすみなさいませ」
いつの間にか口調を戻したネイロスと共にケイルを見送り、騒がしい夜は幕を閉じた。
◇◇◇
諸々の後片付けは俺が風呂に行っている間にネイロスが済ませておいてくれたようで、あとはもう寝るだけだった。
「ネイロス、ほんとに色々とありがとう。お前が来てくれて良かったと心から思うよ」
酒のおかげか、ケイルとの再会で俺も饒舌になっていたのか、そんな言葉が軽々と口を出た。
「唐突になんだ? さすがの妾もそこまでまっすぐ来られると照れるのだがな……」
珍しく頬を薄く染めながら呟くネイロス。
ネイロスとの生活を始めてそれなりの時間が経っていると言うのに、まだまだ全然彼女のことを知らないと、この表情を見て思った。
まぁそれはお互い様な部分もあるだろうし、どうせ長い付き合いになりそうだから追々知って行けばいいか。
そんなことを考えながらネイロスのことを見ていると、髪の艶がいつもより褪せているような気がした。
「あ、そうだ。ネイロスお前も風呂入ってこいよ。初の接客で疲れただろうに気が回らなくてすまんな」
あまりにも自然な溶け込みで失念していたが、ネイロスは今日が初めての接客だったのだ。
どんなことであれ、初めてというのは疲れるものだ。
せっかくゆっくり出来る風呂もある事だし、今日は十分に休んで欲しい。
「うむ、ならばファレスに背中を流してもらうとするか」
「いや、それはちょっと……」
そう思っての提案だったが、好機訪れたり! と言わんばかりに、にやりと音が聞こえそうな顔でそう言うネイロス。
「妾、初めての仕事を終えた従業員を労うのも店主の役割ではないのか?」
まあ、確かに世話になりっぱなしではあるのだが……さすがになぁ。
でも、なるべくネイロスの頼みは叶えてやりたいという気持ちも同時に確かだった。
「……今日はケイルたちもいるから勘弁してくれ。また、宿泊客が来なくなったらその時は背中を流すくらいはいいぞ、やってやろう」
悩んだ末、別に背中を流してやるくらいは俺が折れるべきだろうと判断してそう答えた。
「なんと! まさか許可が出るとは思わなかったぞ!」
するとネイロスは驚き七割喜び三割と言ったような、またも見たことのない顔をしてそう言ってきた。
「ダメ元だったのかよ……」
「ファレス、お主が言ったのだからな? 発言の責任はとってもらうぞ?」
「わかったよ。男に二言はない」
「うむ! 今日のところはそれで満足するとしよう。では風呂に行ってくるが、先に寝るでないぞ? 今日はまだ話し足りないからな!」
なんだ? 急に。寝ていたら顔を踏んで起こしてくる猫みたいなことを言って……。
いや、これもネイロスの新しい一面ってことか。
「わかったよ。でも、明日も早いんだからあんまり長風呂するなよ?」
「むろん、分かっているぞ!」
ドタバタと騒々しい足音を立てて風呂へ走っていくネイロス。
「最近は猫ってより犬っぽい気がしてきたな、あいつ」
黒猫の姿でネイロスがここを訪れた日を懐かしく感じながら、そんなことを思う俺だった。
◇◇◇
就寝の準備を終え、布団に入って待とうと思っていたところに丁度ネイロスが戻って来た。
「ファレス! まだ寝ておらぬな?」
「寝てないよ……ってネイロス、髪くらい乾かしてこいよ。俺たちの魔法なら一瞬だろ?」
「ぬ、忘れておったわ! お主が寝てしまうかもしれぬと思ってな」
「いやいや、約束したからには守るぞ? まあ、良いや」
魔法で温風と冷風を順番に生み出し、ネイロスの髪にそれぞれを当てる。
「うむ、気が利くではないか!」
気分の良さそうな顔でネイロスはご満悦の様子だ。
「それで、何か話したいことでもあったのか?」
「いや? 別にそういう訳ではないぞ?」
「ただいつも通り、駄弁りたかったってことか」
「うむ、妾の接客姿の感想も聞きたかったしな」
まあ、確かにここにネイロスが来てからは基本ずっと二人だったからな。
今日は口調も態度も完全に別人な接客モードだったし、喋り足りないという気持ちは分からなくはない。
「接客姿については正直、想像以上だった。ケイルたちもどこかのご令嬢かと勘違いしていたぞ」
「そうだろう、そうだろう! 魔族には人間のような身分の階級などはないが、その代わりに力がものを言う。妾も最初から魔王であったわけではないからな。昔はああして物腰を低くしていたものよ!」
なるほど……経験があったのか。
道理で妙に堂に入っているように見えたわけだ。
「そう言えばネイロスはいつごろから魔王だったんだ?」
ふとそんなことが気になった。
人類から見た魔王の情報はどれも不確かなものばかり、今となってはあまり関係ないが、興味はあることだ。
「む? それは妾に年齢を聞いているのか?」
「あ、いや、そういう訳ではないけど……」
言われてみればそういうネイロスのプライベートもあまり知らないな……とも思ったが、女性の前で年齢の話は避けるべきと思い言葉を濁した。
「ふふっ、冗談だ。そうだな……ファレス、前に魔王の記憶の話をしたことを覚えているか?」
「ああ、確かネイロスは〈存在しない記憶〉を乗り越えて前魔王の記憶を持っていたんだよな?」
「うむ、その通りだ。だが、記憶を持つ者が必ず魔王になるという訳でもない。周りは覚えていないのだから、はっきりとした記憶でも、いつの間にか何かの思い込みや勘違いだと思うようになる者もいるのだ。だから実質的な魔王でなくとも、力の強い魔族が魔王のように振舞うこともあるのだ」
「ほう……でも、それとネイロスの魔王歴とに何の関係が?」
「そう結論を急ぐな。この話が面白いのはここからなのだ! そして、そんな魔王ではないが力の強い魔族が王のように振舞っていた時代、それがちょうど十一年ほど前までだ」
「十一年前?」
「うむ、そして妾がそれを打倒し、本物の魔王として君臨したという訳だ! つまり魔王歴は十年だな! 奇しくもお主の勇者歴と同じだな」
「なるほど……それは確かに奇妙な縁だな。まあ、俺とお前が今一緒に居るのもそういう不思議な縁の繋がりなのかもな」
「ふふっ、そうかもしれぬな。だが、他に一つとない希少な縁だ。この縁の相手がお主で良かったと思うぞ」
「なんだよ急に」
「先ほど妾を照れさせたお返しだ」
どうやら意外と本気で照れさせてしまっていたようだ。
でもまあ、素直に感情を示すことは悪いことじゃない。
ケイルの涙にしろ、本心をさらけ出すというのはそれだけの信用がなければできないことだ。
「……ま、それについてはさっきも言ったが俺も同じように思っているからな」
とは言え、この妙に気恥しくなる空気間はどうにかならないものだろうか。
………………
………………
………………
「……んんっ、魔王でなくとも、力の強い魔族が王のように君臨するなら魔王を倒してもあまり意味がなくないか?」
微妙な空気間に耐え切れなくなり、強引に話を変えた。
魔王討伐は人類に語り継がれる伝説であり、悲願でもあるわけだが、そう言えばどうして魔王を倒せば良いという考えになっているのだろうか?
「それはまあ、その通りだな。人間だって王が殺されたところで次の王を擁立するであろう? とはいえ、話した通り魔族の社会構造は人とは違うからな。立て直しにかかる時間は人間の比ではない。だから意味がないことはないな」
「言われてみればそうだよな……まあ、俺たちにはもう、関係のない話か」
気になって聞いてみたが、もう俺は勇者ではない。
少し気になる自分もいるが、積極的に気にしていては引退した意味がないだろう。
「うむ、今お主が考えるべきことは、妾とここで少しでも長い時を生きるために魔族と同じくらい長生きをする方法だ!」
「それは……。まあ、俺は魔王討伐をした史上二人目の人間だからな。魔族と同じだけ長生きをした史上一人目の人間になるのを次の目標にするのも悪くないか」
いつもより少し長めの夜更かしをして、いつの間にか俺たちは眠りに落ちていた。
また一つ、心残りの減った今日はいつもよりさらに寝心地の良い夜だった。