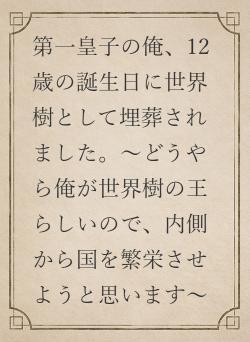「良いのか?」
ケイルを風呂へ案内した後、再び二人だけになった宿の一階でネイロスがそう聞いてきた。
「? 何がだ?」
「分からないふりをしても無駄だぞ? ファレスお主、後悔しているのだろう?」
「――!」
ネイロスの言葉はぐうの音がないほどその通りだった。
はじめは誰の記憶にも残らない完全な引退を望み、だと言うのにミアに覚えていてもらえると分かった途端、何故か気分が軽くなった。
ここに来てガダル爺さんやユーリ、アメリと出会い、俺のことは覚えていなくてもその記憶に俺の影がいることを感じた。
そして王国民ではないため俺のことを覚えていたネイロスとも再開し、この地でともに生きていくと決めた。
「記憶に残らない完全な引退。多くを背負う者からすれば、非常に甘く、魅惑的な言葉だろう。だがな、人も魔族もすべからく他人の中で生きているのだ。この世界は決して、それを忘れさせない。これは魔法ではどうすることもできないことなのだ。たとえ思いだせなくとも、その時間は、感覚はなかったことにはならない」
「ああ、そうだな。……だが」
「だが、なんだ?」
鋭い切り替えし、だが、その言葉からは出来の悪い教え子に何かを気づかせようとするような温かみが含まれていた。
「あえて聞くぞ? ファレス、お主を勇者としていたのは誰だ?」
「……俺、自身か?」
「うむ、そうだ。だが、それでは完璧な答えではない」
そう言うとネイロスは間を置かずに続ける。
「お主を勇者としていたのは他人なのだ。特に関わりがなくとも、お主を勇者として認識していた者たち。それがお主を勇者としていたもう半分だ」
「……そうか。けどそれが何だって言うんだ?」
「まだ、分からぬか? ならばはっきりと言おう。お主をファレスとして認識していた者にまで忘れたままでいてもらう必要はあるのか?」
「――っ!」
今の俺にはあまりにも重く突き刺さる言葉だった。
「大切な者にまで、忘れていてもらう必要はあるのか?」
真摯な眼差しでそう問いかけるネイロス。
「だが、どうすれば? ……これが綻びになったりはしないのか?」
ほぼ、苦し紛れに出た言葉だった。
否定のできない真っ直ぐなネイロスの言葉からの逃げ道を探すような、情けない言葉。
勇者だった頃なら、失望されることを恐れて口にすら出来なかったような、そんな言葉。
しかし、そんな俺をも見越していたかのように、カラッと笑ってネイロスは言い放った。
「妾を誰だと思っている? 無論、解除魔法を作ることなぞ、造作もない」
そして、宙をなぞりながら魔法言語で何かを唱え始めた。
その呪文のような何かは、今までどんな魔法でも一度見れば使うことのできた俺ですら全く理解できないような物だった。
「ふむ、こんなところか。ファレスよ、この魔法をお主に授けよう」
「この魔法って……まさか!? 今、この場で魔法を作り出したのか!?」
「なに、別段おかしなことでもないだろう? 魔法は魔族の生み出した法術。そんな魔族の頭目ともなれば、魔法の一つや二つ即興でも作れる」
そうは言いつつも誇らしげに胸を張るネイロス。
気分が良いのか、いつもよりさらに饒舌に彼女は続ける。
「この魔法はそうだな〈真実の発露〉とでも呼ぶとするか。効果はその名の通り、対象の肉体や精神に眠る記憶を呼び覚ますものだ」
「つまり、この魔法は〈存在しない記憶〉の完全な対抗魔法ってことか?」
「うむ、そういうことだ。さぁ、お主ならば試し打ちの必要も無いだろう? 行って参れ! どうせなら風呂で文字通りの裸の心をぶつけて来い!」
「ネイロス……」
そう言って俺の背中を押してくれるネイロスに、改めてその存在の大きさを感じさせられた。
「ありがとう、ちょっと行ってくる」
「うむ、のぼせるなよ」
ネイロスの言葉を背に受けながら、俺は覚悟を決めた。
そうだ。俺はもう勇者じゃない。勇者であったことに縛られる必要は無いんだ。
情けない葛藤やつまらない責任感はすっかりと俺の中から消えていた。
◇◇◇
「こんな風呂が……これももしかして自作なのか? ファレスさん、本当に底が知れないな」
入浴場へやってきたケイルは想像以上の広さと綺麗さの風呂に感心していた。
「これは戻ったらミア王女に感謝しなければな。まさか任務先でこんなに優雅な生活を体験できるとは」
そう呟きながら、他の隊員には迂闊に話せないとも思った。
更衣室でサッと服を脱ぐとついに風呂へ足を踏み入れる。
すぐに浴槽に近づき、お湯に手をつけた。
「おお! これは芯まで温まりそうだ。では、早速」
備え付けの桶で湯を掬い、足先から温度に慣らしたあと、ケイルは湯船に浸かった。
「ふぅ……。癒されるな。あのベッドも格別だったが、ここはまた違った心地良さがある」
長旅で張った筋肉がほぐれていく。
このお湯に何か効能でもあるのだろうか?
水音だけの静かな空間でケイルは物思いに耽った。
少しして、入浴場の扉を開くような音がした。
「ん? ダンカンか? あいつ寝るとか言っていたくせに」
先程は散々いじられたため小言でも言ってやろうかと、そう思ってケイルが振り返った先にいたのは、宿の店主ファレスだった。
◇◇◇
ネイロスに背中を押された俺は迷いなく、ケイルのいる風呂までやってきた。
「失礼……いや、一緒にいいか? ケイル」
俺はあえて、魔法を使う前に昔の口調でケイルを呼んだ。
「……ファレスさん? 構いませんが……」
突然の態度の変わりように若干困惑した様子のケイル。
だが、それに構わず俺もケイルのいる浴槽まで歩いた。
「湯加減はいいか?」
「え、ええ。とても気持ち良いです。ありがとうございます」
「それならよかった……昔もたまに、一緒に水浴びしたよな」
「昔? 一緒に? 一体なんの話し……うっ」
ケイルが突然頭を抑えるような仕草をした。
「……何か、……なんだこの違和感は」
そしてケイルは喉元まで出かかって、どうしても出てこないと言うようなもどかしそうな表情を浮かべる。
「すまないケイル。俺の勝手で忘れさせて、こうしてまた勝手をすることになって……」
「ファレス……さん? 一体何を?」
苦悶の表情を見せながら俺を見るケイルに謝罪をしながら、先程ネイロスに貰ったばかりの魔法を発動した。
「〈真実の発露〉」
俺の指先から輝く虹色の雫が一滴、ケイルに向かって落ちていく。
「……これは一体?」
そして一瞬、ケイルの視線が明後日の方向へ飛び、再び俺を視界に捉えた。
「すまなかったケイル」
その言葉を聞いた途端、ケイルの脳内で覆い隠されていた記憶の数々が次々に蘇った。
「………………お前、なんだよな? ファレス」
そこにいるケイルは俺のよく知る、いい兄貴分のケイルだった。
「ああ、演説の日ぶりだな」
「……お前っ!」
ケイルは湯船から立ち上がり、俺の肩を掴んで叫ぶように言い放った。
「どういうつもりだ! 帰ってきた途端、俺たちの前から姿を消しやがって! 俺は……俺たちはまたお前と……」
広いとは言っても音のこもる風呂にケイルの慟哭がこだまする。
どうやらこの魔法の効果はただ記憶を呼び起こすだけではなく、俺が居ないことになっていた間の記憶との錯誤も解消してくれるものだったようだ。
本当にネイロスには頭が上がらないな。
「すまなかった」
こうやって違うことを考えなければ、俺は目の前のケイルにつられて涙を流してしまいそうだった。
「くそっ! もう四十近いってのに……くそっ」
もう逃がさないと言わんばかりに、俺の肩を掴んだままケイルの涙は次々に波紋を作った。
「全部話すよ。とりあえず……座ろうぜ」
掴まれた肩に懐かしい馬鹿力を感じて、思わず涙声になりかけた声を何とか抑えると、俺も湯船に入り、ケイルの隣へ腰を下ろす。
「……なんで? とは聞かねえよ。でも一言くらい言ってくれても良かっただろ」
ケイルは鼻をすすり、そう呟く。
「ああ、そうだな。でも、決心が鈍るような気がして、な」
俺はケイルの方は見ずに答えた。
「ミア王女は? まさか俺たちと同じ扱いなんじゃないだろうな?」
「……ミアは知ってる。偶然だったけどな」
俺は右手の指輪をケイルに見せる。
「その指輪……そういえばミア様がよく眺めてたな。……そんな物まで受け取っておきながらお前は!」
「それについては……何も言い返せないな」
「戻ったら、ファレスが美人と宿を経営してましたってチクッといてやるからな」
「なっ!? それはちょっと待ってくれよ!」
「はっ、自業自得だな。……でも」
ケイルはそこで一度言葉を区切ると、大きく深呼吸をしてからこう言った。
「ほんと、お前が死んでなくて良かった」
「な、突然話しを……戻すなよ」
不意に大真面目な表情で心から安堵したという視線を向けられ、一度は引っ込んだ俺の涙が荒れ狂う波の如く押し寄せてきた。
「いい歳した兄貴分を散々泣かせた罰だ。ミア王女への土産話を思う存分作ってやる!」
ひとしきり泣きあった後、ケイルが色々と質問をしてきた。
「なんでここで宿を始めることにしたんだ?」
「ここは……俺のせいで無くなった村なんだ。だからその贖罪かな……いい所だって言うのはもちろんあるけど。あとはさっき宿の方で答えた通りさ」
「……そうか。詳しくは聞かねえよ。けど今はやりたいことがやれてるんだな?」
「ああ、客は少ないが毎日充実してるよ」
「なら良いんだ。……そういえばミア王女はお前のこと知ってるって言ってたけど、この場所も知ってるのか?」
「いや、ここのことは言ってない。だからケイルとここで会えたのも完全な偶然だ」
「そりゃすげえな。これが女の勘ってやつなのか? 浮気してるファレスを裁いて来いって」
確かにミアの指示でケイルがここに来たのは運以上の何かが働いていそうだ。だが、浮気云々は誤解すぎる。
「おい、言いがかりだ! ミアもネイロスも別にそう言う相手じゃない」
「ほ〜う、ファレスくん? ここでの発言は全てミア王女に伝わると分かっているのかい? 俺たちは王女の目となり耳となるためにここに来ているんだぞ?」
「なっ! ケイル、お前そんなやつじゃなかっただろ!」
「はっ! 十年も会わなきゃこんなもんだろ!」
まるで十年以上前から変わらないやり取り。
ああ、どうして俺はこんな大切な物まで消してしまおうと思ったのか。
精神の摩耗と言うのは、魔王なんかよりもよっぽど脅威的だ。
「それより、だ。結局あのネイロスさんはどこで拾ってきたんだ?」
「え、ああ……あいつは……迷い猫みたいなもんだ」
いくらケイルとは言え、嘘でもネイロスが元魔王だとは言う訳にはいかず、咄嗟にそんな言葉が口をついた。
「はぁ? 迷い猫? それで懐かれたとでも?」
「……まあ、そんなところだな」
「あの感じ……どう見ても普通の町娘って感じじゃなかったけど、どっかの貴族様のご令嬢、とかじゃないだろうな? 嫌だぞ? 裁判所で誘拐の罪に問われるお前を見るのは」
「違うわっ! あいつはまあ……なんと言うか、同士みたいなものなんだよ。今日こうやってケイルと話せてるのも、あいつのおかげなんだ」
「ほ〜う、それは感謝しなきゃだな」
「ああ、あいつも今や、ミアやケイルたちと同じくらい大切なんだ」
「……なんだよ。そんな風に言われちゃ、からかいにくいじゃねえか」
「おまっ……まだからかう気だったのかよ!」
親友……いや、家族も同然の二人はこうして絆を取り戻した。
騒がしい夜はさらに更けていく。
そんな様子を満足気な表情で聞いている元魔王。
「大切……か。妾が負けた理由はもしかすると、そこにあったのかもしれぬな」
ファレスには彼を勇者としてではなく、ファレスとして接してくれる人たちがいた。一度は離れても帰る場所があった。
それに比べネイロスには、自分を魔王としてではなくネイロスとして接してくれるような存在はいなかった。
少なくとも、今までは。
「ファレス、お主は妾に感謝をしてくれているようだが、それは妾も同じなのだ。本当に……」
ネイロスにとってファレスはファレスだが、魔王にとってのファレスは紛れもなく勇者であり、光であった。
「お主の代の魔王で在れて良かったと、心から思っているぞ」
ファレスが脱いでいったエプロンをたたみながら、にぎやかな夜に落とされたしっとりとした色は静かに消えていった。
ケイルを風呂へ案内した後、再び二人だけになった宿の一階でネイロスがそう聞いてきた。
「? 何がだ?」
「分からないふりをしても無駄だぞ? ファレスお主、後悔しているのだろう?」
「――!」
ネイロスの言葉はぐうの音がないほどその通りだった。
はじめは誰の記憶にも残らない完全な引退を望み、だと言うのにミアに覚えていてもらえると分かった途端、何故か気分が軽くなった。
ここに来てガダル爺さんやユーリ、アメリと出会い、俺のことは覚えていなくてもその記憶に俺の影がいることを感じた。
そして王国民ではないため俺のことを覚えていたネイロスとも再開し、この地でともに生きていくと決めた。
「記憶に残らない完全な引退。多くを背負う者からすれば、非常に甘く、魅惑的な言葉だろう。だがな、人も魔族もすべからく他人の中で生きているのだ。この世界は決して、それを忘れさせない。これは魔法ではどうすることもできないことなのだ。たとえ思いだせなくとも、その時間は、感覚はなかったことにはならない」
「ああ、そうだな。……だが」
「だが、なんだ?」
鋭い切り替えし、だが、その言葉からは出来の悪い教え子に何かを気づかせようとするような温かみが含まれていた。
「あえて聞くぞ? ファレス、お主を勇者としていたのは誰だ?」
「……俺、自身か?」
「うむ、そうだ。だが、それでは完璧な答えではない」
そう言うとネイロスは間を置かずに続ける。
「お主を勇者としていたのは他人なのだ。特に関わりがなくとも、お主を勇者として認識していた者たち。それがお主を勇者としていたもう半分だ」
「……そうか。けどそれが何だって言うんだ?」
「まだ、分からぬか? ならばはっきりと言おう。お主をファレスとして認識していた者にまで忘れたままでいてもらう必要はあるのか?」
「――っ!」
今の俺にはあまりにも重く突き刺さる言葉だった。
「大切な者にまで、忘れていてもらう必要はあるのか?」
真摯な眼差しでそう問いかけるネイロス。
「だが、どうすれば? ……これが綻びになったりはしないのか?」
ほぼ、苦し紛れに出た言葉だった。
否定のできない真っ直ぐなネイロスの言葉からの逃げ道を探すような、情けない言葉。
勇者だった頃なら、失望されることを恐れて口にすら出来なかったような、そんな言葉。
しかし、そんな俺をも見越していたかのように、カラッと笑ってネイロスは言い放った。
「妾を誰だと思っている? 無論、解除魔法を作ることなぞ、造作もない」
そして、宙をなぞりながら魔法言語で何かを唱え始めた。
その呪文のような何かは、今までどんな魔法でも一度見れば使うことのできた俺ですら全く理解できないような物だった。
「ふむ、こんなところか。ファレスよ、この魔法をお主に授けよう」
「この魔法って……まさか!? 今、この場で魔法を作り出したのか!?」
「なに、別段おかしなことでもないだろう? 魔法は魔族の生み出した法術。そんな魔族の頭目ともなれば、魔法の一つや二つ即興でも作れる」
そうは言いつつも誇らしげに胸を張るネイロス。
気分が良いのか、いつもよりさらに饒舌に彼女は続ける。
「この魔法はそうだな〈真実の発露〉とでも呼ぶとするか。効果はその名の通り、対象の肉体や精神に眠る記憶を呼び覚ますものだ」
「つまり、この魔法は〈存在しない記憶〉の完全な対抗魔法ってことか?」
「うむ、そういうことだ。さぁ、お主ならば試し打ちの必要も無いだろう? 行って参れ! どうせなら風呂で文字通りの裸の心をぶつけて来い!」
「ネイロス……」
そう言って俺の背中を押してくれるネイロスに、改めてその存在の大きさを感じさせられた。
「ありがとう、ちょっと行ってくる」
「うむ、のぼせるなよ」
ネイロスの言葉を背に受けながら、俺は覚悟を決めた。
そうだ。俺はもう勇者じゃない。勇者であったことに縛られる必要は無いんだ。
情けない葛藤やつまらない責任感はすっかりと俺の中から消えていた。
◇◇◇
「こんな風呂が……これももしかして自作なのか? ファレスさん、本当に底が知れないな」
入浴場へやってきたケイルは想像以上の広さと綺麗さの風呂に感心していた。
「これは戻ったらミア王女に感謝しなければな。まさか任務先でこんなに優雅な生活を体験できるとは」
そう呟きながら、他の隊員には迂闊に話せないとも思った。
更衣室でサッと服を脱ぐとついに風呂へ足を踏み入れる。
すぐに浴槽に近づき、お湯に手をつけた。
「おお! これは芯まで温まりそうだ。では、早速」
備え付けの桶で湯を掬い、足先から温度に慣らしたあと、ケイルは湯船に浸かった。
「ふぅ……。癒されるな。あのベッドも格別だったが、ここはまた違った心地良さがある」
長旅で張った筋肉がほぐれていく。
このお湯に何か効能でもあるのだろうか?
水音だけの静かな空間でケイルは物思いに耽った。
少しして、入浴場の扉を開くような音がした。
「ん? ダンカンか? あいつ寝るとか言っていたくせに」
先程は散々いじられたため小言でも言ってやろうかと、そう思ってケイルが振り返った先にいたのは、宿の店主ファレスだった。
◇◇◇
ネイロスに背中を押された俺は迷いなく、ケイルのいる風呂までやってきた。
「失礼……いや、一緒にいいか? ケイル」
俺はあえて、魔法を使う前に昔の口調でケイルを呼んだ。
「……ファレスさん? 構いませんが……」
突然の態度の変わりように若干困惑した様子のケイル。
だが、それに構わず俺もケイルのいる浴槽まで歩いた。
「湯加減はいいか?」
「え、ええ。とても気持ち良いです。ありがとうございます」
「それならよかった……昔もたまに、一緒に水浴びしたよな」
「昔? 一緒に? 一体なんの話し……うっ」
ケイルが突然頭を抑えるような仕草をした。
「……何か、……なんだこの違和感は」
そしてケイルは喉元まで出かかって、どうしても出てこないと言うようなもどかしそうな表情を浮かべる。
「すまないケイル。俺の勝手で忘れさせて、こうしてまた勝手をすることになって……」
「ファレス……さん? 一体何を?」
苦悶の表情を見せながら俺を見るケイルに謝罪をしながら、先程ネイロスに貰ったばかりの魔法を発動した。
「〈真実の発露〉」
俺の指先から輝く虹色の雫が一滴、ケイルに向かって落ちていく。
「……これは一体?」
そして一瞬、ケイルの視線が明後日の方向へ飛び、再び俺を視界に捉えた。
「すまなかったケイル」
その言葉を聞いた途端、ケイルの脳内で覆い隠されていた記憶の数々が次々に蘇った。
「………………お前、なんだよな? ファレス」
そこにいるケイルは俺のよく知る、いい兄貴分のケイルだった。
「ああ、演説の日ぶりだな」
「……お前っ!」
ケイルは湯船から立ち上がり、俺の肩を掴んで叫ぶように言い放った。
「どういうつもりだ! 帰ってきた途端、俺たちの前から姿を消しやがって! 俺は……俺たちはまたお前と……」
広いとは言っても音のこもる風呂にケイルの慟哭がこだまする。
どうやらこの魔法の効果はただ記憶を呼び起こすだけではなく、俺が居ないことになっていた間の記憶との錯誤も解消してくれるものだったようだ。
本当にネイロスには頭が上がらないな。
「すまなかった」
こうやって違うことを考えなければ、俺は目の前のケイルにつられて涙を流してしまいそうだった。
「くそっ! もう四十近いってのに……くそっ」
もう逃がさないと言わんばかりに、俺の肩を掴んだままケイルの涙は次々に波紋を作った。
「全部話すよ。とりあえず……座ろうぜ」
掴まれた肩に懐かしい馬鹿力を感じて、思わず涙声になりかけた声を何とか抑えると、俺も湯船に入り、ケイルの隣へ腰を下ろす。
「……なんで? とは聞かねえよ。でも一言くらい言ってくれても良かっただろ」
ケイルは鼻をすすり、そう呟く。
「ああ、そうだな。でも、決心が鈍るような気がして、な」
俺はケイルの方は見ずに答えた。
「ミア王女は? まさか俺たちと同じ扱いなんじゃないだろうな?」
「……ミアは知ってる。偶然だったけどな」
俺は右手の指輪をケイルに見せる。
「その指輪……そういえばミア様がよく眺めてたな。……そんな物まで受け取っておきながらお前は!」
「それについては……何も言い返せないな」
「戻ったら、ファレスが美人と宿を経営してましたってチクッといてやるからな」
「なっ!? それはちょっと待ってくれよ!」
「はっ、自業自得だな。……でも」
ケイルはそこで一度言葉を区切ると、大きく深呼吸をしてからこう言った。
「ほんと、お前が死んでなくて良かった」
「な、突然話しを……戻すなよ」
不意に大真面目な表情で心から安堵したという視線を向けられ、一度は引っ込んだ俺の涙が荒れ狂う波の如く押し寄せてきた。
「いい歳した兄貴分を散々泣かせた罰だ。ミア王女への土産話を思う存分作ってやる!」
ひとしきり泣きあった後、ケイルが色々と質問をしてきた。
「なんでここで宿を始めることにしたんだ?」
「ここは……俺のせいで無くなった村なんだ。だからその贖罪かな……いい所だって言うのはもちろんあるけど。あとはさっき宿の方で答えた通りさ」
「……そうか。詳しくは聞かねえよ。けど今はやりたいことがやれてるんだな?」
「ああ、客は少ないが毎日充実してるよ」
「なら良いんだ。……そういえばミア王女はお前のこと知ってるって言ってたけど、この場所も知ってるのか?」
「いや、ここのことは言ってない。だからケイルとここで会えたのも完全な偶然だ」
「そりゃすげえな。これが女の勘ってやつなのか? 浮気してるファレスを裁いて来いって」
確かにミアの指示でケイルがここに来たのは運以上の何かが働いていそうだ。だが、浮気云々は誤解すぎる。
「おい、言いがかりだ! ミアもネイロスも別にそう言う相手じゃない」
「ほ〜う、ファレスくん? ここでの発言は全てミア王女に伝わると分かっているのかい? 俺たちは王女の目となり耳となるためにここに来ているんだぞ?」
「なっ! ケイル、お前そんなやつじゃなかっただろ!」
「はっ! 十年も会わなきゃこんなもんだろ!」
まるで十年以上前から変わらないやり取り。
ああ、どうして俺はこんな大切な物まで消してしまおうと思ったのか。
精神の摩耗と言うのは、魔王なんかよりもよっぽど脅威的だ。
「それより、だ。結局あのネイロスさんはどこで拾ってきたんだ?」
「え、ああ……あいつは……迷い猫みたいなもんだ」
いくらケイルとは言え、嘘でもネイロスが元魔王だとは言う訳にはいかず、咄嗟にそんな言葉が口をついた。
「はぁ? 迷い猫? それで懐かれたとでも?」
「……まあ、そんなところだな」
「あの感じ……どう見ても普通の町娘って感じじゃなかったけど、どっかの貴族様のご令嬢、とかじゃないだろうな? 嫌だぞ? 裁判所で誘拐の罪に問われるお前を見るのは」
「違うわっ! あいつはまあ……なんと言うか、同士みたいなものなんだよ。今日こうやってケイルと話せてるのも、あいつのおかげなんだ」
「ほ〜う、それは感謝しなきゃだな」
「ああ、あいつも今や、ミアやケイルたちと同じくらい大切なんだ」
「……なんだよ。そんな風に言われちゃ、からかいにくいじゃねえか」
「おまっ……まだからかう気だったのかよ!」
親友……いや、家族も同然の二人はこうして絆を取り戻した。
騒がしい夜はさらに更けていく。
そんな様子を満足気な表情で聞いている元魔王。
「大切……か。妾が負けた理由はもしかすると、そこにあったのかもしれぬな」
ファレスには彼を勇者としてではなく、ファレスとして接してくれる人たちがいた。一度は離れても帰る場所があった。
それに比べネイロスには、自分を魔王としてではなくネイロスとして接してくれるような存在はいなかった。
少なくとも、今までは。
「ファレス、お主は妾に感謝をしてくれているようだが、それは妾も同じなのだ。本当に……」
ネイロスにとってファレスはファレスだが、魔王にとってのファレスは紛れもなく勇者であり、光であった。
「お主の代の魔王で在れて良かったと、心から思っているぞ」
ファレスが脱いでいったエプロンをたたみながら、にぎやかな夜に落とされたしっとりとした色は静かに消えていった。