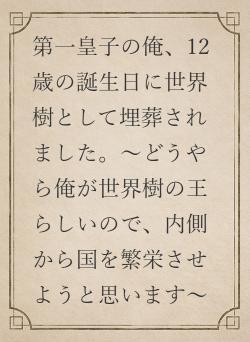「なあ、ファレスよ」
キッチンで夕食を作っていると、エプロンを着けたネイロスがいつもの調子でやってきた。
「どうした? それにしてもネイロス、あんな口調で喋れたんだな」
「む? 口調とな? エホン」
するとネイロスは咳払いをひとつして姿勢を正した。
「こちらの口調のことでしょうか? ファレスさん?」
「おお、それそれ。急に切り替えるから目を疑ったよ」
「ふむ、ファレスはこんな感じの丁寧な話し方が好きなのか?」
「いや、好きとかそういう訳じゃないけど……まぁ、聞き慣れてはいるかもな」
不意に右の中指に目が行った。
ケイルに会ったせいだろうか? 今日はいつもよりやけに懐かしいことを思いだす。
「ほう……それは、その指輪の片割れを持つ女子が理由か?」
「……! 分かるのか?」
まるで名探偵かのごとき鋭さで確信を突いてくるネイロスに思わず、素の反応をしてしまった。
「ふっ、かまをかけて見ただけだがな。妾というものがありながら、お主も罪な男だな」
「いや、ネイロスは従業員だし、ミアも別に……」
言いかけた所で階段を下りてくる足音が聞こえた。
「おっと、仕事の時間だ。さ、テーブルを拭いてきてくれ。俺は料理を盛り付けるから」
「ふん、まあ、いいだろう。いつかそのミアとやらにも会ってみたいものだな」
「……いつか、な」
台拭きを持ってキッチンを出ていく足音を聞きながら、突然に思いだされた懐かしい記憶の数々に想い馳せた。
◇◇◇
「おおっ! これはまた豪勢な……あの、これ本当に大銀貨一枚で出してるんですか?」
ケイルとダンカンが座ったテーブルに一通り料理を並べると、喜びを通り越して遠慮気味になったダンカンがそう聞いて来た。
「ええ、ウチのメインのお客様は初、中級レベルの探索者の方ですので」
「失礼ですが、こちらは何の肉を? 羊肉のチョップステーキに見えるのですが……こんな質感の羊肉は見たことが……」
「副隊長? 相当希少な大羊じゃないんですか?」
「これが大羊の肉に見えるのか? どう見ても……! まさか!?」
ケイルは俺が答えを言う前にたどり着いた様子だ。
ならば俺の口から教えてやる必要はないよな。
「さぁ? とてもおいしい羊肉ですので、是非冷めないうちに」
「そ、そうですよ副隊長! これまで携帯食ばかりでしたし、良いじゃないですか!」
そう言うダンカンは今にもフォークを突き刺しそうな本能を何とかとどめていると言った様子だ。
「……まあ、そうだな。出してもらったものを食べないわけにはいかないか。では、いただきます」
「いただきます!」
言うや否やステーキに噛り付くダンカン。
「……! 何すかこれっ! 美味いなんて次元じゃないっ!」
興奮を隠しきれない、そんな感情がひしひしと伝わって来る。料理した甲斐があったというものだ。
そんなダンカンに続いてケイルもひと口。
「……これは! 王城で食った何よりも美味い……ファレスさん、あなたは本当に何者ですか?」
「しがない宿屋の店主ですよ」
喜んでもらえたようで何よりだ。
だが、幻妖の羊の肉も無限にあるわけじゃないし……今度また取りに行かなきゃな。
そんなことを考えながら、良い食べっぷりを見せる二人と一緒に俺とネイロスも食事を取った。
我ながら今日の料理も会心の出来だった。
「そうだ、ファレスさん。私たちはここに調査へ来たという話、覚えていらっしゃいますか?」
食事が終わり、後片付けをしようとしているとケイルがそう話しかけて来た。
「……ええ、もちろん。確か、魔族の被害に遭われた地域などを視察していらっしゃるんでしたよね?」
「そうなのです。ですが、この辺りにはそんな形跡がなく……なので、ここに住んでいらっしゃるお二人に少しお話を伺いたいのですが」
そうだった。
質問されるまで完全に忘れていたが、彼らは騎士で、ここには視察で来ているのだ。
この辺りについて大して話せることはないのだが……断るわけにはいかないだろう。
「もちろんです。ですが、ネイロスは最近、私が別の街から連れて来た従業員なので、この辺りに詳しいわけではありません。申し訳ないですが、応対は私一人でも?」
「そうだったのですね。もちろん構いませんよ」
魔族被害の話を魔王であるネイロスにさせたくはないと思い咄嗟にそう言った。
確かにシダやマインを殺した魔族のことは憎い。
だが、だからと言ってネイロスが憎いかと言えばそれは違う。
俺たちの敵対関係はお互いがその立場を降りることで解消されているのだから。
「でしたら片付けは私がやっておきます」
「ああ、助かるよ」
そう言い食器を集めるネイロスが一瞬、意味ありげな視線を送って来たが気にせず受け流した。
「ではまず、ファレスさんがこの宿を始めたのはいつ頃からですか? 内装も外装もとてもお綺麗ですので、まだ最近ですか?」
ケイルが質問を始めると、ダンカンは食事で緩んでいた表情を引き締めなおし、紙にメモを取る用意をした。
「ええ、そうです。こんなところですから、誰かに頼るわけにもいかず……時間をかけて、自分で建てました。宿を開き始めたのは本当に最近ですね」
「ご自分で建築を!? それはまた……本当に底知れない方ですね」
「いえいえ、少し便利な魔法を知っていただけですよ」
「魔法……そうですか。正直そちらの話しも気になりますが、今は仕事を続けますね。……では次に、この村が魔族被害に遭った当時のことは知っていますか?」
ケイル、いや、第二近衛騎士隊副隊長とのやり取りは終始和やかに雑談を交えながら進んでいった。
「なるほど。一人でこの村跡地を綺麗な状態に戻し、その上で自分でこの宿を建てて経営を始めたと……正直、この目で見なければ信じられないようなお話ですね」
冗談半分にケイルがそう言う。
「あはは、自分でもよくやったと思いますよ。でも、いつまでもあのままというのは悲しみが滞留してしまっているようでして……」
「ええ、お気持ちを完全に理解することは出来ないですが、心中お察しいたします。……すみません長々と、まだ止まらせていただく間に何度かお話を伺うことになるかもしれませんが……」
「ええ、もちろん。私にお話しできることでしたらなんでも、お話いたしますよ」
ないとは思っていたが、ここで勝手に宿を経営していることを咎められなくてよかった。
そう安堵しているところに、ティーポットを持ったネイロスが戻って来た。
「お仕事ご苦労様です。紅茶を入れましたので、いかがですか?」
「これは……すみません一方的に伺っている立場だというのに」
「いえいえ、この茶葉美味しいんです。ぜひ、いかがですか?」
「では、お言葉に甘えて」
ネイロス……いつの間に紅茶なんて?
いや、淹れたタイミングは分かるのだが、まさかネイロスが紅茶を淹れられるとは思っていなかったので衝撃だ。
人数分のカップを並べて注いでいき、終わると彼女も俺の隣に座った。
いつの間にか完全に食後のティータイムの完成だ。
「あの、ファレスさん。つかぬことをお伺いするのですが……お二人はご結婚をされていらっしゃるのですか?」
それからは仕事に関係のない雑談をしていたのだが、ダンカンが突然一歩踏み入った質問をしてきた。
「……い、いえ、従業員と店主というだけですよ」
俺は思わず紅茶を吹き出しそうになるのを何とかこらえてそう答える。
だが、ネイロスはそんな俺の反応が面白かったのか追撃をかけて来た。
「まだ……というだけ、ですけどね」
「「おおっ!」」
ケイルとダンカンが同時に歓声を上げる。
「ネイロス!?」
「言ったじゃありませんか。私はここであなたと共に在りたいと、ね?」
「ファレスさん! これは男の見せどころですよ」
「聖騎士ではないので祝福の祈りは出来ませんが、お祝いしますよ!」
「ちょ、ちょっと待ってください。本当にそう言うのじゃないですからね? ……んんっ。そう言うケイルさんはどうなんですか? ちょうど適齢期なのでは?」
ネイロスにこれ以上揶揄われてはたまらないと咄嗟に話をケイルに振った。
「そうですよ副隊長! 第二近衛騎士隊の副隊長だって言うのに浮いた話の一つも聞いたことないです」
ダンカンは完全に野次馬モードになったのか、面白い話題なら何でもいいようで、ありがたいことに俺の話に乗って来た。
「残念ながら……。自分でもよくわからないのですが、誰かより先に幸せになるのは違うなという思いが昔からありまして……。まあ、そんな誰かを今は忘れてしまったんですが」
――!
照れたように頭を搔きながら、そう言うケイル。
俺はその誰かに心当たりしかなかった。
「どういうことですか副隊長? モテているうちが花ですよ! きっととその誰かも、副隊長の幸せを願っていますって!」
「……そうなのだろうな。だが――」
「ダンカンさんの言う通りですよ! いつか思いだしたときに幸せになったと報告できる方がずっといいですって!」
俺は半ば自分自身に言い聞かせるようにそう言った。
あの日のケイルの言葉が思い起こされる。
『それも十年で、なんて……まあ、お前みたいな若いヤツの十年を奪っちまったのは……』
あの時は、笑って流してしまったが、ケイルはそう言う男だった。
真面目で正義感が強くて、常に自分より他人を優先する。
この言葉には想像以上に重い後悔が乗っていたのだと、今更ながらに思い知らされた。
「……そう、ですか。では、戻ったら探してみようかなと思います」
柔らかに笑うケイル。
だが、その表情の奥には消化し切れない後悔の色が見えた。
そして、その原因である自分が目の前にいるのに、それ以上何も言えないことが非常にもどかしかった。
そんな空気を察してか、ネイロスがダンカンに話を振った。
「ダンカンさんは? まだお若いようですし、浮いた話の一つや二つあるんじゃないですか?」
「いやっ、全然、全然。あーあ、ネイロスさんがフリーなら良いなと思ってたのに」
だいぶ気が抜けているのか、夕食で出した酒が今頃になって回って来たのか、だいぶ口の軽くなったダンカン。
「ふふっ、ありがとうございます。きっとダンカンさんなら、すぐに良い方が見つかりますよ」
「うわー、もう! ファレスの旦那! こんなに良い人いつまでもほったらかしにしちゃ、ダメですからね!?」
「あはは……」
あーこれ、完全に酔ってるな。
ダンカンはきっと、オンとオフの切り替えがうまいタイプなんだろう。
さっきまでは仕事が残ってたから理性が上回っていただけで、それが終わってしまえばこの通り。
「……すみません、うちの部下が。おいダンカン、王都でもそんな風に酔い散らかしてるんじゃないだろうな?」
「ま、まさかー。あ、あ~俺、突然眠くなってきました。副隊長、先に部屋に戻りますね! ファレスさんもネイロスさんもおやすみなさい」
……酔っても、超えちゃいけないラインの線引きは出来るタイプか。
道理で有望株と言われるわけだ。
「ケイルさんも休まれますか? 良ければうちには入浴場もありますので、どうでしょう?」
「入浴場? 風呂があるんですか!?」
完全にお開きの流れになったので、ついでのつもりで進めて見たのだが、予想以上の反応が返って来た。
「ええ、外に厩ともう一棟建物があったでしょう? あれが入浴施設になってますので、私に声をかけて頂ければ、清掃中以外ならいつでも入浴いただけますよ」
「ぜひ、入らせてください!」
前のめりになって、ケイルが頼んでくる。
ケイルが風呂好きだったなんて知らなかった。
「もちろんです。どうぞこちらへ」
こうして今日も賑やかな夜は更けていった。
キッチンで夕食を作っていると、エプロンを着けたネイロスがいつもの調子でやってきた。
「どうした? それにしてもネイロス、あんな口調で喋れたんだな」
「む? 口調とな? エホン」
するとネイロスは咳払いをひとつして姿勢を正した。
「こちらの口調のことでしょうか? ファレスさん?」
「おお、それそれ。急に切り替えるから目を疑ったよ」
「ふむ、ファレスはこんな感じの丁寧な話し方が好きなのか?」
「いや、好きとかそういう訳じゃないけど……まぁ、聞き慣れてはいるかもな」
不意に右の中指に目が行った。
ケイルに会ったせいだろうか? 今日はいつもよりやけに懐かしいことを思いだす。
「ほう……それは、その指輪の片割れを持つ女子が理由か?」
「……! 分かるのか?」
まるで名探偵かのごとき鋭さで確信を突いてくるネイロスに思わず、素の反応をしてしまった。
「ふっ、かまをかけて見ただけだがな。妾というものがありながら、お主も罪な男だな」
「いや、ネイロスは従業員だし、ミアも別に……」
言いかけた所で階段を下りてくる足音が聞こえた。
「おっと、仕事の時間だ。さ、テーブルを拭いてきてくれ。俺は料理を盛り付けるから」
「ふん、まあ、いいだろう。いつかそのミアとやらにも会ってみたいものだな」
「……いつか、な」
台拭きを持ってキッチンを出ていく足音を聞きながら、突然に思いだされた懐かしい記憶の数々に想い馳せた。
◇◇◇
「おおっ! これはまた豪勢な……あの、これ本当に大銀貨一枚で出してるんですか?」
ケイルとダンカンが座ったテーブルに一通り料理を並べると、喜びを通り越して遠慮気味になったダンカンがそう聞いて来た。
「ええ、ウチのメインのお客様は初、中級レベルの探索者の方ですので」
「失礼ですが、こちらは何の肉を? 羊肉のチョップステーキに見えるのですが……こんな質感の羊肉は見たことが……」
「副隊長? 相当希少な大羊じゃないんですか?」
「これが大羊の肉に見えるのか? どう見ても……! まさか!?」
ケイルは俺が答えを言う前にたどり着いた様子だ。
ならば俺の口から教えてやる必要はないよな。
「さぁ? とてもおいしい羊肉ですので、是非冷めないうちに」
「そ、そうですよ副隊長! これまで携帯食ばかりでしたし、良いじゃないですか!」
そう言うダンカンは今にもフォークを突き刺しそうな本能を何とかとどめていると言った様子だ。
「……まあ、そうだな。出してもらったものを食べないわけにはいかないか。では、いただきます」
「いただきます!」
言うや否やステーキに噛り付くダンカン。
「……! 何すかこれっ! 美味いなんて次元じゃないっ!」
興奮を隠しきれない、そんな感情がひしひしと伝わって来る。料理した甲斐があったというものだ。
そんなダンカンに続いてケイルもひと口。
「……これは! 王城で食った何よりも美味い……ファレスさん、あなたは本当に何者ですか?」
「しがない宿屋の店主ですよ」
喜んでもらえたようで何よりだ。
だが、幻妖の羊の肉も無限にあるわけじゃないし……今度また取りに行かなきゃな。
そんなことを考えながら、良い食べっぷりを見せる二人と一緒に俺とネイロスも食事を取った。
我ながら今日の料理も会心の出来だった。
「そうだ、ファレスさん。私たちはここに調査へ来たという話、覚えていらっしゃいますか?」
食事が終わり、後片付けをしようとしているとケイルがそう話しかけて来た。
「……ええ、もちろん。確か、魔族の被害に遭われた地域などを視察していらっしゃるんでしたよね?」
「そうなのです。ですが、この辺りにはそんな形跡がなく……なので、ここに住んでいらっしゃるお二人に少しお話を伺いたいのですが」
そうだった。
質問されるまで完全に忘れていたが、彼らは騎士で、ここには視察で来ているのだ。
この辺りについて大して話せることはないのだが……断るわけにはいかないだろう。
「もちろんです。ですが、ネイロスは最近、私が別の街から連れて来た従業員なので、この辺りに詳しいわけではありません。申し訳ないですが、応対は私一人でも?」
「そうだったのですね。もちろん構いませんよ」
魔族被害の話を魔王であるネイロスにさせたくはないと思い咄嗟にそう言った。
確かにシダやマインを殺した魔族のことは憎い。
だが、だからと言ってネイロスが憎いかと言えばそれは違う。
俺たちの敵対関係はお互いがその立場を降りることで解消されているのだから。
「でしたら片付けは私がやっておきます」
「ああ、助かるよ」
そう言い食器を集めるネイロスが一瞬、意味ありげな視線を送って来たが気にせず受け流した。
「ではまず、ファレスさんがこの宿を始めたのはいつ頃からですか? 内装も外装もとてもお綺麗ですので、まだ最近ですか?」
ケイルが質問を始めると、ダンカンは食事で緩んでいた表情を引き締めなおし、紙にメモを取る用意をした。
「ええ、そうです。こんなところですから、誰かに頼るわけにもいかず……時間をかけて、自分で建てました。宿を開き始めたのは本当に最近ですね」
「ご自分で建築を!? それはまた……本当に底知れない方ですね」
「いえいえ、少し便利な魔法を知っていただけですよ」
「魔法……そうですか。正直そちらの話しも気になりますが、今は仕事を続けますね。……では次に、この村が魔族被害に遭った当時のことは知っていますか?」
ケイル、いや、第二近衛騎士隊副隊長とのやり取りは終始和やかに雑談を交えながら進んでいった。
「なるほど。一人でこの村跡地を綺麗な状態に戻し、その上で自分でこの宿を建てて経営を始めたと……正直、この目で見なければ信じられないようなお話ですね」
冗談半分にケイルがそう言う。
「あはは、自分でもよくやったと思いますよ。でも、いつまでもあのままというのは悲しみが滞留してしまっているようでして……」
「ええ、お気持ちを完全に理解することは出来ないですが、心中お察しいたします。……すみません長々と、まだ止まらせていただく間に何度かお話を伺うことになるかもしれませんが……」
「ええ、もちろん。私にお話しできることでしたらなんでも、お話いたしますよ」
ないとは思っていたが、ここで勝手に宿を経営していることを咎められなくてよかった。
そう安堵しているところに、ティーポットを持ったネイロスが戻って来た。
「お仕事ご苦労様です。紅茶を入れましたので、いかがですか?」
「これは……すみません一方的に伺っている立場だというのに」
「いえいえ、この茶葉美味しいんです。ぜひ、いかがですか?」
「では、お言葉に甘えて」
ネイロス……いつの間に紅茶なんて?
いや、淹れたタイミングは分かるのだが、まさかネイロスが紅茶を淹れられるとは思っていなかったので衝撃だ。
人数分のカップを並べて注いでいき、終わると彼女も俺の隣に座った。
いつの間にか完全に食後のティータイムの完成だ。
「あの、ファレスさん。つかぬことをお伺いするのですが……お二人はご結婚をされていらっしゃるのですか?」
それからは仕事に関係のない雑談をしていたのだが、ダンカンが突然一歩踏み入った質問をしてきた。
「……い、いえ、従業員と店主というだけですよ」
俺は思わず紅茶を吹き出しそうになるのを何とかこらえてそう答える。
だが、ネイロスはそんな俺の反応が面白かったのか追撃をかけて来た。
「まだ……というだけ、ですけどね」
「「おおっ!」」
ケイルとダンカンが同時に歓声を上げる。
「ネイロス!?」
「言ったじゃありませんか。私はここであなたと共に在りたいと、ね?」
「ファレスさん! これは男の見せどころですよ」
「聖騎士ではないので祝福の祈りは出来ませんが、お祝いしますよ!」
「ちょ、ちょっと待ってください。本当にそう言うのじゃないですからね? ……んんっ。そう言うケイルさんはどうなんですか? ちょうど適齢期なのでは?」
ネイロスにこれ以上揶揄われてはたまらないと咄嗟に話をケイルに振った。
「そうですよ副隊長! 第二近衛騎士隊の副隊長だって言うのに浮いた話の一つも聞いたことないです」
ダンカンは完全に野次馬モードになったのか、面白い話題なら何でもいいようで、ありがたいことに俺の話に乗って来た。
「残念ながら……。自分でもよくわからないのですが、誰かより先に幸せになるのは違うなという思いが昔からありまして……。まあ、そんな誰かを今は忘れてしまったんですが」
――!
照れたように頭を搔きながら、そう言うケイル。
俺はその誰かに心当たりしかなかった。
「どういうことですか副隊長? モテているうちが花ですよ! きっととその誰かも、副隊長の幸せを願っていますって!」
「……そうなのだろうな。だが――」
「ダンカンさんの言う通りですよ! いつか思いだしたときに幸せになったと報告できる方がずっといいですって!」
俺は半ば自分自身に言い聞かせるようにそう言った。
あの日のケイルの言葉が思い起こされる。
『それも十年で、なんて……まあ、お前みたいな若いヤツの十年を奪っちまったのは……』
あの時は、笑って流してしまったが、ケイルはそう言う男だった。
真面目で正義感が強くて、常に自分より他人を優先する。
この言葉には想像以上に重い後悔が乗っていたのだと、今更ながらに思い知らされた。
「……そう、ですか。では、戻ったら探してみようかなと思います」
柔らかに笑うケイル。
だが、その表情の奥には消化し切れない後悔の色が見えた。
そして、その原因である自分が目の前にいるのに、それ以上何も言えないことが非常にもどかしかった。
そんな空気を察してか、ネイロスがダンカンに話を振った。
「ダンカンさんは? まだお若いようですし、浮いた話の一つや二つあるんじゃないですか?」
「いやっ、全然、全然。あーあ、ネイロスさんがフリーなら良いなと思ってたのに」
だいぶ気が抜けているのか、夕食で出した酒が今頃になって回って来たのか、だいぶ口の軽くなったダンカン。
「ふふっ、ありがとうございます。きっとダンカンさんなら、すぐに良い方が見つかりますよ」
「うわー、もう! ファレスの旦那! こんなに良い人いつまでもほったらかしにしちゃ、ダメですからね!?」
「あはは……」
あーこれ、完全に酔ってるな。
ダンカンはきっと、オンとオフの切り替えがうまいタイプなんだろう。
さっきまでは仕事が残ってたから理性が上回っていただけで、それが終わってしまえばこの通り。
「……すみません、うちの部下が。おいダンカン、王都でもそんな風に酔い散らかしてるんじゃないだろうな?」
「ま、まさかー。あ、あ~俺、突然眠くなってきました。副隊長、先に部屋に戻りますね! ファレスさんもネイロスさんもおやすみなさい」
……酔っても、超えちゃいけないラインの線引きは出来るタイプか。
道理で有望株と言われるわけだ。
「ケイルさんも休まれますか? 良ければうちには入浴場もありますので、どうでしょう?」
「入浴場? 風呂があるんですか!?」
完全にお開きの流れになったので、ついでのつもりで進めて見たのだが、予想以上の反応が返って来た。
「ええ、外に厩ともう一棟建物があったでしょう? あれが入浴施設になってますので、私に声をかけて頂ければ、清掃中以外ならいつでも入浴いただけますよ」
「ぜひ、入らせてください!」
前のめりになって、ケイルが頼んでくる。
ケイルが風呂好きだったなんて知らなかった。
「もちろんです。どうぞこちらへ」
こうして今日も賑やかな夜は更けていった。