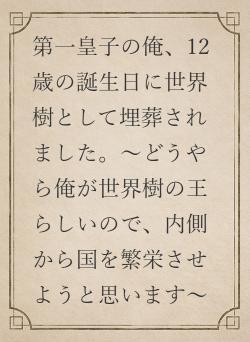疲れきって深い眠りに落ちたケイルは不思議な夢を見ていた。
それはまるで本当だったかのように現実的で、それでいてあり得ない、そんな存在しない記憶を追体験するような夢だった。
◇◇◇
「なあ、ケイル聞いたか?」
騎士見習いとして、ともに訓練に励む仲間がランニング中のケイルに合流しつつ話しかけて来た。
「なんだよ?」
「今日から王城に勇者が来るらしいぞ?」
こいつ仲間の間でも中々の情報通というか、ゴシップ好きでよくこうしてケイルに嘘か本当か怪しい情報を垂れ込んでいた。
「勇者だぁ? バカ言え、もう何年も現れてないっていう伝説上の存在だろ? それとも昨日今日生まれたばかりの赤ん坊が来るとでも言うのかよ」
勇者、その存在は王国に生まれる者ならば知らない者はいない。
だが、だからこそ、勇者という存在は伝説的で象徴的なものなのだ。
そう思ったケイルは、嘘だろうと言う確信をもってそう言った。
「おう、そうらしい。しかも、親元からは引き離されてな」
しかし、どうやらその嘘の通りらしい。
それも、生まれたばかりの子供を親元から引き離すというおまけつき。
「……はぁ!? 何だよそれ? さすがに可哀そうすぎるだろ!」
正義感の強いケイルは憤った。
「まあ、そうだよな。でも俺たちにはどうしようもないさ」
だが、この憤りは無意味なものだ。
今のケイルはただの騎士見習い、権力どころかその権力に跪く存在ですらないのだ。
「……」
無言でランニングのペースを上げる。
「おいっ! そんなスピードじゃ、絶対最後まで持たないぞ!」
ケイルはこの行き場のない怒りを全て訓練にぶつけることにした。
◇◇◇
――六年後。
実力を認められたケイルは十八にして異例の近衛騎士隊入りを果たした。
そしてそこではじめて彼と出会ったのだ。
「■■■■! 待ってください!」
「待っててやるから、転ぶなよミア!」
王女と共に場内を元気に駆け回る少年。
一目見て、理解した。
彼は本物だ、と。
なぜかその彼の姿がまるで破り取られたかのように黒く見えないが、そんな確信を覚えた。
「はぁはぁ……今日はどこに行くのですか?」
「いいとこを見つけたんだ!」
「いいところ?」
「まあ、着けばわかるから、な?」
「歩いて行けばいいじゃないですか! もうっ! 待ってください!」
走っていく幼い彼らが眩しくて、ケイルは二人を追いかけた。
大人の足と子どもの足、それにミア王女を連れている彼に追いつくのは容易いことだった。
「あそこは確か……」
少年とミア王女はもう誰も近づかなくなった旧武器庫へと入っていった。
何となくバレないように後をつけてきてしまったが、流石に武器庫内で王女に怪我でもあれば一大事だ。
そう思ったケイルは注意をしに二人の後について、武器庫内に入った。
「どうだ? ミア。すごいだろ! ここはもう使われてない倉庫なんだってさ!」
何故か姿の見えない少年が嬉しそうにミア王女に自慢している。
「こんなところ……入ってしまっていいのでしょうか?」
「大丈夫大丈夫、バレなきゃ平気だっ――」
自信満々に言おうとした少年と思しき黒い影は少し遅れて武器庫内に入って来たケイルと目が合ってしまいそこで言葉を止めた。
「■■■■? どうしたのですか?」
ミア王女はまだ気がついていないようだった。
そのためケイルはなるべく驚かせないようにやさしい声で伝える。
「お二人とも、ここはもう使われなくなったとはいえ、危険物もある武器庫です。さぁ、もう戻りましょう?」
「騎士さん!? いつの間に……」
少し驚かせてしまったようだが、この程度ならば上出来だろう。
「さぁ、こちらへ」
「■■■■、騎士さんもああ言っていることですし、戻りましょう」
「ああ、分かったよ……」
不服そうな声ではあるが、物わかりの良い子そうで助かった。
……あ、そうだ!
「心配しなくても平気ですよ。ここは私が時間のある時に片付けておきますから、そしたらお二人の遊び場でも秘密基地にでもしてください」
この子達は生まれてすぐに役割を与えられ、きっと今日も何かの時間を縫って、二人で遊んでいたのだろう。
そんな二人の遊び場を取り上げるのは違うとケイルは思った。
バレれば大目玉を食らうこと間違いないだろうが、その時はその時だ。
「いいんですか?」
影の少年が途端に態度を和らげる。
可愛い奴だなとケイルは思った。
「ええ、もちろん。でも、遊ぶときは気を付けてくださいね?」
「わかりました!」
「良かったですね■■■■!」
「ああ!」
この子が勇者であろうとこの眩しい笑顔を守ってやりたいとそう思った。
◇◇◇
――二年後。
ケイルは二十歳、少年とミア王女が八歳になる年にその少年は頭角を現し始めた。
幼いが子供用の剣ならば振り回されない程の力がついてきて、彼はその才能を如何なく発揮するようになった。
はじめは歳の近い騎士見習いとの対決だった。
しかし、歳が近いとは言っても騎士見習いになれるのは十二歳から、子どもの四歳差とはあまりにも大きいと誰もが思っていた。
だが、そんな心配は杞憂だった。
模擬戦開始の合図とともに、少年は目にも留まらぬ速さで加速した。
訓練を続けて来たケイルですら、そのざまだったのだ。
対戦相手の騎士見習いが見えるはずもなく、その模擬戦は文字通りの一瞬で決着した。
「ありがとうございました」
言葉を失っていた観衆は少年のその言葉で大歓声を上げ、それからしばらくして俺たち騎士の間であの少年が話題に上がらない日はなくなった。
そんなある日、ケイルは近衛騎士隊隊長に呼び出されていた。
「お呼びで在りましょうか、隊長!」
「うむ、急に呼んで悪いなケイル」
「いえ、ご命令とあれば、いつどこにでも!」
「ははっ、相変わらずお前は真面目だな。だが、今回はその真面目さと先方の意向がうまく合致したようだ。お前になら安心して任せられる」
「……一体、何を?」
「ケイル、お前に勇者の訓練相手となる任を与える」
「!? 私、ですか!?」
「ああ、どうやら勇者くんきっての意向らしいぞ? お前いつの間に唾をつけてたんだ?」
「唾をつけるだなんて……そんな……」
そう言いかけて思い出す。
そう言えば二年前、彼らのために旧武器庫の片付けをしたことがあった。
もしかしてそのことを覚えていてくれたのだろうか?
「まあ、勇者とは言え子どもの相手なんて面倒だろうが――」
「いえっ! その役目、このケイルが身命をもって引き受けさせていただきます!」
「……そ、そうか。まあ、お前なら大丈夫だろう。必要ならお前の同期連中にも手伝わせたっていいぞ。勇者の成長はこの国にとっても重要だからな」
「はい! 承知しました!」
確かに、近衛騎士という立場まで得て、勇者とは言え子どもの世話のようなことをさせられるというのは普通なら嫌なのかもしれない。
だが、ケイルの頭にはそんな考えの一切がなかった。
彼にとっては、自分がちゃんと誰かの役に立てたというその実感だけで十分だったのだ。
「今日から訓練のお相手を務めるケイルです。よろしくお願いします」
翌日、早速勇者のもとを訪れたケイルは張り切って自己紹介をした。
「こちらこそよろしくお願いします! でも、ケイルさんの方が年上なんだから、敬語じゃなくていいですよ。俺のことも■■■■って呼んでください!」
「そうで――そうか。わかった。じゃあ、■■■■も今日から俺には敬語じゃなくていいぞ! 訓練、頑張ろうな?」
「はい!」
こうしてケイルと少年は毎日のように刃を交えるようになっていった。
◇◇◇
不思議な夢はまだまだ続く。
――あれからさらに七年後。
ケイルは二十七歳、■■■■とミア王女は十五歳になった。
「■■■■、ケイルさんたちもそろそろ休憩してはどうですか?」
最近の■■■■はめっきり訓練に打ち込むようになり、二人でいる姿を見ることは減っていたが、こうして時間を見つけてはミア王女は■■■■に会いに来る。
誰の目から見ても分かりやすい王女を■■■■と仲のいい騎士たちは皆、応援していた。
「お、ミア! そっちはもう終わったのか?」
「はい! ですから昼食をご一緒しませんか?」
ミア王女は持っていたバスケットを掲げてみせる。
なんと健気なことだろうか。
だが、この■■■■という青年は、戦闘のセンスは冴えわたっているというのにこういった面に関してはてんで鈍感なのだ。
「いいね! ケイル、みんなも行こうぜ!」
ケイルは申し訳なさげにミア王女に目配せする。
ミアはそれに肩をすくめて応じ、結局みんなでの昼食となった。
きっと、この二人は距離が近すぎたのだろう。
中々進展のないまま時間だけが過ぎていき、とうとう、そんな王女の健気な姿は娘を溺愛する国王の耳にも届いた。
「ふむ、そうか……。確かに■■■■にとってはミアが傍にいることが当たり前になっているのかもしれぬな」
報告を受けながら国王は一つ妙案を思いついた。
「ならば一度、離してしまえばよいのではないか? うむ、そろそろミアも■■■■も十六、一度任務を与えてみるか」
そして、■■■■が十六歳になるその日に国王は勇者として■■■■を呼び出した。
「■■■■よ。現在の人魔戦線の状況は知っているか?」
「はい、比較的落ち着いており膠着状態にあると」
「うむ、その通りだ。だからこそ、今魔族というものを知っておくべきだとは思わないか?」
「……役目を果たすとき、ということでしょうか」
王の誤算はただ一つ。
■■■■の覚悟を甘く見過ぎていたということだ。
「うむ、実戦もまた訓練になるだろう。どうだ?」
「その通りかと」
「よし、では■■■■よ。そなたに勇者としての役目を果たす機会を与える」
「はっ! 謹んでお受けいたします」
国王としては一、二年現場を見て帰還してくれれば良いと思っていた。
そもそも、魔族による被害はあっても、それは魔物による被害とさほど変わらない数であり、本当に魔王との対戦になるとは微塵も思っていなかった。
――その夜。
なんとなく、懐かしい旧武器庫周辺を歩いていたケイルはその声を聞いた。
「本当に行ってしまうのですか?」
「ああ、だって約束しただろう? それに俺は勇者だからさ」
「……あなたはそういう人でしたね」
「寂しくても泣くなよ?」
「……」
「……そこは言い返してほしかったんだけど」
「……絶対生きて、帰ってきてください」
「当たり前だ。俺は勇者だからな! 死んでちゃ、誰の希望にもなれない」
「そう言うことじゃありません! 私はあなたに……!」
「大丈夫だ。ここに来てからずっと訓練を続けて来た。ケイルや近衛騎士の皆、それにミアにもずっと支えられてきた。だから俺は役目をはたして、その恩に報いたいんだ」
「■■■■……」
そこまで聞いて、ケイルは走り出していた。
当人たちも涙をこらえているだろうに、自分の声で雰囲気を壊したくないと思って。
その日は一晩中ケイルは走り込んでいた。
そして翌日。
「じゃあ、行ってくる」
いつの間にか、王城中の全員の勇者になっていた彼はそれだけ言って、旅立っていった。
あまりに眩しい彼の光は、皆に希望を与えると同時にそれに触れられるものもいないとでも言うような孤高の光で、彼の背中を追えるものは誰もいなかった。
◇◇◇
あれから十年の月日が流れた。
遂に訪れたその知らせは何より早く、王国中に知れ渡った。
魔王討伐。
それを聞いた民衆は大いに盛り上がり、もちろん俺たちも肩を抱き合って喜んだ。
過去一度しか達成されていないその偉業を自らが生きている間に目にすることができるとは、と。
だが、帰ってきた彼には、もう、かつてのような目も眩むような光は見えなかった。
気を抜いたら、いつのまにか目の前からいなくなってしまいそうな、そんな雰囲気を纏っていた。
「――ス」
………………
………………
………………
ドンドンと扉を叩く音が聞こえる。
「副隊長~? あれ、寝てるのか?」
この声は……ダンカン?
寝ぼけた頭がだんだんと覚醒していく。
ここは……宿? そう言えば、俺はミア王女の任務で……。
「副隊長ー! 夕食の時間らしいですよ~!」
なにか、大切な夢を見ていた気がするが……なおも扉を叩いてくるダンカンのせいで思考がまとまらない。
……まあ、本当に大切なことならいつかきっと思いだすか。
そう考えたケイルはやかましいダンカンを叱るべく、起き上がる。
「ダンカンっ! ここは寮じゃないんだぞっ! 普段のつもりで扉を叩くんじゃない!」
「すっ、すみません!」
幻妖の羊の寝具には夢見をよくする力がある。
その力は夢を見る者の最も大切な過去を見せることが多いのだとか。
そのことをケイルが知る日が来るのかは定かではないが、おそらく彼にとっての大切な記憶はどんな魔法でもなかったことにはできないのだろう。
それはまるで本当だったかのように現実的で、それでいてあり得ない、そんな存在しない記憶を追体験するような夢だった。
◇◇◇
「なあ、ケイル聞いたか?」
騎士見習いとして、ともに訓練に励む仲間がランニング中のケイルに合流しつつ話しかけて来た。
「なんだよ?」
「今日から王城に勇者が来るらしいぞ?」
こいつ仲間の間でも中々の情報通というか、ゴシップ好きでよくこうしてケイルに嘘か本当か怪しい情報を垂れ込んでいた。
「勇者だぁ? バカ言え、もう何年も現れてないっていう伝説上の存在だろ? それとも昨日今日生まれたばかりの赤ん坊が来るとでも言うのかよ」
勇者、その存在は王国に生まれる者ならば知らない者はいない。
だが、だからこそ、勇者という存在は伝説的で象徴的なものなのだ。
そう思ったケイルは、嘘だろうと言う確信をもってそう言った。
「おう、そうらしい。しかも、親元からは引き離されてな」
しかし、どうやらその嘘の通りらしい。
それも、生まれたばかりの子供を親元から引き離すというおまけつき。
「……はぁ!? 何だよそれ? さすがに可哀そうすぎるだろ!」
正義感の強いケイルは憤った。
「まあ、そうだよな。でも俺たちにはどうしようもないさ」
だが、この憤りは無意味なものだ。
今のケイルはただの騎士見習い、権力どころかその権力に跪く存在ですらないのだ。
「……」
無言でランニングのペースを上げる。
「おいっ! そんなスピードじゃ、絶対最後まで持たないぞ!」
ケイルはこの行き場のない怒りを全て訓練にぶつけることにした。
◇◇◇
――六年後。
実力を認められたケイルは十八にして異例の近衛騎士隊入りを果たした。
そしてそこではじめて彼と出会ったのだ。
「■■■■! 待ってください!」
「待っててやるから、転ぶなよミア!」
王女と共に場内を元気に駆け回る少年。
一目見て、理解した。
彼は本物だ、と。
なぜかその彼の姿がまるで破り取られたかのように黒く見えないが、そんな確信を覚えた。
「はぁはぁ……今日はどこに行くのですか?」
「いいとこを見つけたんだ!」
「いいところ?」
「まあ、着けばわかるから、な?」
「歩いて行けばいいじゃないですか! もうっ! 待ってください!」
走っていく幼い彼らが眩しくて、ケイルは二人を追いかけた。
大人の足と子どもの足、それにミア王女を連れている彼に追いつくのは容易いことだった。
「あそこは確か……」
少年とミア王女はもう誰も近づかなくなった旧武器庫へと入っていった。
何となくバレないように後をつけてきてしまったが、流石に武器庫内で王女に怪我でもあれば一大事だ。
そう思ったケイルは注意をしに二人の後について、武器庫内に入った。
「どうだ? ミア。すごいだろ! ここはもう使われてない倉庫なんだってさ!」
何故か姿の見えない少年が嬉しそうにミア王女に自慢している。
「こんなところ……入ってしまっていいのでしょうか?」
「大丈夫大丈夫、バレなきゃ平気だっ――」
自信満々に言おうとした少年と思しき黒い影は少し遅れて武器庫内に入って来たケイルと目が合ってしまいそこで言葉を止めた。
「■■■■? どうしたのですか?」
ミア王女はまだ気がついていないようだった。
そのためケイルはなるべく驚かせないようにやさしい声で伝える。
「お二人とも、ここはもう使われなくなったとはいえ、危険物もある武器庫です。さぁ、もう戻りましょう?」
「騎士さん!? いつの間に……」
少し驚かせてしまったようだが、この程度ならば上出来だろう。
「さぁ、こちらへ」
「■■■■、騎士さんもああ言っていることですし、戻りましょう」
「ああ、分かったよ……」
不服そうな声ではあるが、物わかりの良い子そうで助かった。
……あ、そうだ!
「心配しなくても平気ですよ。ここは私が時間のある時に片付けておきますから、そしたらお二人の遊び場でも秘密基地にでもしてください」
この子達は生まれてすぐに役割を与えられ、きっと今日も何かの時間を縫って、二人で遊んでいたのだろう。
そんな二人の遊び場を取り上げるのは違うとケイルは思った。
バレれば大目玉を食らうこと間違いないだろうが、その時はその時だ。
「いいんですか?」
影の少年が途端に態度を和らげる。
可愛い奴だなとケイルは思った。
「ええ、もちろん。でも、遊ぶときは気を付けてくださいね?」
「わかりました!」
「良かったですね■■■■!」
「ああ!」
この子が勇者であろうとこの眩しい笑顔を守ってやりたいとそう思った。
◇◇◇
――二年後。
ケイルは二十歳、少年とミア王女が八歳になる年にその少年は頭角を現し始めた。
幼いが子供用の剣ならば振り回されない程の力がついてきて、彼はその才能を如何なく発揮するようになった。
はじめは歳の近い騎士見習いとの対決だった。
しかし、歳が近いとは言っても騎士見習いになれるのは十二歳から、子どもの四歳差とはあまりにも大きいと誰もが思っていた。
だが、そんな心配は杞憂だった。
模擬戦開始の合図とともに、少年は目にも留まらぬ速さで加速した。
訓練を続けて来たケイルですら、そのざまだったのだ。
対戦相手の騎士見習いが見えるはずもなく、その模擬戦は文字通りの一瞬で決着した。
「ありがとうございました」
言葉を失っていた観衆は少年のその言葉で大歓声を上げ、それからしばらくして俺たち騎士の間であの少年が話題に上がらない日はなくなった。
そんなある日、ケイルは近衛騎士隊隊長に呼び出されていた。
「お呼びで在りましょうか、隊長!」
「うむ、急に呼んで悪いなケイル」
「いえ、ご命令とあれば、いつどこにでも!」
「ははっ、相変わらずお前は真面目だな。だが、今回はその真面目さと先方の意向がうまく合致したようだ。お前になら安心して任せられる」
「……一体、何を?」
「ケイル、お前に勇者の訓練相手となる任を与える」
「!? 私、ですか!?」
「ああ、どうやら勇者くんきっての意向らしいぞ? お前いつの間に唾をつけてたんだ?」
「唾をつけるだなんて……そんな……」
そう言いかけて思い出す。
そう言えば二年前、彼らのために旧武器庫の片付けをしたことがあった。
もしかしてそのことを覚えていてくれたのだろうか?
「まあ、勇者とは言え子どもの相手なんて面倒だろうが――」
「いえっ! その役目、このケイルが身命をもって引き受けさせていただきます!」
「……そ、そうか。まあ、お前なら大丈夫だろう。必要ならお前の同期連中にも手伝わせたっていいぞ。勇者の成長はこの国にとっても重要だからな」
「はい! 承知しました!」
確かに、近衛騎士という立場まで得て、勇者とは言え子どもの世話のようなことをさせられるというのは普通なら嫌なのかもしれない。
だが、ケイルの頭にはそんな考えの一切がなかった。
彼にとっては、自分がちゃんと誰かの役に立てたというその実感だけで十分だったのだ。
「今日から訓練のお相手を務めるケイルです。よろしくお願いします」
翌日、早速勇者のもとを訪れたケイルは張り切って自己紹介をした。
「こちらこそよろしくお願いします! でも、ケイルさんの方が年上なんだから、敬語じゃなくていいですよ。俺のことも■■■■って呼んでください!」
「そうで――そうか。わかった。じゃあ、■■■■も今日から俺には敬語じゃなくていいぞ! 訓練、頑張ろうな?」
「はい!」
こうしてケイルと少年は毎日のように刃を交えるようになっていった。
◇◇◇
不思議な夢はまだまだ続く。
――あれからさらに七年後。
ケイルは二十七歳、■■■■とミア王女は十五歳になった。
「■■■■、ケイルさんたちもそろそろ休憩してはどうですか?」
最近の■■■■はめっきり訓練に打ち込むようになり、二人でいる姿を見ることは減っていたが、こうして時間を見つけてはミア王女は■■■■に会いに来る。
誰の目から見ても分かりやすい王女を■■■■と仲のいい騎士たちは皆、応援していた。
「お、ミア! そっちはもう終わったのか?」
「はい! ですから昼食をご一緒しませんか?」
ミア王女は持っていたバスケットを掲げてみせる。
なんと健気なことだろうか。
だが、この■■■■という青年は、戦闘のセンスは冴えわたっているというのにこういった面に関してはてんで鈍感なのだ。
「いいね! ケイル、みんなも行こうぜ!」
ケイルは申し訳なさげにミア王女に目配せする。
ミアはそれに肩をすくめて応じ、結局みんなでの昼食となった。
きっと、この二人は距離が近すぎたのだろう。
中々進展のないまま時間だけが過ぎていき、とうとう、そんな王女の健気な姿は娘を溺愛する国王の耳にも届いた。
「ふむ、そうか……。確かに■■■■にとってはミアが傍にいることが当たり前になっているのかもしれぬな」
報告を受けながら国王は一つ妙案を思いついた。
「ならば一度、離してしまえばよいのではないか? うむ、そろそろミアも■■■■も十六、一度任務を与えてみるか」
そして、■■■■が十六歳になるその日に国王は勇者として■■■■を呼び出した。
「■■■■よ。現在の人魔戦線の状況は知っているか?」
「はい、比較的落ち着いており膠着状態にあると」
「うむ、その通りだ。だからこそ、今魔族というものを知っておくべきだとは思わないか?」
「……役目を果たすとき、ということでしょうか」
王の誤算はただ一つ。
■■■■の覚悟を甘く見過ぎていたということだ。
「うむ、実戦もまた訓練になるだろう。どうだ?」
「その通りかと」
「よし、では■■■■よ。そなたに勇者としての役目を果たす機会を与える」
「はっ! 謹んでお受けいたします」
国王としては一、二年現場を見て帰還してくれれば良いと思っていた。
そもそも、魔族による被害はあっても、それは魔物による被害とさほど変わらない数であり、本当に魔王との対戦になるとは微塵も思っていなかった。
――その夜。
なんとなく、懐かしい旧武器庫周辺を歩いていたケイルはその声を聞いた。
「本当に行ってしまうのですか?」
「ああ、だって約束しただろう? それに俺は勇者だからさ」
「……あなたはそういう人でしたね」
「寂しくても泣くなよ?」
「……」
「……そこは言い返してほしかったんだけど」
「……絶対生きて、帰ってきてください」
「当たり前だ。俺は勇者だからな! 死んでちゃ、誰の希望にもなれない」
「そう言うことじゃありません! 私はあなたに……!」
「大丈夫だ。ここに来てからずっと訓練を続けて来た。ケイルや近衛騎士の皆、それにミアにもずっと支えられてきた。だから俺は役目をはたして、その恩に報いたいんだ」
「■■■■……」
そこまで聞いて、ケイルは走り出していた。
当人たちも涙をこらえているだろうに、自分の声で雰囲気を壊したくないと思って。
その日は一晩中ケイルは走り込んでいた。
そして翌日。
「じゃあ、行ってくる」
いつの間にか、王城中の全員の勇者になっていた彼はそれだけ言って、旅立っていった。
あまりに眩しい彼の光は、皆に希望を与えると同時にそれに触れられるものもいないとでも言うような孤高の光で、彼の背中を追えるものは誰もいなかった。
◇◇◇
あれから十年の月日が流れた。
遂に訪れたその知らせは何より早く、王国中に知れ渡った。
魔王討伐。
それを聞いた民衆は大いに盛り上がり、もちろん俺たちも肩を抱き合って喜んだ。
過去一度しか達成されていないその偉業を自らが生きている間に目にすることができるとは、と。
だが、帰ってきた彼には、もう、かつてのような目も眩むような光は見えなかった。
気を抜いたら、いつのまにか目の前からいなくなってしまいそうな、そんな雰囲気を纏っていた。
「――ス」
………………
………………
………………
ドンドンと扉を叩く音が聞こえる。
「副隊長~? あれ、寝てるのか?」
この声は……ダンカン?
寝ぼけた頭がだんだんと覚醒していく。
ここは……宿? そう言えば、俺はミア王女の任務で……。
「副隊長ー! 夕食の時間らしいですよ~!」
なにか、大切な夢を見ていた気がするが……なおも扉を叩いてくるダンカンのせいで思考がまとまらない。
……まあ、本当に大切なことならいつかきっと思いだすか。
そう考えたケイルはやかましいダンカンを叱るべく、起き上がる。
「ダンカンっ! ここは寮じゃないんだぞっ! 普段のつもりで扉を叩くんじゃない!」
「すっ、すみません!」
幻妖の羊の寝具には夢見をよくする力がある。
その力は夢を見る者の最も大切な過去を見せることが多いのだとか。
そのことをケイルが知る日が来るのかは定かではないが、おそらく彼にとっての大切な記憶はどんな魔法でもなかったことにはできないのだろう。