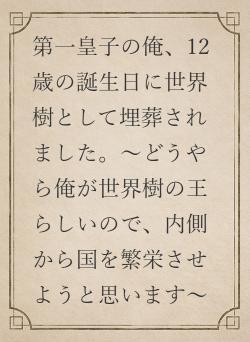「ああ、すみません! 私たちは王国第二近衛騎士隊の者です! ここへは魔族の被害を受け壊滅した村があるという話を伺い、その調査に来ました! ここの住民の方ですか?」
ケイルではない方のまだ若い騎士が俺たちにそう説明する。
「あ、ああ、そうなんですね。……まあ、私たちはここの住民のようなものです。最近戻って来たばかりなのですが……」
突然の再会に目を向いてしまったが、真面目な若い騎士のおかげで何とか平静を装うことができた。
そして俺の言葉を聞くと、同じく固まっていたケイルが口を開く。
「……ここは旅人の宿と書いてありましたが、お二人で経営されているのですか?」
どうやら、俺の正体に気が付いたわけではないようだ。
まあ、魔王の魔法を使ったのだから、大丈夫だとは思っていたが。
「はい……あ、私はここの店主のファレスと言います。こっちは従業員のネイロスです」
「ネイロスと申します」
ネイロスが悠然と挨拶をする。
その姿は上流階級の淑女を思わせるような礼儀正しさで、いつもの天真爛漫な姿とはかけ離れている。
口調を直そうとは言ったが、ここまでできるのか……それともこっちのほうが慣れていたりするのだろうか?
何にせよ、ネイロスに接客の心配もなさそうで安心し、このおかげで俺は完全に、不意の再会で崩した調子を取り戻すことができた。
「これはご丁寧に……副隊長?」
だが――
「もし、勘違いならば申し訳ないのですが、ファレスさん、私たちは何処かであったことがありませんか? どこか、懐かしい空気を感じた気がしたんですが……」
俺の名を聞き違和感を覚えていたのか。
まっすぐ俺を見つめて、ケイルがそう聞いてくる。
「……いえ、王都には行ったことがありますが、近衛騎士さんのお世話になったことはありませんよ」
「……そうですか。失礼しました。私は第二近衛騎士隊で副隊長を務めているケイルと申します。こちらは部下のダンカン」
「ダンカンです!」
あの真摯な目に嘘で答えるのは流石に苦しかったが、いたずらに話して記憶を混濁させるのは俺も本意ではない。
そう考えて、話を逸らした。
「それで、ここには調査を? 滞在はされるのですか?」
「ええ、ここで十四日ほど視察をしたいと考えているのですが……」
そう言いかけてケイルはうちの内装を見回した。
ああ、いかにも高そうだもんなうち……看板は出しているが、見ていなければ衝撃的な値段を恐れるその気持ちもわかる。
そう思って価格を伝えようとしたところ、タイミングよくネイロスがうちの料金表をダンカンに見せていた。
「副隊長! 見てくださいよこれ! 一人一泊小銀貨一枚!」
そして、それを見たダンカンがあまりの衝撃からか、先ほどまでの丁寧な様子を忘れ、隠しきれない興奮を訴えかけるようにケイルに伝えた。
「おいダンカン、何を言っている? こんな宿がそんな値段のはずがないだろう! あまり失礼なことを……」
そう言いながらダンカンに渡された表を見て、ケイルは絶句した。
「……これは、本当に?」
「ええ、もちろん。私たちはお客様第一でサービスをしていますので」
「副隊長! これはもう泊まらせてもらいましょうよ! 夕食まで出してもらえるみたいですよ!」
「あ、ああ……そうだな。では」
そう言ってケイルは小金貨三枚を取り出すと俺に渡してきた。
「十四泊でよろしいでしょうか? するとおつりは……」
「ああ、おつりは大丈夫です。外の厩を勝手に使わせていただいてしまっていますし」
こういう時は下手に断るべきではないか。
客商売は相手を立てることも重要だ。
俺はそれをそのまま受け取り、一人部屋の鍵を二つ取り出すと受付のカウンターを出た。
「ありがとうございます。ではお部屋にご案内いたしますね。ネイロス、厩の馬に水を飲ませてやってくれるか?」
「わかりました」
こちらに軽く頭を下げて厩に向かうネイロスを見るとダンカンが俺に声をかけてきた。
「馬にまでお気遣いありがとうございます。ですが、私の馬は中々に気性の荒い馬でして、代わって来ても?」
ああ、今のネイロスはうちの看板娘のようにしか見えないもんな。
だが、うちの看板娘にはそう言った気遣いは不要だ。
「そうなんですか。でも大丈夫だと思いますよ。うちのネイロスは優秀ですから。それでもと言うのならまずは荷物を置いてからでも十分ですよ」
「ファレスさんがそうおっしゃるのでしたら……ですがやはり心配ですので、少し急ぎましょう」
「承知しました。一人部屋は三階ですので、足元にはお気を付けください」
若干の速足で部屋の前まで二人を案内する。
「こちらの部屋でいかがでしょう? 今は他にお客様はいませんので、別のお部屋をご案内することも可能ですが……」
俺が案内したのは先日、ユーリとアメリに案内したような互いに向かい合った一人部屋だった。
「いえ、ありがとうございます」
「では、こちらが部屋の鍵になります。他のお客様はいらっしゃらないので問題になることはないかと存じますが念のため、お部屋を出る際には戸締りの方をよろしくお願いいたします」
「ご丁寧にありがとうございます」
一礼してその場を後にする。
背後からは〈洗浄〉の魔法が仕込まれた絨毯に驚く二人の声が聞えて来た。
◇◇◇
鎧を外し、数日ぶりにしっかりと休める環境にたどり着いたケイルは衝撃の連続で逆に疲れてしまっていた。
「ほんと……なんなんだよここは」
立派な外装の屋敷だと思い近づいてみれば、まさかの宿屋で宿泊料は大銀貨一枚、各部屋に別々の鍵が付いているだけでなく、近衛騎士隊としてそこそこ給料をもらっている自分でも手が出ないような寝具一式に〈洗浄〉の魔法で全身の汚れを入口で落とさせるという完璧なサービス。
「王城よりも快適だぞ? それに……」
ケイルはこの宿に入った時にファレスが口にしたことを聞き逃していなかった。
「あの店主……俺の顔を見るなりすぐに名前を……」
自分で言うようなことではないが、ケイルは王都ではそこそこの有名人だ。
騎士見習いの頃から、街で罪を犯す者は絶対に見逃さないという自負を持ち、近衛となっても街のことを考える姿勢を貫いてきた彼は多くの市民から好印象を持たれている。
だから、知られているというのは別段特に珍しいことではない。
だが、あの反応は流石に気になった。
そして、ケイル自身にも妙な感覚、あのファレスという店主に対してなんとなくの既視感を覚えていた。
「まあ、今考えても仕方ないか」
わからないことをくよくよ悩むのはケイルの性に合っていない。
どうせここには十四日間も滞在するのだ。
その間にゆっくりと思いだせばいいだろう。
「なにより……今はそれ以上に」
眼下に広がる、明らかに寝心地のよさそうなベッドに向き合う。
先ほどから、このベッドが気になって仕方がなかったのだ。
ダンカンはあのネイロスという娘が心配だったようで見に行ったし、今日くらいは自由に過ごしてもいいだろう。
副隊長として部下より先に休むことには気が引けていたが、このベッドの魅力はそんな葛藤を打ち破るには十分すぎる魅力を放っていた。
「失礼します」
まるで借りてきた猫のような自分に内心苦笑しながらも、そのベッドに腰かけた。
「うおっ!? なんだこれ!?」
腰を掛けた瞬間、聖母に抱かれたかのような感じたことのない心地良さに包まれる。
「これは……無理、だろ……」
そのあまりの心地良さに長旅で疲れ切ったケイルは、途端に襲ってきた眠気に抗うことができず、深い眠りに落ちていった。
◇◇◇
〈洗浄〉の魔法がかけられた絨毯には驚かされたが、今のダンカンにはそれ以上に気がかりなことがあった。
「ファレスさんはああ言っていたが、アロのやつは人見知りが激しいからな」
アロとはダンカンがここまで乗って来た愛馬の名である。
ダンカンは彼と心を通わせ、背に乗せてもらえるようになるまで非常に時間がかかったため、その苦労を文字通り痛いほど理解していた。
手早く鎧を外し、薄着になるとすぐに部屋を飛び出す。
そして……
走って向かった厩で衝撃の光景を目撃した。
「ブルルルゥ」
「そうかそうか、お前の主は良い方なんだな」
自ら首をネイロスに擦り付けて嬉しそうな声で鳴いている愛馬がそこにはいた。
「アロ!? お前、俺にもそんな態度みせたことないのに!?」
「これはダンカンさん。この子はアロというのですか?」
こちらを向いて軽く頭を下げるネイロスを見て、ダンカンは彼女に自分とは違う何かを感じた。
立ちはだかる者には畏怖を与え、付き従う者には圧倒的なまでのカリスマ性で好まれる。
まるで王のような気概をネイロスは放っていると、そう感じさせられた。
「え、ええ。なかなか気難しい奴なんですが……凄いですね」
「ふふっ、ありがとうございます。昔から動物には好かれるのです。特に最近、身を持って体験したおかげで気持ちもある程度は分かるようになりましたし……」
「は、はぁ? そうなんですね?」
ネイロスの落ち着いた仕草に、ダンカンは思わず敬語になっていた。
「とても良い馬ですね。よく手入れされていますし、心も穏やかです。大切にされているのが伝わります」
「い、いえ……まだまだ至らないところも多くて……でも、ありがとうございます」
ネイロスの言葉はどこか不思議な説得力と安心感を持つ物だった。
「もうしばらくすれば夕食の準備が整いますので、それまでごゆっくり」
「……はい!」
彼女の一礼に背を向けて歩き出しながら、ダンカンは一人ごちる。
「……あの人、本当に従業員なんだよな?」
まるで、何か大きなものを背負っているような…そんな風格すら感じてしまう存在感。
しかし、それ以上に強く感じるのは——
「すごく……格好いい、な」
ネイロスの姿を見送る彼の視線は、憧れと尊敬を持つ物に変わっていた。
ケイルではない方のまだ若い騎士が俺たちにそう説明する。
「あ、ああ、そうなんですね。……まあ、私たちはここの住民のようなものです。最近戻って来たばかりなのですが……」
突然の再会に目を向いてしまったが、真面目な若い騎士のおかげで何とか平静を装うことができた。
そして俺の言葉を聞くと、同じく固まっていたケイルが口を開く。
「……ここは旅人の宿と書いてありましたが、お二人で経営されているのですか?」
どうやら、俺の正体に気が付いたわけではないようだ。
まあ、魔王の魔法を使ったのだから、大丈夫だとは思っていたが。
「はい……あ、私はここの店主のファレスと言います。こっちは従業員のネイロスです」
「ネイロスと申します」
ネイロスが悠然と挨拶をする。
その姿は上流階級の淑女を思わせるような礼儀正しさで、いつもの天真爛漫な姿とはかけ離れている。
口調を直そうとは言ったが、ここまでできるのか……それともこっちのほうが慣れていたりするのだろうか?
何にせよ、ネイロスに接客の心配もなさそうで安心し、このおかげで俺は完全に、不意の再会で崩した調子を取り戻すことができた。
「これはご丁寧に……副隊長?」
だが――
「もし、勘違いならば申し訳ないのですが、ファレスさん、私たちは何処かであったことがありませんか? どこか、懐かしい空気を感じた気がしたんですが……」
俺の名を聞き違和感を覚えていたのか。
まっすぐ俺を見つめて、ケイルがそう聞いてくる。
「……いえ、王都には行ったことがありますが、近衛騎士さんのお世話になったことはありませんよ」
「……そうですか。失礼しました。私は第二近衛騎士隊で副隊長を務めているケイルと申します。こちらは部下のダンカン」
「ダンカンです!」
あの真摯な目に嘘で答えるのは流石に苦しかったが、いたずらに話して記憶を混濁させるのは俺も本意ではない。
そう考えて、話を逸らした。
「それで、ここには調査を? 滞在はされるのですか?」
「ええ、ここで十四日ほど視察をしたいと考えているのですが……」
そう言いかけてケイルはうちの内装を見回した。
ああ、いかにも高そうだもんなうち……看板は出しているが、見ていなければ衝撃的な値段を恐れるその気持ちもわかる。
そう思って価格を伝えようとしたところ、タイミングよくネイロスがうちの料金表をダンカンに見せていた。
「副隊長! 見てくださいよこれ! 一人一泊小銀貨一枚!」
そして、それを見たダンカンがあまりの衝撃からか、先ほどまでの丁寧な様子を忘れ、隠しきれない興奮を訴えかけるようにケイルに伝えた。
「おいダンカン、何を言っている? こんな宿がそんな値段のはずがないだろう! あまり失礼なことを……」
そう言いながらダンカンに渡された表を見て、ケイルは絶句した。
「……これは、本当に?」
「ええ、もちろん。私たちはお客様第一でサービスをしていますので」
「副隊長! これはもう泊まらせてもらいましょうよ! 夕食まで出してもらえるみたいですよ!」
「あ、ああ……そうだな。では」
そう言ってケイルは小金貨三枚を取り出すと俺に渡してきた。
「十四泊でよろしいでしょうか? するとおつりは……」
「ああ、おつりは大丈夫です。外の厩を勝手に使わせていただいてしまっていますし」
こういう時は下手に断るべきではないか。
客商売は相手を立てることも重要だ。
俺はそれをそのまま受け取り、一人部屋の鍵を二つ取り出すと受付のカウンターを出た。
「ありがとうございます。ではお部屋にご案内いたしますね。ネイロス、厩の馬に水を飲ませてやってくれるか?」
「わかりました」
こちらに軽く頭を下げて厩に向かうネイロスを見るとダンカンが俺に声をかけてきた。
「馬にまでお気遣いありがとうございます。ですが、私の馬は中々に気性の荒い馬でして、代わって来ても?」
ああ、今のネイロスはうちの看板娘のようにしか見えないもんな。
だが、うちの看板娘にはそう言った気遣いは不要だ。
「そうなんですか。でも大丈夫だと思いますよ。うちのネイロスは優秀ですから。それでもと言うのならまずは荷物を置いてからでも十分ですよ」
「ファレスさんがそうおっしゃるのでしたら……ですがやはり心配ですので、少し急ぎましょう」
「承知しました。一人部屋は三階ですので、足元にはお気を付けください」
若干の速足で部屋の前まで二人を案内する。
「こちらの部屋でいかがでしょう? 今は他にお客様はいませんので、別のお部屋をご案内することも可能ですが……」
俺が案内したのは先日、ユーリとアメリに案内したような互いに向かい合った一人部屋だった。
「いえ、ありがとうございます」
「では、こちらが部屋の鍵になります。他のお客様はいらっしゃらないので問題になることはないかと存じますが念のため、お部屋を出る際には戸締りの方をよろしくお願いいたします」
「ご丁寧にありがとうございます」
一礼してその場を後にする。
背後からは〈洗浄〉の魔法が仕込まれた絨毯に驚く二人の声が聞えて来た。
◇◇◇
鎧を外し、数日ぶりにしっかりと休める環境にたどり着いたケイルは衝撃の連続で逆に疲れてしまっていた。
「ほんと……なんなんだよここは」
立派な外装の屋敷だと思い近づいてみれば、まさかの宿屋で宿泊料は大銀貨一枚、各部屋に別々の鍵が付いているだけでなく、近衛騎士隊としてそこそこ給料をもらっている自分でも手が出ないような寝具一式に〈洗浄〉の魔法で全身の汚れを入口で落とさせるという完璧なサービス。
「王城よりも快適だぞ? それに……」
ケイルはこの宿に入った時にファレスが口にしたことを聞き逃していなかった。
「あの店主……俺の顔を見るなりすぐに名前を……」
自分で言うようなことではないが、ケイルは王都ではそこそこの有名人だ。
騎士見習いの頃から、街で罪を犯す者は絶対に見逃さないという自負を持ち、近衛となっても街のことを考える姿勢を貫いてきた彼は多くの市民から好印象を持たれている。
だから、知られているというのは別段特に珍しいことではない。
だが、あの反応は流石に気になった。
そして、ケイル自身にも妙な感覚、あのファレスという店主に対してなんとなくの既視感を覚えていた。
「まあ、今考えても仕方ないか」
わからないことをくよくよ悩むのはケイルの性に合っていない。
どうせここには十四日間も滞在するのだ。
その間にゆっくりと思いだせばいいだろう。
「なにより……今はそれ以上に」
眼下に広がる、明らかに寝心地のよさそうなベッドに向き合う。
先ほどから、このベッドが気になって仕方がなかったのだ。
ダンカンはあのネイロスという娘が心配だったようで見に行ったし、今日くらいは自由に過ごしてもいいだろう。
副隊長として部下より先に休むことには気が引けていたが、このベッドの魅力はそんな葛藤を打ち破るには十分すぎる魅力を放っていた。
「失礼します」
まるで借りてきた猫のような自分に内心苦笑しながらも、そのベッドに腰かけた。
「うおっ!? なんだこれ!?」
腰を掛けた瞬間、聖母に抱かれたかのような感じたことのない心地良さに包まれる。
「これは……無理、だろ……」
そのあまりの心地良さに長旅で疲れ切ったケイルは、途端に襲ってきた眠気に抗うことができず、深い眠りに落ちていった。
◇◇◇
〈洗浄〉の魔法がかけられた絨毯には驚かされたが、今のダンカンにはそれ以上に気がかりなことがあった。
「ファレスさんはああ言っていたが、アロのやつは人見知りが激しいからな」
アロとはダンカンがここまで乗って来た愛馬の名である。
ダンカンは彼と心を通わせ、背に乗せてもらえるようになるまで非常に時間がかかったため、その苦労を文字通り痛いほど理解していた。
手早く鎧を外し、薄着になるとすぐに部屋を飛び出す。
そして……
走って向かった厩で衝撃の光景を目撃した。
「ブルルルゥ」
「そうかそうか、お前の主は良い方なんだな」
自ら首をネイロスに擦り付けて嬉しそうな声で鳴いている愛馬がそこにはいた。
「アロ!? お前、俺にもそんな態度みせたことないのに!?」
「これはダンカンさん。この子はアロというのですか?」
こちらを向いて軽く頭を下げるネイロスを見て、ダンカンは彼女に自分とは違う何かを感じた。
立ちはだかる者には畏怖を与え、付き従う者には圧倒的なまでのカリスマ性で好まれる。
まるで王のような気概をネイロスは放っていると、そう感じさせられた。
「え、ええ。なかなか気難しい奴なんですが……凄いですね」
「ふふっ、ありがとうございます。昔から動物には好かれるのです。特に最近、身を持って体験したおかげで気持ちもある程度は分かるようになりましたし……」
「は、はぁ? そうなんですね?」
ネイロスの落ち着いた仕草に、ダンカンは思わず敬語になっていた。
「とても良い馬ですね。よく手入れされていますし、心も穏やかです。大切にされているのが伝わります」
「い、いえ……まだまだ至らないところも多くて……でも、ありがとうございます」
ネイロスの言葉はどこか不思議な説得力と安心感を持つ物だった。
「もうしばらくすれば夕食の準備が整いますので、それまでごゆっくり」
「……はい!」
彼女の一礼に背を向けて歩き出しながら、ダンカンは一人ごちる。
「……あの人、本当に従業員なんだよな?」
まるで、何か大きなものを背負っているような…そんな風格すら感じてしまう存在感。
しかし、それ以上に強く感じるのは——
「すごく……格好いい、な」
ネイロスの姿を見送る彼の視線は、憧れと尊敬を持つ物に変わっていた。