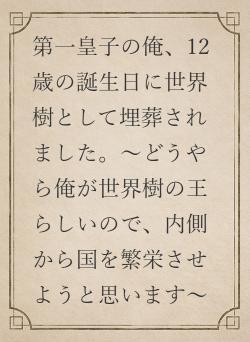「客が……来ない」
ユーリとアメリが去ってから結構な月日が流れた。
その間、俺がしたことと言えば日々の掃除に洗濯、食材の調達など、ごく普通の隠居生活のようなことばかりだった。
「いや、一応それだけではないか……」
宿の外に出て入浴施設の反対側へ歩く。
「勢い余ってこんな物を作ったんだよな……うん、立派な厩だ」
ユーリとアメリが去った後、初の接客を終えてテンションが上がっていた俺は勢いそのままに、旅人や探索者なら馬に乗っている人もいるよな! と言う全く根拠のない考えだけで厩を建ててしまったのだ。
建ててしまったというよりかは、「厩、必要だよな……場所はこの辺りかな?」とひとりでに考えているうちに〈仲間に捧げる理想郷〉がまたもその力を発揮して、建ってしまったという方が正しいか。
「はぁ……さすがに一月以上客が来ないと暇だなぁ」
ずっと言わないようにしていた言葉がついに口を出てしまうくらいには、俺は退屈していた。
常に魔王討伐という大きな目標が頭の中にあったあの頃は、暇な時間に憧れもしたものだが、いざ暇になってしまえば、時間を持て余しているようで非常にもったいなく感じてしまう。
「久しぶりに遠出してみようか? どうせ〈転移〉でいつでも帰って来れるし……」
誰もいないのをいいことに宿の前で大きな独り言を呟きながらふらふらと歩いていると視界の端に妙な黒い塊が映った。
「ん? 何だ今の? この辺りはおそらく俺の魔力のせいで野生動物やその辺の魔物は寄ってこないはずだが……」
……というか、俺がその姿をはっきりと捉えられない?
自分で言うのもアレだが、俺の身体能力は常人のそれをはるかに上回っている。
単身で魔王軍を突破し、魔王を倒すほどなのだから、俺には弱点という弱点はない。
それは動体視力に至っても同じことで、目の前を通り過ぎる小さな虫の顔をはっきりと認識できてしまうほどには目もいいのだ。
そんな俺が視界にとらえる程度しかできない黒い塊?
いったいこんな穏やかな場所に何が現れたというんだ?
久しぶりに味わうひりつくような緊張感に、暇で退屈していた今日ばかりは少し心が躍る気分だった。
襲撃に備えて構える。
極限まで脳に入る情報量を絞り、先ほど捉えた黒い塊の魔力だけに集中する。
――来るっ!
俺は背後からものすごいスピードで飛びかかってくるそれを辛うじて受け止めた。
「グッ……なかなかやる……な?」
小型の獣? いったいこいつは?
そう思って受け止めたそれ、いや、そいつを見て絶句してしまった。
「ミャー」
「……はい?」
愛くるしい顔、甘えたような鳴き声、野生とは思えない程整った毛並みを持つそいつ。
黒い塊の正体……それは猫だった。
「……猫?」
「ニャ?」
「……猫だな」
……とても早い猫。
一体こいつはなんなんだ?
スリスリと頬を擦り付けて来る様子を見るとだいぶ人に慣れていそうな印象だが、この猫を飼いならしていた人がいるなら、ぜひ会ってみたいものだ。
この速さに対応できるのなんて世界で俺と魔王くらいじゃだろうか。
「お前、ほんとキレイな毛並みしてるな」
深く暗い夜空を思わせるような漆黒の毛並みが、何とも形容しがたい触り心地をしており中々手放しがたい。
なにより、これだけ撫でても全く嫌がるそぶりを見せないところが小悪魔的を通り越してもはや悪魔的だ。
「お前はどこから来たんだ~」
最初の警戒や緊張感はどこへやら。
俺は早々にこの猫の魅力に溶かされてしまった。
「ニャニャ」
「おうおう、どうしたどうした~」
猫は目で執拗に俺の中指の指輪を追いかけている。
おもちゃか何かと勘違いしているのだろうか?
「これが気になるのか?」
「ニャー」
「そうかそうか。これはな、俺の大切なやつに貰った指輪なんだ。綺麗だよな」
「ニャニャ!」
ミアのことを思いだし、少し感傷的な気持ちになりながら黒猫に伝えてみると今までで一番大きな反応をする。
「なんだなんだ? これが気に入らないのか? でも、これは外せないんだ。悪いな」
「……ニャー」
「ごめんって。そうだ! 昼食に食べようと思ってた魔鳥のささみがあるぞ。食べるか?」
そう言ってこの猫を抱えたまま宿に戻ると突然どこかから、声が聞えたような気がした。
「(いい加減気が付かぬか!)」
「ん? 何だ今の声? 客が来なさ過ぎてついに幻聴まで聞こえ出したのか?」
「ニャー?ニャニャ(お主は本当にあの勇者か? 妾の魔力を忘れようとは……)」
……? 今、猫の鳴き声と空耳が被っていたような?
「……なぁ、もしかしてお前が喋ってるのか?」
「ニャニャー!(そう言っておるだろう!)」
……間違いない。
この声は空耳ではなく、猫の声だ。
「……でも、俺に猫の知り合いなんていないんだけどな。う~ん? いや、待て……この魔力」
改めて俺の腕の中でまっすぐこちらを見つめている黒猫を見つめ返す。
確かにこの魔力には覚えがある、いや、覚えがあるどころか……。
「……お前、まさかとは思うが……魔王……なのか?」
「ニャー! ニャニャ!(そうだ! 三日三晩戦い続けたあの日々を忘れられたのかと思ったぞ!)」
いやいや。
いやいやいやいや?
こいつほんとに魔王じゃねぇかっ!?
「……は? ……え? ……は? お前……はい?」
だいぶ、いや、それどころではないくらいに弱体化しているが間違いなく俺が討ち果たした魔王その人だ。
「ニャッニャッ!! (まあ、お主のその顔が見られた分で帳消しにしてやろうぞ)」
「……いや、なんで生きてるの? あの時お前完全に滅びた感じたったよな?」
「ニャ!ニャッニャ! (知らぬ! だが、お主にもう一度会いたいと思ってな! そしたら会えたぞ!)」
そう言って何故か嬉しそうにするかつての仇敵はやっぱり黒猫の姿で愛らしい。
……って、ダメだろ!
この姿で誤魔化されそうになったけど、こいつは紛うことなき人類の敵である魔王で、俺は引退したとはいえ一度は魔王討伐を謳った勇者だ。
人にとっての脅威はここで討ち滅ぼしておかなければ。
「悪いな魔王。せっかくの再会だが、あいにく喜ぶわけにはいかないんだ」
「ニャ!? (なんだと!? 妾がわざわざやって来てやったというのに、どうしてだ!?)」
「それは俺が勇者でお前が魔王だからだよ」
「ニャ!ニャニャ! (待て、勇者よ! 妾はもう魔王ではない! お主に見守られながら引退したではないか!)」
「何を言って――」
そう言われて、あの日の光景が蘇る。
◇◇◇
「なかなか……やるではないか。勇者よ」
魔王城、人間にとっては恐怖の象徴でもあった城の中心部で俺と魔王は最後の戦いに臨んでいた。
「お前こそ……なんでそんなに強いんだよ」
魔王は旅に出る前に想像していたような悪逆非道な存在ではなかった。
人間と魔族は本能的に嫌い合い争い合う、と言えばそれまでだが、この魔王にはそんな常識すら打ち破るような確かなカリスマ性と魅力があった。
「ふっ。妾は王なのだぞ? 王が弱くて誰が妾についてこようか! 妾が王である限り、強いことは必然と言えよう!」
魔族の社会は単純明快。
強者は上位者、これだけだ。
一応文明のようなものも存在しているような雰囲気が見て取れたが、人間の物とは比べ物にならないような文明で、まともなのはここ魔王城くらいだった。
「王が強いのは当然、か。確かに魔族らしいな」
「そう言うお主こそ、なぜそこまで強くなれたのだ?」
「俺か? そんなもの勇者だからに決まってるだろう? 勇者は希望だ。人を照らす最も身近な太陽なんだ。その光が弱くてしょぼいなんて許されるわけないだろ?」
「そうか。では、妾もそなたもある意味で似た者同士なのかもしれぬな」
「……まぁ、そうかもな」
戦闘中のほんの一幕。
そしてこの後、長期化した戦闘に終止符を打ったのは俺の方だった。
「なあ、勇者よ」
「なんだ魔王? 生きてたのか?」
「ははっ! なに、そう警戒するでない。じきに死ぬ。だが、その前にやっておきたいことがあってな」
玉座の前で伏した魔王。
あちこちが傷だらけでボロボロで、だというのにカリスマ性やその風格はどういう訳か健在だった。
「なんだよ? 死なばもろともってやつか?」
「違う。お主には一切危害を加えぬ故、そこで見ていてはくれないか?」
普通の魔族が相手ならば絶対にこんな話は聞かず、黙ってとどめを刺しただろう。
だが、相手は魔王。
歴史によれば、王を失った魔族はとてつもない弱体化をして、魔族から魔物になっていくはずだ。
魔族には傷を癒すような魔法文化は存在しない。
ならば、この状態の魔王にとどめを刺す必要ないと俺は判断した。
「……わかった。まあ、ここでお前と死ぬのもそれはそれで悪くないかもな」
「危害は加えぬと言っておろうに。まあ、見る気になってくれたようならそれでいい」
「ああ。で? 何をするんだ?」
「これは初代の魔王が決めたことでな。敗北した魔王はその責任としてすべての魔族の記憶から消え、代わりに魔王軍の敗北を伝えるのじゃ」
「……? どういうことだ?」
「要するに記憶の書き換えだな。ほれ、行くぞ」
そう言うと魔王は震える手を顔の前までもっていき、人差し指を立てた。
「これ以上、無用な争いが起こらぬように。〈存在しない記憶〉」
そう言うと魔王は立てた人差し指に優しく息を吹きかけた。
その息は魔力を伴って徐々に空へと広がっていき、やがて消えた。
「ふぅ、これで妾の魔王としての務めも終わりだ。部下に看取られることは叶わないが、自分を倒した相手に看取られるというのも、存外悪くない気分だな」
「……待てよ。正直最後の魔法は意味が分からないぞ? 敗北した魔王がすべての魔族の記憶から消えるなら、なんでお前はそれを覚えているんだ?」
「死に体にあまり無理をさせるでないわ! と言いたいところだが、良いだろう。お主に免じて教えてやろうぞ。もう、時間はない故、簡単にだがな」
魔王は俺の立っている方へ顔を向け、話し始めた。
「これはつまり魔王の引退なのだ。だからこの時代にも初代魔王のことを覚えているものは妾だけだ。そして、妾だけが覚えていた理由。これは確証がない故、推測にすぎぬが魔王には過去の魔王の記憶が引き継がれるのだ」
そう言うと魔王は一度言葉を止め、浅く咳き込む。
だが、まだ話すことを止めようとはしなかった。
「魔王の引退が死であるとするならば、魔族は初代魔王の死の後で滅びていたはず。それを立て直すのがこの記憶を引き継いだものなのだろうと妾は考えておる」
「……それってつまり、この争いは終わらないってことか?」
「まあ、そうかもしれぬな。だが少なくとも次の魔王の誕生までは人間にとっては平和な世が訪れるだろう」
「そうか、その平和な世って言うのは――」
聞こうとして、言葉を止めた。
こいつはもう、その生の限界を超えている。
目はうつろで、あの強い魔力も今では見る影もない。
「なあ、勇者よ」
「なんだ?」
「最後に妾と握手をしてくれぬか?」
「……いいぞ」
力なく横たわる魔王の手を握り、声をかける。
「これでいいか?」
「ああ、温かいなお主は。別の形で会えていたのならそれは……」
そう言い残し、魔王の命はこと切れた。
それと同時に人間の恐怖の象徴となっていた魔王城もまるで夜空に溶けていくかのように霧散していく。
「……終わった、のか」
横たわり、動かなくなった魔王を見下ろす。
「確かに、別の形で会えていたら、それは……」
その続きを言おうとして、止めた。
だが、この時思ったのだ。
引退も悪くないと。
◇◇◇
「そう言えばそうだったな」
「ニャ! (忘れておったのか!? 薄情な奴め!)」
「あの後俺も色々あったんだって」
「ニャ。(ふむ、その話は追々聞くとしよう)」
「追々って……まさかとは思うがお前」
俺の頭にその可能性がよぎる。
そして、魔王はそれを肯定するかのように俺を見上げるとこう言った。
「ニャニャ! ニャー(うむ。妾はここでお主と共に在ると決めた)」
すると、俺に抱えられた猫に魔力が集まっていく。
「なんだ!?」
その魔力はみるみるうちに人の形を成していき、やがてあの見覚えのある姿になるとそこで止まった。
「会いたかったぞ。勇者」
俺に横抱きにされている魔王が俺の頬に手を伸ばしながら、あの妖艶な笑みを浮かべた。
ユーリとアメリが去ってから結構な月日が流れた。
その間、俺がしたことと言えば日々の掃除に洗濯、食材の調達など、ごく普通の隠居生活のようなことばかりだった。
「いや、一応それだけではないか……」
宿の外に出て入浴施設の反対側へ歩く。
「勢い余ってこんな物を作ったんだよな……うん、立派な厩だ」
ユーリとアメリが去った後、初の接客を終えてテンションが上がっていた俺は勢いそのままに、旅人や探索者なら馬に乗っている人もいるよな! と言う全く根拠のない考えだけで厩を建ててしまったのだ。
建ててしまったというよりかは、「厩、必要だよな……場所はこの辺りかな?」とひとりでに考えているうちに〈仲間に捧げる理想郷〉がまたもその力を発揮して、建ってしまったという方が正しいか。
「はぁ……さすがに一月以上客が来ないと暇だなぁ」
ずっと言わないようにしていた言葉がついに口を出てしまうくらいには、俺は退屈していた。
常に魔王討伐という大きな目標が頭の中にあったあの頃は、暇な時間に憧れもしたものだが、いざ暇になってしまえば、時間を持て余しているようで非常にもったいなく感じてしまう。
「久しぶりに遠出してみようか? どうせ〈転移〉でいつでも帰って来れるし……」
誰もいないのをいいことに宿の前で大きな独り言を呟きながらふらふらと歩いていると視界の端に妙な黒い塊が映った。
「ん? 何だ今の? この辺りはおそらく俺の魔力のせいで野生動物やその辺の魔物は寄ってこないはずだが……」
……というか、俺がその姿をはっきりと捉えられない?
自分で言うのもアレだが、俺の身体能力は常人のそれをはるかに上回っている。
単身で魔王軍を突破し、魔王を倒すほどなのだから、俺には弱点という弱点はない。
それは動体視力に至っても同じことで、目の前を通り過ぎる小さな虫の顔をはっきりと認識できてしまうほどには目もいいのだ。
そんな俺が視界にとらえる程度しかできない黒い塊?
いったいこんな穏やかな場所に何が現れたというんだ?
久しぶりに味わうひりつくような緊張感に、暇で退屈していた今日ばかりは少し心が躍る気分だった。
襲撃に備えて構える。
極限まで脳に入る情報量を絞り、先ほど捉えた黒い塊の魔力だけに集中する。
――来るっ!
俺は背後からものすごいスピードで飛びかかってくるそれを辛うじて受け止めた。
「グッ……なかなかやる……な?」
小型の獣? いったいこいつは?
そう思って受け止めたそれ、いや、そいつを見て絶句してしまった。
「ミャー」
「……はい?」
愛くるしい顔、甘えたような鳴き声、野生とは思えない程整った毛並みを持つそいつ。
黒い塊の正体……それは猫だった。
「……猫?」
「ニャ?」
「……猫だな」
……とても早い猫。
一体こいつはなんなんだ?
スリスリと頬を擦り付けて来る様子を見るとだいぶ人に慣れていそうな印象だが、この猫を飼いならしていた人がいるなら、ぜひ会ってみたいものだ。
この速さに対応できるのなんて世界で俺と魔王くらいじゃだろうか。
「お前、ほんとキレイな毛並みしてるな」
深く暗い夜空を思わせるような漆黒の毛並みが、何とも形容しがたい触り心地をしており中々手放しがたい。
なにより、これだけ撫でても全く嫌がるそぶりを見せないところが小悪魔的を通り越してもはや悪魔的だ。
「お前はどこから来たんだ~」
最初の警戒や緊張感はどこへやら。
俺は早々にこの猫の魅力に溶かされてしまった。
「ニャニャ」
「おうおう、どうしたどうした~」
猫は目で執拗に俺の中指の指輪を追いかけている。
おもちゃか何かと勘違いしているのだろうか?
「これが気になるのか?」
「ニャー」
「そうかそうか。これはな、俺の大切なやつに貰った指輪なんだ。綺麗だよな」
「ニャニャ!」
ミアのことを思いだし、少し感傷的な気持ちになりながら黒猫に伝えてみると今までで一番大きな反応をする。
「なんだなんだ? これが気に入らないのか? でも、これは外せないんだ。悪いな」
「……ニャー」
「ごめんって。そうだ! 昼食に食べようと思ってた魔鳥のささみがあるぞ。食べるか?」
そう言ってこの猫を抱えたまま宿に戻ると突然どこかから、声が聞えたような気がした。
「(いい加減気が付かぬか!)」
「ん? 何だ今の声? 客が来なさ過ぎてついに幻聴まで聞こえ出したのか?」
「ニャー?ニャニャ(お主は本当にあの勇者か? 妾の魔力を忘れようとは……)」
……? 今、猫の鳴き声と空耳が被っていたような?
「……なぁ、もしかしてお前が喋ってるのか?」
「ニャニャー!(そう言っておるだろう!)」
……間違いない。
この声は空耳ではなく、猫の声だ。
「……でも、俺に猫の知り合いなんていないんだけどな。う~ん? いや、待て……この魔力」
改めて俺の腕の中でまっすぐこちらを見つめている黒猫を見つめ返す。
確かにこの魔力には覚えがある、いや、覚えがあるどころか……。
「……お前、まさかとは思うが……魔王……なのか?」
「ニャー! ニャニャ!(そうだ! 三日三晩戦い続けたあの日々を忘れられたのかと思ったぞ!)」
いやいや。
いやいやいやいや?
こいつほんとに魔王じゃねぇかっ!?
「……は? ……え? ……は? お前……はい?」
だいぶ、いや、それどころではないくらいに弱体化しているが間違いなく俺が討ち果たした魔王その人だ。
「ニャッニャッ!! (まあ、お主のその顔が見られた分で帳消しにしてやろうぞ)」
「……いや、なんで生きてるの? あの時お前完全に滅びた感じたったよな?」
「ニャ!ニャッニャ! (知らぬ! だが、お主にもう一度会いたいと思ってな! そしたら会えたぞ!)」
そう言って何故か嬉しそうにするかつての仇敵はやっぱり黒猫の姿で愛らしい。
……って、ダメだろ!
この姿で誤魔化されそうになったけど、こいつは紛うことなき人類の敵である魔王で、俺は引退したとはいえ一度は魔王討伐を謳った勇者だ。
人にとっての脅威はここで討ち滅ぼしておかなければ。
「悪いな魔王。せっかくの再会だが、あいにく喜ぶわけにはいかないんだ」
「ニャ!? (なんだと!? 妾がわざわざやって来てやったというのに、どうしてだ!?)」
「それは俺が勇者でお前が魔王だからだよ」
「ニャ!ニャニャ! (待て、勇者よ! 妾はもう魔王ではない! お主に見守られながら引退したではないか!)」
「何を言って――」
そう言われて、あの日の光景が蘇る。
◇◇◇
「なかなか……やるではないか。勇者よ」
魔王城、人間にとっては恐怖の象徴でもあった城の中心部で俺と魔王は最後の戦いに臨んでいた。
「お前こそ……なんでそんなに強いんだよ」
魔王は旅に出る前に想像していたような悪逆非道な存在ではなかった。
人間と魔族は本能的に嫌い合い争い合う、と言えばそれまでだが、この魔王にはそんな常識すら打ち破るような確かなカリスマ性と魅力があった。
「ふっ。妾は王なのだぞ? 王が弱くて誰が妾についてこようか! 妾が王である限り、強いことは必然と言えよう!」
魔族の社会は単純明快。
強者は上位者、これだけだ。
一応文明のようなものも存在しているような雰囲気が見て取れたが、人間の物とは比べ物にならないような文明で、まともなのはここ魔王城くらいだった。
「王が強いのは当然、か。確かに魔族らしいな」
「そう言うお主こそ、なぜそこまで強くなれたのだ?」
「俺か? そんなもの勇者だからに決まってるだろう? 勇者は希望だ。人を照らす最も身近な太陽なんだ。その光が弱くてしょぼいなんて許されるわけないだろ?」
「そうか。では、妾もそなたもある意味で似た者同士なのかもしれぬな」
「……まぁ、そうかもな」
戦闘中のほんの一幕。
そしてこの後、長期化した戦闘に終止符を打ったのは俺の方だった。
「なあ、勇者よ」
「なんだ魔王? 生きてたのか?」
「ははっ! なに、そう警戒するでない。じきに死ぬ。だが、その前にやっておきたいことがあってな」
玉座の前で伏した魔王。
あちこちが傷だらけでボロボロで、だというのにカリスマ性やその風格はどういう訳か健在だった。
「なんだよ? 死なばもろともってやつか?」
「違う。お主には一切危害を加えぬ故、そこで見ていてはくれないか?」
普通の魔族が相手ならば絶対にこんな話は聞かず、黙ってとどめを刺しただろう。
だが、相手は魔王。
歴史によれば、王を失った魔族はとてつもない弱体化をして、魔族から魔物になっていくはずだ。
魔族には傷を癒すような魔法文化は存在しない。
ならば、この状態の魔王にとどめを刺す必要ないと俺は判断した。
「……わかった。まあ、ここでお前と死ぬのもそれはそれで悪くないかもな」
「危害は加えぬと言っておろうに。まあ、見る気になってくれたようならそれでいい」
「ああ。で? 何をするんだ?」
「これは初代の魔王が決めたことでな。敗北した魔王はその責任としてすべての魔族の記憶から消え、代わりに魔王軍の敗北を伝えるのじゃ」
「……? どういうことだ?」
「要するに記憶の書き換えだな。ほれ、行くぞ」
そう言うと魔王は震える手を顔の前までもっていき、人差し指を立てた。
「これ以上、無用な争いが起こらぬように。〈存在しない記憶〉」
そう言うと魔王は立てた人差し指に優しく息を吹きかけた。
その息は魔力を伴って徐々に空へと広がっていき、やがて消えた。
「ふぅ、これで妾の魔王としての務めも終わりだ。部下に看取られることは叶わないが、自分を倒した相手に看取られるというのも、存外悪くない気分だな」
「……待てよ。正直最後の魔法は意味が分からないぞ? 敗北した魔王がすべての魔族の記憶から消えるなら、なんでお前はそれを覚えているんだ?」
「死に体にあまり無理をさせるでないわ! と言いたいところだが、良いだろう。お主に免じて教えてやろうぞ。もう、時間はない故、簡単にだがな」
魔王は俺の立っている方へ顔を向け、話し始めた。
「これはつまり魔王の引退なのだ。だからこの時代にも初代魔王のことを覚えているものは妾だけだ。そして、妾だけが覚えていた理由。これは確証がない故、推測にすぎぬが魔王には過去の魔王の記憶が引き継がれるのだ」
そう言うと魔王は一度言葉を止め、浅く咳き込む。
だが、まだ話すことを止めようとはしなかった。
「魔王の引退が死であるとするならば、魔族は初代魔王の死の後で滅びていたはず。それを立て直すのがこの記憶を引き継いだものなのだろうと妾は考えておる」
「……それってつまり、この争いは終わらないってことか?」
「まあ、そうかもしれぬな。だが少なくとも次の魔王の誕生までは人間にとっては平和な世が訪れるだろう」
「そうか、その平和な世って言うのは――」
聞こうとして、言葉を止めた。
こいつはもう、その生の限界を超えている。
目はうつろで、あの強い魔力も今では見る影もない。
「なあ、勇者よ」
「なんだ?」
「最後に妾と握手をしてくれぬか?」
「……いいぞ」
力なく横たわる魔王の手を握り、声をかける。
「これでいいか?」
「ああ、温かいなお主は。別の形で会えていたのならそれは……」
そう言い残し、魔王の命はこと切れた。
それと同時に人間の恐怖の象徴となっていた魔王城もまるで夜空に溶けていくかのように霧散していく。
「……終わった、のか」
横たわり、動かなくなった魔王を見下ろす。
「確かに、別の形で会えていたら、それは……」
その続きを言おうとして、止めた。
だが、この時思ったのだ。
引退も悪くないと。
◇◇◇
「そう言えばそうだったな」
「ニャ! (忘れておったのか!? 薄情な奴め!)」
「あの後俺も色々あったんだって」
「ニャ。(ふむ、その話は追々聞くとしよう)」
「追々って……まさかとは思うがお前」
俺の頭にその可能性がよぎる。
そして、魔王はそれを肯定するかのように俺を見上げるとこう言った。
「ニャニャ! ニャー(うむ。妾はここでお主と共に在ると決めた)」
すると、俺に抱えられた猫に魔力が集まっていく。
「なんだ!?」
その魔力はみるみるうちに人の形を成していき、やがてあの見覚えのある姿になるとそこで止まった。
「会いたかったぞ。勇者」
俺に横抱きにされている魔王が俺の頬に手を伸ばしながら、あの妖艶な笑みを浮かべた。