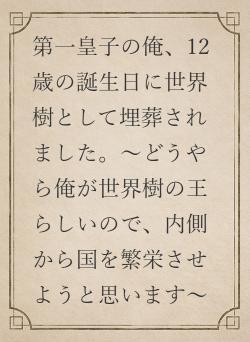初めての宿泊客二人組が部屋に行くのを見送った俺はキッチンで早速夕食の準備を始めた。
今日のメニューは大量にある羊肉(幻妖の羊)を使ったものだ。
ガダル爺さんに解体してもらった後、街の肉屋で腸詰を作ってもらってある。
これを使ってポトフを作ろう。
具材は腸詰のほかに若干大きめに切った羊肉、土イモ、ニンジン、タマネギだ。
材料をあらかた切り終えたら、まずは羊肉を焼いていく。
しっかりと塩と胡椒で下味をつけ、焼き色が付くまでじっくりと焼く。
この羊肉から溶け出す油がポトフの味を一層高めてくれる。
他の肉の油では雑味になることもあるが、幻妖の羊の肉は別格だ。
この肉の油だけでも、もはやスープになりうる。
羊肉が焼けたら仕込んでおいた魔鳥の出汁に野菜と一緒に入れていく。
これで加熱はハイスぺコンロに任せておけば問題ないだろう。
出来上がる少し前のタイミングで腸詰を焼き、最後に加えて少し煮込めば完成だ。
◇◇◇
しばらくして、ユーリとアメリの二人が部屋から降りて来た。
「お待たせしました!」
「いやいや、丁度できた所だよ。部屋の方は気に入ってもらえたかな?」
「店主さんっ! あのベッドはなんですか!? ありえない寝心地の良さだったんですけど!」
配膳前の雑談程度に考えて振った質問だったが、アメリが予想以上の食いつきを見せる。
「ああ、あれは幻妖の羊の羊毛で作った布団だよ。マットレスも王国内では最高級のものを使ってるんだ。うちの自慢だよ」
やはり、幻妖の羊の羊毛で作った布団は最高だよな。
「……幻妖の羊の羊毛?」
「そうそう」
「王室御用達の最高級品の?」
「それそれ」
アメリの表情から色が消えていく。
「……」
「アメリ? どうしたの? 見たことない顔色になってるけど……」
まあ、確かに普通の探索者からしたら衝撃的な話しか。
そう考えると幻妖の羊と聞いても、顔色一つ変えずに相方の心配をしているユーリは大物なのかもしれない。
「じゃあ、好きな席に座っててよ。今から持ってくるから」
「あ、はい! ありがとうございます!」
「さぁどうぞ。羊肉のポトフを召し上がれ!」
「すごい! 腸詰まで乗って……いただきます!」
「あの……この羊肉ってまさか……」
ようやく調子を取り戻しつつあったアメリが恐る恐るといった調子でこちらに視線を向けてくる。
……さすがにここで幻妖の羊だよなんて言って、ポトフが冷めてしまってはもったいない。
そう考えた俺は「さぁ」と首をかしげるだけにとどめておいた。
そんなアメリを置いてユーリが腸詰に噛り付いた。
「! すごい! これ、本当に羊肉ですか!? 臭みが全くない!」
「美味しそうで良かったよ」
そうそう、この顔だ。
探索者とは安定とは程遠い職業である。
それでも探索者が減らないのは、見つかる魔具によってあり得ない程の財を築く者、高難度のダンジョンを攻略して世界的な知名度を得る者が度々現れるからである。
だが、そんな憧れに到達できるのは本当の一握り。
大抵の探索者は年々衰えていく身体や反射神経によって、引退を余儀なくされるか、ダンジョン内で命を落とす。
そんな探索者に安らぎをもたらすこと、それが俺の目標であり、この宿をやる理由だ。
続いてアメリもポトフを一口。
すると見る見るうちに強張っていた表情筋がほどけていく。
「なにこれ……雑味が全くない! 味付けはシンプルなのに複雑な旨みが……」
途端に饒舌になる様子を見て、思わず俺の表情も綻んでしまった。
それからは二人とも会話もそこそこに一心不乱に食事にありつき、二人とも二杯もお代わりをしてくれた。
一杯目は少し申し訳なさそうにしていたが、お腹いっぱい食べてくれたようで俺は大満足だった。
「そういえば、昔ここの辺りにあった村を知っていますか?」
あらかた食事も終わり、食器を下げようとした俺にユーリが話しかけて来た。
「……ああ、知っているよ。でも、どうして急に?」
俺の胸にチクリとした痛みが走る。
ここで生活を始め、ゆっくりと慣れてきたつもりではあったが、ここの過去の話は俺に残る大きな後悔の一つだ。
「両親は言わないですし、幼い頃のことなので確かではないのですが……僕の故郷だった村なんじゃないかなって」
あの日のあの光景が一瞬でフラッシュバックする。
その言葉は俺を驚かせるには十分な衝撃を持っていた。
思わず手に取ったお椀を落としてしまう。
「大丈夫ですか?」
咄嗟にアメリが落としたお椀を拾ってくれる。
どうしてかその表情は少し複雑そうだった。
「あ、ああ、すまない。ちょっとね……」
そんな俺たちに構わずユーリは話を続けた。
「それで、もしよければ、ここにあった村で何があったかを教えてもらえませんか?」
「……」
思わず黙り込んでしまう。
おそらく、ユーリの話は本当なのだろう。
アメリのこの調子も、きっとそれを知っていることが関係しているのではないだろうか。
あの日、俺が村にいさえすれば……まだここで暮らしていたかもしれない生き残り。
俺のせいで大きく未来が変わってしまった、そんな少年が今、目の前にいると思うと……どうにも表現しがたい複雑な感情に苛まれる。
「あ、あの、全然嫌とかなら……」
「いや、話そうか。あの日何があったかを。そして、キミたちを守った探索者の話を」
正直に言うと、あまり話したい内容ではない。
だが、シダとマイン、それ以外のこの村のために戦い亡くなった探索者たちの名は一人でも多くの人に知られるべきだ。
俺は自分から名を消した。でも、あいつらの名前は……きっと誰かに憶えていて欲しい。
彼らは俺のせいで名を上げる機会さえ失ったのだ。
そんな無名の英雄の名が知られるのは悪くないとそう思った。
今日のメニューは大量にある羊肉(幻妖の羊)を使ったものだ。
ガダル爺さんに解体してもらった後、街の肉屋で腸詰を作ってもらってある。
これを使ってポトフを作ろう。
具材は腸詰のほかに若干大きめに切った羊肉、土イモ、ニンジン、タマネギだ。
材料をあらかた切り終えたら、まずは羊肉を焼いていく。
しっかりと塩と胡椒で下味をつけ、焼き色が付くまでじっくりと焼く。
この羊肉から溶け出す油がポトフの味を一層高めてくれる。
他の肉の油では雑味になることもあるが、幻妖の羊の肉は別格だ。
この肉の油だけでも、もはやスープになりうる。
羊肉が焼けたら仕込んでおいた魔鳥の出汁に野菜と一緒に入れていく。
これで加熱はハイスぺコンロに任せておけば問題ないだろう。
出来上がる少し前のタイミングで腸詰を焼き、最後に加えて少し煮込めば完成だ。
◇◇◇
しばらくして、ユーリとアメリの二人が部屋から降りて来た。
「お待たせしました!」
「いやいや、丁度できた所だよ。部屋の方は気に入ってもらえたかな?」
「店主さんっ! あのベッドはなんですか!? ありえない寝心地の良さだったんですけど!」
配膳前の雑談程度に考えて振った質問だったが、アメリが予想以上の食いつきを見せる。
「ああ、あれは幻妖の羊の羊毛で作った布団だよ。マットレスも王国内では最高級のものを使ってるんだ。うちの自慢だよ」
やはり、幻妖の羊の羊毛で作った布団は最高だよな。
「……幻妖の羊の羊毛?」
「そうそう」
「王室御用達の最高級品の?」
「それそれ」
アメリの表情から色が消えていく。
「……」
「アメリ? どうしたの? 見たことない顔色になってるけど……」
まあ、確かに普通の探索者からしたら衝撃的な話しか。
そう考えると幻妖の羊と聞いても、顔色一つ変えずに相方の心配をしているユーリは大物なのかもしれない。
「じゃあ、好きな席に座っててよ。今から持ってくるから」
「あ、はい! ありがとうございます!」
「さぁどうぞ。羊肉のポトフを召し上がれ!」
「すごい! 腸詰まで乗って……いただきます!」
「あの……この羊肉ってまさか……」
ようやく調子を取り戻しつつあったアメリが恐る恐るといった調子でこちらに視線を向けてくる。
……さすがにここで幻妖の羊だよなんて言って、ポトフが冷めてしまってはもったいない。
そう考えた俺は「さぁ」と首をかしげるだけにとどめておいた。
そんなアメリを置いてユーリが腸詰に噛り付いた。
「! すごい! これ、本当に羊肉ですか!? 臭みが全くない!」
「美味しそうで良かったよ」
そうそう、この顔だ。
探索者とは安定とは程遠い職業である。
それでも探索者が減らないのは、見つかる魔具によってあり得ない程の財を築く者、高難度のダンジョンを攻略して世界的な知名度を得る者が度々現れるからである。
だが、そんな憧れに到達できるのは本当の一握り。
大抵の探索者は年々衰えていく身体や反射神経によって、引退を余儀なくされるか、ダンジョン内で命を落とす。
そんな探索者に安らぎをもたらすこと、それが俺の目標であり、この宿をやる理由だ。
続いてアメリもポトフを一口。
すると見る見るうちに強張っていた表情筋がほどけていく。
「なにこれ……雑味が全くない! 味付けはシンプルなのに複雑な旨みが……」
途端に饒舌になる様子を見て、思わず俺の表情も綻んでしまった。
それからは二人とも会話もそこそこに一心不乱に食事にありつき、二人とも二杯もお代わりをしてくれた。
一杯目は少し申し訳なさそうにしていたが、お腹いっぱい食べてくれたようで俺は大満足だった。
「そういえば、昔ここの辺りにあった村を知っていますか?」
あらかた食事も終わり、食器を下げようとした俺にユーリが話しかけて来た。
「……ああ、知っているよ。でも、どうして急に?」
俺の胸にチクリとした痛みが走る。
ここで生活を始め、ゆっくりと慣れてきたつもりではあったが、ここの過去の話は俺に残る大きな後悔の一つだ。
「両親は言わないですし、幼い頃のことなので確かではないのですが……僕の故郷だった村なんじゃないかなって」
あの日のあの光景が一瞬でフラッシュバックする。
その言葉は俺を驚かせるには十分な衝撃を持っていた。
思わず手に取ったお椀を落としてしまう。
「大丈夫ですか?」
咄嗟にアメリが落としたお椀を拾ってくれる。
どうしてかその表情は少し複雑そうだった。
「あ、ああ、すまない。ちょっとね……」
そんな俺たちに構わずユーリは話を続けた。
「それで、もしよければ、ここにあった村で何があったかを教えてもらえませんか?」
「……」
思わず黙り込んでしまう。
おそらく、ユーリの話は本当なのだろう。
アメリのこの調子も、きっとそれを知っていることが関係しているのではないだろうか。
あの日、俺が村にいさえすれば……まだここで暮らしていたかもしれない生き残り。
俺のせいで大きく未来が変わってしまった、そんな少年が今、目の前にいると思うと……どうにも表現しがたい複雑な感情に苛まれる。
「あ、あの、全然嫌とかなら……」
「いや、話そうか。あの日何があったかを。そして、キミたちを守った探索者の話を」
正直に言うと、あまり話したい内容ではない。
だが、シダとマイン、それ以外のこの村のために戦い亡くなった探索者たちの名は一人でも多くの人に知られるべきだ。
俺は自分から名を消した。でも、あいつらの名前は……きっと誰かに憶えていて欲しい。
彼らは俺のせいで名を上げる機会さえ失ったのだ。
そんな無名の英雄の名が知られるのは悪くないとそう思った。