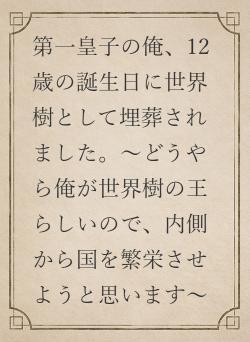「いらっしゃい! 旅人の宿「ピロテス」へようこそ」
宿の扉が開けられるや否や俺は満面の笑みで出迎えた。
「どうも、こんにちは! この近くのシローテダンジョンに挑戦しに来たのですが、宿泊可能ですか?」
すると快活な笑みを浮かべて少年の方がそう言う。
「もちろん! 三日前にこの宿を開いたんだけど、これまで全くお客さんがいなくてさ。こっちからお願いしたいくらいさ」
「やったねアメリ! やっぱりここは大丈夫そうだ!」
「……あなたはどうしてこんなところで宿を? この辺りはダンジョン以外何もなさそうですけど」
好感触な少年とは違いアメリと呼ばれた少女はどこか警戒しているようで、こちらを注意深く窺っている。
まあ、その疑問はもっともだと、この数日落ち着いて考えてみて俺も思った。
「そうだね。この辺りにはもう、何もない。でも過去にはあったんだよ。そんな郷愁に駆られて、ね」
「……そうですか。見た感じ、すごくいい宿に見えるんですけど、本当に大銀貨一枚でいいんですか?」
どうやら、表に設置した看板を見てくれたようだ。
「ああ、もちろん! そうだ! 夕飯は食べた? 新鮮な羊肉があるんだ! 夕食代も代金内に入ってるからもしよければ食べていってよ」
「えぇっ!?」
俺がそう言うとアメリは声を上げて驚き、少年の肩を掴むと俺に背を向けて二人で何かを話し始めた。
「ねえ、ここ本当に大丈夫?」
「どうしたのアメリ? すごくいいところじゃないか! 店主さんもいい人そうだし」
「でも、どう考えたって安すぎると思わない? 一泊夕食付きで大銀貨一枚だよ? 隠居した貴族の道楽っていうなら分かるけど、あの人どう見てもまだ二、三十代くらいだし」
「大丈夫だと思うけどなぁ……」
そんな話をしている。
……警戒していた割に、こっちに丸聞こえだけどそれはいいのか?
あ、俺の聴覚は戦場を駆け回る中で常人のそれより圧倒的に強化されているんだった……。
聞こえてないふりしとかなきゃ。
「でも、泊まるところがないのは事実……」
「そうだよ!」
アメリのぼやきを承認と捉えたユーリが改めて俺に向き直った。
「店主さん! 僕はユーリ、こっちは幼馴染のアメリです! とりあえず、一泊お願いします!」
「ちょ、ユーリ!?」
「よしきたっ! パーティ用の四人部屋と普通の一人部屋があるけどどっちがいい? どっちでも料金は人数分だから、好きな方を選んでいいよ」
「どうするアメリ? 心配なら四人部屋にしてもらう?」
「なっ! 心配って……いいわよ! 一人部屋を二つお願いします」
「はい、じゃあこれ部屋の鍵ね。部屋は三階、二人の部屋は向かい合わせの部屋になってるからゆっくりしてね」
「ありがとうございます! 部屋に荷物を置いたら夕食をいただいてもいいですか?」
「もちろん! 荷物を置いたらそこのテーブル席に座って待っててよ」
もう、どうにでもなれとでも言うようなアメリとすごくテンションの高いユーリたちを見送って俺はキッチンへ入った。
◇◇◇
「ほんとに立派な宿ね」
鍵を受け取り部屋への階段を上がりながら、アメリが呟く。
「ほんとだね。 なんだかいきなり成功者になった気分だね」
「……まあ、部屋はまだわからないけどね」
こんなに都合のいいことがあるのだろうか?
まさにシローテダンジョンに挑戦する者のために作られたような立地、他に何の建物さえなく、ここまでは野宿続きだったであろう探索者が泊まりやすい価格にどうしようもなく惹かれてしまう外観。
まるで吸血鬼のトラップハウスのような……。
「アメリ、ここだよ!」
と、そんなことを考えているうちに鍵に書かれた番号の札が下げられた部屋の前に到着していた。
「そう、ね」
あまり触れたことのない高級そうな扉の装丁に慣れず、どうしてか緊張してしまう。
「じゃあ、荷物置いたらすぐ戻ろうか」
「分かった」
臆さず鍵を開け部屋に入っていくユーリを見習い、アメリも部屋に足を踏み入れた。
瞬間、アメリの身が淡い光に包まれる。
「な、なにっ!?」
咄嗟に警戒態勢を取れたのはここまでどこか抜けた幼馴染と探索者生活を続けて来た賜物だろうか。
だがすぐに、それが余計な心配だったと気が付く。
「これって……〈洗浄〉の魔法!? もしかしてこの絨毯に!?」
汗をかき、着替えたいと思っていた不快感がきれいさっぱりなくなる。
アメリの推測通り、この部屋の入口に引かれた絨毯にはファレスによって踏んだものの全身を綺麗にする〈洗浄〉の魔法がかけられていた。
「ほんと……どうなってるのよ。この宿は」
入口を入ったすぐ先にはもう一つ扉があり、そこは化粧室になっていた。
「個室に化粧室つき!? それに……」
化粧室の扉を閉めて、メインの部屋の方へ向かってみればそこには、見ているだけで惹きつけられるような魅力を放つ魅惑の布団に全身の防具を外しかけて置ける防具立てが設置されている。
ベッドはとても一人部屋とは思えないセミダブルサイズ、だというのに部屋には圧迫感が全くなく、それどころかどこか広々としていた。
「ちょ、ちょっと待ってよ……この布団……」
抗い難い魅力を放つベッドに恐る恐る腰を下ろしてみる。
その途端、フワッと体が浮くような感覚に陥った。
「なにこれ………………最高過ぎるぅ」
まだ横になっていないというのに、一日の疲れが吹き飛んでいくような心地よさ。
もう、このまま寝てしまいたい……。
………………。
………………。
………………。
「アメリっ! アメリっ!」
故郷の自分のベッドよりも落ち着けるその布団に身を任せようとしていると、扉の先で幼馴染が自分を呼んでいる。
「なに? どうかしたの?」
アメリは気の抜けきっただらしない声で反応した。
「どうかしたの? じゃないよ! もう結構な時間が経ってるよ! 早く夕食を食べに行こうよ!」
「えっ!?」
急いでアメリはベッドから立ち上がり、自分が横になっていた敷布団を見つめる。
するとそこには、到底少し横になっていただけではできないほどの人型の沈み込みが出来ていた。
「……うそ」
そう呟いたかと思えば、すぐに化粧室に飛び込み鏡の前で髪に手櫛を通していく。
「あのベッドはもはや魔物より凶悪だわ……でも――これなら夕食にも期待できるわね」
宿に入る前の警戒心はどこへやら。
ユーリとアメリは軽快な足取りで一階のレストランスペースまで降りていった。
宿の扉が開けられるや否や俺は満面の笑みで出迎えた。
「どうも、こんにちは! この近くのシローテダンジョンに挑戦しに来たのですが、宿泊可能ですか?」
すると快活な笑みを浮かべて少年の方がそう言う。
「もちろん! 三日前にこの宿を開いたんだけど、これまで全くお客さんがいなくてさ。こっちからお願いしたいくらいさ」
「やったねアメリ! やっぱりここは大丈夫そうだ!」
「……あなたはどうしてこんなところで宿を? この辺りはダンジョン以外何もなさそうですけど」
好感触な少年とは違いアメリと呼ばれた少女はどこか警戒しているようで、こちらを注意深く窺っている。
まあ、その疑問はもっともだと、この数日落ち着いて考えてみて俺も思った。
「そうだね。この辺りにはもう、何もない。でも過去にはあったんだよ。そんな郷愁に駆られて、ね」
「……そうですか。見た感じ、すごくいい宿に見えるんですけど、本当に大銀貨一枚でいいんですか?」
どうやら、表に設置した看板を見てくれたようだ。
「ああ、もちろん! そうだ! 夕飯は食べた? 新鮮な羊肉があるんだ! 夕食代も代金内に入ってるからもしよければ食べていってよ」
「えぇっ!?」
俺がそう言うとアメリは声を上げて驚き、少年の肩を掴むと俺に背を向けて二人で何かを話し始めた。
「ねえ、ここ本当に大丈夫?」
「どうしたのアメリ? すごくいいところじゃないか! 店主さんもいい人そうだし」
「でも、どう考えたって安すぎると思わない? 一泊夕食付きで大銀貨一枚だよ? 隠居した貴族の道楽っていうなら分かるけど、あの人どう見てもまだ二、三十代くらいだし」
「大丈夫だと思うけどなぁ……」
そんな話をしている。
……警戒していた割に、こっちに丸聞こえだけどそれはいいのか?
あ、俺の聴覚は戦場を駆け回る中で常人のそれより圧倒的に強化されているんだった……。
聞こえてないふりしとかなきゃ。
「でも、泊まるところがないのは事実……」
「そうだよ!」
アメリのぼやきを承認と捉えたユーリが改めて俺に向き直った。
「店主さん! 僕はユーリ、こっちは幼馴染のアメリです! とりあえず、一泊お願いします!」
「ちょ、ユーリ!?」
「よしきたっ! パーティ用の四人部屋と普通の一人部屋があるけどどっちがいい? どっちでも料金は人数分だから、好きな方を選んでいいよ」
「どうするアメリ? 心配なら四人部屋にしてもらう?」
「なっ! 心配って……いいわよ! 一人部屋を二つお願いします」
「はい、じゃあこれ部屋の鍵ね。部屋は三階、二人の部屋は向かい合わせの部屋になってるからゆっくりしてね」
「ありがとうございます! 部屋に荷物を置いたら夕食をいただいてもいいですか?」
「もちろん! 荷物を置いたらそこのテーブル席に座って待っててよ」
もう、どうにでもなれとでも言うようなアメリとすごくテンションの高いユーリたちを見送って俺はキッチンへ入った。
◇◇◇
「ほんとに立派な宿ね」
鍵を受け取り部屋への階段を上がりながら、アメリが呟く。
「ほんとだね。 なんだかいきなり成功者になった気分だね」
「……まあ、部屋はまだわからないけどね」
こんなに都合のいいことがあるのだろうか?
まさにシローテダンジョンに挑戦する者のために作られたような立地、他に何の建物さえなく、ここまでは野宿続きだったであろう探索者が泊まりやすい価格にどうしようもなく惹かれてしまう外観。
まるで吸血鬼のトラップハウスのような……。
「アメリ、ここだよ!」
と、そんなことを考えているうちに鍵に書かれた番号の札が下げられた部屋の前に到着していた。
「そう、ね」
あまり触れたことのない高級そうな扉の装丁に慣れず、どうしてか緊張してしまう。
「じゃあ、荷物置いたらすぐ戻ろうか」
「分かった」
臆さず鍵を開け部屋に入っていくユーリを見習い、アメリも部屋に足を踏み入れた。
瞬間、アメリの身が淡い光に包まれる。
「な、なにっ!?」
咄嗟に警戒態勢を取れたのはここまでどこか抜けた幼馴染と探索者生活を続けて来た賜物だろうか。
だがすぐに、それが余計な心配だったと気が付く。
「これって……〈洗浄〉の魔法!? もしかしてこの絨毯に!?」
汗をかき、着替えたいと思っていた不快感がきれいさっぱりなくなる。
アメリの推測通り、この部屋の入口に引かれた絨毯にはファレスによって踏んだものの全身を綺麗にする〈洗浄〉の魔法がかけられていた。
「ほんと……どうなってるのよ。この宿は」
入口を入ったすぐ先にはもう一つ扉があり、そこは化粧室になっていた。
「個室に化粧室つき!? それに……」
化粧室の扉を閉めて、メインの部屋の方へ向かってみればそこには、見ているだけで惹きつけられるような魅力を放つ魅惑の布団に全身の防具を外しかけて置ける防具立てが設置されている。
ベッドはとても一人部屋とは思えないセミダブルサイズ、だというのに部屋には圧迫感が全くなく、それどころかどこか広々としていた。
「ちょ、ちょっと待ってよ……この布団……」
抗い難い魅力を放つベッドに恐る恐る腰を下ろしてみる。
その途端、フワッと体が浮くような感覚に陥った。
「なにこれ………………最高過ぎるぅ」
まだ横になっていないというのに、一日の疲れが吹き飛んでいくような心地よさ。
もう、このまま寝てしまいたい……。
………………。
………………。
………………。
「アメリっ! アメリっ!」
故郷の自分のベッドよりも落ち着けるその布団に身を任せようとしていると、扉の先で幼馴染が自分を呼んでいる。
「なに? どうかしたの?」
アメリは気の抜けきっただらしない声で反応した。
「どうかしたの? じゃないよ! もう結構な時間が経ってるよ! 早く夕食を食べに行こうよ!」
「えっ!?」
急いでアメリはベッドから立ち上がり、自分が横になっていた敷布団を見つめる。
するとそこには、到底少し横になっていただけではできないほどの人型の沈み込みが出来ていた。
「……うそ」
そう呟いたかと思えば、すぐに化粧室に飛び込み鏡の前で髪に手櫛を通していく。
「あのベッドはもはや魔物より凶悪だわ……でも――これなら夕食にも期待できるわね」
宿に入る前の警戒心はどこへやら。
ユーリとアメリは軽快な足取りで一階のレストランスペースまで降りていった。