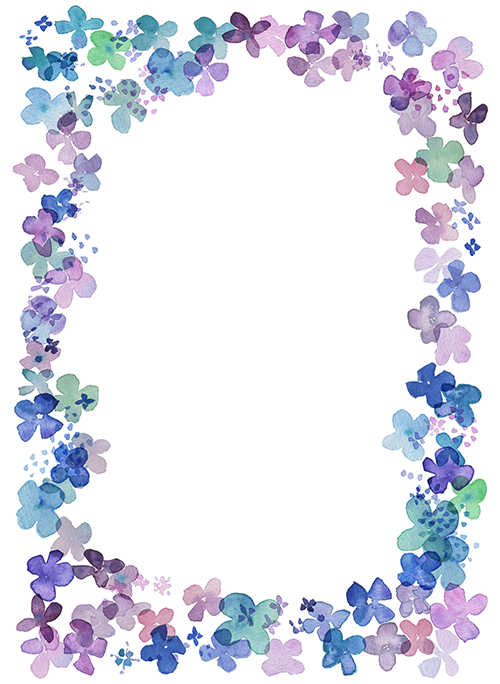狭い路地裏をずんずんと歩く陽介を小走りで追いかける。彼は早歩きなのに、二人の距離はちっとも縮まらない。それでいつも、歩調を合わせてくれていたことを知る。
なんで。
映画館の前で上からこちらを覗き込んだ陽介の顔が頭をよぎる。眉間に深く皺をよせて、むすっと唇を引き延ばして。その顔からゆっくりと力が抜けて、今度は泣き出す寸前のみたいになった。眉間にもう一度皺がよって、唇を強く噛んで、金色の瞳が涙で緩む。
なんで、そんな顔、君がするの。
泣きたいのは、どう考えたって僕の方だよ。
デートを忘れられて、楽しみにしていた特別な映画を、他の人と見に行くと言われて悲しかった。
その人との約束がダメになったからって、都合よく呼び出されたのが悔しかった。
映画館の座席で、まるで誰にも見られたくないみたいに、端っこを選ばれるのが寂しかった。
人恋しさを埋めるためだけに、繋がれる手が空しかった。
悲しくて、痛くて、辛くて、苦しい。
こんな恋、捨ててしまえればと思うのに、それでもまだ好きだから、泣き出しそうな顔を見て、心臓がぎゅっとなった。
「っ」
前を歩く陽介を呼ぼうとして、けれど声が出ない。視界が滲む。いかないで。早いよ。追いつけない。待って。どれも、何も、言葉にできなくて、溢れた気持ちがぼろぼろと涙に変わる。
静かに泣かないと。きっと、陽介の迷惑になる。
悲しくて泣いているのに、陽介に怒られたら、もっと悲しくなってしまう。唇を内側に巻き込んで、息を止める。そうすると、苦しくってもう走れなかった。
足が止まって。
陽介は、何も気づかずに進んでしまう。
離れていく背中が寂しくて、見ていられなくて、その場に蹲った。映画館の入っているビルが日をさえぎるせいで、路地裏は薄暗い。
「……ようすけ」
僕は、君が好きだった。こんなに辛いのに、今もまだ、好きなままだった。
日に透ける金色の細い髪。寒がりですぐにくっつきたがるところ。美味しそうなパン屋さんを見つけるとふらふら吸い込まれていくところ。眠そうなときの、ふにゃふにゃした声。
僕の名前を呼ぶとき、少しだけ、声が低くなるところ。
「いかないで」
もう一度、名前を呼んで。
さみしいから、そばに居て。
「やっと言った」
聞こえた声に、弾かれるように顔をあげた。目を見開いて、彼を見上げる。暗がりの中でも、彼の髪は綺麗だった。形のいい眉をきゅっと寄せて、彼は唇を噛んでいる。
「よう、すけ」
なんで、君が泣きそうなの。
はらり。一筋、涙が頬を伝って、それで随分、視界が鮮明になる。陽介がくしゃくしゃになるくらい、上着の、お腹のあたりを握りしめているのが見えた。
「しわになっちゃうよ」
陽介の顔がさらに歪む。
そんな顔が、見たいわけじゃなかった。
やっぱり、行かないで、なんて、我儘を言わなければよかった。
立ち上がって、笑みを浮かべる。涙の跡は隠しようがないけれど。せめて、上手く笑えているだろうか。
「ごめん、ちょっとお腹が痛くて。今日は、解散にしようか」
顔を見ていられなくてうつむく。背中に回した両手に、痛いほど爪を食い込ませる。
「……んで」
かすれた声が聞こえた。
「なんで、そんなこと言うの」
震えた声が聞こえた。ぎゅっと強く、腕をつかまれる。
「俺のこと、もう好きじゃねーの?」
そんな、こと。
「やっぱ、あいつのがいいわけ? あいつのこと好きになっちゃったから、俺のことはもう要らないんだ?」
腹の底で、火花が散った。
「世界でいちばん幸せにします、とか言ったくせっ」
陽介の言葉が不自然に途切れる。当たり前だ。僕が殴ったから。手のひらがじんじんと痛かった。腹の底から煮えくり返る。陽介を睨みつけて怒鳴った。
「好きじゃないわけないだろ!!」
好きだよ。
「君が、どれだけ女の子と連絡をとっても、僕は何も言わなかった!」
好きだから、君の全部を許したかった。
「君がほかの人に触れていても、僕は絶対に怒らなかった!」
好きだから、行動を縛りたくなかった。
「君からの誘いがどれだけ急だって、僕から断ったことなんてない!」
好きだから、ほんのわずかな時間でも会いたかった。会っていいのだと、許されている関係が幸せだった。
毎日が、幸せで。
この日々が壊れないように、守ろうと必死だった。
「ぜんぶ、君と一緒に居たかったからだよ。陽介に、嫌われないためだよ」
怒りは一瞬で消え去って、胸の奥にぽっかりと巨大な寂しさだけが残る。こんなにも好きな人が、こんなにも傍にいるのに、報われない思いは、ただ、空しくて苦しい。
「……ごめん」
かすれた声で、陽介が言う。別れ話なら、もっとちゃんと言って欲しい。項垂れて、唾を飲み込む。台無しかもしれないけれど、最後の最後くらいは、笑って離れたかった。陽介の中に、ほんの少しでも、綺麗な欠片で残れるように。
「僕の、」
言葉が、途中で途切れる。強く、陽介に抱きしめられている。理解が、追いつかない。
[newpage]
あんな顔が、見たいわけじゃなかった。
苛立ちから歩調が速くなる。それを小走りで追いかける足音が聞こえた。どれだけ速く歩いても、その足音が追いかけてきてくれるのが、どうしようもなく嬉しかった。
まだ、絃は俺を追いかけてくれる。
まだ、俺を選んでくれてる。
でも、足を止めたら、告げられるのは別れ話かもしれないと思うと、歩き続けるしかなかった。目当ての和食屋はとっくに通り過ぎているのに。
あの店は小鉢を三つ、自分で選べるようになっていたから、絃が目を輝かせて、ようやく笑ってくれたかもしれないのに。
ずんずんと歩き続けて、ふと、追いかける足音が聞こえないことに気が付く。はっとして振り返る。絃は足止めて蹲っていた。さすがに速く歩きすぎて疲れたのかもしれない。絃は、あんまり、運動が得意じゃないから。足早に来た道を引き返す。彼の前に立ったとき、ようやく、聞きたかった言葉が聞こえた。
「いかないで」
あぁ、やっと。
「やっと、言った」
その言葉が、ずっと聞きたかった。引き留めて、縛り付けて、ここに居てと強請って欲しかった。
だって、好きってそういうことだろ。
絃が顔をあげる。いかないでと強請った俺が目の前に居たら、今度こそ笑ってくれると思ったのに、絃はまだ、泣いたままだった。ぼろぼろと丸い頬を水滴が伝う。
「よう、すけ」
なんで、泣いてんの。
なんで、もうずっと、俺の前では笑わないの。
映画館の前で、絃に声をかけてきた男の顔が浮かぶ。口元に手をあてて笑う絃は、文句なく楽しそうだった。肋骨の間に氷を押し当てられたような不快感があって、ぎゅっと上着を握りしめる。
「しわになっちゃうよ」
絃はまた、眉をさげて笑う。そんな顔が、見たいわけじゃなかった。そんな、作り笑いをさせたいわけじゃなかった。
「ごめん、ちょっとお腹が痛くて。今日は、解散にしようか」
聞こえた言葉と、逸らされた顔に、全身から力が抜けた。世界がぐにゃりと歪んで、突きつけられた事実に吐き気がする。
解散したら、お前どこ行くの。
あの、笑い合っていた名前も知らない男のとこ?
それとも、俺が見たこともない、ぜんぜん別の奴のとこ?
「……なんで」
俺は、絃が居れば、ほかには何も要らないのに。
「なんで、そんなこと言うの」
ぎゅっと、絃の細い腕をつかむ。手加減なんて、考えている余裕がなかった。
「俺のこと、もう好きじゃねーの?」
違うって、言って。好きだって、笑って。あの日みたいに、心の底からの、笑顔を見せて。
願っても、絃は怯えたように目を見開くばかりで、何も言ってくれない。脳裏にずっと、映画館の前で見た光景がこびりついている。
「やっぱ、あいつのがいいわけ? あいつのこと好きになっちゃったから、俺のことはもう要らないんだ?」
捨てないで。俺がいいって、言って。
「世界でいちばん幸せにします、とか言ったくせっ」
言葉の途中で、脳みそがぐらりと揺れた。遅れて、頬が熱を持つ。痛みはまだ訪れない。細い眉をよせて、絃が俺を睨んでいた。小さな手が赤くなっているから、たぶん、怒った絃が俺を叩いた。そう、遅れて理解する。
「好きじゃないわけないだろ!!!」
初めて、絃の、怒鳴り声を聞いた。
「君が、どれだけ女の子と連絡をとっても、僕は何も言わなかった!」
俺は、なんか言ってほしかった。
「君がほかの人に触れていても、僕は絶対に怒らなかった!」
俺は、僕だけにしてって強請って欲しかった。
「君からの誘いがどれだけ急だって、僕から断ったことなんてない!」
会いたいって言うのは、いつも俺の方からだった。
「ぜんぶ、君と一緒に居たかったからだよ。陽介に、嫌われないためだよ」
はらりと、絃の頬を涙が伝う。
あぁ、なんて馬鹿だったんだろう。
明確に、絃との違いを理解する。不安で、勝手に目をつむっていただけで、明かりはずっと、そこにあったのに。
「ごめん」
ずっと、俺がお前を傷つけてた。
だって、会いたいのも、触れたいのも、好きなのも。ぜんぶ俺だけなのかもとずっと不安だったから。俺にとっての『好き』の表し方と、絃の『好き』の伝え方が違うのかもなんてこと、考えもしなかった。
やさしくて、そのせいで少し臆病なところだって、好きなところのひとつなのに。
「僕の、」
何かを言いかけた絃を抱きしめる。
「ごめん」
もう一度、心の底から謝る。絃が笑えないのは、ずっと、ぜんぶ、俺のせいだった。
「好きだよ」
だから、ずっとそばに居てほしかった。
だから、縛り付けたかった。
同じように、縛ってほしかった。
「絃の前で、女の子と連絡とってる話したの『いかないで』って言って欲しかっただけ。ほんとは、全然、連絡なんかとってない」
しつこく送られてくるメッセージだって、返すのはせいぜい二日に一度。それだって、文字を打つのが面倒だから簡単なスタンプで済ませていた。
「不安だった、ずっと」
格好悪くて隠したかった言葉を、震える声で吐き出す。これで、本当に嫌われてしまうだろうか。やだな。まだ、ずっと、一緒に居たいな。
「会いたいって言うのも、触れるのも、キスすんのも、ぜんぶ俺からばっかりで」
でも、このまま、絃が傷ついて、ぼろぼろ泣いてるままの方が、ずっとやだな。
「俺は、恋人がほかの人とデートしたいって言ったら、いかないでって言うのが、好きってことだと思ってた」
絃の肩に甘えるように額を預ける。思えばいつだって俺は、この細い肩に寄りかかってばかりだ。
「だから、絃が『いかないで』って言ってくれないのが、やだった。俺のこと、もう好きじゃないって言われてるみたいで」
抱き寄せた体が震えている。少し体を離して、指先でそっと、涙をぬぐった。素直に絃が目を閉じるから、つい癖で、唇を重ねる。目を閉じたら、キスの合図。いつの間にか、絃のせいで刷り込まれた癖。
「……ばかだね、僕ら」
絃が涙でくぐもった声で言う。
「うん。ちゃんと言えなくて、ごめん」
絃の両手が、ちゃんと俺の首に回る。
「うん、僕も。会いたいも、好きも、陽介に嫌われるのが怖くて、言えなかった。ごめんね」
とくん、とくん、とくん。くっつくと、二人分の心音が重なって、混ざって、まるでひとつになったみたいな気持ちになる。もうこのままま、とけあって、離れなければいいのに。
「好きだよ、絃」
腕の中の絃に告げる。彼は少し、目を見開いて、それから。
春の空に浮かぶ雲のような、柔らかな笑みを浮かべた。
「僕も。大好きだよ、陽介」
なんで。
映画館の前で上からこちらを覗き込んだ陽介の顔が頭をよぎる。眉間に深く皺をよせて、むすっと唇を引き延ばして。その顔からゆっくりと力が抜けて、今度は泣き出す寸前のみたいになった。眉間にもう一度皺がよって、唇を強く噛んで、金色の瞳が涙で緩む。
なんで、そんな顔、君がするの。
泣きたいのは、どう考えたって僕の方だよ。
デートを忘れられて、楽しみにしていた特別な映画を、他の人と見に行くと言われて悲しかった。
その人との約束がダメになったからって、都合よく呼び出されたのが悔しかった。
映画館の座席で、まるで誰にも見られたくないみたいに、端っこを選ばれるのが寂しかった。
人恋しさを埋めるためだけに、繋がれる手が空しかった。
悲しくて、痛くて、辛くて、苦しい。
こんな恋、捨ててしまえればと思うのに、それでもまだ好きだから、泣き出しそうな顔を見て、心臓がぎゅっとなった。
「っ」
前を歩く陽介を呼ぼうとして、けれど声が出ない。視界が滲む。いかないで。早いよ。追いつけない。待って。どれも、何も、言葉にできなくて、溢れた気持ちがぼろぼろと涙に変わる。
静かに泣かないと。きっと、陽介の迷惑になる。
悲しくて泣いているのに、陽介に怒られたら、もっと悲しくなってしまう。唇を内側に巻き込んで、息を止める。そうすると、苦しくってもう走れなかった。
足が止まって。
陽介は、何も気づかずに進んでしまう。
離れていく背中が寂しくて、見ていられなくて、その場に蹲った。映画館の入っているビルが日をさえぎるせいで、路地裏は薄暗い。
「……ようすけ」
僕は、君が好きだった。こんなに辛いのに、今もまだ、好きなままだった。
日に透ける金色の細い髪。寒がりですぐにくっつきたがるところ。美味しそうなパン屋さんを見つけるとふらふら吸い込まれていくところ。眠そうなときの、ふにゃふにゃした声。
僕の名前を呼ぶとき、少しだけ、声が低くなるところ。
「いかないで」
もう一度、名前を呼んで。
さみしいから、そばに居て。
「やっと言った」
聞こえた声に、弾かれるように顔をあげた。目を見開いて、彼を見上げる。暗がりの中でも、彼の髪は綺麗だった。形のいい眉をきゅっと寄せて、彼は唇を噛んでいる。
「よう、すけ」
なんで、君が泣きそうなの。
はらり。一筋、涙が頬を伝って、それで随分、視界が鮮明になる。陽介がくしゃくしゃになるくらい、上着の、お腹のあたりを握りしめているのが見えた。
「しわになっちゃうよ」
陽介の顔がさらに歪む。
そんな顔が、見たいわけじゃなかった。
やっぱり、行かないで、なんて、我儘を言わなければよかった。
立ち上がって、笑みを浮かべる。涙の跡は隠しようがないけれど。せめて、上手く笑えているだろうか。
「ごめん、ちょっとお腹が痛くて。今日は、解散にしようか」
顔を見ていられなくてうつむく。背中に回した両手に、痛いほど爪を食い込ませる。
「……んで」
かすれた声が聞こえた。
「なんで、そんなこと言うの」
震えた声が聞こえた。ぎゅっと強く、腕をつかまれる。
「俺のこと、もう好きじゃねーの?」
そんな、こと。
「やっぱ、あいつのがいいわけ? あいつのこと好きになっちゃったから、俺のことはもう要らないんだ?」
腹の底で、火花が散った。
「世界でいちばん幸せにします、とか言ったくせっ」
陽介の言葉が不自然に途切れる。当たり前だ。僕が殴ったから。手のひらがじんじんと痛かった。腹の底から煮えくり返る。陽介を睨みつけて怒鳴った。
「好きじゃないわけないだろ!!」
好きだよ。
「君が、どれだけ女の子と連絡をとっても、僕は何も言わなかった!」
好きだから、君の全部を許したかった。
「君がほかの人に触れていても、僕は絶対に怒らなかった!」
好きだから、行動を縛りたくなかった。
「君からの誘いがどれだけ急だって、僕から断ったことなんてない!」
好きだから、ほんのわずかな時間でも会いたかった。会っていいのだと、許されている関係が幸せだった。
毎日が、幸せで。
この日々が壊れないように、守ろうと必死だった。
「ぜんぶ、君と一緒に居たかったからだよ。陽介に、嫌われないためだよ」
怒りは一瞬で消え去って、胸の奥にぽっかりと巨大な寂しさだけが残る。こんなにも好きな人が、こんなにも傍にいるのに、報われない思いは、ただ、空しくて苦しい。
「……ごめん」
かすれた声で、陽介が言う。別れ話なら、もっとちゃんと言って欲しい。項垂れて、唾を飲み込む。台無しかもしれないけれど、最後の最後くらいは、笑って離れたかった。陽介の中に、ほんの少しでも、綺麗な欠片で残れるように。
「僕の、」
言葉が、途中で途切れる。強く、陽介に抱きしめられている。理解が、追いつかない。
[newpage]
あんな顔が、見たいわけじゃなかった。
苛立ちから歩調が速くなる。それを小走りで追いかける足音が聞こえた。どれだけ速く歩いても、その足音が追いかけてきてくれるのが、どうしようもなく嬉しかった。
まだ、絃は俺を追いかけてくれる。
まだ、俺を選んでくれてる。
でも、足を止めたら、告げられるのは別れ話かもしれないと思うと、歩き続けるしかなかった。目当ての和食屋はとっくに通り過ぎているのに。
あの店は小鉢を三つ、自分で選べるようになっていたから、絃が目を輝かせて、ようやく笑ってくれたかもしれないのに。
ずんずんと歩き続けて、ふと、追いかける足音が聞こえないことに気が付く。はっとして振り返る。絃は足止めて蹲っていた。さすがに速く歩きすぎて疲れたのかもしれない。絃は、あんまり、運動が得意じゃないから。足早に来た道を引き返す。彼の前に立ったとき、ようやく、聞きたかった言葉が聞こえた。
「いかないで」
あぁ、やっと。
「やっと、言った」
その言葉が、ずっと聞きたかった。引き留めて、縛り付けて、ここに居てと強請って欲しかった。
だって、好きってそういうことだろ。
絃が顔をあげる。いかないでと強請った俺が目の前に居たら、今度こそ笑ってくれると思ったのに、絃はまだ、泣いたままだった。ぼろぼろと丸い頬を水滴が伝う。
「よう、すけ」
なんで、泣いてんの。
なんで、もうずっと、俺の前では笑わないの。
映画館の前で、絃に声をかけてきた男の顔が浮かぶ。口元に手をあてて笑う絃は、文句なく楽しそうだった。肋骨の間に氷を押し当てられたような不快感があって、ぎゅっと上着を握りしめる。
「しわになっちゃうよ」
絃はまた、眉をさげて笑う。そんな顔が、見たいわけじゃなかった。そんな、作り笑いをさせたいわけじゃなかった。
「ごめん、ちょっとお腹が痛くて。今日は、解散にしようか」
聞こえた言葉と、逸らされた顔に、全身から力が抜けた。世界がぐにゃりと歪んで、突きつけられた事実に吐き気がする。
解散したら、お前どこ行くの。
あの、笑い合っていた名前も知らない男のとこ?
それとも、俺が見たこともない、ぜんぜん別の奴のとこ?
「……なんで」
俺は、絃が居れば、ほかには何も要らないのに。
「なんで、そんなこと言うの」
ぎゅっと、絃の細い腕をつかむ。手加減なんて、考えている余裕がなかった。
「俺のこと、もう好きじゃねーの?」
違うって、言って。好きだって、笑って。あの日みたいに、心の底からの、笑顔を見せて。
願っても、絃は怯えたように目を見開くばかりで、何も言ってくれない。脳裏にずっと、映画館の前で見た光景がこびりついている。
「やっぱ、あいつのがいいわけ? あいつのこと好きになっちゃったから、俺のことはもう要らないんだ?」
捨てないで。俺がいいって、言って。
「世界でいちばん幸せにします、とか言ったくせっ」
言葉の途中で、脳みそがぐらりと揺れた。遅れて、頬が熱を持つ。痛みはまだ訪れない。細い眉をよせて、絃が俺を睨んでいた。小さな手が赤くなっているから、たぶん、怒った絃が俺を叩いた。そう、遅れて理解する。
「好きじゃないわけないだろ!!!」
初めて、絃の、怒鳴り声を聞いた。
「君が、どれだけ女の子と連絡をとっても、僕は何も言わなかった!」
俺は、なんか言ってほしかった。
「君がほかの人に触れていても、僕は絶対に怒らなかった!」
俺は、僕だけにしてって強請って欲しかった。
「君からの誘いがどれだけ急だって、僕から断ったことなんてない!」
会いたいって言うのは、いつも俺の方からだった。
「ぜんぶ、君と一緒に居たかったからだよ。陽介に、嫌われないためだよ」
はらりと、絃の頬を涙が伝う。
あぁ、なんて馬鹿だったんだろう。
明確に、絃との違いを理解する。不安で、勝手に目をつむっていただけで、明かりはずっと、そこにあったのに。
「ごめん」
ずっと、俺がお前を傷つけてた。
だって、会いたいのも、触れたいのも、好きなのも。ぜんぶ俺だけなのかもとずっと不安だったから。俺にとっての『好き』の表し方と、絃の『好き』の伝え方が違うのかもなんてこと、考えもしなかった。
やさしくて、そのせいで少し臆病なところだって、好きなところのひとつなのに。
「僕の、」
何かを言いかけた絃を抱きしめる。
「ごめん」
もう一度、心の底から謝る。絃が笑えないのは、ずっと、ぜんぶ、俺のせいだった。
「好きだよ」
だから、ずっとそばに居てほしかった。
だから、縛り付けたかった。
同じように、縛ってほしかった。
「絃の前で、女の子と連絡とってる話したの『いかないで』って言って欲しかっただけ。ほんとは、全然、連絡なんかとってない」
しつこく送られてくるメッセージだって、返すのはせいぜい二日に一度。それだって、文字を打つのが面倒だから簡単なスタンプで済ませていた。
「不安だった、ずっと」
格好悪くて隠したかった言葉を、震える声で吐き出す。これで、本当に嫌われてしまうだろうか。やだな。まだ、ずっと、一緒に居たいな。
「会いたいって言うのも、触れるのも、キスすんのも、ぜんぶ俺からばっかりで」
でも、このまま、絃が傷ついて、ぼろぼろ泣いてるままの方が、ずっとやだな。
「俺は、恋人がほかの人とデートしたいって言ったら、いかないでって言うのが、好きってことだと思ってた」
絃の肩に甘えるように額を預ける。思えばいつだって俺は、この細い肩に寄りかかってばかりだ。
「だから、絃が『いかないで』って言ってくれないのが、やだった。俺のこと、もう好きじゃないって言われてるみたいで」
抱き寄せた体が震えている。少し体を離して、指先でそっと、涙をぬぐった。素直に絃が目を閉じるから、つい癖で、唇を重ねる。目を閉じたら、キスの合図。いつの間にか、絃のせいで刷り込まれた癖。
「……ばかだね、僕ら」
絃が涙でくぐもった声で言う。
「うん。ちゃんと言えなくて、ごめん」
絃の両手が、ちゃんと俺の首に回る。
「うん、僕も。会いたいも、好きも、陽介に嫌われるのが怖くて、言えなかった。ごめんね」
とくん、とくん、とくん。くっつくと、二人分の心音が重なって、混ざって、まるでひとつになったみたいな気持ちになる。もうこのままま、とけあって、離れなければいいのに。
「好きだよ、絃」
腕の中の絃に告げる。彼は少し、目を見開いて、それから。
春の空に浮かぶ雲のような、柔らかな笑みを浮かべた。
「僕も。大好きだよ、陽介」