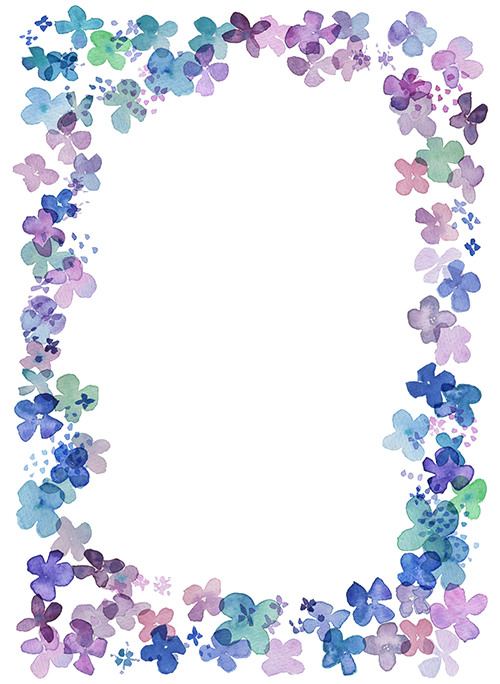好きな子に、好きだと言って。
好きな子が、俺の言葉ではにかむように笑って。
その瞬間を今も、何度でも求めている。
「席、どこがいい?」
映画館の券売機を操作しながら、絃が振り返る。俺よりも少し背が低いから、自然と目線は見上げる形だ。目が合うと少し赤く染まる、丸みを帯びた頬が愛おしい。
「端っこ」
絃の後ろから券売機の液晶に手を伸ばした。細い肩に顎を乗せて画面をのぞき込む。
「珍しいね」
「そ?」
「うん。だいたい、真ん中を選ぶものじゃない?」
絃はせわしなく胸の前で両手を組み替えている。たぶん、後ろから抱きしめるような姿勢が気恥ずかしいのだろう。ついでに顔も近いから、それも彼の落ち着きのなさに拍車をかけている。のだと思う。
「お前とだから、端っこ」
だって、真ん中なんて選んだら、どう頑張っても絃の隣に他人が座る可能性を捨てきれない。隣に座ったそいつは、どさくさに紛れて絃に触れるかもしれない。触れなくても、視界には映すだろう。
そんなことになったら、減るだろ。
俺の絃なのに。
「そっか。なんか、ごめん」
絃は瞼をふせて、組んだ両手に力を込めた。そっと視線だけを動かして顔を覗き込めば、小さな唇は内側に巻き込まれている。
(なんで、そんな顔すんの)
俺が聞く前に絃は取り繕った笑みを浮かべた。だから俺は、何も聞けないまま絃の言葉を聞く。
「ほんとは、リカちゃんと来る予定だったのに、僕相手になっちゃったし」
体温が、少し離れる。絃が身を引いたのだと理解して、眉間に深く皺が寄った。なんで、離れんの。「ごめんね」眉を下げて、絃が笑う。そんな顔が見たいわけじゃないのに、もうずっと、そんな笑みしか見ていないような気がする。
「別に」
そもそも、絃に『いかないで』と言ってほしくて約束を取り付けただけだけで、デートをするつもりなんてなかったから、そんなことは本当に、これっぽっちも、全然気にしていない。けれど、絃が今と同じ顔で、俺がほかの奴とデートすることを『たのしみだね』と言い放ったのは気にしていたから、眉間の皺はさらに深くなった。
小さな音をたてて、映画のチケットが吐き出される。幅広のレシートに似た紙はチケット言うには少し味気ない。二人分のそれを乱暴にとって、財布にしまい込んだ。
これで、絃は映画を見終わるまで、俺のそばを離れられない。
「飯、何にする?」
カーディガンに半分隠れた小さな手を取る。指先をそっと握りこめば、笑ってくれると思った。けれど、絃の肩には力が入るばかりで、表情はずっとぎこちない。
なんで、そんな顔すんの。
なんで、そんななの。
「陽介は、何食べたい? あ、そういえば、陽介が好きなパン屋さん、新作の看板出てたよ」
「ふーん」
あのパン屋は確かに好きだけど、絃はどちらかと言うと和食派だ。映画館の入ったビルから少し歩いたところにある、おいしそうな和食屋さんをもう予約してある。
「パンじゃ、ちょっと軽すぎるか」
うーん、どこがいいかなぁ。
片手でスマホをいじりながら、絃は飯屋を探している。考え事をしているとき、少し唇がとがるのが可愛くて好きだ。今、キスしたら、怒るかな。怒るだろうな。俺はいつだって絃に触れたくて、触れていることで俺のだって他人から分かるようにしていたいけれど、絃はどうも、人前で触れ合うのが嫌いみたいだから。
嫌いなことは、したくない。
だから、きゅっと指先を握る手に力を込めて、体を寄せる。
「食いたいとこある。いこ」
「え。あ、うん」
そっと手を引けば、絃は何も言わずに付いてくる。歩調を緩めて、隣に並んだ。絃が俯いているせいで、顔はよく見えない。苦い唾を飲み込んで、頭をフル回転にして言葉を探した。なにか。なにか、絃を笑わせられるような、そんな言葉。
例えば、あの日と同じように、好きだと言ってみるとか。
例えば、仲良くなりたくて読み込んだ絃の好きな小説家の話とか。
例えば、たとえば。
「い「あれ!? 絃じゃん!」
するりと、指先が離れた。え。なんで。
なんで、今離すの。
絃はくるりと、声がした方を振り返る。その肩から力が抜けたのが、はっきりと分かった。目の前がじぃんと黒に染まる。
「わ、如月くん! 偶然だね」
「な! つか、私服見慣れねー」
「ほんとに」
くすくすと笑い合う絃とそいつは、なんだかとても仲がよさそうだった。
「絃」
焦れて、名前を呼んだ。絃が離れた半歩分の距離をつめて、後ろから抱き寄せる。「え、ちょ、陽介?」戸惑ったような声が聞こえたけれど、それに答える余裕はない。たぶん可愛いことになっているだろう絃の顔を片手で出来る限り隠して、俺はそいつを睨みつけた。
「おまえ、なに」
せっかくのひと月ぶりのデートに水をさして。俺が見たくてたまらない、絃の笑顔を簡単に引き出して。
「え、なにって……友達、だけど」
なんとなく歯切れの悪い答えに、頭の中で何かが繋がる音がする。あるいは、ぱちぱちとパズルのピースがはまる音。
「あっそ」
ぎゅっと、顔を隠していない方の腕で絃の腰を抱き寄せた。こいつが、絃のなんであれ関係はない。絃が俺に好きだと言った日から、絃は俺の物だ。
「お前にかまってる時間ないから、さっさと消えてくんない」
「ちょ、陽介! 何言ってんの」
「お前が何言ってんの。なに、こいつのがいいわけ?」
俺の腕から逃れようともがく絃を上から覗き込む。早く。早く、そんなことないよって言って。俺が好きだって、言って。
「っ」
絃は口をつぐむ。
目の前が、真っ暗になった。
なんて。真っ暗になったのは頭の中だけで、正常な視界は絃の泣き出す寸前のような表情を真正面からとらえていた。
あーぁ。
そんな顔、させたいわけじゃないのに。
初めて好きだと伝えたときの、春の空に浮かぶ雲のような、柔らかな笑みが瞼の裏に浮かんだ。
好きな子が、俺の言葉ではにかむように笑って。
その瞬間を今も、何度でも求めている。
「席、どこがいい?」
映画館の券売機を操作しながら、絃が振り返る。俺よりも少し背が低いから、自然と目線は見上げる形だ。目が合うと少し赤く染まる、丸みを帯びた頬が愛おしい。
「端っこ」
絃の後ろから券売機の液晶に手を伸ばした。細い肩に顎を乗せて画面をのぞき込む。
「珍しいね」
「そ?」
「うん。だいたい、真ん中を選ぶものじゃない?」
絃はせわしなく胸の前で両手を組み替えている。たぶん、後ろから抱きしめるような姿勢が気恥ずかしいのだろう。ついでに顔も近いから、それも彼の落ち着きのなさに拍車をかけている。のだと思う。
「お前とだから、端っこ」
だって、真ん中なんて選んだら、どう頑張っても絃の隣に他人が座る可能性を捨てきれない。隣に座ったそいつは、どさくさに紛れて絃に触れるかもしれない。触れなくても、視界には映すだろう。
そんなことになったら、減るだろ。
俺の絃なのに。
「そっか。なんか、ごめん」
絃は瞼をふせて、組んだ両手に力を込めた。そっと視線だけを動かして顔を覗き込めば、小さな唇は内側に巻き込まれている。
(なんで、そんな顔すんの)
俺が聞く前に絃は取り繕った笑みを浮かべた。だから俺は、何も聞けないまま絃の言葉を聞く。
「ほんとは、リカちゃんと来る予定だったのに、僕相手になっちゃったし」
体温が、少し離れる。絃が身を引いたのだと理解して、眉間に深く皺が寄った。なんで、離れんの。「ごめんね」眉を下げて、絃が笑う。そんな顔が見たいわけじゃないのに、もうずっと、そんな笑みしか見ていないような気がする。
「別に」
そもそも、絃に『いかないで』と言ってほしくて約束を取り付けただけだけで、デートをするつもりなんてなかったから、そんなことは本当に、これっぽっちも、全然気にしていない。けれど、絃が今と同じ顔で、俺がほかの奴とデートすることを『たのしみだね』と言い放ったのは気にしていたから、眉間の皺はさらに深くなった。
小さな音をたてて、映画のチケットが吐き出される。幅広のレシートに似た紙はチケット言うには少し味気ない。二人分のそれを乱暴にとって、財布にしまい込んだ。
これで、絃は映画を見終わるまで、俺のそばを離れられない。
「飯、何にする?」
カーディガンに半分隠れた小さな手を取る。指先をそっと握りこめば、笑ってくれると思った。けれど、絃の肩には力が入るばかりで、表情はずっとぎこちない。
なんで、そんな顔すんの。
なんで、そんななの。
「陽介は、何食べたい? あ、そういえば、陽介が好きなパン屋さん、新作の看板出てたよ」
「ふーん」
あのパン屋は確かに好きだけど、絃はどちらかと言うと和食派だ。映画館の入ったビルから少し歩いたところにある、おいしそうな和食屋さんをもう予約してある。
「パンじゃ、ちょっと軽すぎるか」
うーん、どこがいいかなぁ。
片手でスマホをいじりながら、絃は飯屋を探している。考え事をしているとき、少し唇がとがるのが可愛くて好きだ。今、キスしたら、怒るかな。怒るだろうな。俺はいつだって絃に触れたくて、触れていることで俺のだって他人から分かるようにしていたいけれど、絃はどうも、人前で触れ合うのが嫌いみたいだから。
嫌いなことは、したくない。
だから、きゅっと指先を握る手に力を込めて、体を寄せる。
「食いたいとこある。いこ」
「え。あ、うん」
そっと手を引けば、絃は何も言わずに付いてくる。歩調を緩めて、隣に並んだ。絃が俯いているせいで、顔はよく見えない。苦い唾を飲み込んで、頭をフル回転にして言葉を探した。なにか。なにか、絃を笑わせられるような、そんな言葉。
例えば、あの日と同じように、好きだと言ってみるとか。
例えば、仲良くなりたくて読み込んだ絃の好きな小説家の話とか。
例えば、たとえば。
「い「あれ!? 絃じゃん!」
するりと、指先が離れた。え。なんで。
なんで、今離すの。
絃はくるりと、声がした方を振り返る。その肩から力が抜けたのが、はっきりと分かった。目の前がじぃんと黒に染まる。
「わ、如月くん! 偶然だね」
「な! つか、私服見慣れねー」
「ほんとに」
くすくすと笑い合う絃とそいつは、なんだかとても仲がよさそうだった。
「絃」
焦れて、名前を呼んだ。絃が離れた半歩分の距離をつめて、後ろから抱き寄せる。「え、ちょ、陽介?」戸惑ったような声が聞こえたけれど、それに答える余裕はない。たぶん可愛いことになっているだろう絃の顔を片手で出来る限り隠して、俺はそいつを睨みつけた。
「おまえ、なに」
せっかくのひと月ぶりのデートに水をさして。俺が見たくてたまらない、絃の笑顔を簡単に引き出して。
「え、なにって……友達、だけど」
なんとなく歯切れの悪い答えに、頭の中で何かが繋がる音がする。あるいは、ぱちぱちとパズルのピースがはまる音。
「あっそ」
ぎゅっと、顔を隠していない方の腕で絃の腰を抱き寄せた。こいつが、絃のなんであれ関係はない。絃が俺に好きだと言った日から、絃は俺の物だ。
「お前にかまってる時間ないから、さっさと消えてくんない」
「ちょ、陽介! 何言ってんの」
「お前が何言ってんの。なに、こいつのがいいわけ?」
俺の腕から逃れようともがく絃を上から覗き込む。早く。早く、そんなことないよって言って。俺が好きだって、言って。
「っ」
絃は口をつぐむ。
目の前が、真っ暗になった。
なんて。真っ暗になったのは頭の中だけで、正常な視界は絃の泣き出す寸前のような表情を真正面からとらえていた。
あーぁ。
そんな顔、させたいわけじゃないのに。
初めて好きだと伝えたときの、春の空に浮かぶ雲のような、柔らかな笑みが瞼の裏に浮かんだ。