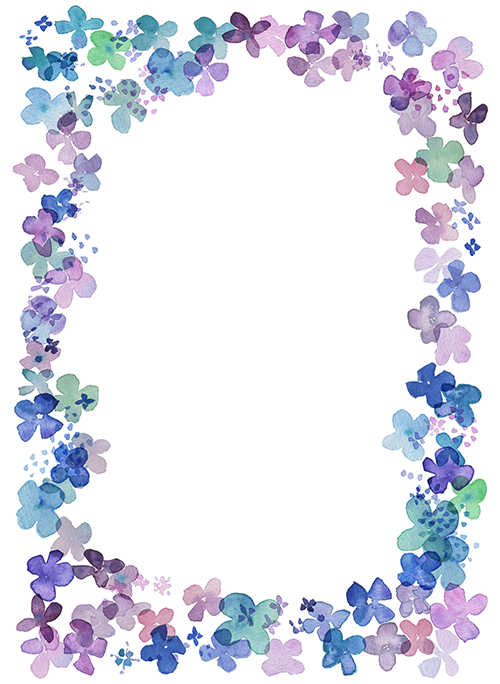好きな人に、好きだと伝えて。
好きな人から、好きだと言われて。
僕の人生は、たぶん、そこがクライマックスだった。
「土曜なんだけどさー、俺、隣のクラスのリカちゃんに誘われちゃって」
少し、冷たい風の吹き始めた屋上に乾いた言葉が転がる。陽介は、食べ終えたメロンパンの袋を丸めながら、上目遣いで僕を見た。
「リカちゃん」
土曜は、ひと月ぶりのデートのはずだったのに。喉元まで出かかった『いかないで』をどうにか飲み込んで、僕は話に出てきた女の子の名前を繰り返す。
「そー。絃も聞いたことあるでしょ? 学年一の美少女って」
そうなんだ。僕の頭に濃く残っている噂は、そんな美少女が陽介を狙っているらしいというもので、学年一なのはすっかり忘れていた。
嘘。
あまりにライバルとして恐ろしいから、そんな情報は忘れたふりをしていた。
「そうなんだ」
お弁当箱の蓋をしめながら答える。
「そうなの。ずっと連絡とってたんだけど、リカちゃんも二ノ前先生好きらしくてさ」
僕と陽介を繋いだ小説家の名前をあげて、陽介はデレっと頬を緩める。僕が弁当箱を袋にしまい終えると、まるでそれを待っていたかのように、陽介は僕の膝に頭を乗せた。いつものルーティーンだ。お昼ご飯を食べ終えてから、昼休みが終わるまでの短い時間を、僕らはこうして恋人らしく、くっついて過ごす。
「ほら、今度映画になんじゃん?」
だから、二人で見に行こうと約束をしていたのに、陽介はそんなこと、すっかり忘れている様子だ。
「そうだね」
僕は何も言えずに、ただ笑って頷く。
「せっかくだから朝イチ見に行って、そのまま飯食いながら語ろーって話になってさぁ」
ゆっくりと陽介の頭を撫でる。懐いた猫みたいに、陽介は気持ちよさそうに目を閉じた。
「たのしみだね」
僕はどうにか、そんな言葉を絞り出す。心の中は大荒れで、少しでも油断したら、行かないでと叫びそうだった。僕以外と連絡なんて取らないでと強請ってしまいそうだった。うっかり、泣いてしまいそうだったら陽介にバレないように空を見上げる。
「……そーなの。ちょー、たのしみ」
ごろん、と陽介が寝返りを打ったのが体重の移動で分かった。そのまま、ぐりぐりとまるで甘えるように、お腹に額をこすりつけられる。くすぐったくて、少し笑えた。目じりに雫がついたのは、笑ったせいだ。
「なに、くすぐったいよ」
陽介のふわふわした金色の髪を撫でつける。ぼんやり、薄く開いた両目が僕をとらえる。髪と同じ、金色の瞳。骨ばった大きな手が首筋を撫でる。ぞくり、と鳥肌が立った。
「いと」
かすれた声で、名前を呼ばれる。それだけでもう、指一本も自由には動かせない。引き寄せられるまま、背中を丸めて。ぐっと上半身を半分起こした陽介との距離が縮まる。「目、閉じて」言われるまま、そっと瞼を下ろす。暗闇の中で、ぬるい温度が唇に触れる。触れ合いは、ほんの一瞬で、縋りつくように目を開いた。
「閉じてろって」
完全に体を起こした陽介が大きな手で目をふさぐ。僕がおとなしく目を閉じると、骨ばった細い指がくすぐるように耳の後ろを撫でた。
「いーこ」
陽介に、褒められるのが好きだ。ご褒美だというように、先ほどよりも長いキスが降ってくる。ぬるりと侵入してくる舌には、まだ慣れない。ぞわぞわする感覚をどこに逃がしたらいいのか分からなくて、ぎゅっと皺になるくらい強く、ズボンを握りしめる。
「よ、すけ」
吐息の隙間で名前を呼ぶ。応えるように陽介の指先が首筋を撫でる。陽介は麻酔みたいだ。触れられたところ全部、力が抜けてしまう。「よう、すけ」触れているところは熱いのに、体の奥には熱がこもるのに、あまりに寂しくて名前を呼んだ。
「なぁに」
うっすらと目を開けると、少しだけ頬を赤く染めた陽介と視線が交わる。
そんな風に、悩まし気な角度で眉を寄せておいて。
そんな風に、愛おしそうに目を細めておいて。
そんな風に、僕が好きでたまらないような顔をしておいて。
「昼休み、もう終わるよ」
陽介は、ひと月ぶりのデートすら、僕に許してはくれないのだ。
遠くで、二人きりの時間の終わりを告げるチャイムが、高らかに鳴り響いた。
好きな人から、好きだと言われて。
僕の人生は、たぶん、そこがクライマックスだった。
「土曜なんだけどさー、俺、隣のクラスのリカちゃんに誘われちゃって」
少し、冷たい風の吹き始めた屋上に乾いた言葉が転がる。陽介は、食べ終えたメロンパンの袋を丸めながら、上目遣いで僕を見た。
「リカちゃん」
土曜は、ひと月ぶりのデートのはずだったのに。喉元まで出かかった『いかないで』をどうにか飲み込んで、僕は話に出てきた女の子の名前を繰り返す。
「そー。絃も聞いたことあるでしょ? 学年一の美少女って」
そうなんだ。僕の頭に濃く残っている噂は、そんな美少女が陽介を狙っているらしいというもので、学年一なのはすっかり忘れていた。
嘘。
あまりにライバルとして恐ろしいから、そんな情報は忘れたふりをしていた。
「そうなんだ」
お弁当箱の蓋をしめながら答える。
「そうなの。ずっと連絡とってたんだけど、リカちゃんも二ノ前先生好きらしくてさ」
僕と陽介を繋いだ小説家の名前をあげて、陽介はデレっと頬を緩める。僕が弁当箱を袋にしまい終えると、まるでそれを待っていたかのように、陽介は僕の膝に頭を乗せた。いつものルーティーンだ。お昼ご飯を食べ終えてから、昼休みが終わるまでの短い時間を、僕らはこうして恋人らしく、くっついて過ごす。
「ほら、今度映画になんじゃん?」
だから、二人で見に行こうと約束をしていたのに、陽介はそんなこと、すっかり忘れている様子だ。
「そうだね」
僕は何も言えずに、ただ笑って頷く。
「せっかくだから朝イチ見に行って、そのまま飯食いながら語ろーって話になってさぁ」
ゆっくりと陽介の頭を撫でる。懐いた猫みたいに、陽介は気持ちよさそうに目を閉じた。
「たのしみだね」
僕はどうにか、そんな言葉を絞り出す。心の中は大荒れで、少しでも油断したら、行かないでと叫びそうだった。僕以外と連絡なんて取らないでと強請ってしまいそうだった。うっかり、泣いてしまいそうだったら陽介にバレないように空を見上げる。
「……そーなの。ちょー、たのしみ」
ごろん、と陽介が寝返りを打ったのが体重の移動で分かった。そのまま、ぐりぐりとまるで甘えるように、お腹に額をこすりつけられる。くすぐったくて、少し笑えた。目じりに雫がついたのは、笑ったせいだ。
「なに、くすぐったいよ」
陽介のふわふわした金色の髪を撫でつける。ぼんやり、薄く開いた両目が僕をとらえる。髪と同じ、金色の瞳。骨ばった大きな手が首筋を撫でる。ぞくり、と鳥肌が立った。
「いと」
かすれた声で、名前を呼ばれる。それだけでもう、指一本も自由には動かせない。引き寄せられるまま、背中を丸めて。ぐっと上半身を半分起こした陽介との距離が縮まる。「目、閉じて」言われるまま、そっと瞼を下ろす。暗闇の中で、ぬるい温度が唇に触れる。触れ合いは、ほんの一瞬で、縋りつくように目を開いた。
「閉じてろって」
完全に体を起こした陽介が大きな手で目をふさぐ。僕がおとなしく目を閉じると、骨ばった細い指がくすぐるように耳の後ろを撫でた。
「いーこ」
陽介に、褒められるのが好きだ。ご褒美だというように、先ほどよりも長いキスが降ってくる。ぬるりと侵入してくる舌には、まだ慣れない。ぞわぞわする感覚をどこに逃がしたらいいのか分からなくて、ぎゅっと皺になるくらい強く、ズボンを握りしめる。
「よ、すけ」
吐息の隙間で名前を呼ぶ。応えるように陽介の指先が首筋を撫でる。陽介は麻酔みたいだ。触れられたところ全部、力が抜けてしまう。「よう、すけ」触れているところは熱いのに、体の奥には熱がこもるのに、あまりに寂しくて名前を呼んだ。
「なぁに」
うっすらと目を開けると、少しだけ頬を赤く染めた陽介と視線が交わる。
そんな風に、悩まし気な角度で眉を寄せておいて。
そんな風に、愛おしそうに目を細めておいて。
そんな風に、僕が好きでたまらないような顔をしておいて。
「昼休み、もう終わるよ」
陽介は、ひと月ぶりのデートすら、僕に許してはくれないのだ。
遠くで、二人きりの時間の終わりを告げるチャイムが、高らかに鳴り響いた。