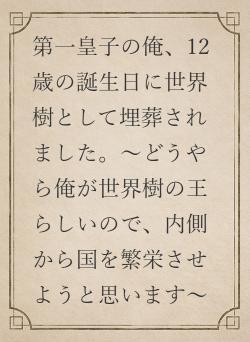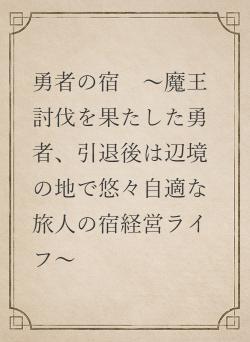「なあ、リシア」
「なんでしょう?」
「そろそろ婚約破棄……」
「嫌です!」
一体何度目のやり取りだろうか。
今日は王太子殿下の誕生パーティーだというのに相も変わらずこの人は……。
「リシアほどの好物件を俺のところに嫁がせるなんてどうやってもおかしいって」
私の横で、割と本気な顔でこんなことを宣うこの男は私の婚約者であるファレス・フェルナード子爵令息だ。子爵家の出身だと言うのに全く貴族らしくないこの男には剣の才も魔法の才も全くと言っていいほどない。
「そうですか?私はそれほど好物件とも思えませんが?」
「いやいや、だってリシアはあの勇爵として高名なマルス伯爵家のご令嬢で学院でも抜群の魔法の才を発揮しているいわば高嶺の花ってやつじゃないか!」
「そう言われましても、戦争が終わってしまった今となっては、力の強い女など白鳥に剣を持たせているようなものですわ」
「はぁ……またその例えか。戦争なんて人が存在し続ける限りいつでも起こりうるんだ。男女関係なく実力があるに越したことはないだろうと言うのに……」
私たちの会話はいつもここで平行線を辿っている。
まぁもし、ファレス様がこれに続く二の矢、三の矢を放って来ようと私がこの手を放すつもりはないのだけれど。
私は控えめに組んだ腕に少し力を込めた。
「お、これはこれは無能のファレスくんではないか。それにリシアさんも。いつ見てもキミは麗しいね。気高く強く、どんな台地でも同じように輝きを放つ一輪の薔薇のようだよ」
「王太子殿下、本日はおめでとうございます」
あれだけ言われても顔色一つ変えないファレス様に続いて私もお祝い申し上げた。
私は正直この男、メフィト王太子殿下が嫌いだ。
「ハハっ、ありがとう。せっかくのパーティーなんだ、無能なキミも楽しんでくれ」
……この男、言わせておけば!
思わず言い返しそうになる私の腕をファレス様は軽く引いた。
すると面白くなさそうな顔をしてメフィト王太子殿下は言葉を続ける。
「そういえば、キミは先日の魔法実技のテストでも最下位を取ったそうじゃないか!情けないとは思わないのかい?キミの婚約者は僕でも及ばない不動のトップだというのに」
主役であり、ただでさえ目立っているというのに周りにも聞かせるように王太子殿下は声を張り上げた。
「おっしゃるとおりかと……全く、自分の無力を嘆く日々です」
それでもファレス様は全く動じた様子を見せない。
心にもないことを……。
「へぇ、ということはキミ自身も自分がリシアさんにふさわしくないことは認めるんだ?」
「もちろんです殿下。リシアは私にはもったいない女性ですよ」
「じゃあ、どうだい?婚約破棄をするというのは」
そのセリフについに我慢の限界に達した私は
「殿下っ!いくら殿下とは言えそのようにプライベートにまで口を出されるのはいかがなものかと!」
と、口に出してしまった。
だが――
「殿下のお言葉はもっともです。ですがリシアの言う通りこれは私とリシアの問題。急ですが今のお話を二人でしたいと思いますので今日はこの辺りでお暇させていただきたく」
ファレス様は殿下の言葉も私の態度を全く気にせず、調子を変えずに淡々とそう言う。
「そうか。いいぞ、二人でよく話し合うといい」
お祝いをした今、無理に引き留める口実はなく、いやな注目を浴びたまま長引きそうだったパーティーをあっさり後にすることができた。
◇◇
「リシア……さすがに殿下に噛みつくのは危ないよ。あの人は最高権力者なんだからね?」
パーティー会場を出て、薄く闇がかった道を歩きながらファレス様に諫められる。
「ファレス様は私のことがお嫌いですか?」
「まさか……俺が嫌われることはあっても俺が嫌うことはないだろう」
……じゃあ、どうして婚約破棄を求め続けているのか。
本当に食えない人だ……。
「それより、婚約破棄の件だが」
「しませんよ?」
またその話か、と若干腹が立つ。
「いったいどうしてリシアはそんなに頑ななんだ……」
ファレス様は額に手を添えて溜息をつくが、そんなもの決まっている。
貴方が――
「貴方が王国の闇と言われる戦争終結の立役者だからです!」
「……何を言っているんだリシア?」
少し驚いた顔をするファレス様をおいて、私は続ける。
「誤魔化さないでください!私はマルス伯爵令嬢ですのよ!いくら隠し立てしようと分かるものは分かるのです!」
一度溢れ出した思いはもう止まらなかった。
「3年前の大戦争。我がマルス伯爵家が勇爵と呼ばれるようになったあの戦争でお父様が立てられた功績は確かに目を見張るものでした。しかし、勇爵の名を賜るに至った最高の功績、帝国指揮官であった皇帝の首を打ち取ったのは貴方でしょう!」
「リシア……ちょっと声を押さえて……」
「ファレス様は詰めが甘かったですわね。こう見えても私、お父様には可愛がられているのです!私が聞けばなんでも教えてくださいますわ!」
そこまで言い切ると、またファレス様は額に手を添えて今度は苦い顔をした。
◇◇◇(3年前ファレス視点 回想)
「貴様は何者だ!」
勇猛果敢、名将と名高いグランデ・マルス伯爵にその瞬間を目撃されてしまった。
「これは……」
俺の目の前に転がるのは敵味方両軍の兵士と一騎当千を謳われ、現役時代は最強と恐れられたと言う帝国の皇帝。
その名の通りもう齢70を過ぎているだろうと言うのに、なかなかに厄介な相手だった。
実際に俺以外の兵は皆やられてしまった。
「いや、待て……その紋はまさか王都の闇!?」
俺の手に握られた短剣の紋を見てグランデ伯爵は俺の二つ名を呼び当てて見せた。
知られているのであればもう隠し立ては出来ない。
先ほどの戦いで顔を隠していたフードは裂けてしまっているし、顔が割れてしまえばもはや闇を名乗ることは叶わない。
「……できればこの件はご内密にしていただけると――」
「まさか、王都をあれだけ騒がせる闇がこんな子供だったとは……それにその顔、確かフェルナード子爵の――ファレス?だったか」
「……はい。グランデ伯爵様のご活躍、耳にしております」
「貴様にそう言われても私に立つ瀬はないのだが……」
「いえ、伯爵様のご高名は今や王国中に知らぬものはいないでしょう。して、そんな英雄である伯爵様に一つお願いが」
「……なんだ?」
「帝国皇帝を討ったのは伯爵様ということにしていただけないでしょうか?」
伯爵には正体がバレてしまったが、戦後の安定が訪れるまでは俺が闇でいることが必須なのだ。
正体不明の暗殺者が存在するということは敵でも味方でも抑止力として作用する。
伯爵も俺の意図を理解してくれたのか頷いた。
「うむ、貴様の言ももっともだ。だが、もう一つ条件を加えさせてもらおう」
「条件とは?」
「うちの娘と婚約してくれないか?」
「……は?」
「なに、それだけで良いのだ。うちの娘は天の使いかと思うほど愛らしく美しいのだが、あまりに才に溢れていてな。まるで剣を持った白鳥なのだ。それに自分より強い者でないと旦那には認めないと言っていてな……この条件を呑んでくれるのならば、私も闇の正体について口を閉ざし、貴様……いやファレス君の言うとおりにすると誓おう」
……つまり貰い先のいないお転婆お嬢様を押し付けたいと?
まあ、これだけ愛されて育ったご令嬢なら俺みたいな地味な奴にはすぐに愛想を尽かすか。
そんな短絡的な思考で引き受け、交渉は成立したのだった。
◇◇◇
「伯爵……口を閉ざす約束だったのに」
「ついに認めましたね。これでもう逃がしませんわ」
「……敵わないなリシアには」
初めてファレス様が本当の笑顔を見せてくれた気がした。
「分かってくれたようで嬉しいですわ。ではもう一つ聞いてもいいでしょうか?」
「もう、全部バレてしまったようだからね。いいよなんでも聞いてくれ」
もう吹っ切れたのか、ファレス様の態度がいつもよりフランクになっている。
「どうして、事あるごとに婚約破棄を迫って来られたのですか?」
「リシア……キミは中々に悪女の素質もあるみたいだね」
「あら?そうでしょうか?」
「……はあ、そうだな。これから王都はどんどん発展していくだろう。王太子もあんなだが、非常に有能な男だ。この先この国は光の時代を迎える。だが、強い光の影には必ず闇が存在するのもまた不変の事実。そうなったときに闇の中の抑止力として動かなければならない俺には常に危険が付きまとってくるだろう。それにリシアを巻き込みたくなかったんだ」
そう語るファレス様の目には輝かしい国の未来が映っているのだろう。
でも、私はそんな未来は、ファレス様が闇に徹するような王国は認めない。
「それならば、一層婚約破棄をするわけにはいきません。勇爵家として、必ずあなたを光の象徴にして見せますわ!」
「ハハっ……それはちょっと困るかな」
いつもよりしっかりと腕を組んでくれるファレス様の腕を負けじと抱きしめ返して、私たちは帰路に就いた。
◇◇◇
「あーあ、うまく行っちゃった……」
そんな二人の姿を楽し気に見下ろす一人の男。
「王都の闇ファレス……僕のものにしたかったのに。ああ、本当に憎い。憎すぎるよリシア。僕が女だったらどれだけよかったか……まあ、どうせ王になれば必ず関わることになるだろうし。また婚約破棄とか言い出したら今度は絶対に逃がさないよファレス?」
次期国王となるその男の目にもまた、ファレスしか映っていなかった。
「なんでしょう?」
「そろそろ婚約破棄……」
「嫌です!」
一体何度目のやり取りだろうか。
今日は王太子殿下の誕生パーティーだというのに相も変わらずこの人は……。
「リシアほどの好物件を俺のところに嫁がせるなんてどうやってもおかしいって」
私の横で、割と本気な顔でこんなことを宣うこの男は私の婚約者であるファレス・フェルナード子爵令息だ。子爵家の出身だと言うのに全く貴族らしくないこの男には剣の才も魔法の才も全くと言っていいほどない。
「そうですか?私はそれほど好物件とも思えませんが?」
「いやいや、だってリシアはあの勇爵として高名なマルス伯爵家のご令嬢で学院でも抜群の魔法の才を発揮しているいわば高嶺の花ってやつじゃないか!」
「そう言われましても、戦争が終わってしまった今となっては、力の強い女など白鳥に剣を持たせているようなものですわ」
「はぁ……またその例えか。戦争なんて人が存在し続ける限りいつでも起こりうるんだ。男女関係なく実力があるに越したことはないだろうと言うのに……」
私たちの会話はいつもここで平行線を辿っている。
まぁもし、ファレス様がこれに続く二の矢、三の矢を放って来ようと私がこの手を放すつもりはないのだけれど。
私は控えめに組んだ腕に少し力を込めた。
「お、これはこれは無能のファレスくんではないか。それにリシアさんも。いつ見てもキミは麗しいね。気高く強く、どんな台地でも同じように輝きを放つ一輪の薔薇のようだよ」
「王太子殿下、本日はおめでとうございます」
あれだけ言われても顔色一つ変えないファレス様に続いて私もお祝い申し上げた。
私は正直この男、メフィト王太子殿下が嫌いだ。
「ハハっ、ありがとう。せっかくのパーティーなんだ、無能なキミも楽しんでくれ」
……この男、言わせておけば!
思わず言い返しそうになる私の腕をファレス様は軽く引いた。
すると面白くなさそうな顔をしてメフィト王太子殿下は言葉を続ける。
「そういえば、キミは先日の魔法実技のテストでも最下位を取ったそうじゃないか!情けないとは思わないのかい?キミの婚約者は僕でも及ばない不動のトップだというのに」
主役であり、ただでさえ目立っているというのに周りにも聞かせるように王太子殿下は声を張り上げた。
「おっしゃるとおりかと……全く、自分の無力を嘆く日々です」
それでもファレス様は全く動じた様子を見せない。
心にもないことを……。
「へぇ、ということはキミ自身も自分がリシアさんにふさわしくないことは認めるんだ?」
「もちろんです殿下。リシアは私にはもったいない女性ですよ」
「じゃあ、どうだい?婚約破棄をするというのは」
そのセリフについに我慢の限界に達した私は
「殿下っ!いくら殿下とは言えそのようにプライベートにまで口を出されるのはいかがなものかと!」
と、口に出してしまった。
だが――
「殿下のお言葉はもっともです。ですがリシアの言う通りこれは私とリシアの問題。急ですが今のお話を二人でしたいと思いますので今日はこの辺りでお暇させていただきたく」
ファレス様は殿下の言葉も私の態度を全く気にせず、調子を変えずに淡々とそう言う。
「そうか。いいぞ、二人でよく話し合うといい」
お祝いをした今、無理に引き留める口実はなく、いやな注目を浴びたまま長引きそうだったパーティーをあっさり後にすることができた。
◇◇
「リシア……さすがに殿下に噛みつくのは危ないよ。あの人は最高権力者なんだからね?」
パーティー会場を出て、薄く闇がかった道を歩きながらファレス様に諫められる。
「ファレス様は私のことがお嫌いですか?」
「まさか……俺が嫌われることはあっても俺が嫌うことはないだろう」
……じゃあ、どうして婚約破棄を求め続けているのか。
本当に食えない人だ……。
「それより、婚約破棄の件だが」
「しませんよ?」
またその話か、と若干腹が立つ。
「いったいどうしてリシアはそんなに頑ななんだ……」
ファレス様は額に手を添えて溜息をつくが、そんなもの決まっている。
貴方が――
「貴方が王国の闇と言われる戦争終結の立役者だからです!」
「……何を言っているんだリシア?」
少し驚いた顔をするファレス様をおいて、私は続ける。
「誤魔化さないでください!私はマルス伯爵令嬢ですのよ!いくら隠し立てしようと分かるものは分かるのです!」
一度溢れ出した思いはもう止まらなかった。
「3年前の大戦争。我がマルス伯爵家が勇爵と呼ばれるようになったあの戦争でお父様が立てられた功績は確かに目を見張るものでした。しかし、勇爵の名を賜るに至った最高の功績、帝国指揮官であった皇帝の首を打ち取ったのは貴方でしょう!」
「リシア……ちょっと声を押さえて……」
「ファレス様は詰めが甘かったですわね。こう見えても私、お父様には可愛がられているのです!私が聞けばなんでも教えてくださいますわ!」
そこまで言い切ると、またファレス様は額に手を添えて今度は苦い顔をした。
◇◇◇(3年前ファレス視点 回想)
「貴様は何者だ!」
勇猛果敢、名将と名高いグランデ・マルス伯爵にその瞬間を目撃されてしまった。
「これは……」
俺の目の前に転がるのは敵味方両軍の兵士と一騎当千を謳われ、現役時代は最強と恐れられたと言う帝国の皇帝。
その名の通りもう齢70を過ぎているだろうと言うのに、なかなかに厄介な相手だった。
実際に俺以外の兵は皆やられてしまった。
「いや、待て……その紋はまさか王都の闇!?」
俺の手に握られた短剣の紋を見てグランデ伯爵は俺の二つ名を呼び当てて見せた。
知られているのであればもう隠し立ては出来ない。
先ほどの戦いで顔を隠していたフードは裂けてしまっているし、顔が割れてしまえばもはや闇を名乗ることは叶わない。
「……できればこの件はご内密にしていただけると――」
「まさか、王都をあれだけ騒がせる闇がこんな子供だったとは……それにその顔、確かフェルナード子爵の――ファレス?だったか」
「……はい。グランデ伯爵様のご活躍、耳にしております」
「貴様にそう言われても私に立つ瀬はないのだが……」
「いえ、伯爵様のご高名は今や王国中に知らぬものはいないでしょう。して、そんな英雄である伯爵様に一つお願いが」
「……なんだ?」
「帝国皇帝を討ったのは伯爵様ということにしていただけないでしょうか?」
伯爵には正体がバレてしまったが、戦後の安定が訪れるまでは俺が闇でいることが必須なのだ。
正体不明の暗殺者が存在するということは敵でも味方でも抑止力として作用する。
伯爵も俺の意図を理解してくれたのか頷いた。
「うむ、貴様の言ももっともだ。だが、もう一つ条件を加えさせてもらおう」
「条件とは?」
「うちの娘と婚約してくれないか?」
「……は?」
「なに、それだけで良いのだ。うちの娘は天の使いかと思うほど愛らしく美しいのだが、あまりに才に溢れていてな。まるで剣を持った白鳥なのだ。それに自分より強い者でないと旦那には認めないと言っていてな……この条件を呑んでくれるのならば、私も闇の正体について口を閉ざし、貴様……いやファレス君の言うとおりにすると誓おう」
……つまり貰い先のいないお転婆お嬢様を押し付けたいと?
まあ、これだけ愛されて育ったご令嬢なら俺みたいな地味な奴にはすぐに愛想を尽かすか。
そんな短絡的な思考で引き受け、交渉は成立したのだった。
◇◇◇
「伯爵……口を閉ざす約束だったのに」
「ついに認めましたね。これでもう逃がしませんわ」
「……敵わないなリシアには」
初めてファレス様が本当の笑顔を見せてくれた気がした。
「分かってくれたようで嬉しいですわ。ではもう一つ聞いてもいいでしょうか?」
「もう、全部バレてしまったようだからね。いいよなんでも聞いてくれ」
もう吹っ切れたのか、ファレス様の態度がいつもよりフランクになっている。
「どうして、事あるごとに婚約破棄を迫って来られたのですか?」
「リシア……キミは中々に悪女の素質もあるみたいだね」
「あら?そうでしょうか?」
「……はあ、そうだな。これから王都はどんどん発展していくだろう。王太子もあんなだが、非常に有能な男だ。この先この国は光の時代を迎える。だが、強い光の影には必ず闇が存在するのもまた不変の事実。そうなったときに闇の中の抑止力として動かなければならない俺には常に危険が付きまとってくるだろう。それにリシアを巻き込みたくなかったんだ」
そう語るファレス様の目には輝かしい国の未来が映っているのだろう。
でも、私はそんな未来は、ファレス様が闇に徹するような王国は認めない。
「それならば、一層婚約破棄をするわけにはいきません。勇爵家として、必ずあなたを光の象徴にして見せますわ!」
「ハハっ……それはちょっと困るかな」
いつもよりしっかりと腕を組んでくれるファレス様の腕を負けじと抱きしめ返して、私たちは帰路に就いた。
◇◇◇
「あーあ、うまく行っちゃった……」
そんな二人の姿を楽し気に見下ろす一人の男。
「王都の闇ファレス……僕のものにしたかったのに。ああ、本当に憎い。憎すぎるよリシア。僕が女だったらどれだけよかったか……まあ、どうせ王になれば必ず関わることになるだろうし。また婚約破棄とか言い出したら今度は絶対に逃がさないよファレス?」
次期国王となるその男の目にもまた、ファレスしか映っていなかった。