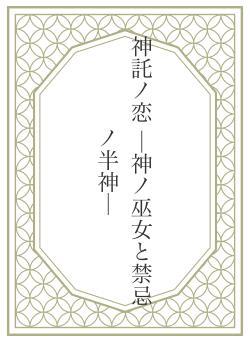『平成なんて終わった とうの昔に 泣くように笑って 笑うように泣いた 新しい朝が来るのが怖くて これからもずっと、君にだけ弱音を吐くんだ』
いつもと変わらない朝。
いつも通り、彼女の歌声で目を覚ます。
目覚ましに設定した彼女の曲を僕は手探りで止める。
――僕自身の手で、止めなければならない。
彼女はこの世界にもういないからだ。
彼女が遺した音楽だけが毎朝、僕を現実へと揺り起こす。
彼女の音楽は、頭の中でずっと鳴っていた。
仕事に行っても、読書をしても、友人と飲みに行っても。
僕の生活の隣には、ずっと彼女がいるようだった。
彼女の死後、彼女の作った音楽が爆発的にヒットする――なんてことはなく、遺された彼女のSNSやファンに撮影されたライブの様子が、再生数を地道に伸ばしているだけだった。
だけど、それで良かったと思う。
彼女の音楽が『消費』されることなく、必要とする人たちに大切にされているからだ。
その証拠に彼女の命日には、「この曲に出会えてよかった」「この曲があるから、今の私がいる」そんなメッセージが寄せられている。
彼女が最後に死を選んだ理由は、僕には今も分からない。
彼女の死が小さなニュースになった当時は、彼女の病気についても憶測が飛び交っていた。
自殺。
その一言は、どうしてもしっくりこなかった。
確かに、鬱病だったかもしれない。
確かに、発達障害だったかもしれない。
だけど、僕は彼女が、人間の意思では抗えない何かに――それを人は運命というのだろうか、に攫われてしまったようにすら思えた。
だって、彼女の歌声はずっと天使みたいだったから。
初めて彼女の歌声を聞いたあの日、僕は僕の天使に出会ったと本気で思っていた。
それは半分正解で、半分不正解だった。
彼女は、みんなにとっての天使になってしまった。
僕は死を肯定するつもりなんて微塵もない。
だって彼女が生きていたら、彼女の歌う曲でもっとたくさんの誰かを救っていたかもしれないから。
だけど彼女が、彼女が生きた19年間という時間は、彼女が天使になるには十分な時間だった。
彼女が月に歌えば、月は美しく彼女を照らしたし、彼女が空に歌えば、空はありえないくらい美しく彼女を濡らした。
彼女のために、僕は生きて、彼女が遺した音楽を聴き続ける。
それがきっと、遺された者の役目だと信じて。