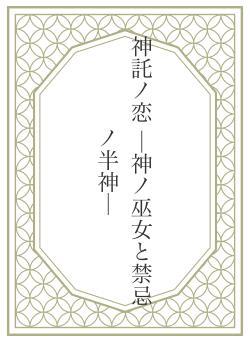彼女には、相棒がいた。
彼女はずぼらだったけれど、彼女の古いギターだけはいつも綺麗に手入れしているようだった。
「ねぇ、聞いて!今度、レイベックスのミニライブに出ませんかって!」
あの日の帰り道。
彼女は、嬉しそうに僕に報告してくれた。
なんでも、レイベックスの関係者の目に止まり、ミニライブ出演の打診が来たようだ。
「すごいじゃん」
そう言って、彼女の隣を歩いていた僕は立ちどまり、彼女に一歩遅れて歩きだす。
「今日の路上ライブも盛況だったしな」
「やっぱり楽しいよ、たくさんの人が聴いてくれてると」
そう言って、ふふっと彼女は笑う。
その瞳は、少し潤んでいるようにも見えた。
いつもより長く歌って、少し疲れたかなと思い、ギター持つよ、と言ったけれど、彼女は最後までギターを離さなかった。
普段から、あまり人には触らせないようにしているみたいだったけれど、僕には預けてくれることが多かった。
だけどその日は、「大丈夫だよ、もう」と言ってギターを下ろそうとはしなかった。
「ライブの話、よかったね」
別れ際に、僕が一言そう言うと、
「ね、このままデビューしちゃうかもよ?」
そう言って、彼女はいたずらっぽく笑った。
プレッシャーなんて、微塵も感じていないような笑顔だった。
僕が彼女を最後に見たのは、その小さな背中に、大きな世界を背負って遠ざかっていく彼女の後ろ姿だった。
彼女はずぼらだったけれど、彼女の古いギターだけはいつも綺麗に手入れしているようだった。
「ねぇ、聞いて!今度、レイベックスのミニライブに出ませんかって!」
あの日の帰り道。
彼女は、嬉しそうに僕に報告してくれた。
なんでも、レイベックスの関係者の目に止まり、ミニライブ出演の打診が来たようだ。
「すごいじゃん」
そう言って、彼女の隣を歩いていた僕は立ちどまり、彼女に一歩遅れて歩きだす。
「今日の路上ライブも盛況だったしな」
「やっぱり楽しいよ、たくさんの人が聴いてくれてると」
そう言って、ふふっと彼女は笑う。
その瞳は、少し潤んでいるようにも見えた。
いつもより長く歌って、少し疲れたかなと思い、ギター持つよ、と言ったけれど、彼女は最後までギターを離さなかった。
普段から、あまり人には触らせないようにしているみたいだったけれど、僕には預けてくれることが多かった。
だけどその日は、「大丈夫だよ、もう」と言ってギターを下ろそうとはしなかった。
「ライブの話、よかったね」
別れ際に、僕が一言そう言うと、
「ね、このままデビューしちゃうかもよ?」
そう言って、彼女はいたずらっぽく笑った。
プレッシャーなんて、微塵も感じていないような笑顔だった。
僕が彼女を最後に見たのは、その小さな背中に、大きな世界を背負って遠ざかっていく彼女の後ろ姿だった。