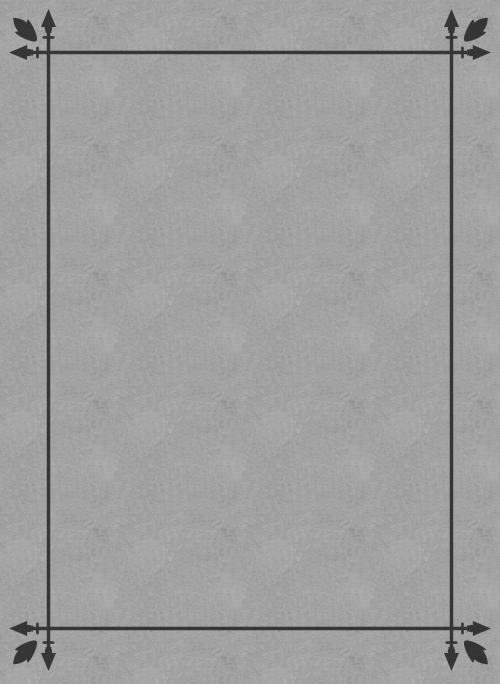漢字
屋上のコンクリートは冷たくて、寂しい。
冬というものは色が無いが、よく見れば、一番色に溢れていて綺麗な季節だと糸は思う。
しかし、今は春で、どこを見ても明るい色に包まれている。
桜や菜の花なんかが代表的だ。よく、絵に描かれる。
糸はキャンバスに色を付けていく。
空は青く、太陽は優しい色をしている。
人生というのは素敵なもので、色で溢れている。
だからこそ、この世界に相応しい、一番綺麗な死に方をしたい。
いつもそう思う。太宰治や芥川龍之介の死因は自殺だったとどこかで聞いたが、
芸術的な考えに侵されていた二人の自身の信念を貫き通した結果なのだろう。
そこだけは尊敬する。
息をついて空を見上げると、強い風が吹いて、思わず目をつぶった。
(風つよ)
目を開けると、目の前に見たことが無い男の子が立っていて、こちらを見ていた。
鼻筋がすっと通って、麗しい顔立ちの彼を糸は見たことが無かった。
記憶力は良い方なので、思い出せないのならあったこともない人だ。
「はじめまして」
彼は丁寧にお辞儀する。
屋上には糸だけしかいないので、他の誰かに言っているとは考えにくい。
糸は一応、小さく会釈した。
「おれは死神。今日から君の担当になります」
(何言ってるんだろう)
変な人に絡まれてしまったかもしれない。
「うわー、上手だね。すっごい」
彼はとたとたと小走りで近づいてくると、キャンバスを覗いて目を輝かせた。
絵を誉められるのは嬉しいが、知らない人に言われるのは少し怖い。
中二病気質なのだろうか。
しばらくすると、糸のほうに向きなおって、どこからか取り出したメモ帳をパラパラとめくる。
「桜木糸(さくらぎいと)さんであってる?」
「そうですけど」
死神にお世話になる予定はない。
糸は健康で、病気もないし、余命もない。
同姓同名の人間違いであってほしい。
まだお迎えを頼む予定はない。
絵ばかり描く人生はそこそこ楽しいのだ。
「もうすぐ死ぬってことですか?」
思わず聞いてしまう。
まだ生きていたい。
死神は、うーん、と唸る。
「死ぬ日がいつなのかは分かんない。だから前から担当がつけられるの」
そう言ってふわあとあくびした。
なんて呑気な死神なんだろう。
「あ、そうそう。おれのことは翠って呼んでね。今日は顔合わせというか、挨拶だけだから」
「え、あ、はい」
翠は、またね、とひらひら手を振って消えた。
どこかふわふわしている、掴みにくい、どちらかと言えば嫌いなタイプだった。
次の日、死神は家にやって来た。
昨日のショックからか驚きからか、糸は熱を出していた。
久しぶりの高熱で、人間なのかよくわからない生き物と会話する気にはなれない。
しかし、翠は近くの椅子に座って部屋をきょろきょろと見まわしている。
両親は海外出張という名の海外旅行中で、家には誰もいない。
その状態が稀というわけではなく、日常なので、部屋は糸が生きやすい環境に模様替えした。
部屋中に描いた絵を飾り、時々買った絵も混ざっている。
壁に取り付けた本棚には、著名な文豪の作品が並んでいる。
翠にとっては珍しい環境なのだろうが、あまりきょろきょろしないでほしい。
なんだかくすぐったい気持ちになる。
「なんか、色でいっぱいだね、この部屋」
「一応、絵描くの好きなので」
翠は、ベッドのそばまで椅子を近づけて、ベッドにもたれた。
ベッドがギシッと鳴ったので、彼にも重さがあるのだろう。驚いた。
「敬語やめない?年近そうだし」
「そうは見えないけど」
昨日と今日だけでも、性格は糸より年が幾らか幼く見える。
容姿だけは秀でているが、性格はあまり大人ではないらしい。
翠はむっとしたのか、頬を膨らませてこちらを見た。
(あざといとはこのことか)
世のアイドルグループにいそうだ。
「一応、君より年上なんだよ」
「いくつ?」
「....ひとつ」
(ひとつなんて誤差だ)
糸は鼻で笑った。
翠はさらに顔を膨らませて、こちらにクッションをぶつけてきた。
クッションはかすりもせずに壁にぶつかって落ちた。
「君は不思議だね。今まで担当してきた子たちは生きるのが嫌だって泣き叫ぶか、早く連れて行ってくれって泣くかどっちかだった んだよね」
「極端」
「でしょ。君はやりたいこととかないの?」
「やりたいこと...」
熱でぐらぐらする頭で考える。
突然、やりたいことなんて言われて思いつくわけないと思ったわけだが、ひとつ思いついた。
「絵、描きたい」
「絵?昨日も描いてたじゃん。いいの?特別なことじゃないけど」
糸は翠の方を見る。
人生がもし、もうすぐ終わってしまうなら、やりたいことはやっておいたほうが良い。
本当なら60を迎えたあたりでやろうと思っていたのだが、予定が狂った。
人生で一番時間をかける、大作を作りたかった。
「翠、あなたをモデルにしてもいい?」
翠はぽかんとしたのち、満面の笑みを浮かべた。
(嬉しそう)
子どもっぽく幼いところがあるが、顔立ちは一級品なので、綺麗なものをモデルにしたい糸としてはぴったりの相手なのだ。
「いいの?おれで」
「うん。綺麗だから」
「えー、うれしー。いつから描く?今日じゃないよね?明日とか?」
(熱上がってきたかな)
視界がぼやぼやして、顔が熱くなってきた。
頭もふんわりしている。
翠が口をパクパクしているので、何か話しているのだろうが、耳鳴りがして聞き取れない。
あまり一気に話さないでほしい。頭を回すのは疲れる。
糸は深い眠りについた。
目が覚めた。
あれから寝てしまったようで、すでに死神の姿はなかった。
(なに考えてるのかわかんなかったな)
だけど、と思う。
(悪い人ではないみたいだ)
ベッドのそばのサイドテーブルに、冷えピタや解熱剤、栄養ドリンクなどが置かれていた。
(そろそろ絵描けるかな)
クローゼットにしまってあった大きなキャンバスを壁にかけて、絵具を取り出す。
熱がなかなか下がらず、四日うなされた。
その間、翠は、安否確認をするためだけに部屋を訪れていたようだった。
体調が悪い時は話しかけてほしくないものなので、そっとしておいてくれるのはありがたかった。
「あ、回復?」
後ろから声が聞こえた。
絵具を出す手を止めて振り向く。
「うん。そこそこには。モデルさんは椅子に座ってもらえる?」
「もちろん。任せてよ」
翠は首が折れるほどうなづくと、椅子に座った。
どんなポーズか悩んだ末、足を組んで姿勢よく座ることにしたようだ。
(一番疲れるのに)
死神に疲れるという概念はないのか。
うきうきとこちらを見つめている。
「じゃあ描くけど、動かないでね」
「はあい」
張り切って絵具を出してしまったが、鉛筆で下書きから始める。
どうせ描くなら綺麗な顔を本物のように表現したい。
(沈黙は気まずい)
翠としても、描いているときに話すのはよくないという遠慮からかあまり口を開かない。
糸も話し上手でもおしゃべり好きでもないので、口数は無いに等しい。
しかし、いくら糸でもこの空気感には堪えられなかった。
「死神なんてしてて楽しい?」
糸はなんとか考えて質問する。
翠は少し眉を下げて悲しそうにした。
死神に感情があるのかは不明なので、それが本当なのか分からないけど。
「楽しくはないよ。交通事故で魂が浮いた人なんて特に」
「なんで?」
「だって血まみれで死にかけの人が、まだ死にたくないとか言うんだよ。運転手の人はすごい焦った顔して電話してるし、
野次馬の人は、すごいひどい目にあった人が目の前にいるのに携帯向けるし。結構辛いよ」
死神にも感情はあるみたいだ。
(交通事故死じゃないといいな)
糸にも優しさというものはあるので、辛い思いをさせたくないなと思う。
(一応聞いておくか)
「わたしはどうやって死ぬの?」
翠は言葉に詰まった。
少しだけ苦しそうな顔をした。
「交通事故、なんだよねえ。それが」
今度は糸が言葉に詰まった。
神様は意地悪だ。
決められたことに逆らうつもりはなかったが、こればかりは逆らいたい。
血まみれになって命乞いをするのはごめんだ。野次馬に携帯を向けられたくもない。
「....回避できない?」
「決められてるからねえ。仕方ないよ」
「そう」
(なんとしてでも回避してやろう)
それに、交通事故は色で溢れた世界に似合わない、綺麗じゃない死に方だ。
糸の目指しているものではない。
糸は翠の輪郭と大まかなパーツの配置を書き込むと、ため息をついて鉛筆を置いた。
「今日はここまで。疲れた」
翠は伸びをした。
「まあ、気にしないでね、さっきの話。そもそもおれの仕事だからさ」
(気にしてないけど)
死んでいる身にトラウマなんて残りはしないだろう。
淡々と仕事をこなすのが仕事な死神なのに、ひとつひとつに感情移入している方が悪いのだ。
どうにかして感情移入しない訓練をすればいいだけ。
糸が気にするべきことではない。
「じゃあ、帰るね。またあした」
翠はぱっと笑うと窓を飛び出していった。
ここは高層マンションの40階なので、人間なら即死だろう。
それが許されるのは死神だけだ。
(どこぞの怪盗みたい)
糸は一人でクスリと笑った。
今回担当の少女は年が近くて、いつもより感情移入してしまいそうだ。
彼女はお金持ちなのか、マンションの40階のかなり広い部屋に一人で住んでいた。
ザ・芸術家という感じの部屋で、そこらじゅうに絵が飾ってあった。
どれも素晴らしい出来で買ったものかと思えば、彼女は自分で描いたと言った。
高校生の彼女が大人になれば、作家として売れただろうけど、残念ながらそれは叶わない。
彼女は、糸は大人になれない女の子だった。
翠も大人になれなかった身として、少し思うところがあったので担当希望は出したくなかった。
しかし、彼女は交通事故死する。
交通事故はあまりにも心を病むので、死神たちが担当になりたがらない。
だから、最年少の翠が選ばれたわけだ。
「すごー、鉛筆だけでも誰か分かるね」
糸は褒めてもあまりうれしそうにしない。
表情が滅多に動かない。
接しにくいタイプかと思ったら、話しかけて見ればよく喋る子だった。
顎ラインで切りそろえられた真っ黒の髪が揺れて振り返る。
大きな瞳はどこかがらんどうで、人形のように見える。
「そう?色塗らないと面白くないけど」
彼女の世界は色で溢れているらしい。
寝室は所々に花があって、どれも綺麗に管理されていた。
「モデルになんてしてもらったことないよ。死神になってよかったって思えたかも」
「お世辞がうまいんだから」
糸は少しだけ微笑んだ。
最近、少しだけだが表情がほぐれた気がする。
高校も通信制で親も海外となれば、人と関わる機会が減るのも納得だ。
それで感情が乏しくなっていたのだろう。
「もう少しすれば色が付けれるよ」
糸は満足そうにキャンバスを見つめるが、翠はふと不思議に思う。
前に担当していた強欲お嬢様は、色んなところに翠を連れまわして彼氏が居るのだと自慢して回り、
買い物に連れ出しては荷物持ちをさせたりと人使いが荒かった。
だけど、彼女はなにもしたいと言わない。
したいことが無いというのは、担当として気になるところだ。
「他にしたいことないの?」
「他に?」
糸は何か考えているのか動きが止まる。
(かわいく思える)
小動物のようだ。
糸は絵を描くことにしか頭が無いので、すぐに他のことは思い浮かばないだろう。
案の定、そうだった。
悪いと思ってしまったのか、逆に尋ねてきた。
「翠はなにかやりたいことないの?」
「おれがしたいことしても意味ないじゃん」
「人について行くの案外好きなんだけどなあ」
糸は残念そうに若干俯く。
(そんなことされると、なにか考えないといけないじゃないか)
年が近いということもあってか、糸には弱いらしい。
翠は立ち上がる。
「じゃあなにか考えてくるよ」
糸は嬉しそうにする。
(演技かな、これは)
彼女は生きるのがうまい。
翠は、ひらりと手を振って窓から飛び降りた。
「あ、帰ってきた」
一面真っ白な空間に入ると、ソファにうつぶせで寝転がっている仲間が見えた。
金髪に染められた髪は彼の幼い顔立ちに似合っていない。
「おかえり」
「うん」
「反抗期かお前は。ただいまだろ」
彼は翠の頭をぐしゃぐしゃと荒く撫でる。
十は年上の彼は翠をいつまでも子ども扱いしてくる。
彼は、翠の先輩にあたる死神で、よくしてもらっている。
名前は類という。
現在、担当は持っているものの、教育係兼フォローとして翠の周りをうろうろしている。
「暇なの?」
「まあね。今日で仕事終わったから。そっちは?」
「もう少しだと思うけど」
「...まーた感情移入しちゃってんの?いい子だねお前は。やっぱ死神向いてないわ」
むっとする。
高校生で死神というものになった者としては、感情移入するなという方が難しい。
それに、今の担当は年が近いので友達と同じ感覚で接してしまう。
それこそ無理だ。
やっぱり、向いていないのだろう。もう近いうちにやめよう。
「すいー」
「んー?」
「これあげるわ。なんか貰った」
「誰に?」
「担当のおばあさん。もういけないからって」
複雑な気持ちになる。
「俺興味ないんだよねー、水族館とか。あげる」
類はチケットを適当に投げたので、翠はそれを慌ててキャッチする。
類は担当に感情移入しないタイプなので、すぐに切り捨ててしまう。
どれだけ相手に良くしてもらっても、その場では笑顔で接するが、すぐに記憶から消す。
(ひどいな。せっかくくれたのに)
こういう人が死神に向いているのだろう。
死神という職業は感情移入をしないのが正義だが、実際それは一部しかできない。
翠にはまだまだ難しい。そろそろ、やめようかとさえ思ってくる。
しかし、いいものを貰った。
翠はいつもより早く来た。
そのおかげで、朝ごはんを中断して客人の接待に回らなくてはいけなくなった。
(フレンチトーストうまくできたのに)
机の上のフレンチトーストは冷えかけている。
ほかほかのままで食べたかった。
翠はなんだかご機嫌そうで、鼻歌を歌いながら出したコーヒーを口にしている。
砂糖がたくさん入っていることを知っているので、かっこいいとは思えない。
「機嫌いいね。彼女でもできたの?」
そんなことを言うと、翠はむせた。
「そんなわけない!」
翠は、じゃーん、と言って二枚のチケットを出した。
ここから少し先の水族館のチケットだった。
死神にそんな伝手があるのだと、素直に驚く。
「これ、行きたいんだけど。付いてきてくれる?」
彼は可愛らしく首をかしげてお願いしてくる。
人混みの耳がキーンとなるのも色々な香水が混ざる匂いもあまり得意では無いので行きたくはない。
(気は乗らないが、誘い方がずるい)
了承することにした。
「...人間になれたんだ」
糸が驚いたように目を開いている。
あまり乗り気ではなさそうだったが、可愛めなワンピースを着ていて、余所行きの格好をしている。
(ちょっと楽しみなんだな)
なんだか可笑しくて笑ってしまう。
「やっぱり人多いね」
「日曜だからね」
やはり水族館は人で溢れている。
糸は人混みが苦手なようで、顔をゆがめている。
「迷子にならないと良いけど」
「迷子にさせないから大丈夫だよ」
糸を見下ろして、そんなことを言うと彼女の手を取ってみる。
糸は驚いていたが、自分のされたことに気づいて頬を桜色に染めた。
肌が白いので、分かりやすい。
(照れてる)
しかし、その白い肌が交通事故で真っ赤に染まるのかと考えると胸が痛い。
それで、彼女もきっと助けを求めるのだろう。
『もう少し生きたい』と。
暗い気持ちになりかけた翠の手を糸は弱く握り返した。
翠の心臓は大きく波打った。
「綺麗」
糸はクラゲの水槽に魅入っている。
フワフワとするクラゲを見たのは何年ぶりだろう。
中学の修学旅行以来だろうか。
自分がもし生きていたらと考えてしまう。
もし生きていたら、今頃大学生で教師になるために勉強していたんだと思う。
教師になりたかった。
だけど、そんな夢は儚く散った。
翠は大人になれなかったからだ。
キラキラと目を輝かせる彼女もいずれは翠と同じ道をたどるのかと考えるともやもやとする。
「クラゲ好きなの?」
「いや、別に」
糸は立ち上がると、隣の水槽に移る。
「こっちのが好き」
糸は砂を出たり入ったりするチンアナゴを指さす。
綺麗な色の魚が好きなわけではなさそうだ。
さっき見ていたクラゲも、絵の題材にしたいなどと考えていたのだろう。
海外から絵具や染料を取り寄せるくらいなので、熱量は素晴らしい。
「死神は担当した人にもらった物とかどうしてるの?」
「もらったものかあ、保管してるよ。気分次第だけど」
「ひど。気分が乗らなかったら捨てるんだ。最悪、最低、女たらし」
糸は翠をディスりながらお土産コーナーを見ている。
女たらし、そんなのはどこから出てきたのだろう。
(女たらしではなかったけど)
彼女もいたことない。
何を根拠に言っているのだろう、この子は。
「女たらしだと思ってたの?」
糸はこちらをちらっと見てから手元に視線を落とす。
「.....顔良い奴はそうなのかと」
「ひどい偏見だね」
翠は笑う。
楽しい。おもしろい。
久しぶりに楽しいと思った。
淡々と仕事しないといけないと思っていたから。
少し、緊張が緩んだ。
「はい。これ、あげる」
糸はいつの間にか買っていたチンアナゴのキーホルダーを翠の手に乗せた。
(チョイスが絶妙)
イルカやカメではなく、チンアナゴという生き物に惹かれるのは珍しい。
「気が向いたら残しておいて」
「...気が向いたらね」
少しだけ意地悪した。
糸はまんざらでもなさそうなのでむっとする。
翠は離れてしまっていた手を握りなおして水族館を出た。
(案外、楽しかった。恋愛をするならあんな子とが良かった)
もうできないけど、と思う。
胴体とはもう少し仲良くしておきたかったが、もう時間は長くない。
まだまだ元気だが、事故死は仕方がない。
首に付けた貝殻のチャームがついたネックレスを外して、ケースに入れる。
翠がくれた。
気が向いたので、大切に持っておこうと思う。
「いらっしゃい」
短いが、糸にとっては長い間というか毎日会っているので、彼の気配を覚えてしまった。
翠はそっと入ってきたつもりだったのか、声をかけられてびっくりしていた。
絵は完成に近づいてきている。やっと、今日から色付けできる。
翠はいつもと同じ場所に座り、足を組んだ。
(もう慣れたものだな)
「ねえ」
「なに?」
「花に興味ある?」
「.....」
(ないんだな)
けれども、毎日話していると会話の話題がなくなるのだ。
糸はテーブルの上に置いた花瓶の中に入っている花を指さす。
丸い、黄色の花。ミモザだ。
「それ、ミモザっていうんだけど、花言葉はひそかな愛」
「ロマンチックだね。あれは?」
「イベリス。初恋の思い出だったかな」
祖母が花屋をしていたころ、手伝いをしていた糸は覚えさせられた。
必死に覚えたので、忘れられない。
翠は面白そうに花を見ている。
「これで調べたら?貸してあげるけど」
花言葉図鑑を手渡す。
もう色を塗るだけなので、色味さえわかれば、ポーズを保っていなくても描ける。
死神に花言葉を覚えさせても意味がないのに、と思ったが、まあいいだろう。
知識は多い方が仕事で役に立つ。
「面白いかも。貸してよこれ」
「あげるよ。もう死ぬんだし」
翠は気まずそうに笑った。
それもそうだ。彼が糸の魂を持っていくのだから。
少しだけ申し訳なくなる。
翠は立ち上がって、窓辺に腰を掛けた。
髪が風になびかれてふわりと揺れる。翠は前髪をかきあげた。
どこかの物語に出てくる王子様はこんな感じなのだろうと思う。
それくらい綺麗だった。
(これを描けばよかったかね)
それでも、キャンバスに描かれた翠はどこの角度から見ても綺麗で、麗しかった。
糸の自信作になりそうな予感がする。
「....なに黄昏てるの?」
翠は恥ずかしそうにうつむいた。
かっこつけたつもりなのだろう。
それか、どうしようか迷った末に変な行動をしてしまったか。
翠のことだ、おそらく後者だ。
「なんとなく?」
「変なの」
「じゃあ帰ろうかな。またあしたね」
翠はいつも通りひらりと手を振って、空に消えた。
きっと、翠は優しいから糸が死んだときのことを考えてしまったのだろう。
交通事故が一番きついと言っていた。
糸はため息をついてベッドに倒れこんだ。
(どうしようかね)
無駄に広い部屋に糸の呼吸だけが響き渡った。
朝七時。
電話が鳴った。
『もしもし?あ、でたでた。糸ちゃん、久しぶり』
母の声だった。
なんだかもう会いたくない。
娘の死ぬ直前まで両親は海外に居るのだろうから。
(最後くらい後悔させてやりたいかも)
糸はにやっとする。小学生以来のいたずらだろうか。
「久しぶり」
『元気にやってる?糸ちゃんはお利口だから大丈夫よって言ったのにお父さんがどうしてもって』
「そう」
『おー、糸。久しぶり』
「久しぶり」
『もう少ししたら帰ろうと思うんだが、糸もこっち来るか?』
ついこの前までは願ってやまなかった言葉だった。
(もう遅い)
置手紙だけ残して海外に飛び立った両親は一年弱連絡をくれなかった。
もう慣れたが、寂しかった。
連絡の一度や二度はしてほしかった。
だけど、自分は二人のお荷物だから、とお利口さんに生きてきた。
この誘いだって、前なら断れなかった。
「ううん。今は絵に集中したいから」
『....そうか。ならいいんだ。じゃあ、また』
また、は来るのだろうか。
笑いがこぼれる。
父は残念そうに息を吐いて電話を切った。
「ねえ。居るんでしょ?」
カーテンの方に声をかける。
ひらりとカーテンが揺れて、翠が顔を出す。
電話を聞いていたらしい。
(別にいいけど)
「聞いちゃってごめんね?」
翠は片目を閉じて可愛らしく両手を合わせた。
(あざとい)
さぞモテただろう。
「いいよ、別に」
糸はパレットを手に取る。
キャンバスに色を付ける。もう少しで完成する。
頬に桜色をつけて、生き生きとさせる。
モネのような淡い水彩画も好きだが、本物に限りなく近い絵柄も好きだ。
今回は本物に近づく絵柄を選んだ。
「えー、すごい。鏡みたいだね。じょーず」
翠は不器用に糸の髪をサラサラと撫でた。
幼稚園児のするそれのように。
「上手なのは知ってるよ。コンテストに選ばれてばっかりなんだから」
「はいはい」
「よし。完成」
糸は満足げにキャンバスを眺める。
生き生きとした翠は本物に近く、糸の人生の中で最高傑作だといえる。
翠も満足そうに何度も見ている。
いつか、時がたった時にこれが発見されれば、白馬の王子様とでも評されて話題になるだろうか。
糸のいない未来を想像して微笑む。
どんな有名な画家も大作を完成させたときはこんな気持ちだったのだろうなと、有名な画家になった気持ちになる。
「ありがとー。おれだけしか見ないの勿体ないね」
「まあね。私が死んだら作品展にでもだしてよ」
「そうだね。努力するよ」
翠は愛おしそうにキャンバスを撫でる。
人を笑顔にさせる作品が作れてうれしい。
「ねえ。どんな死に方が一番綺麗?」
「....は?」
突然、思いついたことを質問してみる。
(急に聞かれても困るか)
「交通事故ってこの世界に相応しくないと思わない?」
(何を言っているんだろう。この子は)
確かに、交通事故は何も美しくないけど、死因に美しいもなにもないだろう。
わからない。頭をフル回転させないと彼女を理解できない。
「なにしようとしてるの?」
出来るだけ笑顔を努力して声をかける。
糸は、顎に手を当てて考えるしぐさをする。
「この世界で一番綺麗に死にたいの。わたし」
「綺麗に死ぬとなくない?」
「まあ、たしかに。けどさ、芸術家だから一応。ちょっと考えちゃうんだよね」
「へ、へえ」
芸術家。
たしかにそうなのかもしれないけど。
そんなことを考えるような子には見えなかった。
だけど、彼女の人生なので翠に言えることは何もない。
「ちょっと、用事思い出したから帰るね」
翠は再び笑顔を作って窓を飛び降りる。
用事があるなんて、ぎこちない言い訳だっただろうか。
「お祭り行こう」
死神と出会って一か月が経とうとしている。
一向にその時は来ない。外に出ると交通事故にあう確率は高くなるが、死ぬ前に花火は見たい。
「いいけど、急だね」
翠はコーヒーを飲んでいる。もちろん、砂糖多めの。
糸も作品が完成したので、ゆっくりとピーチティーを飲んでいる。
「今日の夜なんだけど。行けそう?」
「死神は基本的に暇ですから」
「そう。なら決まりね」
夜七時に海に集合。
そう決めた。
なのに、彼は一時間たっても来ない。
花火はどんどんと打ちあがり、もうすぐ終わりに近づいている。
暇だと言っていたのに、何をしているのだろう。
夜空に咲く花に人々は目を奪われている。
色があふれている。
「ごめんっ」
焦った声が聞こえて、ふわりと甘い匂いが鼻をくすぐった。
翠が隣に座っていた。
「遅いよ。遅刻」
「今来たところとか言うんじゃないんだ」
糸はムカッとして翠の背中を思い切り叩いた。
そこそこ大きな音が鳴ったので、近くの人が数人こちらを見た。
「一時間以上たってるのに今来たわけないでしょ。ばかなの?」
「ごめんなさい」
子犬のようにしゅんとなっている。
(怒れない)
動物は好きなのだ。
「なんか話してくれるなら許す」
考えてみれば、名前を知っているだけでそれ以外は何も知らないのだ。
こっちのことは知っているので、一方的なのは不平等だろう。
(一つくらい聞いても罰は当たらない)
翠は頭を抱えている。
そんなに思い出が無いのだろうか。
「あ、部活の話とかどう?」
「なんでもいい」
「おっけ。おれね高校の時、天文学部だったの。星見るだけみたいな。星好きだから入ったんだけど、実際は部活がだるい陽キャの集まりで、静かに星見てたおれはまあいじめられたの。顔が派手とか髪の色が派手だとか。地毛なのに。それでさ、星見るとかだせえって言われたわけね。好きな子と否定されるってすごい腹立つの。だから、やり返そうと思って、下剤をそいつらの水筒に混ぜて、トイレから出られ無くしてやった。そっからなくなったの、いじめ。いじめられたらおすすめ」
(いじめの話なのに、なぜにこにこしながら話す)
意外とサイコパスらしい。
後輩には慕われていたらしいが、敬語で話すことを嫌っていたので、そこでもなにかあったのだろう。
「ふうん。まあいいや。許してあげる」
翠は小さくガッツポーズした。
(ださい。行動が)
行動がモテなさそう。
所詮、顔だけだ。
「なんで海に来たの?家からでも見えるでしょ」
翠が不思議そうに顔を覗き込んでくる。
近くで見ると、改めて美人の破壊力はすごいとしみじみ感じる。
糸は、暗い海を見つめる。
少し強い風が潮の匂いを運んでくる。
「海が一番綺麗だから、かな」
「まあ。綺麗か。たしかにね」
「わたし、海が一番好きなの」
「へえ」
翠は興味なさそうに相槌を打つと、糸が勝ってきたたこ焼きを勝手に食べた。
なんだかもう、怒る気も消えてなくなった。
糸はふふっと笑う。
「なんか楽しかった。翠が担当で良かった。わたし、眠いから帰る」
糸は来た道を戻って家に帰ることにした。
二人が出会って丁度一か月。
翠の仕事は思わぬ形で終わることになった。
糸が予定にない死に方をした。
彼女なりの”綺麗”の表し方だったのだろうが、翠には理解できない。
桜木糸という名前の、高校生の少女は花緑青という人工染料を飲んで、あの日綺麗だと言った海に飛び込んだ。
色に埋もれて生きてきた彼女の最期はたしかに綺麗だったのかもしれない。
彼女の両親は、警察から伝えられると、驚き、後悔した。
両親と電話した日、糸が望んでいたことだ。
彼女の魂は、虹色で、初めて見た色をしていた。
やはり彼女の世界は色で溢れていたのだと改めて感じる。
糸の虹色の魂はまっすぐに天に昇って行った。
やはり、昨日まであった人が居ないのは寂しいものだ。
数日後。別の担当を天に送り届けた後、いつもならしないのだが、翠は糸の部屋を訪れていた。
翠としてもやはり寂しく思うところがあった。
リビングはやはり色で溢れていて、翠をモデルにして描いた絵も飾られている。
今もまだ、どこかから彼女が顔を出しそうで探してしまいそうになる。
どうか、嘘であってほしい。
しばらく、ぼーっとしていると、彼女のベッドの枕の下から紙が顔を出していたので引っ張ってみた。
”わたしの死神さんへ”
そう書かれた手紙だった。
わたしの死神さんへ
まずは、たくさん色に満ちた思い出をくれてありがとう。
水族館も花火も色でいっぱいでした。
わたしの大好きな色鮮やかな世界です。
翠は、死神というものをやめたいのではありませんか?
わたしにはそう見えました。
優しいあなたに死神は似合わない。
わたしはそう思います。
担当した子に感情移入しちゃうから。
あなたが楽しいなら別にいいけど、魂を取るたびに傷ついているあなたに死神は似合いません。
わたしはやめたほうが良いと思います。
さて、勝手に死んでごめんなさい。
あなたにこれ以上辛い思いをしてほしくないから、傷ついてほしくないから、自分の意志で終わらせました。
迷惑をかけてしまうようならごめんなさい。
だけど、わたしは綺麗にこの世界に相応しく散れました。
わたしの芸術は、わたしという作品で終わることができました。
どうもありがとう。
わたしの担当になってくれてありがとう。
わたしは優しいあなたが大好きです。もし、死神をやめるならこっちに来ますよね。
わたしはずっと待つことにしました。
(図星だな)
死神をやめたいとは、思っていた。
翠は力なく笑う。
封筒の中には、一枚の絵が入っていた。
勿忘草とエーデルワイスが描かれた紙。
勿忘草の花言葉は私を忘れないで。エーデルワイスは大切な思い出。
彼女らしい最期だった。
ふと、肩を叩かれて、視界の端で金髪が揺れる。
「この子も同じだ。俺もお前には向いてないと思う」
類は豪快に白い歯を見せて笑った。
視界が歪む。目に涙がたまっているのだと気づくまで少しだけ時間がかかった。
温かい涙が頬を伝う。
「おれ、死神やめるよ」
類は一瞬言葉に詰まった。
「そうか。良く決断したな」
「糸が待ってるから。また背中殴られちゃうからさ」
翠は口角を上げる。
類は肩をもう一度叩くと、ポケットから白い粉を出して、翠に振りかける。
手の先から光始めて、力が抜けていく。
「しあわせにな」
類が少しだけ寂しそうに微笑む姿が見えたのを最後に翠の視界は真っ白になった。
「早いね。今回は」
聞き覚えのある声が聞こえる。
ふんわり体が何かに包まれる。翠も背中に手を回して力を込めた。
絵具と紙の匂いがする。
「翠、わたしは今来たところ」
翠を迎えた絵描きの少女は満面の笑みを浮かべた。
屋上のコンクリートは冷たくて、寂しい。
冬というものは色が無いが、よく見れば、一番色に溢れていて綺麗な季節だと糸は思う。
しかし、今は春で、どこを見ても明るい色に包まれている。
桜や菜の花なんかが代表的だ。よく、絵に描かれる。
糸はキャンバスに色を付けていく。
空は青く、太陽は優しい色をしている。
人生というのは素敵なもので、色で溢れている。
だからこそ、この世界に相応しい、一番綺麗な死に方をしたい。
いつもそう思う。太宰治や芥川龍之介の死因は自殺だったとどこかで聞いたが、
芸術的な考えに侵されていた二人の自身の信念を貫き通した結果なのだろう。
そこだけは尊敬する。
息をついて空を見上げると、強い風が吹いて、思わず目をつぶった。
(風つよ)
目を開けると、目の前に見たことが無い男の子が立っていて、こちらを見ていた。
鼻筋がすっと通って、麗しい顔立ちの彼を糸は見たことが無かった。
記憶力は良い方なので、思い出せないのならあったこともない人だ。
「はじめまして」
彼は丁寧にお辞儀する。
屋上には糸だけしかいないので、他の誰かに言っているとは考えにくい。
糸は一応、小さく会釈した。
「おれは死神。今日から君の担当になります」
(何言ってるんだろう)
変な人に絡まれてしまったかもしれない。
「うわー、上手だね。すっごい」
彼はとたとたと小走りで近づいてくると、キャンバスを覗いて目を輝かせた。
絵を誉められるのは嬉しいが、知らない人に言われるのは少し怖い。
中二病気質なのだろうか。
しばらくすると、糸のほうに向きなおって、どこからか取り出したメモ帳をパラパラとめくる。
「桜木糸(さくらぎいと)さんであってる?」
「そうですけど」
死神にお世話になる予定はない。
糸は健康で、病気もないし、余命もない。
同姓同名の人間違いであってほしい。
まだお迎えを頼む予定はない。
絵ばかり描く人生はそこそこ楽しいのだ。
「もうすぐ死ぬってことですか?」
思わず聞いてしまう。
まだ生きていたい。
死神は、うーん、と唸る。
「死ぬ日がいつなのかは分かんない。だから前から担当がつけられるの」
そう言ってふわあとあくびした。
なんて呑気な死神なんだろう。
「あ、そうそう。おれのことは翠って呼んでね。今日は顔合わせというか、挨拶だけだから」
「え、あ、はい」
翠は、またね、とひらひら手を振って消えた。
どこかふわふわしている、掴みにくい、どちらかと言えば嫌いなタイプだった。
次の日、死神は家にやって来た。
昨日のショックからか驚きからか、糸は熱を出していた。
久しぶりの高熱で、人間なのかよくわからない生き物と会話する気にはなれない。
しかし、翠は近くの椅子に座って部屋をきょろきょろと見まわしている。
両親は海外出張という名の海外旅行中で、家には誰もいない。
その状態が稀というわけではなく、日常なので、部屋は糸が生きやすい環境に模様替えした。
部屋中に描いた絵を飾り、時々買った絵も混ざっている。
壁に取り付けた本棚には、著名な文豪の作品が並んでいる。
翠にとっては珍しい環境なのだろうが、あまりきょろきょろしないでほしい。
なんだかくすぐったい気持ちになる。
「なんか、色でいっぱいだね、この部屋」
「一応、絵描くの好きなので」
翠は、ベッドのそばまで椅子を近づけて、ベッドにもたれた。
ベッドがギシッと鳴ったので、彼にも重さがあるのだろう。驚いた。
「敬語やめない?年近そうだし」
「そうは見えないけど」
昨日と今日だけでも、性格は糸より年が幾らか幼く見える。
容姿だけは秀でているが、性格はあまり大人ではないらしい。
翠はむっとしたのか、頬を膨らませてこちらを見た。
(あざといとはこのことか)
世のアイドルグループにいそうだ。
「一応、君より年上なんだよ」
「いくつ?」
「....ひとつ」
(ひとつなんて誤差だ)
糸は鼻で笑った。
翠はさらに顔を膨らませて、こちらにクッションをぶつけてきた。
クッションはかすりもせずに壁にぶつかって落ちた。
「君は不思議だね。今まで担当してきた子たちは生きるのが嫌だって泣き叫ぶか、早く連れて行ってくれって泣くかどっちかだった んだよね」
「極端」
「でしょ。君はやりたいこととかないの?」
「やりたいこと...」
熱でぐらぐらする頭で考える。
突然、やりたいことなんて言われて思いつくわけないと思ったわけだが、ひとつ思いついた。
「絵、描きたい」
「絵?昨日も描いてたじゃん。いいの?特別なことじゃないけど」
糸は翠の方を見る。
人生がもし、もうすぐ終わってしまうなら、やりたいことはやっておいたほうが良い。
本当なら60を迎えたあたりでやろうと思っていたのだが、予定が狂った。
人生で一番時間をかける、大作を作りたかった。
「翠、あなたをモデルにしてもいい?」
翠はぽかんとしたのち、満面の笑みを浮かべた。
(嬉しそう)
子どもっぽく幼いところがあるが、顔立ちは一級品なので、綺麗なものをモデルにしたい糸としてはぴったりの相手なのだ。
「いいの?おれで」
「うん。綺麗だから」
「えー、うれしー。いつから描く?今日じゃないよね?明日とか?」
(熱上がってきたかな)
視界がぼやぼやして、顔が熱くなってきた。
頭もふんわりしている。
翠が口をパクパクしているので、何か話しているのだろうが、耳鳴りがして聞き取れない。
あまり一気に話さないでほしい。頭を回すのは疲れる。
糸は深い眠りについた。
目が覚めた。
あれから寝てしまったようで、すでに死神の姿はなかった。
(なに考えてるのかわかんなかったな)
だけど、と思う。
(悪い人ではないみたいだ)
ベッドのそばのサイドテーブルに、冷えピタや解熱剤、栄養ドリンクなどが置かれていた。
(そろそろ絵描けるかな)
クローゼットにしまってあった大きなキャンバスを壁にかけて、絵具を取り出す。
熱がなかなか下がらず、四日うなされた。
その間、翠は、安否確認をするためだけに部屋を訪れていたようだった。
体調が悪い時は話しかけてほしくないものなので、そっとしておいてくれるのはありがたかった。
「あ、回復?」
後ろから声が聞こえた。
絵具を出す手を止めて振り向く。
「うん。そこそこには。モデルさんは椅子に座ってもらえる?」
「もちろん。任せてよ」
翠は首が折れるほどうなづくと、椅子に座った。
どんなポーズか悩んだ末、足を組んで姿勢よく座ることにしたようだ。
(一番疲れるのに)
死神に疲れるという概念はないのか。
うきうきとこちらを見つめている。
「じゃあ描くけど、動かないでね」
「はあい」
張り切って絵具を出してしまったが、鉛筆で下書きから始める。
どうせ描くなら綺麗な顔を本物のように表現したい。
(沈黙は気まずい)
翠としても、描いているときに話すのはよくないという遠慮からかあまり口を開かない。
糸も話し上手でもおしゃべり好きでもないので、口数は無いに等しい。
しかし、いくら糸でもこの空気感には堪えられなかった。
「死神なんてしてて楽しい?」
糸はなんとか考えて質問する。
翠は少し眉を下げて悲しそうにした。
死神に感情があるのかは不明なので、それが本当なのか分からないけど。
「楽しくはないよ。交通事故で魂が浮いた人なんて特に」
「なんで?」
「だって血まみれで死にかけの人が、まだ死にたくないとか言うんだよ。運転手の人はすごい焦った顔して電話してるし、
野次馬の人は、すごいひどい目にあった人が目の前にいるのに携帯向けるし。結構辛いよ」
死神にも感情はあるみたいだ。
(交通事故死じゃないといいな)
糸にも優しさというものはあるので、辛い思いをさせたくないなと思う。
(一応聞いておくか)
「わたしはどうやって死ぬの?」
翠は言葉に詰まった。
少しだけ苦しそうな顔をした。
「交通事故、なんだよねえ。それが」
今度は糸が言葉に詰まった。
神様は意地悪だ。
決められたことに逆らうつもりはなかったが、こればかりは逆らいたい。
血まみれになって命乞いをするのはごめんだ。野次馬に携帯を向けられたくもない。
「....回避できない?」
「決められてるからねえ。仕方ないよ」
「そう」
(なんとしてでも回避してやろう)
それに、交通事故は色で溢れた世界に似合わない、綺麗じゃない死に方だ。
糸の目指しているものではない。
糸は翠の輪郭と大まかなパーツの配置を書き込むと、ため息をついて鉛筆を置いた。
「今日はここまで。疲れた」
翠は伸びをした。
「まあ、気にしないでね、さっきの話。そもそもおれの仕事だからさ」
(気にしてないけど)
死んでいる身にトラウマなんて残りはしないだろう。
淡々と仕事をこなすのが仕事な死神なのに、ひとつひとつに感情移入している方が悪いのだ。
どうにかして感情移入しない訓練をすればいいだけ。
糸が気にするべきことではない。
「じゃあ、帰るね。またあした」
翠はぱっと笑うと窓を飛び出していった。
ここは高層マンションの40階なので、人間なら即死だろう。
それが許されるのは死神だけだ。
(どこぞの怪盗みたい)
糸は一人でクスリと笑った。
今回担当の少女は年が近くて、いつもより感情移入してしまいそうだ。
彼女はお金持ちなのか、マンションの40階のかなり広い部屋に一人で住んでいた。
ザ・芸術家という感じの部屋で、そこらじゅうに絵が飾ってあった。
どれも素晴らしい出来で買ったものかと思えば、彼女は自分で描いたと言った。
高校生の彼女が大人になれば、作家として売れただろうけど、残念ながらそれは叶わない。
彼女は、糸は大人になれない女の子だった。
翠も大人になれなかった身として、少し思うところがあったので担当希望は出したくなかった。
しかし、彼女は交通事故死する。
交通事故はあまりにも心を病むので、死神たちが担当になりたがらない。
だから、最年少の翠が選ばれたわけだ。
「すごー、鉛筆だけでも誰か分かるね」
糸は褒めてもあまりうれしそうにしない。
表情が滅多に動かない。
接しにくいタイプかと思ったら、話しかけて見ればよく喋る子だった。
顎ラインで切りそろえられた真っ黒の髪が揺れて振り返る。
大きな瞳はどこかがらんどうで、人形のように見える。
「そう?色塗らないと面白くないけど」
彼女の世界は色で溢れているらしい。
寝室は所々に花があって、どれも綺麗に管理されていた。
「モデルになんてしてもらったことないよ。死神になってよかったって思えたかも」
「お世辞がうまいんだから」
糸は少しだけ微笑んだ。
最近、少しだけだが表情がほぐれた気がする。
高校も通信制で親も海外となれば、人と関わる機会が減るのも納得だ。
それで感情が乏しくなっていたのだろう。
「もう少しすれば色が付けれるよ」
糸は満足そうにキャンバスを見つめるが、翠はふと不思議に思う。
前に担当していた強欲お嬢様は、色んなところに翠を連れまわして彼氏が居るのだと自慢して回り、
買い物に連れ出しては荷物持ちをさせたりと人使いが荒かった。
だけど、彼女はなにもしたいと言わない。
したいことが無いというのは、担当として気になるところだ。
「他にしたいことないの?」
「他に?」
糸は何か考えているのか動きが止まる。
(かわいく思える)
小動物のようだ。
糸は絵を描くことにしか頭が無いので、すぐに他のことは思い浮かばないだろう。
案の定、そうだった。
悪いと思ってしまったのか、逆に尋ねてきた。
「翠はなにかやりたいことないの?」
「おれがしたいことしても意味ないじゃん」
「人について行くの案外好きなんだけどなあ」
糸は残念そうに若干俯く。
(そんなことされると、なにか考えないといけないじゃないか)
年が近いということもあってか、糸には弱いらしい。
翠は立ち上がる。
「じゃあなにか考えてくるよ」
糸は嬉しそうにする。
(演技かな、これは)
彼女は生きるのがうまい。
翠は、ひらりと手を振って窓から飛び降りた。
「あ、帰ってきた」
一面真っ白な空間に入ると、ソファにうつぶせで寝転がっている仲間が見えた。
金髪に染められた髪は彼の幼い顔立ちに似合っていない。
「おかえり」
「うん」
「反抗期かお前は。ただいまだろ」
彼は翠の頭をぐしゃぐしゃと荒く撫でる。
十は年上の彼は翠をいつまでも子ども扱いしてくる。
彼は、翠の先輩にあたる死神で、よくしてもらっている。
名前は類という。
現在、担当は持っているものの、教育係兼フォローとして翠の周りをうろうろしている。
「暇なの?」
「まあね。今日で仕事終わったから。そっちは?」
「もう少しだと思うけど」
「...まーた感情移入しちゃってんの?いい子だねお前は。やっぱ死神向いてないわ」
むっとする。
高校生で死神というものになった者としては、感情移入するなという方が難しい。
それに、今の担当は年が近いので友達と同じ感覚で接してしまう。
それこそ無理だ。
やっぱり、向いていないのだろう。もう近いうちにやめよう。
「すいー」
「んー?」
「これあげるわ。なんか貰った」
「誰に?」
「担当のおばあさん。もういけないからって」
複雑な気持ちになる。
「俺興味ないんだよねー、水族館とか。あげる」
類はチケットを適当に投げたので、翠はそれを慌ててキャッチする。
類は担当に感情移入しないタイプなので、すぐに切り捨ててしまう。
どれだけ相手に良くしてもらっても、その場では笑顔で接するが、すぐに記憶から消す。
(ひどいな。せっかくくれたのに)
こういう人が死神に向いているのだろう。
死神という職業は感情移入をしないのが正義だが、実際それは一部しかできない。
翠にはまだまだ難しい。そろそろ、やめようかとさえ思ってくる。
しかし、いいものを貰った。
翠はいつもより早く来た。
そのおかげで、朝ごはんを中断して客人の接待に回らなくてはいけなくなった。
(フレンチトーストうまくできたのに)
机の上のフレンチトーストは冷えかけている。
ほかほかのままで食べたかった。
翠はなんだかご機嫌そうで、鼻歌を歌いながら出したコーヒーを口にしている。
砂糖がたくさん入っていることを知っているので、かっこいいとは思えない。
「機嫌いいね。彼女でもできたの?」
そんなことを言うと、翠はむせた。
「そんなわけない!」
翠は、じゃーん、と言って二枚のチケットを出した。
ここから少し先の水族館のチケットだった。
死神にそんな伝手があるのだと、素直に驚く。
「これ、行きたいんだけど。付いてきてくれる?」
彼は可愛らしく首をかしげてお願いしてくる。
人混みの耳がキーンとなるのも色々な香水が混ざる匂いもあまり得意では無いので行きたくはない。
(気は乗らないが、誘い方がずるい)
了承することにした。
「...人間になれたんだ」
糸が驚いたように目を開いている。
あまり乗り気ではなさそうだったが、可愛めなワンピースを着ていて、余所行きの格好をしている。
(ちょっと楽しみなんだな)
なんだか可笑しくて笑ってしまう。
「やっぱり人多いね」
「日曜だからね」
やはり水族館は人で溢れている。
糸は人混みが苦手なようで、顔をゆがめている。
「迷子にならないと良いけど」
「迷子にさせないから大丈夫だよ」
糸を見下ろして、そんなことを言うと彼女の手を取ってみる。
糸は驚いていたが、自分のされたことに気づいて頬を桜色に染めた。
肌が白いので、分かりやすい。
(照れてる)
しかし、その白い肌が交通事故で真っ赤に染まるのかと考えると胸が痛い。
それで、彼女もきっと助けを求めるのだろう。
『もう少し生きたい』と。
暗い気持ちになりかけた翠の手を糸は弱く握り返した。
翠の心臓は大きく波打った。
「綺麗」
糸はクラゲの水槽に魅入っている。
フワフワとするクラゲを見たのは何年ぶりだろう。
中学の修学旅行以来だろうか。
自分がもし生きていたらと考えてしまう。
もし生きていたら、今頃大学生で教師になるために勉強していたんだと思う。
教師になりたかった。
だけど、そんな夢は儚く散った。
翠は大人になれなかったからだ。
キラキラと目を輝かせる彼女もいずれは翠と同じ道をたどるのかと考えるともやもやとする。
「クラゲ好きなの?」
「いや、別に」
糸は立ち上がると、隣の水槽に移る。
「こっちのが好き」
糸は砂を出たり入ったりするチンアナゴを指さす。
綺麗な色の魚が好きなわけではなさそうだ。
さっき見ていたクラゲも、絵の題材にしたいなどと考えていたのだろう。
海外から絵具や染料を取り寄せるくらいなので、熱量は素晴らしい。
「死神は担当した人にもらった物とかどうしてるの?」
「もらったものかあ、保管してるよ。気分次第だけど」
「ひど。気分が乗らなかったら捨てるんだ。最悪、最低、女たらし」
糸は翠をディスりながらお土産コーナーを見ている。
女たらし、そんなのはどこから出てきたのだろう。
(女たらしではなかったけど)
彼女もいたことない。
何を根拠に言っているのだろう、この子は。
「女たらしだと思ってたの?」
糸はこちらをちらっと見てから手元に視線を落とす。
「.....顔良い奴はそうなのかと」
「ひどい偏見だね」
翠は笑う。
楽しい。おもしろい。
久しぶりに楽しいと思った。
淡々と仕事しないといけないと思っていたから。
少し、緊張が緩んだ。
「はい。これ、あげる」
糸はいつの間にか買っていたチンアナゴのキーホルダーを翠の手に乗せた。
(チョイスが絶妙)
イルカやカメではなく、チンアナゴという生き物に惹かれるのは珍しい。
「気が向いたら残しておいて」
「...気が向いたらね」
少しだけ意地悪した。
糸はまんざらでもなさそうなのでむっとする。
翠は離れてしまっていた手を握りなおして水族館を出た。
(案外、楽しかった。恋愛をするならあんな子とが良かった)
もうできないけど、と思う。
胴体とはもう少し仲良くしておきたかったが、もう時間は長くない。
まだまだ元気だが、事故死は仕方がない。
首に付けた貝殻のチャームがついたネックレスを外して、ケースに入れる。
翠がくれた。
気が向いたので、大切に持っておこうと思う。
「いらっしゃい」
短いが、糸にとっては長い間というか毎日会っているので、彼の気配を覚えてしまった。
翠はそっと入ってきたつもりだったのか、声をかけられてびっくりしていた。
絵は完成に近づいてきている。やっと、今日から色付けできる。
翠はいつもと同じ場所に座り、足を組んだ。
(もう慣れたものだな)
「ねえ」
「なに?」
「花に興味ある?」
「.....」
(ないんだな)
けれども、毎日話していると会話の話題がなくなるのだ。
糸はテーブルの上に置いた花瓶の中に入っている花を指さす。
丸い、黄色の花。ミモザだ。
「それ、ミモザっていうんだけど、花言葉はひそかな愛」
「ロマンチックだね。あれは?」
「イベリス。初恋の思い出だったかな」
祖母が花屋をしていたころ、手伝いをしていた糸は覚えさせられた。
必死に覚えたので、忘れられない。
翠は面白そうに花を見ている。
「これで調べたら?貸してあげるけど」
花言葉図鑑を手渡す。
もう色を塗るだけなので、色味さえわかれば、ポーズを保っていなくても描ける。
死神に花言葉を覚えさせても意味がないのに、と思ったが、まあいいだろう。
知識は多い方が仕事で役に立つ。
「面白いかも。貸してよこれ」
「あげるよ。もう死ぬんだし」
翠は気まずそうに笑った。
それもそうだ。彼が糸の魂を持っていくのだから。
少しだけ申し訳なくなる。
翠は立ち上がって、窓辺に腰を掛けた。
髪が風になびかれてふわりと揺れる。翠は前髪をかきあげた。
どこかの物語に出てくる王子様はこんな感じなのだろうと思う。
それくらい綺麗だった。
(これを描けばよかったかね)
それでも、キャンバスに描かれた翠はどこの角度から見ても綺麗で、麗しかった。
糸の自信作になりそうな予感がする。
「....なに黄昏てるの?」
翠は恥ずかしそうにうつむいた。
かっこつけたつもりなのだろう。
それか、どうしようか迷った末に変な行動をしてしまったか。
翠のことだ、おそらく後者だ。
「なんとなく?」
「変なの」
「じゃあ帰ろうかな。またあしたね」
翠はいつも通りひらりと手を振って、空に消えた。
きっと、翠は優しいから糸が死んだときのことを考えてしまったのだろう。
交通事故が一番きついと言っていた。
糸はため息をついてベッドに倒れこんだ。
(どうしようかね)
無駄に広い部屋に糸の呼吸だけが響き渡った。
朝七時。
電話が鳴った。
『もしもし?あ、でたでた。糸ちゃん、久しぶり』
母の声だった。
なんだかもう会いたくない。
娘の死ぬ直前まで両親は海外に居るのだろうから。
(最後くらい後悔させてやりたいかも)
糸はにやっとする。小学生以来のいたずらだろうか。
「久しぶり」
『元気にやってる?糸ちゃんはお利口だから大丈夫よって言ったのにお父さんがどうしてもって』
「そう」
『おー、糸。久しぶり』
「久しぶり」
『もう少ししたら帰ろうと思うんだが、糸もこっち来るか?』
ついこの前までは願ってやまなかった言葉だった。
(もう遅い)
置手紙だけ残して海外に飛び立った両親は一年弱連絡をくれなかった。
もう慣れたが、寂しかった。
連絡の一度や二度はしてほしかった。
だけど、自分は二人のお荷物だから、とお利口さんに生きてきた。
この誘いだって、前なら断れなかった。
「ううん。今は絵に集中したいから」
『....そうか。ならいいんだ。じゃあ、また』
また、は来るのだろうか。
笑いがこぼれる。
父は残念そうに息を吐いて電話を切った。
「ねえ。居るんでしょ?」
カーテンの方に声をかける。
ひらりとカーテンが揺れて、翠が顔を出す。
電話を聞いていたらしい。
(別にいいけど)
「聞いちゃってごめんね?」
翠は片目を閉じて可愛らしく両手を合わせた。
(あざとい)
さぞモテただろう。
「いいよ、別に」
糸はパレットを手に取る。
キャンバスに色を付ける。もう少しで完成する。
頬に桜色をつけて、生き生きとさせる。
モネのような淡い水彩画も好きだが、本物に限りなく近い絵柄も好きだ。
今回は本物に近づく絵柄を選んだ。
「えー、すごい。鏡みたいだね。じょーず」
翠は不器用に糸の髪をサラサラと撫でた。
幼稚園児のするそれのように。
「上手なのは知ってるよ。コンテストに選ばれてばっかりなんだから」
「はいはい」
「よし。完成」
糸は満足げにキャンバスを眺める。
生き生きとした翠は本物に近く、糸の人生の中で最高傑作だといえる。
翠も満足そうに何度も見ている。
いつか、時がたった時にこれが発見されれば、白馬の王子様とでも評されて話題になるだろうか。
糸のいない未来を想像して微笑む。
どんな有名な画家も大作を完成させたときはこんな気持ちだったのだろうなと、有名な画家になった気持ちになる。
「ありがとー。おれだけしか見ないの勿体ないね」
「まあね。私が死んだら作品展にでもだしてよ」
「そうだね。努力するよ」
翠は愛おしそうにキャンバスを撫でる。
人を笑顔にさせる作品が作れてうれしい。
「ねえ。どんな死に方が一番綺麗?」
「....は?」
突然、思いついたことを質問してみる。
(急に聞かれても困るか)
「交通事故ってこの世界に相応しくないと思わない?」
(何を言っているんだろう。この子は)
確かに、交通事故は何も美しくないけど、死因に美しいもなにもないだろう。
わからない。頭をフル回転させないと彼女を理解できない。
「なにしようとしてるの?」
出来るだけ笑顔を努力して声をかける。
糸は、顎に手を当てて考えるしぐさをする。
「この世界で一番綺麗に死にたいの。わたし」
「綺麗に死ぬとなくない?」
「まあ、たしかに。けどさ、芸術家だから一応。ちょっと考えちゃうんだよね」
「へ、へえ」
芸術家。
たしかにそうなのかもしれないけど。
そんなことを考えるような子には見えなかった。
だけど、彼女の人生なので翠に言えることは何もない。
「ちょっと、用事思い出したから帰るね」
翠は再び笑顔を作って窓を飛び降りる。
用事があるなんて、ぎこちない言い訳だっただろうか。
「お祭り行こう」
死神と出会って一か月が経とうとしている。
一向にその時は来ない。外に出ると交通事故にあう確率は高くなるが、死ぬ前に花火は見たい。
「いいけど、急だね」
翠はコーヒーを飲んでいる。もちろん、砂糖多めの。
糸も作品が完成したので、ゆっくりとピーチティーを飲んでいる。
「今日の夜なんだけど。行けそう?」
「死神は基本的に暇ですから」
「そう。なら決まりね」
夜七時に海に集合。
そう決めた。
なのに、彼は一時間たっても来ない。
花火はどんどんと打ちあがり、もうすぐ終わりに近づいている。
暇だと言っていたのに、何をしているのだろう。
夜空に咲く花に人々は目を奪われている。
色があふれている。
「ごめんっ」
焦った声が聞こえて、ふわりと甘い匂いが鼻をくすぐった。
翠が隣に座っていた。
「遅いよ。遅刻」
「今来たところとか言うんじゃないんだ」
糸はムカッとして翠の背中を思い切り叩いた。
そこそこ大きな音が鳴ったので、近くの人が数人こちらを見た。
「一時間以上たってるのに今来たわけないでしょ。ばかなの?」
「ごめんなさい」
子犬のようにしゅんとなっている。
(怒れない)
動物は好きなのだ。
「なんか話してくれるなら許す」
考えてみれば、名前を知っているだけでそれ以外は何も知らないのだ。
こっちのことは知っているので、一方的なのは不平等だろう。
(一つくらい聞いても罰は当たらない)
翠は頭を抱えている。
そんなに思い出が無いのだろうか。
「あ、部活の話とかどう?」
「なんでもいい」
「おっけ。おれね高校の時、天文学部だったの。星見るだけみたいな。星好きだから入ったんだけど、実際は部活がだるい陽キャの集まりで、静かに星見てたおれはまあいじめられたの。顔が派手とか髪の色が派手だとか。地毛なのに。それでさ、星見るとかだせえって言われたわけね。好きな子と否定されるってすごい腹立つの。だから、やり返そうと思って、下剤をそいつらの水筒に混ぜて、トイレから出られ無くしてやった。そっからなくなったの、いじめ。いじめられたらおすすめ」
(いじめの話なのに、なぜにこにこしながら話す)
意外とサイコパスらしい。
後輩には慕われていたらしいが、敬語で話すことを嫌っていたので、そこでもなにかあったのだろう。
「ふうん。まあいいや。許してあげる」
翠は小さくガッツポーズした。
(ださい。行動が)
行動がモテなさそう。
所詮、顔だけだ。
「なんで海に来たの?家からでも見えるでしょ」
翠が不思議そうに顔を覗き込んでくる。
近くで見ると、改めて美人の破壊力はすごいとしみじみ感じる。
糸は、暗い海を見つめる。
少し強い風が潮の匂いを運んでくる。
「海が一番綺麗だから、かな」
「まあ。綺麗か。たしかにね」
「わたし、海が一番好きなの」
「へえ」
翠は興味なさそうに相槌を打つと、糸が勝ってきたたこ焼きを勝手に食べた。
なんだかもう、怒る気も消えてなくなった。
糸はふふっと笑う。
「なんか楽しかった。翠が担当で良かった。わたし、眠いから帰る」
糸は来た道を戻って家に帰ることにした。
二人が出会って丁度一か月。
翠の仕事は思わぬ形で終わることになった。
糸が予定にない死に方をした。
彼女なりの”綺麗”の表し方だったのだろうが、翠には理解できない。
桜木糸という名前の、高校生の少女は花緑青という人工染料を飲んで、あの日綺麗だと言った海に飛び込んだ。
色に埋もれて生きてきた彼女の最期はたしかに綺麗だったのかもしれない。
彼女の両親は、警察から伝えられると、驚き、後悔した。
両親と電話した日、糸が望んでいたことだ。
彼女の魂は、虹色で、初めて見た色をしていた。
やはり彼女の世界は色で溢れていたのだと改めて感じる。
糸の虹色の魂はまっすぐに天に昇って行った。
やはり、昨日まであった人が居ないのは寂しいものだ。
数日後。別の担当を天に送り届けた後、いつもならしないのだが、翠は糸の部屋を訪れていた。
翠としてもやはり寂しく思うところがあった。
リビングはやはり色で溢れていて、翠をモデルにして描いた絵も飾られている。
今もまだ、どこかから彼女が顔を出しそうで探してしまいそうになる。
どうか、嘘であってほしい。
しばらく、ぼーっとしていると、彼女のベッドの枕の下から紙が顔を出していたので引っ張ってみた。
”わたしの死神さんへ”
そう書かれた手紙だった。
わたしの死神さんへ
まずは、たくさん色に満ちた思い出をくれてありがとう。
水族館も花火も色でいっぱいでした。
わたしの大好きな色鮮やかな世界です。
翠は、死神というものをやめたいのではありませんか?
わたしにはそう見えました。
優しいあなたに死神は似合わない。
わたしはそう思います。
担当した子に感情移入しちゃうから。
あなたが楽しいなら別にいいけど、魂を取るたびに傷ついているあなたに死神は似合いません。
わたしはやめたほうが良いと思います。
さて、勝手に死んでごめんなさい。
あなたにこれ以上辛い思いをしてほしくないから、傷ついてほしくないから、自分の意志で終わらせました。
迷惑をかけてしまうようならごめんなさい。
だけど、わたしは綺麗にこの世界に相応しく散れました。
わたしの芸術は、わたしという作品で終わることができました。
どうもありがとう。
わたしの担当になってくれてありがとう。
わたしは優しいあなたが大好きです。もし、死神をやめるならこっちに来ますよね。
わたしはずっと待つことにしました。
(図星だな)
死神をやめたいとは、思っていた。
翠は力なく笑う。
封筒の中には、一枚の絵が入っていた。
勿忘草とエーデルワイスが描かれた紙。
勿忘草の花言葉は私を忘れないで。エーデルワイスは大切な思い出。
彼女らしい最期だった。
ふと、肩を叩かれて、視界の端で金髪が揺れる。
「この子も同じだ。俺もお前には向いてないと思う」
類は豪快に白い歯を見せて笑った。
視界が歪む。目に涙がたまっているのだと気づくまで少しだけ時間がかかった。
温かい涙が頬を伝う。
「おれ、死神やめるよ」
類は一瞬言葉に詰まった。
「そうか。良く決断したな」
「糸が待ってるから。また背中殴られちゃうからさ」
翠は口角を上げる。
類は肩をもう一度叩くと、ポケットから白い粉を出して、翠に振りかける。
手の先から光始めて、力が抜けていく。
「しあわせにな」
類が少しだけ寂しそうに微笑む姿が見えたのを最後に翠の視界は真っ白になった。
「早いね。今回は」
聞き覚えのある声が聞こえる。
ふんわり体が何かに包まれる。翠も背中に手を回して力を込めた。
絵具と紙の匂いがする。
「翠、わたしは今来たところ」
翠を迎えた絵描きの少女は満面の笑みを浮かべた。