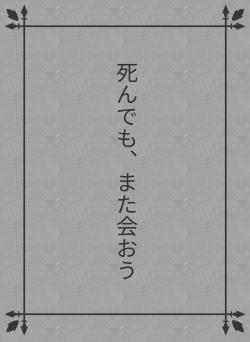時は過ぎ初夏を迎えた。澄み渡る空の下、僕は悩んでいた。どうにも最近、君が心を閉ざしているように見えるのだ。僕と話せば少し笑うものの、目が死んでいる。その上、いつも君から話しかけてくることが減った。何を話してもどこか心に届いていないようで、見ているこちらも悲しくなってくる。
「樹里ちゃん。笑って、笑ってよ。僕、樹里ちゃんの笑顔が見たいよ。」
もう抑えきれなかった。
「そんなこと言ってくれるのともくんだけだよ。ありがとう。」
《なに言ってるの?いるよ。樹里ちゃんの笑顔、見たい人。》とは言えなかった。事実、君にそう願う人は、僕ぐらいしかいないから。僕は無力ながら、押し黙ることしかできなかった。夏休みが明日に迫って来ていた。
「樹里ちゃん。笑って、笑ってよ。僕、樹里ちゃんの笑顔が見たいよ。」
もう抑えきれなかった。
「そんなこと言ってくれるのともくんだけだよ。ありがとう。」
《なに言ってるの?いるよ。樹里ちゃんの笑顔、見たい人。》とは言えなかった。事実、君にそう願う人は、僕ぐらいしかいないから。僕は無力ながら、押し黙ることしかできなかった。夏休みが明日に迫って来ていた。