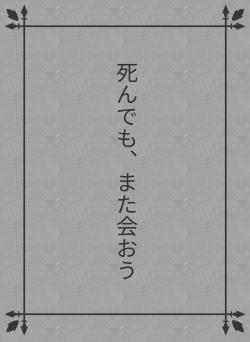季節は過ぎ、高校入学して初めての冬が来た。その日は、凍えるかのような寒さで、僕の手足は氷のように冷たくなっていた。ストーブで手を温めていたその時、気付いた。いつも一番乗りの君がいないことに。ここ数日の君は、いつに増して暗く、影が濃かった。朝のホームルームも1限も、待てど暮せど君は来なかった。チャットで不安そうな顔をする猫のスタンプだけを送って、その日を終えた。返信は…………無かった。
少し寒さが和らいだ頃、君は学校に姿を現した。僕は少しの戸惑いと大きな安堵に包まれて、顔が綻んだ。凄く間抜けな顔をしていただろう。喜びも束の間、僕の思考回路には一つの悩みが生じた。それは、どう声を掛けるか。というものだ。《大丈夫?》は無理に大丈夫と言わせてしまう。《どうした?》は学校に来たことを喜んでなさそうに聞こえてしまう。少し悩んだ末、僕はこう声を掛けることにした。
「樹里ちゃんが学校にいなくて寂しかったよ」
君は泣くように笑った。
「私も、ともくんに会えなくて淋しかったよ。」
「そうか。」
嬉しかった。君が学校に来たのもそうだし、君が僕に会えなくて寂しいという気持ちを抱いていた事が、この上ない喜びだったのだ。
少し寒さが和らいだ頃、君は学校に姿を現した。僕は少しの戸惑いと大きな安堵に包まれて、顔が綻んだ。凄く間抜けな顔をしていただろう。喜びも束の間、僕の思考回路には一つの悩みが生じた。それは、どう声を掛けるか。というものだ。《大丈夫?》は無理に大丈夫と言わせてしまう。《どうした?》は学校に来たことを喜んでなさそうに聞こえてしまう。少し悩んだ末、僕はこう声を掛けることにした。
「樹里ちゃんが学校にいなくて寂しかったよ」
君は泣くように笑った。
「私も、ともくんに会えなくて淋しかったよ。」
「そうか。」
嬉しかった。君が学校に来たのもそうだし、君が僕に会えなくて寂しいという気持ちを抱いていた事が、この上ない喜びだったのだ。