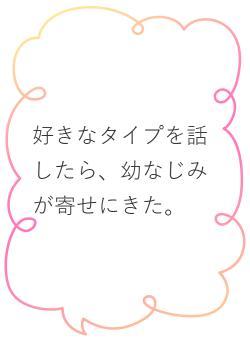◇◇
──やっぱりちょっと早かったな……。
次の日の朝。
いつもなら校門をくぐってすぐに山根くんか海野くんと合流するんだけど、今日は家を出るのが5分くらい早かったせいかどちらにも会わずに教室の前まで来てしまった。
──昨日は久しぶりに山根くんと海野くんと遊べて楽しかったな。
──帰りは桑原くんがほんとに迎えに来てくれたし──……さすがに申し訳なかったからバイト代入ったら何かお礼しよう。
食事制限を始めてからそれに合わせた食事を自分で作るようになって料理の腕がちょっと上がった気がするし、桑原くんにはお弁当でも作って持って行こうかな。いつも学校で食べてるのはコンビニのサラダチキンとサラダとかで料理は苦手そうだし……。
「……ん?」
まずは桑原くんの食べ物の好き嫌いを調査しないとな、あと手作りが大丈夫かも確認を――なんて考えながら教室のドアを開けた僕は──何か愉快なものを見るような視線を浴びた。
「あ、もちもち来た」
「おはよー」
「お、おはよう……?」
挨拶をしてくれたのは葉山さんのグループの女子で、僕に一斉に視線を向けたのもこのグループの人たちだったけど、ここにおはようって言われるの初めてだな……と違和感を抱いた瞬間。
「……!?」
輪の中央にいた葉山さんが持っている冊子に妙に見覚えがあることに気づいた。
「それっ……」
「あ、分かった?もちもちが行ってた小学校の卒業文集!」
僕がよく見えるようにか両手に持ったそれを掲げて、語尾にハートマークでも付きそうな調子で言う葉山さんだけどその目は笑っていない。
「たまたまね?ほんとーにたまたま、昨日他のクラスの友達の家でもちもちの話してたら同じ小学校だったって子がいてさ──それで卒業文集(これ)見せてもらって、もちもちのとこ読んでみたら……ね?」
「うん、めっちゃ笑った」
「もーすっごく面白かったからこれごと借りてきちゃった」
なんで葉山さんがこれを?と聞くまでもなく自分から事情を説明した彼女は、隣にいた他の女子と目線を合わせて吹き出す。──その反応で、文集の中に設けられた“僕・私の夢”の欄が読まれてしまったんだと察する。
「“お姫様抱っこ”って……やる方だとしても笑うけど、もしかしてされる方想定だったりする?」
「……えっと……」
ここで何かうまい返しが出来れば良かったんだろうけど、突然のことにパニックになっていた僕は咄嗟に言葉が出てこなくて──そんな様子を見た葉山さんが「え!?」と大きくリアクションして身を乗り出す。
「否定しないってことは、マジでお姫様抱っこされたかったんだ?」
「……」
「え?え?確かもちもちって、桑原に教えてもらいながらダイエットしてたよね?」
「あ、そゆこと?あの頃の夢をもう一度……ってやつ?」
「やばい、ウチ笑いそう」
「もう笑ってんじゃん」
「……っ」
「あー、傷ついちゃった?」
何も言えないうちに話はどんどん進んで、ついに図星をつかれたのと同時にグループ内で沸き上がった笑い声にいよいよ前を向いてられなくなって俯く。そんな僕に、持っていた文集を机に置いた葉山さんが近づいてくる。
「でも山根に海野に──桑原だって、私らが良いなって思ってる男子みんな望月望月言うから。……正直言って邪魔なんだもん、お前」
「……っ」
「──望月!」
「大丈夫か?」
桑原くんにはまず聞かせないような冷たい声で詰めてくる葉山さんから僕を庇うように前に立ってくれたのは、教室に入って来たばかりだと思われる山根くんと海野くん。
「今ちょっと聞こえたけど、高校生にもなって人の夢にアレコレ言ってくんのはさすがにだるいんじゃねぇの」
「そーだそーだ!俺だって未だにニチアサのヒーローになる夢諦めてないんだぞ!!」
「うん。分かった、山根は今は黙ってて良い」
「は?うちら現実教えてやってるだけなんですけどー」
「そーそー。ダイエットして軽くなったところで望月をお姫様抱っこしたい男なんかいる?って話」
「無駄な努力じゃんね」
──無駄な努力。
最後の葉山さんの一言が背中に重く圧し掛かる。確かに、仮にダイエットが成功して軽々と抱っこできるくらいの体重になったとしても、そんな僕をお姫様抱っこしてくれる素敵な彼氏が出来る予定は今のところはない。
「……そういえば桑原言ってたわ。『望月がしつこいから仕方なくダイエットの面倒見てやってるけど、あのデブはあれ以上痩せられない』って」
「──桑原くんが……?」
追い打ちをかけるつもりだったのか、俯いた僕の頭に浴びせるかのようにそんな暴露をする葉山さん。
「本当に、桑原くんが言ってたの?」
「うん。ね?」
「あー、言ってたかも」
「言ってた言ってた。望月のことデブって114514回くらい言ってた」
「草」
「その数字どっから出てきたん」
そこでやっと顔を上げて確認する僕に、グループ内の他の女子たちを巻き込んで間違いないと頷く葉山さん。……もちろんそれは僕と桑原くんを対立させたい彼女が吐いた嘘だって言うのは分かっていた。
この2ケ月で桑原くんの人となりをじゅうぶん理解したと思われる山根くんと海野くんも、呆れた様子を隠しもせずに彼女たちを見ている。
「あーあれ、望月が怒るやつだ」
そうぼやいて頭の後ろに両手を回したのは山根くんだ。その言葉の通り、僕は次の瞬間にはキッ、と両目に力を入れて葉山さんを睨みつけた。
「それ……訂正して」
「……は?」
「桑原くんが僕のこと『デブ』って言ってたっていうの、嘘だって訂正して。桑原くんがそんなこと言うわけないから」
「な、なに……?」
気弱で何も言い返してこないと思っていた僕が強めの口調で反撃してきたことに怯んだのか、葉山さんはその場から少し後ずさる。
「何お前、さっきまで山根たちの後ろで震えてたくせに急に訂正しろとか言い出して……っ」
「当たり前だよっ、その場の感情でデタラメ言って……桑原くんがクラスメイトに暴言吐いたって、この教室にいる誰かが信じてSNSで拡散しちゃったらどうするの?君たちのくだらない嘘で、桑原くんモデルの仕事出来なくなるかもしれないんだよ……!?」
SNSは友達と好きなアーティストやお店の投稿を見るくらいでしか使っていない僕でも、最近は一度SNSで炎上してしまったらどんなに好感度が高い芸能人でも再起が難しくなるってことだけは分かる。
『モデル仲間はいるっちゃいるけど隙があれば蹴落としてやろうって思ってる奴らばっかで──……』
桑原くんも2ヶ月前にそう語っていたし、影響力の少ない人の投稿でも目敏く見つけた彼をよく思っていない誰かがそこに燃料を投下して大炎上なんてことになったら――考えるだけでも全身の血の気が引いていく。
「そんなの放っとけば良いじゃん!」
「良いわけない!」
制限するべきカロリーの計算の仕方、外食で気をつけること、罪悪感なく食べれる間食――……。
桑原くんが惜しげも無く僕に教えてくれた食事制限のあれこれは、好きな食べ物も同性の友達との交流も全部我慢した彼が自力で手に入れた知識だというのが痛いほど伝わってきて──そうか僕は彼のそんなひたむきなところに惹かれて、好きになっていったんだと。よりにもよってこんなタイミングで納得してしまった僕は──叶う気配のない恋に涙が溢れていた。
「……今までの桑原くんの努力を何だと思ってるんだっ、葉山さんだって無事には済まないかもしれないんだから、変な意地張ってないで早く訂正して!」
「うるさい!絶対言ってた!間違いねぇからっ、桑原はお前のことデブって言ってたんだよ!!」
「なになに?」
「分かんないけど、桑原がなんかやらかしたらしい」
「やめろ、桑原は何もしてない」
「はいはいっ、こちら撮影禁止でーす!」
周りにいた他のクラスメイトも僕らの異変に気づいたようで、桑原、と名前が出てきた時点でスマホを構え出す人も出てきたのを、山根くんと海野くんが止めてくれている。
――どうしよう、真剣に言えば言うほど葉山さんが頑なになる……。
――このままだと訂正出来ないまま授業が始まっちゃう……!
……そんな心配が胸を過ぎった時だった。
「──へぇ、桜太クンにそんなこと言う奴いたの」
「……桑原くん……!」
す、と視界の隅に現れたミニタオルが僕の目尻を覆って、そっと涙を拭う。鮮やかな青色が眩しいそれの持ち主は、いつからそこで見ていたのかスクールバッグを肩に掛けたままの桑原くんだった。
「そのクワバラって奴許せないね、桜太クン」
「……あっ……」
「いや、桑原お前しかいねーから!」
「桑原お前、うちの望月になんてことを」
「は?言ってないし」
茶化しに来る山根くんと海野くんにそう軽く返すと、桑原くんはさりげなくミニタオルを僕に渡しながらこちらを見遣る。
「桜太クンは信じてくれるよね?」
「もちろんっ!」
「良かった。『桑原くんそんなこと言ってたの!?嫌いっ』って言われなくて」
「そっ、そんなこと言うわけないよ!」
「うん、知ってる。さっきも必死に庇ってくれたしね」
「い、いつから見てたの……?」
「ん?葉山が桜太クンの小学校の卒業文集出てきた辺りからかな」
「がっつり最初から……!?」
それならなんで暴言を吐いていたと嘘をつかれた時点で否定に入らなかったのと両肩を揺すって問い質したくなったけど、それをする前に「それよりさぁ」と切り出す桑原くん。
「桜太クン、“お姫様抱っこ”されたかったんならもっと早く言ってくれれば良かったのに」
「えっ、それってどういう──うわぁっ!?」
もしかしてその夢を知られたことで毎日の食事に課せられていた糖質制限が厳しくなる?なんて震えたところで──僕の身体はふわ、と床から離れた。
……桑原くんに抱えられたのだ。
「──お姫様抱っこなんて撮影でもしたことなかったけど、こんな感じなんだね」
「わ、わ……」
「あと葉山、お前来月うちの事務所からCMデビューするらしいじゃん」
「な、なんで桑原がそれ知って……っ」
「清純派で売り出すみたいだけど……そんな奴がこんなことやってて良いの?あ、もちろんスマホで動画撮ってるから──次オレたちに変なことしたらどうなるか分かるでしょ」
「……っ」
「あっ、葉山!」
桑原くんの毅然とした態度に何も言えなくなったらしい葉山さんは大きな音を立ててドアを開けながら教室を出て行って、後を残りの二人の女子が追いかけていく。その間も桑原くんは、涼しい顔をして僕の身体を抱え続けていた。
──まだ高校入学前の体重にすら戻ってないのにこんなに軽々と抱えられるなんてある……!?
「あ、あああの桑原くんっ」
「ん?」
「そ、そろそろ降ろさないと腕とか腰痛めるかもっ」
「あー、気にしないで。オレ結構鍛えてるからこれくらい余裕」
「そうは言っても……、あっ、実は僕、お姫様抱っこは彼氏にやってもらいたくて……!」
「──え」
桑原くんの身体に負担をかけたくない一心で恥を忍んでそう言うけど『じゃあ降りてもらおうかな』とはならず──むしろ胸元にがっちり抱き込まれて閉じ込められるような形になってしまった。
「桜太くん、彼氏いるの?」
「いっ、今はいないけど、いつか出来たらいいなぁって……」
「なんだそういうことか。……オレだったら“そっち”も叶えてあげられるけど」
「……え?」
彼氏はいないと言った途端になぜか少しだけ緩まった腕の中で、一息吐きながら考える。
──“そっち”って、どっちだ。
──彼氏のこと?え、でも。
「桑原くん、好きな人がいるんじゃ……!」
「うん、好きな子いるよ。──選択授業の時に嵌められそうになったオレを助けてくれて、放課後の教室で一人で『痩せたい』ってぼやいてた──いつも一生懸命で可愛い子」
「……!?」
最初に聞いた時よりもずいぶん具体的かつ、身に覚えしかないエピソードに眩暈がしそうだ。 育てちゃいけないと思っていた──叶わないと決めつけていた気持ちが、胸の中でぶわっと花開いていく。
「どうする?オレのこと、彼氏にしてくれる?」
「……あの、僕──」
「──あ、予鈴鳴っちゃった」
未だに僕のことを解放する気のない腕の中で、意を決して答えようと開いた口は、チャイムの音でまた閉じられた。
「もうすぐ先生来るし、続きは別のところで……」
「待て待て待て待て。望月は置いていけ!」
「は?返事聞きたいんだから桜太くんいないと意味ないでしょ」
「おい暫定バカップル、青春するのは放課後になってからだぞー」
当たり前のように僕を連れてサボりに行こうとする桑原くんに、それまで少し離れたところで見守ってくれていた山根くんと海野くんが駆け寄ってくる。
「桑原くん。お返事はちゃんとするから、続きは学校終わってからでも良いかな……?」
「……桜太クンがそう言うなら」
体勢の関係でどうしても上目遣いになってしまうのを恥ずかしく思いながらそうお願いする僕に、桑原くんは何か言いたげにしつつもそっ、と壊れ物を扱うかのように僕を床に降ろしてくれた。
「桜太クン、今日はバイト休みだよね?」
「うん」
「オレも撮影ないから、学校終わったらオレの家来る?」
「いきなり家だなんてふしだらなっ、告白なら校舎裏とかにしときなさいっ!」
「嫌だよお前ら絶対見に来るじゃん」
「当たり前だろ」
「あっ、先生来るよ!」
2人に見られるのは恥ずかしいな、でも好きだと自覚した今いきなり桑原くんの家に行くのも──なんて複雑な気持ちで自分の席に着いたところで、僕のスマホが一回震えてメッセージが来たことを知らせる。……桑原くんからだ。
【放課後、山根と海野にバレないように校舎裏に来て】
教室に入って来た先生にバレないようにそのメッセージを読んで──吹き出しそうになるのを俯いて誤魔化しながら、僕は“OK!”のスタンプを送った。
──その日の放課後、手を繋いで教室へと戻った僕と桑原く──リヒトくんを見るなり、山根くんは「お前らいつの間に!」と叫び、海野くんは「暫定から確定になったわ」と笑っていた。
──やっぱりちょっと早かったな……。
次の日の朝。
いつもなら校門をくぐってすぐに山根くんか海野くんと合流するんだけど、今日は家を出るのが5分くらい早かったせいかどちらにも会わずに教室の前まで来てしまった。
──昨日は久しぶりに山根くんと海野くんと遊べて楽しかったな。
──帰りは桑原くんがほんとに迎えに来てくれたし──……さすがに申し訳なかったからバイト代入ったら何かお礼しよう。
食事制限を始めてからそれに合わせた食事を自分で作るようになって料理の腕がちょっと上がった気がするし、桑原くんにはお弁当でも作って持って行こうかな。いつも学校で食べてるのはコンビニのサラダチキンとサラダとかで料理は苦手そうだし……。
「……ん?」
まずは桑原くんの食べ物の好き嫌いを調査しないとな、あと手作りが大丈夫かも確認を――なんて考えながら教室のドアを開けた僕は──何か愉快なものを見るような視線を浴びた。
「あ、もちもち来た」
「おはよー」
「お、おはよう……?」
挨拶をしてくれたのは葉山さんのグループの女子で、僕に一斉に視線を向けたのもこのグループの人たちだったけど、ここにおはようって言われるの初めてだな……と違和感を抱いた瞬間。
「……!?」
輪の中央にいた葉山さんが持っている冊子に妙に見覚えがあることに気づいた。
「それっ……」
「あ、分かった?もちもちが行ってた小学校の卒業文集!」
僕がよく見えるようにか両手に持ったそれを掲げて、語尾にハートマークでも付きそうな調子で言う葉山さんだけどその目は笑っていない。
「たまたまね?ほんとーにたまたま、昨日他のクラスの友達の家でもちもちの話してたら同じ小学校だったって子がいてさ──それで卒業文集(これ)見せてもらって、もちもちのとこ読んでみたら……ね?」
「うん、めっちゃ笑った」
「もーすっごく面白かったからこれごと借りてきちゃった」
なんで葉山さんがこれを?と聞くまでもなく自分から事情を説明した彼女は、隣にいた他の女子と目線を合わせて吹き出す。──その反応で、文集の中に設けられた“僕・私の夢”の欄が読まれてしまったんだと察する。
「“お姫様抱っこ”って……やる方だとしても笑うけど、もしかしてされる方想定だったりする?」
「……えっと……」
ここで何かうまい返しが出来れば良かったんだろうけど、突然のことにパニックになっていた僕は咄嗟に言葉が出てこなくて──そんな様子を見た葉山さんが「え!?」と大きくリアクションして身を乗り出す。
「否定しないってことは、マジでお姫様抱っこされたかったんだ?」
「……」
「え?え?確かもちもちって、桑原に教えてもらいながらダイエットしてたよね?」
「あ、そゆこと?あの頃の夢をもう一度……ってやつ?」
「やばい、ウチ笑いそう」
「もう笑ってんじゃん」
「……っ」
「あー、傷ついちゃった?」
何も言えないうちに話はどんどん進んで、ついに図星をつかれたのと同時にグループ内で沸き上がった笑い声にいよいよ前を向いてられなくなって俯く。そんな僕に、持っていた文集を机に置いた葉山さんが近づいてくる。
「でも山根に海野に──桑原だって、私らが良いなって思ってる男子みんな望月望月言うから。……正直言って邪魔なんだもん、お前」
「……っ」
「──望月!」
「大丈夫か?」
桑原くんにはまず聞かせないような冷たい声で詰めてくる葉山さんから僕を庇うように前に立ってくれたのは、教室に入って来たばかりだと思われる山根くんと海野くん。
「今ちょっと聞こえたけど、高校生にもなって人の夢にアレコレ言ってくんのはさすがにだるいんじゃねぇの」
「そーだそーだ!俺だって未だにニチアサのヒーローになる夢諦めてないんだぞ!!」
「うん。分かった、山根は今は黙ってて良い」
「は?うちら現実教えてやってるだけなんですけどー」
「そーそー。ダイエットして軽くなったところで望月をお姫様抱っこしたい男なんかいる?って話」
「無駄な努力じゃんね」
──無駄な努力。
最後の葉山さんの一言が背中に重く圧し掛かる。確かに、仮にダイエットが成功して軽々と抱っこできるくらいの体重になったとしても、そんな僕をお姫様抱っこしてくれる素敵な彼氏が出来る予定は今のところはない。
「……そういえば桑原言ってたわ。『望月がしつこいから仕方なくダイエットの面倒見てやってるけど、あのデブはあれ以上痩せられない』って」
「──桑原くんが……?」
追い打ちをかけるつもりだったのか、俯いた僕の頭に浴びせるかのようにそんな暴露をする葉山さん。
「本当に、桑原くんが言ってたの?」
「うん。ね?」
「あー、言ってたかも」
「言ってた言ってた。望月のことデブって114514回くらい言ってた」
「草」
「その数字どっから出てきたん」
そこでやっと顔を上げて確認する僕に、グループ内の他の女子たちを巻き込んで間違いないと頷く葉山さん。……もちろんそれは僕と桑原くんを対立させたい彼女が吐いた嘘だって言うのは分かっていた。
この2ケ月で桑原くんの人となりをじゅうぶん理解したと思われる山根くんと海野くんも、呆れた様子を隠しもせずに彼女たちを見ている。
「あーあれ、望月が怒るやつだ」
そうぼやいて頭の後ろに両手を回したのは山根くんだ。その言葉の通り、僕は次の瞬間にはキッ、と両目に力を入れて葉山さんを睨みつけた。
「それ……訂正して」
「……は?」
「桑原くんが僕のこと『デブ』って言ってたっていうの、嘘だって訂正して。桑原くんがそんなこと言うわけないから」
「な、なに……?」
気弱で何も言い返してこないと思っていた僕が強めの口調で反撃してきたことに怯んだのか、葉山さんはその場から少し後ずさる。
「何お前、さっきまで山根たちの後ろで震えてたくせに急に訂正しろとか言い出して……っ」
「当たり前だよっ、その場の感情でデタラメ言って……桑原くんがクラスメイトに暴言吐いたって、この教室にいる誰かが信じてSNSで拡散しちゃったらどうするの?君たちのくだらない嘘で、桑原くんモデルの仕事出来なくなるかもしれないんだよ……!?」
SNSは友達と好きなアーティストやお店の投稿を見るくらいでしか使っていない僕でも、最近は一度SNSで炎上してしまったらどんなに好感度が高い芸能人でも再起が難しくなるってことだけは分かる。
『モデル仲間はいるっちゃいるけど隙があれば蹴落としてやろうって思ってる奴らばっかで──……』
桑原くんも2ヶ月前にそう語っていたし、影響力の少ない人の投稿でも目敏く見つけた彼をよく思っていない誰かがそこに燃料を投下して大炎上なんてことになったら――考えるだけでも全身の血の気が引いていく。
「そんなの放っとけば良いじゃん!」
「良いわけない!」
制限するべきカロリーの計算の仕方、外食で気をつけること、罪悪感なく食べれる間食――……。
桑原くんが惜しげも無く僕に教えてくれた食事制限のあれこれは、好きな食べ物も同性の友達との交流も全部我慢した彼が自力で手に入れた知識だというのが痛いほど伝わってきて──そうか僕は彼のそんなひたむきなところに惹かれて、好きになっていったんだと。よりにもよってこんなタイミングで納得してしまった僕は──叶う気配のない恋に涙が溢れていた。
「……今までの桑原くんの努力を何だと思ってるんだっ、葉山さんだって無事には済まないかもしれないんだから、変な意地張ってないで早く訂正して!」
「うるさい!絶対言ってた!間違いねぇからっ、桑原はお前のことデブって言ってたんだよ!!」
「なになに?」
「分かんないけど、桑原がなんかやらかしたらしい」
「やめろ、桑原は何もしてない」
「はいはいっ、こちら撮影禁止でーす!」
周りにいた他のクラスメイトも僕らの異変に気づいたようで、桑原、と名前が出てきた時点でスマホを構え出す人も出てきたのを、山根くんと海野くんが止めてくれている。
――どうしよう、真剣に言えば言うほど葉山さんが頑なになる……。
――このままだと訂正出来ないまま授業が始まっちゃう……!
……そんな心配が胸を過ぎった時だった。
「──へぇ、桜太クンにそんなこと言う奴いたの」
「……桑原くん……!」
す、と視界の隅に現れたミニタオルが僕の目尻を覆って、そっと涙を拭う。鮮やかな青色が眩しいそれの持ち主は、いつからそこで見ていたのかスクールバッグを肩に掛けたままの桑原くんだった。
「そのクワバラって奴許せないね、桜太クン」
「……あっ……」
「いや、桑原お前しかいねーから!」
「桑原お前、うちの望月になんてことを」
「は?言ってないし」
茶化しに来る山根くんと海野くんにそう軽く返すと、桑原くんはさりげなくミニタオルを僕に渡しながらこちらを見遣る。
「桜太クンは信じてくれるよね?」
「もちろんっ!」
「良かった。『桑原くんそんなこと言ってたの!?嫌いっ』って言われなくて」
「そっ、そんなこと言うわけないよ!」
「うん、知ってる。さっきも必死に庇ってくれたしね」
「い、いつから見てたの……?」
「ん?葉山が桜太クンの小学校の卒業文集出てきた辺りからかな」
「がっつり最初から……!?」
それならなんで暴言を吐いていたと嘘をつかれた時点で否定に入らなかったのと両肩を揺すって問い質したくなったけど、それをする前に「それよりさぁ」と切り出す桑原くん。
「桜太クン、“お姫様抱っこ”されたかったんならもっと早く言ってくれれば良かったのに」
「えっ、それってどういう──うわぁっ!?」
もしかしてその夢を知られたことで毎日の食事に課せられていた糖質制限が厳しくなる?なんて震えたところで──僕の身体はふわ、と床から離れた。
……桑原くんに抱えられたのだ。
「──お姫様抱っこなんて撮影でもしたことなかったけど、こんな感じなんだね」
「わ、わ……」
「あと葉山、お前来月うちの事務所からCMデビューするらしいじゃん」
「な、なんで桑原がそれ知って……っ」
「清純派で売り出すみたいだけど……そんな奴がこんなことやってて良いの?あ、もちろんスマホで動画撮ってるから──次オレたちに変なことしたらどうなるか分かるでしょ」
「……っ」
「あっ、葉山!」
桑原くんの毅然とした態度に何も言えなくなったらしい葉山さんは大きな音を立ててドアを開けながら教室を出て行って、後を残りの二人の女子が追いかけていく。その間も桑原くんは、涼しい顔をして僕の身体を抱え続けていた。
──まだ高校入学前の体重にすら戻ってないのにこんなに軽々と抱えられるなんてある……!?
「あ、あああの桑原くんっ」
「ん?」
「そ、そろそろ降ろさないと腕とか腰痛めるかもっ」
「あー、気にしないで。オレ結構鍛えてるからこれくらい余裕」
「そうは言っても……、あっ、実は僕、お姫様抱っこは彼氏にやってもらいたくて……!」
「──え」
桑原くんの身体に負担をかけたくない一心で恥を忍んでそう言うけど『じゃあ降りてもらおうかな』とはならず──むしろ胸元にがっちり抱き込まれて閉じ込められるような形になってしまった。
「桜太くん、彼氏いるの?」
「いっ、今はいないけど、いつか出来たらいいなぁって……」
「なんだそういうことか。……オレだったら“そっち”も叶えてあげられるけど」
「……え?」
彼氏はいないと言った途端になぜか少しだけ緩まった腕の中で、一息吐きながら考える。
──“そっち”って、どっちだ。
──彼氏のこと?え、でも。
「桑原くん、好きな人がいるんじゃ……!」
「うん、好きな子いるよ。──選択授業の時に嵌められそうになったオレを助けてくれて、放課後の教室で一人で『痩せたい』ってぼやいてた──いつも一生懸命で可愛い子」
「……!?」
最初に聞いた時よりもずいぶん具体的かつ、身に覚えしかないエピソードに眩暈がしそうだ。 育てちゃいけないと思っていた──叶わないと決めつけていた気持ちが、胸の中でぶわっと花開いていく。
「どうする?オレのこと、彼氏にしてくれる?」
「……あの、僕──」
「──あ、予鈴鳴っちゃった」
未だに僕のことを解放する気のない腕の中で、意を決して答えようと開いた口は、チャイムの音でまた閉じられた。
「もうすぐ先生来るし、続きは別のところで……」
「待て待て待て待て。望月は置いていけ!」
「は?返事聞きたいんだから桜太くんいないと意味ないでしょ」
「おい暫定バカップル、青春するのは放課後になってからだぞー」
当たり前のように僕を連れてサボりに行こうとする桑原くんに、それまで少し離れたところで見守ってくれていた山根くんと海野くんが駆け寄ってくる。
「桑原くん。お返事はちゃんとするから、続きは学校終わってからでも良いかな……?」
「……桜太クンがそう言うなら」
体勢の関係でどうしても上目遣いになってしまうのを恥ずかしく思いながらそうお願いする僕に、桑原くんは何か言いたげにしつつもそっ、と壊れ物を扱うかのように僕を床に降ろしてくれた。
「桜太クン、今日はバイト休みだよね?」
「うん」
「オレも撮影ないから、学校終わったらオレの家来る?」
「いきなり家だなんてふしだらなっ、告白なら校舎裏とかにしときなさいっ!」
「嫌だよお前ら絶対見に来るじゃん」
「当たり前だろ」
「あっ、先生来るよ!」
2人に見られるのは恥ずかしいな、でも好きだと自覚した今いきなり桑原くんの家に行くのも──なんて複雑な気持ちで自分の席に着いたところで、僕のスマホが一回震えてメッセージが来たことを知らせる。……桑原くんからだ。
【放課後、山根と海野にバレないように校舎裏に来て】
教室に入って来た先生にバレないようにそのメッセージを読んで──吹き出しそうになるのを俯いて誤魔化しながら、僕は“OK!”のスタンプを送った。
──その日の放課後、手を繋いで教室へと戻った僕と桑原く──リヒトくんを見るなり、山根くんは「お前らいつの間に!」と叫び、海野くんは「暫定から確定になったわ」と笑っていた。