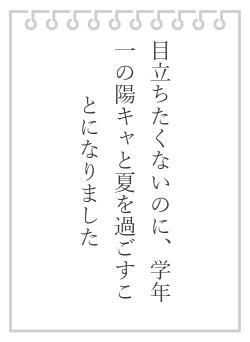澄んだ空に入道雲が浮かんで、アブラゼミがジリジリがなり立てている。
高校二年の寺島輝(てる)は校舎の屋上で柵にもたれて棒アイスを咥えていた。しゃり。青空より少し薄い色をしたソーダ味のアイスは、口内で溶けた瞬間冷たさが広がり、束の間のオアシスを提供する。グラウンドで練習している野球部のノックの快音を背中で聞きながら、入道雲をぼんやり眺める。ゆっくり風に乗って漂う雲に意識をシンクロさせて自分もどこまでも流れていくような感覚に浸っていると、屋上の入り口の扉が開いて一人の男子生徒が現れた。
「・・・輝」
その学生は擦れた声で寺島の名前を呼んだまま俯いてしまった。風が吹いて肩まである銀髪が揺れるが、表情はよく見えない。
「健也?」
様子のおかしいクラスメイトに小首をかしげる。目の前の男子学生——小鳥遊健也は先刻教室にいたときは元気だった。落ち込んだ様子もなく、ただ「屋上に先に行っといてくれ」と言われて笑顔で別れた。それが今小鳥遊は言葉少なく、おそらくしょげている。
「健也? 気分でも悪いのか」寺島は柵にもたれるのを止め、気づかわし気な視線を送る。小鳥遊は声をかけられ小さく身じろぎして、ようやく腹を括ったのか、顔をあげた。
「告白されたってマジ?」
「は?」
予想外の質問に寺島は目を見開いた。聞き間違いかと思ったが、そうではないらしい。小鳥遊の顔は真剣そのものだ。
「なんのこと?」
「とぼけんな。クラスの奴から聞いたぜ。相手は野球部二年のエース相良先輩だって。なあ、本当なのか?」
小鳥遊がぐっと距離を詰めてくる。両手を寺島の頬を添えて寺島の大きめな黒目を覗き込む。まるで真偽を確かめるかのようだ。
「健也、近いって」身じろぎする寺島に対して逃がさないとばかりに小鳥遊は顔を挟む手を添え直す。
「真面目に答えろよ」小鳥遊は切れ長な目が寺島を捉える。その目はまっすぐに寺島の双眸を射抜いている。寺島の視界には青空は映らず、ガタイの良い小鳥遊で埋め尽くされている。白いワイシャツのボタンはすべて開いていて、中から赤いTシャツが覗いている。首筋の玉のような汗が屋上まで走ってきたことを想像させる。
「だとしたら、何だよ」寺島は小鳥遊をジト目で見上げる。
小鳥遊はごくりと息を呑んで訊く。
「受けたのか?」小鳥遊の普段より暗い藤色をした瞳は揺れ、すがるような目で寺島を見下げている。眉は八の字に垂れ下がり、不安げな様子が伝わってくる。
寺島はしばらく小鳥遊の様子を見ていたが、八の字の眉毛がさらに下がっていくのを見て、息をはーっと吐き出し、仕方ないといった風に口を開いた。
「健也の心配するようなことは何もないよ。相良先輩とは何もない。当たり前だろ? オレには健也がいるのに」
聞いたとたん小鳥遊がぶつかるように抱き着いてきた。寺島の背骨が逆に曲る。痛いと訴えるとゆっくりと戻してくれた。
「俺、聞いたとき死ぬかと思った」
「大げさだな。そんなんじゃ人は死なないよ」
「いーや、死ぬね。俺は」小鳥遊は寺島の頭に頬をうりうりと擦り付けながら抗議する。
「だってさ、エースの相良先輩だよ? あの人有名人じゃん。俺なんか叶わないと思うじゃん」
呆れた目をした寺島は反論する。「知名度で恋人を選ばないし。オレのことなんだと思ってるわけ?」
「かわいい俺の輝」
「っ、ふざけてるの?」
文句を言いながらも、寺島はまんざらではなさそうな表情だ。顔を赤らめそっぽを向く寺島を小鳥遊は満足げな顔をして、
「まあ、俺にはさ、輝しかいないから。よろしくな」と言って、親指と人差し指でハートを作って見せてくる。
「何言ってんだよ。お前こそ女子にモテるくせに。二日前だって隣のクラスの女子に告白されてただろ。オレが毎回どんな気持ちか・・・」はーっとため息を再びついた寺島がさらにそっぽを向く。小鳥遊は寺島の顎に手を添えてそっと自分の方を向かせる。
「死にそう?」小鳥遊の悪魔の囁きだ。寺島を覗き込む藤色は仄暗く、口角は挑発的に上がっている。
寺島は慣れた様子で小鳥遊の頬を手で押しのける。
「いや、死にはしないけどモヤモヤはする」
「えー。俺は死にそうなのに」
つれないな、と文句を垂れる小鳥遊に背を向けて、寺島は柵のところにもたせ掛けてある自分の鞄を探る。
「ほら、健也がこの前休んでたときの数学のノート」二年C組寺島輝と書かれたキャンパスノートを差し出す。
「おうサンキュ。久しぶりに風邪ひいて驚いたわ」
「馬鹿は風邪ひかないって言うのにね」
「言うじゃん。マジだけど」
「はは、否定しろよ」と寺島は笑う。
小鳥遊は寺島のノートのページをめくる。「輝、字きれいだよな」
「そう? ふつうだよ」
「いや、見るだけでやる気でるから。理解はできないけど」
「いやしろよ」
「だって三角関数わかんねーんだもん」
「サイン、コサイン、タンジェントをまずは覚えなよ」と寺島は窘める。
小鳥遊は風に遊ぶ銀髪を指で捕まえていじりながらジト目で寺島を見る。「えー無理」
「いやがんばれよ。お前、次の定期テストの成績悪かったら門限六時にされるんだろ? いいの?」
「よくないけど・・・」小鳥遊は唇をとがらせて目をそらす。少し考えるそぶりをみせて何かいい案が思いついたように寺島の方を向いた。
「輝がご褒美くれたらがんばれるかも」
「はあ? 何言ってんだよ」
突飛な案に寺島は訝しがる。そんな寺島の様子とは対照的にニッとする小鳥遊の唇の下から八重歯が覗く。
「いいじゃん。俺のためだと思って。輝だって俺が夜外出られないの嫌だろ? 放課後ファミレス行けなくなるぜ」
寺島はうーんと唸って「いいよ」と返した。寺島たちが屋上を後にする頃には、入道雲は風に吹かれて遠くの方に連れていかれていた。
小鳥遊の家は住宅街の中の一軒家だ。クリーム色の外壁に大きな窓がついて中の白いカーテンが見える。カーテンの内側はリビングになっており、黒色の高級そうなソファーが置かれている。リビング横の階段を登ってすぐ右が小鳥遊の部屋だ。
黒い壁にはバンドのポスターが貼られている。机は四角形の透明な天板に白い足がついていて、今はノートが広げられており、寺島と小鳥遊は問題集とにらめっこ中だ。
「タンジェント、ムズくね」小鳥遊が氷の入った麦茶を手に取り、カランという音がする。
「あー、サインとコサイン合体したみたいなやつね。それは後でいいよ。先にサインとコサイン使えるようになろう。圧倒的に使うから」
「へー。了解です。輝先生」
小鳥遊が問題に取り組んでいる間、寺島は小鳥遊の横顔を盗み見ていた。サララサの銀髪、耳についた重めなシルバーピアス、血色の良い肌、影を落とすまつ毛、ぽってりとした唇。麦茶を飲み干すときに動く喉ぼとけ。たくましい首筋。小鳥遊の特徴は寺島とは対照的だった。寺島は猫毛の黒髪で、ピアスはしておらず、青いくらいに色白で、まつ毛は特徴となるほどは長くなく、唇は薄い。おまけに喉ぼとけも小ぢんまりとしている。筋肉も付きづらい身体だ。
(なにもかもが違うのに惹かれあったなんて不思議だ)
小鳥遊の向かうノートに目をやる。二問目までは解けたようだが、三問目で数式をいくつか書いてシャーペンでバツしている。小鳥遊をみれば眉が下がっている。とうとう小さく唸った。
「詰まった?」
声をかけると小鳥遊は悔しそうな顔をして唸っている。「ヒント出そうか?」助け舟を出すと、小鳥遊は観念したかのように脱力して「頼む」と唇を尖らせた。
「ここにサインをつかって・・・」寺島が解説するのを小鳥遊はふんふんと素直に聞く。わかったらしく、小鳥遊はノートの問三にいくつか数式を書き、正しい答えを得た。寺島は隣でガッツポーズする小鳥遊を見て微笑む。
「健也は地頭がいいよな」
小鳥遊は首をぐるんと寺島の方に向ける。
「マジ? 輝に褒められた」頬が紅色して藤色の目が輝いている。「これはご褒美もらえる?」切れ長の目を細めて、ニッと笑う。
寺島は眉を下げる。寺島は褒美となるものを何も持ち合わせていない。鞄の中には、筆記用具やノート類のみだ。お菓子のひとつも入っていない。食べ終えたアイスの棒がビニール袋に入ってあるだけだ。
恐る恐る尋ねる。「ご褒美って何が欲しいの?」
小鳥遊は笑みを深め、隣にいる寺島にゆっくりと近づく。Tシャツの中が見え、厚い胸板が目に入る。ふわっとシトラスの香りが汗の匂いに交じって飛んでくる。寺島は身体がむずがゆくなる感覚がし、少し身体をそらそうとしたが、小鳥遊が離れるのを許さないとばかりに右腕を掴んできた。ぐいっと引き寄せられ耳元で囁かれる。
「そりゃ決まってるでしょ」小鳥遊のハスキーがかった低音が耳に掠れる。
寺島の口から思わず吐息が漏れる。心拍数が急上昇し、身体がカッと熱くなる。寺島は距離を取ろうと掴まれていない方の手で小鳥遊の胸板を押そうとするが、その力は弱弱しいもので意味をなさなかった。それを良いことに小鳥遊は空いている方の手で寺島の薄い唇を軽くなぞる。反応を示す寺島の黒く潤んだ瞳を覗き込むように見つめる。藤色の双眸は妖しく濡れて光っている。
「俺はこれが欲しいんだけど?」
寺島はそれ以上見つめ合っていられずに視線をそらした。小鳥遊はクスリと笑う。そして催促するように寺島の唇をふにふにと押す。寺島はご褒美をやるまで解放されないのだと悟り、息を鼻で深く吸い込み、「わかった」と返事した。
「一回だけだからな」小鳥遊をジト目で見つめてくぎを刺す。対する小鳥遊は鼻歌を歌いながら、ご褒美を待っている。
寺島は右手を小鳥遊の肩に軽くのせてゆっくり膝歩きで近づく。小鳥遊のぽってりとした唇が目に入る。寺島は左手で胸を押さえてはーっと深呼吸する。
「緊張する?」いたずらに小鳥遊が訊く。
「うるさい」茶々を入れられた寺島はムッとして返す。
そっと唇を合わせる。すぐに退こうとすると小鳥遊が寺島の後頭部に手を添えて引き寄せる。
「ん」
小鳥遊の分厚い唇は熱を帯びており、ぐいぐい押されて、寺島は息が荒くなる。しばらくして解放されたころには寺島は肩で息をしていた。
寺島は熱い視線を送りながら自分の唇を指でなぞっている小鳥遊から目をそらして机の上のノートを見やる。まだ大問が一問しか解かれていない。
「ソーダ味っていいな」小鳥遊はつぶやくように言う。寺島は遅れて意味が分かって頬が赤くなったが、気にしてないふりをする。「まあ、アイス食べたからな」
小鳥遊は畳みかけるように言う。「初恋はレモン味とかいうけど、俺らのはソーダ味だな」
「っ、」
「美味かったぜ、輝」
「ご褒美も済んだし問題続きやるよ」
「えー輝のスパルタ」
「言ってろ」
再び問題集に向かう寺島に続いて、小鳥遊もしぶしぶノートに向かう。
「じゃあ、次の問題はこれね」寺島は問題集を指さす。小鳥遊は問題を眺め顎に手を当てて考えている。小鳥遊の首筋には冷房が効いているにも関わらず汗の玉がうっすら浮かんでいた。寺島は心臓が跳ねるのを感じたが、気づかないふりをした。
次の大問が終わる頃には、また「ご褒美」をねだられて、寺島は下がり眉でご褒美を贈った。
いつのまにか背中が床に着いており、視界は目を閉じた小鳥遊で埋まっている。小鳥遊が動くたび銀髪が頬をくすぐる。
「なあ、輝」小鳥遊から吐息が漏れる。
「相良先輩に告られたとき、ちょっとでも揺れたりした?」前髪の間から覗いている藤色の瞳は不安げだ。
寺島が小鳥遊の胸を強めに押し返すと動きが止まる。
「輝?」
「オレはさ、健也がいいんだよ。来るの待つのも、勉強中にご褒美とか言ってじゃれ合うのも」
「わかってよ」寺島は小鳥遊の頭を引き寄せて唇を合わせる。少し離しては押し付けるのを何度も繰り返す。小鳥遊も応えるように輝の顔に手を添える。
「ごめんな、ちょっと不安になってた」
「いいよ、仕方ないから許してあげる」
カランと麦茶の氷が融ける音がした。
放課のチャイムが鳴る。学生たちはそれぞれ部活動に向かう。小鳥遊は二年の教室へと続く階段を登っていく。見知った姿を見つけて声をかける。
「相良先輩」
声をかけられた相良は戸惑った顔をしている。
「誰かな?」
「寺島輝の彼氏の小鳥遊健也っス。一言いわせてもらいに来ました」
「寺島くんの・・・」
「輝のことは俺が幸せにするんで。きっぱり諦めてください。じゃ失礼します!」
それだけ言うと、小鳥遊は一年の教室に帰っていく。
教室には寺島が一人、机に座って携帯をいじっていた。
「なに調べてんの?」
「新しくできたラーメン屋。駅近の」寺島は小鳥遊に画面を見せる。チャーシューが六枚のったおいしそうなラーメンの写真が映されていた。
「美味そう。今から食いに行こうぜ」
「健也はフットワーク軽いな」
「いいじゃん、行こうぜ」
「はいはい」
小鳥遊は自分の鞄と寺島の鞄をもって教室の入り口まで行く。
「輝、早く!」
「わかったから待ちなよ」
高校二年の寺島輝(てる)は校舎の屋上で柵にもたれて棒アイスを咥えていた。しゃり。青空より少し薄い色をしたソーダ味のアイスは、口内で溶けた瞬間冷たさが広がり、束の間のオアシスを提供する。グラウンドで練習している野球部のノックの快音を背中で聞きながら、入道雲をぼんやり眺める。ゆっくり風に乗って漂う雲に意識をシンクロさせて自分もどこまでも流れていくような感覚に浸っていると、屋上の入り口の扉が開いて一人の男子生徒が現れた。
「・・・輝」
その学生は擦れた声で寺島の名前を呼んだまま俯いてしまった。風が吹いて肩まである銀髪が揺れるが、表情はよく見えない。
「健也?」
様子のおかしいクラスメイトに小首をかしげる。目の前の男子学生——小鳥遊健也は先刻教室にいたときは元気だった。落ち込んだ様子もなく、ただ「屋上に先に行っといてくれ」と言われて笑顔で別れた。それが今小鳥遊は言葉少なく、おそらくしょげている。
「健也? 気分でも悪いのか」寺島は柵にもたれるのを止め、気づかわし気な視線を送る。小鳥遊は声をかけられ小さく身じろぎして、ようやく腹を括ったのか、顔をあげた。
「告白されたってマジ?」
「は?」
予想外の質問に寺島は目を見開いた。聞き間違いかと思ったが、そうではないらしい。小鳥遊の顔は真剣そのものだ。
「なんのこと?」
「とぼけんな。クラスの奴から聞いたぜ。相手は野球部二年のエース相良先輩だって。なあ、本当なのか?」
小鳥遊がぐっと距離を詰めてくる。両手を寺島の頬を添えて寺島の大きめな黒目を覗き込む。まるで真偽を確かめるかのようだ。
「健也、近いって」身じろぎする寺島に対して逃がさないとばかりに小鳥遊は顔を挟む手を添え直す。
「真面目に答えろよ」小鳥遊は切れ長な目が寺島を捉える。その目はまっすぐに寺島の双眸を射抜いている。寺島の視界には青空は映らず、ガタイの良い小鳥遊で埋め尽くされている。白いワイシャツのボタンはすべて開いていて、中から赤いTシャツが覗いている。首筋の玉のような汗が屋上まで走ってきたことを想像させる。
「だとしたら、何だよ」寺島は小鳥遊をジト目で見上げる。
小鳥遊はごくりと息を呑んで訊く。
「受けたのか?」小鳥遊の普段より暗い藤色をした瞳は揺れ、すがるような目で寺島を見下げている。眉は八の字に垂れ下がり、不安げな様子が伝わってくる。
寺島はしばらく小鳥遊の様子を見ていたが、八の字の眉毛がさらに下がっていくのを見て、息をはーっと吐き出し、仕方ないといった風に口を開いた。
「健也の心配するようなことは何もないよ。相良先輩とは何もない。当たり前だろ? オレには健也がいるのに」
聞いたとたん小鳥遊がぶつかるように抱き着いてきた。寺島の背骨が逆に曲る。痛いと訴えるとゆっくりと戻してくれた。
「俺、聞いたとき死ぬかと思った」
「大げさだな。そんなんじゃ人は死なないよ」
「いーや、死ぬね。俺は」小鳥遊は寺島の頭に頬をうりうりと擦り付けながら抗議する。
「だってさ、エースの相良先輩だよ? あの人有名人じゃん。俺なんか叶わないと思うじゃん」
呆れた目をした寺島は反論する。「知名度で恋人を選ばないし。オレのことなんだと思ってるわけ?」
「かわいい俺の輝」
「っ、ふざけてるの?」
文句を言いながらも、寺島はまんざらではなさそうな表情だ。顔を赤らめそっぽを向く寺島を小鳥遊は満足げな顔をして、
「まあ、俺にはさ、輝しかいないから。よろしくな」と言って、親指と人差し指でハートを作って見せてくる。
「何言ってんだよ。お前こそ女子にモテるくせに。二日前だって隣のクラスの女子に告白されてただろ。オレが毎回どんな気持ちか・・・」はーっとため息を再びついた寺島がさらにそっぽを向く。小鳥遊は寺島の顎に手を添えてそっと自分の方を向かせる。
「死にそう?」小鳥遊の悪魔の囁きだ。寺島を覗き込む藤色は仄暗く、口角は挑発的に上がっている。
寺島は慣れた様子で小鳥遊の頬を手で押しのける。
「いや、死にはしないけどモヤモヤはする」
「えー。俺は死にそうなのに」
つれないな、と文句を垂れる小鳥遊に背を向けて、寺島は柵のところにもたせ掛けてある自分の鞄を探る。
「ほら、健也がこの前休んでたときの数学のノート」二年C組寺島輝と書かれたキャンパスノートを差し出す。
「おうサンキュ。久しぶりに風邪ひいて驚いたわ」
「馬鹿は風邪ひかないって言うのにね」
「言うじゃん。マジだけど」
「はは、否定しろよ」と寺島は笑う。
小鳥遊は寺島のノートのページをめくる。「輝、字きれいだよな」
「そう? ふつうだよ」
「いや、見るだけでやる気でるから。理解はできないけど」
「いやしろよ」
「だって三角関数わかんねーんだもん」
「サイン、コサイン、タンジェントをまずは覚えなよ」と寺島は窘める。
小鳥遊は風に遊ぶ銀髪を指で捕まえていじりながらジト目で寺島を見る。「えー無理」
「いやがんばれよ。お前、次の定期テストの成績悪かったら門限六時にされるんだろ? いいの?」
「よくないけど・・・」小鳥遊は唇をとがらせて目をそらす。少し考えるそぶりをみせて何かいい案が思いついたように寺島の方を向いた。
「輝がご褒美くれたらがんばれるかも」
「はあ? 何言ってんだよ」
突飛な案に寺島は訝しがる。そんな寺島の様子とは対照的にニッとする小鳥遊の唇の下から八重歯が覗く。
「いいじゃん。俺のためだと思って。輝だって俺が夜外出られないの嫌だろ? 放課後ファミレス行けなくなるぜ」
寺島はうーんと唸って「いいよ」と返した。寺島たちが屋上を後にする頃には、入道雲は風に吹かれて遠くの方に連れていかれていた。
小鳥遊の家は住宅街の中の一軒家だ。クリーム色の外壁に大きな窓がついて中の白いカーテンが見える。カーテンの内側はリビングになっており、黒色の高級そうなソファーが置かれている。リビング横の階段を登ってすぐ右が小鳥遊の部屋だ。
黒い壁にはバンドのポスターが貼られている。机は四角形の透明な天板に白い足がついていて、今はノートが広げられており、寺島と小鳥遊は問題集とにらめっこ中だ。
「タンジェント、ムズくね」小鳥遊が氷の入った麦茶を手に取り、カランという音がする。
「あー、サインとコサイン合体したみたいなやつね。それは後でいいよ。先にサインとコサイン使えるようになろう。圧倒的に使うから」
「へー。了解です。輝先生」
小鳥遊が問題に取り組んでいる間、寺島は小鳥遊の横顔を盗み見ていた。サララサの銀髪、耳についた重めなシルバーピアス、血色の良い肌、影を落とすまつ毛、ぽってりとした唇。麦茶を飲み干すときに動く喉ぼとけ。たくましい首筋。小鳥遊の特徴は寺島とは対照的だった。寺島は猫毛の黒髪で、ピアスはしておらず、青いくらいに色白で、まつ毛は特徴となるほどは長くなく、唇は薄い。おまけに喉ぼとけも小ぢんまりとしている。筋肉も付きづらい身体だ。
(なにもかもが違うのに惹かれあったなんて不思議だ)
小鳥遊の向かうノートに目をやる。二問目までは解けたようだが、三問目で数式をいくつか書いてシャーペンでバツしている。小鳥遊をみれば眉が下がっている。とうとう小さく唸った。
「詰まった?」
声をかけると小鳥遊は悔しそうな顔をして唸っている。「ヒント出そうか?」助け舟を出すと、小鳥遊は観念したかのように脱力して「頼む」と唇を尖らせた。
「ここにサインをつかって・・・」寺島が解説するのを小鳥遊はふんふんと素直に聞く。わかったらしく、小鳥遊はノートの問三にいくつか数式を書き、正しい答えを得た。寺島は隣でガッツポーズする小鳥遊を見て微笑む。
「健也は地頭がいいよな」
小鳥遊は首をぐるんと寺島の方に向ける。
「マジ? 輝に褒められた」頬が紅色して藤色の目が輝いている。「これはご褒美もらえる?」切れ長の目を細めて、ニッと笑う。
寺島は眉を下げる。寺島は褒美となるものを何も持ち合わせていない。鞄の中には、筆記用具やノート類のみだ。お菓子のひとつも入っていない。食べ終えたアイスの棒がビニール袋に入ってあるだけだ。
恐る恐る尋ねる。「ご褒美って何が欲しいの?」
小鳥遊は笑みを深め、隣にいる寺島にゆっくりと近づく。Tシャツの中が見え、厚い胸板が目に入る。ふわっとシトラスの香りが汗の匂いに交じって飛んでくる。寺島は身体がむずがゆくなる感覚がし、少し身体をそらそうとしたが、小鳥遊が離れるのを許さないとばかりに右腕を掴んできた。ぐいっと引き寄せられ耳元で囁かれる。
「そりゃ決まってるでしょ」小鳥遊のハスキーがかった低音が耳に掠れる。
寺島の口から思わず吐息が漏れる。心拍数が急上昇し、身体がカッと熱くなる。寺島は距離を取ろうと掴まれていない方の手で小鳥遊の胸板を押そうとするが、その力は弱弱しいもので意味をなさなかった。それを良いことに小鳥遊は空いている方の手で寺島の薄い唇を軽くなぞる。反応を示す寺島の黒く潤んだ瞳を覗き込むように見つめる。藤色の双眸は妖しく濡れて光っている。
「俺はこれが欲しいんだけど?」
寺島はそれ以上見つめ合っていられずに視線をそらした。小鳥遊はクスリと笑う。そして催促するように寺島の唇をふにふにと押す。寺島はご褒美をやるまで解放されないのだと悟り、息を鼻で深く吸い込み、「わかった」と返事した。
「一回だけだからな」小鳥遊をジト目で見つめてくぎを刺す。対する小鳥遊は鼻歌を歌いながら、ご褒美を待っている。
寺島は右手を小鳥遊の肩に軽くのせてゆっくり膝歩きで近づく。小鳥遊のぽってりとした唇が目に入る。寺島は左手で胸を押さえてはーっと深呼吸する。
「緊張する?」いたずらに小鳥遊が訊く。
「うるさい」茶々を入れられた寺島はムッとして返す。
そっと唇を合わせる。すぐに退こうとすると小鳥遊が寺島の後頭部に手を添えて引き寄せる。
「ん」
小鳥遊の分厚い唇は熱を帯びており、ぐいぐい押されて、寺島は息が荒くなる。しばらくして解放されたころには寺島は肩で息をしていた。
寺島は熱い視線を送りながら自分の唇を指でなぞっている小鳥遊から目をそらして机の上のノートを見やる。まだ大問が一問しか解かれていない。
「ソーダ味っていいな」小鳥遊はつぶやくように言う。寺島は遅れて意味が分かって頬が赤くなったが、気にしてないふりをする。「まあ、アイス食べたからな」
小鳥遊は畳みかけるように言う。「初恋はレモン味とかいうけど、俺らのはソーダ味だな」
「っ、」
「美味かったぜ、輝」
「ご褒美も済んだし問題続きやるよ」
「えー輝のスパルタ」
「言ってろ」
再び問題集に向かう寺島に続いて、小鳥遊もしぶしぶノートに向かう。
「じゃあ、次の問題はこれね」寺島は問題集を指さす。小鳥遊は問題を眺め顎に手を当てて考えている。小鳥遊の首筋には冷房が効いているにも関わらず汗の玉がうっすら浮かんでいた。寺島は心臓が跳ねるのを感じたが、気づかないふりをした。
次の大問が終わる頃には、また「ご褒美」をねだられて、寺島は下がり眉でご褒美を贈った。
いつのまにか背中が床に着いており、視界は目を閉じた小鳥遊で埋まっている。小鳥遊が動くたび銀髪が頬をくすぐる。
「なあ、輝」小鳥遊から吐息が漏れる。
「相良先輩に告られたとき、ちょっとでも揺れたりした?」前髪の間から覗いている藤色の瞳は不安げだ。
寺島が小鳥遊の胸を強めに押し返すと動きが止まる。
「輝?」
「オレはさ、健也がいいんだよ。来るの待つのも、勉強中にご褒美とか言ってじゃれ合うのも」
「わかってよ」寺島は小鳥遊の頭を引き寄せて唇を合わせる。少し離しては押し付けるのを何度も繰り返す。小鳥遊も応えるように輝の顔に手を添える。
「ごめんな、ちょっと不安になってた」
「いいよ、仕方ないから許してあげる」
カランと麦茶の氷が融ける音がした。
放課のチャイムが鳴る。学生たちはそれぞれ部活動に向かう。小鳥遊は二年の教室へと続く階段を登っていく。見知った姿を見つけて声をかける。
「相良先輩」
声をかけられた相良は戸惑った顔をしている。
「誰かな?」
「寺島輝の彼氏の小鳥遊健也っス。一言いわせてもらいに来ました」
「寺島くんの・・・」
「輝のことは俺が幸せにするんで。きっぱり諦めてください。じゃ失礼します!」
それだけ言うと、小鳥遊は一年の教室に帰っていく。
教室には寺島が一人、机に座って携帯をいじっていた。
「なに調べてんの?」
「新しくできたラーメン屋。駅近の」寺島は小鳥遊に画面を見せる。チャーシューが六枚のったおいしそうなラーメンの写真が映されていた。
「美味そう。今から食いに行こうぜ」
「健也はフットワーク軽いな」
「いいじゃん、行こうぜ」
「はいはい」
小鳥遊は自分の鞄と寺島の鞄をもって教室の入り口まで行く。
「輝、早く!」
「わかったから待ちなよ」