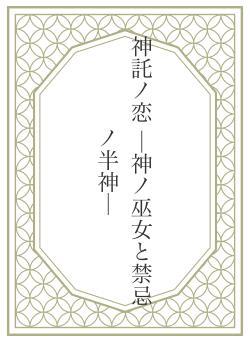あの頃の私は、特別な出会いというものがどこにあって、どんな風に絆を深めて、そしてどうやってそれが終わっていくのか、なんていうことは知らなかった。そして、それが男と女の出会いとなると尚のこと未知であった。
海は不思議なひとだった。
心を逃がしてくれる。海の纏う空気が、凪いだ海のような瞳が、静かに波打つような声が、私の心をここではないどこかに逃がしてくれる。
海といると心が急かない。誰かと同じ空間と時間を共有するのは、ずっと、苦痛なことだと思っていた。
海と話していると私の中で荒れ狂う波が、穏やかに凪いでいくのを感じる。すっと、心にあった何かが溶けて、時間の流れを正しく感じ取れるようになる。私が、私に戻れる。
私の両親はどちらも医者で、優秀な兄は医学部に進学していた。私も医者になることを期待されているのだと、何も言われなくとも肌で感じとっていた。
「やりたいこともなくて、ないなら、医者を目指すしかないのかな。あったとしても許してもらえるかなんて分からないけど」
ある日、そう零した私に海は家族のことを話してくれた。
海の両親は、海に全く興味がないようだった。
寂しくないの?そう言った私に海は遠くを見る目で言った。
「でもそれは裏を返せばしがらみが無いっていうこと。だから俺は自分にとって都合がいい部分だけを利用して生きているんだ。」
大人だと思った。自分の境遇を受けいれ、それをプラスにしようとできる海は、私より遥かに。
海は、私にとって精神安定剤のようだった。
海が特別優しいひと、というわけではないだろう。
ただ、人それぞれに存在する優しさの形のなかで、私は、言葉ではなくてただそっと見守ってくれる海の優しさが心地良かったのだ。
暑い夏の日にかけるエアコンみたいな関係が心地よかった。
だけど、それから海は一人の女性に出会った。
出会ってしまった。
2人は惹かれあっているのだと、直感していた。これが、女の勘というものなのだろうか。
海のことを好きになりたかった。
海を他の誰にも渡したくないという気持ちはあるのに、それが恋ではないことが悔しかった。
恋だったら、繋ぎ止められるのに。
どうして私は海じゃなきゃだめなんだろう。
手を繋ぎたいとか、抱き締めてほしいとか、海を自分のものにしたいとか、そういうんじゃなくて、心の深い部分を共有するだけの関係が心地良かった。
海が誰のものにもならなければいいと思った。彼女のものでも、私のものでも、他の女性のものでもないままに存在していてほしい、と思ってしまった。海はきっと、彼女を好きになる。いや、もう徐々に惹かれ始めているのだと思う。
彼女のことを話す時、海は大好きな写真のことを話す時と同じように、少し熱っぽくなることを私は知っていた。
私を置いていかないでほしい。
私を、置いて、いかないで、ずっと、ここにいて。
海は不思議なひとだった。
心を逃がしてくれる。海の纏う空気が、凪いだ海のような瞳が、静かに波打つような声が、私の心をここではないどこかに逃がしてくれる。
海といると心が急かない。誰かと同じ空間と時間を共有するのは、ずっと、苦痛なことだと思っていた。
海と話していると私の中で荒れ狂う波が、穏やかに凪いでいくのを感じる。すっと、心にあった何かが溶けて、時間の流れを正しく感じ取れるようになる。私が、私に戻れる。
私の両親はどちらも医者で、優秀な兄は医学部に進学していた。私も医者になることを期待されているのだと、何も言われなくとも肌で感じとっていた。
「やりたいこともなくて、ないなら、医者を目指すしかないのかな。あったとしても許してもらえるかなんて分からないけど」
ある日、そう零した私に海は家族のことを話してくれた。
海の両親は、海に全く興味がないようだった。
寂しくないの?そう言った私に海は遠くを見る目で言った。
「でもそれは裏を返せばしがらみが無いっていうこと。だから俺は自分にとって都合がいい部分だけを利用して生きているんだ。」
大人だと思った。自分の境遇を受けいれ、それをプラスにしようとできる海は、私より遥かに。
海は、私にとって精神安定剤のようだった。
海が特別優しいひと、というわけではないだろう。
ただ、人それぞれに存在する優しさの形のなかで、私は、言葉ではなくてただそっと見守ってくれる海の優しさが心地良かったのだ。
暑い夏の日にかけるエアコンみたいな関係が心地よかった。
だけど、それから海は一人の女性に出会った。
出会ってしまった。
2人は惹かれあっているのだと、直感していた。これが、女の勘というものなのだろうか。
海のことを好きになりたかった。
海を他の誰にも渡したくないという気持ちはあるのに、それが恋ではないことが悔しかった。
恋だったら、繋ぎ止められるのに。
どうして私は海じゃなきゃだめなんだろう。
手を繋ぎたいとか、抱き締めてほしいとか、海を自分のものにしたいとか、そういうんじゃなくて、心の深い部分を共有するだけの関係が心地良かった。
海が誰のものにもならなければいいと思った。彼女のものでも、私のものでも、他の女性のものでもないままに存在していてほしい、と思ってしまった。海はきっと、彼女を好きになる。いや、もう徐々に惹かれ始めているのだと思う。
彼女のことを話す時、海は大好きな写真のことを話す時と同じように、少し熱っぽくなることを私は知っていた。
私を置いていかないでほしい。
私を、置いて、いかないで、ずっと、ここにいて。