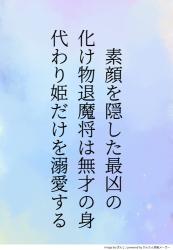ああー……。
今の状況を一言で表すなら、『最悪』だ。
「相良くんに付きあってもらえて助かったよー。わたし一人じゃ、男の子へのプレゼントを選ぶのに不安だったし」
そう。
いま、おれ――相良千秋は、クラスメイトの椎名さんと共に星燐高校近くのショッピングモールを後にして駅に向かっている。
おれは内心のどんよりとした気持ちが顔に出ないように、なんとか愛想笑いをした。
「椎名さんの役に立てたならよかったよ」
「ほんとに助かった! ありがとねっ、相良くん」
この癒される笑みが、おれへの好意から発されたものだったらなぁ……。
数時間前までは、そうかもしれないと期待していたんだけど。今やその期待はガラスのように粉々に砕け散ったというわけだ。
椎名さんは、さっき買った『彼女が好きなひとへのプレゼント』が入った袋を大切そうに抱えながら、溶けそうなほど眩しい笑みを浮かべた。
「じゃあ、また明日、学校でね!」
「うん。またね」
電車通学の椎名さんが改札の向こう側へ吸いこまれていくのを、胸に小さな穴が空いたような気持ちで見送る。もうじき夏がやってくる季節とは思えないほど、肌寒く感じた。さっきの店で冷房に当たりすぎたせいか?
「はあ……」
彼女の華奢な背中が完全に見えなくなったところで、思わず、大きなため息が出た。
さっきまで一緒にいた椎名さんは、クラスメイトの女子だ。そして、おれが異性として気になるひとでもあったのだが……、この通り、たった今ものの見事に失恋した。
おれたちが通っている星燐高校では、四月最初の席順が男女混合の苗字順だ。『しいな』と『さがら』でおれたちは二年生になった一番初めの時期から前後の席だった。
最初、椎名さんはかわいいけど、大人しそうな子だなと思っていた。
でも、たまたま同じ漫画が好きなことがわかって。そこから話が弾むようになって、意識するようになった。
『ねえ、相良くん。その……、バスケ部がない日の放課後に、わたしに付き合ってくれない?』
気になっている子からこんな風に誘われたらさ、思春期の男なんてほぼ全員浮かれるだろ?
今まで彼女がいたことがないおれにも、ついに初めての春がやってくるかもしれない。そんな薔薇色の未来を信じていた。
実際は、本当にただ買い物に付き合ってほしいという意味であり、同時に彼女には他に想い人がいるという残酷な真実がわかっただけだったけど。
「……帰ろ」
あー……。
やっぱりおれは、同年代の女子から見ると『かわいいマスコット』枠で、そういう対象として意識されづらいんだろうか。女子と気さくに話せる性格寄りなのに、今までの人生で告白された経験はゼロというのが物語っているような……。
童顔で中性的な顔立ちも、微妙に170cmに足りていない身長も、全てがコンプレックスに思えてくる。
誰か一人にだけでも、かわいいじゃなくて、かっこいいって思ってもらえたら良いのに。
✳︎
「……ただいま」
「お帰りなさい、千秋」
「は? なんで律がいんの」
気落ちしたまま自分の部屋へ入ったら、なぜか幼馴染の律が居座っていた。
宇佐美律。おれの一つ年下で星燐高校の一年生、軽音部所属。この前の健康診断で身長が169cmだったから悔しい思いをしたおれに対して、律はすでに180cmと長身でモデルのような体型をしている。おまけに、顔も芸能人顔負けの整い方。色白で、すっと通った鼻筋に、切れ長の瞳が印象的な美しい顔だちだ。
うん。
モカブラウン色の髪も超サラサラだし、律は、今日も非の打ちどころのないイケメンだな。
でも、約束もしていないのに、おれの部屋に居座っているのはなんで? ていうか、母さんも律に対してセキュリティ甘過ぎじゃね? どうせこいつの天使の微笑みに簡単に屈したんだろうけど……。おれのプライバシーなんてあったもんじゃない。
「え? 今日、おれと約束とかしてなかったよな?」
「そんなことよりも、千秋。聞きたいことがあります」
おもむろにソファから立ちあがった律が、つかつかとおれの方へ歩み寄ってくる。足の長い律は、何歩か歩いただけで、あっという間におれとの距離を詰めてしまった。後ろは壁、結構な近さで見下ろされる形に。こいつは無駄に顔が良いから妙な迫力がある。
「いや。だから、なんの話?」
「さっき、高校近くのショッピングモールで、女子とデートをしていましたよね?」
「あー……。って、なんでお前が知ってんの⁉」
「話をそらそうとしても無駄です。あの女子は、千秋のなんなんですか?」
「なにって言われても……」
なんでもねえわ! なんなら、さっき失恋したばっかだよ畜生‼
忘れようとしたばかりなのに、傷口へ塩を思いっきり塗りたくられたような気分だ。苦い気持ちが蘇ってきて言葉につまったら、律は、なぜだか切羽詰まったような声を漏らした。
「もしかして……、彼女?」
「違うよ、ただのクラスメイト。……彼女だって言えたら、良かったけどな」
「えっ?」
「だーかーらー、振られたの! 振られたっていうか……、告白すらできなかったっていうか。おれは気になってたけど、向こうは、眼中にもなかったの‼」
自棄になってわめくように叫んだら、律はショックを受けたように瞳を見開いた。
でも、その後すぐに、形の良い唇をヘの字に曲げた。
「なるほど……なんていうか、超フクザツな気分です」
「それはおれの台詞だよ‼ ってか、さっきからお前はなんなの⁉」
「でも、千秋の良さがわからないクソ女なんて、相手にする必要はないですよ」
「は?」
今、いつも丁寧な言葉遣いの律から、黒めの発言がかいま見えたような。
「ねえ、千秋。失恋を忘れるには、新しい恋が効くといいますよね」
「えっ……?」
「あなたの傷心につけこんでも良いですか?」
「いや、なんの話?」
話の流れが全く見えず、素で、首をかしげたら。
律は、その大きな手の平で、おれの片側の頬に恐る恐る触れてきた。
エッ?
つい先日、鮮やかにドラムスティックを操っていたあの手が、まるで壊れ物でも扱うかのような繊細な手つきでおれに触れている。
なにが起こっているのかまるでわからず、戸惑うことしかできない。
「り、律……?」
「僕は、千秋のことが好きです。もちろん、恋愛の意味で」
勘違いしようのないストレートすぎる告白に、心臓がドキリと跳ね上がる。
人生初の告白を、ずっと近くにいた同性の幼馴染から、このタイミングで受けるなんて。
おれしか見えていないというような律の瞳の熱に囚われたようになって、身体が動けない。
「ま、マジで言ってんの?」
「本気も本気です。それも、千秋が想像しているより、ずっと昔から」
「でも、その……。お、おれにとっての律は、幼馴染で……、今までそういう風に考えたことはないっていうか」
「それも知ってる。今は、それで良いですよ」
「そ、そっか」
律はおれの顔から手を放して、一歩下がった。
そして、さびしげに微笑む。
「気持ちに温度差があることは、充分わかっています。でも、さっき千秋が女子と二人きりで遊んでいるところを見て、耐えられそうになかったんだ。千秋が、僕以外の誰かと特別な関係になったりしたら、さびしすぎて死んじゃうかも」
「いやいや冗談でも怖いって!」
「冗談じゃないかもよ? 現に今だって、すぐに話を聴取しなければ気がすまなかったから、ここで千秋を待ちかまえていたんです」
「母さんに気に入られてるからって、簡単にひとの部屋に入りこむな!」
「それは、ごめんなさい。……でも、千秋は彼女と付き合っているのかもしれないと思ったら、いてもたってもいられなくなって」
困って眉尻を下げたおれに、律は、獲物を見定めたかのように瞳を細めた。
「ズルくても、あざとくても、もうなりふり構いません。僕は、千秋に好きになってもらえるように、全力を尽くすことにしました。覚悟していてくださいね?」
✳︎
昨日、クラスメイトの女子に失恋をしたら、年下の美形幼馴染に突然告白をかまされた。
……のだけれども、冷静にあれは現実だったのだろうか? 夢でも見ていたんじゃないか。
だって、相手は、昔からとんでもなくモテる律だぞ。
顔とスタイルが芸能人並みに良い上に、勉強もできて、楽器演奏までできる天が与えすぎのハイスペック男。高校に入学して数か月しか経っていないのに、すでに女の子から告白されるのが日常茶飯事になっているくらいだ。
その人気ぶりの理由は、先日行われた新歓ライブの影響も大きいかもしれない。律が入った軽音部では、毎年、五月中頃に新入生の勧誘を目的とした歓迎ライブを体育館で行う。本来、演奏者としてライブに出れるのは二年生以上なんだけど、たまたまドラムを担当する予定だった先輩が怪我をしてしまったらしく、ピンチヒッターとしてドラム経験者の律が抜擢されたんだって。
おれもそのライブを見にいったんだけど、そのときの律がさ、すげえかっこよかったんだよ。ワイシャツを腕まくりして真剣にドラムを叩く姿が輝いていて、流れる汗にすらも色気があって、思わず目を引きつけられるというか……。これまでも律のドラム演奏を見たことがなかったわけじゃないけど、中学で吹奏楽部の一員として演奏しているのを鑑賞するのとは、違った感動があった。とにかく男のおれでも素直に見惚れてしまったんだから、何人もの女子の心を撃ち抜いたに違いない。
でも、律は、どんな女子に告白されても付き合おうとはしなかった。
誰から告白されてもスマートに振ってしまう律に、おれは、『もったいないなぁ。試しに誰かと付き合ってみても良いのに』と内心では思っていたけど、まさかその理由はおれを好きだったからなのか……? いや、そんなまさかね!
うーんと首をかしげながら、登校するために家を出たら、玄関の前に悩みの種の張本人がスマホを弄びながら立っていた。
「……って、律じゃん! なんでおれの家の前にいんの⁉」
こっちは焦っているというのに、律は、おれを視界にいれた途端にぱあっと顔を輝かせた。
「おはよう、千秋。朝から顔をあわせて一緒に登校だなんて、小学時代を思い出しますね! ふふっ、幸せだなぁ。近くに住んでいるんだし、千秋の朝練さえなければ本当は毎日迎えにきたいくらいです。ついでに抱きしめたいなぁなんて」
「待って! なにもかもがいきなりすぎない⁉」
「僕にとっては、いきなりじゃないですよ。千秋への片想い歴は誰にも負けない自信があります! 昨日告白したことだし、これからは惜しみなく愛を伝えていくスタイルに切り替えようと思って」
「よく恥ずかしげもなく堂々と言えるな……」
「ねえ。千秋もはやく僕のことを好きになって?」
「んー……、とりあえず、早く学校にむかうぞ。遅刻したらやべえし」
「ちぇっ。千秋がツレなーい」
唇を尖らせつつも、隣に並んで歩く律の目元は和らいでいて、なんだかうれしそうだ。
こうして隣に並ぶと頭ひとつ分背が大きくて、おれがすこし見上げる形になるのが悔しい。小学校低学年ぐらいまでは、同じくらいの身長だったのにさ。
「律、ほんとに身長伸びたよな」
「そうですね。千秋はこの前の健康診断で169cmでしたっけ?」
「は? 170cmはあったし!」
「ちなみに僕は180cmでした」
「ケンカ売ってんの?」
てか、なんでおれが身長をひそかに盛ってることまで知ってんの……?
反射的に噛みついたら、律は、なぜか白い頬をうっすらと赤く染めた。
「いえ。ただ、ちょうどいい身長差だなぁと思いまして」
「なんの話?」
首をかしげたら、律はすこしだけ屈んで、おれの耳に唇を寄せた。
そして、吐息を含んだ声で、わざとらしいくらいにゆっくりと言った。
「キスをするのに、です」
……‼
「千秋は知っていましたか? キスをするのにちょうどいい身長差というものがあるんです。僕らの身長差は、ぴったりそれに当てはまっているようですよ?」
耳にすこしだけ触れた律の唇を急に意識してしまって、即座に距離を取った。
な、なんだこれ。心臓バクバクしてるし、顔が熱いんだけど。いや、これは律をそういう意味で好きだからとかそーゆーのじゃなくて、突然こんな不意打ちをくらったら誰だって……!
「律っ。おれをからかうのもいい加減に……!」
しどろもどろになりながら言い返そうとした、そのときだった。
「あっきー、おはよー!」
明るい、聞き慣れた声がして振り向けば、クラスメイトの南優香がおれの隣へ走り寄ってきた。ひょこひょこと揺れるポニーテールが目印の元気女子。
「南じゃん、おはよ」
「通学路でばったり会うのは珍しいねー、いつも体育館の中だもん」
南は、女子バスケ部に入っている。男子バスケ部所属のおれとは、部活動内での交流はないけれど、体育館内でよくすれ違うこともあって喋りやすい女子だ。
一方の律はといえば、南がおれの隣にやってきたとたんに静かになった。さっきまでの軽快な口ぶりが嘘だったかのように。
「あっ。えーと、軽音部のライブでドラムを叩いてた宇佐美くん……だよね? あっきーの知り合いだったんだね」
南が、様子をうかがうように律へと話しかける。後輩だけど、さすがに律のことは知ってたんだな。そりゃ知ってるか、新星イケメンドラマーとして星燐ではほぼ有名人みたいになってるし。
南に話しかけられた律はといえば、愛想よく微笑んだ。
「はい、宇佐美律です。千秋とは、幼稚園時代からの幼馴染なんですよ」
「へぇ〜、幼馴染だったんだ! あっきーってば隅に置けないなぁ、こんなにかっこいい幼馴染がいるなんてさ」
ちょっと待って、その発言は女友達に対して言うやつじゃね?
わかる、わかってるよ。おれって自他ともに認める童顔だし、男っていうよりかはやっぱりマスコットって感じの認識なんだろうな。たぶん、椎名さんの認識もそんな感じだったんだろうね……。やばい、考え出したらまた凹みそう。
ベツに、南は気さくな友だちだし、異性として意識されたいとかじゃないんだけどさ。なんというかこう……、おれは、マスコットってわけじゃないのにって気持ちも心のどこかで拭えないんだよな。
「南さんは、千秋と仲が良いんですね?」
「あー、まーそうだねぇ。あっきーは、バスケ仲間って感じかな」
「なるほど」
すこしの間、黙ったあと。
律はなにを思ったのか、回りこんで南の隣へと移動した。
そして、歩きながら、南の顔を切れ長の瞳で無言のままじいいっと凝視。
「う、宇佐美くん? どうかした?」
その辺の並みの男が同じ行動を取ったら「いきなり隣にやってきて、ジロジロ見るなんてなんのつもり? まじキモい」と即刻陰口祭りの対象になりそうなもんだが、イケメンに限っては違う。
「あ、あの……? あたしの顔、なにかついてるかな?」
な、なんと! どちらかというと普段は男勝りなあの南が、頬をうっすらと赤く染めて乙女モードになっているではないか……! イケメンすげえ。てか、律のやつはなに考えてんだ⁉
南に問いかけられた律は、口角をあげてきれいに微笑んだ。
「突然見つめてしまってすみません。あなたに興味があったもので」
「興味……?」
「南さんには、恋人がいますか?」
「えっ⁉ い、いないですけど……?」
えええええ、律ってばいきなりなに聞いてんのーーー! てか、南も馬鹿正直に答えなくていいよ!
話を止めに入る隙もなく、律はよどみなく続けていく。
「そうですか。気さくでかわいい方なので、てっきり恋人がいらっしゃるのかなぁと思っていました」
「か、かわっ⁉」
「はい。そんなに驚くことですか?」
「か、かわいい……」
ダメだ。南は律の発言に衝撃を受けすぎて、まともに話が聞こえていない。
「そうだ。連絡先を聞いても良いですか?」
「へっ!」
「南さんにお聞きしたいことがあって。良かったらという感じです」
「も、もちろん! これ、あたしのIDですっ」
「わあ、ありがとうございます」
おれにとっては異性に連絡先を聞くだなんてまぁまぁなイベントなのに、律は事もなくわずか数分間で終えてしまった。
校門を抜けて、もうすぐ校舎につきそうというところで、南はいったん別れを切り出した。
「じゃ、じゃあ。あたしは、ちょっと部室に取りに行くものがあるので、これでっ!」
南の奴、いつもハキハキ喋るのに、つっかえてるし……。
動揺したまま、いかにもコイスルオトメな雰囲気で、顔を赤く染めながら去って行ったのだった。
…………。
「なあ、律」
「ん? なぁに、千秋」
「……あれはどーゆー意味だよ」
「あー……。あれは、魔除けのようなものですよ」
「は?」
「あっ、勘違いしないでくださいね⁉ 僕は千秋一筋ですよ! 千秋のことしか見えていませんからっ」
「……いや、そこは聞いてねえんだけど」
急に取り乱すなよ。
おれしか見えてねえとか言われても、反応に困るじゃん。
「大丈夫。千秋は気にしなくて良いことです」
律はニコニコと、腹の底になにか隠していそうな笑顔を浮かべた。
おれのクラスメイトにいきなりやばめの絡み方をしておいて、おれは知らなくて良いってなんなんだよ……。
若干モヤモヤとした気持ちを抱えたまま、校舎の中に入っていく。
「じゃ、おれは下駄箱こっちだから」
「まさかここでバイバイですか⁉ 嫌ですっ。ギリギリまで一緒にいたい!」
「はいはい、わかったよ」
といわれても、一年生の教室は三階で、おれら二年生の教室は二階だから、どちらにせよすぐ離れることにはなるけど。
反論するのも面倒になってうなずけば、律は上機嫌で、自分の下駄箱に上履きを取りに向かった。
「宇佐美くん、おはよぉ。あは、今日もイケメンだねぇ」
「おはようございます。このやりとり何度目です?」
すこし目を離した隙に、だいぶ明るい髪色の同級生っぽい女子に絡まれてるし。
「だって、何度でも思うんだもん。ねね、昨日話した動画は見てくれた?」
「いや……。僕、ひとを待たせているので先に行きますね」
律はわずらわしそうに女子から離れると、階段前の廊下で律を待っていたおれの方へと突進してきた。
「べつに、おれに気ぃ遣わなくても良かったのに」
「気って? なんの話ですか」
「話しかけられてたギャルっぽい子、クラスメイトとかじゃないの? 同じ階だろうし、教室まで一緒に行けば良かったのに」
何気ない気持ちで口にしたら、律はムッと唇を尖らせた。
「どうしてわからないんですか?」
「なにが?」
「僕が、千秋と一秒でも長く一緒にいたいってこと。ほんとは、学年が違うことすらも憎いと思っているんですよ? それなのに、千秋の方は、僕のことなんてどうでもいいって感じなのがムカつく」
心臓がドキッと飛び跳ねた。
一瞬間、教室へ向かう生徒たちからの視線が頭から抜け落ちて、どうしようもないわがままを言う目の前の律だけに脳が支配される。
やべえ。顔、また熱くなってるような気がする。
なんで、お前は、おれなんかにそんな必死なんだよ。
……しかも、めちゃくちゃな言い分だし。
おれの無言をどう受け取ったのか、律は、なぜかしょんぼりとした顔をした。
「……ごめんなさい。これじゃ、ただの駄々っ子ですね」
「わ、わかってるじゃん」
「一日でも早く千秋に好きになってもらいたくて、焦っちゃいました」
だから、誰が聞いてるかもわからない場所で、そーゆー危ない発言をするなって!
階段をのぼって、「じゃあおれはこっちだから」と別れようとしたところで、律に制服の裾ををつかまれた。
「待って、千秋。今度、バスケ部がオフの休日はいつですか?」
「ん? あー、たしか今週の日曜はオフだった気がする」
「わかりました。じゃあ、僕と出かけましょう!」
「強引だな!」
「いいでしょう? 退屈にはさせないからお願い! お願いお願いお願いですっ!」
「んー……。わかったよ」
うちでダラダラしててもつまんねえし。そういえば最近はバスケ部が忙しくて、律とゆっくり過ごしていなかったから。
悪くない案だと思って素直にうなずけば、律は満面の笑みを浮かべた。
「最高のデートにしましょうね!」
えっ……? デート…………⁉
✳︎
去り際のあいつの爆弾発言が頭の隅に引っかかったまま、問題のその日はやってきた。
今日は、律曰く『デート』らしいけど……。
ベツに今までだって、二人で出かけたことがなかったわけじゃない。小学時代なんて、毎日のようにお互いの家を行き来して遊んでいた仲だし。中学に入ってからは、互いの部活動が忙しくなって、さすがに毎日は会わなくなったけど。
だからきっと今日も、意識しすぎなければ大丈夫なはずだ。
いや、大丈夫って……なにが?
自分のよくわからない思考回路に首をかしげながら、待ち合わせ場所として指定された、駅の改札前に到着すれば。
長い足を軽く組みながら、スマホを弄んでいるだけで絵になってしまう律がすでに着いていた。
その美しさは、無表情だとすこし近寄りがたいほどで。本人は気づいていないけど、これでもかというほど駅構内を歩く人々の注目を集めている。
ちょっと話しかけにいきづらいけど、まぁ、これもいつものことだから。
「待たせたな」
「千秋‼ おはようございます!」
律は、おれの姿を認識するなり、ぱあっと花開くように笑った。
今日も完璧なイケメンぶりだ。黒いTシャツにスキニージーンズというごくシンプルな格好なのに、スタイルの良さが際立っていてモデルみたい。
律はニコニコとおれを見つめてきたかと思えば、頬をうっすらと赤く染めた。
「千秋の私服姿、久しぶりに見たけれどやっぱり素敵ですね……。パーカー、とても似合っています」
「素敵……かなあ? とりあえずって感じで、無難に選んだだけなんだけど」
シンプルイズベスト極めつつ超絶かっけえお前になに褒められても嫌味にしか聞こえねえよ、という本音は腹の中に沈めておく。
嫌味を言う気にもなれないほど、律が幸せそうなオーラを振りまいているから。なんだかこっちの調子も狂ってくる。
「なあ。互いの家までほぼ五分なのに、わざわざ駅で待ち合わせする必要あった?」
ちなみに、相良家と宇佐美家は徒歩で約五分ほどだ。
「もちろんです。こうして家からすこし離れた場所で待ち合わせをしたほうが、本格的にデートっぽいでしょ?」
「デ、デートデートって、ただ一緒に出かけるだけだろ?」
「違います、今日は誰がなんと言おうとデートです。はっ! もしかして千秋は、恋人にはお家まで迎えに来てほしい派でしたか⁉ たしかにそれも捨てがたいし、一秒でも早く千秋の愛らしいお顔を拝めるというメリットが……」
「あー、いや……。もうこの話はいいや」
どさくさにまぎれて恋人って言ったな、こいつ。
さすがに冗談にしてはしつこいというか、気合いが入りすぎ……なような気も。
もしかして、本当に本気で、おれのことを昔から?
そういう意味での、特別な『好き』……?
ダメだ。いま考え始めたら、恥ずかしくなって逃げ出したくなりそうな気がする。出かけるどころじゃなくなるわ、思考をそらそう。
「早くしないと、上映時間に間に合わないぞ」
「ですね。行きましょう」
今日のメインイベントは、映画を観ること。
それから、映画館が入っている商業施設内で、昼飯を一緒に食う予定になっている。
駅直結の商業施設に入ったとき、つい数日前は、椎名さんと一緒にこの場所を訪れたことが頭によぎった。
彼女の好きなひとへのプレゼント選びに付き合わされることになった、苦いレモンのような記憶。蒸し暑い外気と、冷房の効いた店内との急な温度差のせいか、軽く寒気がした。
「うわっ」
「千秋」
すれ違ったひとにぶつかりそうになったところを、律に腕を引かれたことで、なんとかセーフ。
律は、おれの腕を引き寄せた手を、そのままおれの手へと滑らせた。そして、手の甲同士を、軽く触れさせる。
律の熱が直に伝わってきて、さっきまで感じていた寒気はすぐに消えてなくなった。
「手をつないでも良いですか?」
「えっ。で、でもっ! 誰が見てるかわかんねえし、高校のやつとすれ違うかも……」
「誰も周囲の他人のことはそれほど気にしていませんよ。それに、こうでもしないと千秋は、僕と一緒にいるのに他のくだらないことを考えるでしょ?」
ハッとして律の顔を見上げたら、切れ長の瞳とバッチリ視線が交差した。
淋しそうな、それでいてどこか危うげな熱を孕んでいるようにも見えて、胸の内がドキドキとしてくる。
「早く、僕に堕ちてきて。他のことなんてどうでも良くなるくらい、千秋だけを甘やかすから」
「っ」
頬がライターで灯されたみたいに、カッと熱くなった。
でも、すぐに我に返る。
「い、いまは、急がないとだって! 映画、まにあわない、からっ」
「ふふっ」
「なにがおかしいんだよ!」
「頬、赤くなってます。意識してくれたの?」
「う、うるさいっ‼」
くつくつと楽しそうに笑う律は、まるで小悪魔のようだ。ちゃっかりおれの手を繋いで、離してないし。
このまま、こいつのペースに流されていたら、まずい気がする。チョコレートみたいに心がドロドロに溶けて、ベツのなにかに変わってしまいそうな危ない予感。
エレベーターで七階まで上がって映画館に着くと、甘いキャラメルの匂いが鼻に広がった。販売されているキャラメルポップコーンの香りだろう。この空気感、映画館にやって来たって感じがして、おれは好き。
休日なのでそれなりに混雑していたけど、あらかじめチケットを買っておいて良かった。QRコードをかざして、目的のシアターへと向かう。
ちなみに、今日観る映画は、おれの指定だ。
いま話題になっている、『天使のきみがいなくなっても』。
青春系の切ないアニメ映画だ。
律が『映画が観たい! 観る映画は、千秋が決めてください』と言ってきたので、話題になっているし、クラスメイトが面白いと言っていたのを決め手とした。律は『あー……まあ、千秋が観たいなら良いけど』というちょっと微妙そうな反応だったけど。それなら別の映画にするかと聞いたら、そのままで良いということだった。
おれたちが指定の席に着くと、すでにほかの映画の宣伝タイムが始まっていた。
そのまま映画が始まり、すぐに、物語の世界へ吸いこまれていったんだ。
*
映画、おれ的には、めちゃくちゃ良かった……!
あとちょっと涙腺を刺激されたら泣きそうなくらい、グッときた!
心臓病を患っていることで余命宣告を受けた高校生の女の子の前に、自分のことを天使だと名乗る不審な男が現れるところから始まる物語。
普通の状態だったら絶対に関わりたくないタイプの怪しい男だけれども、何もかもが投げやりになってしまった主人公は彼がなにかと絡んでくるのを受け入れる。
彼女が、彼に淡い恋心のようなものを抱いたところで、天使の彼が半透明に消えかかっていた。
実は、彼の本当の正体は、未来からタイムリープをしてやってきた将来の主人公のドナーだったことが判明して……二人は最初から結ばれるわけがない関係だったという怒涛の展開で!
クライマックスシーンでは、映画館内にすすり泣く声が広がっていた。
エンドロールが終わったので、切ない余韻に浸りながら、隣に座っている律の様子をうかがった。
「律。……映画、どーだった?」
声をかけたら、律は肩をびくりと跳ね上げた。
お化けにでも声をかけられたかのように大げさに驚いて、自分の顔を手で覆ってしまう。
まるで、おれに見られるのを、嫌がっているかのように。
「律?」
「……み、見ないで」
その頼りない声は、聞き漏らしてしまいそうなほどか細くて。
掠れた声で、おれの視線から逃れるように、意味もなくからだを逸らそうとする。
「……いま、目、真っ赤になってるから、ダメです。見られるの、恥ずかしい」
は?
えっ、なに。もしかして、映画に感動しすぎて目真っ赤になるほど泣いちゃった、ってこと……?
予想外の律の反応にちょっと呆けたあと、自然と口元がニンマリしてしまった。おれも、映画に集中してて、観てる間はぜんぜん隣の様子まで気がつかなかった。
なんだよ、それ。
「かわいい、じゃん」
口にしてから、『おれ、なに言ってんだ?』とすぐに思った。
明確な意思をもって言おうとしたんじゃなくて、気持ちがそのまま口からこぼれ出てしまったみたい。
「は? 千秋、なにを言って」
目の前で、必死に目元を覆いながらもボロボロ泣いていることを全く隠せていない律が、なんだかとても愛おしい。
「ちょっといけ好かねえほどかっこよく成長しちゃったと思ってたけど、昔の、かわいい律のままのところもあるんじゃん」
「……昔のことは、忘れてくれていいのに」
「なんで?」
「だってっ……みっともないし。情けないから」
目の前の律と、幼稚園児で泣き虫だった頃のかわいい律とが、重なって見える。
胸の奥にしまわれていた懐かしい気持ちが蘇り、おれは、導かれるように律の頭を撫でた。
昔は、よくこうして、泣いている律を慰めたんだよな。
「たしかに、律は昔から、よく泣く子だったな」
律と初めて知り合ったのは、もう十数年も前になる。
幼稚園児だった頃、お互いの家から一番近い公園で遊んでいたときが初対面。
おれは公園中を駆け回って遊ぶやんちゃ坊主で、律は砂場でぽつんと砂団子を作っているタイプだった。
律は、昔から、きれいな顔をしていたんだよ。
おれは、天使みたいにきれいな子が砂場で遊んでいるなぁと、最初のうちは遠くからぼうっと見惚れていた記憶がある。
すこし経ってから勇気をもって話しかけて、一緒に遊ぶようになったんだ。家も近かったから、仲良くなってからはしょっちゅうお互いの家を行き来していた。
「……公園で転んだり、一生懸命作っていた砂の城が壊れたり、些細なくだらないことで昔からよく泣いてましたね。あれからすこしは大人になって成長したかと思ってたけど、今でも結局、フィクションの映画でぼろ泣きとか……恥ずかしい」
律は自嘲気味に笑った。
でもおれは、疑問に思って、首をかしげた。
「なんで卑下してんの? 泣くのは、ベツに悪いことじゃないだろ。涙もろいかどうかは、心の内の感情が、表に出やすいかどうかってだけなんだろうし。それにさ、お前はただでさえ完ぺき寄りの人間なんだから、そのぐらいのほうが可愛げがあって良いんだよ」
律が、ようやく自分の顔から手をはずして、おれの様子を恐る恐るうかがう。
泣き腫らしたおかげで、切れ長の瞳が赤くなっていた。
「ふふっ。うさぎみたいだな」
思わずこぼれ出た笑みに、律は、おれを見つめながらぽつりと言った。
「千秋は、やっぱりズルいです」
「なんでだよ」
「……あなたは昔から、いざってときに、かっこよすぎるんですよ」
えっ。
今度は、聞き返すこともできなかった。
たしかめてしまったら、なんだか胸の鼓動が、鳴りやまなくなりそうで。
なぁ。今お前、おれのことを『かっこいい』って、そう言った?
*
映画館を出て、律と一緒に、同じ商業施設内のファストフードショップに入った。
「律、一セットだけで足りるか? バンズ一個とポテトだけじゃ足りなくね?」
「はい、これで大丈夫です。そーゆー千秋は、三つもバンズを頼んで大丈夫ですか?」
「おう。食べ盛りの男子高校生だからな!」
「ふふっ」
「……ちっちゃいくせにって思ってる?」
「ご想像にお任せします」
クソ! 子どもを見守る親のような微笑みが腹立つ。
二人掛けの席に向かいあって座りながら、頼んだ料理を頬張っていく。
「……天きみ、良かったよなぁ」
「千秋が指定してこなかったら、絶対、観に行こうとは思いませんでした」
「あー、やっぱり?」
「気づいてたんですか?」
「うん。お前、ちょい微妙そうな反応してたしな。まあ、変えてくれとは言われなかったら追求はしなかったけど。でも、なんで渋ってたんだよ?」
「……もう、わかってるようなものでしょ」
いじけたようにおれを見つめてくる律を見て、ようやく当初の思惑に気がついた。
「あー! 感動系の映画を一緒に観たら、絶対ボロ泣きするってわかってたからだ!」
「もうこの話は終わりにしてくださいっ!」
「えー、今さらおれには隠さなくて良いのに」
「ごぼっ……い、いきなり、彼氏感出してくるのもやめてください。ときめきすぎるから」
「出してねえわ! でもさ、冗談抜きで、良い映画だっただろ?」
「はい。話の内容はもちろんですけど、挿入曲もすごく素敵でしたね! ベースラインが映えるかっこいい曲で、ノリノリになっちゃっいました」
「へえ。感想もバンドマンっぽいな」
「からかわないでください」
頼んだものをぜんぶ食べ終わり、話題も尽きてきたタイミングで、頭の隅に引っかかっていたあの発言の真意を確認するかどうかで悩んだ。
『……あなたは昔から、いざってときに、かっこよすぎるんですよ』
なぁ。さっき言ってたあれって、どういう意味?
「千秋?」
ついさっきまで、いくらでも流暢に動いていた口が急に重たくなる。
どうして? たった一言、軽く確認すれば良いだけだろ。
こんなに緊張しながら、聞くようなことでもないのに。なぜだか、聞いてしまったらあとに引けない予感が胸を叩いている。
でも、気になって仕方ないから。
「あ、あの……。さっきの」
「あれ? 相良くん」
勇気を絞り出して、聞こうとしたその瞬間だった。
トレイを手に持って空いている席を探している、椎名さんと遭遇したのは。
「椎名さん……」
「友だち? あたし、先にそっちの席についてるね」
「あっ、うん」
立ち止まった椎名さんを見て、彼女と一緒にいた友人らしき女子は、気を遣って先に行ってしまった。
「こんなところで休日に会うなんて偶然だね」
「うん」
椎名さんは、ちらりと律の方へ視線をやった。
自分が現れたことで無言にならざるをえなくなった律に悪いと思ったのか、軽く頭を下げる。
「すみません、会話の邪魔をしちゃったみたいで。相良くん。あらためてになるけど、この前はありがとうね。また学校で」
友人を追いかけて椎名さんが去っていくと、やっと時間が動き出したというように、律が小さく息を吐いた。
「混んできたみたいだし、そろそろ店を出ましょうか」
「そーだな」
連れだって席を立ち、ゴミとトレイを片付けて、店を出る。
突然の椎名さんの登場で、会話の糸口を見失ってしまったみたいに、無言が続いていた。事前に立てていた予定は全部こなしてしまって、この後、どうするかも決めていない。
律、ぜんぜん、椎名さんのこと聞いてこないな。
先日おれが失恋した相手だって、気がついていてもおかしくないのに。
制服姿でない椎名さんを見るのはさっきのが初めてで新鮮だったのに、彼女がどんな格好をしていたか、もう記憶がボヤケ始めている。
そのくらい、隣を歩く律が、今なにを考えているのかの方が気になって。
「なぁ、律」
「うん?」
「これから、どーする?」
「あー……。実は、そろそろ、学校に向かわないといけない時間なんです。さきに言っておけば良かったですね」
「学校? 休みなのに?」
「軽音部の練習です」
「なるほど」
もっと、一緒にいたかったなぁ。
……あれ? おれ、今なにを考えて。
二人一緒に駅の方まで戻ってきた。学校方面へと向かう律とはここで解散だ。
午前中に待ち合わせをしてからずっと一緒にいたのに、いざとなると離れ難いような、さびしい気持ちになって。思わず、律の顔をじっと見つめてしまった。今さらだけど、ほんとにきれいな顔してる。
「千秋?」
「今日は、ありがとな。すげえ楽しかった」
「ほんとに? 僕もです! 今日、またさらに千秋のことを好きになりました」
不意打ちの『好き』に、心臓がドキリと飛び跳ねた。
もう、冗談じゃないかって誤魔化せない。
いや、おれが、誤魔化したくないのかもしれない。
だって、すごく恥ずかしいのに、やさしい瞳をしておれだけを見つめてくる律から視線をそらせない。
「なぁ、律」
「うん?」
「……おれの、どこがそんなに好きなの?」
震える声で、顔をすこし熱くしながら尋ねた。
だってこんな質問、明らかに、律を意識していると見透かされそうで。
でも、椎名さんへ失恋したことが、どうでもよくなりつつある自分がいる。さっきあまり話せなかったことも、全く気にならない。
今のおれが気になっているのは……、目の前のこいつの真意だけ。
律は瞳を大きく見ひらいてきょとんとした後、ふわりと笑った。
「そんなの決まってるじゃないですか。かっこいいところですよ」
息が、止まりそうになる。
「恋に落ちたきっかけは、昔から泣き虫だった僕を、千秋がありのまま認めてくれたからです。僕は、しょうもないことですぐ泣いてしまう自分が嫌いだったけど、千秋はそんな僕を『変えようとしなくて良いじゃん。うさぎみたいでかわいいし、おれは好きだよ』って慰めてくれました。頭を撫でながらあんな風に優しく寄り添われたら、性別関係なく、誰だって恋に落ちると思います」
「そ、それって……、小学校低学年のころとかの話?」
たしかに、昔もそんな話をしたな。
そのときのことは、鮮明に覚えてる。
でも、律があれからずっと、おれのことをそんな風に想っていたなんて。
顔が熱くて仕方がない。思考が溶けてきて、心臓が早鐘を打つ。
「僕は、千秋の言葉に救われました。そんなに考えてはいなさそうだったけど、自然とそう言えてしまうあなたが、すごく魅力的だったんです。それにね、千秋がバスケをしている姿も、かっこよくて大好き。あと、毎日誰よりも早起きをして、朝練に向かう努力家なところも」
「なんでお前が朝練のことまで知ってんの⁉」
「千秋のことはなんでも知りたいから、同じクラスのバスケ部のひとに聞きました。あと、千秋の好きなところは――」
「す、ストップストップストップっ‼」
「なんで。千秋の方から言えっていったのに」
「だ、だって……」
たぶん今のおれ、耳まで真っ赤だ。
ダメだ。律は本気で昔からおれのことを好きで、しかもその理由が『かっこいいと思ってるから』だなんて。
そう思って律のここ最近の言動を思い返すと、胸がいっぱいいっぱいになって、顔をまともに直視できない。
不自然に黙っているおれを見つめながら、律は微笑んだ。
「じゃあ、そろそろ時間なので行きますね。またね、千秋」
一人で自分の家へと帰る間中、頭を飛び交っていたのは、今日の半日でいろんな表情を見せた律のことばかりだ。
朝、待ち合わせ場所に到着したおれを見て、うれしそうにしていたあいつ。
映画を観終わったあと、目を真っ赤にして泣いていたあいつ。
そして……、おれを好きな理由を、瞳を輝かせながら夢中で語るあいつ。
「はあ」
こんなにもぐるぐると考えこんで、あいつのことしか頭に浮かんでこないのは重症だ。
途中、つい先日まで気になっていたはずの女の子にまで、すれ違ったのに。律のことしか考えられない。
もう、認めざるをえないかもしれない。性別とかは、きっと些細な問題だ。
おれも、律のことが――。
*
「なんか今日の千秋、調子悪くね?」
「……わ、わりぃ」
やばい。
バスケ部の練習でこんな凡ミスは滅多にしねえのに、今日のおれは、部員にそう指摘されても仕方がないほどのポンコツだ。さっきから何度もシュートをミスってる。
「おれ、水分なくなったから、ちょっと買ってくるわ」
「はいよ」
休憩時間に体育館を出ると、蒸し暑い空気に身体が包まれた。
律と二人で映画に出かけたあの日から、もうすぐ一週間近くも経つ。
意外なことに、その次の日から、律はなんのアクションも仕掛けてこなかった。
さすがのあいつも、おれの朝練の時間にあわせて家の前で待ち伏せしているようなことはなかったし、同じ学校に通ってるとはいえ、学年が違うからすれ違うことすら滅多にない。
連絡も、あれ以来、一回もきてないし。
なんでおれは、あいつから連絡がきていないことを、気にしているんだろう。
いや、もうそんなのわかってる。
この一週間、会っていない間に、おれの頭の中はずっと律に占拠されていた。
バスケに集中している間以外は、ふとした瞬間に、あいつの笑顔を思い出してしまう。
教室で椎名さんと顔を合わせても、自然な気持ちで、彼女の恋を応援できている自分いる。
二人で一緒に出かけたときに何度も揺れた心は、勘違いじゃなかったって確信してしまった。
早く、もう一度、会いたいな。
それで、おれも律が好きだって、伝えにいきたい。
自分で自分の考えに顔を熱くしながら、校舎の自販機がある場所に向かって進もうとしたそのときだった。
「宇佐美くん。好き」
……⁉
曲がった先は、ちょうど軽音部の部室の目の前で。
おれは、見てしまった。
律が、知らない女子に、制服のネクタイを引っぱられてキスされている瞬間を。
「っ⁉」
キスをされた律の大きく見開かれた瞳と、ばっちり目があって。
一瞬間、時が止まったかのように感じられた。
エッ。
律が、女子に、キスされてる……? しかも、結構な美人っぽい女子に。
頭の中で状況をはっきりと認識した瞬間、おれは、全速力でその場を逃げ出した。
は……?
なに。なんなの。なんなんだよ、あれ……‼
到底、体育館に戻る気になんてなれなかった。
だって、よくわかんねえけど、涙が止まらない。壊れたダムみたいに、ボロボロとあふれてくる。
顔も、心の中も、どうしようもないくらいにぐちゃぐちゃだ。
今までに感じたことのない、どす黒い焔に焼かれたような気持ちでいっぱいで、胸がたまらなく苦しい。
「律のバカっっ‼」
誰も使っていない空き教室に逃げこんで、膝を抱えながらうずくまった。
胸の中だけにとどめてはおけなくて、悪態がつらつらと口から出てしまう。
「バカ、バカ。なんで、女にキスなんかされてんだよ‼ あんなに散々おれに好きだとか言ってきて……、おれの頭は、もうお前でいっぱいなのに。当のお前は、おれなんて色目を使ううちの一人で、結局どうでも良いってことかよ‼」
自分で、自分の言葉に、深く心が傷つく。
こんな気持ちは、知らない。
椎名さんに失恋したときよりもはるかに深い胸の痛みに、涙が一向に止まる気配がなくて。もう部活の休憩時間が終わるってわかっていても、動く気になれなかった。
「千秋‼ やっと見つけたっ」
なんで、追ってくるんだよ。
顔を上げなくても、その声だけで、律が追ってきたのだとわかってしまう。
ついさっきまで、今すぐにでも会いたかったのに。
今は、すこしでも、遠ざけたい。会話をするなんてもってのほかだ。
あえて顔を上げずに、地獄から這いのぼってきたかのような低い声で、牽制する。
「……来るな」
「いやです」
「……おい。おれに、それ以上近寄るな」
「いやだと言っているでしょ! どれだけ心配したと思ってるんですかっ」
はあ? おれのメンタルを失墜させた当のお前が心配とか言うのかよ。そんな権利、一ミリもないくせに!
「っ。お前の顔なんて、見たくねえんだよ。さっきの女子のところに帰れ、バカ律」
ヤケになって、叫んだら。
次の瞬間、律に、身体をふわりと抱きしめられていた。
こんな状況でも、意識している奴からそんな風に触れられたら、胸がドキッとしてしまうし、顔が熱くなってしまう。
「な、なに勝手に触ってんだよ! 離せっ」
「さっきのことは、何度でも謝ります。でも、千秋はたぶん誤解してる」
「謝る? なにを? お前は、おれに謝るようなことをしたのか? おれの気持ちを弄んでたこと?」
どす黒い気持ちが止まらなくなって、言いたいことを全部、投げつければ。
律は、頬をふくらませて、本気で怒ってきた。
「なんで、そんなにわからずやなんですか⁉ 良いですか、僕はさっきの女子とは初めて喋りました。ライブを見て僕に好意を持ったそうだけど、付き合うことはできないって言った直後に、あのおぞましい行動をいきなり取ってきたんですっ。しかも、よりにもよってその場面を、愛しの千秋に見られた‼ わかりますか? 僕は完全に被害者ですよ⁉ そんなこともわからずいじけているなんて、バカは千秋の方です‼」
一気にまくしたてられて、ビックリした。
こんなにも本気で怒っている律を見るのは、初めてかもしれない。
「……悪い」
こいつは、とにかくモテる。すこし冷静になって考えてみれば、その可能性にも気がつけたかもしれない。
律は、嘘は吐いていないだろう。現に、おれを心配して即座に追いかけてきたわけだし、あの女子は、律にとって本当に災難みたいなものだったのかも。
あれ。
もしかしておかしいのは、律と女子がキスしているのを目撃した瞬間に、ありえないほど嫉妬して悪い妄想をふくらませたおれのほう……?
急に、悪態をつきまくってしまったことも、律に抱きしめられていることも恥ずかしくなって、うつむいた。
「バカって言って、悪かった。おれ……、そろそろ、部活に戻るわ」
「それ、本気で言ってますか?」
「えっ。だ、だって、もうとっくに休憩時間終わってるしっ」
おれを抱きしめる律の腕に、力がこもる。
まるで、行くなと言うみたいに。
「ねえ、千秋。そろそろ素直になって」
請うように告げられて、いやがおうにも胸が高鳴る。
「どうして千秋は、泣いているの?」
のぞきこんでくる律の瞳の熱に、思考がチョコレートみたいにどろどろに溶けていく。
もうダメだ。
こんな醜態までさらしておいて、今さら、この気持ちを隠せるわけがない。
「……嫉妬、したんだ」
「うん」
「……律が、おれ以外の誰かとキスをしていたのが、すごく、いやで」
最後まで、言葉を紡ぐことができなかった。
律に、唇を奪われていたから。
「っ」
触れるだけの一瞬のキスだったけど、すごく、胸がドキドキとして心が満たされた。
「嫌じゃなかった?」
たしかめるように尋ねてくる律のことを、とろんと見つめながら、こくりとうなずけば。
律は余裕なさそうに顔をカーッと赤く染めて、顔を手で覆ってしまった。
「……千秋、かわいすぎる」
「か、かわいいって言うな‼」
「わかってます。千秋は、ものすごくかっこいいって、僕はちゃんと知ってるから」
こ、こいつ。おれをキュン死にでもさせる気か……?
「ねえ、千秋。僕のことが好き?」
こつんと額同士をくっつけながら、あざとく聞いてくるなんて、反則以外の何者でもない。
熱に浮かされながら、伝えたかった想いがあふれ出す。
「好き。律と同じ意味で好きだって、やっと気がついた。だから……、甘いことを言うのも、こういうことをするのも、全部おれだけにして」
その後また、今度はもっと深くキスをされて。
いきなりだったからビックリしすぎて、「バカ律‼」って叫ぶことになったのだ。
そして。
これは、おれと律が両想いになってから、後になって聞いた話。
あの日、なかなかバスケ部の練習に戻ってこないおれを心配して、なんとバスケ部の部員たちが総出でおれを探していたらしい。
「一人が、空き教室にいるのを見つけたんだけど、千秋が噂の新入生となんかすごく良い感じだっっていうからー。放っておいて、あとでたっぷり話を聞こうと思ったんだよ」と部員の一人からニヤニヤ笑顔で言われて、恥ずかしさのあまり、また顔が真っ赤になったのだった。【完】
今の状況を一言で表すなら、『最悪』だ。
「相良くんに付きあってもらえて助かったよー。わたし一人じゃ、男の子へのプレゼントを選ぶのに不安だったし」
そう。
いま、おれ――相良千秋は、クラスメイトの椎名さんと共に星燐高校近くのショッピングモールを後にして駅に向かっている。
おれは内心のどんよりとした気持ちが顔に出ないように、なんとか愛想笑いをした。
「椎名さんの役に立てたならよかったよ」
「ほんとに助かった! ありがとねっ、相良くん」
この癒される笑みが、おれへの好意から発されたものだったらなぁ……。
数時間前までは、そうかもしれないと期待していたんだけど。今やその期待はガラスのように粉々に砕け散ったというわけだ。
椎名さんは、さっき買った『彼女が好きなひとへのプレゼント』が入った袋を大切そうに抱えながら、溶けそうなほど眩しい笑みを浮かべた。
「じゃあ、また明日、学校でね!」
「うん。またね」
電車通学の椎名さんが改札の向こう側へ吸いこまれていくのを、胸に小さな穴が空いたような気持ちで見送る。もうじき夏がやってくる季節とは思えないほど、肌寒く感じた。さっきの店で冷房に当たりすぎたせいか?
「はあ……」
彼女の華奢な背中が完全に見えなくなったところで、思わず、大きなため息が出た。
さっきまで一緒にいた椎名さんは、クラスメイトの女子だ。そして、おれが異性として気になるひとでもあったのだが……、この通り、たった今ものの見事に失恋した。
おれたちが通っている星燐高校では、四月最初の席順が男女混合の苗字順だ。『しいな』と『さがら』でおれたちは二年生になった一番初めの時期から前後の席だった。
最初、椎名さんはかわいいけど、大人しそうな子だなと思っていた。
でも、たまたま同じ漫画が好きなことがわかって。そこから話が弾むようになって、意識するようになった。
『ねえ、相良くん。その……、バスケ部がない日の放課後に、わたしに付き合ってくれない?』
気になっている子からこんな風に誘われたらさ、思春期の男なんてほぼ全員浮かれるだろ?
今まで彼女がいたことがないおれにも、ついに初めての春がやってくるかもしれない。そんな薔薇色の未来を信じていた。
実際は、本当にただ買い物に付き合ってほしいという意味であり、同時に彼女には他に想い人がいるという残酷な真実がわかっただけだったけど。
「……帰ろ」
あー……。
やっぱりおれは、同年代の女子から見ると『かわいいマスコット』枠で、そういう対象として意識されづらいんだろうか。女子と気さくに話せる性格寄りなのに、今までの人生で告白された経験はゼロというのが物語っているような……。
童顔で中性的な顔立ちも、微妙に170cmに足りていない身長も、全てがコンプレックスに思えてくる。
誰か一人にだけでも、かわいいじゃなくて、かっこいいって思ってもらえたら良いのに。
✳︎
「……ただいま」
「お帰りなさい、千秋」
「は? なんで律がいんの」
気落ちしたまま自分の部屋へ入ったら、なぜか幼馴染の律が居座っていた。
宇佐美律。おれの一つ年下で星燐高校の一年生、軽音部所属。この前の健康診断で身長が169cmだったから悔しい思いをしたおれに対して、律はすでに180cmと長身でモデルのような体型をしている。おまけに、顔も芸能人顔負けの整い方。色白で、すっと通った鼻筋に、切れ長の瞳が印象的な美しい顔だちだ。
うん。
モカブラウン色の髪も超サラサラだし、律は、今日も非の打ちどころのないイケメンだな。
でも、約束もしていないのに、おれの部屋に居座っているのはなんで? ていうか、母さんも律に対してセキュリティ甘過ぎじゃね? どうせこいつの天使の微笑みに簡単に屈したんだろうけど……。おれのプライバシーなんてあったもんじゃない。
「え? 今日、おれと約束とかしてなかったよな?」
「そんなことよりも、千秋。聞きたいことがあります」
おもむろにソファから立ちあがった律が、つかつかとおれの方へ歩み寄ってくる。足の長い律は、何歩か歩いただけで、あっという間におれとの距離を詰めてしまった。後ろは壁、結構な近さで見下ろされる形に。こいつは無駄に顔が良いから妙な迫力がある。
「いや。だから、なんの話?」
「さっき、高校近くのショッピングモールで、女子とデートをしていましたよね?」
「あー……。って、なんでお前が知ってんの⁉」
「話をそらそうとしても無駄です。あの女子は、千秋のなんなんですか?」
「なにって言われても……」
なんでもねえわ! なんなら、さっき失恋したばっかだよ畜生‼
忘れようとしたばかりなのに、傷口へ塩を思いっきり塗りたくられたような気分だ。苦い気持ちが蘇ってきて言葉につまったら、律は、なぜだか切羽詰まったような声を漏らした。
「もしかして……、彼女?」
「違うよ、ただのクラスメイト。……彼女だって言えたら、良かったけどな」
「えっ?」
「だーかーらー、振られたの! 振られたっていうか……、告白すらできなかったっていうか。おれは気になってたけど、向こうは、眼中にもなかったの‼」
自棄になってわめくように叫んだら、律はショックを受けたように瞳を見開いた。
でも、その後すぐに、形の良い唇をヘの字に曲げた。
「なるほど……なんていうか、超フクザツな気分です」
「それはおれの台詞だよ‼ ってか、さっきからお前はなんなの⁉」
「でも、千秋の良さがわからないクソ女なんて、相手にする必要はないですよ」
「は?」
今、いつも丁寧な言葉遣いの律から、黒めの発言がかいま見えたような。
「ねえ、千秋。失恋を忘れるには、新しい恋が効くといいますよね」
「えっ……?」
「あなたの傷心につけこんでも良いですか?」
「いや、なんの話?」
話の流れが全く見えず、素で、首をかしげたら。
律は、その大きな手の平で、おれの片側の頬に恐る恐る触れてきた。
エッ?
つい先日、鮮やかにドラムスティックを操っていたあの手が、まるで壊れ物でも扱うかのような繊細な手つきでおれに触れている。
なにが起こっているのかまるでわからず、戸惑うことしかできない。
「り、律……?」
「僕は、千秋のことが好きです。もちろん、恋愛の意味で」
勘違いしようのないストレートすぎる告白に、心臓がドキリと跳ね上がる。
人生初の告白を、ずっと近くにいた同性の幼馴染から、このタイミングで受けるなんて。
おれしか見えていないというような律の瞳の熱に囚われたようになって、身体が動けない。
「ま、マジで言ってんの?」
「本気も本気です。それも、千秋が想像しているより、ずっと昔から」
「でも、その……。お、おれにとっての律は、幼馴染で……、今までそういう風に考えたことはないっていうか」
「それも知ってる。今は、それで良いですよ」
「そ、そっか」
律はおれの顔から手を放して、一歩下がった。
そして、さびしげに微笑む。
「気持ちに温度差があることは、充分わかっています。でも、さっき千秋が女子と二人きりで遊んでいるところを見て、耐えられそうになかったんだ。千秋が、僕以外の誰かと特別な関係になったりしたら、さびしすぎて死んじゃうかも」
「いやいや冗談でも怖いって!」
「冗談じゃないかもよ? 現に今だって、すぐに話を聴取しなければ気がすまなかったから、ここで千秋を待ちかまえていたんです」
「母さんに気に入られてるからって、簡単にひとの部屋に入りこむな!」
「それは、ごめんなさい。……でも、千秋は彼女と付き合っているのかもしれないと思ったら、いてもたってもいられなくなって」
困って眉尻を下げたおれに、律は、獲物を見定めたかのように瞳を細めた。
「ズルくても、あざとくても、もうなりふり構いません。僕は、千秋に好きになってもらえるように、全力を尽くすことにしました。覚悟していてくださいね?」
✳︎
昨日、クラスメイトの女子に失恋をしたら、年下の美形幼馴染に突然告白をかまされた。
……のだけれども、冷静にあれは現実だったのだろうか? 夢でも見ていたんじゃないか。
だって、相手は、昔からとんでもなくモテる律だぞ。
顔とスタイルが芸能人並みに良い上に、勉強もできて、楽器演奏までできる天が与えすぎのハイスペック男。高校に入学して数か月しか経っていないのに、すでに女の子から告白されるのが日常茶飯事になっているくらいだ。
その人気ぶりの理由は、先日行われた新歓ライブの影響も大きいかもしれない。律が入った軽音部では、毎年、五月中頃に新入生の勧誘を目的とした歓迎ライブを体育館で行う。本来、演奏者としてライブに出れるのは二年生以上なんだけど、たまたまドラムを担当する予定だった先輩が怪我をしてしまったらしく、ピンチヒッターとしてドラム経験者の律が抜擢されたんだって。
おれもそのライブを見にいったんだけど、そのときの律がさ、すげえかっこよかったんだよ。ワイシャツを腕まくりして真剣にドラムを叩く姿が輝いていて、流れる汗にすらも色気があって、思わず目を引きつけられるというか……。これまでも律のドラム演奏を見たことがなかったわけじゃないけど、中学で吹奏楽部の一員として演奏しているのを鑑賞するのとは、違った感動があった。とにかく男のおれでも素直に見惚れてしまったんだから、何人もの女子の心を撃ち抜いたに違いない。
でも、律は、どんな女子に告白されても付き合おうとはしなかった。
誰から告白されてもスマートに振ってしまう律に、おれは、『もったいないなぁ。試しに誰かと付き合ってみても良いのに』と内心では思っていたけど、まさかその理由はおれを好きだったからなのか……? いや、そんなまさかね!
うーんと首をかしげながら、登校するために家を出たら、玄関の前に悩みの種の張本人がスマホを弄びながら立っていた。
「……って、律じゃん! なんでおれの家の前にいんの⁉」
こっちは焦っているというのに、律は、おれを視界にいれた途端にぱあっと顔を輝かせた。
「おはよう、千秋。朝から顔をあわせて一緒に登校だなんて、小学時代を思い出しますね! ふふっ、幸せだなぁ。近くに住んでいるんだし、千秋の朝練さえなければ本当は毎日迎えにきたいくらいです。ついでに抱きしめたいなぁなんて」
「待って! なにもかもがいきなりすぎない⁉」
「僕にとっては、いきなりじゃないですよ。千秋への片想い歴は誰にも負けない自信があります! 昨日告白したことだし、これからは惜しみなく愛を伝えていくスタイルに切り替えようと思って」
「よく恥ずかしげもなく堂々と言えるな……」
「ねえ。千秋もはやく僕のことを好きになって?」
「んー……、とりあえず、早く学校にむかうぞ。遅刻したらやべえし」
「ちぇっ。千秋がツレなーい」
唇を尖らせつつも、隣に並んで歩く律の目元は和らいでいて、なんだかうれしそうだ。
こうして隣に並ぶと頭ひとつ分背が大きくて、おれがすこし見上げる形になるのが悔しい。小学校低学年ぐらいまでは、同じくらいの身長だったのにさ。
「律、ほんとに身長伸びたよな」
「そうですね。千秋はこの前の健康診断で169cmでしたっけ?」
「は? 170cmはあったし!」
「ちなみに僕は180cmでした」
「ケンカ売ってんの?」
てか、なんでおれが身長をひそかに盛ってることまで知ってんの……?
反射的に噛みついたら、律は、なぜか白い頬をうっすらと赤く染めた。
「いえ。ただ、ちょうどいい身長差だなぁと思いまして」
「なんの話?」
首をかしげたら、律はすこしだけ屈んで、おれの耳に唇を寄せた。
そして、吐息を含んだ声で、わざとらしいくらいにゆっくりと言った。
「キスをするのに、です」
……‼
「千秋は知っていましたか? キスをするのにちょうどいい身長差というものがあるんです。僕らの身長差は、ぴったりそれに当てはまっているようですよ?」
耳にすこしだけ触れた律の唇を急に意識してしまって、即座に距離を取った。
な、なんだこれ。心臓バクバクしてるし、顔が熱いんだけど。いや、これは律をそういう意味で好きだからとかそーゆーのじゃなくて、突然こんな不意打ちをくらったら誰だって……!
「律っ。おれをからかうのもいい加減に……!」
しどろもどろになりながら言い返そうとした、そのときだった。
「あっきー、おはよー!」
明るい、聞き慣れた声がして振り向けば、クラスメイトの南優香がおれの隣へ走り寄ってきた。ひょこひょこと揺れるポニーテールが目印の元気女子。
「南じゃん、おはよ」
「通学路でばったり会うのは珍しいねー、いつも体育館の中だもん」
南は、女子バスケ部に入っている。男子バスケ部所属のおれとは、部活動内での交流はないけれど、体育館内でよくすれ違うこともあって喋りやすい女子だ。
一方の律はといえば、南がおれの隣にやってきたとたんに静かになった。さっきまでの軽快な口ぶりが嘘だったかのように。
「あっ。えーと、軽音部のライブでドラムを叩いてた宇佐美くん……だよね? あっきーの知り合いだったんだね」
南が、様子をうかがうように律へと話しかける。後輩だけど、さすがに律のことは知ってたんだな。そりゃ知ってるか、新星イケメンドラマーとして星燐ではほぼ有名人みたいになってるし。
南に話しかけられた律はといえば、愛想よく微笑んだ。
「はい、宇佐美律です。千秋とは、幼稚園時代からの幼馴染なんですよ」
「へぇ〜、幼馴染だったんだ! あっきーってば隅に置けないなぁ、こんなにかっこいい幼馴染がいるなんてさ」
ちょっと待って、その発言は女友達に対して言うやつじゃね?
わかる、わかってるよ。おれって自他ともに認める童顔だし、男っていうよりかはやっぱりマスコットって感じの認識なんだろうな。たぶん、椎名さんの認識もそんな感じだったんだろうね……。やばい、考え出したらまた凹みそう。
ベツに、南は気さくな友だちだし、異性として意識されたいとかじゃないんだけどさ。なんというかこう……、おれは、マスコットってわけじゃないのにって気持ちも心のどこかで拭えないんだよな。
「南さんは、千秋と仲が良いんですね?」
「あー、まーそうだねぇ。あっきーは、バスケ仲間って感じかな」
「なるほど」
すこしの間、黙ったあと。
律はなにを思ったのか、回りこんで南の隣へと移動した。
そして、歩きながら、南の顔を切れ長の瞳で無言のままじいいっと凝視。
「う、宇佐美くん? どうかした?」
その辺の並みの男が同じ行動を取ったら「いきなり隣にやってきて、ジロジロ見るなんてなんのつもり? まじキモい」と即刻陰口祭りの対象になりそうなもんだが、イケメンに限っては違う。
「あ、あの……? あたしの顔、なにかついてるかな?」
な、なんと! どちらかというと普段は男勝りなあの南が、頬をうっすらと赤く染めて乙女モードになっているではないか……! イケメンすげえ。てか、律のやつはなに考えてんだ⁉
南に問いかけられた律は、口角をあげてきれいに微笑んだ。
「突然見つめてしまってすみません。あなたに興味があったもので」
「興味……?」
「南さんには、恋人がいますか?」
「えっ⁉ い、いないですけど……?」
えええええ、律ってばいきなりなに聞いてんのーーー! てか、南も馬鹿正直に答えなくていいよ!
話を止めに入る隙もなく、律はよどみなく続けていく。
「そうですか。気さくでかわいい方なので、てっきり恋人がいらっしゃるのかなぁと思っていました」
「か、かわっ⁉」
「はい。そんなに驚くことですか?」
「か、かわいい……」
ダメだ。南は律の発言に衝撃を受けすぎて、まともに話が聞こえていない。
「そうだ。連絡先を聞いても良いですか?」
「へっ!」
「南さんにお聞きしたいことがあって。良かったらという感じです」
「も、もちろん! これ、あたしのIDですっ」
「わあ、ありがとうございます」
おれにとっては異性に連絡先を聞くだなんてまぁまぁなイベントなのに、律は事もなくわずか数分間で終えてしまった。
校門を抜けて、もうすぐ校舎につきそうというところで、南はいったん別れを切り出した。
「じゃ、じゃあ。あたしは、ちょっと部室に取りに行くものがあるので、これでっ!」
南の奴、いつもハキハキ喋るのに、つっかえてるし……。
動揺したまま、いかにもコイスルオトメな雰囲気で、顔を赤く染めながら去って行ったのだった。
…………。
「なあ、律」
「ん? なぁに、千秋」
「……あれはどーゆー意味だよ」
「あー……。あれは、魔除けのようなものですよ」
「は?」
「あっ、勘違いしないでくださいね⁉ 僕は千秋一筋ですよ! 千秋のことしか見えていませんからっ」
「……いや、そこは聞いてねえんだけど」
急に取り乱すなよ。
おれしか見えてねえとか言われても、反応に困るじゃん。
「大丈夫。千秋は気にしなくて良いことです」
律はニコニコと、腹の底になにか隠していそうな笑顔を浮かべた。
おれのクラスメイトにいきなりやばめの絡み方をしておいて、おれは知らなくて良いってなんなんだよ……。
若干モヤモヤとした気持ちを抱えたまま、校舎の中に入っていく。
「じゃ、おれは下駄箱こっちだから」
「まさかここでバイバイですか⁉ 嫌ですっ。ギリギリまで一緒にいたい!」
「はいはい、わかったよ」
といわれても、一年生の教室は三階で、おれら二年生の教室は二階だから、どちらにせよすぐ離れることにはなるけど。
反論するのも面倒になってうなずけば、律は上機嫌で、自分の下駄箱に上履きを取りに向かった。
「宇佐美くん、おはよぉ。あは、今日もイケメンだねぇ」
「おはようございます。このやりとり何度目です?」
すこし目を離した隙に、だいぶ明るい髪色の同級生っぽい女子に絡まれてるし。
「だって、何度でも思うんだもん。ねね、昨日話した動画は見てくれた?」
「いや……。僕、ひとを待たせているので先に行きますね」
律はわずらわしそうに女子から離れると、階段前の廊下で律を待っていたおれの方へと突進してきた。
「べつに、おれに気ぃ遣わなくても良かったのに」
「気って? なんの話ですか」
「話しかけられてたギャルっぽい子、クラスメイトとかじゃないの? 同じ階だろうし、教室まで一緒に行けば良かったのに」
何気ない気持ちで口にしたら、律はムッと唇を尖らせた。
「どうしてわからないんですか?」
「なにが?」
「僕が、千秋と一秒でも長く一緒にいたいってこと。ほんとは、学年が違うことすらも憎いと思っているんですよ? それなのに、千秋の方は、僕のことなんてどうでもいいって感じなのがムカつく」
心臓がドキッと飛び跳ねた。
一瞬間、教室へ向かう生徒たちからの視線が頭から抜け落ちて、どうしようもないわがままを言う目の前の律だけに脳が支配される。
やべえ。顔、また熱くなってるような気がする。
なんで、お前は、おれなんかにそんな必死なんだよ。
……しかも、めちゃくちゃな言い分だし。
おれの無言をどう受け取ったのか、律は、なぜかしょんぼりとした顔をした。
「……ごめんなさい。これじゃ、ただの駄々っ子ですね」
「わ、わかってるじゃん」
「一日でも早く千秋に好きになってもらいたくて、焦っちゃいました」
だから、誰が聞いてるかもわからない場所で、そーゆー危ない発言をするなって!
階段をのぼって、「じゃあおれはこっちだから」と別れようとしたところで、律に制服の裾ををつかまれた。
「待って、千秋。今度、バスケ部がオフの休日はいつですか?」
「ん? あー、たしか今週の日曜はオフだった気がする」
「わかりました。じゃあ、僕と出かけましょう!」
「強引だな!」
「いいでしょう? 退屈にはさせないからお願い! お願いお願いお願いですっ!」
「んー……。わかったよ」
うちでダラダラしててもつまんねえし。そういえば最近はバスケ部が忙しくて、律とゆっくり過ごしていなかったから。
悪くない案だと思って素直にうなずけば、律は満面の笑みを浮かべた。
「最高のデートにしましょうね!」
えっ……? デート…………⁉
✳︎
去り際のあいつの爆弾発言が頭の隅に引っかかったまま、問題のその日はやってきた。
今日は、律曰く『デート』らしいけど……。
ベツに今までだって、二人で出かけたことがなかったわけじゃない。小学時代なんて、毎日のようにお互いの家を行き来して遊んでいた仲だし。中学に入ってからは、互いの部活動が忙しくなって、さすがに毎日は会わなくなったけど。
だからきっと今日も、意識しすぎなければ大丈夫なはずだ。
いや、大丈夫って……なにが?
自分のよくわからない思考回路に首をかしげながら、待ち合わせ場所として指定された、駅の改札前に到着すれば。
長い足を軽く組みながら、スマホを弄んでいるだけで絵になってしまう律がすでに着いていた。
その美しさは、無表情だとすこし近寄りがたいほどで。本人は気づいていないけど、これでもかというほど駅構内を歩く人々の注目を集めている。
ちょっと話しかけにいきづらいけど、まぁ、これもいつものことだから。
「待たせたな」
「千秋‼ おはようございます!」
律は、おれの姿を認識するなり、ぱあっと花開くように笑った。
今日も完璧なイケメンぶりだ。黒いTシャツにスキニージーンズというごくシンプルな格好なのに、スタイルの良さが際立っていてモデルみたい。
律はニコニコとおれを見つめてきたかと思えば、頬をうっすらと赤く染めた。
「千秋の私服姿、久しぶりに見たけれどやっぱり素敵ですね……。パーカー、とても似合っています」
「素敵……かなあ? とりあえずって感じで、無難に選んだだけなんだけど」
シンプルイズベスト極めつつ超絶かっけえお前になに褒められても嫌味にしか聞こえねえよ、という本音は腹の中に沈めておく。
嫌味を言う気にもなれないほど、律が幸せそうなオーラを振りまいているから。なんだかこっちの調子も狂ってくる。
「なあ。互いの家までほぼ五分なのに、わざわざ駅で待ち合わせする必要あった?」
ちなみに、相良家と宇佐美家は徒歩で約五分ほどだ。
「もちろんです。こうして家からすこし離れた場所で待ち合わせをしたほうが、本格的にデートっぽいでしょ?」
「デ、デートデートって、ただ一緒に出かけるだけだろ?」
「違います、今日は誰がなんと言おうとデートです。はっ! もしかして千秋は、恋人にはお家まで迎えに来てほしい派でしたか⁉ たしかにそれも捨てがたいし、一秒でも早く千秋の愛らしいお顔を拝めるというメリットが……」
「あー、いや……。もうこの話はいいや」
どさくさにまぎれて恋人って言ったな、こいつ。
さすがに冗談にしてはしつこいというか、気合いが入りすぎ……なような気も。
もしかして、本当に本気で、おれのことを昔から?
そういう意味での、特別な『好き』……?
ダメだ。いま考え始めたら、恥ずかしくなって逃げ出したくなりそうな気がする。出かけるどころじゃなくなるわ、思考をそらそう。
「早くしないと、上映時間に間に合わないぞ」
「ですね。行きましょう」
今日のメインイベントは、映画を観ること。
それから、映画館が入っている商業施設内で、昼飯を一緒に食う予定になっている。
駅直結の商業施設に入ったとき、つい数日前は、椎名さんと一緒にこの場所を訪れたことが頭によぎった。
彼女の好きなひとへのプレゼント選びに付き合わされることになった、苦いレモンのような記憶。蒸し暑い外気と、冷房の効いた店内との急な温度差のせいか、軽く寒気がした。
「うわっ」
「千秋」
すれ違ったひとにぶつかりそうになったところを、律に腕を引かれたことで、なんとかセーフ。
律は、おれの腕を引き寄せた手を、そのままおれの手へと滑らせた。そして、手の甲同士を、軽く触れさせる。
律の熱が直に伝わってきて、さっきまで感じていた寒気はすぐに消えてなくなった。
「手をつないでも良いですか?」
「えっ。で、でもっ! 誰が見てるかわかんねえし、高校のやつとすれ違うかも……」
「誰も周囲の他人のことはそれほど気にしていませんよ。それに、こうでもしないと千秋は、僕と一緒にいるのに他のくだらないことを考えるでしょ?」
ハッとして律の顔を見上げたら、切れ長の瞳とバッチリ視線が交差した。
淋しそうな、それでいてどこか危うげな熱を孕んでいるようにも見えて、胸の内がドキドキとしてくる。
「早く、僕に堕ちてきて。他のことなんてどうでも良くなるくらい、千秋だけを甘やかすから」
「っ」
頬がライターで灯されたみたいに、カッと熱くなった。
でも、すぐに我に返る。
「い、いまは、急がないとだって! 映画、まにあわない、からっ」
「ふふっ」
「なにがおかしいんだよ!」
「頬、赤くなってます。意識してくれたの?」
「う、うるさいっ‼」
くつくつと楽しそうに笑う律は、まるで小悪魔のようだ。ちゃっかりおれの手を繋いで、離してないし。
このまま、こいつのペースに流されていたら、まずい気がする。チョコレートみたいに心がドロドロに溶けて、ベツのなにかに変わってしまいそうな危ない予感。
エレベーターで七階まで上がって映画館に着くと、甘いキャラメルの匂いが鼻に広がった。販売されているキャラメルポップコーンの香りだろう。この空気感、映画館にやって来たって感じがして、おれは好き。
休日なのでそれなりに混雑していたけど、あらかじめチケットを買っておいて良かった。QRコードをかざして、目的のシアターへと向かう。
ちなみに、今日観る映画は、おれの指定だ。
いま話題になっている、『天使のきみがいなくなっても』。
青春系の切ないアニメ映画だ。
律が『映画が観たい! 観る映画は、千秋が決めてください』と言ってきたので、話題になっているし、クラスメイトが面白いと言っていたのを決め手とした。律は『あー……まあ、千秋が観たいなら良いけど』というちょっと微妙そうな反応だったけど。それなら別の映画にするかと聞いたら、そのままで良いということだった。
おれたちが指定の席に着くと、すでにほかの映画の宣伝タイムが始まっていた。
そのまま映画が始まり、すぐに、物語の世界へ吸いこまれていったんだ。
*
映画、おれ的には、めちゃくちゃ良かった……!
あとちょっと涙腺を刺激されたら泣きそうなくらい、グッときた!
心臓病を患っていることで余命宣告を受けた高校生の女の子の前に、自分のことを天使だと名乗る不審な男が現れるところから始まる物語。
普通の状態だったら絶対に関わりたくないタイプの怪しい男だけれども、何もかもが投げやりになってしまった主人公は彼がなにかと絡んでくるのを受け入れる。
彼女が、彼に淡い恋心のようなものを抱いたところで、天使の彼が半透明に消えかかっていた。
実は、彼の本当の正体は、未来からタイムリープをしてやってきた将来の主人公のドナーだったことが判明して……二人は最初から結ばれるわけがない関係だったという怒涛の展開で!
クライマックスシーンでは、映画館内にすすり泣く声が広がっていた。
エンドロールが終わったので、切ない余韻に浸りながら、隣に座っている律の様子をうかがった。
「律。……映画、どーだった?」
声をかけたら、律は肩をびくりと跳ね上げた。
お化けにでも声をかけられたかのように大げさに驚いて、自分の顔を手で覆ってしまう。
まるで、おれに見られるのを、嫌がっているかのように。
「律?」
「……み、見ないで」
その頼りない声は、聞き漏らしてしまいそうなほどか細くて。
掠れた声で、おれの視線から逃れるように、意味もなくからだを逸らそうとする。
「……いま、目、真っ赤になってるから、ダメです。見られるの、恥ずかしい」
は?
えっ、なに。もしかして、映画に感動しすぎて目真っ赤になるほど泣いちゃった、ってこと……?
予想外の律の反応にちょっと呆けたあと、自然と口元がニンマリしてしまった。おれも、映画に集中してて、観てる間はぜんぜん隣の様子まで気がつかなかった。
なんだよ、それ。
「かわいい、じゃん」
口にしてから、『おれ、なに言ってんだ?』とすぐに思った。
明確な意思をもって言おうとしたんじゃなくて、気持ちがそのまま口からこぼれ出てしまったみたい。
「は? 千秋、なにを言って」
目の前で、必死に目元を覆いながらもボロボロ泣いていることを全く隠せていない律が、なんだかとても愛おしい。
「ちょっといけ好かねえほどかっこよく成長しちゃったと思ってたけど、昔の、かわいい律のままのところもあるんじゃん」
「……昔のことは、忘れてくれていいのに」
「なんで?」
「だってっ……みっともないし。情けないから」
目の前の律と、幼稚園児で泣き虫だった頃のかわいい律とが、重なって見える。
胸の奥にしまわれていた懐かしい気持ちが蘇り、おれは、導かれるように律の頭を撫でた。
昔は、よくこうして、泣いている律を慰めたんだよな。
「たしかに、律は昔から、よく泣く子だったな」
律と初めて知り合ったのは、もう十数年も前になる。
幼稚園児だった頃、お互いの家から一番近い公園で遊んでいたときが初対面。
おれは公園中を駆け回って遊ぶやんちゃ坊主で、律は砂場でぽつんと砂団子を作っているタイプだった。
律は、昔から、きれいな顔をしていたんだよ。
おれは、天使みたいにきれいな子が砂場で遊んでいるなぁと、最初のうちは遠くからぼうっと見惚れていた記憶がある。
すこし経ってから勇気をもって話しかけて、一緒に遊ぶようになったんだ。家も近かったから、仲良くなってからはしょっちゅうお互いの家を行き来していた。
「……公園で転んだり、一生懸命作っていた砂の城が壊れたり、些細なくだらないことで昔からよく泣いてましたね。あれからすこしは大人になって成長したかと思ってたけど、今でも結局、フィクションの映画でぼろ泣きとか……恥ずかしい」
律は自嘲気味に笑った。
でもおれは、疑問に思って、首をかしげた。
「なんで卑下してんの? 泣くのは、ベツに悪いことじゃないだろ。涙もろいかどうかは、心の内の感情が、表に出やすいかどうかってだけなんだろうし。それにさ、お前はただでさえ完ぺき寄りの人間なんだから、そのぐらいのほうが可愛げがあって良いんだよ」
律が、ようやく自分の顔から手をはずして、おれの様子を恐る恐るうかがう。
泣き腫らしたおかげで、切れ長の瞳が赤くなっていた。
「ふふっ。うさぎみたいだな」
思わずこぼれ出た笑みに、律は、おれを見つめながらぽつりと言った。
「千秋は、やっぱりズルいです」
「なんでだよ」
「……あなたは昔から、いざってときに、かっこよすぎるんですよ」
えっ。
今度は、聞き返すこともできなかった。
たしかめてしまったら、なんだか胸の鼓動が、鳴りやまなくなりそうで。
なぁ。今お前、おれのことを『かっこいい』って、そう言った?
*
映画館を出て、律と一緒に、同じ商業施設内のファストフードショップに入った。
「律、一セットだけで足りるか? バンズ一個とポテトだけじゃ足りなくね?」
「はい、これで大丈夫です。そーゆー千秋は、三つもバンズを頼んで大丈夫ですか?」
「おう。食べ盛りの男子高校生だからな!」
「ふふっ」
「……ちっちゃいくせにって思ってる?」
「ご想像にお任せします」
クソ! 子どもを見守る親のような微笑みが腹立つ。
二人掛けの席に向かいあって座りながら、頼んだ料理を頬張っていく。
「……天きみ、良かったよなぁ」
「千秋が指定してこなかったら、絶対、観に行こうとは思いませんでした」
「あー、やっぱり?」
「気づいてたんですか?」
「うん。お前、ちょい微妙そうな反応してたしな。まあ、変えてくれとは言われなかったら追求はしなかったけど。でも、なんで渋ってたんだよ?」
「……もう、わかってるようなものでしょ」
いじけたようにおれを見つめてくる律を見て、ようやく当初の思惑に気がついた。
「あー! 感動系の映画を一緒に観たら、絶対ボロ泣きするってわかってたからだ!」
「もうこの話は終わりにしてくださいっ!」
「えー、今さらおれには隠さなくて良いのに」
「ごぼっ……い、いきなり、彼氏感出してくるのもやめてください。ときめきすぎるから」
「出してねえわ! でもさ、冗談抜きで、良い映画だっただろ?」
「はい。話の内容はもちろんですけど、挿入曲もすごく素敵でしたね! ベースラインが映えるかっこいい曲で、ノリノリになっちゃっいました」
「へえ。感想もバンドマンっぽいな」
「からかわないでください」
頼んだものをぜんぶ食べ終わり、話題も尽きてきたタイミングで、頭の隅に引っかかっていたあの発言の真意を確認するかどうかで悩んだ。
『……あなたは昔から、いざってときに、かっこよすぎるんですよ』
なぁ。さっき言ってたあれって、どういう意味?
「千秋?」
ついさっきまで、いくらでも流暢に動いていた口が急に重たくなる。
どうして? たった一言、軽く確認すれば良いだけだろ。
こんなに緊張しながら、聞くようなことでもないのに。なぜだか、聞いてしまったらあとに引けない予感が胸を叩いている。
でも、気になって仕方ないから。
「あ、あの……。さっきの」
「あれ? 相良くん」
勇気を絞り出して、聞こうとしたその瞬間だった。
トレイを手に持って空いている席を探している、椎名さんと遭遇したのは。
「椎名さん……」
「友だち? あたし、先にそっちの席についてるね」
「あっ、うん」
立ち止まった椎名さんを見て、彼女と一緒にいた友人らしき女子は、気を遣って先に行ってしまった。
「こんなところで休日に会うなんて偶然だね」
「うん」
椎名さんは、ちらりと律の方へ視線をやった。
自分が現れたことで無言にならざるをえなくなった律に悪いと思ったのか、軽く頭を下げる。
「すみません、会話の邪魔をしちゃったみたいで。相良くん。あらためてになるけど、この前はありがとうね。また学校で」
友人を追いかけて椎名さんが去っていくと、やっと時間が動き出したというように、律が小さく息を吐いた。
「混んできたみたいだし、そろそろ店を出ましょうか」
「そーだな」
連れだって席を立ち、ゴミとトレイを片付けて、店を出る。
突然の椎名さんの登場で、会話の糸口を見失ってしまったみたいに、無言が続いていた。事前に立てていた予定は全部こなしてしまって、この後、どうするかも決めていない。
律、ぜんぜん、椎名さんのこと聞いてこないな。
先日おれが失恋した相手だって、気がついていてもおかしくないのに。
制服姿でない椎名さんを見るのはさっきのが初めてで新鮮だったのに、彼女がどんな格好をしていたか、もう記憶がボヤケ始めている。
そのくらい、隣を歩く律が、今なにを考えているのかの方が気になって。
「なぁ、律」
「うん?」
「これから、どーする?」
「あー……。実は、そろそろ、学校に向かわないといけない時間なんです。さきに言っておけば良かったですね」
「学校? 休みなのに?」
「軽音部の練習です」
「なるほど」
もっと、一緒にいたかったなぁ。
……あれ? おれ、今なにを考えて。
二人一緒に駅の方まで戻ってきた。学校方面へと向かう律とはここで解散だ。
午前中に待ち合わせをしてからずっと一緒にいたのに、いざとなると離れ難いような、さびしい気持ちになって。思わず、律の顔をじっと見つめてしまった。今さらだけど、ほんとにきれいな顔してる。
「千秋?」
「今日は、ありがとな。すげえ楽しかった」
「ほんとに? 僕もです! 今日、またさらに千秋のことを好きになりました」
不意打ちの『好き』に、心臓がドキリと飛び跳ねた。
もう、冗談じゃないかって誤魔化せない。
いや、おれが、誤魔化したくないのかもしれない。
だって、すごく恥ずかしいのに、やさしい瞳をしておれだけを見つめてくる律から視線をそらせない。
「なぁ、律」
「うん?」
「……おれの、どこがそんなに好きなの?」
震える声で、顔をすこし熱くしながら尋ねた。
だってこんな質問、明らかに、律を意識していると見透かされそうで。
でも、椎名さんへ失恋したことが、どうでもよくなりつつある自分がいる。さっきあまり話せなかったことも、全く気にならない。
今のおれが気になっているのは……、目の前のこいつの真意だけ。
律は瞳を大きく見ひらいてきょとんとした後、ふわりと笑った。
「そんなの決まってるじゃないですか。かっこいいところですよ」
息が、止まりそうになる。
「恋に落ちたきっかけは、昔から泣き虫だった僕を、千秋がありのまま認めてくれたからです。僕は、しょうもないことですぐ泣いてしまう自分が嫌いだったけど、千秋はそんな僕を『変えようとしなくて良いじゃん。うさぎみたいでかわいいし、おれは好きだよ』って慰めてくれました。頭を撫でながらあんな風に優しく寄り添われたら、性別関係なく、誰だって恋に落ちると思います」
「そ、それって……、小学校低学年のころとかの話?」
たしかに、昔もそんな話をしたな。
そのときのことは、鮮明に覚えてる。
でも、律があれからずっと、おれのことをそんな風に想っていたなんて。
顔が熱くて仕方がない。思考が溶けてきて、心臓が早鐘を打つ。
「僕は、千秋の言葉に救われました。そんなに考えてはいなさそうだったけど、自然とそう言えてしまうあなたが、すごく魅力的だったんです。それにね、千秋がバスケをしている姿も、かっこよくて大好き。あと、毎日誰よりも早起きをして、朝練に向かう努力家なところも」
「なんでお前が朝練のことまで知ってんの⁉」
「千秋のことはなんでも知りたいから、同じクラスのバスケ部のひとに聞きました。あと、千秋の好きなところは――」
「す、ストップストップストップっ‼」
「なんで。千秋の方から言えっていったのに」
「だ、だって……」
たぶん今のおれ、耳まで真っ赤だ。
ダメだ。律は本気で昔からおれのことを好きで、しかもその理由が『かっこいいと思ってるから』だなんて。
そう思って律のここ最近の言動を思い返すと、胸がいっぱいいっぱいになって、顔をまともに直視できない。
不自然に黙っているおれを見つめながら、律は微笑んだ。
「じゃあ、そろそろ時間なので行きますね。またね、千秋」
一人で自分の家へと帰る間中、頭を飛び交っていたのは、今日の半日でいろんな表情を見せた律のことばかりだ。
朝、待ち合わせ場所に到着したおれを見て、うれしそうにしていたあいつ。
映画を観終わったあと、目を真っ赤にして泣いていたあいつ。
そして……、おれを好きな理由を、瞳を輝かせながら夢中で語るあいつ。
「はあ」
こんなにもぐるぐると考えこんで、あいつのことしか頭に浮かんでこないのは重症だ。
途中、つい先日まで気になっていたはずの女の子にまで、すれ違ったのに。律のことしか考えられない。
もう、認めざるをえないかもしれない。性別とかは、きっと些細な問題だ。
おれも、律のことが――。
*
「なんか今日の千秋、調子悪くね?」
「……わ、わりぃ」
やばい。
バスケ部の練習でこんな凡ミスは滅多にしねえのに、今日のおれは、部員にそう指摘されても仕方がないほどのポンコツだ。さっきから何度もシュートをミスってる。
「おれ、水分なくなったから、ちょっと買ってくるわ」
「はいよ」
休憩時間に体育館を出ると、蒸し暑い空気に身体が包まれた。
律と二人で映画に出かけたあの日から、もうすぐ一週間近くも経つ。
意外なことに、その次の日から、律はなんのアクションも仕掛けてこなかった。
さすがのあいつも、おれの朝練の時間にあわせて家の前で待ち伏せしているようなことはなかったし、同じ学校に通ってるとはいえ、学年が違うからすれ違うことすら滅多にない。
連絡も、あれ以来、一回もきてないし。
なんでおれは、あいつから連絡がきていないことを、気にしているんだろう。
いや、もうそんなのわかってる。
この一週間、会っていない間に、おれの頭の中はずっと律に占拠されていた。
バスケに集中している間以外は、ふとした瞬間に、あいつの笑顔を思い出してしまう。
教室で椎名さんと顔を合わせても、自然な気持ちで、彼女の恋を応援できている自分いる。
二人で一緒に出かけたときに何度も揺れた心は、勘違いじゃなかったって確信してしまった。
早く、もう一度、会いたいな。
それで、おれも律が好きだって、伝えにいきたい。
自分で自分の考えに顔を熱くしながら、校舎の自販機がある場所に向かって進もうとしたそのときだった。
「宇佐美くん。好き」
……⁉
曲がった先は、ちょうど軽音部の部室の目の前で。
おれは、見てしまった。
律が、知らない女子に、制服のネクタイを引っぱられてキスされている瞬間を。
「っ⁉」
キスをされた律の大きく見開かれた瞳と、ばっちり目があって。
一瞬間、時が止まったかのように感じられた。
エッ。
律が、女子に、キスされてる……? しかも、結構な美人っぽい女子に。
頭の中で状況をはっきりと認識した瞬間、おれは、全速力でその場を逃げ出した。
は……?
なに。なんなの。なんなんだよ、あれ……‼
到底、体育館に戻る気になんてなれなかった。
だって、よくわかんねえけど、涙が止まらない。壊れたダムみたいに、ボロボロとあふれてくる。
顔も、心の中も、どうしようもないくらいにぐちゃぐちゃだ。
今までに感じたことのない、どす黒い焔に焼かれたような気持ちでいっぱいで、胸がたまらなく苦しい。
「律のバカっっ‼」
誰も使っていない空き教室に逃げこんで、膝を抱えながらうずくまった。
胸の中だけにとどめてはおけなくて、悪態がつらつらと口から出てしまう。
「バカ、バカ。なんで、女にキスなんかされてんだよ‼ あんなに散々おれに好きだとか言ってきて……、おれの頭は、もうお前でいっぱいなのに。当のお前は、おれなんて色目を使ううちの一人で、結局どうでも良いってことかよ‼」
自分で、自分の言葉に、深く心が傷つく。
こんな気持ちは、知らない。
椎名さんに失恋したときよりもはるかに深い胸の痛みに、涙が一向に止まる気配がなくて。もう部活の休憩時間が終わるってわかっていても、動く気になれなかった。
「千秋‼ やっと見つけたっ」
なんで、追ってくるんだよ。
顔を上げなくても、その声だけで、律が追ってきたのだとわかってしまう。
ついさっきまで、今すぐにでも会いたかったのに。
今は、すこしでも、遠ざけたい。会話をするなんてもってのほかだ。
あえて顔を上げずに、地獄から這いのぼってきたかのような低い声で、牽制する。
「……来るな」
「いやです」
「……おい。おれに、それ以上近寄るな」
「いやだと言っているでしょ! どれだけ心配したと思ってるんですかっ」
はあ? おれのメンタルを失墜させた当のお前が心配とか言うのかよ。そんな権利、一ミリもないくせに!
「っ。お前の顔なんて、見たくねえんだよ。さっきの女子のところに帰れ、バカ律」
ヤケになって、叫んだら。
次の瞬間、律に、身体をふわりと抱きしめられていた。
こんな状況でも、意識している奴からそんな風に触れられたら、胸がドキッとしてしまうし、顔が熱くなってしまう。
「な、なに勝手に触ってんだよ! 離せっ」
「さっきのことは、何度でも謝ります。でも、千秋はたぶん誤解してる」
「謝る? なにを? お前は、おれに謝るようなことをしたのか? おれの気持ちを弄んでたこと?」
どす黒い気持ちが止まらなくなって、言いたいことを全部、投げつければ。
律は、頬をふくらませて、本気で怒ってきた。
「なんで、そんなにわからずやなんですか⁉ 良いですか、僕はさっきの女子とは初めて喋りました。ライブを見て僕に好意を持ったそうだけど、付き合うことはできないって言った直後に、あのおぞましい行動をいきなり取ってきたんですっ。しかも、よりにもよってその場面を、愛しの千秋に見られた‼ わかりますか? 僕は完全に被害者ですよ⁉ そんなこともわからずいじけているなんて、バカは千秋の方です‼」
一気にまくしたてられて、ビックリした。
こんなにも本気で怒っている律を見るのは、初めてかもしれない。
「……悪い」
こいつは、とにかくモテる。すこし冷静になって考えてみれば、その可能性にも気がつけたかもしれない。
律は、嘘は吐いていないだろう。現に、おれを心配して即座に追いかけてきたわけだし、あの女子は、律にとって本当に災難みたいなものだったのかも。
あれ。
もしかしておかしいのは、律と女子がキスしているのを目撃した瞬間に、ありえないほど嫉妬して悪い妄想をふくらませたおれのほう……?
急に、悪態をつきまくってしまったことも、律に抱きしめられていることも恥ずかしくなって、うつむいた。
「バカって言って、悪かった。おれ……、そろそろ、部活に戻るわ」
「それ、本気で言ってますか?」
「えっ。だ、だって、もうとっくに休憩時間終わってるしっ」
おれを抱きしめる律の腕に、力がこもる。
まるで、行くなと言うみたいに。
「ねえ、千秋。そろそろ素直になって」
請うように告げられて、いやがおうにも胸が高鳴る。
「どうして千秋は、泣いているの?」
のぞきこんでくる律の瞳の熱に、思考がチョコレートみたいにどろどろに溶けていく。
もうダメだ。
こんな醜態までさらしておいて、今さら、この気持ちを隠せるわけがない。
「……嫉妬、したんだ」
「うん」
「……律が、おれ以外の誰かとキスをしていたのが、すごく、いやで」
最後まで、言葉を紡ぐことができなかった。
律に、唇を奪われていたから。
「っ」
触れるだけの一瞬のキスだったけど、すごく、胸がドキドキとして心が満たされた。
「嫌じゃなかった?」
たしかめるように尋ねてくる律のことを、とろんと見つめながら、こくりとうなずけば。
律は余裕なさそうに顔をカーッと赤く染めて、顔を手で覆ってしまった。
「……千秋、かわいすぎる」
「か、かわいいって言うな‼」
「わかってます。千秋は、ものすごくかっこいいって、僕はちゃんと知ってるから」
こ、こいつ。おれをキュン死にでもさせる気か……?
「ねえ、千秋。僕のことが好き?」
こつんと額同士をくっつけながら、あざとく聞いてくるなんて、反則以外の何者でもない。
熱に浮かされながら、伝えたかった想いがあふれ出す。
「好き。律と同じ意味で好きだって、やっと気がついた。だから……、甘いことを言うのも、こういうことをするのも、全部おれだけにして」
その後また、今度はもっと深くキスをされて。
いきなりだったからビックリしすぎて、「バカ律‼」って叫ぶことになったのだ。
そして。
これは、おれと律が両想いになってから、後になって聞いた話。
あの日、なかなかバスケ部の練習に戻ってこないおれを心配して、なんとバスケ部の部員たちが総出でおれを探していたらしい。
「一人が、空き教室にいるのを見つけたんだけど、千秋が噂の新入生となんかすごく良い感じだっっていうからー。放っておいて、あとでたっぷり話を聞こうと思ったんだよ」と部員の一人からニヤニヤ笑顔で言われて、恥ずかしさのあまり、また顔が真っ赤になったのだった。【完】