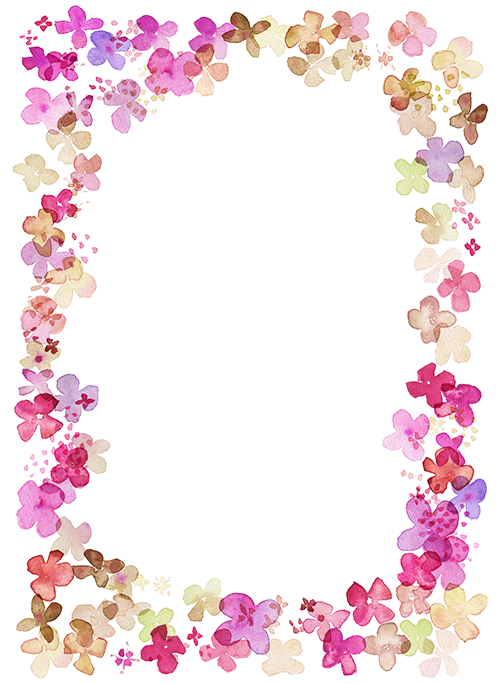祭りの喧騒が、深い森小屋にまで聞こえてくる。
にぎやかな宵闇に目を細めながら、赤毛の女性が問いかけた。
「行かないの?」
「私は仕事があるので」
「こんな日に仕事もないでしょう」
赤毛の女性は肩を竦めて、呆れたように言う。
「今年は長老からも瑠璃を出したのよ? 私たちも、これでようやく人とエルフのしがらみがなくなるって喜んでるのに」
「あなた方は景気が良すぎる。精霊の誇りはどこへやったのです?」
冷ややかに睨みつけた青年は、中性的な容姿に似合わず迫力のある目をしていた。けれど赤毛の女性は怖気づいた様子もなく、鼻で笑って返す。
「なーにが誇りよ。あんたみたいな頭の固いのが多いから、私たちが仲介してるのに。エルフが絶対者って時代は終わったのよ」
「少なくとも人間よりは上だと思いますが」
「馬鹿ね。人間の酒ばっかり飲んだくれてるくせに」
「酒を造るくらいしか人間に取り柄はないでしょう」
ふいに女性は青年の頭を軽くはたいた。
「ゼーラ、何する……」
「固いだけじゃなく、この頭は腐ってるらしいわね。昔のあなたはお馬鹿だったけど、もう少しまともだったわ」
ゼーラは彼に冷ややかな一瞥をくれて、窓の木枠に片足を掛けた。
彼女は窓から空に飛び立ち、翼を動かしながら青年を振り返る。
「じゃ、私は行くわ。篭りたければ一生篭ってなさいよ」
長い赤毛が風に舞い、黄金色の肌を撫でていく。血の色だと忌み嫌われていた紅の翼は、彼女のような妖艶な女にはよく似合っていた。
「愚かなエルフも、瑠璃の道が導いてくれますように」
祭りの文句だけ呟いて、ゼーラはそのまま振り返らずに飛び去っていた。
今日は人もエルフも、「瑠璃の道が導いてくれるように」と言祝ぎ合う。
瑠璃の道と呼ばれるそれは、エルフの聖域と人間たちの国をつないでいるものだ。今日はそれを遠路はるばる辿ってやって来た人間たちに、エルフが歓迎の祭りを開く日。
森小屋に一人残された青年は、窓に手をかけて光の溢れる場所を見やった。その目は祭りを羨んでいるようであり、疎んでいるようでもあった。
彼はエルフの森と人間の世界を分ける、結界の番人。
古くはエルフが迂闊に外へ出て人間に悪さをしないよう、また人間がエルフの宝を奪わないよう、森小屋で見届ける一族だった。
「ルフィーゼ」
名を呼ばれて、彼は振り返る。そこに、鋼のような肉体の壮年の男がいた。
「伯父上。びっくりさせないでください」
長い耳と緑の髪は、エルフの証だ。男は苦笑いして、青年の肩を軽く叩いた。
「お前も随分大人しくなったものだ。昔は本当にやんちゃだったのに」
「仕方ないでしょう。番人が思慮のないエルフでは困ります」
ルフィーゼは、番人一族の中では最も若かった。ルフィーゼの父が早くに亡くなって、まだ少年の頃に父の跡を継いだためだ。
そのため、彼は少年時代のほとんどを番人としての教育に費やして成長した。外の世界には触れずに、深い森の中で何十年も過ごしてきた。
ゆえに老齢のエルフたちの、いささか古い価値観をそのまま受け継いでいた。
彼の伯父はそんなルフィーゼに、もどかしいような顔をして言う。
「番はしていてやるから、今日くらいは羽を伸ばしてこい。飛ぶのにも苦労した子どもの頃とは違うだろう?」
ルフィーゼが目を伏せると、叔父はふっと笑って言った。
「それに、番人が人間嫌いでは困ったものだ。人間の女とでも遊んでこい」
伯父はそう言葉を切ると、片手でルフィーゼを外へ追いやった。
人間だったら樹上の森小屋から真っ逆さまに落下するところだが、彼はエルフだ。
「何が、遊んで来いか……」
ルフィーゼは事も無げに背中から緑色の翼を出すと、軽やかに羽ばたきながらぼやく。
「人など、すぐに死んでしまう弱い生き物ではないか」
彼は番人としては優秀だが、異質な種である人と付き合うことは苦手だった。
ルフィーゼは仕方なくぶらぶらと街道を歩いた。道の脇にはエルフと人間が、呑気に酒を飲み交わしている光景が続く。
「おい、にーちゃん。ちょっと飲まないかい」
「そこのきれーなにーちゃんってば。あそびましょーよ」
既に呂律の回らなくなっている男や、女。エルフや、人間。
「わ、私は結構です」
「やー。ウブな子だねー」
彼は騒がしいだけで気後れしてしまう男だった。それはエルフに対しても同じで、女性は余計に苦手だ。
ルフィーゼはうつむいたままそそくさと横を通り過ぎ、酒の隊商へと向かう。
踊る者たちに、何度もぶつかった。きらきらと輝く瑠璃を身につけて歌う者たちを、眩しくて直視できずに通り過ぎた。
隊商に着くと、なじみの男が明るく声を上げる。
「ルフィーゼさんか。いらっしゃい」
「いつものください」
「はいよ」
まもなくルフィーゼの前に、木の杯になみなみと注がれた酒が置かれた。
瑠璃の道が導いてくれますよう。
エルフと人間の双方から挙がる、明るい声。
人間は瑠璃を司るエルフたちに、敬愛をこめて。
エルフは遠来の友である人間たちに、親愛をこめて。
その中でうつむいて酒をあおる自分は、確かに時代遅れなのかもしれないとルフィーゼは思う。
ルフィーゼは独り言のようにつぶやく。
「夏も終わりですね」
「ああ。そろそろ俺たちもデル・フィーズに帰らないといけないんで」
人間とエルフは、ルフィーゼが子供の頃は犬猿の仲だった。エルフの森の前にデル・フィーズ帝国の軍隊が押し寄せたこともあったし、逆もあった。
老年のエルフには今でも人間を憎む者が多い。深い森の中で老エルフの呪いの言葉を聞いて育ったルフィーゼには、人間への直接の憎しみはないが、恐れる思いはある。
ただ、ルフィーゼが青年となった今は、状況が一変していた。
隊商の男は悪びれずに笑って言う。
「いつも大騒ぎしてすみませんね」
「いえ。若者連中は、あなた方と一緒になって騒いでますし」
ルフィーゼはなんともいえない顔をして返す。
今は、人間とエルフの仲は良好になってしまった。人間と交際する者も多いし、エルフの宝である瑠璃の交易も行っている。
……ちょうど、彼の婚約者であるゼーラのように。ルフィーゼはそれを思って苦笑した。
「またゼーラが寂しがるでしょうね」
夏の終わり、まもなく人間たちは自国へと帰る。隊商の男は肩に力を入れずに答えた。
「ま、来年も来ますから。できればその時まで、ゼーラさんとは結婚しないでくださいよ」
「はは……どうなんでしょう」
ルフィーゼは口の端を下げて笑う。
ゼーラとルフィーゼは幼馴染だ。最近になって結婚話が持ち上がったが、ゼーラもルフィーゼもお互い戸惑っている。
ひどく内向的なルフィーゼを、人間にも親しむゼーラは受け入れがたいのだろう。
ルフィーゼは立ち上がって、銀貨を取り出しながら言う。
「来年には他人になっているかもしれませんね」
代金を払ってから、ルフィーゼは隊商を後にした。
ほてった体に、夏の涼しい風が心地よかった。
「ちょっと飲みすぎたかな」
ふふ、と笑う。いつもしかめ面しか見ていないエルフたちが見たら、病気かと思われるような緩んだ顔だ。
またのんびりと街道を歩く。遠い向こう、人間たちがやってくる、デル・フィーズ帝国まで続くという輝く道を見やる。
「綺麗だな」
ルフィーゼにだって、瑠璃の欠片が詰まった道を愛でる気持ちはある。
「瑠璃の道は、西の彼方に……」
ルフィーゼは、帝国の人間が教えてくれた、どこか郷愁を誘うような歌を口ずさんだ。
――瑠璃の道は、西の彼方に。
エルフの聖地から始まって。
岩壁を走り、森を潜り抜け。
遠い遠い、デル・フィーズへ続く。
結界から魔物がでてきたら、どうするの。
大丈夫。赤羽のロームが助けてくれる。
岩壁には怖い、盗賊がいるよ。
大丈夫。高貴な騎士が、助けてくれる。
こんな長い道、一人じゃ怖くて帰れない。
「……大丈夫」
ぽつりと呟いて、ルフィーゼは森の外れで足を止めた。
「エルフが私を、導いてくれる」
大樹が枝を広げて、静かに佇んでいた。
ルフィーゼはそこに背中をつけて、道の行き着く先を見つめる。
「私と君をつなぐ道……瑠璃の道」
風はまもなく秋の訪れを告げる。エルフたちが森に篭って眠りにつく、長い冬がやって来る。
ただ一本の大樹だけがそびえ立つ、瑠璃の道の終着点。
ルフィーゼはその木陰に座り込み、闇の中で目を閉じていた。
――フィー。
幼い声が耳の奥に響いて、まただとルフィーゼは思う。
森の向こうから、十歳くらいの少女が駆けてくる。
――夏が来たよ。あそぼ、フィー。
その声は、ルフィーゼの心に閉じ込めた記憶を思い起こさせた。
「……ラピ」
瑠璃を名前に持つ少女を呼んで、ルフィーゼは少しの間過去に浸っていた。
ラピはエルフの聖域の外の、小さな家に住んでいた子どもだった。
ルフィーゼも子どもだったその頃、エルフの森近くに人間が住むことは極めて珍しかった。ルフィーゼは詳しく知らないが、人間の国との盟約で、エルフの側近くで保護することになっていたのだそうだ。
黒髪に紫の瞳。エルフに比べると耳が小さく、そばかすがあって、正直ルフィーゼには美人になると思えなかった。だが、紫の瞳が感情の移ろうままに色を変えるのが瑠璃みたいで……ルフィーゼは、妹のように可愛がっていた。
ルフィーゼはよく、ラピを連れてこっそりとエルフの森に連れて行った。
「夜はね、蛍鳥が出るから。本当は近寄っちゃ駄目だけど、ちょっとだけ僕と森へ入って見に行こう」
「ほたるどり?」
「ぴかぴか光る、鳥だよ。大人に見つかると怒られちゃうから、こっそり会いに行くんだ」
ラピは賢い子供だったが、エルフの世界はあまり知らなかった。
燐光を放つ羽を持ち、人語も解する蛍鳥のことも。
人懐っこい性格で優しいエルフの変種、赤羽のロームのことも。
木に埋もれた水晶に、聖域に浮く瑠璃も、見るたび目を輝かせていた。
ラピはある日、ルフィーゼがいつも持っている瑠璃に気づいて言った。
「フィーが首に下げてるの、瑠璃なの?」
「うん。お父さんがお母さんにあげたもの。触ってみる?」
渡した瞬間に、瑠璃は僅かに輝いた。ルフィーゼは驚いて、思わず瑠璃を取り返してしまった。
「反応したってことは、ラピは魔力があるみたいだね。人間には隠しておいた方がいいよ」
「どうして?」
「悪用されちゃうから。悪い人がラピの魔力を搾り取って、悪いことに使うから」
「悪いことってどんなこと?」
無邪気に癖毛を揺らして、彼女は問いかけた。ルフィーゼは声を落として返す。
「戦争、かな。人やエルフを、たくさん殺しちゃうんだ」
そう言ったルフィーゼを見つめて、人間の少女は神妙に頷いた。
森の外に住む彼女と遊ぶことができるのは、夏の間だけだった。
護衛というより監視のような大人がいるだけで、家族もいなかった。ルフィーゼが冬に目覚めるたび、毎年一つずつ、年を取っていた。
「フィーは変わらないね。大きくならないの?」
「ちょっとずつ大きくなるんだ。ラピよりゆっくり大きくなるから、気づかないだろうけど」
初めて会った時、彼女は七歳だった。
その時はルフィーゼが十三歳で、兄妹のように遊ぶことができた。
森を駆け回ったり、洞窟を探検したり。
夏の間中、走り回った輝かしい時間。
ある年のことだった。
「フィー。今年は国に帰ることになったの」
ラピが、十二歳の夏のことだった。
「来年の夏、またエルフの森に来ることができるかは……わからない」
突然の別れに、ルフィーゼは不満を隠さなかった。
「去年、いっぱい遊ぶ計画立てたのに」
ルフィーゼがむっとして言い返すと、ラピはうつむいて泣き出した。
ラピが泣くことはめったになくて、ルフィーゼを慌てさせた。押し殺した泣き声は何かに耐えるようで、とても苦しい泣き方だったから。
ルフィーゼは怒気を収めて、慌てて言った。
「ごめんごめん。大丈夫。計画はまた立てればいいよ。ええと……」
すっかり身長も高くなって、ルフィーゼにあと少しで届くラピ。
来年は追いつかれてしまうかなと、思っていた。
「じゃあ、来年やりたいことを今のうちに考えとこう。ラピ、何がしたい?」
そうしたらラピは顔を上げて、紫の目を輝かせて言った。
「えっとね。私、冒険したいな」
「冒険?」
「うん。エルフの聖地から始まって、岩壁を走って……」
ああ、とルフィーゼは頷いた。瑠璃の道を通ってやって来る商人たちが、節をつけて歌っている、旅の冒険だ。
ルフィーゼはおどけて問いかける。
「魔物がでてきたら?」
「赤羽のロームさんを仲間に加えてね、助けてもらうの」
「盗賊がいるかもしれないよ?」
「立派な騎士さんがね、来てくれるの」
うきうきと語るラピに、ルフィーゼは笑いながら言った。
「あんまりに長い道のりで、怖くなるかもしれないね」
「うん。でも……」
ラピは弾けるように笑って、ルフィーゼの首に後ろから抱きついた。
「フィーがいるもん。そうだよね?」
うん、とルフィーゼは頷いた。
「来年は僕も一緒に冒険に行く。だからラピ、ちゃんとここへ来るんだよ」
西の果て。遥か彼方のデル・フィーズ。
遠い国への冒険物語を思って、笑い合った夏の日々。
二度と帰らない、儚い約束。
「……来なかったくせに」
目を開き、闇の中を見つめるルフィーゼの瞳は暗い。
あれから五十年。ラピがエルフの森に来なくなってから、瞬く間に時は駆けていった。
険悪だった人間とエルフの仲は良好になって。
魔物も減って、盗賊も取り締まられ、安全になった。
瑠璃の道を通ってやってくる人間は加速的に増えていった。
それでも、ラピは二度と戻って来なかった。
「もう、私のことも忘れたかな」
本名すら定かでない、素性のわからない人間の子供。
あの頃はまだ、エルフと人間が憎み合う時期だった。物珍しさで一緒に遊んだだけで、成長したら魔法という異質な力を持つ一族が怖くなったのかもしれない。
風は、今も西から吹いてくる。遠いデル・フィーズに続く道から。
祭りの喧騒は消えていた。屋台の光もなくなり、皆が寝静まる時に差し掛かったらしい。
ルフィーゼは軽く土を払い、木陰から立ち上がった。
「こんな真夜中に、木陰に座らなくても」
必要があるのは、真夏の日中だけ。
ラピが森の向こうから駆けてくるのを待ち侘びていた、遥か昔の夏の間だけだ。
「……帰ろう」
ルフィーゼは踵を返し、帰路を辿ろうと闇の空を見上げる。
そのときふいに、背後に何かが近づく気配を感じた。
気配を消して近づくことに、まともな理由があるとは思えない。
ルフィーゼは瞬時に振り返って、手元に炎の塊を作り出す。
音を立てて炎は四方八方へ散り、辺りは瞬時に明るく照らされた。
「失礼。驚かせてしまいましたか」
闇夜に流れるように美しい声音が響いた。
ルフィーゼはそのとき見てしまった。その人物の持つ、瑠璃のように艶やかな紫の瞳。
「な……」
それは忘れようとしても忘れられない、あの少女の持つ色だった。
声の主は、二十代ほどの黒髪の女性だった。隊商の者たちのように質素な旅装束をまとっていた。
「私を見て覚えがあるのなら、やはりあなたですね。ルフィーゼさん」
女性は、闇に解けるような静かな声で空気を震わす。
馬鹿なとルフィーゼは呟く。
あれから五十年。彼女がこんなに若いはずはない。人は、すぐに年老いて死ぬのだから。
ルフィーゼは首を振りながら、引き寄せられるように女性に歩み寄る。
「あなたは、何者だ……?」
「ラピリア様の縁者です。あなたにお願いがあって参りました」
女性は腰を折って礼を取ると、ルフィーゼに言葉をかけた。
「ラピリア様……あなたがラピと呼ぶ少女を、王座まで連れてきていただきたいのです」
燐光が彼女の内部から生まれて、段々と女性の輪郭を覆いつくしていく。
何かの呪文のように、女性は小声で繰り返す。
「そうでなければ、今の平和は失われてしまう。どうか」
「ま、待ってくれっ!」
ルフィーゼは思わず、力いっぱい女性を引き寄せた。
温かい。この人は、まだ生きている。
もしかしたら自分は夢を見ているのではないかと、ルフィーゼは自問する。
そしてすぐに、その問いを捨て去る。
「あなたの言うことはわからない! ……けれどラピとは約束をしている!」
ルフィーゼは光で覆われて、もはやどこが何かわからない女性の体を抱きしめた。
「瑠璃の道を辿って……デル・フィーズに行くと約束したんだ!」
あの夏、ラピが十三歳になるはずだった夏は、ルフィーゼと彼女は共に過ごすことができなかった。
けれどずっと望んでいた。毎年待っていた。
一年たりとも、ルフィーゼはラピとの約束を忘れたことなどなかった。
「瑠璃の道があなたを導いてくれるよう」
女性が、小さく祭りの文句を呟いた。
「……さあ、最後の夏を始めましょう」
女性の姿が歪み、ルフィーゼの姿もまた歪んだ。
二人は暗闇の中の青い渦に吸い込まれていく。
落ちていく時間は、ルフィーゼにとって永遠のようにも思えた。
けれどやがて止まった闇の底で、ルフィーゼは自分の名前を聞いた気がした。
誰か、懐かしい人が呼んでいる。
呼び声を頼りに少しずつ上っていくと、そこは光があふれる真昼だった。
水の流れる音もまた懐かしい。
甘くて芳しい香りのする、聖水の音だ。
ふいに冷たい感触が彼の体を包みこんだ。
「ひゃっ」
間抜けな声を上げて、ルフィーゼは飛び起きた。
ぱちぱちと瞬きをして、身震いをする。
「よっ、起きたか」
目の前に木桶を抱えて立っていた青年に、ルフィーゼは思わず目を見開く。
「……ち、父上っ?」
「父上だぁ?」
エルフにしては短い緑髪を首の後ろで括り、戦士を思わせる鋭い眼差しは、今は少し怪訝な色を帯びていた。
「おとうさん、怖いよーとかぴーぴー言ってたくせに。お前、本っ当に飛ぶの下手くそだな。エルフが木から落ちるのなんて、俺は生まれて初めて見たぞ」
「い、いやその……」
彼は腰に手を当てて、びしょ濡れのルフィーゼを見下ろす。
ルフィーゼはそれをまじまじと見つめて、信じられないといったように首を振った。
「父上は、亡くなったんじゃ……」
「おい、不吉なこと言うんじゃねぇよ。お前変なところ打ったな?」
彼は屈んで、節くれだった手でルフィーゼの頭をガシガシと押さえる。
「んー。特に変なとこはないと思うがね」
「あ、あの……」
ルフィーゼはふいに泣きたくなるような思いでつぶやく。
「ん?」
「ほんとに、父上ですよね」
「ああ?」
ルフィーゼの問いに、彼は笑って猫のように目を細める。
「ふん。じゃ、お前は誰の子だ?」
「戦士ウィリと、人形師エレーナの子供です……」
「なら俺の子だ。俺の馬鹿息子は一人しかいない。ルフィーゼ」
ルフィーゼの頭を叩いて、ウィリは緑の双眸でルフィーゼを呼んだ。
呆然と父親を見上げていたルフィーゼは、やがて泣き笑いのような顔になって、こくこくと頷く。
「そう……だ。お父さんが簡単に死ぬわけない。お父さんは強いもん」
「何だ、どうした?」
ルフィーゼはぎゅっとウィリの袖を握り締める。ルフィーゼの手が震えているのを見て、ウィリは眉を寄せた。
「やっぱり変なとこ打ったな。今日の飛行練習はここまでにするか」
ウィリはぽんぽんとルフィーゼの頭を叩き、彼の後ろへ目をやる。
「せっかくの夏をウチの馬鹿に費やさせて悪いなぁ」
「そんなこと!」
慌てて言葉を返したのは、十台前半の少女の声だ。
「フィーが、一生懸命飛ぼうとしてるから。つい声が掛けられなくて」
彼女はひょっこりとウィリの後ろから首だけ出して、ルフィーゼに笑いかける。
「大丈夫。もうちょっとで飛べるよ、フィー」
柔らかそうな、肩までの黒髪。
そばかすはだいぶ消えて、ほんのり紅く染まった頬。
……その中で紫の、鮮やかな瞳が輝いていた。
ぴちゃんと聖水の鳴る音が響いた。
ルフィーゼの目が大きく見開かれる。
「……ラピ」
聖水が木々から流れ出し、螺旋状に空へと昇っていく。
聖水の頂点に、エルフたちの命を司る、巨大な瑠璃が煌めきながら回っている。
「約束通り今年は早く来たよ。夏の冒険に、一緒に行くんだよね」
新緑の木々と透き通った聖水が渦巻く、そこはエルフの聖域だ。
「私、十三歳になったんだよ。フィーと背丈、おんなじになったね」
二度と姿を見ることがなかった、十三歳のラピ。
失われた時が、少年の前に広がっていた。
にぎやかな宵闇に目を細めながら、赤毛の女性が問いかけた。
「行かないの?」
「私は仕事があるので」
「こんな日に仕事もないでしょう」
赤毛の女性は肩を竦めて、呆れたように言う。
「今年は長老からも瑠璃を出したのよ? 私たちも、これでようやく人とエルフのしがらみがなくなるって喜んでるのに」
「あなた方は景気が良すぎる。精霊の誇りはどこへやったのです?」
冷ややかに睨みつけた青年は、中性的な容姿に似合わず迫力のある目をしていた。けれど赤毛の女性は怖気づいた様子もなく、鼻で笑って返す。
「なーにが誇りよ。あんたみたいな頭の固いのが多いから、私たちが仲介してるのに。エルフが絶対者って時代は終わったのよ」
「少なくとも人間よりは上だと思いますが」
「馬鹿ね。人間の酒ばっかり飲んだくれてるくせに」
「酒を造るくらいしか人間に取り柄はないでしょう」
ふいに女性は青年の頭を軽くはたいた。
「ゼーラ、何する……」
「固いだけじゃなく、この頭は腐ってるらしいわね。昔のあなたはお馬鹿だったけど、もう少しまともだったわ」
ゼーラは彼に冷ややかな一瞥をくれて、窓の木枠に片足を掛けた。
彼女は窓から空に飛び立ち、翼を動かしながら青年を振り返る。
「じゃ、私は行くわ。篭りたければ一生篭ってなさいよ」
長い赤毛が風に舞い、黄金色の肌を撫でていく。血の色だと忌み嫌われていた紅の翼は、彼女のような妖艶な女にはよく似合っていた。
「愚かなエルフも、瑠璃の道が導いてくれますように」
祭りの文句だけ呟いて、ゼーラはそのまま振り返らずに飛び去っていた。
今日は人もエルフも、「瑠璃の道が導いてくれるように」と言祝ぎ合う。
瑠璃の道と呼ばれるそれは、エルフの聖域と人間たちの国をつないでいるものだ。今日はそれを遠路はるばる辿ってやって来た人間たちに、エルフが歓迎の祭りを開く日。
森小屋に一人残された青年は、窓に手をかけて光の溢れる場所を見やった。その目は祭りを羨んでいるようであり、疎んでいるようでもあった。
彼はエルフの森と人間の世界を分ける、結界の番人。
古くはエルフが迂闊に外へ出て人間に悪さをしないよう、また人間がエルフの宝を奪わないよう、森小屋で見届ける一族だった。
「ルフィーゼ」
名を呼ばれて、彼は振り返る。そこに、鋼のような肉体の壮年の男がいた。
「伯父上。びっくりさせないでください」
長い耳と緑の髪は、エルフの証だ。男は苦笑いして、青年の肩を軽く叩いた。
「お前も随分大人しくなったものだ。昔は本当にやんちゃだったのに」
「仕方ないでしょう。番人が思慮のないエルフでは困ります」
ルフィーゼは、番人一族の中では最も若かった。ルフィーゼの父が早くに亡くなって、まだ少年の頃に父の跡を継いだためだ。
そのため、彼は少年時代のほとんどを番人としての教育に費やして成長した。外の世界には触れずに、深い森の中で何十年も過ごしてきた。
ゆえに老齢のエルフたちの、いささか古い価値観をそのまま受け継いでいた。
彼の伯父はそんなルフィーゼに、もどかしいような顔をして言う。
「番はしていてやるから、今日くらいは羽を伸ばしてこい。飛ぶのにも苦労した子どもの頃とは違うだろう?」
ルフィーゼが目を伏せると、叔父はふっと笑って言った。
「それに、番人が人間嫌いでは困ったものだ。人間の女とでも遊んでこい」
伯父はそう言葉を切ると、片手でルフィーゼを外へ追いやった。
人間だったら樹上の森小屋から真っ逆さまに落下するところだが、彼はエルフだ。
「何が、遊んで来いか……」
ルフィーゼは事も無げに背中から緑色の翼を出すと、軽やかに羽ばたきながらぼやく。
「人など、すぐに死んでしまう弱い生き物ではないか」
彼は番人としては優秀だが、異質な種である人と付き合うことは苦手だった。
ルフィーゼは仕方なくぶらぶらと街道を歩いた。道の脇にはエルフと人間が、呑気に酒を飲み交わしている光景が続く。
「おい、にーちゃん。ちょっと飲まないかい」
「そこのきれーなにーちゃんってば。あそびましょーよ」
既に呂律の回らなくなっている男や、女。エルフや、人間。
「わ、私は結構です」
「やー。ウブな子だねー」
彼は騒がしいだけで気後れしてしまう男だった。それはエルフに対しても同じで、女性は余計に苦手だ。
ルフィーゼはうつむいたままそそくさと横を通り過ぎ、酒の隊商へと向かう。
踊る者たちに、何度もぶつかった。きらきらと輝く瑠璃を身につけて歌う者たちを、眩しくて直視できずに通り過ぎた。
隊商に着くと、なじみの男が明るく声を上げる。
「ルフィーゼさんか。いらっしゃい」
「いつものください」
「はいよ」
まもなくルフィーゼの前に、木の杯になみなみと注がれた酒が置かれた。
瑠璃の道が導いてくれますよう。
エルフと人間の双方から挙がる、明るい声。
人間は瑠璃を司るエルフたちに、敬愛をこめて。
エルフは遠来の友である人間たちに、親愛をこめて。
その中でうつむいて酒をあおる自分は、確かに時代遅れなのかもしれないとルフィーゼは思う。
ルフィーゼは独り言のようにつぶやく。
「夏も終わりですね」
「ああ。そろそろ俺たちもデル・フィーズに帰らないといけないんで」
人間とエルフは、ルフィーゼが子供の頃は犬猿の仲だった。エルフの森の前にデル・フィーズ帝国の軍隊が押し寄せたこともあったし、逆もあった。
老年のエルフには今でも人間を憎む者が多い。深い森の中で老エルフの呪いの言葉を聞いて育ったルフィーゼには、人間への直接の憎しみはないが、恐れる思いはある。
ただ、ルフィーゼが青年となった今は、状況が一変していた。
隊商の男は悪びれずに笑って言う。
「いつも大騒ぎしてすみませんね」
「いえ。若者連中は、あなた方と一緒になって騒いでますし」
ルフィーゼはなんともいえない顔をして返す。
今は、人間とエルフの仲は良好になってしまった。人間と交際する者も多いし、エルフの宝である瑠璃の交易も行っている。
……ちょうど、彼の婚約者であるゼーラのように。ルフィーゼはそれを思って苦笑した。
「またゼーラが寂しがるでしょうね」
夏の終わり、まもなく人間たちは自国へと帰る。隊商の男は肩に力を入れずに答えた。
「ま、来年も来ますから。できればその時まで、ゼーラさんとは結婚しないでくださいよ」
「はは……どうなんでしょう」
ルフィーゼは口の端を下げて笑う。
ゼーラとルフィーゼは幼馴染だ。最近になって結婚話が持ち上がったが、ゼーラもルフィーゼもお互い戸惑っている。
ひどく内向的なルフィーゼを、人間にも親しむゼーラは受け入れがたいのだろう。
ルフィーゼは立ち上がって、銀貨を取り出しながら言う。
「来年には他人になっているかもしれませんね」
代金を払ってから、ルフィーゼは隊商を後にした。
ほてった体に、夏の涼しい風が心地よかった。
「ちょっと飲みすぎたかな」
ふふ、と笑う。いつもしかめ面しか見ていないエルフたちが見たら、病気かと思われるような緩んだ顔だ。
またのんびりと街道を歩く。遠い向こう、人間たちがやってくる、デル・フィーズ帝国まで続くという輝く道を見やる。
「綺麗だな」
ルフィーゼにだって、瑠璃の欠片が詰まった道を愛でる気持ちはある。
「瑠璃の道は、西の彼方に……」
ルフィーゼは、帝国の人間が教えてくれた、どこか郷愁を誘うような歌を口ずさんだ。
――瑠璃の道は、西の彼方に。
エルフの聖地から始まって。
岩壁を走り、森を潜り抜け。
遠い遠い、デル・フィーズへ続く。
結界から魔物がでてきたら、どうするの。
大丈夫。赤羽のロームが助けてくれる。
岩壁には怖い、盗賊がいるよ。
大丈夫。高貴な騎士が、助けてくれる。
こんな長い道、一人じゃ怖くて帰れない。
「……大丈夫」
ぽつりと呟いて、ルフィーゼは森の外れで足を止めた。
「エルフが私を、導いてくれる」
大樹が枝を広げて、静かに佇んでいた。
ルフィーゼはそこに背中をつけて、道の行き着く先を見つめる。
「私と君をつなぐ道……瑠璃の道」
風はまもなく秋の訪れを告げる。エルフたちが森に篭って眠りにつく、長い冬がやって来る。
ただ一本の大樹だけがそびえ立つ、瑠璃の道の終着点。
ルフィーゼはその木陰に座り込み、闇の中で目を閉じていた。
――フィー。
幼い声が耳の奥に響いて、まただとルフィーゼは思う。
森の向こうから、十歳くらいの少女が駆けてくる。
――夏が来たよ。あそぼ、フィー。
その声は、ルフィーゼの心に閉じ込めた記憶を思い起こさせた。
「……ラピ」
瑠璃を名前に持つ少女を呼んで、ルフィーゼは少しの間過去に浸っていた。
ラピはエルフの聖域の外の、小さな家に住んでいた子どもだった。
ルフィーゼも子どもだったその頃、エルフの森近くに人間が住むことは極めて珍しかった。ルフィーゼは詳しく知らないが、人間の国との盟約で、エルフの側近くで保護することになっていたのだそうだ。
黒髪に紫の瞳。エルフに比べると耳が小さく、そばかすがあって、正直ルフィーゼには美人になると思えなかった。だが、紫の瞳が感情の移ろうままに色を変えるのが瑠璃みたいで……ルフィーゼは、妹のように可愛がっていた。
ルフィーゼはよく、ラピを連れてこっそりとエルフの森に連れて行った。
「夜はね、蛍鳥が出るから。本当は近寄っちゃ駄目だけど、ちょっとだけ僕と森へ入って見に行こう」
「ほたるどり?」
「ぴかぴか光る、鳥だよ。大人に見つかると怒られちゃうから、こっそり会いに行くんだ」
ラピは賢い子供だったが、エルフの世界はあまり知らなかった。
燐光を放つ羽を持ち、人語も解する蛍鳥のことも。
人懐っこい性格で優しいエルフの変種、赤羽のロームのことも。
木に埋もれた水晶に、聖域に浮く瑠璃も、見るたび目を輝かせていた。
ラピはある日、ルフィーゼがいつも持っている瑠璃に気づいて言った。
「フィーが首に下げてるの、瑠璃なの?」
「うん。お父さんがお母さんにあげたもの。触ってみる?」
渡した瞬間に、瑠璃は僅かに輝いた。ルフィーゼは驚いて、思わず瑠璃を取り返してしまった。
「反応したってことは、ラピは魔力があるみたいだね。人間には隠しておいた方がいいよ」
「どうして?」
「悪用されちゃうから。悪い人がラピの魔力を搾り取って、悪いことに使うから」
「悪いことってどんなこと?」
無邪気に癖毛を揺らして、彼女は問いかけた。ルフィーゼは声を落として返す。
「戦争、かな。人やエルフを、たくさん殺しちゃうんだ」
そう言ったルフィーゼを見つめて、人間の少女は神妙に頷いた。
森の外に住む彼女と遊ぶことができるのは、夏の間だけだった。
護衛というより監視のような大人がいるだけで、家族もいなかった。ルフィーゼが冬に目覚めるたび、毎年一つずつ、年を取っていた。
「フィーは変わらないね。大きくならないの?」
「ちょっとずつ大きくなるんだ。ラピよりゆっくり大きくなるから、気づかないだろうけど」
初めて会った時、彼女は七歳だった。
その時はルフィーゼが十三歳で、兄妹のように遊ぶことができた。
森を駆け回ったり、洞窟を探検したり。
夏の間中、走り回った輝かしい時間。
ある年のことだった。
「フィー。今年は国に帰ることになったの」
ラピが、十二歳の夏のことだった。
「来年の夏、またエルフの森に来ることができるかは……わからない」
突然の別れに、ルフィーゼは不満を隠さなかった。
「去年、いっぱい遊ぶ計画立てたのに」
ルフィーゼがむっとして言い返すと、ラピはうつむいて泣き出した。
ラピが泣くことはめったになくて、ルフィーゼを慌てさせた。押し殺した泣き声は何かに耐えるようで、とても苦しい泣き方だったから。
ルフィーゼは怒気を収めて、慌てて言った。
「ごめんごめん。大丈夫。計画はまた立てればいいよ。ええと……」
すっかり身長も高くなって、ルフィーゼにあと少しで届くラピ。
来年は追いつかれてしまうかなと、思っていた。
「じゃあ、来年やりたいことを今のうちに考えとこう。ラピ、何がしたい?」
そうしたらラピは顔を上げて、紫の目を輝かせて言った。
「えっとね。私、冒険したいな」
「冒険?」
「うん。エルフの聖地から始まって、岩壁を走って……」
ああ、とルフィーゼは頷いた。瑠璃の道を通ってやって来る商人たちが、節をつけて歌っている、旅の冒険だ。
ルフィーゼはおどけて問いかける。
「魔物がでてきたら?」
「赤羽のロームさんを仲間に加えてね、助けてもらうの」
「盗賊がいるかもしれないよ?」
「立派な騎士さんがね、来てくれるの」
うきうきと語るラピに、ルフィーゼは笑いながら言った。
「あんまりに長い道のりで、怖くなるかもしれないね」
「うん。でも……」
ラピは弾けるように笑って、ルフィーゼの首に後ろから抱きついた。
「フィーがいるもん。そうだよね?」
うん、とルフィーゼは頷いた。
「来年は僕も一緒に冒険に行く。だからラピ、ちゃんとここへ来るんだよ」
西の果て。遥か彼方のデル・フィーズ。
遠い国への冒険物語を思って、笑い合った夏の日々。
二度と帰らない、儚い約束。
「……来なかったくせに」
目を開き、闇の中を見つめるルフィーゼの瞳は暗い。
あれから五十年。ラピがエルフの森に来なくなってから、瞬く間に時は駆けていった。
険悪だった人間とエルフの仲は良好になって。
魔物も減って、盗賊も取り締まられ、安全になった。
瑠璃の道を通ってやってくる人間は加速的に増えていった。
それでも、ラピは二度と戻って来なかった。
「もう、私のことも忘れたかな」
本名すら定かでない、素性のわからない人間の子供。
あの頃はまだ、エルフと人間が憎み合う時期だった。物珍しさで一緒に遊んだだけで、成長したら魔法という異質な力を持つ一族が怖くなったのかもしれない。
風は、今も西から吹いてくる。遠いデル・フィーズに続く道から。
祭りの喧騒は消えていた。屋台の光もなくなり、皆が寝静まる時に差し掛かったらしい。
ルフィーゼは軽く土を払い、木陰から立ち上がった。
「こんな真夜中に、木陰に座らなくても」
必要があるのは、真夏の日中だけ。
ラピが森の向こうから駆けてくるのを待ち侘びていた、遥か昔の夏の間だけだ。
「……帰ろう」
ルフィーゼは踵を返し、帰路を辿ろうと闇の空を見上げる。
そのときふいに、背後に何かが近づく気配を感じた。
気配を消して近づくことに、まともな理由があるとは思えない。
ルフィーゼは瞬時に振り返って、手元に炎の塊を作り出す。
音を立てて炎は四方八方へ散り、辺りは瞬時に明るく照らされた。
「失礼。驚かせてしまいましたか」
闇夜に流れるように美しい声音が響いた。
ルフィーゼはそのとき見てしまった。その人物の持つ、瑠璃のように艶やかな紫の瞳。
「な……」
それは忘れようとしても忘れられない、あの少女の持つ色だった。
声の主は、二十代ほどの黒髪の女性だった。隊商の者たちのように質素な旅装束をまとっていた。
「私を見て覚えがあるのなら、やはりあなたですね。ルフィーゼさん」
女性は、闇に解けるような静かな声で空気を震わす。
馬鹿なとルフィーゼは呟く。
あれから五十年。彼女がこんなに若いはずはない。人は、すぐに年老いて死ぬのだから。
ルフィーゼは首を振りながら、引き寄せられるように女性に歩み寄る。
「あなたは、何者だ……?」
「ラピリア様の縁者です。あなたにお願いがあって参りました」
女性は腰を折って礼を取ると、ルフィーゼに言葉をかけた。
「ラピリア様……あなたがラピと呼ぶ少女を、王座まで連れてきていただきたいのです」
燐光が彼女の内部から生まれて、段々と女性の輪郭を覆いつくしていく。
何かの呪文のように、女性は小声で繰り返す。
「そうでなければ、今の平和は失われてしまう。どうか」
「ま、待ってくれっ!」
ルフィーゼは思わず、力いっぱい女性を引き寄せた。
温かい。この人は、まだ生きている。
もしかしたら自分は夢を見ているのではないかと、ルフィーゼは自問する。
そしてすぐに、その問いを捨て去る。
「あなたの言うことはわからない! ……けれどラピとは約束をしている!」
ルフィーゼは光で覆われて、もはやどこが何かわからない女性の体を抱きしめた。
「瑠璃の道を辿って……デル・フィーズに行くと約束したんだ!」
あの夏、ラピが十三歳になるはずだった夏は、ルフィーゼと彼女は共に過ごすことができなかった。
けれどずっと望んでいた。毎年待っていた。
一年たりとも、ルフィーゼはラピとの約束を忘れたことなどなかった。
「瑠璃の道があなたを導いてくれるよう」
女性が、小さく祭りの文句を呟いた。
「……さあ、最後の夏を始めましょう」
女性の姿が歪み、ルフィーゼの姿もまた歪んだ。
二人は暗闇の中の青い渦に吸い込まれていく。
落ちていく時間は、ルフィーゼにとって永遠のようにも思えた。
けれどやがて止まった闇の底で、ルフィーゼは自分の名前を聞いた気がした。
誰か、懐かしい人が呼んでいる。
呼び声を頼りに少しずつ上っていくと、そこは光があふれる真昼だった。
水の流れる音もまた懐かしい。
甘くて芳しい香りのする、聖水の音だ。
ふいに冷たい感触が彼の体を包みこんだ。
「ひゃっ」
間抜けな声を上げて、ルフィーゼは飛び起きた。
ぱちぱちと瞬きをして、身震いをする。
「よっ、起きたか」
目の前に木桶を抱えて立っていた青年に、ルフィーゼは思わず目を見開く。
「……ち、父上っ?」
「父上だぁ?」
エルフにしては短い緑髪を首の後ろで括り、戦士を思わせる鋭い眼差しは、今は少し怪訝な色を帯びていた。
「おとうさん、怖いよーとかぴーぴー言ってたくせに。お前、本っ当に飛ぶの下手くそだな。エルフが木から落ちるのなんて、俺は生まれて初めて見たぞ」
「い、いやその……」
彼は腰に手を当てて、びしょ濡れのルフィーゼを見下ろす。
ルフィーゼはそれをまじまじと見つめて、信じられないといったように首を振った。
「父上は、亡くなったんじゃ……」
「おい、不吉なこと言うんじゃねぇよ。お前変なところ打ったな?」
彼は屈んで、節くれだった手でルフィーゼの頭をガシガシと押さえる。
「んー。特に変なとこはないと思うがね」
「あ、あの……」
ルフィーゼはふいに泣きたくなるような思いでつぶやく。
「ん?」
「ほんとに、父上ですよね」
「ああ?」
ルフィーゼの問いに、彼は笑って猫のように目を細める。
「ふん。じゃ、お前は誰の子だ?」
「戦士ウィリと、人形師エレーナの子供です……」
「なら俺の子だ。俺の馬鹿息子は一人しかいない。ルフィーゼ」
ルフィーゼの頭を叩いて、ウィリは緑の双眸でルフィーゼを呼んだ。
呆然と父親を見上げていたルフィーゼは、やがて泣き笑いのような顔になって、こくこくと頷く。
「そう……だ。お父さんが簡単に死ぬわけない。お父さんは強いもん」
「何だ、どうした?」
ルフィーゼはぎゅっとウィリの袖を握り締める。ルフィーゼの手が震えているのを見て、ウィリは眉を寄せた。
「やっぱり変なとこ打ったな。今日の飛行練習はここまでにするか」
ウィリはぽんぽんとルフィーゼの頭を叩き、彼の後ろへ目をやる。
「せっかくの夏をウチの馬鹿に費やさせて悪いなぁ」
「そんなこと!」
慌てて言葉を返したのは、十台前半の少女の声だ。
「フィーが、一生懸命飛ぼうとしてるから。つい声が掛けられなくて」
彼女はひょっこりとウィリの後ろから首だけ出して、ルフィーゼに笑いかける。
「大丈夫。もうちょっとで飛べるよ、フィー」
柔らかそうな、肩までの黒髪。
そばかすはだいぶ消えて、ほんのり紅く染まった頬。
……その中で紫の、鮮やかな瞳が輝いていた。
ぴちゃんと聖水の鳴る音が響いた。
ルフィーゼの目が大きく見開かれる。
「……ラピ」
聖水が木々から流れ出し、螺旋状に空へと昇っていく。
聖水の頂点に、エルフたちの命を司る、巨大な瑠璃が煌めきながら回っている。
「約束通り今年は早く来たよ。夏の冒険に、一緒に行くんだよね」
新緑の木々と透き通った聖水が渦巻く、そこはエルフの聖域だ。
「私、十三歳になったんだよ。フィーと背丈、おんなじになったね」
二度と姿を見ることがなかった、十三歳のラピ。
失われた時が、少年の前に広がっていた。