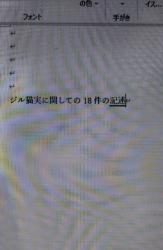[3]
「実験です」
K君は大好物だというガトーショコラを前にし、口許を綻ばせたまま私の質問に応じた。

(※イメージ 引用:Pixabay)
全国ツアー開催中の秋の終わりに、多忙な合間を縫って彼と会ったのは、M君への取材の際と同様に、レーベル事務所が構える下北沢だった。平日の閑散としたそのカフェは週末には名物らしいナポリタンとスイーツを求める女性のふたり連れやカップルで賑わい、夜には音楽好きで溢れるミュージックバーになる。待ち合わせより少し遅れてやってきた彼は黒いシースルーのハイネックとタランチュラのような柄のカーディガン、膝に大きな穴の空いたダメージジーンズを細身の身体に纏った姿で、謝罪もそこそこに着席し、嬉しいです、とにっこり微笑んだ。
「███さんとふたりでお話したいって、ずっと思ってたから」
それには概ね同意だが、私は本心では、もう少し別の話題について話を聞きたいと思っていた。たとえば、楽曲の制作秘話。自身の音楽的ルーツ。有り体な内容のインタビューの方が、どれほど嬉しかったろう。
私は彼に対して以前より、バンドメンバーのなかでも特に興味深い人物だと感じていた。才気溢れるメインコンポーザーであり、ステージではベースだけでなくキーボードやシンセサイザーなども演奏し、自身もボーカルを執る。トラックメイカーでもある彼は楽曲のなかでは雄弁でありながら、その人物像はどことなく浮世離れした、いわゆるミステリアスなタイプだった。SNSの更新も少なく、過去のインタビューに目を通しても言葉数は多くない。しかし時折紡ぐ言葉は作詞と同様不思議な求心力を持っており、その独特な存在感に注目しているというファンも多いようだった。
遠慮がちに注文した好物を思いのほか大きくフォークで掬うと、口許に落ちかかる金髪の後れ毛を耳にかけて大口を開ける。数え切れないほどの数のピアスが、鋭い光で目を射る。
褐色の塊をゆっくりと口に運ぶ彼に、M君から聞いた話を簡単にまとめて伝えると、彼は驚いたような表情を浮かべたのち、苦笑いの混じった表情で喉仏を上下させた。
「あいつ、そんなこと言ってたんですか!?」
フフ、と肩を揺らして小さく笑うと、彼はあっさりと、盗作に気づいていたことを認めた。何故件の音源をM君に聴かせたのか、という質問に対しては、まあ多少は、痛い目に遭えばいいのにって思ってはいましたけど、と、さもM君の行為へのささやかな仕返しであったかのような物言いをする。
しかし彼は、でも本当の理由はそうではなくて、と続けた。
「実験のつもりだったんです」
その言葉の真意を測りかねた私は、まず順を追った説明を求めた。件の睡眠用BGMを制作するに至った経緯、そして、それをM君に薦めた「本当の理由」について。
M君が聞いていた通り、K君は学生時代の先輩に依頼を受け、アルバイトとしてリラクゼーション音源を制作していたのだという。作業の内容は、現在通信教育で臨床心理学の勉強をしているという先輩――依頼者が予め制作した、一定の周波数を持つ単調な音源をベース音として使用し、耳馴染みのいいインストゥルメンタルミュージックに仕上げるというものだった。本数は全部で10本。耳馴染みが良ければ盛り上がりも上手い構成も要らない、シンプルなものでいいとの依頼だったようだが、K君は「プロ意識が許さなかった」と言う。
「どうせやるならもっと美しくて、聴いてて楽しい方がいいじゃないですか。なので、自分の好きなようにやることにしたんです。『提供した音をベースに使ってくれれば好きにしていい』とは最初から言われてましたし。それでね、ちゃんとテーマも設けて、1本の音源のなかでストーリーも意識したりして」
テーマは何だったのかと問うと、彼は重めの前髪の奥の瞳を輝かせて、夢日記です、と答えた。
「自分が過去に見た夢に着想を得て作ってみようかなって。夢を記録している日記っていう体で。だからタイトルも日付に統一して。日付自体には特に意味はなくて、架空の人物の夢日記をイメージしているんです」
私は、胸に立ち込める嫌な予感を打ち消すように、そういえば夢日記つけてるって仰ってましたもんね、と返した。彼は覚えててくれたんですか、と表情を輝かせる。
「依頼通り10本作って、先輩も喜んでくれて。全部聴いてみたけど絶対収益化できるよ、お前に頼んで良かった、って言ってもらえたんですけど。
でも、そのひと月後ぐらいかなあ。ネットで話題になってたこと、あったじゃないですか。ほら、あの、自殺したひとたち10人が、同じチャンネルの睡眠用BGM聴いてたっていう話。たった10本しか動画が公開されてないチャンネルで、登録者数も少ないのに、何人も同じ動画を観ているのはおかしいって。
あの動画、先輩のチャンネルの動画なんです。つまり、僕が作った音源」
例の噂に驚いた先輩は、動画をすぐに非公開にした。初めはどうせ偶然だろうと気に留めないように努めていたようだが、噂が拡散されるたびに視聴数が増えていき、単なる噂だと無視できなくなってしまったのだという。
悪い予感が、どんどんと輪郭を伴っていく。乾いた唇を紅茶で潤してから、その先輩は今はどうされているんですか、と問うと、K君は表情ひとつ変えずに答えた。
「亡くなりました」
思わず言葉を失う。すると、彼は失笑し、すみません、と謝罪した。
「悪い冗談でしたね。嘘です。全然健在ですよ。今でも時々連絡取り合ったりしています。
でもね、最近はちょっと塞ぎ込んじゃって、音楽もやってないみたいなんですよね」
そういえば、とK君は紅茶に少し口をつけて続けた。
「そういえば、先輩も悪夢をよく見るって言ってたな、あの音源作ってた頃」
なんでも、先輩はK君の作った音源をチェックしたり調整したりといった作業をしている間、連日悪夢を見続けていて寝不足だ、と零していたのだという。たとえば、雑踏に踏み殺される蟻になる夢。小川のある山の中で遭難する夢。そして、真っ暗な小部屋に閉じ込められた、巨大な虫の姿になってしまう夢。

(※イメージ)
私は、K君の夢日記を読んだことがあった。利用者数の決して多くないブログサービスで開設されたそのアカウントは、これまでにたった一度きり、SNSの24時間で消えてしまうリール動画にのみリンクが掲載された。アカウント名は彼の生年月日。私のような、一部のディープファンしか知らないようなアカウント。
そこに記録され続けていたのは、全てが悪夢だった。想像するだけでも悍ましい夢たち――踏み殺される蟻になったり、暗い山中で迷ったり、赤い雨が降る小部屋の窓を、じっと見つめることしかできないような、息も詰まるような光景。不気味な悪夢の光景たちが、その手触りやにおい、痛みや息苦しさまで、身の毛がよだつほど詳細なディテールまで描写されていたのだった。
巨大な虫になり、狭い小部屋で赤い雨の降る窓の外を見つめ続ける夢は、M君が不眠に苦しめられていた時期に見ていたという夢によく似ていた。しかし、その結末だけが少し違っていた。
K君の夢日記に記録されていたその夢では、目の前が突然明るくなり、嘘のように身体が軽くなると、背中から大きな羽根が生えてきたと綴られていた。自身は手足が無数にある虫のような姿のままで、一糸纏わぬ身体は黒光りしている。背中から生えてきた羽根はセロファンのように薄く繊細で、青白く淡い輝きを湛えている。まるで、サナギから羽化したばかりの蝉や繭を破った蚕のような羽根だったという。ちょうど、M君が過労のせいだと一笑に付した、あの悪夢に登場したK君らしき人物――と言い表して良いものかもわからないが――と同じ姿だ。
K君は夢の中で、羽化したばかりの己の足元に目をやった。そこには、人間である自分自身が、抜け殻のようになって落ちていたという。まるで綿の抜かれたぬいぐるみのようになったそれは、内容物の失くなった虫の繭のように、頭部がぱっくりと割れていたと、綴られていた。
「だからね、僕、もしかしたらと思ったんです。もしかしたら、本当にあの音源にそういう力があるのかもって。そのせいでひとが亡くなったり、心を病んだりしたのかもって。僕が伝えようとしたことが、伝わりすぎちゃったのかもしれないと思ったんです」
僕があの音源で伝えたいと思ったストーリーが、あれを聴いたひとたちにそのまま伝わったのだとしたら、多少落ち込んじゃうようなこともあるかなって。ガトーショコラを平らげた彼は上品な所作で紙ナプキンを使い口許を拭うと、少しだけ目を泳がせた。まつ毛が僅かに震えている。まるで怯えを隠そうとしているかのようだが、その目に翳りはない。
「自分も割とそうなんでわかるんですけど、ああいう音源にお世話になってるひとってだいたいちょっとストレスが多かったり、メンタル病んでますからね。だから、場合によってはそういう、自殺、とかもあるのかなって」
心持ち、声を顰めて言う。私は、彼が言わんとしていることを理解できず、話を急かすように質問を重ねた。だから、実験、なんですか。
「ええ、そうです。実験のつもりでした。もしもあの音源で僕が伝えたかったことが、そっくりそのまま聴き手に伝わるのだとしたら、Mもあの夢の続きが見られるのかも、と思って。僕も、彼と同じような夢を見ることがあるんですよ。でも彼の見る夢と僕の見るそれはちょっと違うところがあったから、もしかしたら、と思って。聴かせてみました」
不思議ですよね、やっぱり一緒にバンドやってると似てくるのかな。彼はさっきまでの怯えの混じったような表情が嘘のように、心底愉快そうにフフ、と笑った。
私は彼の言っていることを、何ひとつ理解できなかった。
いや、理解できなかったわけではない。きっと、理解したくなかったのだろう。理解するのが、怖かったのだ。

(※イメージ)
「███さん、音楽って魔法だと思いますか」
帰り際、どうしてもお代を出すと言って聞かないK君を制して会計を済ませ、ビルの古いエレベーターの前に出ると、彼が言った。惚れ惚れするほど穏やかな声だった。私は少し考えたのちに持論を答えた。音楽そのものに大それた力はないが、それを作り、演奏するひとの想いが込められることによって魔法のような力を発揮するものなのではないか、と。
K君は、ライターさんらしいご意見ですね、中庸で素敵な考え方だ、と言い、くわえていた煙草の煙に目を細めた。エレベーター脇の灰皿に、長く残った灰を振り落として、僕は魔法だと思います、と、断言するように言う。
「必ずしも幸せの魔法とは言いきれないですけど。でも、もしも音楽ひとつで他人の心のなかをハックできるのだとしたら、それは立派な魔法だし、すごく面白いな、と思っています」
乗り込んだエレベーターの中で、私は、実験は成功したのですか、とK君に問うた。K君は秘密です、と微笑んで見せる。
「まだまだ全然、検証の途中なので」

(※イメージ)
『いい音楽』、というのは、一体どのようなものだろう。
誰の耳にも心地好い音楽だろうか。今まで誰も聴いたことのないような斬新な音楽だろうか。有名なプロデューサーや評論家が「良い」と言った音楽だろうか。それとも、動画や配信音源が何億回再生もされている音楽だろうか。そのどれもが結局は個人の主観、「好き」や「嫌い」が積み重ねられた相対的な評価でしかなく、絶対的な「良さ」「悪さ」なんてものはこの世に存在していないということを、私たちは心のどこかで既に知っている。音楽に限らない。映画も、小説も、絵画も漫画も、全てのコンテンツは同様だ。私たちが「良い」と感じた音楽は、結局私たちそれぞれの色眼鏡を通して、私たちそれぞれの琴線に触れた、ただそれだけでしかない。
しかし、だからこそ、私たちはその「良い」という感覚を、自分自身の感性を信じることができる。自分自身が、自分自身の感性で「良い」と感じたことを誇り、自分自身の感性を愛することができる。
だが、もしもその、自分自身が自分自身の感性に従って「良い」と感じたものに、予め『魔法』が仕込まれていたとしたら。
その魔法が私たちの心を『ハック』し、この作品は「良い」ものなのだと、思わされていたのだとしたら。
私がこの記事を公開した理由は、耐えられなくなってしまったからだ。
彼らはきっとこれから売れるだろう。私たちが想像するよりもずっと、瞬く間に人心を動かすロックバンドとなるはずだ。かつて私が偶然の悪戯によって一瞬で心を捉えられたように、これから彼らの音楽に夢中になっていくリスナーは、たとえ少しずつであろうとも、続々と増え続けるはずだ。
しかし、これからそんな彼らを、特にK君の姿を目にするたび、K君が手掛けた彼らの音楽を耳にするたび、あの日、夕暮れの街に消えていくK君の細身の後ろ姿を見送ったときの、あの薄ら寒いような感覚を幾度も思い出すのであろうことに。そんな、近い未来に。
私ひとりきりでは、耐えられなくなってしまったのだ。
(終)
「実験です」
K君は大好物だというガトーショコラを前にし、口許を綻ばせたまま私の質問に応じた。

(※イメージ 引用:Pixabay)
全国ツアー開催中の秋の終わりに、多忙な合間を縫って彼と会ったのは、M君への取材の際と同様に、レーベル事務所が構える下北沢だった。平日の閑散としたそのカフェは週末には名物らしいナポリタンとスイーツを求める女性のふたり連れやカップルで賑わい、夜には音楽好きで溢れるミュージックバーになる。待ち合わせより少し遅れてやってきた彼は黒いシースルーのハイネックとタランチュラのような柄のカーディガン、膝に大きな穴の空いたダメージジーンズを細身の身体に纏った姿で、謝罪もそこそこに着席し、嬉しいです、とにっこり微笑んだ。
「███さんとふたりでお話したいって、ずっと思ってたから」
それには概ね同意だが、私は本心では、もう少し別の話題について話を聞きたいと思っていた。たとえば、楽曲の制作秘話。自身の音楽的ルーツ。有り体な内容のインタビューの方が、どれほど嬉しかったろう。
私は彼に対して以前より、バンドメンバーのなかでも特に興味深い人物だと感じていた。才気溢れるメインコンポーザーであり、ステージではベースだけでなくキーボードやシンセサイザーなども演奏し、自身もボーカルを執る。トラックメイカーでもある彼は楽曲のなかでは雄弁でありながら、その人物像はどことなく浮世離れした、いわゆるミステリアスなタイプだった。SNSの更新も少なく、過去のインタビューに目を通しても言葉数は多くない。しかし時折紡ぐ言葉は作詞と同様不思議な求心力を持っており、その独特な存在感に注目しているというファンも多いようだった。
遠慮がちに注文した好物を思いのほか大きくフォークで掬うと、口許に落ちかかる金髪の後れ毛を耳にかけて大口を開ける。数え切れないほどの数のピアスが、鋭い光で目を射る。
褐色の塊をゆっくりと口に運ぶ彼に、M君から聞いた話を簡単にまとめて伝えると、彼は驚いたような表情を浮かべたのち、苦笑いの混じった表情で喉仏を上下させた。
「あいつ、そんなこと言ってたんですか!?」
フフ、と肩を揺らして小さく笑うと、彼はあっさりと、盗作に気づいていたことを認めた。何故件の音源をM君に聴かせたのか、という質問に対しては、まあ多少は、痛い目に遭えばいいのにって思ってはいましたけど、と、さもM君の行為へのささやかな仕返しであったかのような物言いをする。
しかし彼は、でも本当の理由はそうではなくて、と続けた。
「実験のつもりだったんです」
その言葉の真意を測りかねた私は、まず順を追った説明を求めた。件の睡眠用BGMを制作するに至った経緯、そして、それをM君に薦めた「本当の理由」について。
M君が聞いていた通り、K君は学生時代の先輩に依頼を受け、アルバイトとしてリラクゼーション音源を制作していたのだという。作業の内容は、現在通信教育で臨床心理学の勉強をしているという先輩――依頼者が予め制作した、一定の周波数を持つ単調な音源をベース音として使用し、耳馴染みのいいインストゥルメンタルミュージックに仕上げるというものだった。本数は全部で10本。耳馴染みが良ければ盛り上がりも上手い構成も要らない、シンプルなものでいいとの依頼だったようだが、K君は「プロ意識が許さなかった」と言う。
「どうせやるならもっと美しくて、聴いてて楽しい方がいいじゃないですか。なので、自分の好きなようにやることにしたんです。『提供した音をベースに使ってくれれば好きにしていい』とは最初から言われてましたし。それでね、ちゃんとテーマも設けて、1本の音源のなかでストーリーも意識したりして」
テーマは何だったのかと問うと、彼は重めの前髪の奥の瞳を輝かせて、夢日記です、と答えた。
「自分が過去に見た夢に着想を得て作ってみようかなって。夢を記録している日記っていう体で。だからタイトルも日付に統一して。日付自体には特に意味はなくて、架空の人物の夢日記をイメージしているんです」
私は、胸に立ち込める嫌な予感を打ち消すように、そういえば夢日記つけてるって仰ってましたもんね、と返した。彼は覚えててくれたんですか、と表情を輝かせる。
「依頼通り10本作って、先輩も喜んでくれて。全部聴いてみたけど絶対収益化できるよ、お前に頼んで良かった、って言ってもらえたんですけど。
でも、そのひと月後ぐらいかなあ。ネットで話題になってたこと、あったじゃないですか。ほら、あの、自殺したひとたち10人が、同じチャンネルの睡眠用BGM聴いてたっていう話。たった10本しか動画が公開されてないチャンネルで、登録者数も少ないのに、何人も同じ動画を観ているのはおかしいって。
あの動画、先輩のチャンネルの動画なんです。つまり、僕が作った音源」
例の噂に驚いた先輩は、動画をすぐに非公開にした。初めはどうせ偶然だろうと気に留めないように努めていたようだが、噂が拡散されるたびに視聴数が増えていき、単なる噂だと無視できなくなってしまったのだという。
悪い予感が、どんどんと輪郭を伴っていく。乾いた唇を紅茶で潤してから、その先輩は今はどうされているんですか、と問うと、K君は表情ひとつ変えずに答えた。
「亡くなりました」
思わず言葉を失う。すると、彼は失笑し、すみません、と謝罪した。
「悪い冗談でしたね。嘘です。全然健在ですよ。今でも時々連絡取り合ったりしています。
でもね、最近はちょっと塞ぎ込んじゃって、音楽もやってないみたいなんですよね」
そういえば、とK君は紅茶に少し口をつけて続けた。
「そういえば、先輩も悪夢をよく見るって言ってたな、あの音源作ってた頃」
なんでも、先輩はK君の作った音源をチェックしたり調整したりといった作業をしている間、連日悪夢を見続けていて寝不足だ、と零していたのだという。たとえば、雑踏に踏み殺される蟻になる夢。小川のある山の中で遭難する夢。そして、真っ暗な小部屋に閉じ込められた、巨大な虫の姿になってしまう夢。

(※イメージ)
私は、K君の夢日記を読んだことがあった。利用者数の決して多くないブログサービスで開設されたそのアカウントは、これまでにたった一度きり、SNSの24時間で消えてしまうリール動画にのみリンクが掲載された。アカウント名は彼の生年月日。私のような、一部のディープファンしか知らないようなアカウント。
そこに記録され続けていたのは、全てが悪夢だった。想像するだけでも悍ましい夢たち――踏み殺される蟻になったり、暗い山中で迷ったり、赤い雨が降る小部屋の窓を、じっと見つめることしかできないような、息も詰まるような光景。不気味な悪夢の光景たちが、その手触りやにおい、痛みや息苦しさまで、身の毛がよだつほど詳細なディテールまで描写されていたのだった。
巨大な虫になり、狭い小部屋で赤い雨の降る窓の外を見つめ続ける夢は、M君が不眠に苦しめられていた時期に見ていたという夢によく似ていた。しかし、その結末だけが少し違っていた。
K君の夢日記に記録されていたその夢では、目の前が突然明るくなり、嘘のように身体が軽くなると、背中から大きな羽根が生えてきたと綴られていた。自身は手足が無数にある虫のような姿のままで、一糸纏わぬ身体は黒光りしている。背中から生えてきた羽根はセロファンのように薄く繊細で、青白く淡い輝きを湛えている。まるで、サナギから羽化したばかりの蝉や繭を破った蚕のような羽根だったという。ちょうど、M君が過労のせいだと一笑に付した、あの悪夢に登場したK君らしき人物――と言い表して良いものかもわからないが――と同じ姿だ。
K君は夢の中で、羽化したばかりの己の足元に目をやった。そこには、人間である自分自身が、抜け殻のようになって落ちていたという。まるで綿の抜かれたぬいぐるみのようになったそれは、内容物の失くなった虫の繭のように、頭部がぱっくりと割れていたと、綴られていた。
「だからね、僕、もしかしたらと思ったんです。もしかしたら、本当にあの音源にそういう力があるのかもって。そのせいでひとが亡くなったり、心を病んだりしたのかもって。僕が伝えようとしたことが、伝わりすぎちゃったのかもしれないと思ったんです」
僕があの音源で伝えたいと思ったストーリーが、あれを聴いたひとたちにそのまま伝わったのだとしたら、多少落ち込んじゃうようなこともあるかなって。ガトーショコラを平らげた彼は上品な所作で紙ナプキンを使い口許を拭うと、少しだけ目を泳がせた。まつ毛が僅かに震えている。まるで怯えを隠そうとしているかのようだが、その目に翳りはない。
「自分も割とそうなんでわかるんですけど、ああいう音源にお世話になってるひとってだいたいちょっとストレスが多かったり、メンタル病んでますからね。だから、場合によってはそういう、自殺、とかもあるのかなって」
心持ち、声を顰めて言う。私は、彼が言わんとしていることを理解できず、話を急かすように質問を重ねた。だから、実験、なんですか。
「ええ、そうです。実験のつもりでした。もしもあの音源で僕が伝えたかったことが、そっくりそのまま聴き手に伝わるのだとしたら、Mもあの夢の続きが見られるのかも、と思って。僕も、彼と同じような夢を見ることがあるんですよ。でも彼の見る夢と僕の見るそれはちょっと違うところがあったから、もしかしたら、と思って。聴かせてみました」
不思議ですよね、やっぱり一緒にバンドやってると似てくるのかな。彼はさっきまでの怯えの混じったような表情が嘘のように、心底愉快そうにフフ、と笑った。
私は彼の言っていることを、何ひとつ理解できなかった。
いや、理解できなかったわけではない。きっと、理解したくなかったのだろう。理解するのが、怖かったのだ。

(※イメージ)
「███さん、音楽って魔法だと思いますか」
帰り際、どうしてもお代を出すと言って聞かないK君を制して会計を済ませ、ビルの古いエレベーターの前に出ると、彼が言った。惚れ惚れするほど穏やかな声だった。私は少し考えたのちに持論を答えた。音楽そのものに大それた力はないが、それを作り、演奏するひとの想いが込められることによって魔法のような力を発揮するものなのではないか、と。
K君は、ライターさんらしいご意見ですね、中庸で素敵な考え方だ、と言い、くわえていた煙草の煙に目を細めた。エレベーター脇の灰皿に、長く残った灰を振り落として、僕は魔法だと思います、と、断言するように言う。
「必ずしも幸せの魔法とは言いきれないですけど。でも、もしも音楽ひとつで他人の心のなかをハックできるのだとしたら、それは立派な魔法だし、すごく面白いな、と思っています」
乗り込んだエレベーターの中で、私は、実験は成功したのですか、とK君に問うた。K君は秘密です、と微笑んで見せる。
「まだまだ全然、検証の途中なので」

(※イメージ)
『いい音楽』、というのは、一体どのようなものだろう。
誰の耳にも心地好い音楽だろうか。今まで誰も聴いたことのないような斬新な音楽だろうか。有名なプロデューサーや評論家が「良い」と言った音楽だろうか。それとも、動画や配信音源が何億回再生もされている音楽だろうか。そのどれもが結局は個人の主観、「好き」や「嫌い」が積み重ねられた相対的な評価でしかなく、絶対的な「良さ」「悪さ」なんてものはこの世に存在していないということを、私たちは心のどこかで既に知っている。音楽に限らない。映画も、小説も、絵画も漫画も、全てのコンテンツは同様だ。私たちが「良い」と感じた音楽は、結局私たちそれぞれの色眼鏡を通して、私たちそれぞれの琴線に触れた、ただそれだけでしかない。
しかし、だからこそ、私たちはその「良い」という感覚を、自分自身の感性を信じることができる。自分自身が、自分自身の感性で「良い」と感じたことを誇り、自分自身の感性を愛することができる。
だが、もしもその、自分自身が自分自身の感性に従って「良い」と感じたものに、予め『魔法』が仕込まれていたとしたら。
その魔法が私たちの心を『ハック』し、この作品は「良い」ものなのだと、思わされていたのだとしたら。
私がこの記事を公開した理由は、耐えられなくなってしまったからだ。
彼らはきっとこれから売れるだろう。私たちが想像するよりもずっと、瞬く間に人心を動かすロックバンドとなるはずだ。かつて私が偶然の悪戯によって一瞬で心を捉えられたように、これから彼らの音楽に夢中になっていくリスナーは、たとえ少しずつであろうとも、続々と増え続けるはずだ。
しかし、これからそんな彼らを、特にK君の姿を目にするたび、K君が手掛けた彼らの音楽を耳にするたび、あの日、夕暮れの街に消えていくK君の細身の後ろ姿を見送ったときの、あの薄ら寒いような感覚を幾度も思い出すのであろうことに。そんな、近い未来に。
私ひとりきりでは、耐えられなくなってしまったのだ。
(終)