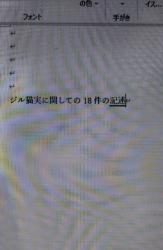※
以下の記事内に登場するロックバンドのメンバー構成、活動歴や結成理由などのエピソード、メンバーの容姿等には、本人たちの要望により脚色を加えている。プライバシー保護の観点より、本人たちの実際の身元などは特定しないよう留意頂けると幸いだ。
[1]
とあるロックバンドがインターネットで炎上した。昨今のSNSなどではざらにある出来事だ。
一方で、このような軽い言葉で片付けてしまっては、彼らのミュージシャンとしての矜恃に傷をつけてしまうことになるだろう、という懸念もある。私とて物書きの端くれであるし、彼らのファンでもある故、その当事者である彼の行いがどれほど愚かであり、しかし何かしらの葛藤の末に生じてしまった事件であろうということは、全く想像に難くない。
しかし、まだ駆け出しのインディーズバンドである彼らの身に起こったその炎上騒動の顛末は、外野の目から見ればネットの海の底辺を舐める暴露系配信者ですら跨いで通るほど、ありきたりで呆気ないものだった。

(※イメージ 引用:Pixabay)
彼らは今から6年ほど前、メンバーが全員都内の音楽専門学校生だった頃に結成された。無所属のインディーズバンド、更に決して長くはない活動歴のうち一年間は就職活動のために実質休止状態だったにも関わらず、アルバムを2枚、EPは5枚、リリース楽曲は60曲以上に及ぶほど精力的に活動を続け、今年には3都市ツアーも決行し、疫病の蔓延などの影響でこれまで降り立つことのなかった関西や東海地方のライブハウスにも訪れ、オーディエンスを沸かせてきた。昨今はSNSのフォロワー数などでファンダムの規模が可視化されやすいが、彼らの場合は今年やっと5000人を超えたところで、無名と言うには勿体ないが、まだまだ人気バンドとは言えない段階だ。しかし、この4人の若者たちには、途方もないポテンシャルがあると、私は高く評価している。
メンバー全員が曲を作り、歌詞を書き、それぞれに役割を担っている彼らは活動初期の頃、『東京・下北沢を拠点とするDIYバンド』を惹句として自称していた。リーダーであるF君はバンドの発起人であり、専門学校1年生の頃に現メンバーを招集してバンドを結成。なんでも、「当時好意を抱いていたヘビースモーカーの女性先輩に想いを伝えたが強かに玉砕し、まだ未成年でありながら学内の喫煙所でやけ煙草していたところを必死に止めてくれた面々に声をかけた」のだと、過去のインタビューで自ら語っていた。高校時代に同じ部活に入っており、たまたま同じ専門学校に進学していたのだという3人のメンバーのうち、ドラマーのH君はF君とは幼稚園児の頃からの幼馴染で、バンド専属のアートディレクターのような役割も担っているという。学生時代から映画やアニメが好きだった彼は持ち前の明るさを活かしてその手の人脈を広げ、時には自ら自分を含むメンバーのスタイリングやメイクも担当。これまでインタビューをしてきたなかでも彼は、笑顔を弾けさせながら「おれがやってるのはメンバーと曲への愛情表現なんです」と、よく口にしていた。
そんなバンドの二本柱とも言えるのが、ギターボーカルとベースボーカルのふたりだ。ギターボーカルのM君は如何にも今どきのロックボーカリストといった趣きのストリートスタイルのファッションと鋭い目付きに反して、専門学校在学時にはボーカル科でもトップクラスの成績を残した優等生だったという。
「でもおれ、卒業発表のとき、スカウトに来てたレコード会社の大人のひとらから、ひとりたりとも声掛けてもらえんかったんですよ。なんや、イキってるように見えたんすかね」と、母親の故郷のお国言葉だという方言混じりの口調で自嘲する彼の書く詞には、バンドのブログでのエッセイ連載が好評を集めるほどの持ち前の文章力を活かした物語性と、胸に秘めたハングリー精神が表れた愚直な真っ当さがあり、彼らのロックバンドらしさを下支えする精神的支柱となっている。
一方、ベースボーカルのK君はいわゆる追加メンバーだったという。ほかのふたりと同様にF君から声をかけられてはいたが、「すぐには返事ができなかった」と語っている。なんでも、10代の頃に所属していたバンドが解散して以来、自身をバンドに向いていないタイプだと思っており、ロックバンドをやりたいという自分自身の夢を押し殺してきていたのだ、と口にしていた。その証左なのか、就活に伴う活休中、彼はボカロPとしての活動を開始。たった1曲ではあるがいわゆる“殿堂入り”を果たすほどの再生数を誇るヒット曲を生み出している。バンドのすべての楽曲のトラックメイキングを一手に引き受け、そのうえリスナーの間で人気のアンセムはすべて彼の手掛けた楽曲であることから、彼こそがバンドのキーパーソンであると言えるが、K君は自身のことを「特撮の追加戦士みたいなもの。シルバーはレッドとイエローとブルーの間には入れない」と言い表していた。
今から4年前、疫病の蔓延を防ぐ目的で各地のライブハウスが次々と閉鎖していた時期に、私は彼らの存在を知った。CDや書籍も取り扱っている都内の小さな雑貨屋の片隅で、宣伝用の小さなテレビから流れるR&B風の日本語ロックは、同じ店内で流されていたどのミュージシャンの楽曲とも被らない個性があるように私の耳には届き、無性に惹かれたのだ。
音楽ライターという職業柄、シーンのトレンドらしいものには日々それなりに気を配ってはいるものの、実際は、“これから流行る(かもしれない)もの”よりも“今流行っているもの”を取り扱った記事の方がPVがいい。そのため、私が仕事という名目で彼らのライブに折に触れて足を運び、挨拶ができるタイミングでは積極的に話しかけ、クライアントの音楽メディア関係者の前でも盛んに彼らの話をしてインタビューや取材などにも赴くことができるほどになったのは、ひとえに自身の肩書きの影響ではなく、ただただ彼らの音楽を広く伝える、その一端を担えればという、いちファンとしての情熱のみに過ぎなかった。平たく言えば職務という名目を借りた、大いなる“推し活”だ。それほどまでに、目覚めたばかりの才能がみるみるうちに進化していく様を至近距離で見届けられるというのは、私のような好事家にとっては大変に甘美な体験なのだった。それはさながら大輪の花の開花を目撃したときのような、或いは神話の興りを目の前で見届けるかのような、えも言われぬ恍惚感を伴っていた。

(※イメージ)
そんな、私をはじめリスナーの期待を一身に受ける彼らに異変があったのは、今年の6月。公式SNSアカウントに、十数行に渡るテキストが打ち込まれた画像が投稿された。「皆様へのお詫びとお知らせ」と題されたその明朝体のテキストには、ギターボーカルのM君が、別の人物の楽曲を剽窃していた、というようなことが綴られていた。しかも、あろうことかその相手はボーカルの相方であるK君だという。
M君は数年前にK君から送られてきた、後に没作となったデモ音源を自身のPCの中から発見し、そのあまりの出来の良さに魔が差して無断で借用してしまったのだと、件の画像の文言には綴られていた。K君自身もその曲のことを覚えておらず(日常的に作曲に触れている多作なミュージシャンにとっては、“あるある”なのかもしれない)、誰にも気づかれずに今年の初旬にレコーディングを終え、バンドの曲として無事リリースされてしまった、のだという。事実と反省の念だけを記した、事務的でありながらも真摯なその文章はM君自身の手によるもので、公式サイトに記載されたディスコグラフィーのうち、当該楽曲のクレジットは既に修正されていた。
いわば事後報告のような発表ではあったが、この告白は界隈に、小さな波紋を広げた。ネット炎上絡みの案件にすぐに飛びつくインフルエンサーが目敏く嗅ぎつけてきたことをきっかけに、御仁と同様の思想を持つSNSユーザーの間で瞬く間に当該投稿が拡散されたのだ。とはいえ全体の7割は無言で拡散するだけ、2割はただ見知らぬ有名人ぶった若人を叩きたいだけの暇人、1割は彼らのファンで、当のファンたちも「他のミュージシャンからパクったわけじゃないし、解決済みなら許す」「女性関係の揉め事や暴力沙汰や酔っ払って居酒屋の店員にダル絡みしたとかじゃなくて良かった」というような、寛容なリアクションを示している人々が大半だった。なかには「素直に告白してくれて寧ろ有難い。黙って修正しちゃっても騒ぎになんてならなかっただろうに、きちんと謝罪文掲出するところに性格の良さが出てる」というような、M君の人柄を高く評価する意見も散見された。
確かにそうだ、と私も感じた。同じバンドメンバーの、しかも世に出していない没作から拝借した曲だなんて、何も言わなければ誰にもバレやしない。本人同士の間に合意と和解さえあるのなら、ファンに向けて何も発表せず、ディスコグラフィーや配信サイトでの情報をこっそり修正してしまえばいいだけの話だ。もしもなにか言われようものなら、「間違えて記載してしまっていたので修正しました」とでも言い訳すればいい。なにもわざわざ、ネットの底辺に棲まうドブさらいのオモチャになるような行動を律儀に選ぶ必要などなかったはずなのだ。私の場合、彼の正直過ぎるその対応へ抱いた感情は、感心というよりも小さな疑念とでも表した方が正しいものだった。
疑問は残るものの、私は彼らのその後の動向を暫し静観した。俄かに議論を誘ったのは、ドブさらいを生業としているようなネットニュースサイトに取り上げられた後の1週間程度だけで、世間にはあっという間に忘れ去られたようだった。私と同様に心配と疑問を抱えた心情をタイムラインに吐露していたファンも、いつの間にやら取り立ててそのことを話題にすることもなくなった。私は翌月に彼らのワンマンライブの取材を控えていたが、この疑念について彼らに直接問いかけるという選択肢はもとより持ち合わせていなかった。わざわざ公に謝罪文を発表したということは、そこに合理的な理由があると考えて当然だとは思うが、その理由を彼らが自ら明らかにしていないということは、きっと踏み込まれたくない次元の物事なのだろう、と考えたのだ。物書きの端くれとして、そのブラックボックスに興味がないとは本音では言いきれないが、彼らのいちファンとしては、しっかりと閉じられたその蓋をわざわざこじ開けるような、野暮なことはしたくなかった。
しかし、そのライブの終演後、彼らの楽屋を訪ねていつものように手短に挨拶を済ませた後、事態は急変した。
地下のライブハウスから外への階段を上って帰ろうとした矢先、背後から呼び止める声に足を止めた。思わずよろける身体を、様々なライブ公演を告知するポスターが所狭しと貼られてカラフルになった壁に手をやって立て直し、慌てて振り返る。私を直々に呼び止めたのはなんとM君で、彼はいつも人の好さそうな笑顔を浮かべているはずの相貌を強張らせ、まるで初めて立つ大きな舞台で観客を前にしたときのように、凛々しい目元を更に眼光鋭く細めていた。楽屋から急いで私を追ってきたのか、大きく肩で息を吐くと、職務質問に来た強面の警官のような神妙な面持ちで、すみません、あとでDM送るので見たらお返事頂けると嬉しいです、とだけ告げ、今日はありがとう、と建物の奥へ戻っていってしまった。
いつになくただならない空気を纏ったM君の様子にやや動転しながらも、自宅への帰路の道中、彼らとの唯一の直接的なコミュニケーションツールであるSNSの受信ボックスを見ると、そこにはM君からの取材の申し出が届いていた。私に是非聞いてほしいことがあるから直接一対一で話ができる場を設けられないか、自分の身元さえ明かさなければ記事や本にしてもらっても構わない、他に聞いてもらえそうな記者を知らないのだ、というようなことが、いつになく丁寧な言葉で綴られていた。そのメッセージの最後は、以下のようにまとめられていた。
「お話したいことの内容としましては、先月謝罪文を発表した、楽曲の剽窃の件に関し、自分ひとりで抱え続けることが困難な体験と感情があるため、███さんの今後の文筆活動に活かして頂ければ……と思い、ご連絡した次第です」
以下の記事内に登場するロックバンドのメンバー構成、活動歴や結成理由などのエピソード、メンバーの容姿等には、本人たちの要望により脚色を加えている。プライバシー保護の観点より、本人たちの実際の身元などは特定しないよう留意頂けると幸いだ。
[1]
とあるロックバンドがインターネットで炎上した。昨今のSNSなどではざらにある出来事だ。
一方で、このような軽い言葉で片付けてしまっては、彼らのミュージシャンとしての矜恃に傷をつけてしまうことになるだろう、という懸念もある。私とて物書きの端くれであるし、彼らのファンでもある故、その当事者である彼の行いがどれほど愚かであり、しかし何かしらの葛藤の末に生じてしまった事件であろうということは、全く想像に難くない。
しかし、まだ駆け出しのインディーズバンドである彼らの身に起こったその炎上騒動の顛末は、外野の目から見ればネットの海の底辺を舐める暴露系配信者ですら跨いで通るほど、ありきたりで呆気ないものだった。

(※イメージ 引用:Pixabay)
彼らは今から6年ほど前、メンバーが全員都内の音楽専門学校生だった頃に結成された。無所属のインディーズバンド、更に決して長くはない活動歴のうち一年間は就職活動のために実質休止状態だったにも関わらず、アルバムを2枚、EPは5枚、リリース楽曲は60曲以上に及ぶほど精力的に活動を続け、今年には3都市ツアーも決行し、疫病の蔓延などの影響でこれまで降り立つことのなかった関西や東海地方のライブハウスにも訪れ、オーディエンスを沸かせてきた。昨今はSNSのフォロワー数などでファンダムの規模が可視化されやすいが、彼らの場合は今年やっと5000人を超えたところで、無名と言うには勿体ないが、まだまだ人気バンドとは言えない段階だ。しかし、この4人の若者たちには、途方もないポテンシャルがあると、私は高く評価している。
メンバー全員が曲を作り、歌詞を書き、それぞれに役割を担っている彼らは活動初期の頃、『東京・下北沢を拠点とするDIYバンド』を惹句として自称していた。リーダーであるF君はバンドの発起人であり、専門学校1年生の頃に現メンバーを招集してバンドを結成。なんでも、「当時好意を抱いていたヘビースモーカーの女性先輩に想いを伝えたが強かに玉砕し、まだ未成年でありながら学内の喫煙所でやけ煙草していたところを必死に止めてくれた面々に声をかけた」のだと、過去のインタビューで自ら語っていた。高校時代に同じ部活に入っており、たまたま同じ専門学校に進学していたのだという3人のメンバーのうち、ドラマーのH君はF君とは幼稚園児の頃からの幼馴染で、バンド専属のアートディレクターのような役割も担っているという。学生時代から映画やアニメが好きだった彼は持ち前の明るさを活かしてその手の人脈を広げ、時には自ら自分を含むメンバーのスタイリングやメイクも担当。これまでインタビューをしてきたなかでも彼は、笑顔を弾けさせながら「おれがやってるのはメンバーと曲への愛情表現なんです」と、よく口にしていた。
そんなバンドの二本柱とも言えるのが、ギターボーカルとベースボーカルのふたりだ。ギターボーカルのM君は如何にも今どきのロックボーカリストといった趣きのストリートスタイルのファッションと鋭い目付きに反して、専門学校在学時にはボーカル科でもトップクラスの成績を残した優等生だったという。
「でもおれ、卒業発表のとき、スカウトに来てたレコード会社の大人のひとらから、ひとりたりとも声掛けてもらえんかったんですよ。なんや、イキってるように見えたんすかね」と、母親の故郷のお国言葉だという方言混じりの口調で自嘲する彼の書く詞には、バンドのブログでのエッセイ連載が好評を集めるほどの持ち前の文章力を活かした物語性と、胸に秘めたハングリー精神が表れた愚直な真っ当さがあり、彼らのロックバンドらしさを下支えする精神的支柱となっている。
一方、ベースボーカルのK君はいわゆる追加メンバーだったという。ほかのふたりと同様にF君から声をかけられてはいたが、「すぐには返事ができなかった」と語っている。なんでも、10代の頃に所属していたバンドが解散して以来、自身をバンドに向いていないタイプだと思っており、ロックバンドをやりたいという自分自身の夢を押し殺してきていたのだ、と口にしていた。その証左なのか、就活に伴う活休中、彼はボカロPとしての活動を開始。たった1曲ではあるがいわゆる“殿堂入り”を果たすほどの再生数を誇るヒット曲を生み出している。バンドのすべての楽曲のトラックメイキングを一手に引き受け、そのうえリスナーの間で人気のアンセムはすべて彼の手掛けた楽曲であることから、彼こそがバンドのキーパーソンであると言えるが、K君は自身のことを「特撮の追加戦士みたいなもの。シルバーはレッドとイエローとブルーの間には入れない」と言い表していた。
今から4年前、疫病の蔓延を防ぐ目的で各地のライブハウスが次々と閉鎖していた時期に、私は彼らの存在を知った。CDや書籍も取り扱っている都内の小さな雑貨屋の片隅で、宣伝用の小さなテレビから流れるR&B風の日本語ロックは、同じ店内で流されていたどのミュージシャンの楽曲とも被らない個性があるように私の耳には届き、無性に惹かれたのだ。
音楽ライターという職業柄、シーンのトレンドらしいものには日々それなりに気を配ってはいるものの、実際は、“これから流行る(かもしれない)もの”よりも“今流行っているもの”を取り扱った記事の方がPVがいい。そのため、私が仕事という名目で彼らのライブに折に触れて足を運び、挨拶ができるタイミングでは積極的に話しかけ、クライアントの音楽メディア関係者の前でも盛んに彼らの話をしてインタビューや取材などにも赴くことができるほどになったのは、ひとえに自身の肩書きの影響ではなく、ただただ彼らの音楽を広く伝える、その一端を担えればという、いちファンとしての情熱のみに過ぎなかった。平たく言えば職務という名目を借りた、大いなる“推し活”だ。それほどまでに、目覚めたばかりの才能がみるみるうちに進化していく様を至近距離で見届けられるというのは、私のような好事家にとっては大変に甘美な体験なのだった。それはさながら大輪の花の開花を目撃したときのような、或いは神話の興りを目の前で見届けるかのような、えも言われぬ恍惚感を伴っていた。

(※イメージ)
そんな、私をはじめリスナーの期待を一身に受ける彼らに異変があったのは、今年の6月。公式SNSアカウントに、十数行に渡るテキストが打ち込まれた画像が投稿された。「皆様へのお詫びとお知らせ」と題されたその明朝体のテキストには、ギターボーカルのM君が、別の人物の楽曲を剽窃していた、というようなことが綴られていた。しかも、あろうことかその相手はボーカルの相方であるK君だという。
M君は数年前にK君から送られてきた、後に没作となったデモ音源を自身のPCの中から発見し、そのあまりの出来の良さに魔が差して無断で借用してしまったのだと、件の画像の文言には綴られていた。K君自身もその曲のことを覚えておらず(日常的に作曲に触れている多作なミュージシャンにとっては、“あるある”なのかもしれない)、誰にも気づかれずに今年の初旬にレコーディングを終え、バンドの曲として無事リリースされてしまった、のだという。事実と反省の念だけを記した、事務的でありながらも真摯なその文章はM君自身の手によるもので、公式サイトに記載されたディスコグラフィーのうち、当該楽曲のクレジットは既に修正されていた。
いわば事後報告のような発表ではあったが、この告白は界隈に、小さな波紋を広げた。ネット炎上絡みの案件にすぐに飛びつくインフルエンサーが目敏く嗅ぎつけてきたことをきっかけに、御仁と同様の思想を持つSNSユーザーの間で瞬く間に当該投稿が拡散されたのだ。とはいえ全体の7割は無言で拡散するだけ、2割はただ見知らぬ有名人ぶった若人を叩きたいだけの暇人、1割は彼らのファンで、当のファンたちも「他のミュージシャンからパクったわけじゃないし、解決済みなら許す」「女性関係の揉め事や暴力沙汰や酔っ払って居酒屋の店員にダル絡みしたとかじゃなくて良かった」というような、寛容なリアクションを示している人々が大半だった。なかには「素直に告白してくれて寧ろ有難い。黙って修正しちゃっても騒ぎになんてならなかっただろうに、きちんと謝罪文掲出するところに性格の良さが出てる」というような、M君の人柄を高く評価する意見も散見された。
確かにそうだ、と私も感じた。同じバンドメンバーの、しかも世に出していない没作から拝借した曲だなんて、何も言わなければ誰にもバレやしない。本人同士の間に合意と和解さえあるのなら、ファンに向けて何も発表せず、ディスコグラフィーや配信サイトでの情報をこっそり修正してしまえばいいだけの話だ。もしもなにか言われようものなら、「間違えて記載してしまっていたので修正しました」とでも言い訳すればいい。なにもわざわざ、ネットの底辺に棲まうドブさらいのオモチャになるような行動を律儀に選ぶ必要などなかったはずなのだ。私の場合、彼の正直過ぎるその対応へ抱いた感情は、感心というよりも小さな疑念とでも表した方が正しいものだった。
疑問は残るものの、私は彼らのその後の動向を暫し静観した。俄かに議論を誘ったのは、ドブさらいを生業としているようなネットニュースサイトに取り上げられた後の1週間程度だけで、世間にはあっという間に忘れ去られたようだった。私と同様に心配と疑問を抱えた心情をタイムラインに吐露していたファンも、いつの間にやら取り立ててそのことを話題にすることもなくなった。私は翌月に彼らのワンマンライブの取材を控えていたが、この疑念について彼らに直接問いかけるという選択肢はもとより持ち合わせていなかった。わざわざ公に謝罪文を発表したということは、そこに合理的な理由があると考えて当然だとは思うが、その理由を彼らが自ら明らかにしていないということは、きっと踏み込まれたくない次元の物事なのだろう、と考えたのだ。物書きの端くれとして、そのブラックボックスに興味がないとは本音では言いきれないが、彼らのいちファンとしては、しっかりと閉じられたその蓋をわざわざこじ開けるような、野暮なことはしたくなかった。
しかし、そのライブの終演後、彼らの楽屋を訪ねていつものように手短に挨拶を済ませた後、事態は急変した。
地下のライブハウスから外への階段を上って帰ろうとした矢先、背後から呼び止める声に足を止めた。思わずよろける身体を、様々なライブ公演を告知するポスターが所狭しと貼られてカラフルになった壁に手をやって立て直し、慌てて振り返る。私を直々に呼び止めたのはなんとM君で、彼はいつも人の好さそうな笑顔を浮かべているはずの相貌を強張らせ、まるで初めて立つ大きな舞台で観客を前にしたときのように、凛々しい目元を更に眼光鋭く細めていた。楽屋から急いで私を追ってきたのか、大きく肩で息を吐くと、職務質問に来た強面の警官のような神妙な面持ちで、すみません、あとでDM送るので見たらお返事頂けると嬉しいです、とだけ告げ、今日はありがとう、と建物の奥へ戻っていってしまった。
いつになくただならない空気を纏ったM君の様子にやや動転しながらも、自宅への帰路の道中、彼らとの唯一の直接的なコミュニケーションツールであるSNSの受信ボックスを見ると、そこにはM君からの取材の申し出が届いていた。私に是非聞いてほしいことがあるから直接一対一で話ができる場を設けられないか、自分の身元さえ明かさなければ記事や本にしてもらっても構わない、他に聞いてもらえそうな記者を知らないのだ、というようなことが、いつになく丁寧な言葉で綴られていた。そのメッセージの最後は、以下のようにまとめられていた。
「お話したいことの内容としましては、先月謝罪文を発表した、楽曲の剽窃の件に関し、自分ひとりで抱え続けることが困難な体験と感情があるため、███さんの今後の文筆活動に活かして頂ければ……と思い、ご連絡した次第です」