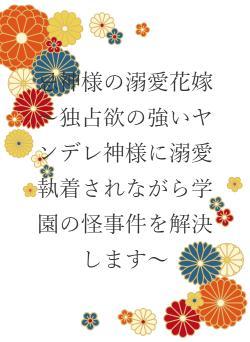魔法薬学を終え、私は何度もクライヴにお礼をし、それぞれの寮へと帰っていった。
現在は選択授業中。アイネは選択授業を受けに行ったが、私はこのコマは何も入れていないので、一時間ほど暇をすることになる。
自習とは名ばかりで、だいたいの生徒が思い思いに暇をつぶしている。さすがに目立って遊んでいると先生たちから怒られるが。
(さてどうしようかな。お昼休みにはアルバートから校舎案内してもらえるし……ここは手近な図書室にでも行こうかしら)
自習をするよりも、本を読みたいと思った。とくにこの学園の図書室は広く、書物も多いとゲーム設定にあった。実際にその様を見てみたいのである。
善は急げだと私は図書室に急いだ。
東棟の一階、渡り廊下を行った突き当りに大きな扉が開放されている。出入口の構えからして、現実世界で学生の時に利用した図書室と全然違うのがわかる。
中に入り、私は思わずその壮大さに声を上げそうになった。
見上げても視界に収まりきらないほど高い本棚が、何十も室内に設置されている。同じように授業を入れておらず時間が余っているのであろう生徒たちがちらほらおり、図書室でありながら軽いざわめきが起こっていた。
(ひえ~、す、凄い。こんだけ広いと目当ての本を探すだけで大変そう……。あ、でもそういうのも魔法を使って探すのか)
その辺りの細かいことまではゲームの設定資料集に乗っていないので推測である。
(思えば私、魔法って使えるのかな? 転生してきた身だから使えなくてもおかしくないんだよな)
1年生の授業は座学と魔法薬学が大半で、実技を伴った呪文学と箒に乗る飛空術の授業はまだ行われていない。
自分が魔法を使えるかどうかはもう少し先になるかもしれない。
とりあえず今は、世界中の本を集めたかのようなこの図書室で、読みたい本を読むのが先決だ。
私は図書室の奥の方へと入っていく。
と、不意に。
「あれ?」
近くにいた男子生徒が、何かを思い立ったような声を上げた。
つられてそちらを見ると、本棚の近くにあるテーブルに、数人の男子生徒が座っている。勉強をしたり本を読んだり……ではなく、カードゲームで遊んでいるのがわかった。
いわゆるたむろしている男子生徒の内の一人から、何故か私は指を差されている。
「あんた確か、クライヴ先輩の……」
「えっ」
まさかクライヴの名前が出てくるとは思わず、私は固まってしまう。
よく見ると校章のカラーが黄色で、クライヴと同じオルニス寮の生徒だとわかる。
(な、なんだろ……なんか治安の悪い人たちに絡まれたような……)
人を見かけで判断してはならないと。それは確かにその通りなのだが、やっぱりどこか恐い見た目をしている人には近寄らないのがベストだ。
実際、彼らの態度はどこか失礼で威圧的だった。
「なんかこの人、クライヴ先輩の恋人らしくてさー」
「は?」
「先輩の恋人ぉ?」
声は抑え気味だったが、私は真正面からゲラゲラと笑われた。
頭から水を被らされたような寒気と、うなじがカッと熱くなる気持ちが同時に沸き起こった。
なんでこんな人たちにいきなりそんなことを言われなきゃならないんだとも思ったし、やっぱり自分はクライヴの恋人に相応しくないと言われるんだとも思った。
様々なショックで固まる私に、男子生徒たちはニヤニヤと笑いながら追撃してくる。
「冗談キッツイんですけど」
「俺、先輩の恋人はもっと色気ある感じだと思ってた」
「っていうか、自称してるだけなんじゃね?」
「あぁー、なるほどね」
これ以上は聞いていられないと思った。
何より、何も言い返せない自分自身が情けなくて涙がにじんだ。
「わ、私、は……」
何て言えばいい。何も思いつかない。
だけどこいつらの前で泣きたくなんてない。
悔しさで握り締めた拳に当たる爪が痛い。
その時だった。
「うるさいんですけど」
暗い、嫌そうな低音ボイスが割り込んだ。
私も男子生徒たちも、第三者の介入に口を紡ぐ。
(あれ……この声……)
浮かんだ涙をそっと拭い、私は恐る恐る振り向き……そこで石のように固まった。
そこにいたのはネイト・コンステラシオン。つまり私の推しだった。
肩にかかる夜色の黒髪に、前髪に隠れた紅い瞳。
姿勢が悪くて猫背だが、ちゃんと立つと180センチもある長身。
夜の国の大貴族コンステラシオン家の一人息子で、桁違いの魔力を持って生まれたことで、国の人だけでなく学生たちからも距離を置かれている18歳。
当の本人は根暗で、魔法よりも機械いじりが好きというギャップ付き。
そんな彼が、分厚い本を手に、ジト目でこちらを睨んでいた。
「あ、あわ、あわわ……」
私はさっきまでの悲しい気持ちも何処へやら、突然の推しの登場にわなわなと震えていた。
震えるといえば男子生徒たちも同様だった。
「げっ……ネイト・コンステラシオン」
「やば……」
ネイトから溢れ出る強すぎる魔力を感じ取ってか、借りてきた猫のように大人しくなった男子生徒たちは、そそくさと尻尾を巻いて逃げていった。
残された私は、いまだ震えが止まらないまま、茫然とした顔でネイトの方を見た。
(お、おおお推しがっ……本物の推しがいる……!)
歓喜と感動とその他もろもろの喜びが溢れ、違う意味で私は泣きそうになった。
そんな私を、おそらく男子生徒たちが恐かったのだと思われたのか、ネイトは目を反らしながらゆっくりと告げた。
「あんなの気にすることないですよ。所詮は負け犬の遠吠えなので」
その捻くれた感じも原作そのものだ。
私は心の中で自分の頬を叩き、何とか平常心を保とうとする。
「あ、あああのっ……助けてくれてありがとうございます」
「べつに。うるさかったからうるさいって言ったまでです」
「それでも助かりました!」
つい声を張り上げてしまい、近くの生徒から視線を感じ、慌てて口を閉じる。
少し落ち着きを取り戻した私は、改めてネイトの方を向く。
「本当に……ありがとうございました……あっ」
途端にポロリと涙が零れた。
張り詰めていた緊張と、込み上げた怒りと、自分自身への情けなさと、推しに助けてもらえた嬉しさが一気にきてしまった。
「す、すみません、つい……」
「………」
ネイトは、彼がお得意とするジト目でしばらくこちらを眺めていたかと思うと、ため息混じりに一枚のハンカチを差し出してくれた。
「え……でも……」
「いいから使って下さい。俺が泣かしてると思われるのも嫌なんで」
やはりどこか捻くれた口調。
だけどしてくれていることはとても紳士的で優しい。
私はハンカチを受け取ると、それで溢れる涙を何とか拭った。
「何から何まですみません。ありがとうございます。これ、洗って返しますので……」
「いいよ。あげます」
「ええっ、そんな……」
だがよく考えたら、知らない人の涙が染み込んだハンカチなど洗った程度では使いたくないかもしれない。
ここは新しい物を買って返す方が筋というものだろう。
そう思った私は、もらったハンカチをギュッと握り締めた。
(改めてだけど……本当に推しがいる……目の前に)
ネイトはすでに私から興味を無くしているのか、本を選んでいる。
その所作の一つ一つがとても愛しい。
あまりにも彼のことを見つめすぎていたのか、ネイトは怪訝そうな表情で振り返った。
「まだ何か?」
「い、いえ、あの……」
ドキドキと高鳴る鼓動を抑えるよう、胸元に手を当てた。
彼に言いたいことなど本当にたくさんある。
ゲームのキャラクターとして、私の推しとして、現実世界では何度も私を元気にしてくれた。辛くて嫌なことがあっても、ネイトがいるからと何度頑張れたことか。
だから気付くと私は、その思いの丈を口にしていた。
「あの……上手く言えないんですけど。ネイト……先輩が居てくれただけで、私はいつも頑張れているんです」
「………」
「こんなこと、意味わかんないと思うかもしれませんが言わせて下さい。生まれてきてくれてありがとうございます……っ!」
「……!」
本当に自分は何を言っているんだと思いつつ、感極まったあまりどうにも止まらなかった。
案の定、ネイトは驚いた猫のように目を見開き、しばし瞬きを忘れていた。
そしてハッと我に返った彼は、すぐに私から視線を反らしてしまった。
「……本当に意味わからないです」
「そ、そうですよね、すみません」
「ただ……」
「……?」
「そんなこと、生まれて初めて言われた」
ネイトの色白の顔は、どこか赤く色付いている。
思えばネイトは、産まれながらに魔力が強すぎて、両親からも忌み子扱いされた過去がある。
そう思うと、「生まれてきてくれてありがとう」は確かに生まれて初めて言われた言葉になるのかもしれない。
(勢い任せに言っちゃったけど、怒らせたわけじゃなくて良かった~)
ホッと安心した私は深くお辞儀をし、もらったハンカチを胸にその場を立ち去ったのだった。
「……メア・モノクロイド」
立ち去った後、ネイトが私の名前を口にしていたのも知らず、私は推しに会えた喜びでいっぱいになっていたのだった。
現在は選択授業中。アイネは選択授業を受けに行ったが、私はこのコマは何も入れていないので、一時間ほど暇をすることになる。
自習とは名ばかりで、だいたいの生徒が思い思いに暇をつぶしている。さすがに目立って遊んでいると先生たちから怒られるが。
(さてどうしようかな。お昼休みにはアルバートから校舎案内してもらえるし……ここは手近な図書室にでも行こうかしら)
自習をするよりも、本を読みたいと思った。とくにこの学園の図書室は広く、書物も多いとゲーム設定にあった。実際にその様を見てみたいのである。
善は急げだと私は図書室に急いだ。
東棟の一階、渡り廊下を行った突き当りに大きな扉が開放されている。出入口の構えからして、現実世界で学生の時に利用した図書室と全然違うのがわかる。
中に入り、私は思わずその壮大さに声を上げそうになった。
見上げても視界に収まりきらないほど高い本棚が、何十も室内に設置されている。同じように授業を入れておらず時間が余っているのであろう生徒たちがちらほらおり、図書室でありながら軽いざわめきが起こっていた。
(ひえ~、す、凄い。こんだけ広いと目当ての本を探すだけで大変そう……。あ、でもそういうのも魔法を使って探すのか)
その辺りの細かいことまではゲームの設定資料集に乗っていないので推測である。
(思えば私、魔法って使えるのかな? 転生してきた身だから使えなくてもおかしくないんだよな)
1年生の授業は座学と魔法薬学が大半で、実技を伴った呪文学と箒に乗る飛空術の授業はまだ行われていない。
自分が魔法を使えるかどうかはもう少し先になるかもしれない。
とりあえず今は、世界中の本を集めたかのようなこの図書室で、読みたい本を読むのが先決だ。
私は図書室の奥の方へと入っていく。
と、不意に。
「あれ?」
近くにいた男子生徒が、何かを思い立ったような声を上げた。
つられてそちらを見ると、本棚の近くにあるテーブルに、数人の男子生徒が座っている。勉強をしたり本を読んだり……ではなく、カードゲームで遊んでいるのがわかった。
いわゆるたむろしている男子生徒の内の一人から、何故か私は指を差されている。
「あんた確か、クライヴ先輩の……」
「えっ」
まさかクライヴの名前が出てくるとは思わず、私は固まってしまう。
よく見ると校章のカラーが黄色で、クライヴと同じオルニス寮の生徒だとわかる。
(な、なんだろ……なんか治安の悪い人たちに絡まれたような……)
人を見かけで判断してはならないと。それは確かにその通りなのだが、やっぱりどこか恐い見た目をしている人には近寄らないのがベストだ。
実際、彼らの態度はどこか失礼で威圧的だった。
「なんかこの人、クライヴ先輩の恋人らしくてさー」
「は?」
「先輩の恋人ぉ?」
声は抑え気味だったが、私は真正面からゲラゲラと笑われた。
頭から水を被らされたような寒気と、うなじがカッと熱くなる気持ちが同時に沸き起こった。
なんでこんな人たちにいきなりそんなことを言われなきゃならないんだとも思ったし、やっぱり自分はクライヴの恋人に相応しくないと言われるんだとも思った。
様々なショックで固まる私に、男子生徒たちはニヤニヤと笑いながら追撃してくる。
「冗談キッツイんですけど」
「俺、先輩の恋人はもっと色気ある感じだと思ってた」
「っていうか、自称してるだけなんじゃね?」
「あぁー、なるほどね」
これ以上は聞いていられないと思った。
何より、何も言い返せない自分自身が情けなくて涙がにじんだ。
「わ、私、は……」
何て言えばいい。何も思いつかない。
だけどこいつらの前で泣きたくなんてない。
悔しさで握り締めた拳に当たる爪が痛い。
その時だった。
「うるさいんですけど」
暗い、嫌そうな低音ボイスが割り込んだ。
私も男子生徒たちも、第三者の介入に口を紡ぐ。
(あれ……この声……)
浮かんだ涙をそっと拭い、私は恐る恐る振り向き……そこで石のように固まった。
そこにいたのはネイト・コンステラシオン。つまり私の推しだった。
肩にかかる夜色の黒髪に、前髪に隠れた紅い瞳。
姿勢が悪くて猫背だが、ちゃんと立つと180センチもある長身。
夜の国の大貴族コンステラシオン家の一人息子で、桁違いの魔力を持って生まれたことで、国の人だけでなく学生たちからも距離を置かれている18歳。
当の本人は根暗で、魔法よりも機械いじりが好きというギャップ付き。
そんな彼が、分厚い本を手に、ジト目でこちらを睨んでいた。
「あ、あわ、あわわ……」
私はさっきまでの悲しい気持ちも何処へやら、突然の推しの登場にわなわなと震えていた。
震えるといえば男子生徒たちも同様だった。
「げっ……ネイト・コンステラシオン」
「やば……」
ネイトから溢れ出る強すぎる魔力を感じ取ってか、借りてきた猫のように大人しくなった男子生徒たちは、そそくさと尻尾を巻いて逃げていった。
残された私は、いまだ震えが止まらないまま、茫然とした顔でネイトの方を見た。
(お、おおお推しがっ……本物の推しがいる……!)
歓喜と感動とその他もろもろの喜びが溢れ、違う意味で私は泣きそうになった。
そんな私を、おそらく男子生徒たちが恐かったのだと思われたのか、ネイトは目を反らしながらゆっくりと告げた。
「あんなの気にすることないですよ。所詮は負け犬の遠吠えなので」
その捻くれた感じも原作そのものだ。
私は心の中で自分の頬を叩き、何とか平常心を保とうとする。
「あ、あああのっ……助けてくれてありがとうございます」
「べつに。うるさかったからうるさいって言ったまでです」
「それでも助かりました!」
つい声を張り上げてしまい、近くの生徒から視線を感じ、慌てて口を閉じる。
少し落ち着きを取り戻した私は、改めてネイトの方を向く。
「本当に……ありがとうございました……あっ」
途端にポロリと涙が零れた。
張り詰めていた緊張と、込み上げた怒りと、自分自身への情けなさと、推しに助けてもらえた嬉しさが一気にきてしまった。
「す、すみません、つい……」
「………」
ネイトは、彼がお得意とするジト目でしばらくこちらを眺めていたかと思うと、ため息混じりに一枚のハンカチを差し出してくれた。
「え……でも……」
「いいから使って下さい。俺が泣かしてると思われるのも嫌なんで」
やはりどこか捻くれた口調。
だけどしてくれていることはとても紳士的で優しい。
私はハンカチを受け取ると、それで溢れる涙を何とか拭った。
「何から何まですみません。ありがとうございます。これ、洗って返しますので……」
「いいよ。あげます」
「ええっ、そんな……」
だがよく考えたら、知らない人の涙が染み込んだハンカチなど洗った程度では使いたくないかもしれない。
ここは新しい物を買って返す方が筋というものだろう。
そう思った私は、もらったハンカチをギュッと握り締めた。
(改めてだけど……本当に推しがいる……目の前に)
ネイトはすでに私から興味を無くしているのか、本を選んでいる。
その所作の一つ一つがとても愛しい。
あまりにも彼のことを見つめすぎていたのか、ネイトは怪訝そうな表情で振り返った。
「まだ何か?」
「い、いえ、あの……」
ドキドキと高鳴る鼓動を抑えるよう、胸元に手を当てた。
彼に言いたいことなど本当にたくさんある。
ゲームのキャラクターとして、私の推しとして、現実世界では何度も私を元気にしてくれた。辛くて嫌なことがあっても、ネイトがいるからと何度頑張れたことか。
だから気付くと私は、その思いの丈を口にしていた。
「あの……上手く言えないんですけど。ネイト……先輩が居てくれただけで、私はいつも頑張れているんです」
「………」
「こんなこと、意味わかんないと思うかもしれませんが言わせて下さい。生まれてきてくれてありがとうございます……っ!」
「……!」
本当に自分は何を言っているんだと思いつつ、感極まったあまりどうにも止まらなかった。
案の定、ネイトは驚いた猫のように目を見開き、しばし瞬きを忘れていた。
そしてハッと我に返った彼は、すぐに私から視線を反らしてしまった。
「……本当に意味わからないです」
「そ、そうですよね、すみません」
「ただ……」
「……?」
「そんなこと、生まれて初めて言われた」
ネイトの色白の顔は、どこか赤く色付いている。
思えばネイトは、産まれながらに魔力が強すぎて、両親からも忌み子扱いされた過去がある。
そう思うと、「生まれてきてくれてありがとう」は確かに生まれて初めて言われた言葉になるのかもしれない。
(勢い任せに言っちゃったけど、怒らせたわけじゃなくて良かった~)
ホッと安心した私は深くお辞儀をし、もらったハンカチを胸にその場を立ち去ったのだった。
「……メア・モノクロイド」
立ち去った後、ネイトが私の名前を口にしていたのも知らず、私は推しに会えた喜びでいっぱいになっていたのだった。