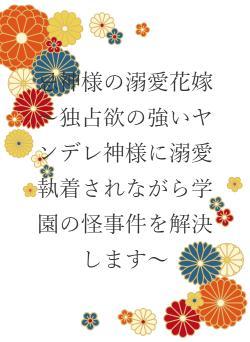壁際に並べられた薬草の入ったいくつもの瓶に、凶器にもなりそうなほど分厚い本。
大きなテーブルの上には、等間隔で並べられた小釜やフラスコが、それぞれのペアで使うように置かれている。
石造りで出来た教室は、まるでちょっとした隠れ家のようだった。
というか私からすると映画のセットか何かのようにすら思えた。
「わぁあ……凄い。魔法学校って感じだぁ」
「何わけわかんねぇこと言ってんだ。あとよそ見してると危ねぇだろうが」
「ぐえっ、す、すみません」
あっちを見たりこっちを見たりの私の首根っこを掴み、指定された席へと座らされる。
無理矢理席に着かされた私は、改めてクライヴの方を見た。
魔法薬学授業専用の白衣を着たクライヴ。正直このスキンのクライヴも格好いい。
「はいはい、ではね、魔法薬学の授業をやっていきますよ」
パンパンと手を叩きながら、魔法薬学担当の教師、ブルーノ・エルブ先生が登壇した。
今年で60歳になるブルーノ先生は、魔法薬学をそれはもう愛しているひょうきんな先生だ。
白髪混じりの黒髪に、廊下の曲がり角でもブルーノ先生がいるとわかるほど薬品の染み込んだ大きめの白衣。
小柄で面白い先生なのもあり、メインキャラではないものの「私あの先生けっこう好き」という意見の多いキャラである。
(本物のブルーノ先生だぁ……魔法薬学も本当にやれるし、ワクワクが止まらないんですが!)
モーリス先生の魔法史の授業も楽しかったが、魔法薬学は実験をする体験型の授業だ。『マジナイ』オタクの身としては、大はしゃぎせずにはいられない。
私は隣のクライヴからの視線も気にせず、食い入るようにブルーノ先生の方を見た。
「今日は簡単な傷薬を作りますからね。材料はウキウキにんじんと癒しの葉。これを沸騰したお湯へ投入。その後の火加減には要注意。1年生はまだ慣れないことも多いだろうから、先輩の力を借りるんですよ」
教室のあちこちから「はーい」という声が上がる。
だいたいの1年生たちは、初めましてな先輩たちに声をかけ、緊張しながら班を作っていく。部活で顔見知りから班を作る生徒は本当に少ししかいない。
そう思うと、強引ではあったが緊張はしないクライヴに誘ってもらえて良かったかもしれない。
「クライヴ先輩、改めてよろしくお願いします!」
「威勢のいいこった。目ぇキラキラさせやがって……そんなに魔法薬学の授業が好きなのか?」
「魔法使いっぽくて面白くないですか?」
「そうかぁ? 俺はもう飽き飽きだけどな」
猫科のように口を開けてあくびをしつつ、クライヴは頬杖をついてにやりと笑った。
「まあ、そんなに楽しそうにしてるなら俺が出る幕は無いな」
「というと?」
「できるところまで一人で頑張ってみるんだな」
「ええー!? そ、そんな殺生な……少しは手伝って下さいよぉ」
「俺が見ててやるからとっととやれ」
くそー、何様俺様クライヴ様め。
とは言いつつ、なんだかんだちゃんと見守ってくれてるのは優しいんだよな。実際、やらなきゃ覚えないことだらけだから、自由にやらせてくれるのも理にかなっているし。
なので私は、早速材料を取りに、教室の後ろにある大きなテーブルへと急いだ。
「えーとウキウキにんじん3本と癒しの葉2枚……と」
「材料はここから取っていってね」
不意に声をかけられ私はそちらを向く。そこには白衣を着た女性が立っていた。
ウェーブのかかった長い黒髪に、色気のある赤い瞳。体つきも豊満で、同性の私から見て羨まし過ぎるプロポーションだった。
(こんな美人な先生いたっけ……?)
差し出された材料を受け取りながら、私はついまじまじと彼女を見てしまう。
「ミシェル・ベネノよ、転入生さん。主に魔法薬学の補佐をしてるわ。よろしくお願いね」
「えっ、あ、は、はい。よろしくお願いします」
まるで心を読まれたかのようなタイミングに、ついキョドった反応をしてしまった。
ミシェル・ベネノ……記憶に無い名前である。魔法薬学の先生にも、補佐なんていただろうか。
しかししっかりと意思があって名乗ってもいるのだから、彼女だって公式キャラということだ。何より先生としてこれからお世話にもなるのである。ちゃんと覚えておかなければ。
「クライヴくんの班になったのよね?」
「あ、はい、そうです」
「じゃあ安心ね。彼、魔法薬学の実技は得意だから」
「そうなんですか……」
知らないフリをしたが実際そうなのである。
クライヴはスポーツ万能な上に、実技系の授業ではかなり良い点を取っている。
さすがは時期王様。英才教育も行き届いているのだろう。
「クライヴくんにもよろしくね」
「はーい」
言って、私は席に戻る。
そこには頬杖を付いたまま眠そうにしているクライヴがいて、なんだか安心した。
「ちゃんと持ってきたか?」
「大丈夫です。ウキウキにんじん3本と癒しの葉2枚、ちゃんと持ってきました」
「肝心なのはこっからだからな。火加減に気を付けろよ」
「わかりました!」
ちゃんと注意点も言ってくれて優しいなぁ。
私は小釜の下の着火装置で点火し、湯を沸かす。しばらくするとゴポゴポと音が立ち沸騰の合図がくる。
そうして煮立ったお湯の中にウキウキにんじんと癒しの葉を入れた。
ここからが勝負。
火の強さを中火に変え、小釜の中身をしっかりチェックする。
なんだか料理を作るのと似ているなと思った。
そうこうしているうちに、小釜の中のお湯の色が濁った緑色から鮮やかな桃色へと変わる。
「く、クライヴ先輩見てください! できた! できましたよ!」
思わずクライヴに満面の笑みを見せれば、やれやれと言いつつ同じように笑みを浮かべるクライヴの姿があった。
クライヴは立ち上がり、一緒に小釜の中を見る。
「言っとくけど傷薬は初歩中の初歩だからな。こんぐらいで一喜一憂してると……」
「……?」
言いながら言葉の途切れたクライヴに、私は首を傾げる。
どうしたのだろうか。
そう思っていた矢先、小釜の中身が突如としてどす黒い紫色へと変化する。
何か、やばい。
その瞬間。
「くそっ!」
「ッ!」
ボンッという破裂音と共に、小釜の中身が爆発した。
その中身が私にかかるという直前で、私はクライヴに抱きしめられた。
「先輩!」
「あっちぃ~」
クライヴは、身を挺して庇ってくれたのだ。
私を。
まだ知り合って間もないこの私を。
「せ、先輩……やだ……大丈夫ですか!?」
「ちょっと熱かっただけだ」
「そんなわけ……あんなに煮立ってたのに……。は、早く水! 水を……っ!」
「落ち着け」
慌てふためく私の顔を掴み、クライヴは真っ直ぐこちらを見つめた。
鋭い金色の瞳は、夜空に浮かぶ月のように落ち着き払っている。
その瞳を前にして、私も少しずつ落ち着きを取り戻す。
「大丈夫かい!」
気付くと、周囲の生徒をかきわけブルーノ先生がやって来た。
先生が杖を振ると、キラキラとした輝きがクライヴの背中に当たる。
恐らく火傷を治してくれたのだろう。クライヴの表情が安堵したものへと変わった。
「すみません……私、私が小釜を爆発させて……」
「俺の監督不行き届きでした。すみません」
「っ……!」
体を張って庇うだけでなく、私の失敗まで庇ってくれるなんて。
私は……クライヴというキャラクターのことを何もわかっていなかった。
表面上の設定だけを追ってわかった気でいただけだ。
こんなに紳士で思い遣りがある人だったんだ。
私を数々のことから守ってくれたクライヴに、自然と涙が込み上げた。
「まあまあ、そんな落ち込まないで。だいたい1年生はやらかすもんだから。クライヴくん、メアさんを守って偉かったね」
「ごめんなさい、クライヴ先輩」
「謝るな。悪いと思うなら次こそ成功させろ」
「先輩……」
「何泣いてんだ」
ポンポンと頭を撫でられ、私は涙を拭った。
これはもう、絶対に次を成功させなきゃ駄目なやつだ。
「次は失敗しませんから! 見ててください!」
「ああ」
クライヴの優しい微笑みに背中を押され、私は再び作業に取り掛かり、今度こそ完璧な成功を収めるのだった。
大きなテーブルの上には、等間隔で並べられた小釜やフラスコが、それぞれのペアで使うように置かれている。
石造りで出来た教室は、まるでちょっとした隠れ家のようだった。
というか私からすると映画のセットか何かのようにすら思えた。
「わぁあ……凄い。魔法学校って感じだぁ」
「何わけわかんねぇこと言ってんだ。あとよそ見してると危ねぇだろうが」
「ぐえっ、す、すみません」
あっちを見たりこっちを見たりの私の首根っこを掴み、指定された席へと座らされる。
無理矢理席に着かされた私は、改めてクライヴの方を見た。
魔法薬学授業専用の白衣を着たクライヴ。正直このスキンのクライヴも格好いい。
「はいはい、ではね、魔法薬学の授業をやっていきますよ」
パンパンと手を叩きながら、魔法薬学担当の教師、ブルーノ・エルブ先生が登壇した。
今年で60歳になるブルーノ先生は、魔法薬学をそれはもう愛しているひょうきんな先生だ。
白髪混じりの黒髪に、廊下の曲がり角でもブルーノ先生がいるとわかるほど薬品の染み込んだ大きめの白衣。
小柄で面白い先生なのもあり、メインキャラではないものの「私あの先生けっこう好き」という意見の多いキャラである。
(本物のブルーノ先生だぁ……魔法薬学も本当にやれるし、ワクワクが止まらないんですが!)
モーリス先生の魔法史の授業も楽しかったが、魔法薬学は実験をする体験型の授業だ。『マジナイ』オタクの身としては、大はしゃぎせずにはいられない。
私は隣のクライヴからの視線も気にせず、食い入るようにブルーノ先生の方を見た。
「今日は簡単な傷薬を作りますからね。材料はウキウキにんじんと癒しの葉。これを沸騰したお湯へ投入。その後の火加減には要注意。1年生はまだ慣れないことも多いだろうから、先輩の力を借りるんですよ」
教室のあちこちから「はーい」という声が上がる。
だいたいの1年生たちは、初めましてな先輩たちに声をかけ、緊張しながら班を作っていく。部活で顔見知りから班を作る生徒は本当に少ししかいない。
そう思うと、強引ではあったが緊張はしないクライヴに誘ってもらえて良かったかもしれない。
「クライヴ先輩、改めてよろしくお願いします!」
「威勢のいいこった。目ぇキラキラさせやがって……そんなに魔法薬学の授業が好きなのか?」
「魔法使いっぽくて面白くないですか?」
「そうかぁ? 俺はもう飽き飽きだけどな」
猫科のように口を開けてあくびをしつつ、クライヴは頬杖をついてにやりと笑った。
「まあ、そんなに楽しそうにしてるなら俺が出る幕は無いな」
「というと?」
「できるところまで一人で頑張ってみるんだな」
「ええー!? そ、そんな殺生な……少しは手伝って下さいよぉ」
「俺が見ててやるからとっととやれ」
くそー、何様俺様クライヴ様め。
とは言いつつ、なんだかんだちゃんと見守ってくれてるのは優しいんだよな。実際、やらなきゃ覚えないことだらけだから、自由にやらせてくれるのも理にかなっているし。
なので私は、早速材料を取りに、教室の後ろにある大きなテーブルへと急いだ。
「えーとウキウキにんじん3本と癒しの葉2枚……と」
「材料はここから取っていってね」
不意に声をかけられ私はそちらを向く。そこには白衣を着た女性が立っていた。
ウェーブのかかった長い黒髪に、色気のある赤い瞳。体つきも豊満で、同性の私から見て羨まし過ぎるプロポーションだった。
(こんな美人な先生いたっけ……?)
差し出された材料を受け取りながら、私はついまじまじと彼女を見てしまう。
「ミシェル・ベネノよ、転入生さん。主に魔法薬学の補佐をしてるわ。よろしくお願いね」
「えっ、あ、は、はい。よろしくお願いします」
まるで心を読まれたかのようなタイミングに、ついキョドった反応をしてしまった。
ミシェル・ベネノ……記憶に無い名前である。魔法薬学の先生にも、補佐なんていただろうか。
しかししっかりと意思があって名乗ってもいるのだから、彼女だって公式キャラということだ。何より先生としてこれからお世話にもなるのである。ちゃんと覚えておかなければ。
「クライヴくんの班になったのよね?」
「あ、はい、そうです」
「じゃあ安心ね。彼、魔法薬学の実技は得意だから」
「そうなんですか……」
知らないフリをしたが実際そうなのである。
クライヴはスポーツ万能な上に、実技系の授業ではかなり良い点を取っている。
さすがは時期王様。英才教育も行き届いているのだろう。
「クライヴくんにもよろしくね」
「はーい」
言って、私は席に戻る。
そこには頬杖を付いたまま眠そうにしているクライヴがいて、なんだか安心した。
「ちゃんと持ってきたか?」
「大丈夫です。ウキウキにんじん3本と癒しの葉2枚、ちゃんと持ってきました」
「肝心なのはこっからだからな。火加減に気を付けろよ」
「わかりました!」
ちゃんと注意点も言ってくれて優しいなぁ。
私は小釜の下の着火装置で点火し、湯を沸かす。しばらくするとゴポゴポと音が立ち沸騰の合図がくる。
そうして煮立ったお湯の中にウキウキにんじんと癒しの葉を入れた。
ここからが勝負。
火の強さを中火に変え、小釜の中身をしっかりチェックする。
なんだか料理を作るのと似ているなと思った。
そうこうしているうちに、小釜の中のお湯の色が濁った緑色から鮮やかな桃色へと変わる。
「く、クライヴ先輩見てください! できた! できましたよ!」
思わずクライヴに満面の笑みを見せれば、やれやれと言いつつ同じように笑みを浮かべるクライヴの姿があった。
クライヴは立ち上がり、一緒に小釜の中を見る。
「言っとくけど傷薬は初歩中の初歩だからな。こんぐらいで一喜一憂してると……」
「……?」
言いながら言葉の途切れたクライヴに、私は首を傾げる。
どうしたのだろうか。
そう思っていた矢先、小釜の中身が突如としてどす黒い紫色へと変化する。
何か、やばい。
その瞬間。
「くそっ!」
「ッ!」
ボンッという破裂音と共に、小釜の中身が爆発した。
その中身が私にかかるという直前で、私はクライヴに抱きしめられた。
「先輩!」
「あっちぃ~」
クライヴは、身を挺して庇ってくれたのだ。
私を。
まだ知り合って間もないこの私を。
「せ、先輩……やだ……大丈夫ですか!?」
「ちょっと熱かっただけだ」
「そんなわけ……あんなに煮立ってたのに……。は、早く水! 水を……っ!」
「落ち着け」
慌てふためく私の顔を掴み、クライヴは真っ直ぐこちらを見つめた。
鋭い金色の瞳は、夜空に浮かぶ月のように落ち着き払っている。
その瞳を前にして、私も少しずつ落ち着きを取り戻す。
「大丈夫かい!」
気付くと、周囲の生徒をかきわけブルーノ先生がやって来た。
先生が杖を振ると、キラキラとした輝きがクライヴの背中に当たる。
恐らく火傷を治してくれたのだろう。クライヴの表情が安堵したものへと変わった。
「すみません……私、私が小釜を爆発させて……」
「俺の監督不行き届きでした。すみません」
「っ……!」
体を張って庇うだけでなく、私の失敗まで庇ってくれるなんて。
私は……クライヴというキャラクターのことを何もわかっていなかった。
表面上の設定だけを追ってわかった気でいただけだ。
こんなに紳士で思い遣りがある人だったんだ。
私を数々のことから守ってくれたクライヴに、自然と涙が込み上げた。
「まあまあ、そんな落ち込まないで。だいたい1年生はやらかすもんだから。クライヴくん、メアさんを守って偉かったね」
「ごめんなさい、クライヴ先輩」
「謝るな。悪いと思うなら次こそ成功させろ」
「先輩……」
「何泣いてんだ」
ポンポンと頭を撫でられ、私は涙を拭った。
これはもう、絶対に次を成功させなきゃ駄目なやつだ。
「次は失敗しませんから! 見ててください!」
「ああ」
クライヴの優しい微笑みに背中を押され、私は再び作業に取り掛かり、今度こそ完璧な成功を収めるのだった。