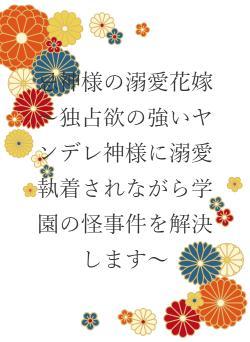「く、クライヴ先輩……!」
気だるそうとは違う、明らかにどこか不機嫌そうな表情でクライヴは私たちを見ている。
しっかり筋肉もついていて背丈も高いため、非常に圧を感じるのだった。
「ど、どうしたんですか……?」
「どうしたはこっちの台詞だ。俺は何度かおまえのマジパッドに連絡を入れたぜ?」
「えっ」
言われて慌ててマジパッドを取り出すと、確かにクライヴから数件のメッセージが入っていた。
これは……つまり未読無視の状態だ。
「ひえっ! す、すすすみません、全然気付いてなくて……」
「おまえなぁ」
一歩、クライヴが私に近付こうとした。
しかしその前に、私とクライヴの間にアルバートが割り込んだ。
まるでアルバートに庇われるような位置関係になり、私は目を丸くしてしまう。
「あ?」
「僕が彼女を引き留めていたんだ。僕からも謝ろう。すまなかった」
しかめっ面をしているクライヴと、キラキラ笑顔で謝罪するアルバート。
完全に悪役に絡まれた私を助けてくれるプリンスの図である。
実際の王子様の肩書きを持っているのはクライヴの方だというのに。
(あれ……そういえばこの二人って……)
私はふと思い出す。
確かこの二人、公式で犬猿の仲だったはず。
俺様王子なクライヴが、なんとなくアルバートのことをいけ好かなく思っていて、アルバートはアルバートでクライヴからの挑発を難なくかわしているから、とにかく相性の悪い二人なのだ。
しかしファンからすると、そういったキャラの関係性も美味しかったりして。けっこうこの二人が描かれたファンアートも多い。
「おい、なんだよアルバート。俺はそいつと話してんだ。どけ」
「どうして君はそう威圧的なんだ。メアが怯えてるじゃないか」
「『メア』だぁ?」
前言撤回。
この二人の関係性が美味しいとか思えるのは、自分が関わっていないからに限る。
何なんだこの一触即発な恐ろしい空気は。
しかも自分が話題の中心になっているものだから、その恐怖感といったらない。
私はアルバートの背中から少し横にずれ、恐る恐るクライヴの方を見る。
バッチリ目が合うと、やはりそこには不機嫌そうなクライヴの姿があった。
「あのあの、未読無視しちゃってすみませんでしたホントに」
「……べつにんなことで怒ってんじゃねぇよ。よりにもよってこのすかした野郎と関わってるから注意しに来ただけだ」
「注意って……」
「酷いなぁクライヴ」
のほほんと苦笑するアルバートに、クライヴは痺れを切らしたのか一歩前に出る。
そしてアルバートの後ろにいる私の腕が引かれ、私はクライヴの隣に立つことになった。
「自分の女に余計な虫が付くのは困るんでな」
「!?」
クライヴの発言に私は口を開けて固まった。
まさかアルバートの前でも恋人の主張をするとは思っておらず、ドクドクと心臓が早くなる。
アルバートも、珍しくキョトンとした表情を浮かべていた。
「え……君たち付き合っているのかい?」
「そう言ってんだろ」
「いやあのえーと……ひぃっ!」
反射的に弁明を試みようとしてしまい、私はクライヴから睨まれた。
だっていきなり恋人宣言されるの、やっぱりまだ慣れないというか心臓に悪いというか。
しかしそんな私の気も知らないで、クライヴは私の腰を抱いて更に引き寄せる。
「ちょッ!?」
「ははっ。なんだその間抜け面」
慌てふためく私を見て、ようやくクライヴは笑ってみせた。
子供のように笑うその姿に、思わず私はドキリと胸を鳴らした。
私は私が思っている以上に、クライヴのこの笑顔が好きなのかもしれない。
「そうか、付き合っているのか」
一方、アルバートは何故か真剣な顔をしてそう呟いていた。
私の方をジッと見て、何かを考えているようだった……の、だが、彼はマジパッドを取り出しニコリと笑う。
「でも連絡先の交換はいいよね?」
満面の笑顔でアルバートはそんな提案をしてくる。
太陽光に照らされ、キラキラと輝いているアルバートはまさにプリンスで、その笑顔だけでSSRカードだと思った。
「あぁ? 誰がおまえと……」
「えー! ぜひしたいです!」
反射的に私は子供のようにキャッキャとはしゃいでしまった。
だってメインキャラと仲良くなれるならそれに越したことはない。普通に嬉し過ぎる。
だから私は隣に立つクライヴを見上げ、ウルウルと目をうるませて懇願した。
「クライヴ先輩~」
「……ちっ。別に俺はそこまで心の狭い男じゃねぇよ」
さっきまで拒否ろうとしていたくせに、なんとも可愛い男である。
私はホクホク顔でマジパッドを取り出した。
アルバートもニコニコと笑いながらマジパッドを近付け、シャランッという音と共にお互いの連絡先が交換される。
「ありがとうございます」
「僕こそありがとう。何か用があったら気兼ねなく連絡してね」
「はい!」
「それじゃあ」
柔らかな笑みと共に礼をして、軽やかにアルバートは去って行く。
去り際も実にスマートで、何て素敵な王子様だろうと思った。
「おまえ、ああいうのが好みなのか?」
「はい?」
しばらくアルバートの姿を見送っていたら、隣からそんなことを言われた。
また、どことなく不機嫌になりかけているクライヴは、ジト目で私を見下ろしている。
「いや、好みとかそういうんじゃ……」
「ふぅん。まあ、もし本当に好きな奴ができたら偽りの恋人役も取り止めでいいけどな」
「え……」
「一人の女の恋路を邪魔してまで自分が得しようとは思ってねぇよ」
その金色の瞳は、どこか遠い所を見ている。
本当は家のこと、跡継ぎのこと、婚約者のことで滅入っているくせに、その言葉はどこか寂しげで優しい。
だから私は、ポンポンとクライヴの背中を軽く叩いた。
「大丈夫ですよ。私、たぶん恋とかしないと思うんで。ちゃんと先輩の恋人役を全うしますよ」
「なんで恋しないって断言できる?」
「いや、それはその……」
ここが推しゲーム『マジナイ』の中だから、というわけにもいかない。
だって『マジナイ』のキャラに対する思いってのは『推し』なのだ。『好き』の種類が違う。
だから恋なんてしないと思うのだ。普通にメインキャラたちとの日々を楽しく送れればそれでいいと考えている。
(それとも……気付いたら誰かに恋してるなんてことあるのかな……)
ぼんやりとそんなことを思っていたら、目の前にクライヴの顔があり私は目を見開く。
「俺がいながら恋しないなんて本当に断言できんのか?」
「んなっ……なんて自信過剰なお言葉……」
「ははっ、冗談だ」
また、子供のようにケラケラと笑うクライヴ。
悔しいがその様子も凄く格好良くて、アルバートに対して抱いていたのとは違う照れがやってくる。
もしクライヴ推しの人がこの世界に来て偽りの恋人役を申し出られたらどうなっていたんだろうか。
「そういえば先輩、私に何のメッセージ送ったんです?」
「ああ。次の魔法薬学、フィオーレ寮とオルニス寮の1年と4年が合同だろ? だから一緒に組もうと思ってな」
「えっ、先輩と!?」
「なんだ、不服か?」
「不服じゃないですけど……先輩と組みたがっている人、たくさんいると思うんですが……」
とくにこの人、女子生徒はもちろん男子生徒からも熱い支持を得ている。ただでさえ恋人役で女子生徒たちから白い目で見られそうだというのに、男子生徒たちからも反感は買いたくない。
だが、断りムードな私を、クライヴは鋭く睨みつけている。
「俺がおまえと組んでやるって言ってんだ。文句あるのか?」
「な、無いです……」
私が小声でそう返すと、ようやく満足したのかクライヴはふんっと笑ってみせた。
(魔法薬学なんてやったことないのに、いきなりクライヴと組むだなんて……絶対何かやらかすよ~)
嫌な予感を抱く私を余所に、何故かクライヴはご機嫌なのだった。
気だるそうとは違う、明らかにどこか不機嫌そうな表情でクライヴは私たちを見ている。
しっかり筋肉もついていて背丈も高いため、非常に圧を感じるのだった。
「ど、どうしたんですか……?」
「どうしたはこっちの台詞だ。俺は何度かおまえのマジパッドに連絡を入れたぜ?」
「えっ」
言われて慌ててマジパッドを取り出すと、確かにクライヴから数件のメッセージが入っていた。
これは……つまり未読無視の状態だ。
「ひえっ! す、すすすみません、全然気付いてなくて……」
「おまえなぁ」
一歩、クライヴが私に近付こうとした。
しかしその前に、私とクライヴの間にアルバートが割り込んだ。
まるでアルバートに庇われるような位置関係になり、私は目を丸くしてしまう。
「あ?」
「僕が彼女を引き留めていたんだ。僕からも謝ろう。すまなかった」
しかめっ面をしているクライヴと、キラキラ笑顔で謝罪するアルバート。
完全に悪役に絡まれた私を助けてくれるプリンスの図である。
実際の王子様の肩書きを持っているのはクライヴの方だというのに。
(あれ……そういえばこの二人って……)
私はふと思い出す。
確かこの二人、公式で犬猿の仲だったはず。
俺様王子なクライヴが、なんとなくアルバートのことをいけ好かなく思っていて、アルバートはアルバートでクライヴからの挑発を難なくかわしているから、とにかく相性の悪い二人なのだ。
しかしファンからすると、そういったキャラの関係性も美味しかったりして。けっこうこの二人が描かれたファンアートも多い。
「おい、なんだよアルバート。俺はそいつと話してんだ。どけ」
「どうして君はそう威圧的なんだ。メアが怯えてるじゃないか」
「『メア』だぁ?」
前言撤回。
この二人の関係性が美味しいとか思えるのは、自分が関わっていないからに限る。
何なんだこの一触即発な恐ろしい空気は。
しかも自分が話題の中心になっているものだから、その恐怖感といったらない。
私はアルバートの背中から少し横にずれ、恐る恐るクライヴの方を見る。
バッチリ目が合うと、やはりそこには不機嫌そうなクライヴの姿があった。
「あのあの、未読無視しちゃってすみませんでしたホントに」
「……べつにんなことで怒ってんじゃねぇよ。よりにもよってこのすかした野郎と関わってるから注意しに来ただけだ」
「注意って……」
「酷いなぁクライヴ」
のほほんと苦笑するアルバートに、クライヴは痺れを切らしたのか一歩前に出る。
そしてアルバートの後ろにいる私の腕が引かれ、私はクライヴの隣に立つことになった。
「自分の女に余計な虫が付くのは困るんでな」
「!?」
クライヴの発言に私は口を開けて固まった。
まさかアルバートの前でも恋人の主張をするとは思っておらず、ドクドクと心臓が早くなる。
アルバートも、珍しくキョトンとした表情を浮かべていた。
「え……君たち付き合っているのかい?」
「そう言ってんだろ」
「いやあのえーと……ひぃっ!」
反射的に弁明を試みようとしてしまい、私はクライヴから睨まれた。
だっていきなり恋人宣言されるの、やっぱりまだ慣れないというか心臓に悪いというか。
しかしそんな私の気も知らないで、クライヴは私の腰を抱いて更に引き寄せる。
「ちょッ!?」
「ははっ。なんだその間抜け面」
慌てふためく私を見て、ようやくクライヴは笑ってみせた。
子供のように笑うその姿に、思わず私はドキリと胸を鳴らした。
私は私が思っている以上に、クライヴのこの笑顔が好きなのかもしれない。
「そうか、付き合っているのか」
一方、アルバートは何故か真剣な顔をしてそう呟いていた。
私の方をジッと見て、何かを考えているようだった……の、だが、彼はマジパッドを取り出しニコリと笑う。
「でも連絡先の交換はいいよね?」
満面の笑顔でアルバートはそんな提案をしてくる。
太陽光に照らされ、キラキラと輝いているアルバートはまさにプリンスで、その笑顔だけでSSRカードだと思った。
「あぁ? 誰がおまえと……」
「えー! ぜひしたいです!」
反射的に私は子供のようにキャッキャとはしゃいでしまった。
だってメインキャラと仲良くなれるならそれに越したことはない。普通に嬉し過ぎる。
だから私は隣に立つクライヴを見上げ、ウルウルと目をうるませて懇願した。
「クライヴ先輩~」
「……ちっ。別に俺はそこまで心の狭い男じゃねぇよ」
さっきまで拒否ろうとしていたくせに、なんとも可愛い男である。
私はホクホク顔でマジパッドを取り出した。
アルバートもニコニコと笑いながらマジパッドを近付け、シャランッという音と共にお互いの連絡先が交換される。
「ありがとうございます」
「僕こそありがとう。何か用があったら気兼ねなく連絡してね」
「はい!」
「それじゃあ」
柔らかな笑みと共に礼をして、軽やかにアルバートは去って行く。
去り際も実にスマートで、何て素敵な王子様だろうと思った。
「おまえ、ああいうのが好みなのか?」
「はい?」
しばらくアルバートの姿を見送っていたら、隣からそんなことを言われた。
また、どことなく不機嫌になりかけているクライヴは、ジト目で私を見下ろしている。
「いや、好みとかそういうんじゃ……」
「ふぅん。まあ、もし本当に好きな奴ができたら偽りの恋人役も取り止めでいいけどな」
「え……」
「一人の女の恋路を邪魔してまで自分が得しようとは思ってねぇよ」
その金色の瞳は、どこか遠い所を見ている。
本当は家のこと、跡継ぎのこと、婚約者のことで滅入っているくせに、その言葉はどこか寂しげで優しい。
だから私は、ポンポンとクライヴの背中を軽く叩いた。
「大丈夫ですよ。私、たぶん恋とかしないと思うんで。ちゃんと先輩の恋人役を全うしますよ」
「なんで恋しないって断言できる?」
「いや、それはその……」
ここが推しゲーム『マジナイ』の中だから、というわけにもいかない。
だって『マジナイ』のキャラに対する思いってのは『推し』なのだ。『好き』の種類が違う。
だから恋なんてしないと思うのだ。普通にメインキャラたちとの日々を楽しく送れればそれでいいと考えている。
(それとも……気付いたら誰かに恋してるなんてことあるのかな……)
ぼんやりとそんなことを思っていたら、目の前にクライヴの顔があり私は目を見開く。
「俺がいながら恋しないなんて本当に断言できんのか?」
「んなっ……なんて自信過剰なお言葉……」
「ははっ、冗談だ」
また、子供のようにケラケラと笑うクライヴ。
悔しいがその様子も凄く格好良くて、アルバートに対して抱いていたのとは違う照れがやってくる。
もしクライヴ推しの人がこの世界に来て偽りの恋人役を申し出られたらどうなっていたんだろうか。
「そういえば先輩、私に何のメッセージ送ったんです?」
「ああ。次の魔法薬学、フィオーレ寮とオルニス寮の1年と4年が合同だろ? だから一緒に組もうと思ってな」
「えっ、先輩と!?」
「なんだ、不服か?」
「不服じゃないですけど……先輩と組みたがっている人、たくさんいると思うんですが……」
とくにこの人、女子生徒はもちろん男子生徒からも熱い支持を得ている。ただでさえ恋人役で女子生徒たちから白い目で見られそうだというのに、男子生徒たちからも反感は買いたくない。
だが、断りムードな私を、クライヴは鋭く睨みつけている。
「俺がおまえと組んでやるって言ってんだ。文句あるのか?」
「な、無いです……」
私が小声でそう返すと、ようやく満足したのかクライヴはふんっと笑ってみせた。
(魔法薬学なんてやったことないのに、いきなりクライヴと組むだなんて……絶対何かやらかすよ~)
嫌な予感を抱く私を余所に、何故かクライヴはご機嫌なのだった。