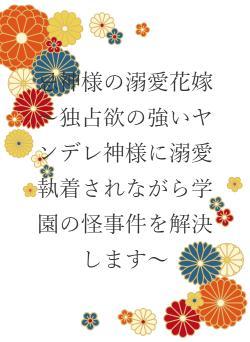「というわけで来週はこの範囲から小テストを行うからな。きちんと予習してくるように」
魔法史を教えていたモーリス先生がそう言い終えるのと同時に、鐘の音が鳴り響く。真面目で几帳面な先生らしく、ピッタリと授業を終えてくれた。
今回は1、2学年のフィオーレ寮とオルニス寮合同の授業だったのもあり、授業が終わるや否や、フィオーレ寮の女子生徒に、オルニス寮の男子生徒が声をかけ始めていた。
体育会系のオルニス寮の男子生徒なだけあって、ナンパっぽい仕草もどこかサマになっている。
「来週小テストですって。メア、ちゃんと予習するのよ」
「お、オッケー」
「まあ、私が予習に付き合ってもよろしくてよ」
「アイネ様ぁ……」
もうわかりやすいツンデレで可愛すぎる。
それにしても小テストだなんて何年ぶりだろうか。
授業も懐かしいなぁなんて思いながら受けていて、正直楽しかったぐらいだ。
と、その時。
「お、おいあれ……」
「え、マジかよ」
それまで女性生徒たちに声をかけていたオルニス寮の男子生徒たちが、何やら違うざわつきを見せ始めた。
何やら廊下の方を見ているので、私もそちらへつられて見てみればそこには……
「よお」
バッチリ目が合ったそこにいたのはクライヴだった。
そうか、道理でオルニス寮の男子生徒が騒ぐわけだ。クライヴはオルニス寮でカリスマ的存在として崇められているのだから。
(え、まさか私……?)
その予感は的中で、クライヴは私を見ながら人差し指をくいくいと動かし、こっちに来いと目で訴えかけていた。
私は急いでそちらへ向かう。
「クライヴ先輩、どうしたんですか……?」
「そういやぁ連絡先聞いてなかったと思ってな」
言って、クライヴはマジパッドを出す。
マジパッドとは正式名称マジックパッドと言い、現実世界で言うスマホと同じものだ。
私はそこで気付く。
マジパッドを持っていないことに。
「あ、あの」
「なんだよ?」
「私その……マジパッド持っていなくてですね」
「は?」
クライヴは信じられないものを見る目を私に向けた。
それはそうだろうな。
10歳ぐらいの子すら持っていてもおかしくない、生活の必需品のようなものだ。
とはいえ私は転生してきた身。
マジパッドなど持っているわけがないのである。
(確かメインストーリーが進んでいくと、モーリス先生が買ってくれるんだよなぁ)
早くマジパッドを触ってみたいが、それまでは色々とお預けということだ。
と、私が落ち込んでいた矢先……
「ああ。最速で届けろ。すぐにだ」
「……?」
クライヴは何やら誰かと通話していたかと思うと、こちらを向いた。
「おまえのマジパッド、次の授業が終わる頃には到着する」
「は、へ?」
「そこに俺の連絡先も入れておくからな」
「え、ちょ、それって……ええ!? か、買ってくれたんですか!?」
けっこういいお値段するマジパッドを、クライヴは今の電話一本で買ったということになる。
信じられなくて慌てる私に、近くでそれを見ていて更にざわつくオルニス寮の男子生徒たち。
だが、当のクライヴは気だるそうな表情で落ち着き払っている。
「わ、わ、悪いですよそれ。あのじゃあ、まとまったお金ができたらすぐに返しま……」
「おい。あんまり俺に恥かかすな。付き合ってる女の欲しいものぐらい買わせろ」
ハッキリと言い放ったクライヴの言葉に、オルニス寮の男子生徒だけでなくフィオーレ寮の女子生徒たちまでどよめきを見せた。
「え、今付き合ってるって……」
「クライヴ様があの子と……?」
「嘘だろ、マジかよ……」
マジかよはこっちの台詞である。
なにもこんなところでバラさなくてもと思う反面、偽りの恋人役をやるということはこういうことなのだと身に染みる。
慌てふためく私を見て、またツボっているのかクライヴはその端正な顔に笑みを浮かべていた。
「じゃ、用はそれだけだ。使いの奴が届けるから、ちゃんと受け取れよ?」
「は、はい……」
言って、クライヴは颯爽と去って行く。
残された私はその場で俯き、周りの目が恐くて仕方がなかった。
「メア! どういうことなの! 説明して!」
それまで静かにしていたアイネが、勢いよくこちらへやって来る。
とりあえず私はアイネを連れて教室を出た。
そしてひと気の無い階段付近で立ち止まる。
「えーと……なんやかんやでクライヴ先輩とお付き合いすることになりまして」
「なんやかんやってなんですの!? 一体いつの間に!」
「話せば長くなるような短くなるような……」
しどろもどろになる私を哀れに思ったのか、アイネはそれ以上質問をしてこなかった。
しばらく腕を組んでこちらを見ていたかと思うと、深く息を吐いた。
「ふう。わかりましたわ」
「え?」
「メアとクライヴ先輩の恋、応援いたしますわ!」
「ええ!?」
まさかの発言に私は声を上げてしまう。
しかしアイネの表情は輝きに満ちており、がっしりと私は手を掴まれた。
(これは本気だ。本気で応援する目だ)
アイネはこれと決めたら真っ直ぐに突き進む子である。
つまり心の底から、私とクライヴを応援してくれることだろう。
けれど私たちのお付き合いは嘘のようなもの。
なんだか悪いような気もしてしまう。
(やっぱり偽りの恋人役、早まったかなぁ……)
ついついそんなことを考えてしまう私の元には、次の授業が終わった後、王族彼氏からのマジパッドが本当に届いたのだった。
魔法史を教えていたモーリス先生がそう言い終えるのと同時に、鐘の音が鳴り響く。真面目で几帳面な先生らしく、ピッタリと授業を終えてくれた。
今回は1、2学年のフィオーレ寮とオルニス寮合同の授業だったのもあり、授業が終わるや否や、フィオーレ寮の女子生徒に、オルニス寮の男子生徒が声をかけ始めていた。
体育会系のオルニス寮の男子生徒なだけあって、ナンパっぽい仕草もどこかサマになっている。
「来週小テストですって。メア、ちゃんと予習するのよ」
「お、オッケー」
「まあ、私が予習に付き合ってもよろしくてよ」
「アイネ様ぁ……」
もうわかりやすいツンデレで可愛すぎる。
それにしても小テストだなんて何年ぶりだろうか。
授業も懐かしいなぁなんて思いながら受けていて、正直楽しかったぐらいだ。
と、その時。
「お、おいあれ……」
「え、マジかよ」
それまで女性生徒たちに声をかけていたオルニス寮の男子生徒たちが、何やら違うざわつきを見せ始めた。
何やら廊下の方を見ているので、私もそちらへつられて見てみればそこには……
「よお」
バッチリ目が合ったそこにいたのはクライヴだった。
そうか、道理でオルニス寮の男子生徒が騒ぐわけだ。クライヴはオルニス寮でカリスマ的存在として崇められているのだから。
(え、まさか私……?)
その予感は的中で、クライヴは私を見ながら人差し指をくいくいと動かし、こっちに来いと目で訴えかけていた。
私は急いでそちらへ向かう。
「クライヴ先輩、どうしたんですか……?」
「そういやぁ連絡先聞いてなかったと思ってな」
言って、クライヴはマジパッドを出す。
マジパッドとは正式名称マジックパッドと言い、現実世界で言うスマホと同じものだ。
私はそこで気付く。
マジパッドを持っていないことに。
「あ、あの」
「なんだよ?」
「私その……マジパッド持っていなくてですね」
「は?」
クライヴは信じられないものを見る目を私に向けた。
それはそうだろうな。
10歳ぐらいの子すら持っていてもおかしくない、生活の必需品のようなものだ。
とはいえ私は転生してきた身。
マジパッドなど持っているわけがないのである。
(確かメインストーリーが進んでいくと、モーリス先生が買ってくれるんだよなぁ)
早くマジパッドを触ってみたいが、それまでは色々とお預けということだ。
と、私が落ち込んでいた矢先……
「ああ。最速で届けろ。すぐにだ」
「……?」
クライヴは何やら誰かと通話していたかと思うと、こちらを向いた。
「おまえのマジパッド、次の授業が終わる頃には到着する」
「は、へ?」
「そこに俺の連絡先も入れておくからな」
「え、ちょ、それって……ええ!? か、買ってくれたんですか!?」
けっこういいお値段するマジパッドを、クライヴは今の電話一本で買ったということになる。
信じられなくて慌てる私に、近くでそれを見ていて更にざわつくオルニス寮の男子生徒たち。
だが、当のクライヴは気だるそうな表情で落ち着き払っている。
「わ、わ、悪いですよそれ。あのじゃあ、まとまったお金ができたらすぐに返しま……」
「おい。あんまり俺に恥かかすな。付き合ってる女の欲しいものぐらい買わせろ」
ハッキリと言い放ったクライヴの言葉に、オルニス寮の男子生徒だけでなくフィオーレ寮の女子生徒たちまでどよめきを見せた。
「え、今付き合ってるって……」
「クライヴ様があの子と……?」
「嘘だろ、マジかよ……」
マジかよはこっちの台詞である。
なにもこんなところでバラさなくてもと思う反面、偽りの恋人役をやるということはこういうことなのだと身に染みる。
慌てふためく私を見て、またツボっているのかクライヴはその端正な顔に笑みを浮かべていた。
「じゃ、用はそれだけだ。使いの奴が届けるから、ちゃんと受け取れよ?」
「は、はい……」
言って、クライヴは颯爽と去って行く。
残された私はその場で俯き、周りの目が恐くて仕方がなかった。
「メア! どういうことなの! 説明して!」
それまで静かにしていたアイネが、勢いよくこちらへやって来る。
とりあえず私はアイネを連れて教室を出た。
そしてひと気の無い階段付近で立ち止まる。
「えーと……なんやかんやでクライヴ先輩とお付き合いすることになりまして」
「なんやかんやってなんですの!? 一体いつの間に!」
「話せば長くなるような短くなるような……」
しどろもどろになる私を哀れに思ったのか、アイネはそれ以上質問をしてこなかった。
しばらく腕を組んでこちらを見ていたかと思うと、深く息を吐いた。
「ふう。わかりましたわ」
「え?」
「メアとクライヴ先輩の恋、応援いたしますわ!」
「ええ!?」
まさかの発言に私は声を上げてしまう。
しかしアイネの表情は輝きに満ちており、がっしりと私は手を掴まれた。
(これは本気だ。本気で応援する目だ)
アイネはこれと決めたら真っ直ぐに突き進む子である。
つまり心の底から、私とクライヴを応援してくれることだろう。
けれど私たちのお付き合いは嘘のようなもの。
なんだか悪いような気もしてしまう。
(やっぱり偽りの恋人役、早まったかなぁ……)
ついついそんなことを考えてしまう私の元には、次の授業が終わった後、王族彼氏からのマジパッドが本当に届いたのだった。