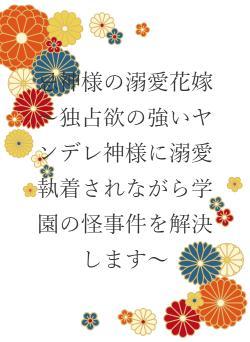一目見てわかった。
こいつが俺のことを『そういう目』で見ていないことを。
突然ずぶ濡れで現れたそいつは、先日転入生としてこの学園にやって来たメア・モノクロイドだった。
といっても知っているのはそれぐらいで、俺とそう関わることも無いと思っていた。
にも関わらず、人の名前を大声で呼ぶわ、ずぶ濡れだわで、だいぶ変な奴なんだという印象がついた。
基本的に女と関わるのは面倒臭い。
昔はそんな考えもなかったが、俺が年頃になってきたからか、家の奴らも含め『そういう目』からの束縛がうざくなってきた。
自分の容姿、肩書きを目当てに近寄る女の量も最近では増える一方だ。
ただでさえ家のことでこっちはナーバスになっているってのに、女のことまで追加されていい加減頭に来ていたところだ。
かといって、家の奴らを黙らせるための偽りの恋人探しも、そう簡単なものではない。
ここでチョイスをミスると、ますます面倒臭いことになるのは目に見えている。
だから俺は慎重に、それでいて急ぎでそういう女を探していた。
そこに現れたのがこいつ、メア・モノクロイドだ。
俺と対面して目の色を少しも変えなかった女。
そんな女、ここしばらく出会ったことが無い。
それになんというか……色恋を含んだ『そういう目』で俺を見ていない。
そんなことよりずぶ濡れなのをどうにかしたい、そういった感じだ。
だから俺はつい言ってしまった。
「おまえ、俺の恋人になれ」
「……は?」
「偽りのな」
「……は?」
そこからの挙動不審なこいつの態度は、いちいち俺のツボに入った。
こんなふうに笑うのもなかなか無い。
最初は勢い任せに言っちまったもんかとも思ったが、意外と適性の女を選べたような気がしてきた。
「わ……わかりました。なります、偽りの恋人に」
「物分かりがいいじゃねぇか」
「でも、言っておきますけど私は何もできませんからね? その辺りはクライヴ……先輩が、上手くやってくださいね!」
「わかったわかった」
言って俺は、こいつの頭をくしゃりと撫でた。
思っていたより小さいその頭に、何故か俺はご機嫌になる。
「これで交渉成立だ。あー、しばらくは家のうるせぇ奴らが静かになるな。助かるぜ」
心からの言葉だった。
言ってから、だいぶこのことが最近しんどくてたまらなかったのだとよくわかる。
そして、そのしんどさから救ってくれたこいつに、改めて俺は感謝の気持ちが募った。
「それじゃあ、よろしくお願いします?」
「ああ。安心しろ。それなりに優遇してやっから」
ついそんなことまで言ってしまう。
この俺が、優遇だなんて笑っちまう。
どうやら俺は、自分で思っている以上に機嫌が良いようだ。
ついでに何か言ってやろうとしたが、その前に鐘の音が聞こえてくる。休み時間も終わりのようだ。
「じゃあな」
「あ、は、はい」
少し冷静さを取り戻し、俺は俺らしい態度でメアと別れた。
だがそれでも自然と鼻歌を歌い、足取りも軽やかだ。
やっと学園生活を満喫できるかもしれねぇな。
俺は一人でにやりと笑い、校舎へと戻って行ったのだった。
こいつが俺のことを『そういう目』で見ていないことを。
突然ずぶ濡れで現れたそいつは、先日転入生としてこの学園にやって来たメア・モノクロイドだった。
といっても知っているのはそれぐらいで、俺とそう関わることも無いと思っていた。
にも関わらず、人の名前を大声で呼ぶわ、ずぶ濡れだわで、だいぶ変な奴なんだという印象がついた。
基本的に女と関わるのは面倒臭い。
昔はそんな考えもなかったが、俺が年頃になってきたからか、家の奴らも含め『そういう目』からの束縛がうざくなってきた。
自分の容姿、肩書きを目当てに近寄る女の量も最近では増える一方だ。
ただでさえ家のことでこっちはナーバスになっているってのに、女のことまで追加されていい加減頭に来ていたところだ。
かといって、家の奴らを黙らせるための偽りの恋人探しも、そう簡単なものではない。
ここでチョイスをミスると、ますます面倒臭いことになるのは目に見えている。
だから俺は慎重に、それでいて急ぎでそういう女を探していた。
そこに現れたのがこいつ、メア・モノクロイドだ。
俺と対面して目の色を少しも変えなかった女。
そんな女、ここしばらく出会ったことが無い。
それになんというか……色恋を含んだ『そういう目』で俺を見ていない。
そんなことよりずぶ濡れなのをどうにかしたい、そういった感じだ。
だから俺はつい言ってしまった。
「おまえ、俺の恋人になれ」
「……は?」
「偽りのな」
「……は?」
そこからの挙動不審なこいつの態度は、いちいち俺のツボに入った。
こんなふうに笑うのもなかなか無い。
最初は勢い任せに言っちまったもんかとも思ったが、意外と適性の女を選べたような気がしてきた。
「わ……わかりました。なります、偽りの恋人に」
「物分かりがいいじゃねぇか」
「でも、言っておきますけど私は何もできませんからね? その辺りはクライヴ……先輩が、上手くやってくださいね!」
「わかったわかった」
言って俺は、こいつの頭をくしゃりと撫でた。
思っていたより小さいその頭に、何故か俺はご機嫌になる。
「これで交渉成立だ。あー、しばらくは家のうるせぇ奴らが静かになるな。助かるぜ」
心からの言葉だった。
言ってから、だいぶこのことが最近しんどくてたまらなかったのだとよくわかる。
そして、そのしんどさから救ってくれたこいつに、改めて俺は感謝の気持ちが募った。
「それじゃあ、よろしくお願いします?」
「ああ。安心しろ。それなりに優遇してやっから」
ついそんなことまで言ってしまう。
この俺が、優遇だなんて笑っちまう。
どうやら俺は、自分で思っている以上に機嫌が良いようだ。
ついでに何か言ってやろうとしたが、その前に鐘の音が聞こえてくる。休み時間も終わりのようだ。
「じゃあな」
「あ、は、はい」
少し冷静さを取り戻し、俺は俺らしい態度でメアと別れた。
だがそれでも自然と鼻歌を歌い、足取りも軽やかだ。
やっと学園生活を満喫できるかもしれねぇな。
俺は一人でにやりと笑い、校舎へと戻って行ったのだった。