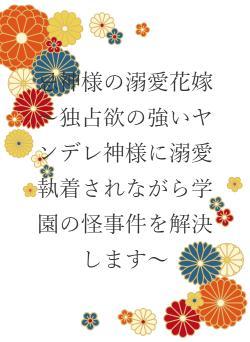「随分楽しそうだったじゃねぇか」
アルバートの借り物として競技に参加した私は、二位という成績を収めた。
共にアルバートとキャッキャしていたわけだが、赤組席のとある一画から物凄い殺気を向けられていたので慌てて解散した。
殺気を飛ばしていた人物……クライヴの元へ戻ると、彼は腕を組んだまま開口一番そう言い放った。
(ひえぇ……なんかわからんけど怒ってるよ……)
クライヴとアルバートは何かと相性が良くないから、それに巻き込まれている感じなのだろうか。
とりあえず私はクライヴの気を落ち着かせるため、違う話題を振った。
「と、というかお昼休み来ますね! ちゃんとお弁当作ったんですよ!」
「……ほお」
まるで悪代官のように笑ってみせるクライヴ。その笑みの感じから、どうやら機嫌は直ったようだ。
そんなやり取りをかわしている間に前半の種目が終了となる。
「前半戦も思った以上に白熱しましたねー! ではではみなさん、お昼休みにしっかり休息を取って後半戦もがんばりましょー!」
その放送を合図に、お昼休みとなった。
移動する生徒もいれば、その場でお昼ご飯を広げる生徒もいる。
すると……
「ねえクライヴ。お昼、一緒しない?」
振り返ると、そこには美女と呼ぶに相応しい女生徒がお弁当片手にクライヴに近寄っていた。
頬にかかる髪を耳にかけるその仕草だけで、男子生徒は見惚れてしまいそうだ。
しかし当のクライヴは私の腕を掴んで立ち上がる。
「悪いけど先約がある」
それだけ告げ、クライヴは私を引き連れるかたちでその場を後にした。
フラれた彼女の顔が恐ろしくて見ることができず、私は黙ってクライヴに連れて行かれていった。
しばらくして到着したのは、あの、図書室の裏の庭園だった。
「やっぱりここなんですね」
「ここが一番落ち着くからな」
朗らかな横顔を見せ、クライヴは魔法で草むらの上にシートを敷き、私にそこに座るよう促した。
私が座ると、クライヴもその隣に座る。
私は持ってきたお弁当を急いで広げた。
「お口に合うかわかりませんが……」
よく考えたら、クライヴは王族の男。普段から一流のシェフが手掛けたのであろうお弁当を毎日食しているのである。
それを思うと、今更ながら自分のお弁当がとても貧相なものに感じられてきた。
彩や量を必死に考えた自分のお弁当が、逆に幼稚園児のままごとのように思えてきてしまう。
だが、クライヴの視線はお弁当から私の方へと移り、目を細めて笑った。
「な、なんですか?」
「食べさせてくれよ」
「ええっ!?」
予想外の要望に、思わず声を上げてしまう。
だってまさか、そんな『恋人』らしいことをしてほしいだなんて。
「クライヴ先輩、わかってます? 私たち、偽りの恋人なんですよ?」
「だからだろ」
「へ?」
「今日は関係者席に俺の家の従者たちが何人か来てるんだ。そいつらに、ちゃんと恋人がいるところを見てもらわなきゃいけねぇからな」
「だからって、お弁当を食べさせるのは……」
「つれないこと言うなよ」
口角を上げて笑うそのサマは、獲物を前にした猛禽類のそれだ。
絶対に逃すまいという意思と、強者の余裕が見え隠れしている。
「なあ?」
耳朶に触れる低音ボイスに、有無を言わせぬ整った顔立ち。
それを突き付けられてNOと言える人間がいるだろうか。
覚悟を決めた私は箸を持ち、タコさんウィンナーを掴んで、そっとクライヴに近付けた。
「いただきます」
クライヴはお行儀よくそう告げると、パクリ、とタコさんウィンナーを口に入れた。
気分は肉食動物にエサをやる飼育員である。
「……どうでしょうか?」
「うん。美味い」
「つっても既製品を炒めただけですけどね」
「そういうことじゃねぇんだろ」
「え?」
「おまえが俺のために作ってくれたその気持ちが美味いんだよ」
「……!」
意図も簡単にそんなことを言ってのけるクライヴに、私は頬が熱を持つのを感じた。
さすがはメインキャラ。爆発力が凄まじい。
「あ、あとはご自分でどうぞ……っ!」
「はいはい」
からかうように返事をしながら、クライヴは様々なおかずやおにぎりをパクパク食べていく。
その様子は無理したものではなく、本当に美味しそうに食べてくれているものだから、私はホッと胸をなでおろした。
しばらく、私たちはお互いにお弁当を食べ合った。自分で言うのもなんだが、やはりけっこう美味くできたと思い、私もパクパクとおかずやおにぎりを味わっていく。
そこでふと、気になったことを私はクライヴに訊いてみた。
「あのー……偽りの恋人って、あとどういったことをすればいいんでしょうか?」
おにぎりを頬張りながら、クライヴはしばし考え込んでいた。
そして口の中の米粒を飲み込むと、硬い口調で喋り出した。
「そうだな……。これだけアピールしてるから、そろそろ家の方から呼び出しがかかる筈だ」
「よ、呼び出しと言いますと……?」
「うちの母親に挨拶だろ」
「え、え、えぇえええ!?」
思わず大声が出た。
だってクライヴの母親ということは王妃様ということだ。
そんな方に彼女として紹介されるだなんて、考えただけで足が竦む。
「挨拶なんてしたら、後に引けなくなりませんか!?」
「別に婚約するわけじゃねぇんだ。顔見せだけして、今の彼女つって、だから学生の内は見合い話持ってくんなよ、って言う流れなんだから。適当に俺の隣で笑っておきゃ問題ねぇ」
「そ、そんな簡単にいくんでしょうか……」
「へーきだろ。だいたい……」
と、そこでクライヴの表情が固まる。
目を見開いたかと思えば、杖を持ち、近くの大木の上の方へそれを向けた。
一体何事かと思えば、大木の上の方から何かがザザザッと降りてきた。
「ね、ネイト先輩!?」
「………」
そこにあったのはネイトの姿だった。
彼は寝起きのようにあくびをしつつ、殺気立ったクライヴと対峙する。
「てめぇ……最初から魔力を消して隠れていやがったのか。陰険なやつめ」
「俺の方が先に来ていたんで、そんな言われは無いかと思うんですが」
獅子のように吠えるクライヴと、ボソボソと喋るネイト。
なんとも対照的な二人を前に、私はどうしたものかと一人慌てた。
何より、ネイトがずっと木の上に居たとなると、つまり……
「……それで。どこまで話を聞いてやがる」
「全部聞こえてましたけど」
「ちっ」
つまりクライヴと偽りの恋人をしていることがバレたわけである。
別にバレたところでネイトは言いふらしたりするタイプではないのでそこは安心だが、クライヴの心境としては弱みを掴まれたという点で機嫌を悪くしている。
「……何が望みだ?」
「はい?」
「口止め料だよ」
「そんなの……」
ネイトはおそらく、いらない、と答えるつもりだったのだろう。
けれどそこで言葉は途切れ、代わりに私と私のお弁当を見た。
そこでネイトが、ふ、と笑う。
「じゃあ、そのお弁当ちょうだい」
「はあ?」
「メアの手作り弁当を貰えるなら、恋人ごっこのこと黙っておきます」
「てめぇ……」
のらりくらりとしたネイトの態度が気に入らないのか、それとも本気でお弁当を分けるのが嫌なのか。
クライヴが今にもネイトに掴みかかりそうだったので、私は二人の間に入って仲裁をした。
「お、お弁当で良ければいくらでもどうぞ!」
「おい!」
「いいじゃないですか。みんなで食べましょうよ」
「……ちっ」
隠す気も無いほど盛大に舌打ちをし、諦めたのか、クライヴは元いた場所へ座り込んだ。
私も元の位置へ戻ると、ネイトがゆっくりと隣にやってきた。
(お、お、推しに手作り弁当を食べてもらうだなんて、マジかぁ~!)
実のところ今の私にとって、偽りの恋人のことがバレたことより、手作り弁当を食べてもらうことの方が重大だった。
ネイトが近くにあったおにぎりに手を付け、そのまま頬張る姿をジッと見続けた。
「……うん。美味しい」
「ホントですか!?」
嬉しさと安堵でつい声を上げて喜んでしまった。
だがその瞬間。
クライヴからガシィッと頭を掴まれ、無理矢理そちらを向かされた。
「あいたたたたたたっ」
「おまえは誰のために弁当作ったんだ?」
「す、すみません……クライヴ先輩ですぅ……」
そんなやり取りをする私たちを横目に、ネイトは美味しそうにもぐもぐとお弁当を食べ進めていくのだった。
アルバートの借り物として競技に参加した私は、二位という成績を収めた。
共にアルバートとキャッキャしていたわけだが、赤組席のとある一画から物凄い殺気を向けられていたので慌てて解散した。
殺気を飛ばしていた人物……クライヴの元へ戻ると、彼は腕を組んだまま開口一番そう言い放った。
(ひえぇ……なんかわからんけど怒ってるよ……)
クライヴとアルバートは何かと相性が良くないから、それに巻き込まれている感じなのだろうか。
とりあえず私はクライヴの気を落ち着かせるため、違う話題を振った。
「と、というかお昼休み来ますね! ちゃんとお弁当作ったんですよ!」
「……ほお」
まるで悪代官のように笑ってみせるクライヴ。その笑みの感じから、どうやら機嫌は直ったようだ。
そんなやり取りをかわしている間に前半の種目が終了となる。
「前半戦も思った以上に白熱しましたねー! ではではみなさん、お昼休みにしっかり休息を取って後半戦もがんばりましょー!」
その放送を合図に、お昼休みとなった。
移動する生徒もいれば、その場でお昼ご飯を広げる生徒もいる。
すると……
「ねえクライヴ。お昼、一緒しない?」
振り返ると、そこには美女と呼ぶに相応しい女生徒がお弁当片手にクライヴに近寄っていた。
頬にかかる髪を耳にかけるその仕草だけで、男子生徒は見惚れてしまいそうだ。
しかし当のクライヴは私の腕を掴んで立ち上がる。
「悪いけど先約がある」
それだけ告げ、クライヴは私を引き連れるかたちでその場を後にした。
フラれた彼女の顔が恐ろしくて見ることができず、私は黙ってクライヴに連れて行かれていった。
しばらくして到着したのは、あの、図書室の裏の庭園だった。
「やっぱりここなんですね」
「ここが一番落ち着くからな」
朗らかな横顔を見せ、クライヴは魔法で草むらの上にシートを敷き、私にそこに座るよう促した。
私が座ると、クライヴもその隣に座る。
私は持ってきたお弁当を急いで広げた。
「お口に合うかわかりませんが……」
よく考えたら、クライヴは王族の男。普段から一流のシェフが手掛けたのであろうお弁当を毎日食しているのである。
それを思うと、今更ながら自分のお弁当がとても貧相なものに感じられてきた。
彩や量を必死に考えた自分のお弁当が、逆に幼稚園児のままごとのように思えてきてしまう。
だが、クライヴの視線はお弁当から私の方へと移り、目を細めて笑った。
「な、なんですか?」
「食べさせてくれよ」
「ええっ!?」
予想外の要望に、思わず声を上げてしまう。
だってまさか、そんな『恋人』らしいことをしてほしいだなんて。
「クライヴ先輩、わかってます? 私たち、偽りの恋人なんですよ?」
「だからだろ」
「へ?」
「今日は関係者席に俺の家の従者たちが何人か来てるんだ。そいつらに、ちゃんと恋人がいるところを見てもらわなきゃいけねぇからな」
「だからって、お弁当を食べさせるのは……」
「つれないこと言うなよ」
口角を上げて笑うそのサマは、獲物を前にした猛禽類のそれだ。
絶対に逃すまいという意思と、強者の余裕が見え隠れしている。
「なあ?」
耳朶に触れる低音ボイスに、有無を言わせぬ整った顔立ち。
それを突き付けられてNOと言える人間がいるだろうか。
覚悟を決めた私は箸を持ち、タコさんウィンナーを掴んで、そっとクライヴに近付けた。
「いただきます」
クライヴはお行儀よくそう告げると、パクリ、とタコさんウィンナーを口に入れた。
気分は肉食動物にエサをやる飼育員である。
「……どうでしょうか?」
「うん。美味い」
「つっても既製品を炒めただけですけどね」
「そういうことじゃねぇんだろ」
「え?」
「おまえが俺のために作ってくれたその気持ちが美味いんだよ」
「……!」
意図も簡単にそんなことを言ってのけるクライヴに、私は頬が熱を持つのを感じた。
さすがはメインキャラ。爆発力が凄まじい。
「あ、あとはご自分でどうぞ……っ!」
「はいはい」
からかうように返事をしながら、クライヴは様々なおかずやおにぎりをパクパク食べていく。
その様子は無理したものではなく、本当に美味しそうに食べてくれているものだから、私はホッと胸をなでおろした。
しばらく、私たちはお互いにお弁当を食べ合った。自分で言うのもなんだが、やはりけっこう美味くできたと思い、私もパクパクとおかずやおにぎりを味わっていく。
そこでふと、気になったことを私はクライヴに訊いてみた。
「あのー……偽りの恋人って、あとどういったことをすればいいんでしょうか?」
おにぎりを頬張りながら、クライヴはしばし考え込んでいた。
そして口の中の米粒を飲み込むと、硬い口調で喋り出した。
「そうだな……。これだけアピールしてるから、そろそろ家の方から呼び出しがかかる筈だ」
「よ、呼び出しと言いますと……?」
「うちの母親に挨拶だろ」
「え、え、えぇえええ!?」
思わず大声が出た。
だってクライヴの母親ということは王妃様ということだ。
そんな方に彼女として紹介されるだなんて、考えただけで足が竦む。
「挨拶なんてしたら、後に引けなくなりませんか!?」
「別に婚約するわけじゃねぇんだ。顔見せだけして、今の彼女つって、だから学生の内は見合い話持ってくんなよ、って言う流れなんだから。適当に俺の隣で笑っておきゃ問題ねぇ」
「そ、そんな簡単にいくんでしょうか……」
「へーきだろ。だいたい……」
と、そこでクライヴの表情が固まる。
目を見開いたかと思えば、杖を持ち、近くの大木の上の方へそれを向けた。
一体何事かと思えば、大木の上の方から何かがザザザッと降りてきた。
「ね、ネイト先輩!?」
「………」
そこにあったのはネイトの姿だった。
彼は寝起きのようにあくびをしつつ、殺気立ったクライヴと対峙する。
「てめぇ……最初から魔力を消して隠れていやがったのか。陰険なやつめ」
「俺の方が先に来ていたんで、そんな言われは無いかと思うんですが」
獅子のように吠えるクライヴと、ボソボソと喋るネイト。
なんとも対照的な二人を前に、私はどうしたものかと一人慌てた。
何より、ネイトがずっと木の上に居たとなると、つまり……
「……それで。どこまで話を聞いてやがる」
「全部聞こえてましたけど」
「ちっ」
つまりクライヴと偽りの恋人をしていることがバレたわけである。
別にバレたところでネイトは言いふらしたりするタイプではないのでそこは安心だが、クライヴの心境としては弱みを掴まれたという点で機嫌を悪くしている。
「……何が望みだ?」
「はい?」
「口止め料だよ」
「そんなの……」
ネイトはおそらく、いらない、と答えるつもりだったのだろう。
けれどそこで言葉は途切れ、代わりに私と私のお弁当を見た。
そこでネイトが、ふ、と笑う。
「じゃあ、そのお弁当ちょうだい」
「はあ?」
「メアの手作り弁当を貰えるなら、恋人ごっこのこと黙っておきます」
「てめぇ……」
のらりくらりとしたネイトの態度が気に入らないのか、それとも本気でお弁当を分けるのが嫌なのか。
クライヴが今にもネイトに掴みかかりそうだったので、私は二人の間に入って仲裁をした。
「お、お弁当で良ければいくらでもどうぞ!」
「おい!」
「いいじゃないですか。みんなで食べましょうよ」
「……ちっ」
隠す気も無いほど盛大に舌打ちをし、諦めたのか、クライヴは元いた場所へ座り込んだ。
私も元の位置へ戻ると、ネイトがゆっくりと隣にやってきた。
(お、お、推しに手作り弁当を食べてもらうだなんて、マジかぁ~!)
実のところ今の私にとって、偽りの恋人のことがバレたことより、手作り弁当を食べてもらうことの方が重大だった。
ネイトが近くにあったおにぎりに手を付け、そのまま頬張る姿をジッと見続けた。
「……うん。美味しい」
「ホントですか!?」
嬉しさと安堵でつい声を上げて喜んでしまった。
だがその瞬間。
クライヴからガシィッと頭を掴まれ、無理矢理そちらを向かされた。
「あいたたたたたたっ」
「おまえは誰のために弁当作ったんだ?」
「す、すみません……クライヴ先輩ですぅ……」
そんなやり取りをする私たちを横目に、ネイトは美味しそうにもぐもぐとお弁当を食べ進めていくのだった。