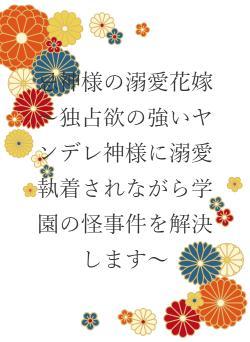呼び出しを喰らったあの後、クライヴから来るように言われてのこのことついて行った私は、気付けば赤組の席にいた。
というかそこは、赤組のクライヴの特等席だった。他の人たちと違ってかなりのスペースがあり、私一人が追加されても余裕があるほどに広い席である。
ついさっきまでの呼び出しについての考え事をしていた所為で反応が遅れてしまい、あれよあれよという間に私はそのスペースでクライヴの隣に座ることになっていた。
「何か飲むか?」
「い、いえ……大丈夫です」
「ふぅん」
言いながらクライヴはスポーツドリンクを飲んでいる。
よく考えればこの人、大会の第一種目で自己ベスト出した後、私を助けるために正確な魔法を打ったわけである。
普通の生徒ならこの両方をこなすなんてまず無理だろう。
「あの……さっきは助けてくれてありがとうございました」
私の言葉を横目で聞くと、クライヴは口端を持ち上げてこちらを向いた。
「んなことはいいんだよ。それより……」
「それより?」
「自己ベスト出した恋人に、何かねぇのか?」
にやにやと笑いながら、クライヴは催促する。
自分に自信が無いと絶対にできないような表情だ。
なんだか悔しい気持ちにさせられたが、それでも助けてもらったお礼も込めて、ここは正直に思いを伝えることにした。
「……格好良かったです」
「へえ」
「先輩だけ群を抜いて格好良かったです」
「だろ?」
「……!」
自信に溢れた低音ボイスが耳にこびりつく。
(くぅううう、なんて自信満々な……! でもそれが許されるだけの実力が備わってるんだよなぁ、この人!)
「しばらく俺は暇だから、一緒に観戦でもしようぜ」
「でも私、サポート委員の仕事が……」
「あ?」
「ひえっ」
肉食獣のような鋭い眼光で睨まれ、思わず喉が鳴る。
私は急ぎ、マジパッドでアイネに現状の連絡を入れた。するとすぐに返信が来る。
内容は、いくらでも仕事は代わる、とのこと。
(うううう……アイネ、私とクライヴの恋路を応援してくれるからなぁ。そりゃこう返ってくるかぁ)
「おい」
「は、はい!?」
マジパッドから顔を上げれば、こちらに上体を近付け、覗き込んでくるクライヴの姿があった。
野性味のある端正なその顔立ちに、ドキリと心臓が飛び跳ねる。
「一緒にいれんだろ?」
「は……い」
「よし」
悪だくみが成功したかのように、クライヴは歯を見せて笑う。
なんだか全てがクライヴの手の内のようで悔しいが仕方ない。
そうこうしている内に、校庭の中央には次の競技の選手が集められていた。
次の競技は『借り物競争』である。
ふとよく見れば、レーン付近には見知った顔が……アルバートの姿がそこにあった。
(彼のところだけ不思議とキラキラしてるんだよなぁ。応援席からも『プリンスー!』ってナチュラルに呼ばれてて凄いや)
そんなことを考えながら彼を凝視していた所為か、アルバートがこちらを向いた。バッチリと目が合ったまま、アルバートは私に向けて大きく手を振ってきた。
同じチームなのもあり応援の意味を込め、私も手を振り返す。
何故か隣のクライヴから舌打ちが聞こえてきたが。
「さてさて、次の競技はみなさんお待ちかねの『借り物競争』です!」
「この競技は選手だけでなく、選手の借り物のために選手以外も協力する競技ですからね、他とは違う熱さがありますよね」
「道具から人物まで、今年はどんな借り物があるんでしょうか!」
ミハエルとアンジェリークが、よりいっそう場を盛り上げてくれる。実際に各チームの応援席からも太鼓やラッパでの演奏や声援が発せられていた。
実況と解説の言う通り、『借り物競争』は速さだけを競うわけではなく、借り物を探すてんやわんやなところを楽しむお祭りのようなところがある。
選手だけでなく、この場にいる誰もが参加する競技だった。
「位置について、よーい……」
パンッ、と威勢の良い音と共にアルバートたちが走り始めた。
身体能力の差はそこまで無いようで、どの選手も借り物の紙が置かれたテーブルまで同時に到着していた。
(アルバートの借り物は何だろう。簡単なのですように……!)
クライヴに連れられ赤組の席にいるが、心はしっかりアルバートと同じ青組である。
私はアルバートが一位を取れるよう、心の中で応援していた。
すると、アルバートは借り物の紙を見るや否や、ふ、と笑みを浮かべ何故かこちらへ走ってきた。
そして気付けば私の元まで辿り着いていたのだった。
「メア。良ければいいかな?」
「えっ!」
「あぁ?」
私の驚きの声と、クライヴの不機嫌な声が重なった。
しかしアルバートは少しも動じた様子も無く、私に手を差し伸べている。
それはまるでお姫様にダンスを誘う王子様そのものの絵面で……傍にいた赤組の女子生徒たちが頬を染めているのが見えた。
「あ、え、えーと」
「お願い」
「は、は、はい!」
最初は困惑したものの、チームの勝敗が自分にかかっているのだと意識を改め、急いでアルバートの手を取った。
そしてそのままレーンに入り、アルバートに手を引かれるまま走り始めた。
「速すぎたら言ってね」
「はい!」
さすがプリンス。気遣いの男である。
私の走れる速度を気にしながら走るその様は、紳士のエスコートそのものだ。
「ゴール! アルバート選手、ゴールです!」
コースを駆け抜けた私たちは、そこそこの体力を残し、ゴールまで辿り着いた。
ゴール付近には借り物を確認するサポート委員がおり、アルバートの借り物についてチェックしていた。
そこには『これから仲良くなりたい人』の文字が。
「これ……」
「駄目かな?」
凪いだ海のように優しいコバルトブルーの瞳が、私に穏やかな眼差しを向けている。
(こ、こ、こんなのときめいちゃうでしょうがぁああああ!)
私は心の中で盛大にそう叫びながら、赤い顔のまま一つ静かに頷いた。
というかそこは、赤組のクライヴの特等席だった。他の人たちと違ってかなりのスペースがあり、私一人が追加されても余裕があるほどに広い席である。
ついさっきまでの呼び出しについての考え事をしていた所為で反応が遅れてしまい、あれよあれよという間に私はそのスペースでクライヴの隣に座ることになっていた。
「何か飲むか?」
「い、いえ……大丈夫です」
「ふぅん」
言いながらクライヴはスポーツドリンクを飲んでいる。
よく考えればこの人、大会の第一種目で自己ベスト出した後、私を助けるために正確な魔法を打ったわけである。
普通の生徒ならこの両方をこなすなんてまず無理だろう。
「あの……さっきは助けてくれてありがとうございました」
私の言葉を横目で聞くと、クライヴは口端を持ち上げてこちらを向いた。
「んなことはいいんだよ。それより……」
「それより?」
「自己ベスト出した恋人に、何かねぇのか?」
にやにやと笑いながら、クライヴは催促する。
自分に自信が無いと絶対にできないような表情だ。
なんだか悔しい気持ちにさせられたが、それでも助けてもらったお礼も込めて、ここは正直に思いを伝えることにした。
「……格好良かったです」
「へえ」
「先輩だけ群を抜いて格好良かったです」
「だろ?」
「……!」
自信に溢れた低音ボイスが耳にこびりつく。
(くぅううう、なんて自信満々な……! でもそれが許されるだけの実力が備わってるんだよなぁ、この人!)
「しばらく俺は暇だから、一緒に観戦でもしようぜ」
「でも私、サポート委員の仕事が……」
「あ?」
「ひえっ」
肉食獣のような鋭い眼光で睨まれ、思わず喉が鳴る。
私は急ぎ、マジパッドでアイネに現状の連絡を入れた。するとすぐに返信が来る。
内容は、いくらでも仕事は代わる、とのこと。
(うううう……アイネ、私とクライヴの恋路を応援してくれるからなぁ。そりゃこう返ってくるかぁ)
「おい」
「は、はい!?」
マジパッドから顔を上げれば、こちらに上体を近付け、覗き込んでくるクライヴの姿があった。
野性味のある端正なその顔立ちに、ドキリと心臓が飛び跳ねる。
「一緒にいれんだろ?」
「は……い」
「よし」
悪だくみが成功したかのように、クライヴは歯を見せて笑う。
なんだか全てがクライヴの手の内のようで悔しいが仕方ない。
そうこうしている内に、校庭の中央には次の競技の選手が集められていた。
次の競技は『借り物競争』である。
ふとよく見れば、レーン付近には見知った顔が……アルバートの姿がそこにあった。
(彼のところだけ不思議とキラキラしてるんだよなぁ。応援席からも『プリンスー!』ってナチュラルに呼ばれてて凄いや)
そんなことを考えながら彼を凝視していた所為か、アルバートがこちらを向いた。バッチリと目が合ったまま、アルバートは私に向けて大きく手を振ってきた。
同じチームなのもあり応援の意味を込め、私も手を振り返す。
何故か隣のクライヴから舌打ちが聞こえてきたが。
「さてさて、次の競技はみなさんお待ちかねの『借り物競争』です!」
「この競技は選手だけでなく、選手の借り物のために選手以外も協力する競技ですからね、他とは違う熱さがありますよね」
「道具から人物まで、今年はどんな借り物があるんでしょうか!」
ミハエルとアンジェリークが、よりいっそう場を盛り上げてくれる。実際に各チームの応援席からも太鼓やラッパでの演奏や声援が発せられていた。
実況と解説の言う通り、『借り物競争』は速さだけを競うわけではなく、借り物を探すてんやわんやなところを楽しむお祭りのようなところがある。
選手だけでなく、この場にいる誰もが参加する競技だった。
「位置について、よーい……」
パンッ、と威勢の良い音と共にアルバートたちが走り始めた。
身体能力の差はそこまで無いようで、どの選手も借り物の紙が置かれたテーブルまで同時に到着していた。
(アルバートの借り物は何だろう。簡単なのですように……!)
クライヴに連れられ赤組の席にいるが、心はしっかりアルバートと同じ青組である。
私はアルバートが一位を取れるよう、心の中で応援していた。
すると、アルバートは借り物の紙を見るや否や、ふ、と笑みを浮かべ何故かこちらへ走ってきた。
そして気付けば私の元まで辿り着いていたのだった。
「メア。良ければいいかな?」
「えっ!」
「あぁ?」
私の驚きの声と、クライヴの不機嫌な声が重なった。
しかしアルバートは少しも動じた様子も無く、私に手を差し伸べている。
それはまるでお姫様にダンスを誘う王子様そのものの絵面で……傍にいた赤組の女子生徒たちが頬を染めているのが見えた。
「あ、え、えーと」
「お願い」
「は、は、はい!」
最初は困惑したものの、チームの勝敗が自分にかかっているのだと意識を改め、急いでアルバートの手を取った。
そしてそのままレーンに入り、アルバートに手を引かれるまま走り始めた。
「速すぎたら言ってね」
「はい!」
さすがプリンス。気遣いの男である。
私の走れる速度を気にしながら走るその様は、紳士のエスコートそのものだ。
「ゴール! アルバート選手、ゴールです!」
コースを駆け抜けた私たちは、そこそこの体力を残し、ゴールまで辿り着いた。
ゴール付近には借り物を確認するサポート委員がおり、アルバートの借り物についてチェックしていた。
そこには『これから仲良くなりたい人』の文字が。
「これ……」
「駄目かな?」
凪いだ海のように優しいコバルトブルーの瞳が、私に穏やかな眼差しを向けている。
(こ、こ、こんなのときめいちゃうでしょうがぁああああ!)
私は心の中で盛大にそう叫びながら、赤い顔のまま一つ静かに頷いた。