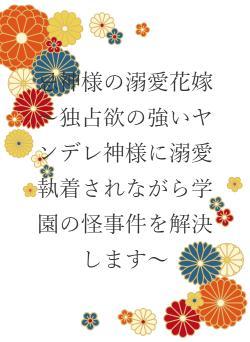「ちょっといい?」
「へ?」
トイレから出たところで突然そんなことを言われ、私は振り返った。
そこには三名の女生徒がおり、どこか機嫌の悪そうな顔をしている。
それぞれがしている鉢巻きのチームカラーはバラバラだし、サポート委員会にも確かいなかったメンツだ。
つまり今この場が初対面ということになるが、一体どうしてそんなに機嫌が悪いのか、まるで見当が付かなかった。
「えっと……」
「こっち来てくれる?」
有無を言わせぬ態度を取られ、私は仕方なく彼女たちについていった。
校庭では今も競技が行われているというのに、向かう先は真逆の中庭だ。普段ならちらほらと生徒がいるここも、今では貸し切り状態となっている。
到着と共にしばらく沈黙して向き合っていたら、ようやく向こうが口を開いた。
「転入生のメア・モノクロイドよね?」
「そ、そうですけど……」
「あんた、クライヴ先輩と付き合ってるってホント?」
言われてギクリとした。
それと同時に、つまりこれはそういう関係の呼び出しなのだと合点がいく。
できるだけ事を穏便にしようと、私は平常心を保つように努めた。
「えーと、はい、そうです」
「ふーん」
目の前の彼女は腕を組み、何かを考えているようだった。後ろの二人もどこか釈然としない顔でこちらを見ている。
やっぱり彼女たちもクライヴが好きとかそういうのなのだろうか……と思いきや、話は思わぬ方向へ転がった。
「だったらなんでアルバート様と出かけてんの?」
「へ?」
「しらばっくれないでよ。先週、アルバート様と一緒にお茶してるの見たんですけど?」
まさかアルバートの名前が出るとは思わず、私は間の抜けた声を上げてしまった。
しかしそれが火に油を注いでしまったのか、彼女は目を吊り上げて怒鳴り出した。
「あの、それは……あの時はそもそもアイネと一緒に出かけて、たまたまアルバート先輩と会っただけで……」
そう弁解してみるものの、聞いてるのか聞いていないのか、彼女からの追撃は止まらない。
それにしても、なんだろうか、このニオイは。
彼女たちが現れた辺りから、何か、甘酸っぱいニオイが鼻について仕方がない。
悪い香りではないのだが、どうにも受け入れがたいニオイというか……
「聞いてんのかよ!」
「っ!」
ハッと我に返った時にはもう遅く、思い切り突き飛ばされてしまった。
無様なまでに尻餅をついた私は、恐る恐る彼女を見上げた。
(お、怒ってるのはわかるけど、こんな手が出るほど~!?)
なんというか、突然の挙動にパニックになってしまった。
彼女の後ろにいる二人も、私と同じように驚いている。どうやらここまでのことを私にするつもりではなかったようだ。
そうこうしているうちにも、彼女の感情はどんどんヒートアップしていく。
「アルバート様にはね、抜け駆け禁止っていう暗黙の了解があるんだよ! それを転入生の分際で何!? アルバート様の優しさに付け入りやがって!」
彼女のアルバートへの気持ちはよくわかった。
だが、こんなにも理性を失わせてしまうほどのことを私はしてしまったのだろうか。
なんだか様子がおかしくないか……と、そう思った瞬間だった。
「ちょ、ちょっと」
「え、やばいって……」
後ろの二人が同時に声を上げた。
一方の私は、逆に声を上げられなかった。
何故なら彼女が、魔法の杖を私に向けていたからだ。
こんなの、拳銃を向けられているのと何ら変わりない。思わず私はゴクリと息を呑んだ。
「あんたさえいなきゃ……あんたさえ……!」
もはや弁解どころか、何か言おうものなら一触即発の空気。
そうして杖が振り上げられ、私はギュッと目をつぶった。
「きゃあ!」
悲鳴を上げたのは、私ではなく彼女の方だった。
「……?」
恐る恐る目を開けると、目の前には杖を持っていた筈の手を痛そうに反対側の手で庇う彼女の姿が。
そうして右方から現れたのは、杖を片手に酷く恐い形相でこちらにやってくるクライヴの姿があった。
「……何やってんだ?」
地の底から響くようなその声音に、その場にいる誰もが縮こまった。
彼女の後ろの二人など、見るからに顔面蒼白になっている。
クライヴはまだ杖を持って警戒したまま、ゆっくりと私の近くまで来た。そしてエスコートするような優しい所作で腕を掴み、そっと私を立たせてくれる。
「話し合いなら見過ごしてやったが、明らかに魔法を使うところだったよなぁ?」
青筋を立て、私を庇うようにクライヴは彼女と対峙する。
普通ならばここで退散してもおかしくないほど、クライヴからの殺気は凄い。
しかし、彼女はそれでも退かず、むしろ目を血走らせて怒りを露わにした。
「……ずるい。ずるいずるいずるい! そうやってアルバート様にも取り入ったんでしょう!? 許せない……許せないっ!」
「……!」
彼女の目にはクライヴなど映っていない。
私を親の仇か何かかのような勢いで睨み付け、この状況下でありながらも、彼女は私に掴みかかろうとした。
だがその寸前で、クライヴの杖先から放たれた光が、彼女の脳天を貫いた。
「あ……あ……」
彼女の両眼はグルンと白目を向き、そのまま仰向けに倒れ込んだ。
残された二人は慌てて彼女の傍に寄る。
さっきまでしていた甘酸っぱいニオイは、もうしていない。
「く、クライヴ先輩。一体何の魔法を……」
「感情を鎮静化させる魔法だ。ここまで効くとは思っていなかったがな」
たいして悪びれた様子も無く、クライヴはその鋭い目を私の方へ向ける。
大きな手の平が、私の頬を優しく撫でた。
「平気か?」
「は……はい。ありがとうございました」
「何があった?」
「なんというか……ちょっとした呼び出しだったんですけど、なんだか突然相手がエスカレートしていって、魔法まで……って感じです」
あまりアルバートの名前を出すのは悪いかと思い、そこは伏せておいた。
クライヴもそのあたりはそれ以上追求しなかった。
「そこの女の理性が飛ぶほどのことしたのか?」
「いや、それはないと思います。何か言う前に一方的にキレてた感じで……」
「そうか」
するり、と。
クライヴの大きな手が、再度私の頬を撫でる。
「……無事で良かった」
「……っ」
低く、柔らかく、甘い声音だった。
一気に顔が火照ってしまい、触れられている頬の部分からそれが伝わってしまいそうでますます恥ずかしかった。
その時。
「おーい君たち。競技中だよ?」
「モーリス先生……」
中庭に、モーリス先生が現れた。
彼は倒れ込む女生徒を見て、しかし非常に冷静にこの中で一番の年長者であるクライヴの方を向いた。
「一体何が……?」
「あー……魔法が暴発しそうになってたんで、それを止めました」
一連のことを全て庇ったクライヴのその言い回しは非常にナイスだった。
まさか嫉妬という個人的なそれで魔法を使ったとなれば、下手すると停学処分になりかねない。
一方的なことをされた側ではあるが、どうしても彼女の様子がおかしかったこともあり、そこまでの処分は受けてほしくないと思っていたのだ。だからクライヴの言い訳はとてもありがたかった。
「そうか、大変だったな。とりあえず彼女は私が医務室に運ぶから、君たちは校庭に戻りなさい」
モーリス先生も、おそらくはクライヴが彼女を庇っていることぐらいお見通しだろう。
それでもその言い訳に乗ってくれるのだから、やはり良い先生だとわかる。
「……不思議な香りだな」
この場を立ち去る前にモーリス先生のそんな呟きを耳にしながら、私たちは急いで校庭へと戻っていくのだった。
「へ?」
トイレから出たところで突然そんなことを言われ、私は振り返った。
そこには三名の女生徒がおり、どこか機嫌の悪そうな顔をしている。
それぞれがしている鉢巻きのチームカラーはバラバラだし、サポート委員会にも確かいなかったメンツだ。
つまり今この場が初対面ということになるが、一体どうしてそんなに機嫌が悪いのか、まるで見当が付かなかった。
「えっと……」
「こっち来てくれる?」
有無を言わせぬ態度を取られ、私は仕方なく彼女たちについていった。
校庭では今も競技が行われているというのに、向かう先は真逆の中庭だ。普段ならちらほらと生徒がいるここも、今では貸し切り状態となっている。
到着と共にしばらく沈黙して向き合っていたら、ようやく向こうが口を開いた。
「転入生のメア・モノクロイドよね?」
「そ、そうですけど……」
「あんた、クライヴ先輩と付き合ってるってホント?」
言われてギクリとした。
それと同時に、つまりこれはそういう関係の呼び出しなのだと合点がいく。
できるだけ事を穏便にしようと、私は平常心を保つように努めた。
「えーと、はい、そうです」
「ふーん」
目の前の彼女は腕を組み、何かを考えているようだった。後ろの二人もどこか釈然としない顔でこちらを見ている。
やっぱり彼女たちもクライヴが好きとかそういうのなのだろうか……と思いきや、話は思わぬ方向へ転がった。
「だったらなんでアルバート様と出かけてんの?」
「へ?」
「しらばっくれないでよ。先週、アルバート様と一緒にお茶してるの見たんですけど?」
まさかアルバートの名前が出るとは思わず、私は間の抜けた声を上げてしまった。
しかしそれが火に油を注いでしまったのか、彼女は目を吊り上げて怒鳴り出した。
「あの、それは……あの時はそもそもアイネと一緒に出かけて、たまたまアルバート先輩と会っただけで……」
そう弁解してみるものの、聞いてるのか聞いていないのか、彼女からの追撃は止まらない。
それにしても、なんだろうか、このニオイは。
彼女たちが現れた辺りから、何か、甘酸っぱいニオイが鼻について仕方がない。
悪い香りではないのだが、どうにも受け入れがたいニオイというか……
「聞いてんのかよ!」
「っ!」
ハッと我に返った時にはもう遅く、思い切り突き飛ばされてしまった。
無様なまでに尻餅をついた私は、恐る恐る彼女を見上げた。
(お、怒ってるのはわかるけど、こんな手が出るほど~!?)
なんというか、突然の挙動にパニックになってしまった。
彼女の後ろにいる二人も、私と同じように驚いている。どうやらここまでのことを私にするつもりではなかったようだ。
そうこうしているうちにも、彼女の感情はどんどんヒートアップしていく。
「アルバート様にはね、抜け駆け禁止っていう暗黙の了解があるんだよ! それを転入生の分際で何!? アルバート様の優しさに付け入りやがって!」
彼女のアルバートへの気持ちはよくわかった。
だが、こんなにも理性を失わせてしまうほどのことを私はしてしまったのだろうか。
なんだか様子がおかしくないか……と、そう思った瞬間だった。
「ちょ、ちょっと」
「え、やばいって……」
後ろの二人が同時に声を上げた。
一方の私は、逆に声を上げられなかった。
何故なら彼女が、魔法の杖を私に向けていたからだ。
こんなの、拳銃を向けられているのと何ら変わりない。思わず私はゴクリと息を呑んだ。
「あんたさえいなきゃ……あんたさえ……!」
もはや弁解どころか、何か言おうものなら一触即発の空気。
そうして杖が振り上げられ、私はギュッと目をつぶった。
「きゃあ!」
悲鳴を上げたのは、私ではなく彼女の方だった。
「……?」
恐る恐る目を開けると、目の前には杖を持っていた筈の手を痛そうに反対側の手で庇う彼女の姿が。
そうして右方から現れたのは、杖を片手に酷く恐い形相でこちらにやってくるクライヴの姿があった。
「……何やってんだ?」
地の底から響くようなその声音に、その場にいる誰もが縮こまった。
彼女の後ろの二人など、見るからに顔面蒼白になっている。
クライヴはまだ杖を持って警戒したまま、ゆっくりと私の近くまで来た。そしてエスコートするような優しい所作で腕を掴み、そっと私を立たせてくれる。
「話し合いなら見過ごしてやったが、明らかに魔法を使うところだったよなぁ?」
青筋を立て、私を庇うようにクライヴは彼女と対峙する。
普通ならばここで退散してもおかしくないほど、クライヴからの殺気は凄い。
しかし、彼女はそれでも退かず、むしろ目を血走らせて怒りを露わにした。
「……ずるい。ずるいずるいずるい! そうやってアルバート様にも取り入ったんでしょう!? 許せない……許せないっ!」
「……!」
彼女の目にはクライヴなど映っていない。
私を親の仇か何かかのような勢いで睨み付け、この状況下でありながらも、彼女は私に掴みかかろうとした。
だがその寸前で、クライヴの杖先から放たれた光が、彼女の脳天を貫いた。
「あ……あ……」
彼女の両眼はグルンと白目を向き、そのまま仰向けに倒れ込んだ。
残された二人は慌てて彼女の傍に寄る。
さっきまでしていた甘酸っぱいニオイは、もうしていない。
「く、クライヴ先輩。一体何の魔法を……」
「感情を鎮静化させる魔法だ。ここまで効くとは思っていなかったがな」
たいして悪びれた様子も無く、クライヴはその鋭い目を私の方へ向ける。
大きな手の平が、私の頬を優しく撫でた。
「平気か?」
「は……はい。ありがとうございました」
「何があった?」
「なんというか……ちょっとした呼び出しだったんですけど、なんだか突然相手がエスカレートしていって、魔法まで……って感じです」
あまりアルバートの名前を出すのは悪いかと思い、そこは伏せておいた。
クライヴもそのあたりはそれ以上追求しなかった。
「そこの女の理性が飛ぶほどのことしたのか?」
「いや、それはないと思います。何か言う前に一方的にキレてた感じで……」
「そうか」
するり、と。
クライヴの大きな手が、再度私の頬を撫でる。
「……無事で良かった」
「……っ」
低く、柔らかく、甘い声音だった。
一気に顔が火照ってしまい、触れられている頬の部分からそれが伝わってしまいそうでますます恥ずかしかった。
その時。
「おーい君たち。競技中だよ?」
「モーリス先生……」
中庭に、モーリス先生が現れた。
彼は倒れ込む女生徒を見て、しかし非常に冷静にこの中で一番の年長者であるクライヴの方を向いた。
「一体何が……?」
「あー……魔法が暴発しそうになってたんで、それを止めました」
一連のことを全て庇ったクライヴのその言い回しは非常にナイスだった。
まさか嫉妬という個人的なそれで魔法を使ったとなれば、下手すると停学処分になりかねない。
一方的なことをされた側ではあるが、どうしても彼女の様子がおかしかったこともあり、そこまでの処分は受けてほしくないと思っていたのだ。だからクライヴの言い訳はとてもありがたかった。
「そうか、大変だったな。とりあえず彼女は私が医務室に運ぶから、君たちは校庭に戻りなさい」
モーリス先生も、おそらくはクライヴが彼女を庇っていることぐらいお見通しだろう。
それでもその言い訳に乗ってくれるのだから、やはり良い先生だとわかる。
「……不思議な香りだな」
この場を立ち去る前にモーリス先生のそんな呟きを耳にしながら、私たちは急いで校庭へと戻っていくのだった。