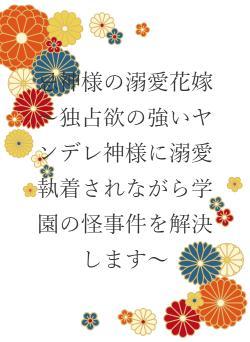「あらメア。早起きね」
眠たい目を擦る私とは逆に、今起きたばかりだというのに美しい佇まいをしているアイネから声をかけられた。
キッチンを占領していた私は邪魔ではないかと尋ねたが、アイネは大丈夫だと答えてくれた。
「朝ご飯にしては大量じゃない」
「あ、えーと……実はお弁当も作ってるの」
「偉いわね。でも……メアの分だけにしたって多くない?」
鋭いアイネの質問に、私は何となく照れながら答えた。
「あはは。実はクライヴ先輩の分も作ってまして……!」
「あら、素敵ね!」
途端にアイネの目が輝いた。
アイネは冷蔵庫からオレンジジュースを取り出して優雅に飲みながら、ニコニコとした笑顔をこちらに向けている。
「私、応援団のこと知らなくて、メアをサポート委員に誘ってしまったこと、少し後悔していたの。ごめんなさい」
「そんな! 謝らないでよ! 私がもしそのことを知ってたとしても、アイネと一緒にサポート委員やってたよ」
「あら、嬉しいわ」
そう。私はそのことを知っていながら、クライヴのことをすっかり忘れてサポート委員に入っていた薄情な奴なのだ。
先日、クライヴがちょっと拗ねていた気持ちもわからなくもないが……でもまあ偽りの恋人なんだしいいでしょう、と結論付けていた。
「私こそ、今日のお昼は一緒できなくてごめんね」
「べ、べつにそんなのよろしくってよ。クライヴ先輩と仲良くお昼、楽しんで」
少しだけ顔を赤くさせるアイネは本当に愛らしい。
「ありがとう。お礼に上手くできたタコさんウィンナーをあげる~」
言って、あーん、とアイネに催促する。
始めは恥ずかしがっていたアイネもゆっくりと口を開け、タコさんウィンナーを食してくれた。
「うん。美味しいわ。これでクライヴさんも大満足ね」
「ははは、だといいけど」
正直言って、食べ物の好みを聞き忘れていたし、そもそも運動しまくりの男子ってどれぐらい食べるのかわからない。
その所為でけっこうな量になってしまったが……クライヴには責任持って食べてもらおうと思った。
「今日は敵チーム同士だけどよろしくね」
「ええ。とはいっても私たちは委員会の方を頑張るんですけど」
「確かに」
そうして私は再びお弁当箱におかずたちを詰める作業に戻った。
時計を見ると思っていたより時間が進んでいて、ちょっと慌てながら作業を進めるのだった。
***
「みなさん、おはようございます! やってまいりました、『ナイトメアスポーツトーナメント』! 見事な晴天に我々の心も清々しいスポーツマンシップに満ち溢れていることでしょう! 去年に引き続き、実況は私、ミハエル・クリプトンと……」
「解説は私、アンジェリーク・ソワナでお送りします」
校庭に到着すると、ポンポンと花火が上がる傍ら、マイク越しにそんなハイテンションな放送が流れた。
彼らは『ナイトメアスポーツトーナメント』名脇役、ミハエルとアンジェリーク。天性の喋り上手なこともあり、1年生の時に名実況と解説をし、今年もその役目を務めることになった二人である。
(ファンブック情報だと確か幼馴染なんだよね。実はけっこう好きな二人だったりする)
懐かしいファンブックの内容を思い浮かべながら、私は青組のサポート委員の席へと着く。
フィールドにはすでに選手たちが勢揃いしていた。どの生徒も選手に選ばれるだけあって、非常に良いスタイルをしている。そんな生徒たちが集まっているものだから、なんだかそこだけ次元が違うように感じた。
(やっぱ運動できる人ってかっこいいよねぇ~。スタイルも抜群だし)
そんな中でも、やはり一際目立つのがクライヴだ。
運動着によって、制服の時よりも肌面積が露わになっており、その細身の筋肉質な体に思わず釘付けになってしまう。
よく聞くと赤組の応援団の席からは、早くもクライヴに向けて歓声が上がっている。
応援団はチームの組み分けは関係無いので、青組や黄組の裏切者も中にはいる。さすがはクライヴなだけあって、応援団の人数も多い。若干男の野太い声の方が多い気がするが。
そんなクライヴをついつい目で追っていた私は、クライヴの傍に女子選手がいることに気が付いた。スラリとした長い手足を持つスポーティーな彼女は、屈託のない表情でクライヴと談笑している。
クライヴも何やら楽しそうな笑顔を浮かべていて、思わず胸がずくりと痛む。
(う……うん? なんで胸が痛むんだ?)
身に覚えの無い症状に首を傾げている間に、第一競技が開始された。
最初の種目は50Mの徒競走。魔法での細工は一切無しの、純粋な運動神経勝負。
これはいわば、体育会系のオルニス寮生がこぞって挑む競技である。
案の定、レーンに並ぶ選手たちは皆、オルニス寮生だ。
「位置について、よーい……」
パンッという音と共に、選手たちが一斉に駆け出す。
草原を駆ける野生動物のようなその速さに、思わず目もくらんでしまう。
そんな試合が何度か続き、実況と解説も相まって大会も大いに盛り上がってきた。
そして徒競走のラストには、あのクライヴがレーンにいた。
「さあ、ラストのレーンにはあのクライヴ選手が立っています。応援席だけならず赤組からの声援が凄いですねー」
「毎年自己ベストを出していますから、今回も挑むんじゃないでしょうか」
「うおっ、それは実に楽しみだ! もちろんクライヴ選手を打ち負かす選手が現れることも期待したいところですが……!」
レーンに立つクライヴ以外の選手は二分されていた。
半ば戦意喪失している選手と、何が何でもクライヴに勝ってやるという選手だ。
当のクライヴは呑気にあくびをしていて、それがまた余裕のある感じで悔しいけど格好いい。
「位置について」
会場中が固唾を飲んで選手たちに注目する。
選手たちだけじゃなく、私たちも緊張してしまうほど張り詰めた空気だった。
「よーい……」
パンッという小気味良い音と共に、選手たちが一斉に駆け出した。
最初はみんな同じぐらいだった。しかし始まって少しも経たない内に、ぐん、と列から飛び出たのはクライヴだ。
彼の走りは、草原を駆ける野生動物なんて可愛らしいものではない。草食動物を追いかける肉食動物の狩りそのものだった。
「クライヴせんぱーい!」
「きゃー! クライヴくん頑張ってー!」
男女問わず、チーム問わず、応援と歓声が湧き起こる。
各言う私も何か言おうと思った。
思ったがしかし、私は何も言えなかった。
見惚れていたのだ。クライヴに。立ち尽くしたまま。
「ゴォオオオオオオル! 早い! 圧倒的に早かったクライヴ選手!」
「去年より早かったんじゃないですか?」
「今っ、計測器がタイムを出すところです……」
「……出たようですね」
「ああっ、これは! これは去年のタイムより一秒も早くなっています!」
実況と解説に合わせ、再び歓声が湧き起こった。
今ばかりは、会場中がクライヴを中心に盛り上がっている。
走り終えたクライヴはまだ余力を残していそうな佇まいで、汗をシャツで拭い、しばらくするとキョロキョロと何かを探していた。
「……!」
その探しものはどうやら私だったらしく、バッチリと目が合う。
瞬間、クライヴはニヤリと笑い、小さなガッツポーズを私に見せた。
(な、な、なにそれっ……かっこいいんだけど……!)
立ち尽くしたまま思わず顔を赤くしてしまった私は、慌ててクライヴから目を反らした。
イベントシナリオでは数行程度にしか描写されていなかった試合も、こうして間近で見ると、迫力もその凄さも全然違うのだとわからせられた。
眠たい目を擦る私とは逆に、今起きたばかりだというのに美しい佇まいをしているアイネから声をかけられた。
キッチンを占領していた私は邪魔ではないかと尋ねたが、アイネは大丈夫だと答えてくれた。
「朝ご飯にしては大量じゃない」
「あ、えーと……実はお弁当も作ってるの」
「偉いわね。でも……メアの分だけにしたって多くない?」
鋭いアイネの質問に、私は何となく照れながら答えた。
「あはは。実はクライヴ先輩の分も作ってまして……!」
「あら、素敵ね!」
途端にアイネの目が輝いた。
アイネは冷蔵庫からオレンジジュースを取り出して優雅に飲みながら、ニコニコとした笑顔をこちらに向けている。
「私、応援団のこと知らなくて、メアをサポート委員に誘ってしまったこと、少し後悔していたの。ごめんなさい」
「そんな! 謝らないでよ! 私がもしそのことを知ってたとしても、アイネと一緒にサポート委員やってたよ」
「あら、嬉しいわ」
そう。私はそのことを知っていながら、クライヴのことをすっかり忘れてサポート委員に入っていた薄情な奴なのだ。
先日、クライヴがちょっと拗ねていた気持ちもわからなくもないが……でもまあ偽りの恋人なんだしいいでしょう、と結論付けていた。
「私こそ、今日のお昼は一緒できなくてごめんね」
「べ、べつにそんなのよろしくってよ。クライヴ先輩と仲良くお昼、楽しんで」
少しだけ顔を赤くさせるアイネは本当に愛らしい。
「ありがとう。お礼に上手くできたタコさんウィンナーをあげる~」
言って、あーん、とアイネに催促する。
始めは恥ずかしがっていたアイネもゆっくりと口を開け、タコさんウィンナーを食してくれた。
「うん。美味しいわ。これでクライヴさんも大満足ね」
「ははは、だといいけど」
正直言って、食べ物の好みを聞き忘れていたし、そもそも運動しまくりの男子ってどれぐらい食べるのかわからない。
その所為でけっこうな量になってしまったが……クライヴには責任持って食べてもらおうと思った。
「今日は敵チーム同士だけどよろしくね」
「ええ。とはいっても私たちは委員会の方を頑張るんですけど」
「確かに」
そうして私は再びお弁当箱におかずたちを詰める作業に戻った。
時計を見ると思っていたより時間が進んでいて、ちょっと慌てながら作業を進めるのだった。
***
「みなさん、おはようございます! やってまいりました、『ナイトメアスポーツトーナメント』! 見事な晴天に我々の心も清々しいスポーツマンシップに満ち溢れていることでしょう! 去年に引き続き、実況は私、ミハエル・クリプトンと……」
「解説は私、アンジェリーク・ソワナでお送りします」
校庭に到着すると、ポンポンと花火が上がる傍ら、マイク越しにそんなハイテンションな放送が流れた。
彼らは『ナイトメアスポーツトーナメント』名脇役、ミハエルとアンジェリーク。天性の喋り上手なこともあり、1年生の時に名実況と解説をし、今年もその役目を務めることになった二人である。
(ファンブック情報だと確か幼馴染なんだよね。実はけっこう好きな二人だったりする)
懐かしいファンブックの内容を思い浮かべながら、私は青組のサポート委員の席へと着く。
フィールドにはすでに選手たちが勢揃いしていた。どの生徒も選手に選ばれるだけあって、非常に良いスタイルをしている。そんな生徒たちが集まっているものだから、なんだかそこだけ次元が違うように感じた。
(やっぱ運動できる人ってかっこいいよねぇ~。スタイルも抜群だし)
そんな中でも、やはり一際目立つのがクライヴだ。
運動着によって、制服の時よりも肌面積が露わになっており、その細身の筋肉質な体に思わず釘付けになってしまう。
よく聞くと赤組の応援団の席からは、早くもクライヴに向けて歓声が上がっている。
応援団はチームの組み分けは関係無いので、青組や黄組の裏切者も中にはいる。さすがはクライヴなだけあって、応援団の人数も多い。若干男の野太い声の方が多い気がするが。
そんなクライヴをついつい目で追っていた私は、クライヴの傍に女子選手がいることに気が付いた。スラリとした長い手足を持つスポーティーな彼女は、屈託のない表情でクライヴと談笑している。
クライヴも何やら楽しそうな笑顔を浮かべていて、思わず胸がずくりと痛む。
(う……うん? なんで胸が痛むんだ?)
身に覚えの無い症状に首を傾げている間に、第一競技が開始された。
最初の種目は50Mの徒競走。魔法での細工は一切無しの、純粋な運動神経勝負。
これはいわば、体育会系のオルニス寮生がこぞって挑む競技である。
案の定、レーンに並ぶ選手たちは皆、オルニス寮生だ。
「位置について、よーい……」
パンッという音と共に、選手たちが一斉に駆け出す。
草原を駆ける野生動物のようなその速さに、思わず目もくらんでしまう。
そんな試合が何度か続き、実況と解説も相まって大会も大いに盛り上がってきた。
そして徒競走のラストには、あのクライヴがレーンにいた。
「さあ、ラストのレーンにはあのクライヴ選手が立っています。応援席だけならず赤組からの声援が凄いですねー」
「毎年自己ベストを出していますから、今回も挑むんじゃないでしょうか」
「うおっ、それは実に楽しみだ! もちろんクライヴ選手を打ち負かす選手が現れることも期待したいところですが……!」
レーンに立つクライヴ以外の選手は二分されていた。
半ば戦意喪失している選手と、何が何でもクライヴに勝ってやるという選手だ。
当のクライヴは呑気にあくびをしていて、それがまた余裕のある感じで悔しいけど格好いい。
「位置について」
会場中が固唾を飲んで選手たちに注目する。
選手たちだけじゃなく、私たちも緊張してしまうほど張り詰めた空気だった。
「よーい……」
パンッという小気味良い音と共に、選手たちが一斉に駆け出した。
最初はみんな同じぐらいだった。しかし始まって少しも経たない内に、ぐん、と列から飛び出たのはクライヴだ。
彼の走りは、草原を駆ける野生動物なんて可愛らしいものではない。草食動物を追いかける肉食動物の狩りそのものだった。
「クライヴせんぱーい!」
「きゃー! クライヴくん頑張ってー!」
男女問わず、チーム問わず、応援と歓声が湧き起こる。
各言う私も何か言おうと思った。
思ったがしかし、私は何も言えなかった。
見惚れていたのだ。クライヴに。立ち尽くしたまま。
「ゴォオオオオオオル! 早い! 圧倒的に早かったクライヴ選手!」
「去年より早かったんじゃないですか?」
「今っ、計測器がタイムを出すところです……」
「……出たようですね」
「ああっ、これは! これは去年のタイムより一秒も早くなっています!」
実況と解説に合わせ、再び歓声が湧き起こった。
今ばかりは、会場中がクライヴを中心に盛り上がっている。
走り終えたクライヴはまだ余力を残していそうな佇まいで、汗をシャツで拭い、しばらくするとキョロキョロと何かを探していた。
「……!」
その探しものはどうやら私だったらしく、バッチリと目が合う。
瞬間、クライヴはニヤリと笑い、小さなガッツポーズを私に見せた。
(な、な、なにそれっ……かっこいいんだけど……!)
立ち尽くしたまま思わず顔を赤くしてしまった私は、慌ててクライヴから目を反らした。
イベントシナリオでは数行程度にしか描写されていなかった試合も、こうして間近で見ると、迫力もその凄さも全然違うのだとわからせられた。