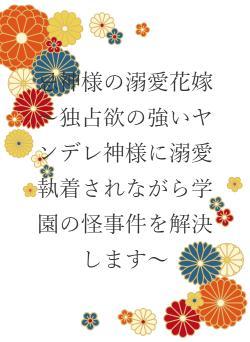そんなこんなで、現在の学園での話題は『ナイトメアスポーツトーナメント』一色だった。
各寮ごちゃまぜで、赤組・青組・黄組の3チームに分かれるわけだが……アイネは赤組、私は青組という結果になった。
サポート委員で一緒に行動できるものの、同じチームになれなかったのは非常に残念だ。
そして今日の放課後、青組の選手が校庭で自主練をするということで、私はそれに付き合うことになった。参加は自由だったが、せっかくのイベントシナリオなのだ……積極的に参加しなければ損である。
全ての授業を終えた私が校庭に出ると、広大な敷地にも関わらず、それなりの生徒で埋まっていた。青組だけでなく他のチームも自主練に燃えているようだ。
各カラーの鉢巻きを付けているため、青組が集まっている場所もすぐにわかった。
と、そちらに向かう前に、ポンポンと肩を叩かれる。
振り返るとそこにはアルバートの姿があった。
「やあ。もしかしてメアも青組?」
そう爽やかに挨拶してくるアルバートも、青色の鉢巻きを巻いていた。
つまり同じチームである。
「はい! アルバート先輩も青組だったんですね」
「メアと同じチームだったらな、って思っていたから嬉しいよ」
何とも嬉しいことを、自然な流れで言ってくれるものである。
運動着を着たフレッシュなプリンスも、実に素敵であった。
「先輩は選手……ですよね?」
アルバートの運動神経ならそうだろうという確信があった。
案の定、アルバートは笑顔で頷く。
「一応ね。オルニス寮生の人たちと比べたら全然だけど」
謙遜してみせるが、アルバートの運動能力は決して低くない。
そして何より『ナイトメアスポーツトーナメント』の競技は、純粋な運動能力勝負ではなく、そこに魔法や知恵の勝負も加わってくるところが面白いのだ。100M走なんかは、相手の走行を魔法で妨害するのがアリなため、非常に見応えがある。
なので、体力自慢のオルニス寮生が有利と言えばそうではないのが、この『ナイトメアスポーツトーナメント』の面白いところなのだった。
何より私は、このイベントシナリオでアルバートが善戦するのを知っている。プリンスの敬称に恥じない騎士道精神で、対戦相手を負かしていくサマは非常に格好良かった。
「そういえばメアはどうしてここに? クライヴの応援団なんじゃないの?」
アルバートからもそのことを言われ、私は口元を引き攣らせた。
「あはは……それがその、私がサポート委員になりたかったので、応援団は遠慮しておきました」
「そうなの?」
するとアルバートはキラキラとした笑顔をこちらに向けてきた。
「じゃあ、打倒クライヴだね。一緒に頑張ろう」
(ううっ、なんて眩しい笑顔……!)
おとぎ話に出てきてもおかしくないようなプリンススマイルに目をやられながら、私も必死に笑顔を返していた。
と、不意に、和気あいあいとしていた私たちの間に、第三者の陰が割り込んだ。
「おい。何してんだ」
「クライヴ先輩……!」
獰猛な獣のように唸り声を上げながら、そこには赤い鉢巻きを付けたクライヴの姿があった。
運動着に身を包むと、筋肉質な体躯がより顕著になって見惚れてしまいそうになる。
「やあクライヴ。君も練習かい?」
「当たり前だろ。それよりおまえら、同じチームなのかよ」
「は、はい。そうみたいです」
「ふーん」
今にも舌打ちしそうなほど、どこかクライヴの機嫌が悪い。
いつの間にか私の隣に立っているし。
「残念だったなおまえ。負けるチームに入っちまって」
「んな!? 何を根拠に……」
「俺のいるチームが負けるわけねぇだろ」
唖然としてしまうほど自信満々にそう言い切ったクライヴは、いっそのこと格好良すぎた。有言実行してしまえるだろう実力と自信が漲っている。
実のところこのイベント、クライヴのいる赤組が勝つのである。
だが、それはそれとして一生懸命練習に励むアルバートや他の生徒のことを思うと、結果はわかっていても頑張りたい気持ちがあった。
なので私は口をへの字にしてアルバートの隣へと移動する。
「勝負は当日までわからないし、そんなだと足元すくわれますよーだ」
「ははは。確かにメアの言う通りだ」
「あぁ?」
さっきまでこれ以上無いほどの余裕を見せていたのに、今はガラの悪い顔でこちらを睨みつけている。
しかし先に喧嘩を売ってきたのはクライヴの方だし、彼が言う通り我々は敵対チームである。この構図で間違っていないはずだ。
「クライヴ。確かに運動神経だけなら君には勝てないだろうけど、『ナイトメアスポーツトーナメント』は魔法アリの競技ばかりだ。去年も一昨年もMVPを取っていたけど、今年こそは負けないよ」
「はっ。言ってろ」
アルバートの意気込みを、クライヴは鼻で笑う。
なんだかあまりにもアルバートがキラキラしている所為か、クライヴが悪役みたいな対比になっていて笑いそうになってしまった。
だが、こっそりと笑う前にクライヴから再度睨まれた。
「……おまえ」
「……はい?」
「本当にサポート委員なんかやる気か……?」
ジトッとした眼差しを向けられる。
機嫌が悪いようにも、どこか拗ねているようにも見えて、私は首を傾げた。
すると、隣に立つアルバートがニコニコと笑いながら口を開く。
「ふふっ。クライヴはよっぽどメアに応援団に入ってほしいんだね」
「えっ」
「うるせぇな」
まさかそういう意味だとは思わず、私はアルバートとクライヴを交互に見た。
そしてクライヴと目が合うと、やはりどこか拗ねた様子で舌打ちする。
「ぜってぇ負かしてやるからな」
「ひえぇ」
最初はアルバートにのみ向けられていた敵意が、今度はこちらにも向いていた。
間違いなく赤組の総大将であるクライヴ直々に負かす宣言をされ、これは当日、一体どんな試合が繰り広げられるのだと心配になった。
隣に立つアルバートだけが、のほほんとしている。
前途多難なイベントシナリオになりそうである。
各寮ごちゃまぜで、赤組・青組・黄組の3チームに分かれるわけだが……アイネは赤組、私は青組という結果になった。
サポート委員で一緒に行動できるものの、同じチームになれなかったのは非常に残念だ。
そして今日の放課後、青組の選手が校庭で自主練をするということで、私はそれに付き合うことになった。参加は自由だったが、せっかくのイベントシナリオなのだ……積極的に参加しなければ損である。
全ての授業を終えた私が校庭に出ると、広大な敷地にも関わらず、それなりの生徒で埋まっていた。青組だけでなく他のチームも自主練に燃えているようだ。
各カラーの鉢巻きを付けているため、青組が集まっている場所もすぐにわかった。
と、そちらに向かう前に、ポンポンと肩を叩かれる。
振り返るとそこにはアルバートの姿があった。
「やあ。もしかしてメアも青組?」
そう爽やかに挨拶してくるアルバートも、青色の鉢巻きを巻いていた。
つまり同じチームである。
「はい! アルバート先輩も青組だったんですね」
「メアと同じチームだったらな、って思っていたから嬉しいよ」
何とも嬉しいことを、自然な流れで言ってくれるものである。
運動着を着たフレッシュなプリンスも、実に素敵であった。
「先輩は選手……ですよね?」
アルバートの運動神経ならそうだろうという確信があった。
案の定、アルバートは笑顔で頷く。
「一応ね。オルニス寮生の人たちと比べたら全然だけど」
謙遜してみせるが、アルバートの運動能力は決して低くない。
そして何より『ナイトメアスポーツトーナメント』の競技は、純粋な運動能力勝負ではなく、そこに魔法や知恵の勝負も加わってくるところが面白いのだ。100M走なんかは、相手の走行を魔法で妨害するのがアリなため、非常に見応えがある。
なので、体力自慢のオルニス寮生が有利と言えばそうではないのが、この『ナイトメアスポーツトーナメント』の面白いところなのだった。
何より私は、このイベントシナリオでアルバートが善戦するのを知っている。プリンスの敬称に恥じない騎士道精神で、対戦相手を負かしていくサマは非常に格好良かった。
「そういえばメアはどうしてここに? クライヴの応援団なんじゃないの?」
アルバートからもそのことを言われ、私は口元を引き攣らせた。
「あはは……それがその、私がサポート委員になりたかったので、応援団は遠慮しておきました」
「そうなの?」
するとアルバートはキラキラとした笑顔をこちらに向けてきた。
「じゃあ、打倒クライヴだね。一緒に頑張ろう」
(ううっ、なんて眩しい笑顔……!)
おとぎ話に出てきてもおかしくないようなプリンススマイルに目をやられながら、私も必死に笑顔を返していた。
と、不意に、和気あいあいとしていた私たちの間に、第三者の陰が割り込んだ。
「おい。何してんだ」
「クライヴ先輩……!」
獰猛な獣のように唸り声を上げながら、そこには赤い鉢巻きを付けたクライヴの姿があった。
運動着に身を包むと、筋肉質な体躯がより顕著になって見惚れてしまいそうになる。
「やあクライヴ。君も練習かい?」
「当たり前だろ。それよりおまえら、同じチームなのかよ」
「は、はい。そうみたいです」
「ふーん」
今にも舌打ちしそうなほど、どこかクライヴの機嫌が悪い。
いつの間にか私の隣に立っているし。
「残念だったなおまえ。負けるチームに入っちまって」
「んな!? 何を根拠に……」
「俺のいるチームが負けるわけねぇだろ」
唖然としてしまうほど自信満々にそう言い切ったクライヴは、いっそのこと格好良すぎた。有言実行してしまえるだろう実力と自信が漲っている。
実のところこのイベント、クライヴのいる赤組が勝つのである。
だが、それはそれとして一生懸命練習に励むアルバートや他の生徒のことを思うと、結果はわかっていても頑張りたい気持ちがあった。
なので私は口をへの字にしてアルバートの隣へと移動する。
「勝負は当日までわからないし、そんなだと足元すくわれますよーだ」
「ははは。確かにメアの言う通りだ」
「あぁ?」
さっきまでこれ以上無いほどの余裕を見せていたのに、今はガラの悪い顔でこちらを睨みつけている。
しかし先に喧嘩を売ってきたのはクライヴの方だし、彼が言う通り我々は敵対チームである。この構図で間違っていないはずだ。
「クライヴ。確かに運動神経だけなら君には勝てないだろうけど、『ナイトメアスポーツトーナメント』は魔法アリの競技ばかりだ。去年も一昨年もMVPを取っていたけど、今年こそは負けないよ」
「はっ。言ってろ」
アルバートの意気込みを、クライヴは鼻で笑う。
なんだかあまりにもアルバートがキラキラしている所為か、クライヴが悪役みたいな対比になっていて笑いそうになってしまった。
だが、こっそりと笑う前にクライヴから再度睨まれた。
「……おまえ」
「……はい?」
「本当にサポート委員なんかやる気か……?」
ジトッとした眼差しを向けられる。
機嫌が悪いようにも、どこか拗ねているようにも見えて、私は首を傾げた。
すると、隣に立つアルバートがニコニコと笑いながら口を開く。
「ふふっ。クライヴはよっぽどメアに応援団に入ってほしいんだね」
「えっ」
「うるせぇな」
まさかそういう意味だとは思わず、私はアルバートとクライヴを交互に見た。
そしてクライヴと目が合うと、やはりどこか拗ねた様子で舌打ちする。
「ぜってぇ負かしてやるからな」
「ひえぇ」
最初はアルバートにのみ向けられていた敵意が、今度はこちらにも向いていた。
間違いなく赤組の総大将であるクライヴ直々に負かす宣言をされ、これは当日、一体どんな試合が繰り広げられるのだと心配になった。
隣に立つアルバートだけが、のほほんとしている。
前途多難なイベントシナリオになりそうである。