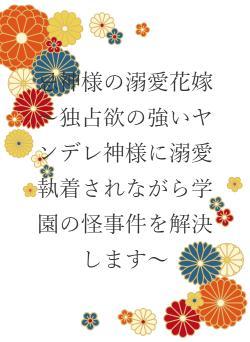「ねえアイネ。ハンカチを買うのにいいお店知らない?」
「ハンカチ?」
全ての授業を終え、フィオーレ寮の自室に戻った私は、同室のアイネにそう訊ねた。
ネイトに返すハンカチ……買うなら早めの方がいい。
ちょうど明日は休日だ。お出掛けにもってこいである。
「ハンカチが必要なら取り寄せますけど?」
「そ、それじゃ駄目なの。私が買うことに意味がある!」
「あらそう」
お嬢様らしいアイネの提案を、私は慌てて却下した。
アイネに頼めば、素晴らしい刺繍の入ったハンカチを何百枚と用意してくれるだろう。
「そうね……学園の近くに良い雑貨屋があったはずよ。以前、お父様への贈り物でそのお店を利用した覚えがあるわ」
「まさにそういうお店が知りたかったの! ありがとう!」
「……一人で行くの?」
「そのつもりだけど……」
「じゃあ私が同行してもよろしくて?」
「ええーホント? 嬉しいよ!」
まさかアイネが一緒に行ってくれるとは思わず、私は彼女に抱き付いた。
さすが主人公のお助けキャラ。困っていると自然と助けてくれる。
それに友人として休日に遊べるのは純粋に嬉しい。
「ありがとアイネ! 明日が楽しみ!」
「私もよ、メア」
私たちはお互い笑顔を見せ合いながら、明日の事へ思いをはせた。とびきり楽しい休日になるよう、あれやこれやとスケジュールを立てながら。
***
「わぁー、すてき」
翌日。
アイネに連れられて入った雑貨屋は、想像以上に可愛く、そして趣があった。
まさに魔法グッズを置いてある店のイメージそのもので、店内はそこそこの広さがあるのに、所狭しとありとあらゆる雑貨が置かれていた。
シルバーアクセや箒、ドレスに小物……ここには何でも揃えられているのではないかと錯覚してしまう。
もちろんお目当てのハンカチも豊富に取り揃えてあり、私は笑顔でそのコーナーへと急いだ。
「こんなにあると逆に迷う~。これいいなぁ……あ、でもこっちも捨てがたい……」
「それ、男物ですけど……もしかしてプレゼントされるの?」
「うん、そうなの。この間ハンカチもらっちゃって……そのお返しに」
「まあ」
色々端折ったが嘘ではない。
しかし、果たしてネイトは今日選んだハンカチを受け取ってくれるだろうか。
もしかしたら余計なお世話だと受け取ってくれないかもしれない。好感度が低い時のネイトは、かなりとっつきにくいから。
(でも好感度が上がった時のネイトのギャップが凄くて……私はそれで推しになったところあるしな~)
ゲームと同じほどじゃなくてもいいから、せっかくだし仲良くなりたいとは思う。
そのためにも、彼に受け取ってもらえるようなハンカチを選びたい。
「あ、これ……」
ふと手に取ったのは、黒い生地に宝石をモチーフにした赤い刺繍の入ったハンカチだった。
ちょうどその組み合わせはネイトの髪色と目の色と一緒である。
シンプルかつ上品なそのハンカチは、まさにこれだ、という一品だと思った。
「これにする!」
「あら、素敵ね」
アイネからのお墨付きももらえ、私はレジへと向かう。
店長と思われるおじいさんはラッピングを快く受け入れてくれて、カウンターに箱からリボンまであらゆる種類のものを披露してくれた。
私はハンカチ選びと同じぐらい悩みながら、ハンカチと同じ色合いの、黒い箱と赤いリボンでお願いする。
おじいさんがサッと杖を振ると、たちまちリボンと箱が動き出し、すぐさまラッピングが完了した。
「ありがとうございます!」
「こちらこそありがとね。こんなにお嬢ちゃんに一生懸命考えてもらえて、貰う相手は幸運な人だ」
気持ちの良いことを言ってくれるおじいさんの言葉を背に受けながら、私たちは店を後にした。
アイネが言う通り本当に良いお店だったので、今後も何かある時はお世話になろうと思った。
「アイネのお陰でいい買い物ができたよ~ありがとう」
「それなら良かったわ。少し休憩する?」
「うん、そうしよう」
「美味しいココアを飲めるお店を知ってるのよ。良ければそこにしませんこと?」
「うわー最高! 行く行く!」
休日に友達とこうして遊ぶのも、最近は本当に無かったのでなんだか懐かしい気持ちになる。
何よりアイネとこうしている時間が楽しくてしょうがない。
『マジナイ』のゲーム内でも、主人公を何かと気にかけては支えてくれる。そんなアイネというキャラに「むしろアイネルート作ってくれ!」と一部界隈からそんな意見も出るぐらいだった。
学校での時間も楽しいが、こんな休日のような時間がいつまでも続けばいいな。
そう思っていた、の、だが。
「ねえねえ、良ければ一緒にお茶しない?」
街道に差し掛かったところで、典型的なナンパと遭遇してしまった。
せっかく楽しんでいたテンションが一気にガタ落ちである。
私はアイネの手を引いて、サッと横を通り過ぎようとした。
しかし。
「きゃっ!」
「つれないことしないでよ」
男にいきなり手を掴まれ、思わず悲鳴が出た。
当人は大した力じゃないのだろうが、私からすると掴まれている手首がとても痛い。
更に男女の力の差なのかビクともせず、それがとても恐かった。
「お茶ぐらいイイじゃん。奢るからさ」
「けっこうですわ。それよりメアの手を離しなさい」
「えー、こっちも気が強いんだー。俺、気の強い子好みなんだよねー」
男の態度はどこまでも余裕だった。
女二人ぐらいどうとでもなるというおごりからだろうか。
しかし男は気付いていない。アイネは貴族ハーティア家の子女である。
おそらく今日だって護衛が遠巻きにこの光景を見ているはずだ。
(護衛の人……た、助けて~……!)
心の中で私は必死にお願いする。
と、願いが通じたのか一人の男が傍に寄って来た。
だがその顔は見知ったもので、私は口を開けて驚いてしまった。
「君、やめないか」
「あ?」
そこには、男の腕を掴むアルバートの姿があった。
普段の制服と同じように、キッチリと着こなしたワイシャツとパンツスタイル。カジュアルな服装でも、品性が隠し切れていない。
「げっ……アルバート・バシレウス……」
「ほお。僕を知っているということは学園の生徒かな? 学園長に言って調べさせてもらおうか?」
「ちっ」
男は忌々しそうに舌打ちし、虚勢は張っていたものの、しばしアルバートを睨みつけ、私の腕を突き放す。
思わずよろけた私を、アルバートは受け止めてくれる。
「家の威光を借りてるだけのくせに」
「困っている人を助けられるならいくらでも借りるさ」
淀みないアルバートの物言い。その眼差しは真っ直ぐで、少しもぶれていない。
かなわないと感じたのか、再度男は舌打ちをし、そこでようやく去って行った。
私は男の姿が小さくなる頃、自分がアルバートに支えられていたことを思い出し、慌てて離れる。
「あのっ……ありがとうございます」
「腕、大丈夫だった?」
「あ、はい。ちょっとビックリしただけで……」
「それなら良かった。アイネさんも大丈夫?」
「ええ。メアが庇ってくれたから大丈夫でしたわ」
アイネの言葉に、アルバートは眉をしかめる。
「あんまり無理しちゃ駄目だよ」
まるで春の木漏れ日のようにその眼差しは優しい。
容姿だけでなく性格まで魅力的なアルバートに、思わず私は頬を染めてしまう。
現実世界では好き寄りの普通ぐらいのキャラだったのに、実際にこうして出会ってみるとその破壊力はすさまじい。
(好きになっちゃうよこんなの!)
何度目かわからないほど心の中で頭を抱えている私を余所に、アイネが落ち着いた様子でアルバートに話しかけた。
「アルバートさんはどうしてこちらへ?」
「授業で使う書物を買いに本屋に寄ってたんだ。それでたまたま君たちを見かけたと思ったら、あまりよくない輩に絡まれていたから……つい、ね」
「うちの護衛より早い判断で助かりましたわ」
微笑し合っている二人の姿は、何とも絵になっている。
一方はフワフワのクルミ色の茶髪に、甘いチェリーピンク色の大きな瞳を持ち合わせたお嬢様。もう一方はサラサラのシルバーアッシュに、柔和なコバルトブルーの瞳を輝かせたプリンス。
まるでおとぎ話の王子様とお姫様のような二人に、ついつい私は見惚れてしまう。
「メア……あんまり見られていると恥ずかしいよ」
「そうよ。何をそんなに見ているの?」
「はっ! ご、ごめん、つい」
二人からのツッコミに、私は慌てて緩みきった顔を正す。
少しだけ顔を赤くしたアルバートが、咳払いをして私の方へと向き直った。
「二人はこれから何処かに行く予定なの?」
「アイネがオススメのココアを出すお店に行くところでした」
「ああ、僕もそこは知ってるな。じゃあ……この間の埋め合わせに、二人にココアを奢るよ」
「ええっ!? そんな……助けてもらっただけで充分なのに……」
「埋め合わせなんて無くたって、僕は君を助けたよ」
あまりにも格好いい返しをされ、私は乙女のようにときめいてしまった。
そんな私の様子を隣で眺めていたアイネは、毅然とした態度でアルバートに告げる。
「お二人の間での埋め合わせなら、私の分は自分で買いますわ」
「でも……」
「それが筋というものよ。メアの埋め合わせはメアだけにしてあげてくださいまし」
「……そっか。優しいね、アイネさん」
アルバートの言う通り優しくて、そしてアイネもアイネで格好いいと思った。
これが気高い貴族魂というものなのだろうかと、私は一人感心してしまう。
こうしてアルバートと共に、私たちはアイネがオススメする喫茶店へと入った。
アイボリーを基調とした店内は非常に落ち着く空間で、ココアだけでなくコーヒーや紅茶の種類も豊富に用意されていた。ショーケースに並んだケーキやパニーニにも目を奪われる。
私とアイネは席に着き、アルバートがレジへと向かった。
「アルバートさんと知り合いだったのね」
「え? ああ、うん。昨日、使い魔のオロールを助けてあげて、それでね」
「ふうん」
口元に手を当て、何やら考え込んだ様子のアイネ。
何か変なことを言ってしまっただろうか。
というか、お助けキャラのアイネ的に、アルバートはどういう立ち位置のキャラになるのだろうか。
そんなことを考えている内に、アルバートがトレイを持って席にやって来た。
「はい、ココア。あとケーキも」
「え!」
「ショーケースの見てたでしょ? それともいらない?」
「いや……でも……」
「嫌じゃなきゃぜひ食べてほしいな」
「じゃ、じゃあ……お言葉に甘えて」
どこまでも気の利く男・アルバートの気遣いに、私は絆されていく。
もし彼氏とデート中にこんなことされたら、胸キュンどころじゃ済まない。
(アルバートルートをいくと、たぶん毎回これぐらい甘やかしてもらえるんだろうなぁ。うわぁ~、絶対私落ちる、ってか沼る)
一人でドキドキしながらココアに口を付けると、濃厚なカカオの味が口内に広がり、自然とホッとした安心感が訪れた。
アイネの言う通り美味しいココアである。
「美味しい……! ケーキも、すっごく美味しい」
「それなら良かったわ」
「良かったね、メア」
私は子供のように感激しながら、二人に見守られてココアを飲み、ケーキを食した。
なんだか二人の目があまりにも慈愛に満ちていて恥ずかしくなってしまう。
それからしばらく私たちは会話に花を咲かせた。
アルバートの家とも関わりのあるアイネの貴族らしい話から、学園の先輩としてアルバートによる小テストで良い点を取るためのコツなど、話題には事欠かなかった。
「私、ちょっとお手洗いに行ってくるね」
入店してだいぶ時間が経った頃、私は生理現象を催し、そう言って席を立った。
残された二人を見ると、やっぱり二人はとても絵になり、お似合いだとすら思えた。
(あの席だけキラキラ度が違う……)
私はキラキラと輝く席を後にし、トイレへと急ぐのだった。
「……意外でしたわ」
「え?」
「アルバートさんが家の事を盾にして助けて下さったこと」
「ああ。無我夢中でね」
「『メア』だから、ではなくて?」
「………」
「どうなんですの?」
「……メアは、クライヴと付き合っているし、そんなんじゃないよ」
「まるでメアがクライヴさんと付き合っていなければ、って言ってるようなものですわ」
「……難しいことを言うなぁ」
「まあ、私としてはメアに好意を寄せる殿方が何人いても嬉しいの。だから貴方がもしそうなら、クライヴさんとは別に応援してもよくってよ」
「ははっ。それは頼もしいなぁ」
「ただいまー。何の話?」
トイレから帰って来た私に、二人は口を揃えて「秘密」とだけ告げた。
非常に内容が気になるものだが、なんだか二人の仲が深まっているようで、それはそれで嬉しかったのだった。
「ハンカチ?」
全ての授業を終え、フィオーレ寮の自室に戻った私は、同室のアイネにそう訊ねた。
ネイトに返すハンカチ……買うなら早めの方がいい。
ちょうど明日は休日だ。お出掛けにもってこいである。
「ハンカチが必要なら取り寄せますけど?」
「そ、それじゃ駄目なの。私が買うことに意味がある!」
「あらそう」
お嬢様らしいアイネの提案を、私は慌てて却下した。
アイネに頼めば、素晴らしい刺繍の入ったハンカチを何百枚と用意してくれるだろう。
「そうね……学園の近くに良い雑貨屋があったはずよ。以前、お父様への贈り物でそのお店を利用した覚えがあるわ」
「まさにそういうお店が知りたかったの! ありがとう!」
「……一人で行くの?」
「そのつもりだけど……」
「じゃあ私が同行してもよろしくて?」
「ええーホント? 嬉しいよ!」
まさかアイネが一緒に行ってくれるとは思わず、私は彼女に抱き付いた。
さすが主人公のお助けキャラ。困っていると自然と助けてくれる。
それに友人として休日に遊べるのは純粋に嬉しい。
「ありがとアイネ! 明日が楽しみ!」
「私もよ、メア」
私たちはお互い笑顔を見せ合いながら、明日の事へ思いをはせた。とびきり楽しい休日になるよう、あれやこれやとスケジュールを立てながら。
***
「わぁー、すてき」
翌日。
アイネに連れられて入った雑貨屋は、想像以上に可愛く、そして趣があった。
まさに魔法グッズを置いてある店のイメージそのもので、店内はそこそこの広さがあるのに、所狭しとありとあらゆる雑貨が置かれていた。
シルバーアクセや箒、ドレスに小物……ここには何でも揃えられているのではないかと錯覚してしまう。
もちろんお目当てのハンカチも豊富に取り揃えてあり、私は笑顔でそのコーナーへと急いだ。
「こんなにあると逆に迷う~。これいいなぁ……あ、でもこっちも捨てがたい……」
「それ、男物ですけど……もしかしてプレゼントされるの?」
「うん、そうなの。この間ハンカチもらっちゃって……そのお返しに」
「まあ」
色々端折ったが嘘ではない。
しかし、果たしてネイトは今日選んだハンカチを受け取ってくれるだろうか。
もしかしたら余計なお世話だと受け取ってくれないかもしれない。好感度が低い時のネイトは、かなりとっつきにくいから。
(でも好感度が上がった時のネイトのギャップが凄くて……私はそれで推しになったところあるしな~)
ゲームと同じほどじゃなくてもいいから、せっかくだし仲良くなりたいとは思う。
そのためにも、彼に受け取ってもらえるようなハンカチを選びたい。
「あ、これ……」
ふと手に取ったのは、黒い生地に宝石をモチーフにした赤い刺繍の入ったハンカチだった。
ちょうどその組み合わせはネイトの髪色と目の色と一緒である。
シンプルかつ上品なそのハンカチは、まさにこれだ、という一品だと思った。
「これにする!」
「あら、素敵ね」
アイネからのお墨付きももらえ、私はレジへと向かう。
店長と思われるおじいさんはラッピングを快く受け入れてくれて、カウンターに箱からリボンまであらゆる種類のものを披露してくれた。
私はハンカチ選びと同じぐらい悩みながら、ハンカチと同じ色合いの、黒い箱と赤いリボンでお願いする。
おじいさんがサッと杖を振ると、たちまちリボンと箱が動き出し、すぐさまラッピングが完了した。
「ありがとうございます!」
「こちらこそありがとね。こんなにお嬢ちゃんに一生懸命考えてもらえて、貰う相手は幸運な人だ」
気持ちの良いことを言ってくれるおじいさんの言葉を背に受けながら、私たちは店を後にした。
アイネが言う通り本当に良いお店だったので、今後も何かある時はお世話になろうと思った。
「アイネのお陰でいい買い物ができたよ~ありがとう」
「それなら良かったわ。少し休憩する?」
「うん、そうしよう」
「美味しいココアを飲めるお店を知ってるのよ。良ければそこにしませんこと?」
「うわー最高! 行く行く!」
休日に友達とこうして遊ぶのも、最近は本当に無かったのでなんだか懐かしい気持ちになる。
何よりアイネとこうしている時間が楽しくてしょうがない。
『マジナイ』のゲーム内でも、主人公を何かと気にかけては支えてくれる。そんなアイネというキャラに「むしろアイネルート作ってくれ!」と一部界隈からそんな意見も出るぐらいだった。
学校での時間も楽しいが、こんな休日のような時間がいつまでも続けばいいな。
そう思っていた、の、だが。
「ねえねえ、良ければ一緒にお茶しない?」
街道に差し掛かったところで、典型的なナンパと遭遇してしまった。
せっかく楽しんでいたテンションが一気にガタ落ちである。
私はアイネの手を引いて、サッと横を通り過ぎようとした。
しかし。
「きゃっ!」
「つれないことしないでよ」
男にいきなり手を掴まれ、思わず悲鳴が出た。
当人は大した力じゃないのだろうが、私からすると掴まれている手首がとても痛い。
更に男女の力の差なのかビクともせず、それがとても恐かった。
「お茶ぐらいイイじゃん。奢るからさ」
「けっこうですわ。それよりメアの手を離しなさい」
「えー、こっちも気が強いんだー。俺、気の強い子好みなんだよねー」
男の態度はどこまでも余裕だった。
女二人ぐらいどうとでもなるというおごりからだろうか。
しかし男は気付いていない。アイネは貴族ハーティア家の子女である。
おそらく今日だって護衛が遠巻きにこの光景を見ているはずだ。
(護衛の人……た、助けて~……!)
心の中で私は必死にお願いする。
と、願いが通じたのか一人の男が傍に寄って来た。
だがその顔は見知ったもので、私は口を開けて驚いてしまった。
「君、やめないか」
「あ?」
そこには、男の腕を掴むアルバートの姿があった。
普段の制服と同じように、キッチリと着こなしたワイシャツとパンツスタイル。カジュアルな服装でも、品性が隠し切れていない。
「げっ……アルバート・バシレウス……」
「ほお。僕を知っているということは学園の生徒かな? 学園長に言って調べさせてもらおうか?」
「ちっ」
男は忌々しそうに舌打ちし、虚勢は張っていたものの、しばしアルバートを睨みつけ、私の腕を突き放す。
思わずよろけた私を、アルバートは受け止めてくれる。
「家の威光を借りてるだけのくせに」
「困っている人を助けられるならいくらでも借りるさ」
淀みないアルバートの物言い。その眼差しは真っ直ぐで、少しもぶれていない。
かなわないと感じたのか、再度男は舌打ちをし、そこでようやく去って行った。
私は男の姿が小さくなる頃、自分がアルバートに支えられていたことを思い出し、慌てて離れる。
「あのっ……ありがとうございます」
「腕、大丈夫だった?」
「あ、はい。ちょっとビックリしただけで……」
「それなら良かった。アイネさんも大丈夫?」
「ええ。メアが庇ってくれたから大丈夫でしたわ」
アイネの言葉に、アルバートは眉をしかめる。
「あんまり無理しちゃ駄目だよ」
まるで春の木漏れ日のようにその眼差しは優しい。
容姿だけでなく性格まで魅力的なアルバートに、思わず私は頬を染めてしまう。
現実世界では好き寄りの普通ぐらいのキャラだったのに、実際にこうして出会ってみるとその破壊力はすさまじい。
(好きになっちゃうよこんなの!)
何度目かわからないほど心の中で頭を抱えている私を余所に、アイネが落ち着いた様子でアルバートに話しかけた。
「アルバートさんはどうしてこちらへ?」
「授業で使う書物を買いに本屋に寄ってたんだ。それでたまたま君たちを見かけたと思ったら、あまりよくない輩に絡まれていたから……つい、ね」
「うちの護衛より早い判断で助かりましたわ」
微笑し合っている二人の姿は、何とも絵になっている。
一方はフワフワのクルミ色の茶髪に、甘いチェリーピンク色の大きな瞳を持ち合わせたお嬢様。もう一方はサラサラのシルバーアッシュに、柔和なコバルトブルーの瞳を輝かせたプリンス。
まるでおとぎ話の王子様とお姫様のような二人に、ついつい私は見惚れてしまう。
「メア……あんまり見られていると恥ずかしいよ」
「そうよ。何をそんなに見ているの?」
「はっ! ご、ごめん、つい」
二人からのツッコミに、私は慌てて緩みきった顔を正す。
少しだけ顔を赤くしたアルバートが、咳払いをして私の方へと向き直った。
「二人はこれから何処かに行く予定なの?」
「アイネがオススメのココアを出すお店に行くところでした」
「ああ、僕もそこは知ってるな。じゃあ……この間の埋め合わせに、二人にココアを奢るよ」
「ええっ!? そんな……助けてもらっただけで充分なのに……」
「埋め合わせなんて無くたって、僕は君を助けたよ」
あまりにも格好いい返しをされ、私は乙女のようにときめいてしまった。
そんな私の様子を隣で眺めていたアイネは、毅然とした態度でアルバートに告げる。
「お二人の間での埋め合わせなら、私の分は自分で買いますわ」
「でも……」
「それが筋というものよ。メアの埋め合わせはメアだけにしてあげてくださいまし」
「……そっか。優しいね、アイネさん」
アルバートの言う通り優しくて、そしてアイネもアイネで格好いいと思った。
これが気高い貴族魂というものなのだろうかと、私は一人感心してしまう。
こうしてアルバートと共に、私たちはアイネがオススメする喫茶店へと入った。
アイボリーを基調とした店内は非常に落ち着く空間で、ココアだけでなくコーヒーや紅茶の種類も豊富に用意されていた。ショーケースに並んだケーキやパニーニにも目を奪われる。
私とアイネは席に着き、アルバートがレジへと向かった。
「アルバートさんと知り合いだったのね」
「え? ああ、うん。昨日、使い魔のオロールを助けてあげて、それでね」
「ふうん」
口元に手を当て、何やら考え込んだ様子のアイネ。
何か変なことを言ってしまっただろうか。
というか、お助けキャラのアイネ的に、アルバートはどういう立ち位置のキャラになるのだろうか。
そんなことを考えている内に、アルバートがトレイを持って席にやって来た。
「はい、ココア。あとケーキも」
「え!」
「ショーケースの見てたでしょ? それともいらない?」
「いや……でも……」
「嫌じゃなきゃぜひ食べてほしいな」
「じゃ、じゃあ……お言葉に甘えて」
どこまでも気の利く男・アルバートの気遣いに、私は絆されていく。
もし彼氏とデート中にこんなことされたら、胸キュンどころじゃ済まない。
(アルバートルートをいくと、たぶん毎回これぐらい甘やかしてもらえるんだろうなぁ。うわぁ~、絶対私落ちる、ってか沼る)
一人でドキドキしながらココアに口を付けると、濃厚なカカオの味が口内に広がり、自然とホッとした安心感が訪れた。
アイネの言う通り美味しいココアである。
「美味しい……! ケーキも、すっごく美味しい」
「それなら良かったわ」
「良かったね、メア」
私は子供のように感激しながら、二人に見守られてココアを飲み、ケーキを食した。
なんだか二人の目があまりにも慈愛に満ちていて恥ずかしくなってしまう。
それからしばらく私たちは会話に花を咲かせた。
アルバートの家とも関わりのあるアイネの貴族らしい話から、学園の先輩としてアルバートによる小テストで良い点を取るためのコツなど、話題には事欠かなかった。
「私、ちょっとお手洗いに行ってくるね」
入店してだいぶ時間が経った頃、私は生理現象を催し、そう言って席を立った。
残された二人を見ると、やっぱり二人はとても絵になり、お似合いだとすら思えた。
(あの席だけキラキラ度が違う……)
私はキラキラと輝く席を後にし、トイレへと急ぐのだった。
「……意外でしたわ」
「え?」
「アルバートさんが家の事を盾にして助けて下さったこと」
「ああ。無我夢中でね」
「『メア』だから、ではなくて?」
「………」
「どうなんですの?」
「……メアは、クライヴと付き合っているし、そんなんじゃないよ」
「まるでメアがクライヴさんと付き合っていなければ、って言ってるようなものですわ」
「……難しいことを言うなぁ」
「まあ、私としてはメアに好意を寄せる殿方が何人いても嬉しいの。だから貴方がもしそうなら、クライヴさんとは別に応援してもよくってよ」
「ははっ。それは頼もしいなぁ」
「ただいまー。何の話?」
トイレから帰って来た私に、二人は口を揃えて「秘密」とだけ告げた。
非常に内容が気になるものだが、なんだか二人の仲が深まっているようで、それはそれで嬉しかったのだった。