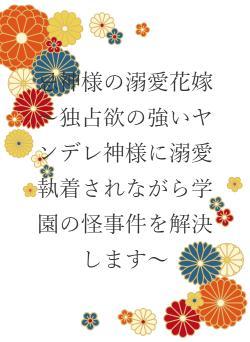『生徒会役員の仕事が入ってしまった。すまないが学園の案内はまた今度になりそうだ。ごめんね。埋め合わせは必ずするから』
お昼休みを告げる鐘の音が鳴る頃、アルバートからそんなメッセージが届いていた。残念そうなスタンプ付きで。
アルバートは何を隠そう生徒会長を務めている。そんな忙しい身であるにも関わらず、私に学園の案内をしてくれようとしたその心持ちだけでありがたい限りだ。
「埋め合わせなんて別にいいのにー」
しかし真面目でプリンスな彼のことだ。きっとちゃんとした埋め合わせをしようとしてくるだろう。
「さてどうしようかな」
私はポツンと図書室の前に立っていた。
アイネは授業のことで先生に相談に行っており、一緒にお昼ができないと連絡が来ていた。
となると一人でお昼を食べなければならないわけだが、転生してきたばかりで、当然お弁当などの類は持ち合わせていないのだ。
「えーと……『マジナイ』って確か購買部あったよね。でもいつも人が殺到してるんだっけ」
お昼の購買部は男子生徒たちによる購入で常に戦場と化している……って描写があったような気がするのだ。
そんなところに女の身で行って果たして生きて帰れるだろうか。
想像して思わず身震いをしていた矢先、私は声をかけられる。
「おい、何してんだ?」
「クライヴ先輩……!」
振り返ればそこには、あくびをしながらこちらへやって来るクライヴの姿があった。
気崩した制服にも関わらず、どことなく品位が溢れているのはさすが王族の人間というべきか。
クライヴの眠たそうな眼は、私と、後ろの図書室を交互に見ていた。
「図書室に行くのか?」
「いえ、それはもう終わったところでして。購買部に行ってみようかと意気込んでいたところです」
「購買部だぁ?」
顔を歪め、呆れているような表情を浮かべるクライヴ。
その顔はつまり、あんだけ男たちで溢れ返った戦場に女の身一つで行く気なのか、と言っているも同然だった。
(やっぱりクライヴからしても危ないところなのか、購買部……)
しかしそうは言っても、食べるものを何も持ち合わせていないわけでして。
そうなるともう、今日のお昼は無しという選択肢しか残っていない。
だが、そんな苦渋の決断をするしかない私に、クライヴから助け船が渡された。
「俺の飯、やるよ」
「へ?」
「いつも家の奴がアホほど作って寄越してくるんだ。いらねーからやる」
なんともまあぶっきらぼうにそんなことを言われ、私はどうすればいいのかわからなくなる。
すると更にクライヴは、人差し指をくいくいと動かし、突いてくるように促してきた。
「ついて来い」
「……?」
言われるがまま、私はクライヴの後を追う。
クライヴは図書室ではなく、その裏手へと周っていく。
そこにはいくつかの木々と小さな庭園が広がっており、私は思わず感嘆の声を上げてしまった。
「う、わぁー素敵」
「ここは人が来ないからな。俺はいつもここで過ごしてる」
「そうなんですか……いいなぁ」
「……べつにおまえも来たけりゃ好きに来ればいい」
「えっ、でも……邪魔になりませんか?」
「おまえが静かにしてればいいだけだ」
クライヴはケラケラと笑いながら、奥の木陰でごろんと横になった。きっとそこが、いつものクライヴの特等席なのだろう。
なんだか秘密の場所を教えてもらえた気分で、私は嬉しくなった。
「それで、クライヴ先輩のご飯は何処に?」
「ああ。もう少しで届けに来る」
なるほど、さすがは王族。従者あたりが届けに来てくれるのか。
などと考えていたら、何やら遠くからドドドドと地響きとクライヴの名を呼ぶ声が近付いてきた。
「え……」
「ほら、来た」
何事かと固まっている私を余所に、クライヴはまたあくびをしながら、のそりと体を起こす。
「クライヴ様ぁあああああああああ!」
「あっ!」
そうして突如として現れた人物を見て、私も思わず声を上げてしまった。
クライヴの従者といえば欠かせないキャラクターがいるではないか。
ステルラ・ダズル。オルニス寮の16歳。
金髪のツンツンの短髪に、星のように輝く黄色の瞳。
170センチの、この世界水準だとやや小柄な体躯をモノともしないほど、声がアホのようにデカい男。
言うまでも無くクライヴを崇拝しており、もともとステルラの家系もクライヴの一族に付き従う従者の一族なのであった。
(声が馬鹿でかいキャラとは聞いていたけど、ホントにうるさい!)
物凄い勢いで登場したステルラは、持っていた包みを大仰な仕草でクライヴへと差し出した。
「クライヴ様、お待たせいたしました! 本日のお昼ご飯でございます!」
「わかったわかった。もう少しボリューム下げろ」
「はいッ!」
何にもわかっていないように、大声で返事をするステルラ。
と、それまでクライヴしか映っていなかったその目に私の姿が入ったのだろう。ステルラは驚愕、といった顔で一度固まり、信じられないといった表情でクライヴの方を向き直した。
「く、く、クライヴ様! こちらの女性は何ですか!?」
「ああ。俺の恋人」
「んなぁッ!?」
あまりにもあっさり衝撃的なことを言われ、ステルラは石化の魔法でも喰らっていたように固まった。
各言う私も、クライヴのその大胆な発言にはいまだに慣れず、つい頬が赤くなってしまう。
(クライヴにとっては偽りの恋人だからそんなあっさり言えるんだろうけどさ……こっちは毎回身が持たないっつーの)
パタパタと顔を扇ぎながら、私は二人の動向を黙って見守ることにした。
案の定、ステルラは餌をねだる鯉のように、パクパクと口を動かし言葉に詰まっている。
「クライヴ様、そんな……城に積まれたお見合い写真がいくつあるかご存知ですか? 同じ王族から名立たる貴族まで、素敵な方がクライヴ様の隣に立ちたいと列を成していらっしゃるというのに……なのにっ!」
「おい。俺が選んだ女にケチつけるのか?」
ギロリ、とクライヴに睨まれ、ステルラは口を閉じて委縮する。
まあ、ステルラの気持ちもわからなくはない。
クライヴはドラゴン族の王子様。それはもう手塩にかけて育てられた、大事な大事な王族の後継者だ。ステルラも従者として、クライヴが英才教育と向き合う努力の様子を見てきたのであろう。
そんなクライヴの隣に立つ女性が、先日転入してきた文字通り身の程もわからない女では文句の一つも言いたくなるといったものだ。
(図書室で絡んできた奴らはむかつくけど、ステルラに言われるのはなんか納得してしまうなぁ)
それだけステルラがクライヴを崇拝しており、それに見合うだけ従者として頑張っているのを知っているからである。
だから私は嫌な顔一つせず、むしろ温かい目でステルラを見つめていた。
「ステルラ。用が済んだなら行け」
「は、はい。失礼しました」
言って、ステルラはクライヴに頭を下げそそくさと去って行く。
もちろん去り際に、私のことを睨みつけるのを忘れずに。
なんだか嵐が去った後のような静けさで、思わず笑ってしまった。
「クライヴ先輩。私、先輩に見合う女性になるようもう少し頑張りますね」
思ったことを口にしただけなのだが、クライヴは少し驚いた表情を浮かべた後、ゆっくりと私の方へと近寄って来た。
端正な顔を私に近付け、その強い眼差しで私を射抜く。
「ステルラの態度か? それとも……誰かに何か言われたのか?」
鋭い。実際その通りだ。
ステルラはともかく、図書室での一件は私なりに響いていた。だから自分でももっと頑張ろうと思って言葉にしてみたのだが……クライヴには全てお見通しのような気がした。
「えっと、まあ、その……偽りの恋人でも、やっぱり隣に立つからにはもう少しクライヴ先輩に相応しい女になった方がいいかな、と」
「………」
「なんて、思ったり、して」
気まずい沈黙。
私としては決意表明をしただけなのだが、何故だかクライヴの表情は不機嫌で、それが余計に気まずさを増長させている。
何か怒らせるようなことを言ってしまっただろうかと不安になっていたら、スッとクライヴの手が私の頬に添えられた。
「おまえは、そのままでいい」
「えっ……」
「俺のために変わる必要なんてねぇよ。そのままでいい」
それはたぶん偽りの恋人だからだ、と思いつつも、あまりにも真剣に私を射抜くクライヴの瞳に、思わずドキドキと胸が高鳴ってしまった。
「おまえに何か言う奴は全員俺が締めてやるから言え」
「ひえっ」
「それとも……」
そこでクライヴは、一旦言葉を詰まらせた。
一度目を反らし、何か言いにくそうにしつつも、もう一度私の方を見て言葉を続けた。
「もしおまえが嫌なら……」
「………」
「恋人役を辞めても……」
「嫌じゃないです」
「……!」
「私、クライヴ先輩の恋人役、全然嫌じゃないんで!」
自然とハッキリそう告げていた。
言った後で、自分が思っていた以上にクライヴの恋人役にプライドを持っていることに気が付いた。だからこそ図書室で馬鹿にされた時に悔しかったのだと、改めて気付かされる。
「……そうか」
しばし黙っていたクライヴが、ホッとしたような物言いと共に微笑した。
その王子様スマイルに、思わず私はときめいてしまう。顔のイイ男の微笑みは何度見たってイイものだ。
「よし、飯にするか」
「はーい!」
言ってクライヴは、ステルラが持ってきた包みを開ける。
そこには三段ものお重が入っており、どの段にもみっちり豪華なおかずと主食が入れられていた。
こんなおせちみたいなものを毎日食べているのであろうクライヴに、さすが王族だなぁなどと変に感心してしまう。
「ホントにこんな豪華なもの頂いていいんですか?」
「ああ。好きなだけ食えよ」
「じゃあ……いっただきまーす!」
お言葉に甘え、私は端から端まで気になるものに手を付けては、美味しい美味しいと喜んで食べ続けた。
そんな私を見るクライヴの目が、どこか優しいことに、食べることに夢中な私は全然気付いていないのだった。
お昼休みを告げる鐘の音が鳴る頃、アルバートからそんなメッセージが届いていた。残念そうなスタンプ付きで。
アルバートは何を隠そう生徒会長を務めている。そんな忙しい身であるにも関わらず、私に学園の案内をしてくれようとしたその心持ちだけでありがたい限りだ。
「埋め合わせなんて別にいいのにー」
しかし真面目でプリンスな彼のことだ。きっとちゃんとした埋め合わせをしようとしてくるだろう。
「さてどうしようかな」
私はポツンと図書室の前に立っていた。
アイネは授業のことで先生に相談に行っており、一緒にお昼ができないと連絡が来ていた。
となると一人でお昼を食べなければならないわけだが、転生してきたばかりで、当然お弁当などの類は持ち合わせていないのだ。
「えーと……『マジナイ』って確か購買部あったよね。でもいつも人が殺到してるんだっけ」
お昼の購買部は男子生徒たちによる購入で常に戦場と化している……って描写があったような気がするのだ。
そんなところに女の身で行って果たして生きて帰れるだろうか。
想像して思わず身震いをしていた矢先、私は声をかけられる。
「おい、何してんだ?」
「クライヴ先輩……!」
振り返ればそこには、あくびをしながらこちらへやって来るクライヴの姿があった。
気崩した制服にも関わらず、どことなく品位が溢れているのはさすが王族の人間というべきか。
クライヴの眠たそうな眼は、私と、後ろの図書室を交互に見ていた。
「図書室に行くのか?」
「いえ、それはもう終わったところでして。購買部に行ってみようかと意気込んでいたところです」
「購買部だぁ?」
顔を歪め、呆れているような表情を浮かべるクライヴ。
その顔はつまり、あんだけ男たちで溢れ返った戦場に女の身一つで行く気なのか、と言っているも同然だった。
(やっぱりクライヴからしても危ないところなのか、購買部……)
しかしそうは言っても、食べるものを何も持ち合わせていないわけでして。
そうなるともう、今日のお昼は無しという選択肢しか残っていない。
だが、そんな苦渋の決断をするしかない私に、クライヴから助け船が渡された。
「俺の飯、やるよ」
「へ?」
「いつも家の奴がアホほど作って寄越してくるんだ。いらねーからやる」
なんともまあぶっきらぼうにそんなことを言われ、私はどうすればいいのかわからなくなる。
すると更にクライヴは、人差し指をくいくいと動かし、突いてくるように促してきた。
「ついて来い」
「……?」
言われるがまま、私はクライヴの後を追う。
クライヴは図書室ではなく、その裏手へと周っていく。
そこにはいくつかの木々と小さな庭園が広がっており、私は思わず感嘆の声を上げてしまった。
「う、わぁー素敵」
「ここは人が来ないからな。俺はいつもここで過ごしてる」
「そうなんですか……いいなぁ」
「……べつにおまえも来たけりゃ好きに来ればいい」
「えっ、でも……邪魔になりませんか?」
「おまえが静かにしてればいいだけだ」
クライヴはケラケラと笑いながら、奥の木陰でごろんと横になった。きっとそこが、いつものクライヴの特等席なのだろう。
なんだか秘密の場所を教えてもらえた気分で、私は嬉しくなった。
「それで、クライヴ先輩のご飯は何処に?」
「ああ。もう少しで届けに来る」
なるほど、さすがは王族。従者あたりが届けに来てくれるのか。
などと考えていたら、何やら遠くからドドドドと地響きとクライヴの名を呼ぶ声が近付いてきた。
「え……」
「ほら、来た」
何事かと固まっている私を余所に、クライヴはまたあくびをしながら、のそりと体を起こす。
「クライヴ様ぁあああああああああ!」
「あっ!」
そうして突如として現れた人物を見て、私も思わず声を上げてしまった。
クライヴの従者といえば欠かせないキャラクターがいるではないか。
ステルラ・ダズル。オルニス寮の16歳。
金髪のツンツンの短髪に、星のように輝く黄色の瞳。
170センチの、この世界水準だとやや小柄な体躯をモノともしないほど、声がアホのようにデカい男。
言うまでも無くクライヴを崇拝しており、もともとステルラの家系もクライヴの一族に付き従う従者の一族なのであった。
(声が馬鹿でかいキャラとは聞いていたけど、ホントにうるさい!)
物凄い勢いで登場したステルラは、持っていた包みを大仰な仕草でクライヴへと差し出した。
「クライヴ様、お待たせいたしました! 本日のお昼ご飯でございます!」
「わかったわかった。もう少しボリューム下げろ」
「はいッ!」
何にもわかっていないように、大声で返事をするステルラ。
と、それまでクライヴしか映っていなかったその目に私の姿が入ったのだろう。ステルラは驚愕、といった顔で一度固まり、信じられないといった表情でクライヴの方を向き直した。
「く、く、クライヴ様! こちらの女性は何ですか!?」
「ああ。俺の恋人」
「んなぁッ!?」
あまりにもあっさり衝撃的なことを言われ、ステルラは石化の魔法でも喰らっていたように固まった。
各言う私も、クライヴのその大胆な発言にはいまだに慣れず、つい頬が赤くなってしまう。
(クライヴにとっては偽りの恋人だからそんなあっさり言えるんだろうけどさ……こっちは毎回身が持たないっつーの)
パタパタと顔を扇ぎながら、私は二人の動向を黙って見守ることにした。
案の定、ステルラは餌をねだる鯉のように、パクパクと口を動かし言葉に詰まっている。
「クライヴ様、そんな……城に積まれたお見合い写真がいくつあるかご存知ですか? 同じ王族から名立たる貴族まで、素敵な方がクライヴ様の隣に立ちたいと列を成していらっしゃるというのに……なのにっ!」
「おい。俺が選んだ女にケチつけるのか?」
ギロリ、とクライヴに睨まれ、ステルラは口を閉じて委縮する。
まあ、ステルラの気持ちもわからなくはない。
クライヴはドラゴン族の王子様。それはもう手塩にかけて育てられた、大事な大事な王族の後継者だ。ステルラも従者として、クライヴが英才教育と向き合う努力の様子を見てきたのであろう。
そんなクライヴの隣に立つ女性が、先日転入してきた文字通り身の程もわからない女では文句の一つも言いたくなるといったものだ。
(図書室で絡んできた奴らはむかつくけど、ステルラに言われるのはなんか納得してしまうなぁ)
それだけステルラがクライヴを崇拝しており、それに見合うだけ従者として頑張っているのを知っているからである。
だから私は嫌な顔一つせず、むしろ温かい目でステルラを見つめていた。
「ステルラ。用が済んだなら行け」
「は、はい。失礼しました」
言って、ステルラはクライヴに頭を下げそそくさと去って行く。
もちろん去り際に、私のことを睨みつけるのを忘れずに。
なんだか嵐が去った後のような静けさで、思わず笑ってしまった。
「クライヴ先輩。私、先輩に見合う女性になるようもう少し頑張りますね」
思ったことを口にしただけなのだが、クライヴは少し驚いた表情を浮かべた後、ゆっくりと私の方へと近寄って来た。
端正な顔を私に近付け、その強い眼差しで私を射抜く。
「ステルラの態度か? それとも……誰かに何か言われたのか?」
鋭い。実際その通りだ。
ステルラはともかく、図書室での一件は私なりに響いていた。だから自分でももっと頑張ろうと思って言葉にしてみたのだが……クライヴには全てお見通しのような気がした。
「えっと、まあ、その……偽りの恋人でも、やっぱり隣に立つからにはもう少しクライヴ先輩に相応しい女になった方がいいかな、と」
「………」
「なんて、思ったり、して」
気まずい沈黙。
私としては決意表明をしただけなのだが、何故だかクライヴの表情は不機嫌で、それが余計に気まずさを増長させている。
何か怒らせるようなことを言ってしまっただろうかと不安になっていたら、スッとクライヴの手が私の頬に添えられた。
「おまえは、そのままでいい」
「えっ……」
「俺のために変わる必要なんてねぇよ。そのままでいい」
それはたぶん偽りの恋人だからだ、と思いつつも、あまりにも真剣に私を射抜くクライヴの瞳に、思わずドキドキと胸が高鳴ってしまった。
「おまえに何か言う奴は全員俺が締めてやるから言え」
「ひえっ」
「それとも……」
そこでクライヴは、一旦言葉を詰まらせた。
一度目を反らし、何か言いにくそうにしつつも、もう一度私の方を見て言葉を続けた。
「もしおまえが嫌なら……」
「………」
「恋人役を辞めても……」
「嫌じゃないです」
「……!」
「私、クライヴ先輩の恋人役、全然嫌じゃないんで!」
自然とハッキリそう告げていた。
言った後で、自分が思っていた以上にクライヴの恋人役にプライドを持っていることに気が付いた。だからこそ図書室で馬鹿にされた時に悔しかったのだと、改めて気付かされる。
「……そうか」
しばし黙っていたクライヴが、ホッとしたような物言いと共に微笑した。
その王子様スマイルに、思わず私はときめいてしまう。顔のイイ男の微笑みは何度見たってイイものだ。
「よし、飯にするか」
「はーい!」
言ってクライヴは、ステルラが持ってきた包みを開ける。
そこには三段ものお重が入っており、どの段にもみっちり豪華なおかずと主食が入れられていた。
こんなおせちみたいなものを毎日食べているのであろうクライヴに、さすが王族だなぁなどと変に感心してしまう。
「ホントにこんな豪華なもの頂いていいんですか?」
「ああ。好きなだけ食えよ」
「じゃあ……いっただきまーす!」
お言葉に甘え、私は端から端まで気になるものに手を付けては、美味しい美味しいと喜んで食べ続けた。
そんな私を見るクライヴの目が、どこか優しいことに、食べることに夢中な私は全然気付いていないのだった。