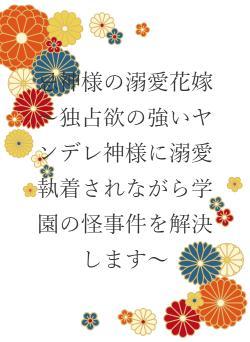バシャンッという音に続いてやってきたのは冷たいという感覚。
気付けば私は小さな噴水の中で尻餅をついていた。
(は? え? 何……?)
状況が読み込めない私は、必死に頭をフル回転させる。
確かクソ上司から仕事を増やされて、さっきまで残業を終えて帰るところだったはず。
……いいや違う。
私の背筋がぞくりと震えた。
そうだ私、青信号なのにも関わらず突っ込んできたトラックにひかれて……
「私、死んだの……? っていうか冷たい!」
いつまでも水に浸かっている必要も無く、私は急いで噴水から出た。
濡れてしまった服を見ると、黒を基調としたブレザーとスカートが目に入る。
「この服、何処かで見たことがあるような……」
言いながら辺りを見渡してみる。
どうやら自分は庭のような場所にいるらしく、剪定された庭木やおしゃれなベンチが並んでいる。
誰か、この状況を説明できる人はいないだろうか。誰でもいい。
そう思って歩き出した私は、近くの大木に寄りかかる男の人の存在に気が付いた。
「あ、あの……!」
意を決し、声をかけてみる。
こんなびしょ濡れの女、不審者でしかないかもしれないが、今は四の五の言ってられない。
「あぁ?」
男からの返答は不機嫌そのものだった。
面倒臭そうに男はこちらを見て、立ち上がる。
肩に付くぐらいのワインレッド色の赤髪を後ろで一つにくくり、気だるそうながらも鋭い金色の瞳をこちらに向けるその男を見た瞬間、私は目を見開いて反射的に口を開いた。
「く、クライヴ・ド・ラゴーネ!?」
言って、しまった、と口元を手で塞ぐ。
しかし時すでに遅し。
男は非常にこちらを怪しんだ表情で、更に不機嫌そうに口角を下げた。
「なんでいきなり俺の名前を呼び捨てにしてんだ」
「あ、あ、いえ、あの、すみません、つい」
「そーいやおまえ、この間転入生って紹介されていた奴か。名前は確か……メア・モノクロイド」
「転入生……メア・モノクロイド……!?」
男――クライヴの言葉で、私はどんどん顔を青くさせていく。
だって、何故ならここは……
(私、『マジナイ』の世界に来ちゃってる!?)
『マジナイ』とは、正式名称『マジカルナイトメア ~魔法学園のときめきラブロマンス~』という乙女ゲームのことだ。
豪華な声優と美麗なイラスト、そして胸に刺さるストーリーも相まって、人気絶頂の乙女ゲームとして名を馳せている『マジナイ』。グッズやメディア展開も幅広く、乙女ゲームに興味が無い人も手を出すほどの人気っぷりだった。
私もガッツリハマった側で、メインストーリーとサブストーリーはもちろん、イベントで実装されるガチャ要素にいくらつぎ込んだことやら。そのお陰でときめきカードと特殊スチルのほとんどを集められたんだけどね。
いや、とにかく。
どうりでこの服を見たことがある気がしたんだ。
この服は『マジナイ』の女子の制服なのだ。
それにメア・モノクロイドとは『マジナイ』のデフォルトネームである。
まさか私がメア自身になっているなんて……!
そして――
(そして目の間にいるこの人……本当に本物のクライヴなんだ……)
改めて私は、目の前の彼をまじまじと見つめ返す。
彼はドラゴン族の第一王子で、俺様気質でナチュラル王族体質。
スポーツを得意としており運動神経も抜群。
生まれつき魔力も高い反面、魔法史の授業は面倒臭がっている。でも頭もいい。
その圧のある体格と180センチ越えの背丈、そして少しのことじゃ物怖じしない態度から、カリスマがあると男子たちからの人気も高い。
(私の推しじゃないけど、顔も声もやっぱりイイ……!)
「おい。何ジロジロ見てる」
「あ、いえ、お気になさらず」
「っつーかなんんでそんなずぶ濡れなんだ?」
「はっ!」
色々と衝撃なことが起こり過ぎていて、自分がずぶ濡れなことをすっかり忘れていた。
改めて濡れていることを意識すると、だんだん肌寒くもなってきた。
「す、すみません。服を乾かす魔法なんてものは……」
「………」
「な、ないですかね?」
まるで役人にこびへつらう平民のように手を合わせてみるが、クライヴの目は冷ややかだ。
今度はクライヴの方がジロジロと私の方を見ている。
(ああ~、ここで出会うのがクライヴだったのが運が無い~。もしもプリンスで名高いアルバートや、私の推しのネイトだったらまた話が違ってきたのに~)
私は頭を抱えながら地団太を踏む。
さてどうしたものか。
そもそも今はメインストーリーでいうどこらへんなんだろうか。
などなど、考えることが山積みの私の脳に、クライヴの声が割り込む。
「おい」
「え、は、はい?」
「おまえ、付き合ってる奴いるか?」
「はい!?」
「うるせぇな。いるのかいないのか訊いてんだ」
「いやあの、いません、けど」
付き合うも何も今はそれどころではないのだ。
しかし人の気も知らず、クライヴはにやりと口角を上げた。
それでもサマになっているのだから、イケメンずるいと心の中で唱えてしまう。
「おまえ、俺の恋人になれ」
「……は?」
「偽りのな」
「……は?」
何を言われているのか全く理解ができない。
きっと私は相当なアホ面を浮かべていたのだろう。クライヴが噴き出していた。
気付けば私は小さな噴水の中で尻餅をついていた。
(は? え? 何……?)
状況が読み込めない私は、必死に頭をフル回転させる。
確かクソ上司から仕事を増やされて、さっきまで残業を終えて帰るところだったはず。
……いいや違う。
私の背筋がぞくりと震えた。
そうだ私、青信号なのにも関わらず突っ込んできたトラックにひかれて……
「私、死んだの……? っていうか冷たい!」
いつまでも水に浸かっている必要も無く、私は急いで噴水から出た。
濡れてしまった服を見ると、黒を基調としたブレザーとスカートが目に入る。
「この服、何処かで見たことがあるような……」
言いながら辺りを見渡してみる。
どうやら自分は庭のような場所にいるらしく、剪定された庭木やおしゃれなベンチが並んでいる。
誰か、この状況を説明できる人はいないだろうか。誰でもいい。
そう思って歩き出した私は、近くの大木に寄りかかる男の人の存在に気が付いた。
「あ、あの……!」
意を決し、声をかけてみる。
こんなびしょ濡れの女、不審者でしかないかもしれないが、今は四の五の言ってられない。
「あぁ?」
男からの返答は不機嫌そのものだった。
面倒臭そうに男はこちらを見て、立ち上がる。
肩に付くぐらいのワインレッド色の赤髪を後ろで一つにくくり、気だるそうながらも鋭い金色の瞳をこちらに向けるその男を見た瞬間、私は目を見開いて反射的に口を開いた。
「く、クライヴ・ド・ラゴーネ!?」
言って、しまった、と口元を手で塞ぐ。
しかし時すでに遅し。
男は非常にこちらを怪しんだ表情で、更に不機嫌そうに口角を下げた。
「なんでいきなり俺の名前を呼び捨てにしてんだ」
「あ、あ、いえ、あの、すみません、つい」
「そーいやおまえ、この間転入生って紹介されていた奴か。名前は確か……メア・モノクロイド」
「転入生……メア・モノクロイド……!?」
男――クライヴの言葉で、私はどんどん顔を青くさせていく。
だって、何故ならここは……
(私、『マジナイ』の世界に来ちゃってる!?)
『マジナイ』とは、正式名称『マジカルナイトメア ~魔法学園のときめきラブロマンス~』という乙女ゲームのことだ。
豪華な声優と美麗なイラスト、そして胸に刺さるストーリーも相まって、人気絶頂の乙女ゲームとして名を馳せている『マジナイ』。グッズやメディア展開も幅広く、乙女ゲームに興味が無い人も手を出すほどの人気っぷりだった。
私もガッツリハマった側で、メインストーリーとサブストーリーはもちろん、イベントで実装されるガチャ要素にいくらつぎ込んだことやら。そのお陰でときめきカードと特殊スチルのほとんどを集められたんだけどね。
いや、とにかく。
どうりでこの服を見たことがある気がしたんだ。
この服は『マジナイ』の女子の制服なのだ。
それにメア・モノクロイドとは『マジナイ』のデフォルトネームである。
まさか私がメア自身になっているなんて……!
そして――
(そして目の間にいるこの人……本当に本物のクライヴなんだ……)
改めて私は、目の前の彼をまじまじと見つめ返す。
彼はドラゴン族の第一王子で、俺様気質でナチュラル王族体質。
スポーツを得意としており運動神経も抜群。
生まれつき魔力も高い反面、魔法史の授業は面倒臭がっている。でも頭もいい。
その圧のある体格と180センチ越えの背丈、そして少しのことじゃ物怖じしない態度から、カリスマがあると男子たちからの人気も高い。
(私の推しじゃないけど、顔も声もやっぱりイイ……!)
「おい。何ジロジロ見てる」
「あ、いえ、お気になさらず」
「っつーかなんんでそんなずぶ濡れなんだ?」
「はっ!」
色々と衝撃なことが起こり過ぎていて、自分がずぶ濡れなことをすっかり忘れていた。
改めて濡れていることを意識すると、だんだん肌寒くもなってきた。
「す、すみません。服を乾かす魔法なんてものは……」
「………」
「な、ないですかね?」
まるで役人にこびへつらう平民のように手を合わせてみるが、クライヴの目は冷ややかだ。
今度はクライヴの方がジロジロと私の方を見ている。
(ああ~、ここで出会うのがクライヴだったのが運が無い~。もしもプリンスで名高いアルバートや、私の推しのネイトだったらまた話が違ってきたのに~)
私は頭を抱えながら地団太を踏む。
さてどうしたものか。
そもそも今はメインストーリーでいうどこらへんなんだろうか。
などなど、考えることが山積みの私の脳に、クライヴの声が割り込む。
「おい」
「え、は、はい?」
「おまえ、付き合ってる奴いるか?」
「はい!?」
「うるせぇな。いるのかいないのか訊いてんだ」
「いやあの、いません、けど」
付き合うも何も今はそれどころではないのだ。
しかし人の気も知らず、クライヴはにやりと口角を上げた。
それでもサマになっているのだから、イケメンずるいと心の中で唱えてしまう。
「おまえ、俺の恋人になれ」
「……は?」
「偽りのな」
「……は?」
何を言われているのか全く理解ができない。
きっと私は相当なアホ面を浮かべていたのだろう。クライヴが噴き出していた。