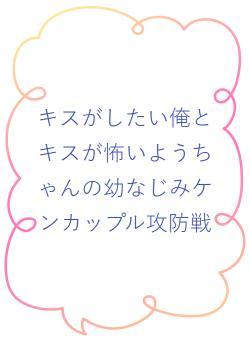顔をぺたぺたと触られているような感触がして目が覚めた。霞がかった視界が徐々にクリアになっていく。目の前に九条が現れて俺の頬をゆっくりと撫でていた。
「あ、春樹おはよ」
ゆっくりと上半身を起こして周りを見回す。俺はでっかいベッドに寝ていて、その傍らに九条が座っている。照明は薄暗く、少し埃っぽい匂いがした。部屋の中には小さいテーブルとソファ、大きなテレビ、窓はあるけどなにかが張り付けてあるのか外はみえないようになっている。もしかしてこの場所は…
「ラブホ?」
「そうそう。飲食店だと匂いが気になるかなと思って。カラオケやネカフェは遠いしビジホは入りにくくて」
そういえば入る前に、ラブホでいい? と九条から聞かれた気がする。
「…ラブホのが入りにくいだろ。男同士だし」
「受付とかないし、誰にも会わないからいいかなって」
「まぁ、確かに…。俺どんくらい寝てた?」
「たぶん30分くらいかな~」
「マジか…」
わざわざここまで俺を連れてきてくれて寝かせてくれたんだと思うと申し訳ない。九条にごめんとありがとうを伝えたら今度倍返ししてくれたらいいよと笑っていて、某ドラマの有名なセリフが頭に浮かんだ。
「これさ、ここいじったら照明とか変えれるし音楽も流せるんだよ。すごくない?」
ベットサイドのパネルをいじって照明を明るくしたり、BGMの有線のチャンネルを変えて遊んでいる。
「タブレットで食べ物注文できるんだって!カラオケもあるしゲームもあるし、俺ここに住もうかな?」
初めて来たときは俺もはしゃいでたな~と無邪気な九条を微笑ましくみていると、九条がテレビのリモコンを手に取った。
「あ!」
やばいと思った時にはもう手遅れで、大画面に裸の女の人が映し出され甲高い嬌声が部屋中に響いている。九条は口を開けたまま固まってしまい、俺は九条の手からリモコンを奪いすぐにテレビを消した。
「…びっくりしたー……そっか、ラブホだからこういうのがあるんだ…」
「俺も初めて来たときやらかしてちょっと気まずくなった。まさかテレビからあんなの流れてくるとか思わないじゃん」
気まずさを和らげようとしたのに裏目に出たのか、なぜか九条は黙ってしまった。あれ?余計に気まずくなった?
「腹へってない?なんか食べる?」
タブレットに手を伸ばしメニューをみていると、九条がベッドに上がり俺の正面に座った。
「誰と来たの?さっき雑貨屋で会った子?」
「いや、あいつとはすぐわかれたから…」
「誰?俺の知らない子?」
「なんだよ、なんか怖いんだけど」
いつになく真剣な顔でまっすぐにみつめてくる。いつも笑っている九条にこんな顔をされたら、胸がざわざわして落ち着かない。なにも悪いことをしていないのに責められている気分だ。九条の視線に抗うことをあきらめてため息をつき、ベッドサイドにタブレットを戻した。
「他校の女子、年上だったかな。2年の時に逆ナンされてラブホいって、それっきり会ってない」
「ふ~ん…他には?」
「え?」
「それだけじゃないよね?」
口元は笑ってるけど目が笑ってない。尋問されてるみたいだ。こえーよ、なんなんだよ。
「…去年の夏休みに、女子大生と…」
まだじっとみてくるので、この2回だけだと付け足すと、ふ~んとまだ納得していない様子で俺の左手を取る。
「この子とはより戻すの?」
手の平に書かれた市原華のアカウントを指さしている。
「より戻す気ならちゃんと連絡先交換するだろ」
ポケットからスマホを取り出してみせると、持ってたんだと眉を下げて笑った。
「じゃあこれは必要ないから消すね?」
俺の返事を待たずにベッドサイドにあるウェットティッシュに手を伸ばし、それで俺の手の平を拭き始めた。
「…初めて付き合った子でさ、めちゃくちゃ好きだったんだけど、二股された挙句すぐにふられた」
「えぐいね…もしかして、それ以来誰とも付き合ってないとか?」
「え?」
「他校の女子と女子大生だっけ?さっきの口ぶりからして、この二人とは付き合ってはないんだろうなって思ったから」
「当たり……ださいよな。傷つきたくなくて避けてたらいつの間にかまともに恋愛できなくなってた」
「ださくない…ださくないけど、」
ずっと俺の手の平をみていた九条が、顔を上げて真っすぐに俺を見据える。
「そろそろこっち側に戻ってきてもいいんじゃない?」
九条が拭いてくれた手の平、書かれていた文字は消えて、少し赤くなっていた。
「ねっ?」
(やばい、なんで泣きそうになってんだよ…)
九条が、あまりにも優しい顔で穏やかに笑うから、きゅっと胸が苦しくなった。
「あ、春樹おはよ」
ゆっくりと上半身を起こして周りを見回す。俺はでっかいベッドに寝ていて、その傍らに九条が座っている。照明は薄暗く、少し埃っぽい匂いがした。部屋の中には小さいテーブルとソファ、大きなテレビ、窓はあるけどなにかが張り付けてあるのか外はみえないようになっている。もしかしてこの場所は…
「ラブホ?」
「そうそう。飲食店だと匂いが気になるかなと思って。カラオケやネカフェは遠いしビジホは入りにくくて」
そういえば入る前に、ラブホでいい? と九条から聞かれた気がする。
「…ラブホのが入りにくいだろ。男同士だし」
「受付とかないし、誰にも会わないからいいかなって」
「まぁ、確かに…。俺どんくらい寝てた?」
「たぶん30分くらいかな~」
「マジか…」
わざわざここまで俺を連れてきてくれて寝かせてくれたんだと思うと申し訳ない。九条にごめんとありがとうを伝えたら今度倍返ししてくれたらいいよと笑っていて、某ドラマの有名なセリフが頭に浮かんだ。
「これさ、ここいじったら照明とか変えれるし音楽も流せるんだよ。すごくない?」
ベットサイドのパネルをいじって照明を明るくしたり、BGMの有線のチャンネルを変えて遊んでいる。
「タブレットで食べ物注文できるんだって!カラオケもあるしゲームもあるし、俺ここに住もうかな?」
初めて来たときは俺もはしゃいでたな~と無邪気な九条を微笑ましくみていると、九条がテレビのリモコンを手に取った。
「あ!」
やばいと思った時にはもう手遅れで、大画面に裸の女の人が映し出され甲高い嬌声が部屋中に響いている。九条は口を開けたまま固まってしまい、俺は九条の手からリモコンを奪いすぐにテレビを消した。
「…びっくりしたー……そっか、ラブホだからこういうのがあるんだ…」
「俺も初めて来たときやらかしてちょっと気まずくなった。まさかテレビからあんなの流れてくるとか思わないじゃん」
気まずさを和らげようとしたのに裏目に出たのか、なぜか九条は黙ってしまった。あれ?余計に気まずくなった?
「腹へってない?なんか食べる?」
タブレットに手を伸ばしメニューをみていると、九条がベッドに上がり俺の正面に座った。
「誰と来たの?さっき雑貨屋で会った子?」
「いや、あいつとはすぐわかれたから…」
「誰?俺の知らない子?」
「なんだよ、なんか怖いんだけど」
いつになく真剣な顔でまっすぐにみつめてくる。いつも笑っている九条にこんな顔をされたら、胸がざわざわして落ち着かない。なにも悪いことをしていないのに責められている気分だ。九条の視線に抗うことをあきらめてため息をつき、ベッドサイドにタブレットを戻した。
「他校の女子、年上だったかな。2年の時に逆ナンされてラブホいって、それっきり会ってない」
「ふ~ん…他には?」
「え?」
「それだけじゃないよね?」
口元は笑ってるけど目が笑ってない。尋問されてるみたいだ。こえーよ、なんなんだよ。
「…去年の夏休みに、女子大生と…」
まだじっとみてくるので、この2回だけだと付け足すと、ふ~んとまだ納得していない様子で俺の左手を取る。
「この子とはより戻すの?」
手の平に書かれた市原華のアカウントを指さしている。
「より戻す気ならちゃんと連絡先交換するだろ」
ポケットからスマホを取り出してみせると、持ってたんだと眉を下げて笑った。
「じゃあこれは必要ないから消すね?」
俺の返事を待たずにベッドサイドにあるウェットティッシュに手を伸ばし、それで俺の手の平を拭き始めた。
「…初めて付き合った子でさ、めちゃくちゃ好きだったんだけど、二股された挙句すぐにふられた」
「えぐいね…もしかして、それ以来誰とも付き合ってないとか?」
「え?」
「他校の女子と女子大生だっけ?さっきの口ぶりからして、この二人とは付き合ってはないんだろうなって思ったから」
「当たり……ださいよな。傷つきたくなくて避けてたらいつの間にかまともに恋愛できなくなってた」
「ださくない…ださくないけど、」
ずっと俺の手の平をみていた九条が、顔を上げて真っすぐに俺を見据える。
「そろそろこっち側に戻ってきてもいいんじゃない?」
九条が拭いてくれた手の平、書かれていた文字は消えて、少し赤くなっていた。
「ねっ?」
(やばい、なんで泣きそうになってんだよ…)
九条が、あまりにも優しい顔で穏やかに笑うから、きゅっと胸が苦しくなった。