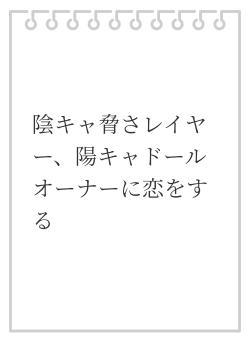とある国にゴリラ伯爵と言う男がいた。伯爵はその名の通り体が大きく、馬に乗れば直ぐに疲れさせてしまう。伯爵が走ったかと思えば領民は地震かと勘違いし、剣を振れば風圧で木が倒れてしまう。男から見ればとても憧れる人物だ。しかし、女からは怖がられていた。そう、伯爵は女にモテないのだ。今まで手紙を書き、紙と言う資源をどれくらい無駄にしたのか考えるだけ空しくなるほどであった。
「うぃーのめのめぇ!」
伯爵の屋敷では毎晩の様に友人の貴族を集め、どんちゃん騒ぎをしていた。使用人達は忙しくパタパタと走り回っていた。
「お酒、お持ちしました」
「旦那様。屋敷の点検の結果、三階のバルコニーの手すりが劣化しております」
「旦那様。こちらの書類、明日まで目を通していただきませんと!」
「旦那様。ルーク男爵がいらっしゃいました。お通ししてもよろしいでしょうか?」
「構わん、通せ通せ!」
ルーク男爵が部屋に入ると伯爵に挨拶もそこそこに隅にある椅子に座り、外を眺める。伯爵は気にせず談笑していた。
「伯爵。俺、婚約したんですよ! お祝いしてくださいよぉ」
酔った一人の貴族が伯爵に絡んだ。その時、伯爵が凍った。
「なんだと……? ちょっと待て? では俺だけか? 女の気配がないのは」
話題を出した貴族は、はっと口を押えたが吐いた言葉は戻らない。他の貴族が慌ててフォローする。
「伯爵は逞しく、優しいですから! 大丈夫です! 今はご縁がないだけです!」
「「「そーだ! そーだ!」」」
その場にいる貴族達は同調した。
「いや、まてよ? 女の気配がないのは……」
また貴族の一人が余計な事を言う。皆ルーク男爵に視線を移した。
「ばか、あいつは女の気配がないんじゃない。決まった女がいないだけだ」
伯爵は少し考えるとズカズカと男爵に近寄る。男爵は本を読み、寛いでいた。何故か鼻をひくつかせている。クシャミでもするのだろうかと思ったが気にせず声をかけた。
「お寛ぎの所失礼。ルーク男爵」
「くっさ!」
男爵はばねが仕込まれたおもちゃの様に跳ね上がった。
「臭い? 俺が臭いだと?」
「酒臭い」
伯爵は腕やシャツをクンクンと匂いを確認したがいまいちピンと来ないようだった。
「伯爵。僕に何の用でしょうか?」
「お前、先月何通のラブレターを暖炉にくべたんだ?」
あまりにもストレートな問い方にその場にいた者皆ズッコケた。
「伯爵! 心の声が漏れてます!」
「あ、いや、違う。すまん。どうしたら女にモテるんだ?」
男爵は口をポカンと開けたかと思うと、深くため息をついた。
「伯爵が無駄にした資源よりは少ないはずですよ……伯爵。ハッキリ言います。このままではモテるどころか一人の女に愛される事すら無理ですよ。鏡をご覧になったことありますか?」
「毎日見ているぞ」
男爵は近くにいた使用人に大きな鏡を持ってくるように命じた。鏡に伯爵を映し、指摘する。
「まず、何です。この農民みたいな服は」
「農民と共に畑を耕すのはいいぞ」
「貧乏くさく薄汚れた服の男にどんな女が寄り付きますか」
「人は中身だ」
伯爵はそう言うと貴族たちが「そーだ!」と同調した。
「身だしなみを整えてこそ、そう言えるんですよ。次。女代わりと言わんばかりに酒瓶抱いてちゃ嫌に決まってるでしょう? あと酒臭い。香水臭い方が幾分かマシなくらいです」
「あ……」
伯爵は握っていた酒瓶を背中に隠した。男爵はあれやこれやと伯爵のダメな所を指摘した。
「どうしても。と仰るなら最終手段は恩を売ることですね。例えば、困っている女性に恩を売る。余程のアホじゃない限り好きな振りくらいはしてくれますよ。そこから好きになってもらえるようにあの手この手尽くしてみたらいかがです?」
「よし、では恩を売ってくる」
伯爵はドスドスと走り去った。屋敷が心なしか揺れている。一時間ほどすると少女を抱えて戻って来た。
「これは、何です?」
男爵は指を震わせながら少女を指差した。
「死にかけていたから拾ってきた。彼女の家族に暫く困らない程の金貨を渡してきた」
冗談を真に受けるとは……。男爵は冷や汗をかいた。
「お前ら! 男爵以外帰れ帰れ! 今日は解散だ!」
伯爵と男爵とそして伯爵の腕の中で眠る少女が一人。
「僕も帰っていいかな」
本を懐にしまい、立ち上がる男爵。
「男爵は女性の扱いに慣れているだろう? アドバイスをした責任をとってもらおう!」
「冗談だとわかれ! それにこのお嬢さんとの年齢差を考えてください! どう見たって十五歳くらいでしょう?」
「十年もたてば誤差の範囲だ!」
「う……」
伯爵は二十五歳。十年たてば三十五歳。少女、仮に今十五歳だとすると二十五歳。どんぶり勘定過ぎる伯爵に男爵は呆れた。
少女が目を覚ました。
「男爵! どうしたらいい?」
「伯爵! 貴方は何もするな。女の使用人に任せろ! お前はこの子の首を折りかねん」
「お、おう」
伯爵は使用人にすべて任せた。
翌日の夜もまたどんちゃん騒ぎが始まった。伯爵はワザとらしく咳払いをすると
「俺の恋人を紹介しよう」
男爵を除いた貴族たちは歓喜に沸いた。伯爵が目配せするとメイドが扉を開けた。
「エ……エマと申します」
豪華なドレスに身を包んだ少女はぎこちなくお辞儀をした。
「ヒュー! 可愛い!」
「俺の嫁と交換しない?」
「黙れロリコンが! 怖がらせてどうする!」
エマはキョロキョロと辺りを見渡す。男爵を見つけると満面の笑みで歩みを進めた。
「あの、あの……昨日はありがとうございました」
「僕は何もしていないが」
「あの太い腕の中から解放してくださいました」
「苦しそうだったから正直に伯爵に伝えただけ」
「少し、庭で散歩しません?」
「嫌だ。誘うならあっちで泣きそうな表情をしている伯爵にしなよ」
エマは振り返る。涙目の伯爵と目が合う。
「ご、ごめんなさい!」
エマは気まずさを感じ、部屋を飛び出した。
「男爵! エマを泣かすな!」
「好みじゃないから断っただけ。それともそのまま受け入れて伯爵はおひとり様になりたいと?」
「うっ」
「追って慰めるくらいしたらどうですか」
「はっ! 成程。さすが女たらし!」
伯爵は大股で扉に向かおうとした時
「キャー!」
エマの悲鳴が屋敷にこだました。
「上からだ! ……まさか!」
伯爵はドスドスと走り出した。悲鳴がした場所へたどり着くと、エマが崩れたバルコニーにぶら下がっていた。
「今助ける!」
後から追ってきた男爵が伯爵を止めようとした。
「伯爵! 貴方の体重では!」
しかし、時既に遅し、ドスドスと駆け寄った伯爵の体重に耐え切れず、バルコニーは完全に崩れ、エマも一緒に落ちた。大砲の弾が落ちたのかと思わせるほどの大きな音がした。男爵を始め、他の貴族たちは恐る恐る地面を覗き込んだ。
「ぶ、無事ですか?」
男爵は震える声で安否の確認をした。
「無事だ!」
「伯爵ではない。お嬢さんだ」
「気絶しているが、怪我はなさそうだが念のため医者を呼んでくれ」
一同、安堵の表情を浮かべることが出来た。その日、これ以上飲み会を続けるわけには行かず、解散となった。原因の一端を担ってしまった男爵は責任感から伯爵家の使用人達と共に看病をした。
翌朝エマは目を覚ました。部屋には本を片手に男爵が椅子に腰掛けていた。
「あの……」
「お目覚めかい? 今伯爵を呼んでくる」
「貴方と、話がしたいです」
立ち上がった男爵であったが、渋々椅子に腰掛けた。
「何が聞きたいんだ?」
「貴方の事」
「平民のお前さんなんかに頭の良さを期待していないが、まず聞くべきは伯爵の事ではないか?」
「伯爵の事」
エマは仕方なさそうに言うと、男爵はため込んだ感情を吐き出した。
「これからお前にご飯を食べさせてくれるのは伯爵。教育を受けさせてくれるのも伯爵。愛情を注いてくれるのも伯爵。我がまま言ってもいい相手も伯爵。僕の事聞きたいって? 冗談よしてくれ。僕は君なんかに惚れられても困るの。わかった? わかんない? わかったふりで良いからとりあえずわかって」
「いきなりここへ連れてこられてわけわかんない。貴方が一番まともそうで、イケメン」
「もっとペースト状になるくらい噛み砕いて説明してやろう。お前は伯爵の嫁になるために伯爵に買われたんだ。家族に売り飛ばされたんだよ。お前の仕事は伯爵を愛する事。いきなりは難しいと思うし、わけわからないと思うけど、手っ取り早く欲しい物おねだりしてみてもいい。男は気になる女に頼られると嬉しいものだ」
「欲しい物?」
「何かしらあるだろう? ドレスや宝石、豪華な馬車だって何でもいい」
「……貴方と仲良くしたいって願いは聞いてもらえるかしら」
「あぁ、もう。面倒くさいねお前。いいよ。伯爵を愛することが出来たら友達くらいにはなってやる」
「……頑張ってみる」
エマは毛布に潜り込んだ。
「その、伯爵は貴族にしてはちょっと頭が悪いが、根は悪くない。きっと好きになる」
「貴方は伯爵のどんなところが好きなの?」
「孤立じゃなくて孤独を楽しませてくれる」
「だから隅でおひとり様だったのね」
ズシズシ足音とバタンと扉が開く音がした。
「エマ! もう大丈夫か? 声が聞こえたから!」
伯爵は喜びを隠しきれない表情でエマの名を呼んだ。
「じゃ、僕はもう帰るね」
「朝食くらい食べていけ」
「僕は団子より夢だからね。おやすみなさい」
「ダン……? 眠いなら客室の準備をさせるが」
「僕は枕が変わると眠れないの。じゃ、またねー」
男爵は大きくあくびと背伸びをしながら帰った。
「落ち着きのない奴だな……」
「は、伯爵」
「あぁ騒がしくしてすまない。今朝食を運ばせよう」
「あの……! あの!」
「俺が怖いのか?すまない今すぐ出ていく」
エマは混乱していた。家族に売られた。ならばここから追い出されたらまた死にかける。男爵が言った男は頼られると嬉しい。伯爵と仲良くなったら男爵とも仲良くなれる。何か切っ掛けを作らなければ。
「違うんです! 私、ケーキが食べたい!」
エマはしまったと心の中で頭を抱えた。話がかみ合っていない。何を言っているのだろうと
「紅茶は……紅茶はいらないのか? それともコーヒーか?」
伯爵はエマを優しい瞳で見下ろしていた。
「紅茶がいいです!」
その日の午後三時、初めて恋人の真似事が出来た二人であった。
「うぃーのめのめぇ!」
伯爵の屋敷では毎晩の様に友人の貴族を集め、どんちゃん騒ぎをしていた。使用人達は忙しくパタパタと走り回っていた。
「お酒、お持ちしました」
「旦那様。屋敷の点検の結果、三階のバルコニーの手すりが劣化しております」
「旦那様。こちらの書類、明日まで目を通していただきませんと!」
「旦那様。ルーク男爵がいらっしゃいました。お通ししてもよろしいでしょうか?」
「構わん、通せ通せ!」
ルーク男爵が部屋に入ると伯爵に挨拶もそこそこに隅にある椅子に座り、外を眺める。伯爵は気にせず談笑していた。
「伯爵。俺、婚約したんですよ! お祝いしてくださいよぉ」
酔った一人の貴族が伯爵に絡んだ。その時、伯爵が凍った。
「なんだと……? ちょっと待て? では俺だけか? 女の気配がないのは」
話題を出した貴族は、はっと口を押えたが吐いた言葉は戻らない。他の貴族が慌ててフォローする。
「伯爵は逞しく、優しいですから! 大丈夫です! 今はご縁がないだけです!」
「「「そーだ! そーだ!」」」
その場にいる貴族達は同調した。
「いや、まてよ? 女の気配がないのは……」
また貴族の一人が余計な事を言う。皆ルーク男爵に視線を移した。
「ばか、あいつは女の気配がないんじゃない。決まった女がいないだけだ」
伯爵は少し考えるとズカズカと男爵に近寄る。男爵は本を読み、寛いでいた。何故か鼻をひくつかせている。クシャミでもするのだろうかと思ったが気にせず声をかけた。
「お寛ぎの所失礼。ルーク男爵」
「くっさ!」
男爵はばねが仕込まれたおもちゃの様に跳ね上がった。
「臭い? 俺が臭いだと?」
「酒臭い」
伯爵は腕やシャツをクンクンと匂いを確認したがいまいちピンと来ないようだった。
「伯爵。僕に何の用でしょうか?」
「お前、先月何通のラブレターを暖炉にくべたんだ?」
あまりにもストレートな問い方にその場にいた者皆ズッコケた。
「伯爵! 心の声が漏れてます!」
「あ、いや、違う。すまん。どうしたら女にモテるんだ?」
男爵は口をポカンと開けたかと思うと、深くため息をついた。
「伯爵が無駄にした資源よりは少ないはずですよ……伯爵。ハッキリ言います。このままではモテるどころか一人の女に愛される事すら無理ですよ。鏡をご覧になったことありますか?」
「毎日見ているぞ」
男爵は近くにいた使用人に大きな鏡を持ってくるように命じた。鏡に伯爵を映し、指摘する。
「まず、何です。この農民みたいな服は」
「農民と共に畑を耕すのはいいぞ」
「貧乏くさく薄汚れた服の男にどんな女が寄り付きますか」
「人は中身だ」
伯爵はそう言うと貴族たちが「そーだ!」と同調した。
「身だしなみを整えてこそ、そう言えるんですよ。次。女代わりと言わんばかりに酒瓶抱いてちゃ嫌に決まってるでしょう? あと酒臭い。香水臭い方が幾分かマシなくらいです」
「あ……」
伯爵は握っていた酒瓶を背中に隠した。男爵はあれやこれやと伯爵のダメな所を指摘した。
「どうしても。と仰るなら最終手段は恩を売ることですね。例えば、困っている女性に恩を売る。余程のアホじゃない限り好きな振りくらいはしてくれますよ。そこから好きになってもらえるようにあの手この手尽くしてみたらいかがです?」
「よし、では恩を売ってくる」
伯爵はドスドスと走り去った。屋敷が心なしか揺れている。一時間ほどすると少女を抱えて戻って来た。
「これは、何です?」
男爵は指を震わせながら少女を指差した。
「死にかけていたから拾ってきた。彼女の家族に暫く困らない程の金貨を渡してきた」
冗談を真に受けるとは……。男爵は冷や汗をかいた。
「お前ら! 男爵以外帰れ帰れ! 今日は解散だ!」
伯爵と男爵とそして伯爵の腕の中で眠る少女が一人。
「僕も帰っていいかな」
本を懐にしまい、立ち上がる男爵。
「男爵は女性の扱いに慣れているだろう? アドバイスをした責任をとってもらおう!」
「冗談だとわかれ! それにこのお嬢さんとの年齢差を考えてください! どう見たって十五歳くらいでしょう?」
「十年もたてば誤差の範囲だ!」
「う……」
伯爵は二十五歳。十年たてば三十五歳。少女、仮に今十五歳だとすると二十五歳。どんぶり勘定過ぎる伯爵に男爵は呆れた。
少女が目を覚ました。
「男爵! どうしたらいい?」
「伯爵! 貴方は何もするな。女の使用人に任せろ! お前はこの子の首を折りかねん」
「お、おう」
伯爵は使用人にすべて任せた。
翌日の夜もまたどんちゃん騒ぎが始まった。伯爵はワザとらしく咳払いをすると
「俺の恋人を紹介しよう」
男爵を除いた貴族たちは歓喜に沸いた。伯爵が目配せするとメイドが扉を開けた。
「エ……エマと申します」
豪華なドレスに身を包んだ少女はぎこちなくお辞儀をした。
「ヒュー! 可愛い!」
「俺の嫁と交換しない?」
「黙れロリコンが! 怖がらせてどうする!」
エマはキョロキョロと辺りを見渡す。男爵を見つけると満面の笑みで歩みを進めた。
「あの、あの……昨日はありがとうございました」
「僕は何もしていないが」
「あの太い腕の中から解放してくださいました」
「苦しそうだったから正直に伯爵に伝えただけ」
「少し、庭で散歩しません?」
「嫌だ。誘うならあっちで泣きそうな表情をしている伯爵にしなよ」
エマは振り返る。涙目の伯爵と目が合う。
「ご、ごめんなさい!」
エマは気まずさを感じ、部屋を飛び出した。
「男爵! エマを泣かすな!」
「好みじゃないから断っただけ。それともそのまま受け入れて伯爵はおひとり様になりたいと?」
「うっ」
「追って慰めるくらいしたらどうですか」
「はっ! 成程。さすが女たらし!」
伯爵は大股で扉に向かおうとした時
「キャー!」
エマの悲鳴が屋敷にこだました。
「上からだ! ……まさか!」
伯爵はドスドスと走り出した。悲鳴がした場所へたどり着くと、エマが崩れたバルコニーにぶら下がっていた。
「今助ける!」
後から追ってきた男爵が伯爵を止めようとした。
「伯爵! 貴方の体重では!」
しかし、時既に遅し、ドスドスと駆け寄った伯爵の体重に耐え切れず、バルコニーは完全に崩れ、エマも一緒に落ちた。大砲の弾が落ちたのかと思わせるほどの大きな音がした。男爵を始め、他の貴族たちは恐る恐る地面を覗き込んだ。
「ぶ、無事ですか?」
男爵は震える声で安否の確認をした。
「無事だ!」
「伯爵ではない。お嬢さんだ」
「気絶しているが、怪我はなさそうだが念のため医者を呼んでくれ」
一同、安堵の表情を浮かべることが出来た。その日、これ以上飲み会を続けるわけには行かず、解散となった。原因の一端を担ってしまった男爵は責任感から伯爵家の使用人達と共に看病をした。
翌朝エマは目を覚ました。部屋には本を片手に男爵が椅子に腰掛けていた。
「あの……」
「お目覚めかい? 今伯爵を呼んでくる」
「貴方と、話がしたいです」
立ち上がった男爵であったが、渋々椅子に腰掛けた。
「何が聞きたいんだ?」
「貴方の事」
「平民のお前さんなんかに頭の良さを期待していないが、まず聞くべきは伯爵の事ではないか?」
「伯爵の事」
エマは仕方なさそうに言うと、男爵はため込んだ感情を吐き出した。
「これからお前にご飯を食べさせてくれるのは伯爵。教育を受けさせてくれるのも伯爵。愛情を注いてくれるのも伯爵。我がまま言ってもいい相手も伯爵。僕の事聞きたいって? 冗談よしてくれ。僕は君なんかに惚れられても困るの。わかった? わかんない? わかったふりで良いからとりあえずわかって」
「いきなりここへ連れてこられてわけわかんない。貴方が一番まともそうで、イケメン」
「もっとペースト状になるくらい噛み砕いて説明してやろう。お前は伯爵の嫁になるために伯爵に買われたんだ。家族に売り飛ばされたんだよ。お前の仕事は伯爵を愛する事。いきなりは難しいと思うし、わけわからないと思うけど、手っ取り早く欲しい物おねだりしてみてもいい。男は気になる女に頼られると嬉しいものだ」
「欲しい物?」
「何かしらあるだろう? ドレスや宝石、豪華な馬車だって何でもいい」
「……貴方と仲良くしたいって願いは聞いてもらえるかしら」
「あぁ、もう。面倒くさいねお前。いいよ。伯爵を愛することが出来たら友達くらいにはなってやる」
「……頑張ってみる」
エマは毛布に潜り込んだ。
「その、伯爵は貴族にしてはちょっと頭が悪いが、根は悪くない。きっと好きになる」
「貴方は伯爵のどんなところが好きなの?」
「孤立じゃなくて孤独を楽しませてくれる」
「だから隅でおひとり様だったのね」
ズシズシ足音とバタンと扉が開く音がした。
「エマ! もう大丈夫か? 声が聞こえたから!」
伯爵は喜びを隠しきれない表情でエマの名を呼んだ。
「じゃ、僕はもう帰るね」
「朝食くらい食べていけ」
「僕は団子より夢だからね。おやすみなさい」
「ダン……? 眠いなら客室の準備をさせるが」
「僕は枕が変わると眠れないの。じゃ、またねー」
男爵は大きくあくびと背伸びをしながら帰った。
「落ち着きのない奴だな……」
「は、伯爵」
「あぁ騒がしくしてすまない。今朝食を運ばせよう」
「あの……! あの!」
「俺が怖いのか?すまない今すぐ出ていく」
エマは混乱していた。家族に売られた。ならばここから追い出されたらまた死にかける。男爵が言った男は頼られると嬉しい。伯爵と仲良くなったら男爵とも仲良くなれる。何か切っ掛けを作らなければ。
「違うんです! 私、ケーキが食べたい!」
エマはしまったと心の中で頭を抱えた。話がかみ合っていない。何を言っているのだろうと
「紅茶は……紅茶はいらないのか? それともコーヒーか?」
伯爵はエマを優しい瞳で見下ろしていた。
「紅茶がいいです!」
その日の午後三時、初めて恋人の真似事が出来た二人であった。