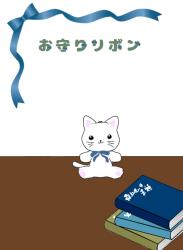雪も溶け、少しずつ暖かくなってきた頃。俺達は新しい教室の前でたむろしていた。
「同じクラスなれたかな?」
「楽しみだね」
「うん」
佐野友里、俺の初恋の人。そして俺の大好きな恋人。
「二人だけずるいぞ」
「俺らも混ぜて」
こいつらは山本宏太と高橋隼人。こっちは友達以上恋人未満のBFFみたいな存在。
「お前と佐野が同じクラスだったらイチャイチャしすぎて留年すんじゃねぇの?」
「は?そんなことねぇし」
「まぁまぁ、落ち着いて」
「佐野ちゃんは俺らと同じクラスなりたい?」
「う、うんできれば…」
「あ、やべそろそろ時間か」
「さっさと確認しちゃおー!」
「えーっと…」
俺は自分の名前を探す。すると2組に俺の名前が入っていた。
(じゃあ友里は…)
急いで友里の名前を探すが見当たらない。
「あ、俺1組…」
「佐野ちゃんと一緒のクラス〜」
「え…」
どうやら最悪なことに友里とは別のクラスになってしまったようだ
「おい!高橋!俺と代われ!」
「えーやだー」
「…そうだ!山本は!?」
「俺3組」
「おいお前ら、名前確認したならさっさと教室入れ」
「ちょっと先生!なんで俺と友里たち違うクラスなの!?」
「そう言われてもな、会議で決まったことなんだよ」
「そんなー…」
「燈也が別のクラス行っても嫌いにならないから、安心して」
「友里ぃ…」俺が泣きながら友里に抱きつこうとした手は高橋に止められた。
「いつでも会えるでしょ?合同授業だってあるし」
「それもそうだけど…」
俺らが教室の前で話していると後ろからすごくやばい気配を感じた。
「文句言ってねぇで早く入れ!」
「ゲッ…!木村!お前なんでここいんだよ」
「木村先生だ!お前のクラスの担任になったからだ!」
「はぁ!?まだ蛯名先生いるでしょ!」
去年2組の担任は蛯名先生だから普通蛯名先生になるはずだ。それに木村は去年は教科担任だっただけで今年で定年だったはず…
「蛯名は3組になった。お前森先生やめてたろ、覚えてねぇのか」
「え!でも木村先生定年じゃねえの?」
「そうだな、“今年で”定年だな」
「今年でって…まさか!」
俺はてっきりもう定年を迎えて今年で辞めてたもんかと思ったがどうやら今年で定年なだけで今年中はここにいるそうだ。
「さ、始まるぞ来い」
「ヤダー!助けてー!」
「俺らも教室入ろっか〜佐野ちゃーん」
「う、うん…」
燈也と離れちゃうなんて残念……早く会いたいな
今日は新学期はじめということもあり、学校は午前中で終わった。
「友里帰ろー!」
「うん!ちょっとまってて」
「外で待ってるね〜」
「はーい」
今日はこのあと一緒にご飯食べに行こう。山本と高橋も久々に誘って4人で食べに行こう。
「あ、あの!」
「え?」
「月嶋くん!ちょっと話したいことが…」
あー告白か、初日に告白なんて珍しいな…
女子の方を見ると隣の席になったあの黒髪の子だった。
「何?手短にね」
「いいの?じゃあさ、ちょっと聞きたいんだけど…」
「何聞きたいの?勉強と告白ならパスね」
そう言うと話しかけてきた隣の女子は俺にだけ聞こえるような声でこう聞いてきた
「月嶋くんと佐野くんって付き合ってるの?」
「うん…ん?」
今なんて?よく聞いてなかったがすごい質問だった気がする…
「やっぱり!応援してるね」
「…え」
女子からは想像してなかった返答がきた。
「私佐野くんと同じ中学だったんだけど、佐野くんかわいいよね」
「…そだな」
「あ、もちろんこの話は秘密にするね」
「おう、じゃあな」
「あれ、外行ってるんじゃなかったの?」
「あ、友里ちょっとこの子と話してて…高橋は?」
「呼んだ〜?」
「呼んだ、山本は?」
「何?」
「おっし、全員揃ったな」
「?」
「何?」
「今日この後暇?」
「暇だけど」
「なにするの〜?」
「飯食いに行こーぜ」
「「え!いいの!?」」
高橋と山本が声を揃え聞いてきた。どうやら自分たちは誘われないと思っていたっぽい。
「いいけど」
「久々に誘ってくれた…」
「な、俺らのこと忘れたのかと…」
「んなわけねえだろ、俺のマブダチなんだから」
「マブ…って何?」
「親友ってこと」
「佐野ちゃんも俺らにとってはマブダチだよ〜!」
「え、いいの?俺なんかが…」
「いいの!ねー?こうちゃん!」
「その呼び方やめろ」
「…山本は俺なんかがマブダチでいいの?」
「まぁ…なんでも」
「こうちゃん佐野ちゃん大好きなんだね〜」
「え!?」
「はぁ?俺の友里だし」
「!?」
「はいはい、知ってるよそれくらい」
「おーい、そろそろ帰れよ〜」
俺らがいつものように駄弁っていると朝のようにもっちーの声がかかった。木村だったら強制退場だろうな…もっちーはそんなことしないしありがたい。
「とりま木村来る前に帰るか」
「はーい」
「おう」
「どこ行きたい?」
「はい!俺肉食いたい!」
「なんでもいい」
高橋と山本は即答だったが友里はなんだかもじもじしている。
「友里はどこ行きたい?」
「えっと…」
「特にないなら肉になるけど」
「燈也がいるなら何でも美味しいから…俺もなんでも嬉しい」
「俺も友里と一緒なら何でも嬉しいよ♡」
「息をするように惚気けるな」
「いいじゃん、俺ら付き合ってるんだし。な?友里」
「う、うん…」
「佐野ちゃん照れてる〜!」
「じゃあ上々苑行くか」
「やったー!」
「俺金なくなったからお前の奢りな」
「嘘つくな山本、お前昨日バイト代入ったって言ってたろ」
「上々苑って高いんでしょ?俺払えるかな…」
「友里の分は俺が出したげる〜」
「えーずるーい」
「月嶋くんがいじめてくる〜」
「だー!わかったから!じゃあ今度はお前らが奢れよ!」
「やったー!」
「ふふっ」
結局俺が全員分奢ることになったが友里が笑ってくれるなら結果オーライだ。
「うまそー!」
「いただきます」
「たらふく食え」
上々苑に到着し早速注文をし始める
「あの人達かっこよくない?」
「わかるー、高校生かな?」
周りからはそんな声がちらほら聞こえてくる
「高い肉食おー!」
「お前遠慮って知ってる?」
「佐野を見習え」
「せっかく来たんだからいいじゃん!ねぇ佐野ちゃん」
「え、うーん…確かに?好きなの頼んでもいいんじゃない?」
「ほらー!」
「何がほらだ」
「好きなものってだけで高いものなんて言ってない」
「俺は高いお肉が好きなの!」
「上々苑はだいたい全部高いだろ」
「そういうことじゃないの!」
「楽しめればいいんじゃない…?」
「ね〜?佐野ちゃんも言ってるよ」
「…友里が言うなら」
「やったー!」
上々苑って初めてきたけど…全部高いな…
あんなこと言ったけどこうも高いと頼みにくい…みんなが頼んだもの食べてよう…
「俺ネギタン塩食べたい」
「俺はカルビ」
「シャトーブリアン!!」
「…ほんとに高いの頼みやがった…友里は?」
「えっ…いや俺は何でも…みんなが頼んだの食べるよ」
「佐野は偉いな、シャトーブリアンくんとは違って」
「むーっ!別に食べたいんだからいいじゃん!」
「友里遠慮しなくていいよ、いっぱい食べよ♡」
「じ、じゃあロース」
「オッケー、飲み物は?」
「俺コーラ!」
「烏龍茶」
「友里は?」
「オレンジジュースで」
「り!じゃあ俺はジンジャーエール」
「り?」
聞き慣れない言葉だ…りって何?
「了解ってこと、了解のりね」
りって何?って顔をしていた俺に山本が教えてくれた。今の子達はりで略すのか…
「それにしても…燈也ってジンジャーエール好きなの?」
「ん?そうだよ」
「この間も飲んでたよね」
「この間?」
「あっ…」
高橋は察したのか俺と燈也をちらっと見てニヤついた。
「何したの〜?」
「映画見ただけ…」
「鬼殺のな」
「え!?鬼殺の勇者二人だけで見たの!?」
「そうだけど…デートだったし」
「うん」
高橋は俺も見たかったと嘆くが、デートだからでなんとか納得してくれた
「その時もジンジャーエール頼んでたから」
「ふーん…あ!そうだ!」
「?」
高橋は何かを思いついたのか俺の耳元であることを囁く。
「え!?」
「がんば!」
「がんば!って…応援することなの?」
「するよ〜」
「二人で何話してたの?」
「えっ、いやぁ…なんでも…」
「高橋のことだからなんでもないわけない」
山本の言葉に燈也もウンウンと頷く
「ほらほら〜」
「うっ…」
こうなったら言うしかないか…人多いけど仕方ない…
「燈也は…」
「ん?」
「と、燈也は…俺とジンジャーエールどっちが好きなの…?」
「…なんてこと吹き込んでんだ!しかもジンジャーエールって…」
「へへ〜私と仕事どっちが大事なの!みたいなの見てみたかったの」
「はぁ?」
「それより答えてあげなよ〜」
「…そんなの答えなくてもわかんだろ」
「きゃー!かわいいー!」
「照れてる」
「燈也かわいい」
「…じゃあ一瞬な」
「…言ってくれないの?俺は燈也のこと…す、好きなのに」
「っ…!わかったよ!」
「わくわく…!」
一瞬の間が入った後燈也の口が動いた
「友里のほうが…好き…」
それは耳を澄まさないと聞こえないくらい小さかった。それでも俺にはちゃんと聞こえ、少し照れくさい…
「え?なんて?」
「高橋はおじいちゃんだもんね、俺と佐野は聞こえたけど」
「えー!聞きたかった!」
「聞くもんじゃねえだろ」
「…確かに」
「それより肉食おうぜ」
「そうだな」
ナイス山本!
「えー」
「このハラミおいしい…」
「タンもどーぞ♡」
「んー」
「おいし?」
「うん♡」
「息するようにいちゃつかないでもらえます?」
「俺達もいるよぉ」
「あ…ごめん」
「俺に変なこと言わせたのだーれだ」
「むぅ…」
「まぁいいけど、せめて控えろよ」
「わかってる」
「気をつける…」
「もっと頼もうぜ、月嶋くんの奢りだし」
「だね〜」
「友里ももっと頼んでいいよ」
「うん、いっぱい食べる」
「よしよし」
そうして俺達は焼き肉を楽しんだ。
「食った食った〜」
「高橋が一番食ってたな」
「シャトーブリアンくん太るよ」
「せっかくの焼き肉楽しめたんだからいいでしょ」
「それはそうだけど」
「友里もいっぱい食べててかわいかったよ」
「…でも燈也死ぬほど写真撮ってたよね」
「うっ…それは…」
そうだ。燈也は俺が食べているとき写真をめちゃくちゃ撮っていたのだ。最初は俺もノリノリでピースしていたが、だんだんコマ撮りかってくらい連射したりしてきてちょっと食べづらかった…
「ごめん…友里がかわいすぎるから」
「むぅ…じゃあ俺にも撮らせて」
「え」
「燈也がかっこよすぎるから…」
「はぅ…」
「じゃあ俺ら先行ってるな」
「お幸せに〜」
「え、ちょ!」
「後で送っといて〜」
「うん、わかった」
「えー…」
「じゃあいくよ」
俺は高橋と山本が向こうに行ったのを見計らってスマホのシャッターを切った
「待って、いきなり撮られたら盛れない…」
「…盛らなくてもかっこいいじゃん」
「もー…すぐそういう事言う…」
「へへ、仕返し」
「貸して」
「えっ」
燈也は俺からスマホを奪い俺の肩を自分の方へと寄せた。
「この方がいいでしょ」
「…燈也の写真撮るはずだったのに」
「ツーショだけ撮らせて、お願い」
「…仕方ないなぁ」
俺は燈也のお願いに弱いんだろうな…それかただ単にツーショを撮りたかったのか…距離が近く、胸の鼓動が早いからかよく考えられない…
「撮るよ〜」
「うん」
「はいチーズ!」
俺はシャッターがなる直前に燈也の方に少し寄りかかった。
「…撮れたよ」
「うん…」
「俺の写真撮るんじゃなかったの?」
「また今度…今はこうしてたい…」
「…そっか、じゃあまた今度にお預けだね」
「うん…」
「じゃあもうちょっとしたら二人のとこ戻ろっか」
「わかった」
俺は燈也の手を握り、二人の方へと向かった。
優しくて、イケメンで…ちょっと重いところもあるけど誰よりも一生懸命な彼氏ができて、今まで話したこともなかったのにすぐに仲良くしてくれたクールで一番頭がよかったり、背丈が近く俺をいつも元気づけてくれる二人の親友。他にも最初は警戒していたのにいつの間にか仲が良くなった弟くんや、俺を家族のように接してくれた二人。一人で俺のために働いてくれた母さん。俺に優しく勉強を教えてくれた先生。ちょっと変だけどとっても優しいカフェのお姉さん。
そもそも俺が小学生の時燈也に何も話していなかったら…保健係になっていなかったらこんなことにはなっていなかったんだろうな。
この幸せな時間は俺達が一つ一つの積み重ねで作ったんだ。この時間を永遠に続けていけるように頑張ろう。
こんな俺がかっこよくて、お金持ちで、みんな思いの燈也と付き合えてしまうだなんて
こんなの絶対、裏がある!
「同じクラスなれたかな?」
「楽しみだね」
「うん」
佐野友里、俺の初恋の人。そして俺の大好きな恋人。
「二人だけずるいぞ」
「俺らも混ぜて」
こいつらは山本宏太と高橋隼人。こっちは友達以上恋人未満のBFFみたいな存在。
「お前と佐野が同じクラスだったらイチャイチャしすぎて留年すんじゃねぇの?」
「は?そんなことねぇし」
「まぁまぁ、落ち着いて」
「佐野ちゃんは俺らと同じクラスなりたい?」
「う、うんできれば…」
「あ、やべそろそろ時間か」
「さっさと確認しちゃおー!」
「えーっと…」
俺は自分の名前を探す。すると2組に俺の名前が入っていた。
(じゃあ友里は…)
急いで友里の名前を探すが見当たらない。
「あ、俺1組…」
「佐野ちゃんと一緒のクラス〜」
「え…」
どうやら最悪なことに友里とは別のクラスになってしまったようだ
「おい!高橋!俺と代われ!」
「えーやだー」
「…そうだ!山本は!?」
「俺3組」
「おいお前ら、名前確認したならさっさと教室入れ」
「ちょっと先生!なんで俺と友里たち違うクラスなの!?」
「そう言われてもな、会議で決まったことなんだよ」
「そんなー…」
「燈也が別のクラス行っても嫌いにならないから、安心して」
「友里ぃ…」俺が泣きながら友里に抱きつこうとした手は高橋に止められた。
「いつでも会えるでしょ?合同授業だってあるし」
「それもそうだけど…」
俺らが教室の前で話していると後ろからすごくやばい気配を感じた。
「文句言ってねぇで早く入れ!」
「ゲッ…!木村!お前なんでここいんだよ」
「木村先生だ!お前のクラスの担任になったからだ!」
「はぁ!?まだ蛯名先生いるでしょ!」
去年2組の担任は蛯名先生だから普通蛯名先生になるはずだ。それに木村は去年は教科担任だっただけで今年で定年だったはず…
「蛯名は3組になった。お前森先生やめてたろ、覚えてねぇのか」
「え!でも木村先生定年じゃねえの?」
「そうだな、“今年で”定年だな」
「今年でって…まさか!」
俺はてっきりもう定年を迎えて今年で辞めてたもんかと思ったがどうやら今年で定年なだけで今年中はここにいるそうだ。
「さ、始まるぞ来い」
「ヤダー!助けてー!」
「俺らも教室入ろっか〜佐野ちゃーん」
「う、うん…」
燈也と離れちゃうなんて残念……早く会いたいな
今日は新学期はじめということもあり、学校は午前中で終わった。
「友里帰ろー!」
「うん!ちょっとまってて」
「外で待ってるね〜」
「はーい」
今日はこのあと一緒にご飯食べに行こう。山本と高橋も久々に誘って4人で食べに行こう。
「あ、あの!」
「え?」
「月嶋くん!ちょっと話したいことが…」
あー告白か、初日に告白なんて珍しいな…
女子の方を見ると隣の席になったあの黒髪の子だった。
「何?手短にね」
「いいの?じゃあさ、ちょっと聞きたいんだけど…」
「何聞きたいの?勉強と告白ならパスね」
そう言うと話しかけてきた隣の女子は俺にだけ聞こえるような声でこう聞いてきた
「月嶋くんと佐野くんって付き合ってるの?」
「うん…ん?」
今なんて?よく聞いてなかったがすごい質問だった気がする…
「やっぱり!応援してるね」
「…え」
女子からは想像してなかった返答がきた。
「私佐野くんと同じ中学だったんだけど、佐野くんかわいいよね」
「…そだな」
「あ、もちろんこの話は秘密にするね」
「おう、じゃあな」
「あれ、外行ってるんじゃなかったの?」
「あ、友里ちょっとこの子と話してて…高橋は?」
「呼んだ〜?」
「呼んだ、山本は?」
「何?」
「おっし、全員揃ったな」
「?」
「何?」
「今日この後暇?」
「暇だけど」
「なにするの〜?」
「飯食いに行こーぜ」
「「え!いいの!?」」
高橋と山本が声を揃え聞いてきた。どうやら自分たちは誘われないと思っていたっぽい。
「いいけど」
「久々に誘ってくれた…」
「な、俺らのこと忘れたのかと…」
「んなわけねえだろ、俺のマブダチなんだから」
「マブ…って何?」
「親友ってこと」
「佐野ちゃんも俺らにとってはマブダチだよ〜!」
「え、いいの?俺なんかが…」
「いいの!ねー?こうちゃん!」
「その呼び方やめろ」
「…山本は俺なんかがマブダチでいいの?」
「まぁ…なんでも」
「こうちゃん佐野ちゃん大好きなんだね〜」
「え!?」
「はぁ?俺の友里だし」
「!?」
「はいはい、知ってるよそれくらい」
「おーい、そろそろ帰れよ〜」
俺らがいつものように駄弁っていると朝のようにもっちーの声がかかった。木村だったら強制退場だろうな…もっちーはそんなことしないしありがたい。
「とりま木村来る前に帰るか」
「はーい」
「おう」
「どこ行きたい?」
「はい!俺肉食いたい!」
「なんでもいい」
高橋と山本は即答だったが友里はなんだかもじもじしている。
「友里はどこ行きたい?」
「えっと…」
「特にないなら肉になるけど」
「燈也がいるなら何でも美味しいから…俺もなんでも嬉しい」
「俺も友里と一緒なら何でも嬉しいよ♡」
「息をするように惚気けるな」
「いいじゃん、俺ら付き合ってるんだし。な?友里」
「う、うん…」
「佐野ちゃん照れてる〜!」
「じゃあ上々苑行くか」
「やったー!」
「俺金なくなったからお前の奢りな」
「嘘つくな山本、お前昨日バイト代入ったって言ってたろ」
「上々苑って高いんでしょ?俺払えるかな…」
「友里の分は俺が出したげる〜」
「えーずるーい」
「月嶋くんがいじめてくる〜」
「だー!わかったから!じゃあ今度はお前らが奢れよ!」
「やったー!」
「ふふっ」
結局俺が全員分奢ることになったが友里が笑ってくれるなら結果オーライだ。
「うまそー!」
「いただきます」
「たらふく食え」
上々苑に到着し早速注文をし始める
「あの人達かっこよくない?」
「わかるー、高校生かな?」
周りからはそんな声がちらほら聞こえてくる
「高い肉食おー!」
「お前遠慮って知ってる?」
「佐野を見習え」
「せっかく来たんだからいいじゃん!ねぇ佐野ちゃん」
「え、うーん…確かに?好きなの頼んでもいいんじゃない?」
「ほらー!」
「何がほらだ」
「好きなものってだけで高いものなんて言ってない」
「俺は高いお肉が好きなの!」
「上々苑はだいたい全部高いだろ」
「そういうことじゃないの!」
「楽しめればいいんじゃない…?」
「ね〜?佐野ちゃんも言ってるよ」
「…友里が言うなら」
「やったー!」
上々苑って初めてきたけど…全部高いな…
あんなこと言ったけどこうも高いと頼みにくい…みんなが頼んだもの食べてよう…
「俺ネギタン塩食べたい」
「俺はカルビ」
「シャトーブリアン!!」
「…ほんとに高いの頼みやがった…友里は?」
「えっ…いや俺は何でも…みんなが頼んだの食べるよ」
「佐野は偉いな、シャトーブリアンくんとは違って」
「むーっ!別に食べたいんだからいいじゃん!」
「友里遠慮しなくていいよ、いっぱい食べよ♡」
「じ、じゃあロース」
「オッケー、飲み物は?」
「俺コーラ!」
「烏龍茶」
「友里は?」
「オレンジジュースで」
「り!じゃあ俺はジンジャーエール」
「り?」
聞き慣れない言葉だ…りって何?
「了解ってこと、了解のりね」
りって何?って顔をしていた俺に山本が教えてくれた。今の子達はりで略すのか…
「それにしても…燈也ってジンジャーエール好きなの?」
「ん?そうだよ」
「この間も飲んでたよね」
「この間?」
「あっ…」
高橋は察したのか俺と燈也をちらっと見てニヤついた。
「何したの〜?」
「映画見ただけ…」
「鬼殺のな」
「え!?鬼殺の勇者二人だけで見たの!?」
「そうだけど…デートだったし」
「うん」
高橋は俺も見たかったと嘆くが、デートだからでなんとか納得してくれた
「その時もジンジャーエール頼んでたから」
「ふーん…あ!そうだ!」
「?」
高橋は何かを思いついたのか俺の耳元であることを囁く。
「え!?」
「がんば!」
「がんば!って…応援することなの?」
「するよ〜」
「二人で何話してたの?」
「えっ、いやぁ…なんでも…」
「高橋のことだからなんでもないわけない」
山本の言葉に燈也もウンウンと頷く
「ほらほら〜」
「うっ…」
こうなったら言うしかないか…人多いけど仕方ない…
「燈也は…」
「ん?」
「と、燈也は…俺とジンジャーエールどっちが好きなの…?」
「…なんてこと吹き込んでんだ!しかもジンジャーエールって…」
「へへ〜私と仕事どっちが大事なの!みたいなの見てみたかったの」
「はぁ?」
「それより答えてあげなよ〜」
「…そんなの答えなくてもわかんだろ」
「きゃー!かわいいー!」
「照れてる」
「燈也かわいい」
「…じゃあ一瞬な」
「…言ってくれないの?俺は燈也のこと…す、好きなのに」
「っ…!わかったよ!」
「わくわく…!」
一瞬の間が入った後燈也の口が動いた
「友里のほうが…好き…」
それは耳を澄まさないと聞こえないくらい小さかった。それでも俺にはちゃんと聞こえ、少し照れくさい…
「え?なんて?」
「高橋はおじいちゃんだもんね、俺と佐野は聞こえたけど」
「えー!聞きたかった!」
「聞くもんじゃねえだろ」
「…確かに」
「それより肉食おうぜ」
「そうだな」
ナイス山本!
「えー」
「このハラミおいしい…」
「タンもどーぞ♡」
「んー」
「おいし?」
「うん♡」
「息するようにいちゃつかないでもらえます?」
「俺達もいるよぉ」
「あ…ごめん」
「俺に変なこと言わせたのだーれだ」
「むぅ…」
「まぁいいけど、せめて控えろよ」
「わかってる」
「気をつける…」
「もっと頼もうぜ、月嶋くんの奢りだし」
「だね〜」
「友里ももっと頼んでいいよ」
「うん、いっぱい食べる」
「よしよし」
そうして俺達は焼き肉を楽しんだ。
「食った食った〜」
「高橋が一番食ってたな」
「シャトーブリアンくん太るよ」
「せっかくの焼き肉楽しめたんだからいいでしょ」
「それはそうだけど」
「友里もいっぱい食べててかわいかったよ」
「…でも燈也死ぬほど写真撮ってたよね」
「うっ…それは…」
そうだ。燈也は俺が食べているとき写真をめちゃくちゃ撮っていたのだ。最初は俺もノリノリでピースしていたが、だんだんコマ撮りかってくらい連射したりしてきてちょっと食べづらかった…
「ごめん…友里がかわいすぎるから」
「むぅ…じゃあ俺にも撮らせて」
「え」
「燈也がかっこよすぎるから…」
「はぅ…」
「じゃあ俺ら先行ってるな」
「お幸せに〜」
「え、ちょ!」
「後で送っといて〜」
「うん、わかった」
「えー…」
「じゃあいくよ」
俺は高橋と山本が向こうに行ったのを見計らってスマホのシャッターを切った
「待って、いきなり撮られたら盛れない…」
「…盛らなくてもかっこいいじゃん」
「もー…すぐそういう事言う…」
「へへ、仕返し」
「貸して」
「えっ」
燈也は俺からスマホを奪い俺の肩を自分の方へと寄せた。
「この方がいいでしょ」
「…燈也の写真撮るはずだったのに」
「ツーショだけ撮らせて、お願い」
「…仕方ないなぁ」
俺は燈也のお願いに弱いんだろうな…それかただ単にツーショを撮りたかったのか…距離が近く、胸の鼓動が早いからかよく考えられない…
「撮るよ〜」
「うん」
「はいチーズ!」
俺はシャッターがなる直前に燈也の方に少し寄りかかった。
「…撮れたよ」
「うん…」
「俺の写真撮るんじゃなかったの?」
「また今度…今はこうしてたい…」
「…そっか、じゃあまた今度にお預けだね」
「うん…」
「じゃあもうちょっとしたら二人のとこ戻ろっか」
「わかった」
俺は燈也の手を握り、二人の方へと向かった。
優しくて、イケメンで…ちょっと重いところもあるけど誰よりも一生懸命な彼氏ができて、今まで話したこともなかったのにすぐに仲良くしてくれたクールで一番頭がよかったり、背丈が近く俺をいつも元気づけてくれる二人の親友。他にも最初は警戒していたのにいつの間にか仲が良くなった弟くんや、俺を家族のように接してくれた二人。一人で俺のために働いてくれた母さん。俺に優しく勉強を教えてくれた先生。ちょっと変だけどとっても優しいカフェのお姉さん。
そもそも俺が小学生の時燈也に何も話していなかったら…保健係になっていなかったらこんなことにはなっていなかったんだろうな。
この幸せな時間は俺達が一つ一つの積み重ねで作ったんだ。この時間を永遠に続けていけるように頑張ろう。
こんな俺がかっこよくて、お金持ちで、みんな思いの燈也と付き合えてしまうだなんて
こんなの絶対、裏がある!