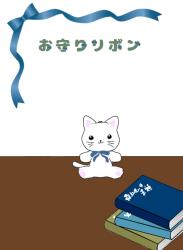時は流れ12月24日。街では完全にクリスマスムード。それに今日から冬休みも始まるからみんなウキウキしている。俺もその一人。
去年は一人さみしくケーキを食べすぐ寝ていた。高校生にもなったしプレゼントは貰っていない。
でも今年は違う。だって燈也と付き合ってるんだもの!
「ゆーりっ」
「ひぁ」
突然声をかけられたものだから変な声が漏れた。
「ははっ!かわいい〜」
「びっくりした…」
「よしよし、一緒に帰ろ」
「いいよ、二人は?」いつもは高橋や山本もいるが今日は見当たらない
「二人で帰ろっ」
「えっ」
「ん?俺と二人きりヤダ?」
「いや、そうじゃなくて…」
燈也と二人きりで帰ったら燈也ファンたちに刺されるかもしれない…なにげに最初から二人きりは初めてな気がする。
「じゃ、強制連行!」
「え?何…」
俺が何をするのか聞こうとした途端燈矢に担がれた。
「えっ!ちょ!おろして!」
「玄関着いたらね〜」
「ちょっとー!」こんなの更に目立つのに!
でもさすが陸上部、一瞬で到着した。
「よっと、とーちゃーく」
「は、速かった」
「あー、絶叫系だめだったっけ」
「いや、ギリ乗れる…」
「ギリってなんだよ」
「乗れなくはない…」
「じゃあ担がれるの嫌?」
「い、嫌じゃないけど…手繋いでる方が好き」
もちろん、こんなこと大声で言えるわけもなく玄関の音にかき消されて誰も聞こえないようなボリュームだった。
「そっか、じゃあ手繋いで帰ろっか」と燈也が耳元で囁く
「聞こえてたの…?」
「もちろん」
マジか…今のが聞こえるだなんて相当な地獄耳だな…
「じ、じゃあ校門出たらね」
「わかった、靴履き終わったね?」
「うん?」なんだか嫌な予感がする…
「じゃ、飛ばすぞ」
また教室の時みたいに体が浮いた。
「え!?また!?」
「担いじゃダメなんて言ってないでしょ」
「うっ…」
(言えばよかった…)
「しゅっぱーつ!」
そのまま燈也は目にも止まらぬ速さで校門まで駆け抜けた
「……あんなに速い月嶋初めて見た」
「俺も……」
そして瞬く間に校門を過ぎ、人通りが少ないところで俺は降ろされた
「とーちゃーく」
「は、速い……」
「じゃ、帰ろ」
「うん」
俺が頷いた途端燈也は俺の手を握った。
「明日って暇?」
「うん。一日中暇だよ。」
「じゃあ一日中デートしよっか」
「い、いいけど…」
「チンピラにカツアゲされないでよ?」
「流石にされないよ」
「ほんとにー?」
「ほんとに」
多分、されない………燈也といればなんとかなるだろうし
「あ、そうだ。蒼真も友里に会いたいって、だから午前中家来れる?」
「いいよ、何時くらいがいい?」
「んーまぁ9時くらいなら」
「りょーかい」
そんなこんな話している間にいつもの道へと出てしまった。
「じゃあ、バイバイ」俺は少し惜しそうにしながらも手をほどいた。
「……ねぇ、家までついてっていい?」
「…?いいよ」こんなに悲しそうな燈也は初めて見た。それに俺ももうちょっと一緒にいたかったしちょうどいい。
「ありがと」
そういった燈也の顔はさっきと比べてみるとちょっと嬉しそうだった。
燈也もかっこいいだけじゃなくてこんな可愛いところもあるんだな。これがギャップ萌えというものなんだろう。
「…そういえば俺おっきくなったんじゃない?」
「確かに最近友里の顔近い気がする」
「でしょ〜このまま燈也も抜くから」
「ふふっ、じゃあ俺ももっとおっきくなろっかな」
「…それでも抜くから」
「頑張ってね」
「うん」
「あ、そうだ!」俺が頷くと燈也は何かを閃いたようだ
「何?」
「友里このあと暇?」
「うん、一応…」
「じゃあ帰ったらデートしよっか」
「えっ」
「それならもっと一緒にいれるよ」
「確かに…」そうか、別にデートは明日だけってわけじゃないしな。この後ちょうど暇だったし好都合だ。
そんな話をしていればいつの間にか家の前に着いた
「じゃあ決まりな」
「うん、また後で」そう言ってまた手を振りほどこうとした瞬間燈矢の方へと引き寄せられた。
「じゃあね、迎えに行くから」
「うん…」
燈也に一旦別れを告げ家へと入っていく。
家は今日もとても静か。母は仕事が忙しくてあまり一緒にいた記憶がない。
高校に入ってからもちょくちょくバイトをしてるからさみしいなんて思ったことはあまりない。それにおんぶにだっことまではいっていないし、お金もちゃんと入れている。
ただ俺は学生だから足りるわけもない。だから仕方ないと思うことにしている。
高一のときは寂しさをバイトで紛らわせていたがきつかった。
俺の誕生日は2月だからまだ先だけど今からすでに楽しみな自分がいる。
机の上にはいつものようにお小遣いとメモがある。自分も苦しいはずなのに週1で5000円を置いてくれる。俺は自炊もできるので冷蔵庫の中にあるもので自分と母で2人分の料理を作っている。母さんが帰ってくるのは深夜だからいつもはラップをして冷蔵庫に入れている。
(とりあえず着替えも終わったし母さんの分だけでも作るか…)
俺は別に外で食べても問題ない。今日はこのあとデートだし……
「あ!デート!」
すっかり忘れていた…料理していたら間に合わない…そんな事を考えている間に玄関のチャイムが鳴った。
「…帰ったら作るか」
とりあえず母さんにはLIMEで『今日燈也と遊ぶ約束してるから帰るのちょっと遅くなるかも』とだけ伝え玄関の扉を開けた。
「おまたせ」
「友里の私服かわいいね、じゃあ行こっか」
「う、うん…」
勘弁してくれ、俺のライフは少ないんだ……褒められ慣れてもないからなおさら…
「友里どした?俺の顔になにかついてる?」
「いや…その…なんでもない……それより早く行こ」
「…おう、そうだな」
(褒められて嬉しかったなんて恥ずかしくて言えないし…まともな言い訳も思いつかなかった…)
「そういや友里って大学行くの?」
「えっ、うんそのつもり」
「どこの大学?東大?」
「東大は…多分無理」
「無難に北大?」
「んー、北大までならなんとかなると思う」
「友里はどこに行きたいの?」
「えーっと……」
考えたこともなかった。俺はどこに行きたいんだろうか…
「俺は別に友里の行きたいところならどこでもいいよ?なんなら勉強教えるし」
「あ、うんありがと」
「ま、この話はまた今度でいっか」
「そう…だね」
「まぁ勉強なら山本のほうがいいか、あいつ教えるのうまいし」
「そうなの?」
「ああ、でもうまいけど厳しいというか…」
「……でも俺燈也に教わりたい。燈也と勉強するの楽しいから。」
「友里……!」
そして燈也は嬉しそうに俺を抱きしめた。それに燈也のいい匂いがして赤くなる。
「いい匂い…」つい言葉が漏れてしまった。それも燈也はしっかり聞いていたようだ。これだけくっついているのだから聞こえないほうがおかしいまである
「でしょ?俺もこのヘアオイル気に入ってんの」
「へあ…おいる?」おしゃれに疎い俺には聞き慣れない言葉だ。
「そう、髪につけるオイル」
「シャンプーとは違うの?」
「うん、シャンプーより匂い強くなった感じ?」
「香水みたいなもん?」
「そだね、髪につける香水って思えばいいかも」
「そうなんだ…あ、それってなんの匂い?甘いような…」
「ああこれ?バニラだよ」
「バニラってあの?」
「そう、バニラアイスのバニラ!まぁ正確にはバニラビーンズだけど」
「アイスってわけじゃないんだ」
「あ、そうだ友里も使う?」
「え?」
「今日俺とおんなじの買ってあげる」
「ほんと!?ありがと!」
「…どういたしまして」
燈也をよく見ると耳が赤くなっている。
「ふふっ、燈也耳赤いね」
「これは………寒いから…」
キモがってなんかなかったんだ。そう思うとさっきの気持ちも晴れ嬉しくなった。
「じゃあ俺が温めてあげる」そう言って俺は燈也の手を取った
「っ……」
「えへへ…どう?あったかい?」
「まだ寒いから抱きしめてよ」
「えっ……」
でも付き合えた今なら……とちょっとだけ燈也に抱きついた。抱きついたと言えるのかわからないけど……
「あったまれた、ありがと友里」
「ど、どういたしまして…」
今思い出すとすっごく恥ずかしい。こんな道端でイチャイチャしちゃった……
「…あれ、そういえばどこ行くの?」
行き先は聞けてなかった。結構歩いた気がするがどこに行くか見当がつかない。
「こっちだよ」
そう言って燈也は俺を人気のない道路へと引っ張る
「着いたよ」
連れてこられた先は見たことないようなきれいな外装の小さなお店だった。なんだかシーンとしていてちょっと怖いような…
燈也はそんなことも気にせず扉を開ける
「やっほー!来たよー!」
「いらっしゃ〜い」
お店の奥から出てきたのはメガネを掛け、緑のエプロンを着たお姉さんがだった。
「あら、その子燈也くんのお友達?」
「あ、は…」
「いや?彼氏」
(え!?言っちゃうの!?)
男同士で付き合ってるだなんて…変な目で見られるんじゃ…
「なっ…彼氏!?」
「その…変ですかね…」
「いいじゃない!最高だわ!」
「……え?」
「二人はどういう関係?幼馴染?クラスメイト?」
「小学校の頃から一緒、中学以外」
「幼馴染カップル!」
「えーっと…この人は?」
「あー、俺のいとこ」
「どうも〜菅原晶子です」
「この人腐女子だから彼氏って言っても大丈夫だよ」
「…あれ、じゃあこの子って前言ってた好きな子?」
「そう、その子」
「そう!じゃあ好きなスイーツ食べさせてあげる」
「ここそういう店だろ」
「ここってカフェなの?」
「そうよ!ここ私のカフェなの〜」
「穴場なんだぜここ、晶子さんの腕前プロだから」
「やだも〜お世辞〜?」
「お世辞なわけ無いでしょ〜」
「褒めても何も出ないからね〜」
「じゃあ早速頼もっか、友里」
「うん」
それにしても内装もとってもきれいだ。おしゃれで静かで落ち着く。机の上には申し訳程度にクリスマスツリーの置物がある。
「決まった?」
「え、あ、じゃあプリンで」
「俺シフォンケーキ」
「は~いお飲み物はどうしますか?」
「俺いつもの、友里は?」
「オレンジジュースで」
「ご注文承りました〜」
「…ここって菅原さん一人で経営してるの?」
「そだね、晶子さん一人」
「大変じゃない?」
「どうかね、週休3日もあるしそこまで大変じゃないと思うよ」
「そうなんだ」
「それに穴場って言ったろ?常連さんいるけど初めての人ってそんなにこないんだよね」
「でも潰れたりしないの?」
「いや、あの人も結構金持ちだから」
「あの人?」
「俺の叔父さん、確か投資家だっけ?」
「そうね〜、はいこちらどうぞ」
「美味しそう…」
「じゃあ食べよっか」
「燈也のコーヒー?」
「うん良い豆使ってんだよね」
「へぇ〜、ブラックで飲むの?」
「うん、いつもブラックだよ」
「すご、かっこいい」
「そ、そう…」
(はぁ〜!燈也くんこんな顔できたのね…佐野くんもかわいい…)
「晶子さんどした?顔になんかついてた?」
「え?いやなんでも…」
燈也と菅原さんが話してる間に俺は生クリームやいちごがたっぷり乗っているプリンを口に運んだ
「んー!このプリンすっごい美味しいです!」
「そう?お口に合ってるみたいでよかったわ〜」
「友里、俺にも一口ちょーだい」
「いいよ、あーん」
「ん、ありがと、じゃあ俺のもどうぞ」
「いいの?じゃあ…」
俺は燈也からもシフォンケーキをもらう。シフォンケーキも口に入れた瞬間甘いクリームとスポンジがいい感じに合わさりとても美味しい
「ケーキも美味しいね」
「だろ?よかったらもっと頼む…って晶子さん!?」
ふと菅原さんの方を見ると顔が赤くなったまま倒れていた
「え、ちょ大丈夫ですか!?」
「ん…ああ、気にしないで久々にいいもの見れたから…」
「知らない間に連続で働いてたんじゃと思ったけどそんなことなかったわ…」
「ごめんなさいね、また後で〜」そう言ってそそくさと店の奥へと消えてしまった…
「…ほんとに大丈夫なのかな」
「あの人昔からああいう人だから…」
「そうなんだ…?」
「それより食べちゃおっか、買い物もいかなきゃ」
「そ、そうだね」
そして俺達は急いで食事を終わらせた。
「友里先出てていいよ俺が払っとく」
「え、悪いよ俺が払うから」
「いいの、俺が連れてきたんだし」
「でも…たまには俺にもカッコつけさせてよ」
「んーじゃあお言葉に甘えちゃおっかな」
「じゃあ外で待っててね」
「うん」
燈也が外に出たのを見送り、俺は会計をするため財布を取り出す
「すみませーん」
「はーいちょっと待ってて〜」
そう言って店の奥から出てきたのは鼻つっぺをした菅原さんだった
「え!どうされたんですかそれ!?」
「いやぁ…ちょっと鼻ぶつけちゃって…」
「そうなんですね…お大事に…」
「ありがと、それでお会計でしょ?」
「あ、はい」
「ほんとは1573円なんだけどクリスマスだから特別に10%OFFの1430円でいいわよ〜」
「え、いいんですか?」
「まぁ明日休みだし大丈夫よ」
「あ、ありがとうございます」
「いえいえ」
「それじゃあちょうどで、ありがとうございました」
「こちらこそ〜またきてね」
菅原さんに笑顔で手を振り返し俺は店を出た。
「おまたせ、行こっか」
「おう」
「いつもどこで買ってるの?そのヘアオイル」
「ドラッグストアとかに売ってるよ」
「そうなんだ」
「ちょうどそこにあるから寄ろ」
「うん」
それにしても今日は一段と寒い…さすが北海道と言ったところだろうか…
「友里どした?寒い?」
「えっ…っとちょっと…?」
「じゃあこうしよっか」
そう言って燈也は俺の手を握り自分のポケットに入れた。
「!?」
「友里の手冷たいね」
「…うん」
ドキドキして落ち着かない。こんなんで明日のデート大丈夫なのかよ…
(でも…)
燈也の手…あったかい…俺の手を優しく包んでくれて…
「着いたよ」
「あ、ありがと…」
「もうちょっとつなぐ?」
「店の中ではいいよ……外でなら」
「うん、じゃあ外でつなごっか」
「……」燈也を見てられない…ぶっ倒れちゃうかも…
「あ、これこれ」
「何が?」
「これが俺のヘアオイル」
「へぇ~…え!?」
(5000円!?高っ!)
5000円以上もするとかドラッグストアで売っていいのかよ…!
「いやぁ…でも俺やっぱり…あれ!?いない!?」
「1点で5060円となります」
「はーい」
「え!?」
気づけば燈也はレジに並んでいた。しかも会計まで…
「悪いよ…こんなに高いとは…」
「いいよ全然あんな安いの」
「え、安くなんかないでしょ」
「友里のために買いに来たんだから、友里が喜んでくれればそれで充分」
燈也は優しいな…俺がこの匂い好きとか言わなければこんな買い物しなくてもよかったのに…
「明日も早いし帰ろ」
「うん…」
「明日のデート楽しみだね」
「うん」
「あ、そうそうヘアオイルつけ過ぎたら臭いから気をつけなよ」
「うん、気をつける」
「あと毎日ヘアオイルだと髪も痛むから程々にね」
「そうなの?」
「うん、ヘアオイルってオイルだから髪の毛の潤い?逃がしちゃうんだって」
「?うん?わかった?」
「んー簡単に言うと水と油みたいな?水と油って混ざらないだろ」
「あー」
「そゆこと」
「詳しいね」
「まぁ俺も勉強したからね」
「そうなんだ?」
「友里の隣に立ってても恥ずかしくないように」
「…それって俺がする側じゃ…燈也顔いいじゃん」
「言うて友里も顔面偏差値高いと思うよ」
「そんなことない」
「そんな事ある」
「…ほんと?」
「ほんとだよ?友里ってまつ毛長いよね〜」
「それは…言われるかも」
「二重もきれいだし…」
「えへへ…そう?」
「…友里って家庭的だしかわいいし…非の打ち所がないよね」
「そんなことない、俺成績普通だし…それを言うなら燈也だってイケメンで頭もいいし背高いじゃん」
「でも俺家事全くできないからさ、そこそこ勉強できて優しくて家事もできる友里のほうがハイスペだよ」
「うーん…そうなのかな…」
「そうだよ〜友里は俺の自慢の彼氏なんだから」
「ありがと…」
こんなに褒められちゃった…そもそも俺が家事できるようになったのは父さんがいなくなって母さんが仕事で忙しくなったからだ。それまでは全くできなかった。
「その…今日は色々ありがとう」
「どういたしまして」
「じゃあまた明日」
「うん、ばいばい」
――翌日
「フンフン♪」
朝から鼻歌を歌いながら燈也の家へと向かう。
午前中は蒼真くんの希望で燈也の家でおうちデート。ちゃんと弟思いで優しいな。
「お、友里」
「友里兄ちゃんいらっしゃい!」
「お邪魔します」
二人に出迎えられてから、俺は家の中へと入る。
「友里早速あれ使ってるんだ」
「うん、臭くない?」
「全然」
「あら佐野くん!いらっしゃい!」
「こんにちは」
「お母さん呼びでもいいわよ〜佐野くんも家族みたいなもんだし」
「そんな、恐れ多いです」
俺が戸惑っていると燈也が俺の腕を引いて部屋へと連れて行ってくれた。
「よっしゃー!コインゲット!」
「俺のコインだぞ!」
「ふふっ」
いつもこんな兄弟喧嘩をしているのかな?相変わらず仲が良くて安心する。俺は一人っ子だから羨ましいな…
「みんなー!できたわよー!」
「はーい」
「一旦終わりな」
「はーい…」
「友里も行こ」
「え、いいの?」
「いいの、母さんも友里の分用意してると思うよ」
「友里兄ちゃんがいいなら!」
「あ、じゃあいただこうかな…」
「「やったー!」」
一旦ゲームを終わり食卓へと向かった
「めしあがれ〜」
食卓にはフライドチキンやナポリタンなんかのごちそうがずらりと並んでいた。
「こんな時間からいいんですか?」
「夜外で食べるんでしょう?ならお昼に食べちゃいなさい」
「え、そうなの?」
「家で食べたかった?」
「いや…別にいいんだけど」
「それに…」
「それに?」
「いや、なんでもない。早く食べよ!」
「うん…?いただきます」
何を言おうとしてたんだろう…
「えー!俺も食べに行きたい!」
「蒼真はまた今度な、今日はお留守番」
「えー!」
「燈也が食べない分ケーキとかいっぱい食べれるわよ」
「それもそっか」
(いいの!?)
「燈也たちも先に食べてきなさい」
そう言って瑠那さんはケーキを一切れ出した。
「ありがとうございます」
「いえいえ」
俺がケーキを受け取った瞬間蒼真くんが声をかけてきた
「ねぇ…友里兄ちゃんこれ食べたら行っちゃうの?」
「んー、多分…ごめんね」
「ううん…いいの、でもまた遊んでね」
「もちろん」
「約束だよ!」
「うん」
「友里ほっぺクリーム付いてるよ」
「え、ほんと?どこにある?」
舌で探すが見つからない。その時燈矢の指が肌に触れた。
「取れたよ」
「ありがと…」
舌で探してたのけど見つからなかったし…それを燈也が取ってくれたり…色々重なってとても恥ずかしい
「ごちそうさまでした…」
「もっと食べてもいいのよ?」
「いえ、大丈夫です」
「そう?まぁ二人とも気をつけるのよ」
「わかってるよ」
「はい、気をつけます」
「いってらっしゃい」
「いってきます」
玄関まで見送りに来てくれた蒼真くんに別れを告げ、俺達は家を後にした。
「それにしても蒼真のやつだいぶ友里に懐いたよな、何したの?」
「いや…俺もよくわかってない」
「そっか」
蒼真くんは燈矢を俺に取られたと思っていただけだ。それも今は和解してだいぶ仲も良くなった。
「今日はどこ行くの?」
「ん?今流行りの映画見に行く」
「それって鬼殺の勇者?」
「そうそれ」
ちょうど気になってたやつだ。アニメも漫画も全部見てて好きな作品の一つ。
「鬼殺見てなかった?ネタバレになっちゃうしやめとく?」
「いや、全部見てるよちょうど見たかったから」
「そう、ならよかった!」
燈也の笑顔が眩しい。俺が鬼だったら多分灰になって消えてる…
「あ、晶子さん」
「えっ、なんでここに燈也くんが!?」
「今日この後鬼殺の映画見に行くから」
「どうも…」
「奇遇ね〜私も見に行くところなの」
「そうなんですか!じゃあ一緒に…」
「あ!友達待たせてるんだった!じゃあねー!」そう言って菅原さんは逃げるように走り去っていった
(行っちゃった…)
「…混む前に俺達も急ぐか」
「うん」
「乗って」
「…え?」
燈也は背中に乗れと言わんばかりにかがみだした。
「いいから乗って」
「ひ…人来ちゃう」
「だから乗るの、早くしないと映画始まるよ」
はいを押さないと進めないタイプだ……こうなると断れない…
俺は仕方なく燈也の背中に乗った。燈也の背中は大きくてガッチリしている。
「飛ばすよ、掴まってて」
「うん」
俺が燈也の肩を掴んだ途端燈矢の雰囲気が変わった。ボルトもびっくりの速さで人混みを駆け抜けあっという間に映画館へと着いた。
「着いたよ、大丈夫?」
「うん…なんとか」
まだ始まるまで30分以上あるというのに映画館は人がとても多かった。
「ポップコーン買ってくるけど何味がいい?」
「キャラメルで…」
「飲み物は?」
「コーラ」
「おっけー、じゃあ待ってて」
「うんわかった」
それにしても人多いな…鬼殺目当てじゃない人もいるんだろうけどさすがの人気だな…
「おまたせ」
「え、もう!?」あまりにも早すぎる。だってこんなに人がいるのに…
「いやぁ…なぜかお先にどうぞって…」
人混みの方を見ると燈也をチラチラ見ている人がいたりこちらに小さく黄色い歓声が上がっている。
これもイケメンパワーなのか…?何もしてないのに道を開けられるなんて
「友里?どうかした?」
「え?あ、いやなんでもない」
「じゃあ行こ」
「うん」
そのままポップコーンと飲み物を受け取り指定された席に座る
「人多いね…」
「まぁ鬼殺だからな」
「早めに来れてよかったね」
「そだね、もうちょっと遅かったら友里人混みに流されてたかも」
「確かに」
そんな話をしている間に場内がだんだんと暗くなっていき、おなじみのカメラ人間とパトランプ人間が映し出される
「友里のポップコーンちょうだい」
「うんいいよ」
「ありがと、俺のも食べたくなったら取ってって。ずっとキャラメルだと飽きるかなって塩味頼んできたから」
「うん、じゃあ後でもらうね」
ポップコーンの交換こをしていると映画怪盗も終わり本編が始まった。
鬼のトップ、鬼舞山無惨やその部下の鬼たちとの最終決戦。最初から迫力満点だった。
(喉乾いた…)
俺はおもむろにドリンクを飲む。だが味はコーラではなくジンジャーエールだった。戸惑っていると隣から燈也がとても小さな声で話しかけてきた
「それ俺の…」
「あ、ごめん…」
「…間接キスだね」
「なっ…たしかに…」
間接キスしちゃった…付き合ってるから余計意識しちゃう
「ほんとごめん…俺のだと思った」俺が小さくそう言うと燈也は何かを思いついたかのようにこちらを見る
「じゃあ友里のコーラもちょうだい」
「えっ…!?」
燈也は俺のコーラに手を伸ばし飲みだした。
「ちょっと…」
「これで一緒、映画見よ」
「……勝手に飲むなよ」
「ごめん」
「……燈也ならいいけど」
「…かわいい奴め」
その後はドキドキしてあまり覚えてない。いつの間にかエンドロールが流れだした。
「終わっちゃったね、続きいつ来るのかな」
「……」
「友里?」
「…あ、うん楽しみだね…」
「コーラ飲んでほしくなかった?」
「いや、全然…それは嬉しかった…」
「…照れちゃった?」
その問いに小さく頷く。それを見た燈也はニヤリとした。
「じゃあ間接じゃないキスする?」
「えっ、ここで!?」
「え、ここでしてほしいの?」
「いや…そうじゃない…」
「じゃあしたい?」
「……うん」
俺は燈也にだけ聞こえるようなボリュームで呟いた。
燈也は優しく俺の頭を撫でて微笑んだ。
「そっか、じゃあ後でいっぱいしてあげる」
「うん」
「じゃあそろそろ行こっか」
「どこに?」
「いいところ」
「?」
「じゃあ、しゅっぱーつ!」
「しんこー!」
「着いたよ〜」
「ここ…!」
連れてこられた場所はイルミネーションが綺麗なおしゃれでとても高そうなレストランだった。
「きれー!」
「でしょ?」
「でも高そう…」
「えーそう?」
「俺あっちのゴストでいいよ…」
「えー…でも予約入れちゃった」
「よや…!?」
予約制なら相当高いんじゃ!?でも予約されてる手前断るわけにもいかない…
「しかたない…キャンセル」
「しなくていい!」
「え?でもここ嫌なんでしょ?」
「嫌とは言ってない…ただ高そうだから…」
「気にしなくていいよ〜俺が払うし」
「申し訳ないから…」
「気にしないで、友里のためにここ予約したんだから」
「俺こんなところ来たことないけど…」
俺は庶民だ。御曹司の燈也とは違い、こんなところに来るお金なんてない。
「だからだよ」
「え?」
「たまには贅沢させてあげたいから。それでいい思い出になってくれれば嬉しいなって…」
「っ…!」
俺のために映画だけでなくこんないいところまで予約してくれたんだ、やっぱり燈也は優しいな…
「あ、もう時間だ、早く入ろ」
「うん、わかった」
燈也に手を引かれ俺はレストランへと入っていった。
「予約の月嶋です」
「月嶋様ですね、お待ちしておりました!こちらへどうぞ」
(おお…)
店内はめちゃくちゃ豪華。パーティでもするんじゃないかってくらい明るく、上品。本当に俺が来てよかったのだろうか…
「友里はなに頼む?」
「えーっと…じゃあ…」
恐る恐るメニュー表を見るがズラッと並んだメニューの値段はほぼすべて4桁を超えていた。一番安いのは600円のコーンスープ。これだけじゃ腹は膨れない…4桁の中でも一番安いオムレツを頼もう…
「ご注文をお伺いいたします」
「俺はハンバーグで」
「じゃあオムレツで…」
「えーそれだけで足りる?」
「さっきポップコーン食べたし…」
そう言った途端俺のお腹の音が大きく鳴り響いた。周りからは小さくクスクスと笑い声が聞こえる。最悪だ…初めて来たのにこんな…しかも彼氏の前で…
「ははっ、さっき走ってきたからおなかすいてんじゃん」
「うっ…」
「遠慮しなくていいよ、俺に気遣ってくれるのは嬉しいけど俺は友里がお腹いっぱい食べてくれるのが一番嬉しいんだから」
やっぱり燈也は違うな…こんな時まで俺のことを優先してくれて…いくらお小遣いがあるからって最近お金を使いすぎてるんじゃないか…ヘアオイルだったり映画だったり…決して安くないのに
「…じゃあこの…ボロネーゼで」
「かしこまりました、麺やソースの量やグラムはどういたしましょう」
「ハンバーグは200gで」
「え、量とか決めれるの?」俺の知ってるレストランはこういうのは量が決まっている
「はい、こちらではお客様にあった量でご提供させていただいております。小、並、大、特盛がございます。並が普通サイズで小は並に比べ少ないため100円ほど減額いたします。もちろん多くなれば追加料金が発生いたしますが…」
「そうなんですか、じゃあしょ…」
小でいいですと言おうとしたが流石にここでも気を遣えば嫌われてしまうかもしれない…ここは正直に行こう…
「お、大盛りで」
「一緒にお飲み物はいかがですか?」
「じゃあオレンジジュースで」
「俺も同じのを…」
「かしこまりました、少々お待ちください」
「はーい」
「…ねぇほんとにいいの?」
「何が?」
「だって最近お金いっぱい使ってる気がして」
「遠慮しないでって言ったでしょ?それにこの店のオーナー父さんだから」
「…え!?そうなの!?でも社長なんじゃ」
「あの人忙しい人だから」
「そうなんだ…?」
よくわかんないな…
「そうだ!食後にデザート頼む?」
「え、いいの?」
「もちろん、後からも注文していいんだよ」
「そうなんだ…じゃあショートケーキ」
「俺にチョコケーキしよ」
「お待たせいたしました、こちらボロネーゼとハンバーグでございます」
「あ、ありがとうございます…」
俺は先に自分のボロネーゼとオレンジジュースをもらう
「追加で食後にショートケーキとチョコケーキくださいな」
「かしこまりました、それではお食事が終わり次第またお呼びください」
「はーい」
こんな店でも食後に注文できるんだな…装飾や値段はともかく普段行くようなファミレスに似てるんだな…
「冷めないうちに食べちゃお」
「うん」
俺はボロネーゼを一口運んだ。その瞬間トマトの甘酸っぱい香りともちもちの麺が口の中でとろけて今まで食べたことがないくらい美味しかった。
「美味しい?」
「うん、めっちゃ美味しい」
「そっか、よかった」
「って…もう食べ終わったの!?」
知らない間に燈也のハンバーグは一瞬にして消えていた。まだ10分も経ってないのに…
「俺が一番走ったから…」
…確かに振り返ってみれば俺を背負って映画館だったりレストランだったりを全速力で走っていた。
「今日はほんと、ありがとね」
「へへ、どういたしまして」
「そうだ、今日はね燈也にプレゼント持ってきたの」
「プレゼント?」
「そう、今は渡せないから後でね」
「はーい」
俺も負けてられない。急いでボロネーゼを夷らげ、デザートを頼む。
「ここのケーキ甘くて美味しいね」
「でしょ?晶子さんとこも美味しいけどここも結構おすすめなんだ」
「へー…」
そうなんだ、でも正直菅原さんのお店のほうが良心的な価格だからそっち行くだろうけど…
「あ、友里ほっぺにクリーム付いてるよ」
「え」
俺が取ろうとした瞬間燈也の指が俺の頬を撫でる。
「うん、美味しい」
「……ちょっと…」
こんなところでイチャイチャしちゃっていいのか…?まぁ見られてないようでとりあえず安心…
「美味しかったね」
「うん…その…トイレ行きたいんだけど…」
「あー、それならレジの隣にあるから行ってきな」
「うん待ってて」
「はーい」
(うう…こんなんでこれ渡せるのか?)
ドキドキして渡せれない気がする…燈也が悪いんだ…俺をドキドキさせるから…
「おまたせ」
「じゃ、いこっか」
「え?会計は?」
「もう済ましてる」
「え!?俺も払うよ、いくらだったの?」
「大丈夫だよ」
「でも…」
「んーじゃあさ、プレゼントちょうだい」
「それは外でね」
「じゃ早く外出よ」
「うん」
「みんなまたね~」
燈也は店の人に手を振り店を出た
「じゃ、もうちょっと明るいところに行こ…」
「ん?どうした…」
「隠れて!」
「え?」
急に隠れてって…一体何が?路地の隙間から覗くと向かい側に警察?の人がいた
「今何時?」
「8時…」
「こんな時間から補導員いるのか」
「燈也は大丈夫なの?」
「俺は全然、大人ですみたいにしてればいいけど…友里は怪しまれるだろ」
「…わかった」
ちょっとして補導員がいなくなったようで燈也が優しく声をかけてきた
「…よし、いなくなった…出てきていいよ」
「……」
「…?友里?」
「何?」
「…怒ってる?」
「別に」
「ごめんって、機嫌直して」
俺は怒ってなんかいない。高校生だから補導されるのは当たり前だし…そんなことより俺はプレゼントを渡したい。ただそれだけだった。
「元から機嫌なんて悪くない…それよりまた指導員の人来る前にプレゼント渡したい」
「そ、そうだよね!早く行こ!」
「ん…」
俺は燈也の手を握り、大きなクリスマスツリーがある場所へと連れられた。
「ここのほうが補導員いるんじゃ…」
「いや、その分人もいるから大丈夫」
「そう…?」
「そうそう、俺も友里のためにプレゼント用意してんだ」
「そうなの?」
「そりゃあ…クリスマスだし」
燈也は照れているのか頬がちょっと赤くなった。
「じゃあ先に俺からあげたい」
「いいよ、友里のプレゼント楽しみ」
「こ…これ…」
俺は持ってきたバッグからプレゼントを取り出し、燈也に渡した。
「開けていい?」
「もちろん」
まるでサンタからプレゼントをもらった子供のようにはしゃぐ燈也を見て自然と笑みがこぼれる。
「これ…!」
俺が燈也にあげたのはマフラー。ネットで調べて頑張って編んだ傑作だ。
「頑張って編んだの…」
「ありがと、大切にする」
「つけてみてよ」
「わかった」
燈也はもらったマフラーを巻いた。燈也はとてもうれしそうに笑ってくれて嬉しい。
「じゃあ俺からのプレゼント」
そう言って燈也は細長い箱を渡してきた
「なにこれ?」
「開けてみて」
俺はラッピングを丁寧に剥がしてみた。中はめちゃくちゃ高そうなケースが入っていた。恐る恐る開けてみれば中にはダイヤモンドが使われたネックレスがキラキラ輝いていた。
「!?」
「友里もつけてみて」
燈也はネックレスを取り俺の首元へと手を伸ばす
「いや、こんないいものもらえない…」
「ええ、俺この日のために先月から用意してたんだよ」
「そんな前から…?」
俺なんて三日前に編み終わったっていうのに…
「友里はこれじゃ嫌?」
なんだか悲しそう…嫌なわけじゃない。俺なんかにこんないいものきっと似合わないと思ってしまっているだけ。
「…嫌じゃない…ただ…似合わないかもって…」
「……」
嫌われたかもしれない…俺がせっかくのプレゼントを受け取ろうとしないから…
「そんなことないよ」
「…え」
燈也からは想像していなかった言葉が出る。
「このマフラー俺には似合わない?」
「っ…!そんなこと…!」
そんなことない。そう言いかけた瞬間燈也の手が頭に触れた。
「これだって同じだよ、マフラーと同じ」
「え?」
「服じゃないんだからそうジロジロと見られるもんじゃないよ」
「でも…」
「いちいち値段なんて気にしてたらきりがないから…」
「そうだけど…」
「友里だってこのマフラー俺のために編んでくれたんでしょ?俺も友里のために選んだんだよ」
「……!」
たしかにそうだ…俺だって燈也のことを思って作っていたはずだ。燈也も同じ気持ちで俺のために選んでくれたもの。それを値段で拒否しようとした俺は最低だ。
「俺は友里みたいに器用じゃないし家事もできないからこんなのしか用意できなかったけど…」
「…ごめん」
「仕方ないよ、俺の方こそ…」
「そうじゃなくて…燈也が俺のために買ってくれたのに…それを踏みにじって…」
「踏みにじってなんかないよ」
「でも目が覚めた気がする。ありがと、燈也…このネックレスすごく嬉しい」
「ほんと?」
「うん、一生大事にする」
「気遣ってる?」
「そんなことない…本音だから」
「…そういえばさ、プレゼントにも色々な意味があるんだって」
「例えばどんなの?」
「ネックレスだと束縛とか…」
「え…」
「別に束縛しないから…多分」
「多分って…」
「あ、マフラーも束縛だって」
「え、そうだったの?」
束縛って意味があるならやめといたほうがよかったかな…
「でもネックレスの束縛もマフラーの束縛も束縛したいくらい好きって意味らしいよ」
「そうなんだ…」
なんだ、てっきり俺はメンヘラだよって言ってるようなもんだと思ってた…
「俺達束縛カップルだね」
「あはは、何だよそれ」
「…それとさそのダイヤモンドにも意味があってね」
「そうなんだ、誕生石なのは知ってたけどプレゼントの意味もあるんだね」
「そう、その意味なんだけど…」
なんだろう…もしかしてやばい意味だった!?もうすぐ死ぬとか…
「永遠の愛…って意味があるんだって」
「それって……」
「知っててあげたんだ」
「え…」
「あれ、ドン引き?」
「そんなんじゃない、嬉しくて」
俺だって同じ気持ちだ。燈也のことは永遠に愛したい。
「……それじゃあこの先…大学も、その後も一生、一緒にいてくれる?」
「もちろん」
「ほんと?」
「うん」
俺がそういった瞬間燈也は思い切り抱きしめた。
「よかった…」
とっても嬉しそうだな、燈也
俺も燈也をぎこちなくだが抱き返した。
「…大好き」
「俺も」
今が一番幸せなのかもしれない…燈也は温かい。外で冷えた体を優しく包んで温めてくれている。
「帰ろっか」
「うん」
「このまま泊まってく?」
「泊まっていいなら……あ、でも補導されるかも」
「じゃあ父さんに迎えに来てもらお」
「え、いいの?」
「んーまぁ……ちょうど仕事終わった頃だと思う」
「そうなんだ、じゃあ先に待ち合わせ場所まで行こ」
「そうだな、人多いし」
それから10分後俺達の前に一台の高級車が停まった
「迎えに来たぞ〜!」
「この車燈也のお父さんのだったんですね」
「そうだぞ〜!佐野くんもお父さんって呼んでくれていいんだからな!」
「あはは…まだ早いかな」
「それより早く帰ろ、車出して」
「はいはい、じゃあ二人は後ろ乗りなさい」
「はーい」
俺が乗り終え扉を閉めようと手を伸ばしたが自動で閉まる車だったようで勝手に動いた。
「いやぁ、それにしても燈也がこんなに成長するとは…!」
「おかげさまで」
「佐野くんも燈也と仲良くしてやってくれな」
「は、はい…」
こんな高級車初めて乗った…燈也の家本当にお金持ちなんだな……
「それで、佐野くんのお家は?」
「あ、今日泊まりたいなって話してたんですけど……だめですかね」
「おお、そうか!じゃあ泊まってきなさい!」
「はい、ありがとうございます」
「また蒼真と三人でメリパしような」
「うん!」
「えーずるいぞ、父さんも混ぜてよ」
「あんた仕事あんだろ」
「年末年始は休みだぞ」
「年末年始だと友里のほうができないだろ」
「んー……よし、着いたぞ」
「友里着いたって……友里?」
「むにゃ…」
「なんだ、寝ちゃったか」
「そうみたい、俺運ぶわ」
「わかった、起こしてやるんじゃないぞ」
「はーい」
ん…なんか浮いてる…?寝ちゃってたのかな…ここどこだろう…
「あれ、起きちゃった?」
「ん……?」
「家着いたとき友里寝ちゃってたから…」
あれ、俺いつの間にか寝てたのか…というかこれは…
(お姫様抱っこされてる!?)
「起きたなら降りる?」
「え……っと………大丈夫」
今日くらい甘えたい…そんな気分だ。燈也ならお願い聞いてくれるよね…
「そっか、とりあえず風呂は入っとこ」
「うん…」
「じゃあ一緒に入るか」
「うん……ん!?」
え、今なんて……
「熱くない?」
「う、うん」
なんでこんなことに…!?
「熱かったら言ってね〜」
「うん…」
燈也と一緒のお風呂なんて狭いんじゃとも思ったがそんなことはないようだ
「それにしても友里細いね〜、ちゃんと食べてる?」
「えーっと…多分」
「多分って何!食べてないんじゃないの?」
「いや…昼と夜は食べてる」
「昼と夜はってことは朝食べてないの?」
「うん…あんま食欲ないから」
「倒れないかな心配、もっと食べな」
心配してくれてるんだな…俺も食べたいけどやっぱり食欲がないとどうしようもない…
「心配してくれてありがと、でもその分間食いっぱいしてるし…」
「流石にそれだけじゃ心配だよ、休みの日まともに運動もしてないでしょ?」
「うっ…」
図星だ…
「友里今体重どんくらい?」
「んー、48kgだと思う…」
「俺より10kgも軽いじゃん」
「そりゃあ燈也身長高いもん」
「あはは、友里ちっちゃいからか〜」
「なっ…!まだ伸びますけど!」
「えー、伸びなくていいのに」
「なんで…」
俺はずっとチビなんてごめんだ。身長も伸びればかっこよくなれる!多分…
「友里がおっきくなったらだっこできないじゃん」
「そんな理由!?」
「そうだよ?友里だって俺にお姫様抱っこされて嬉しかったでしょ?」
「うぐっ…」
それは否定できない…
「そろそろ上がろっか、この前みたいにのぼせないうちに」
「うん…」
時間は午後10時。俺は睡魔に耐えながら燈也とおしゃべりしている。
「友里〜、明日もデートする?」
「ん…」
「おっけー」
「とーや…」
「ん?どうしたの?」
「大好き…」
「き、きゅうにどしたの…」
「なんでも〜?」
「友里眠い?もう寝よっか?」
「ん…じゃあ…」
「なあに?」
「ちゅーしよ…」
「えっ」
…あれ?今俺なんて…
「仕方ないなぁ」
俺がやっぱなし取り消そうとしたが間に合わなかったようで燈也の唇が俺の唇へと触れた。
「おやすみ」
燈也はそう言って部屋の電気を消した。
「おやすみ……」
それにしても今日はとっても楽しかったな、みんなでゲームをして、お昼を食べて、映画を見て、高そうなお店で美味しいボロネーゼを食べて……それにあんなに良いものをもらって。
こんな幸せな時間が永遠に続いてほしいな……
去年は一人さみしくケーキを食べすぐ寝ていた。高校生にもなったしプレゼントは貰っていない。
でも今年は違う。だって燈也と付き合ってるんだもの!
「ゆーりっ」
「ひぁ」
突然声をかけられたものだから変な声が漏れた。
「ははっ!かわいい〜」
「びっくりした…」
「よしよし、一緒に帰ろ」
「いいよ、二人は?」いつもは高橋や山本もいるが今日は見当たらない
「二人で帰ろっ」
「えっ」
「ん?俺と二人きりヤダ?」
「いや、そうじゃなくて…」
燈也と二人きりで帰ったら燈也ファンたちに刺されるかもしれない…なにげに最初から二人きりは初めてな気がする。
「じゃ、強制連行!」
「え?何…」
俺が何をするのか聞こうとした途端燈矢に担がれた。
「えっ!ちょ!おろして!」
「玄関着いたらね〜」
「ちょっとー!」こんなの更に目立つのに!
でもさすが陸上部、一瞬で到着した。
「よっと、とーちゃーく」
「は、速かった」
「あー、絶叫系だめだったっけ」
「いや、ギリ乗れる…」
「ギリってなんだよ」
「乗れなくはない…」
「じゃあ担がれるの嫌?」
「い、嫌じゃないけど…手繋いでる方が好き」
もちろん、こんなこと大声で言えるわけもなく玄関の音にかき消されて誰も聞こえないようなボリュームだった。
「そっか、じゃあ手繋いで帰ろっか」と燈也が耳元で囁く
「聞こえてたの…?」
「もちろん」
マジか…今のが聞こえるだなんて相当な地獄耳だな…
「じ、じゃあ校門出たらね」
「わかった、靴履き終わったね?」
「うん?」なんだか嫌な予感がする…
「じゃ、飛ばすぞ」
また教室の時みたいに体が浮いた。
「え!?また!?」
「担いじゃダメなんて言ってないでしょ」
「うっ…」
(言えばよかった…)
「しゅっぱーつ!」
そのまま燈也は目にも止まらぬ速さで校門まで駆け抜けた
「……あんなに速い月嶋初めて見た」
「俺も……」
そして瞬く間に校門を過ぎ、人通りが少ないところで俺は降ろされた
「とーちゃーく」
「は、速い……」
「じゃ、帰ろ」
「うん」
俺が頷いた途端燈也は俺の手を握った。
「明日って暇?」
「うん。一日中暇だよ。」
「じゃあ一日中デートしよっか」
「い、いいけど…」
「チンピラにカツアゲされないでよ?」
「流石にされないよ」
「ほんとにー?」
「ほんとに」
多分、されない………燈也といればなんとかなるだろうし
「あ、そうだ。蒼真も友里に会いたいって、だから午前中家来れる?」
「いいよ、何時くらいがいい?」
「んーまぁ9時くらいなら」
「りょーかい」
そんなこんな話している間にいつもの道へと出てしまった。
「じゃあ、バイバイ」俺は少し惜しそうにしながらも手をほどいた。
「……ねぇ、家までついてっていい?」
「…?いいよ」こんなに悲しそうな燈也は初めて見た。それに俺ももうちょっと一緒にいたかったしちょうどいい。
「ありがと」
そういった燈也の顔はさっきと比べてみるとちょっと嬉しそうだった。
燈也もかっこいいだけじゃなくてこんな可愛いところもあるんだな。これがギャップ萌えというものなんだろう。
「…そういえば俺おっきくなったんじゃない?」
「確かに最近友里の顔近い気がする」
「でしょ〜このまま燈也も抜くから」
「ふふっ、じゃあ俺ももっとおっきくなろっかな」
「…それでも抜くから」
「頑張ってね」
「うん」
「あ、そうだ!」俺が頷くと燈也は何かを閃いたようだ
「何?」
「友里このあと暇?」
「うん、一応…」
「じゃあ帰ったらデートしよっか」
「えっ」
「それならもっと一緒にいれるよ」
「確かに…」そうか、別にデートは明日だけってわけじゃないしな。この後ちょうど暇だったし好都合だ。
そんな話をしていればいつの間にか家の前に着いた
「じゃあ決まりな」
「うん、また後で」そう言ってまた手を振りほどこうとした瞬間燈矢の方へと引き寄せられた。
「じゃあね、迎えに行くから」
「うん…」
燈也に一旦別れを告げ家へと入っていく。
家は今日もとても静か。母は仕事が忙しくてあまり一緒にいた記憶がない。
高校に入ってからもちょくちょくバイトをしてるからさみしいなんて思ったことはあまりない。それにおんぶにだっことまではいっていないし、お金もちゃんと入れている。
ただ俺は学生だから足りるわけもない。だから仕方ないと思うことにしている。
高一のときは寂しさをバイトで紛らわせていたがきつかった。
俺の誕生日は2月だからまだ先だけど今からすでに楽しみな自分がいる。
机の上にはいつものようにお小遣いとメモがある。自分も苦しいはずなのに週1で5000円を置いてくれる。俺は自炊もできるので冷蔵庫の中にあるもので自分と母で2人分の料理を作っている。母さんが帰ってくるのは深夜だからいつもはラップをして冷蔵庫に入れている。
(とりあえず着替えも終わったし母さんの分だけでも作るか…)
俺は別に外で食べても問題ない。今日はこのあとデートだし……
「あ!デート!」
すっかり忘れていた…料理していたら間に合わない…そんな事を考えている間に玄関のチャイムが鳴った。
「…帰ったら作るか」
とりあえず母さんにはLIMEで『今日燈也と遊ぶ約束してるから帰るのちょっと遅くなるかも』とだけ伝え玄関の扉を開けた。
「おまたせ」
「友里の私服かわいいね、じゃあ行こっか」
「う、うん…」
勘弁してくれ、俺のライフは少ないんだ……褒められ慣れてもないからなおさら…
「友里どした?俺の顔になにかついてる?」
「いや…その…なんでもない……それより早く行こ」
「…おう、そうだな」
(褒められて嬉しかったなんて恥ずかしくて言えないし…まともな言い訳も思いつかなかった…)
「そういや友里って大学行くの?」
「えっ、うんそのつもり」
「どこの大学?東大?」
「東大は…多分無理」
「無難に北大?」
「んー、北大までならなんとかなると思う」
「友里はどこに行きたいの?」
「えーっと……」
考えたこともなかった。俺はどこに行きたいんだろうか…
「俺は別に友里の行きたいところならどこでもいいよ?なんなら勉強教えるし」
「あ、うんありがと」
「ま、この話はまた今度でいっか」
「そう…だね」
「まぁ勉強なら山本のほうがいいか、あいつ教えるのうまいし」
「そうなの?」
「ああ、でもうまいけど厳しいというか…」
「……でも俺燈也に教わりたい。燈也と勉強するの楽しいから。」
「友里……!」
そして燈也は嬉しそうに俺を抱きしめた。それに燈也のいい匂いがして赤くなる。
「いい匂い…」つい言葉が漏れてしまった。それも燈也はしっかり聞いていたようだ。これだけくっついているのだから聞こえないほうがおかしいまである
「でしょ?俺もこのヘアオイル気に入ってんの」
「へあ…おいる?」おしゃれに疎い俺には聞き慣れない言葉だ。
「そう、髪につけるオイル」
「シャンプーとは違うの?」
「うん、シャンプーより匂い強くなった感じ?」
「香水みたいなもん?」
「そだね、髪につける香水って思えばいいかも」
「そうなんだ…あ、それってなんの匂い?甘いような…」
「ああこれ?バニラだよ」
「バニラってあの?」
「そう、バニラアイスのバニラ!まぁ正確にはバニラビーンズだけど」
「アイスってわけじゃないんだ」
「あ、そうだ友里も使う?」
「え?」
「今日俺とおんなじの買ってあげる」
「ほんと!?ありがと!」
「…どういたしまして」
燈也をよく見ると耳が赤くなっている。
「ふふっ、燈也耳赤いね」
「これは………寒いから…」
キモがってなんかなかったんだ。そう思うとさっきの気持ちも晴れ嬉しくなった。
「じゃあ俺が温めてあげる」そう言って俺は燈也の手を取った
「っ……」
「えへへ…どう?あったかい?」
「まだ寒いから抱きしめてよ」
「えっ……」
でも付き合えた今なら……とちょっとだけ燈也に抱きついた。抱きついたと言えるのかわからないけど……
「あったまれた、ありがと友里」
「ど、どういたしまして…」
今思い出すとすっごく恥ずかしい。こんな道端でイチャイチャしちゃった……
「…あれ、そういえばどこ行くの?」
行き先は聞けてなかった。結構歩いた気がするがどこに行くか見当がつかない。
「こっちだよ」
そう言って燈也は俺を人気のない道路へと引っ張る
「着いたよ」
連れてこられた先は見たことないようなきれいな外装の小さなお店だった。なんだかシーンとしていてちょっと怖いような…
燈也はそんなことも気にせず扉を開ける
「やっほー!来たよー!」
「いらっしゃ〜い」
お店の奥から出てきたのはメガネを掛け、緑のエプロンを着たお姉さんがだった。
「あら、その子燈也くんのお友達?」
「あ、は…」
「いや?彼氏」
(え!?言っちゃうの!?)
男同士で付き合ってるだなんて…変な目で見られるんじゃ…
「なっ…彼氏!?」
「その…変ですかね…」
「いいじゃない!最高だわ!」
「……え?」
「二人はどういう関係?幼馴染?クラスメイト?」
「小学校の頃から一緒、中学以外」
「幼馴染カップル!」
「えーっと…この人は?」
「あー、俺のいとこ」
「どうも〜菅原晶子です」
「この人腐女子だから彼氏って言っても大丈夫だよ」
「…あれ、じゃあこの子って前言ってた好きな子?」
「そう、その子」
「そう!じゃあ好きなスイーツ食べさせてあげる」
「ここそういう店だろ」
「ここってカフェなの?」
「そうよ!ここ私のカフェなの〜」
「穴場なんだぜここ、晶子さんの腕前プロだから」
「やだも〜お世辞〜?」
「お世辞なわけ無いでしょ〜」
「褒めても何も出ないからね〜」
「じゃあ早速頼もっか、友里」
「うん」
それにしても内装もとってもきれいだ。おしゃれで静かで落ち着く。机の上には申し訳程度にクリスマスツリーの置物がある。
「決まった?」
「え、あ、じゃあプリンで」
「俺シフォンケーキ」
「は~いお飲み物はどうしますか?」
「俺いつもの、友里は?」
「オレンジジュースで」
「ご注文承りました〜」
「…ここって菅原さん一人で経営してるの?」
「そだね、晶子さん一人」
「大変じゃない?」
「どうかね、週休3日もあるしそこまで大変じゃないと思うよ」
「そうなんだ」
「それに穴場って言ったろ?常連さんいるけど初めての人ってそんなにこないんだよね」
「でも潰れたりしないの?」
「いや、あの人も結構金持ちだから」
「あの人?」
「俺の叔父さん、確か投資家だっけ?」
「そうね〜、はいこちらどうぞ」
「美味しそう…」
「じゃあ食べよっか」
「燈也のコーヒー?」
「うん良い豆使ってんだよね」
「へぇ〜、ブラックで飲むの?」
「うん、いつもブラックだよ」
「すご、かっこいい」
「そ、そう…」
(はぁ〜!燈也くんこんな顔できたのね…佐野くんもかわいい…)
「晶子さんどした?顔になんかついてた?」
「え?いやなんでも…」
燈也と菅原さんが話してる間に俺は生クリームやいちごがたっぷり乗っているプリンを口に運んだ
「んー!このプリンすっごい美味しいです!」
「そう?お口に合ってるみたいでよかったわ〜」
「友里、俺にも一口ちょーだい」
「いいよ、あーん」
「ん、ありがと、じゃあ俺のもどうぞ」
「いいの?じゃあ…」
俺は燈也からもシフォンケーキをもらう。シフォンケーキも口に入れた瞬間甘いクリームとスポンジがいい感じに合わさりとても美味しい
「ケーキも美味しいね」
「だろ?よかったらもっと頼む…って晶子さん!?」
ふと菅原さんの方を見ると顔が赤くなったまま倒れていた
「え、ちょ大丈夫ですか!?」
「ん…ああ、気にしないで久々にいいもの見れたから…」
「知らない間に連続で働いてたんじゃと思ったけどそんなことなかったわ…」
「ごめんなさいね、また後で〜」そう言ってそそくさと店の奥へと消えてしまった…
「…ほんとに大丈夫なのかな」
「あの人昔からああいう人だから…」
「そうなんだ…?」
「それより食べちゃおっか、買い物もいかなきゃ」
「そ、そうだね」
そして俺達は急いで食事を終わらせた。
「友里先出てていいよ俺が払っとく」
「え、悪いよ俺が払うから」
「いいの、俺が連れてきたんだし」
「でも…たまには俺にもカッコつけさせてよ」
「んーじゃあお言葉に甘えちゃおっかな」
「じゃあ外で待っててね」
「うん」
燈也が外に出たのを見送り、俺は会計をするため財布を取り出す
「すみませーん」
「はーいちょっと待ってて〜」
そう言って店の奥から出てきたのは鼻つっぺをした菅原さんだった
「え!どうされたんですかそれ!?」
「いやぁ…ちょっと鼻ぶつけちゃって…」
「そうなんですね…お大事に…」
「ありがと、それでお会計でしょ?」
「あ、はい」
「ほんとは1573円なんだけどクリスマスだから特別に10%OFFの1430円でいいわよ〜」
「え、いいんですか?」
「まぁ明日休みだし大丈夫よ」
「あ、ありがとうございます」
「いえいえ」
「それじゃあちょうどで、ありがとうございました」
「こちらこそ〜またきてね」
菅原さんに笑顔で手を振り返し俺は店を出た。
「おまたせ、行こっか」
「おう」
「いつもどこで買ってるの?そのヘアオイル」
「ドラッグストアとかに売ってるよ」
「そうなんだ」
「ちょうどそこにあるから寄ろ」
「うん」
それにしても今日は一段と寒い…さすが北海道と言ったところだろうか…
「友里どした?寒い?」
「えっ…っとちょっと…?」
「じゃあこうしよっか」
そう言って燈也は俺の手を握り自分のポケットに入れた。
「!?」
「友里の手冷たいね」
「…うん」
ドキドキして落ち着かない。こんなんで明日のデート大丈夫なのかよ…
(でも…)
燈也の手…あったかい…俺の手を優しく包んでくれて…
「着いたよ」
「あ、ありがと…」
「もうちょっとつなぐ?」
「店の中ではいいよ……外でなら」
「うん、じゃあ外でつなごっか」
「……」燈也を見てられない…ぶっ倒れちゃうかも…
「あ、これこれ」
「何が?」
「これが俺のヘアオイル」
「へぇ~…え!?」
(5000円!?高っ!)
5000円以上もするとかドラッグストアで売っていいのかよ…!
「いやぁ…でも俺やっぱり…あれ!?いない!?」
「1点で5060円となります」
「はーい」
「え!?」
気づけば燈也はレジに並んでいた。しかも会計まで…
「悪いよ…こんなに高いとは…」
「いいよ全然あんな安いの」
「え、安くなんかないでしょ」
「友里のために買いに来たんだから、友里が喜んでくれればそれで充分」
燈也は優しいな…俺がこの匂い好きとか言わなければこんな買い物しなくてもよかったのに…
「明日も早いし帰ろ」
「うん…」
「明日のデート楽しみだね」
「うん」
「あ、そうそうヘアオイルつけ過ぎたら臭いから気をつけなよ」
「うん、気をつける」
「あと毎日ヘアオイルだと髪も痛むから程々にね」
「そうなの?」
「うん、ヘアオイルってオイルだから髪の毛の潤い?逃がしちゃうんだって」
「?うん?わかった?」
「んー簡単に言うと水と油みたいな?水と油って混ざらないだろ」
「あー」
「そゆこと」
「詳しいね」
「まぁ俺も勉強したからね」
「そうなんだ?」
「友里の隣に立ってても恥ずかしくないように」
「…それって俺がする側じゃ…燈也顔いいじゃん」
「言うて友里も顔面偏差値高いと思うよ」
「そんなことない」
「そんな事ある」
「…ほんと?」
「ほんとだよ?友里ってまつ毛長いよね〜」
「それは…言われるかも」
「二重もきれいだし…」
「えへへ…そう?」
「…友里って家庭的だしかわいいし…非の打ち所がないよね」
「そんなことない、俺成績普通だし…それを言うなら燈也だってイケメンで頭もいいし背高いじゃん」
「でも俺家事全くできないからさ、そこそこ勉強できて優しくて家事もできる友里のほうがハイスペだよ」
「うーん…そうなのかな…」
「そうだよ〜友里は俺の自慢の彼氏なんだから」
「ありがと…」
こんなに褒められちゃった…そもそも俺が家事できるようになったのは父さんがいなくなって母さんが仕事で忙しくなったからだ。それまでは全くできなかった。
「その…今日は色々ありがとう」
「どういたしまして」
「じゃあまた明日」
「うん、ばいばい」
――翌日
「フンフン♪」
朝から鼻歌を歌いながら燈也の家へと向かう。
午前中は蒼真くんの希望で燈也の家でおうちデート。ちゃんと弟思いで優しいな。
「お、友里」
「友里兄ちゃんいらっしゃい!」
「お邪魔します」
二人に出迎えられてから、俺は家の中へと入る。
「友里早速あれ使ってるんだ」
「うん、臭くない?」
「全然」
「あら佐野くん!いらっしゃい!」
「こんにちは」
「お母さん呼びでもいいわよ〜佐野くんも家族みたいなもんだし」
「そんな、恐れ多いです」
俺が戸惑っていると燈也が俺の腕を引いて部屋へと連れて行ってくれた。
「よっしゃー!コインゲット!」
「俺のコインだぞ!」
「ふふっ」
いつもこんな兄弟喧嘩をしているのかな?相変わらず仲が良くて安心する。俺は一人っ子だから羨ましいな…
「みんなー!できたわよー!」
「はーい」
「一旦終わりな」
「はーい…」
「友里も行こ」
「え、いいの?」
「いいの、母さんも友里の分用意してると思うよ」
「友里兄ちゃんがいいなら!」
「あ、じゃあいただこうかな…」
「「やったー!」」
一旦ゲームを終わり食卓へと向かった
「めしあがれ〜」
食卓にはフライドチキンやナポリタンなんかのごちそうがずらりと並んでいた。
「こんな時間からいいんですか?」
「夜外で食べるんでしょう?ならお昼に食べちゃいなさい」
「え、そうなの?」
「家で食べたかった?」
「いや…別にいいんだけど」
「それに…」
「それに?」
「いや、なんでもない。早く食べよ!」
「うん…?いただきます」
何を言おうとしてたんだろう…
「えー!俺も食べに行きたい!」
「蒼真はまた今度な、今日はお留守番」
「えー!」
「燈也が食べない分ケーキとかいっぱい食べれるわよ」
「それもそっか」
(いいの!?)
「燈也たちも先に食べてきなさい」
そう言って瑠那さんはケーキを一切れ出した。
「ありがとうございます」
「いえいえ」
俺がケーキを受け取った瞬間蒼真くんが声をかけてきた
「ねぇ…友里兄ちゃんこれ食べたら行っちゃうの?」
「んー、多分…ごめんね」
「ううん…いいの、でもまた遊んでね」
「もちろん」
「約束だよ!」
「うん」
「友里ほっぺクリーム付いてるよ」
「え、ほんと?どこにある?」
舌で探すが見つからない。その時燈矢の指が肌に触れた。
「取れたよ」
「ありがと…」
舌で探してたのけど見つからなかったし…それを燈也が取ってくれたり…色々重なってとても恥ずかしい
「ごちそうさまでした…」
「もっと食べてもいいのよ?」
「いえ、大丈夫です」
「そう?まぁ二人とも気をつけるのよ」
「わかってるよ」
「はい、気をつけます」
「いってらっしゃい」
「いってきます」
玄関まで見送りに来てくれた蒼真くんに別れを告げ、俺達は家を後にした。
「それにしても蒼真のやつだいぶ友里に懐いたよな、何したの?」
「いや…俺もよくわかってない」
「そっか」
蒼真くんは燈矢を俺に取られたと思っていただけだ。それも今は和解してだいぶ仲も良くなった。
「今日はどこ行くの?」
「ん?今流行りの映画見に行く」
「それって鬼殺の勇者?」
「そうそれ」
ちょうど気になってたやつだ。アニメも漫画も全部見てて好きな作品の一つ。
「鬼殺見てなかった?ネタバレになっちゃうしやめとく?」
「いや、全部見てるよちょうど見たかったから」
「そう、ならよかった!」
燈也の笑顔が眩しい。俺が鬼だったら多分灰になって消えてる…
「あ、晶子さん」
「えっ、なんでここに燈也くんが!?」
「今日この後鬼殺の映画見に行くから」
「どうも…」
「奇遇ね〜私も見に行くところなの」
「そうなんですか!じゃあ一緒に…」
「あ!友達待たせてるんだった!じゃあねー!」そう言って菅原さんは逃げるように走り去っていった
(行っちゃった…)
「…混む前に俺達も急ぐか」
「うん」
「乗って」
「…え?」
燈也は背中に乗れと言わんばかりにかがみだした。
「いいから乗って」
「ひ…人来ちゃう」
「だから乗るの、早くしないと映画始まるよ」
はいを押さないと進めないタイプだ……こうなると断れない…
俺は仕方なく燈也の背中に乗った。燈也の背中は大きくてガッチリしている。
「飛ばすよ、掴まってて」
「うん」
俺が燈也の肩を掴んだ途端燈矢の雰囲気が変わった。ボルトもびっくりの速さで人混みを駆け抜けあっという間に映画館へと着いた。
「着いたよ、大丈夫?」
「うん…なんとか」
まだ始まるまで30分以上あるというのに映画館は人がとても多かった。
「ポップコーン買ってくるけど何味がいい?」
「キャラメルで…」
「飲み物は?」
「コーラ」
「おっけー、じゃあ待ってて」
「うんわかった」
それにしても人多いな…鬼殺目当てじゃない人もいるんだろうけどさすがの人気だな…
「おまたせ」
「え、もう!?」あまりにも早すぎる。だってこんなに人がいるのに…
「いやぁ…なぜかお先にどうぞって…」
人混みの方を見ると燈也をチラチラ見ている人がいたりこちらに小さく黄色い歓声が上がっている。
これもイケメンパワーなのか…?何もしてないのに道を開けられるなんて
「友里?どうかした?」
「え?あ、いやなんでもない」
「じゃあ行こ」
「うん」
そのままポップコーンと飲み物を受け取り指定された席に座る
「人多いね…」
「まぁ鬼殺だからな」
「早めに来れてよかったね」
「そだね、もうちょっと遅かったら友里人混みに流されてたかも」
「確かに」
そんな話をしている間に場内がだんだんと暗くなっていき、おなじみのカメラ人間とパトランプ人間が映し出される
「友里のポップコーンちょうだい」
「うんいいよ」
「ありがと、俺のも食べたくなったら取ってって。ずっとキャラメルだと飽きるかなって塩味頼んできたから」
「うん、じゃあ後でもらうね」
ポップコーンの交換こをしていると映画怪盗も終わり本編が始まった。
鬼のトップ、鬼舞山無惨やその部下の鬼たちとの最終決戦。最初から迫力満点だった。
(喉乾いた…)
俺はおもむろにドリンクを飲む。だが味はコーラではなくジンジャーエールだった。戸惑っていると隣から燈也がとても小さな声で話しかけてきた
「それ俺の…」
「あ、ごめん…」
「…間接キスだね」
「なっ…たしかに…」
間接キスしちゃった…付き合ってるから余計意識しちゃう
「ほんとごめん…俺のだと思った」俺が小さくそう言うと燈也は何かを思いついたかのようにこちらを見る
「じゃあ友里のコーラもちょうだい」
「えっ…!?」
燈也は俺のコーラに手を伸ばし飲みだした。
「ちょっと…」
「これで一緒、映画見よ」
「……勝手に飲むなよ」
「ごめん」
「……燈也ならいいけど」
「…かわいい奴め」
その後はドキドキしてあまり覚えてない。いつの間にかエンドロールが流れだした。
「終わっちゃったね、続きいつ来るのかな」
「……」
「友里?」
「…あ、うん楽しみだね…」
「コーラ飲んでほしくなかった?」
「いや、全然…それは嬉しかった…」
「…照れちゃった?」
その問いに小さく頷く。それを見た燈也はニヤリとした。
「じゃあ間接じゃないキスする?」
「えっ、ここで!?」
「え、ここでしてほしいの?」
「いや…そうじゃない…」
「じゃあしたい?」
「……うん」
俺は燈也にだけ聞こえるようなボリュームで呟いた。
燈也は優しく俺の頭を撫でて微笑んだ。
「そっか、じゃあ後でいっぱいしてあげる」
「うん」
「じゃあそろそろ行こっか」
「どこに?」
「いいところ」
「?」
「じゃあ、しゅっぱーつ!」
「しんこー!」
「着いたよ〜」
「ここ…!」
連れてこられた場所はイルミネーションが綺麗なおしゃれでとても高そうなレストランだった。
「きれー!」
「でしょ?」
「でも高そう…」
「えーそう?」
「俺あっちのゴストでいいよ…」
「えー…でも予約入れちゃった」
「よや…!?」
予約制なら相当高いんじゃ!?でも予約されてる手前断るわけにもいかない…
「しかたない…キャンセル」
「しなくていい!」
「え?でもここ嫌なんでしょ?」
「嫌とは言ってない…ただ高そうだから…」
「気にしなくていいよ〜俺が払うし」
「申し訳ないから…」
「気にしないで、友里のためにここ予約したんだから」
「俺こんなところ来たことないけど…」
俺は庶民だ。御曹司の燈也とは違い、こんなところに来るお金なんてない。
「だからだよ」
「え?」
「たまには贅沢させてあげたいから。それでいい思い出になってくれれば嬉しいなって…」
「っ…!」
俺のために映画だけでなくこんないいところまで予約してくれたんだ、やっぱり燈也は優しいな…
「あ、もう時間だ、早く入ろ」
「うん、わかった」
燈也に手を引かれ俺はレストランへと入っていった。
「予約の月嶋です」
「月嶋様ですね、お待ちしておりました!こちらへどうぞ」
(おお…)
店内はめちゃくちゃ豪華。パーティでもするんじゃないかってくらい明るく、上品。本当に俺が来てよかったのだろうか…
「友里はなに頼む?」
「えーっと…じゃあ…」
恐る恐るメニュー表を見るがズラッと並んだメニューの値段はほぼすべて4桁を超えていた。一番安いのは600円のコーンスープ。これだけじゃ腹は膨れない…4桁の中でも一番安いオムレツを頼もう…
「ご注文をお伺いいたします」
「俺はハンバーグで」
「じゃあオムレツで…」
「えーそれだけで足りる?」
「さっきポップコーン食べたし…」
そう言った途端俺のお腹の音が大きく鳴り響いた。周りからは小さくクスクスと笑い声が聞こえる。最悪だ…初めて来たのにこんな…しかも彼氏の前で…
「ははっ、さっき走ってきたからおなかすいてんじゃん」
「うっ…」
「遠慮しなくていいよ、俺に気遣ってくれるのは嬉しいけど俺は友里がお腹いっぱい食べてくれるのが一番嬉しいんだから」
やっぱり燈也は違うな…こんな時まで俺のことを優先してくれて…いくらお小遣いがあるからって最近お金を使いすぎてるんじゃないか…ヘアオイルだったり映画だったり…決して安くないのに
「…じゃあこの…ボロネーゼで」
「かしこまりました、麺やソースの量やグラムはどういたしましょう」
「ハンバーグは200gで」
「え、量とか決めれるの?」俺の知ってるレストランはこういうのは量が決まっている
「はい、こちらではお客様にあった量でご提供させていただいております。小、並、大、特盛がございます。並が普通サイズで小は並に比べ少ないため100円ほど減額いたします。もちろん多くなれば追加料金が発生いたしますが…」
「そうなんですか、じゃあしょ…」
小でいいですと言おうとしたが流石にここでも気を遣えば嫌われてしまうかもしれない…ここは正直に行こう…
「お、大盛りで」
「一緒にお飲み物はいかがですか?」
「じゃあオレンジジュースで」
「俺も同じのを…」
「かしこまりました、少々お待ちください」
「はーい」
「…ねぇほんとにいいの?」
「何が?」
「だって最近お金いっぱい使ってる気がして」
「遠慮しないでって言ったでしょ?それにこの店のオーナー父さんだから」
「…え!?そうなの!?でも社長なんじゃ」
「あの人忙しい人だから」
「そうなんだ…?」
よくわかんないな…
「そうだ!食後にデザート頼む?」
「え、いいの?」
「もちろん、後からも注文していいんだよ」
「そうなんだ…じゃあショートケーキ」
「俺にチョコケーキしよ」
「お待たせいたしました、こちらボロネーゼとハンバーグでございます」
「あ、ありがとうございます…」
俺は先に自分のボロネーゼとオレンジジュースをもらう
「追加で食後にショートケーキとチョコケーキくださいな」
「かしこまりました、それではお食事が終わり次第またお呼びください」
「はーい」
こんな店でも食後に注文できるんだな…装飾や値段はともかく普段行くようなファミレスに似てるんだな…
「冷めないうちに食べちゃお」
「うん」
俺はボロネーゼを一口運んだ。その瞬間トマトの甘酸っぱい香りともちもちの麺が口の中でとろけて今まで食べたことがないくらい美味しかった。
「美味しい?」
「うん、めっちゃ美味しい」
「そっか、よかった」
「って…もう食べ終わったの!?」
知らない間に燈也のハンバーグは一瞬にして消えていた。まだ10分も経ってないのに…
「俺が一番走ったから…」
…確かに振り返ってみれば俺を背負って映画館だったりレストランだったりを全速力で走っていた。
「今日はほんと、ありがとね」
「へへ、どういたしまして」
「そうだ、今日はね燈也にプレゼント持ってきたの」
「プレゼント?」
「そう、今は渡せないから後でね」
「はーい」
俺も負けてられない。急いでボロネーゼを夷らげ、デザートを頼む。
「ここのケーキ甘くて美味しいね」
「でしょ?晶子さんとこも美味しいけどここも結構おすすめなんだ」
「へー…」
そうなんだ、でも正直菅原さんのお店のほうが良心的な価格だからそっち行くだろうけど…
「あ、友里ほっぺにクリーム付いてるよ」
「え」
俺が取ろうとした瞬間燈也の指が俺の頬を撫でる。
「うん、美味しい」
「……ちょっと…」
こんなところでイチャイチャしちゃっていいのか…?まぁ見られてないようでとりあえず安心…
「美味しかったね」
「うん…その…トイレ行きたいんだけど…」
「あー、それならレジの隣にあるから行ってきな」
「うん待ってて」
「はーい」
(うう…こんなんでこれ渡せるのか?)
ドキドキして渡せれない気がする…燈也が悪いんだ…俺をドキドキさせるから…
「おまたせ」
「じゃ、いこっか」
「え?会計は?」
「もう済ましてる」
「え!?俺も払うよ、いくらだったの?」
「大丈夫だよ」
「でも…」
「んーじゃあさ、プレゼントちょうだい」
「それは外でね」
「じゃ早く外出よ」
「うん」
「みんなまたね~」
燈也は店の人に手を振り店を出た
「じゃ、もうちょっと明るいところに行こ…」
「ん?どうした…」
「隠れて!」
「え?」
急に隠れてって…一体何が?路地の隙間から覗くと向かい側に警察?の人がいた
「今何時?」
「8時…」
「こんな時間から補導員いるのか」
「燈也は大丈夫なの?」
「俺は全然、大人ですみたいにしてればいいけど…友里は怪しまれるだろ」
「…わかった」
ちょっとして補導員がいなくなったようで燈也が優しく声をかけてきた
「…よし、いなくなった…出てきていいよ」
「……」
「…?友里?」
「何?」
「…怒ってる?」
「別に」
「ごめんって、機嫌直して」
俺は怒ってなんかいない。高校生だから補導されるのは当たり前だし…そんなことより俺はプレゼントを渡したい。ただそれだけだった。
「元から機嫌なんて悪くない…それよりまた指導員の人来る前にプレゼント渡したい」
「そ、そうだよね!早く行こ!」
「ん…」
俺は燈也の手を握り、大きなクリスマスツリーがある場所へと連れられた。
「ここのほうが補導員いるんじゃ…」
「いや、その分人もいるから大丈夫」
「そう…?」
「そうそう、俺も友里のためにプレゼント用意してんだ」
「そうなの?」
「そりゃあ…クリスマスだし」
燈也は照れているのか頬がちょっと赤くなった。
「じゃあ先に俺からあげたい」
「いいよ、友里のプレゼント楽しみ」
「こ…これ…」
俺は持ってきたバッグからプレゼントを取り出し、燈也に渡した。
「開けていい?」
「もちろん」
まるでサンタからプレゼントをもらった子供のようにはしゃぐ燈也を見て自然と笑みがこぼれる。
「これ…!」
俺が燈也にあげたのはマフラー。ネットで調べて頑張って編んだ傑作だ。
「頑張って編んだの…」
「ありがと、大切にする」
「つけてみてよ」
「わかった」
燈也はもらったマフラーを巻いた。燈也はとてもうれしそうに笑ってくれて嬉しい。
「じゃあ俺からのプレゼント」
そう言って燈也は細長い箱を渡してきた
「なにこれ?」
「開けてみて」
俺はラッピングを丁寧に剥がしてみた。中はめちゃくちゃ高そうなケースが入っていた。恐る恐る開けてみれば中にはダイヤモンドが使われたネックレスがキラキラ輝いていた。
「!?」
「友里もつけてみて」
燈也はネックレスを取り俺の首元へと手を伸ばす
「いや、こんないいものもらえない…」
「ええ、俺この日のために先月から用意してたんだよ」
「そんな前から…?」
俺なんて三日前に編み終わったっていうのに…
「友里はこれじゃ嫌?」
なんだか悲しそう…嫌なわけじゃない。俺なんかにこんないいものきっと似合わないと思ってしまっているだけ。
「…嫌じゃない…ただ…似合わないかもって…」
「……」
嫌われたかもしれない…俺がせっかくのプレゼントを受け取ろうとしないから…
「そんなことないよ」
「…え」
燈也からは想像していなかった言葉が出る。
「このマフラー俺には似合わない?」
「っ…!そんなこと…!」
そんなことない。そう言いかけた瞬間燈也の手が頭に触れた。
「これだって同じだよ、マフラーと同じ」
「え?」
「服じゃないんだからそうジロジロと見られるもんじゃないよ」
「でも…」
「いちいち値段なんて気にしてたらきりがないから…」
「そうだけど…」
「友里だってこのマフラー俺のために編んでくれたんでしょ?俺も友里のために選んだんだよ」
「……!」
たしかにそうだ…俺だって燈也のことを思って作っていたはずだ。燈也も同じ気持ちで俺のために選んでくれたもの。それを値段で拒否しようとした俺は最低だ。
「俺は友里みたいに器用じゃないし家事もできないからこんなのしか用意できなかったけど…」
「…ごめん」
「仕方ないよ、俺の方こそ…」
「そうじゃなくて…燈也が俺のために買ってくれたのに…それを踏みにじって…」
「踏みにじってなんかないよ」
「でも目が覚めた気がする。ありがと、燈也…このネックレスすごく嬉しい」
「ほんと?」
「うん、一生大事にする」
「気遣ってる?」
「そんなことない…本音だから」
「…そういえばさ、プレゼントにも色々な意味があるんだって」
「例えばどんなの?」
「ネックレスだと束縛とか…」
「え…」
「別に束縛しないから…多分」
「多分って…」
「あ、マフラーも束縛だって」
「え、そうだったの?」
束縛って意味があるならやめといたほうがよかったかな…
「でもネックレスの束縛もマフラーの束縛も束縛したいくらい好きって意味らしいよ」
「そうなんだ…」
なんだ、てっきり俺はメンヘラだよって言ってるようなもんだと思ってた…
「俺達束縛カップルだね」
「あはは、何だよそれ」
「…それとさそのダイヤモンドにも意味があってね」
「そうなんだ、誕生石なのは知ってたけどプレゼントの意味もあるんだね」
「そう、その意味なんだけど…」
なんだろう…もしかしてやばい意味だった!?もうすぐ死ぬとか…
「永遠の愛…って意味があるんだって」
「それって……」
「知っててあげたんだ」
「え…」
「あれ、ドン引き?」
「そんなんじゃない、嬉しくて」
俺だって同じ気持ちだ。燈也のことは永遠に愛したい。
「……それじゃあこの先…大学も、その後も一生、一緒にいてくれる?」
「もちろん」
「ほんと?」
「うん」
俺がそういった瞬間燈也は思い切り抱きしめた。
「よかった…」
とっても嬉しそうだな、燈也
俺も燈也をぎこちなくだが抱き返した。
「…大好き」
「俺も」
今が一番幸せなのかもしれない…燈也は温かい。外で冷えた体を優しく包んで温めてくれている。
「帰ろっか」
「うん」
「このまま泊まってく?」
「泊まっていいなら……あ、でも補導されるかも」
「じゃあ父さんに迎えに来てもらお」
「え、いいの?」
「んーまぁ……ちょうど仕事終わった頃だと思う」
「そうなんだ、じゃあ先に待ち合わせ場所まで行こ」
「そうだな、人多いし」
それから10分後俺達の前に一台の高級車が停まった
「迎えに来たぞ〜!」
「この車燈也のお父さんのだったんですね」
「そうだぞ〜!佐野くんもお父さんって呼んでくれていいんだからな!」
「あはは…まだ早いかな」
「それより早く帰ろ、車出して」
「はいはい、じゃあ二人は後ろ乗りなさい」
「はーい」
俺が乗り終え扉を閉めようと手を伸ばしたが自動で閉まる車だったようで勝手に動いた。
「いやぁ、それにしても燈也がこんなに成長するとは…!」
「おかげさまで」
「佐野くんも燈也と仲良くしてやってくれな」
「は、はい…」
こんな高級車初めて乗った…燈也の家本当にお金持ちなんだな……
「それで、佐野くんのお家は?」
「あ、今日泊まりたいなって話してたんですけど……だめですかね」
「おお、そうか!じゃあ泊まってきなさい!」
「はい、ありがとうございます」
「また蒼真と三人でメリパしような」
「うん!」
「えーずるいぞ、父さんも混ぜてよ」
「あんた仕事あんだろ」
「年末年始は休みだぞ」
「年末年始だと友里のほうができないだろ」
「んー……よし、着いたぞ」
「友里着いたって……友里?」
「むにゃ…」
「なんだ、寝ちゃったか」
「そうみたい、俺運ぶわ」
「わかった、起こしてやるんじゃないぞ」
「はーい」
ん…なんか浮いてる…?寝ちゃってたのかな…ここどこだろう…
「あれ、起きちゃった?」
「ん……?」
「家着いたとき友里寝ちゃってたから…」
あれ、俺いつの間にか寝てたのか…というかこれは…
(お姫様抱っこされてる!?)
「起きたなら降りる?」
「え……っと………大丈夫」
今日くらい甘えたい…そんな気分だ。燈也ならお願い聞いてくれるよね…
「そっか、とりあえず風呂は入っとこ」
「うん…」
「じゃあ一緒に入るか」
「うん……ん!?」
え、今なんて……
「熱くない?」
「う、うん」
なんでこんなことに…!?
「熱かったら言ってね〜」
「うん…」
燈也と一緒のお風呂なんて狭いんじゃとも思ったがそんなことはないようだ
「それにしても友里細いね〜、ちゃんと食べてる?」
「えーっと…多分」
「多分って何!食べてないんじゃないの?」
「いや…昼と夜は食べてる」
「昼と夜はってことは朝食べてないの?」
「うん…あんま食欲ないから」
「倒れないかな心配、もっと食べな」
心配してくれてるんだな…俺も食べたいけどやっぱり食欲がないとどうしようもない…
「心配してくれてありがと、でもその分間食いっぱいしてるし…」
「流石にそれだけじゃ心配だよ、休みの日まともに運動もしてないでしょ?」
「うっ…」
図星だ…
「友里今体重どんくらい?」
「んー、48kgだと思う…」
「俺より10kgも軽いじゃん」
「そりゃあ燈也身長高いもん」
「あはは、友里ちっちゃいからか〜」
「なっ…!まだ伸びますけど!」
「えー、伸びなくていいのに」
「なんで…」
俺はずっとチビなんてごめんだ。身長も伸びればかっこよくなれる!多分…
「友里がおっきくなったらだっこできないじゃん」
「そんな理由!?」
「そうだよ?友里だって俺にお姫様抱っこされて嬉しかったでしょ?」
「うぐっ…」
それは否定できない…
「そろそろ上がろっか、この前みたいにのぼせないうちに」
「うん…」
時間は午後10時。俺は睡魔に耐えながら燈也とおしゃべりしている。
「友里〜、明日もデートする?」
「ん…」
「おっけー」
「とーや…」
「ん?どうしたの?」
「大好き…」
「き、きゅうにどしたの…」
「なんでも〜?」
「友里眠い?もう寝よっか?」
「ん…じゃあ…」
「なあに?」
「ちゅーしよ…」
「えっ」
…あれ?今俺なんて…
「仕方ないなぁ」
俺がやっぱなし取り消そうとしたが間に合わなかったようで燈也の唇が俺の唇へと触れた。
「おやすみ」
燈也はそう言って部屋の電気を消した。
「おやすみ……」
それにしても今日はとっても楽しかったな、みんなでゲームをして、お昼を食べて、映画を見て、高そうなお店で美味しいボロネーゼを食べて……それにあんなに良いものをもらって。
こんな幸せな時間が永遠に続いてほしいな……