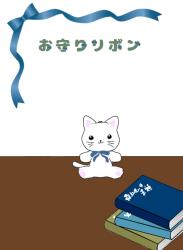今日は待ちに待った文化祭だ。他校の生徒や親なんかも来る一大イベント…とは言っても俺が着るのはメイド服。
「おー!佐野くん似合うねー!」
「そう?はは…」
もともとはクラスの女子からの提案で男子がメイド役をすることになるはずだったが男子は俺とネタに走るのが好きそうな五十嵐。その五十嵐の仕事は後半なので実質俺一人だ
「友里かわいい」
俺が恥ずかしそうに隅で丸まっていると月嶋が声をかけてくる。月嶋はタキシードビシッと決まっていてとてもかっこいい。
「ありがと…」
「もうすぐ始まるよだから…」月嶋がそう言いかけた途端
「え!?莉乃ちゃんメイドできないの!?」
先ほど俺のメイド姿を似合うと言ってくれた女子が驚く。
「うん…ちょっとお腹痛くて…」
「でも佐野くん一人じゃなぁ…誰かやってくれる人いない?」
その声に手を挙げる者はいない。
「私は受付だし…」そんなとき月嶋が手を挙げた
「じゃあ高橋は?」
「え゙」
「高橋くんやってくれる?」
「うーん…それは」
「高橋、今なら俺達4人一緒だぞ」
「んー…まぁ確かにそれなら…」
「ほんと!?ありがと!じゃあこれはい!」そう言って高橋にメイド服を渡す
「あ、はい…着替えてきます」
「急げよ〜」月嶋は高橋にそう言って自分の仕事の準備に戻る。俺も戻ろうとしたその時山本が声をかけてきた
「なぁ佐野、ちょっといいか?」
「ん?何?」
「後半さ、月嶋と二人きりで回ったらどう?」
「え?二人も一緒じゃないの?」
「お前も月嶋と二人のほうがいいだろ?俺らはいいからさ」
「…じゃあお言葉に甘えて」
「うん、じゃあ位置について」
「はっ、もうこんな時間!」
「ただいまー」高橋が戻ったと同時に開始のチャイムが鳴る
「じゃあみんな頑張ろー!」
「おー!」
「兄ちゃん来たよー!」
記念すべき最初のお客様…いやご主人様?は蒼真くんだった。
「蒼真じゃん久しぶり〜」
「隼人兄メイド服きてんの?似合うじゃん」
「そうか?あんま嬉しくねえな」
「蒼真一人で来たのか?」
「お母さんと来た」
「燈也ー!来たわよー!」
「げ…」
「お!もしかして月嶋くんのお母さんですか?受付お願いしまーす」
「そうなのよ〜燈也ったらこの前…」
「わ゙ー!席ご案内しますね」
「もー燈也ったら…って佐野くんと山本くん?」
「「ゲッ」」思わず声が揃ってしまう
「やだ〜二人ともかわいいじゃない」
「はは…どうも」
「…あ、ありがとう…ございます」
山本はタキシードだからまだいいが俺はメイド服だ。恥ずかしくてあまりうまく話せない。
「宏太兄かっけー!兄ちゃんの次くらいに」
「あっそ…ご注文は?」
「じゃあ俺オムライス!」
あ、俺には触れないのね…俺的にはいいんだけどなんかさみしいような
「お待たせしましたー」
(え!?はや!)
「サービスとしてメイドさんがケチャップでハート描いてくれまーす」山本はそう言って俺の方を見る。
「え!?俺!?」
「はいどうぞ」そう言いケチャップを握らせてきた
「友里描くの?」
「佐野くんが描いてくれるっていいじゃない」
「ふーん」蒼真くんがこちらを睨む
「ヒイッ」
「こら、そんな顔しないの」
「じ、じゃあ描かさせていただきます」
さっさと終わらせよう…ただでさえ恥ずかしいし…俺は心のなかでそう言いながらオムライスにハートを描いたその時
「続いてはおまじないをかけてもらいまーす」
「は!?」山本のその一言に思わず声が出る
「いいじゃんそのほうがメイド喫茶っぽいだろ」
「ええ…」
月嶋と高橋は他の人対応してるし…始まったばかりで客があまりいないのが救いだ。まぁ教室の外は観客ですごいけど…
「まだ〜?」
「はいただいま…って何するんですか」
「何って記念に撮っておきたくて…ダメだったかしら」
「全然オッケーですよ」そういったのはまたもや山本だった。
「なっ…」
「お詫びとしてチップ払っとくから!」
「う…お、美味しくなあれ萌え萌えキュン…」
「ありがと~!はいこれ」そう言って月嶋ママは俺にチップを握らせる
「お会計のときに…」
「あ、そうよねじゃあまた後でね」
「はい…」(なんとか終わった…)
「佐野、お客さん」
「はーい」俺が振り向くと入口には母さんが立っていた
「あら友里!随分とかわいい格好しちゃって」
「あ…」
終わった…こんな姿見られたくないランキングトップ2の二人に見られてしまった…ちなみにもう一人は月嶋ママ。好きな人の母親に見られるのもだいぶ気まずいっていうのにもっと気まずい自分の母親って…
「佐野、俺は蒼真んとこ行くから席案内してあげて」
「あ、はーい…」
(なんで自分の母さんを案内させられるんだ…!山本のバカ!)
これも仕事だ…仕方なく席を案内する。
「…席ご案内します」
「緊張しなくていいのよ〜」
(緊張というよりあんま見られたくないんだよ…!)
おしゃべり好きな母さんだからできるだけ月嶋ママたちからは離れた席に案内しようとしたのだが…
「こちらになります…」
残念なことに真隣しか空いていなかった。もし話されでもしたらいろんなことを全部吐き出してしまいそうだから不安だ。
そして案の定…
「あら?もしかして瑠那ちゃん?」
「ええ…ってもしかして優香!?」
「久しぶり〜」
(げ…知り合いだったのか…)
まあ、それもそうか小学校が一緒だったことを覚えてるくらいだし…ふと月嶋を見るとこの世の終わりのような顔をしていた。
月嶋が俺に向かってぼそっと「なああれ友里の母ちゃんだよな」と聞いてきた。俺は小さく頷く。
「俺の母さんあることないこと全部言ったりしそうだからさ…」
「そうなの?」
「ああ、この前なんて…」月嶋はそう言いかけたと思ったら「やっぱやめた」と言った。
「なにそれ気になるじゃん」
「それは…」月嶋がそう言いかけた瞬間
「え!?燈也くん彼女いなかったの!?」そういったのは俺の母さんだった
そして月嶋ママが「そうなのよ〜あの子ったらどうしてもゆ…」と言おうとした瞬間
「お話の途中すみません!ご注文お伺いします!」月嶋が声をかき消すかのように話しかける。
「あら燈也くん元気にしてた?」
「おかげさまで…」
「そう?よかった~、じゃあふわふわ天使パンケーキ?を一つくださいな」
「承知しましたお嬢様」
「やだお嬢様なんて〜」
「ははは…」
そして月嶋ママたちは母さんと一緒に回ることになったらしく3人で教室を出ていった。母さんたちが出た後もお客さんは絶えず数時間してやっと暇になった。
「はぁ…疲れた」
「ね、まさかあの人達が来るなんて…」
「お二人さん、もうそろ休憩だから先着替えて来な」
「え、いいの?」
「山本が後半の準備やんの?」
「高橋もいる、それにそこまで汚れてないから平気」
「というわけだからあとは俺らに任せて」そう言って高橋は俺らを廊下へ押し出す。それと同時にチャイムが鳴る。
「もうそんな時間か、着替えよっか」いつの間にか後半に切り替わる時間になっていたようだ。やっとこの姿から開放される…俺は急いで更衣室へ走る。そんなとき
「うわっ」今の俺は普段とは違いスカート、履き慣れていないスカートで走れば足を取られるのは当然と言ってもいい。
「友里!」俺が頭から着地しかけたところで月嶋が俺を引っ張る。
「大丈夫か?」
「うん、ありがと」
「そんな格好で走るんじゃねえよ」
「ごめんなさい…」
「…怪我ないならいいんだよ」
「うん……あ、着替えてくるから待ってて」
「うんわかった」
そうして俺は急いで着替えを終わらせ月嶋のもとへ向かうのであった。
着替え終わったと同時に後半開始のチャイムがなる。俺は急いで月嶋のもとへ向かう。
「おまたせ、待った?」
「全然」
「じゃあお店、回ろっか」
「うん」
高橋の提案で二人で回ることになった。二人きりなんて修学旅行以来。楽しみで思わず顔がニヤける。
「どこ行きたい?」
「んーそうだな…」
「俺はどこでもいいよ、友里がいれば。」
「じゃあここ行きたい」
「いいよ、行こ」
そして到着した先はフォトスポット。
「友里がこんなところ来たがるって珍しいね」
「月嶋と一緒に写真撮っておきたいから」
俺のその言葉に月嶋はただ「……そ」とだけ言いそっぽを向く
(そんなに嫌だった…?)
俺と写真を撮りたくないのかな、そんな事を考えていると…
「月嶋くん!一緒に写真撮らない?」
隣のクラスの女子が月嶋に話しかける。その子に続くように何人かの生徒が月嶋を誘う。
(月嶋も俺なんかより女子たちのほうがいいよね…)と思っていたら
「俺、先客いるからじゃあね」そう言って俺の手を引っ張る。
月嶋と写真を撮りたかったであろう女子たちからの視線が痛い
「いいよ、俺と撮りたくないんでしょ?」
「そんなことない。何枚でも撮るよ。」
「…ほんと?」
「うん、ほら撮ろ」
月嶋は俺の肩を抱いて器用に写真を撮る。ついでに俺も自分のスマホで写真を撮る。そして月嶋は満足したのかスマホをいじりだす。
「友里もインスタに上げよ」どうやらインスタに今取った写真を上げていたようだ
「あ、うん」
「友里顔写っちゃっても良い系?嫌なら鍵の方に上げるけど」
「鍵?」インスタには鍵があるのか?
「あー鍵垢ってこと。フォローしてる人しか見えないやつ。」
「あー…」
「今その垢高橋と山本しか入れてないから友里にも教えてあげる」
「あ、ありがと」
「これIDね」そう言って月嶋は2つのIDが書かれたメモを渡してきた。片方は鍵を開けている垢のようだ。
「どうやるの?」
「あーそこからか、検索マークあるだろ?それにID打ち込んで上に出てきたアカウントが俺のね」
「わかった」
そのまま月嶋の鍵垢とつながることになった。正直まだよくわかってない。
「次どこ行きたい?」
「それじゃあ……」次にどこに行こうか考えているとお腹が鳴った。
「お腹空いた?じゃあなにか食べに行こっか」
「う、うん」
「食べたいものとかある?」
「んーそうだな…」
食べ歩きできれば月嶋と一緒に色んなところを回れるし…マップを見ればちょうど3年生がお祭りの屋台のような展示をしているのが見えた。
「あ、3年生のお祭りのやつとか」
「あー…っと…いいよ」
「?いやだった?」
「そういうのじゃないから!」
「ならいいんだけど」
「友里は何食べたいの?」
「りんご飴とか食べたい」
「へぇ、じゃあ俺も食お」
「まぁないかもだけど」
「きっとあるだろ」
「そだね」
「3年教室2階だし混む前に行こ」
「うん」とその時だった
「あ、月嶋くん!ちょっと話したいことが…」他クラスの女子だった。慌てぶりとかを見るとなんとなく告白だとわかる。
「何?手短に頼むわ」
(え!?ここで言わすの!?)
「あ、ここじゃあれだし…人いないところで…」
普通そうだよな…告白なんて大勢の前でするもんじゃない。俺だってこんなところじゃしたくない。
「じゃあパス」
「えっ…」
「俺忙しいから、行くぞ友里」
「あ、うん」そう言って俺は月嶋に強制的に手を引かれ階段を降りる。後ろからものすごい視線を感じるけど…
「ねぇ、あれいいの?」
「あれって?」
「女子たち、あれ告白じゃ…」
「あー、俺ああいう空気読めないやつ無理。友里と話してたのにさ。」
「俺は別によかったのに」
「俺はよくないの」
「そ、そう」
「着いたよ友里」
「あ、ホントだ」
「お、りんご飴あるじゃんよかったね」
「うん!」
「そんなに好きなの?」
「えっ、あ…うん」ついはしゃぎすぎたか…恥ずかしい
「ふふっ、かわい」
「そんなこと…」
「友里はりんご飴と俺どっちが好き?」
「え」思ってもいなかった質問に驚く
「なーんてね、入ろっか」
「………」
「友里?」
「ああ、いや…なんでも」
「じゃあ行こ…」月嶋がそう言いかけたときだった
「あれー!?ツッキーだ!」
「ゲッ…」
「つ、つっきー?」
月嶋をツッキーと呼ぶ彼は月嶋よりもちょっと小さく、俺よりもちょっと大きい人だった。
「ん?この子ツッキーの彼ピ?」
「か!?」
「ちげぇから、まだ…」
彼ピ?は多分彼氏のことだろ…ん?月嶋今なんて…
「あーそう?お前がヤマピとかたかちゃんと一緒じゃないなんて珍しいからてっきり」
「というかこの人は?」
「ん、あー陸上部の先輩」
「ども~!高澤でーす!」
「え?そうだっけ…」
「あー、まあ今年辞めたし会ってなくて当然」
「そだね~」
「そうなんですね…」
「それよりこの子は?」
「あー、今年のマネっす」
「えー!この子が!?」
高澤先輩は目を丸くして俺を見つめてきた。
「陽輝ーちょっと手伝ってー」
「オッケー!じゃあね〜!」
「行っちゃった」
「…まぁ俺達も入るか」
「うん」
教室に入るとクオリティの高い提灯や屋台がずらりと並んでいた。
「教室そこまで広くないのにすご…」
「確かに…」
それはそうと月嶋が入った途端なんだかざわめき出した
「りんご飴食いに行くか」
「うん」
そして俺達は奥の方にある屋台へと向かった。
「りんご飴2つくださ…」
「お、さっきぶり!」
「げ…なんで」
「なんでって…俺のクラス来たくせに」
「月嶋と高澤先輩って仲悪いん?」
「そんなことないよ〜!な!ツッキー!」
月嶋はめんどくさそうに「そんな記憶ございません」と答えた。どこかのお偉いさんか?
「えー」
「それより早くくれません?」
「せっかち〜」
「うっさい、友里困ってるでしょ」
「いや俺は全然」
「大丈夫だってさ〜」
「あのねぇ…」
「…あ!もしかして……」
「?」
先輩は月嶋にだけ聞こえる声でなにか言ったようだった。
「は!?」
「ツッキー声でか〜い」
ふと隣を見ると月嶋の耳が少し赤くなっていた。なんの話してたんだろうか…
「頑張れよ!これ先輩からのプレゼント!」
「ありがとうございます…」俺は礼を言い、財布に手を伸ばした
「あ、お代はいらないよプレゼントだし」
「え、でも…」
「いいからいいから」
「お言葉に甘えようぜ」
「じゃ、じゃあ…ありがとうございます」
「おう!お幸せに!」
「…さっさと行こ」
「う、うん」
「ばいばーい」
俺はまた月嶋に手を引かれ外に出る。
「あ、写真撮ろ」
「いいよ、写メ撮ろ」
「写メ…?」
「写メール、とはいってもインスタに上げるだけだけど、やだ?」
「やじゃないけど」
「はいチーズ」
「ちょ、いきなり…」
俺の言葉も届かずスマホのシャッターが鳴る。
「もう一回撮りたい」
「いいよ」
さっきは急だったため少しぶれたからとりあえず俺のスマホで撮り直した
「ありがと」
「どういたしまして、それ後で送っといて」
「うん」
「じゃあこっち来て」
「え?ちょ…」俺がインスタに写真を投稿しようとしていたら急に腕を引っ張られた。せめてどこに行くか言ってくれ…
そして連れられた先はいつも昼食を食べる屋上。屋上に出し物はないはず…
「ねぇこんなところに何が…」俺がそう言いかけると月嶋が口を開いた。
「友里、話しておきたいことがあるんだけど」
「…?」何を言われるのだろう。もしかして俺と回るのが嫌だったとか…
だが月嶋の口から出た言葉は意外なものだった。
「友里好きだ、俺と付き合ってくれ」
「……え?」
突然のことに思わず声が出る
「ダメ?」
「え、ドッキリ?だって月嶋好きな人いるんじゃ」その言葉に月嶋は大きくため息をつく
「友里ってホント鈍感だよな、俺は好きな人以外にキスなんてしないよ」
…たしかに冷静に考えてみればそうだ。日本ではキスが挨拶というわけでもないし、最近距離が近いのも納得する。
俺は月嶋の言葉に安心したのかいつの間にかいつもより赤い頬に涙が伝う。
「…泣くほど嫌だった?」月嶋が悲しそうな声で問いかけてくる。
そんなわけがない。俺は自分で涙を拭った。
「違う…嬉しくて」
「…ほんと?」
「うん、俺も燈也大好き」
今までなんとなく抵抗があった下の名前で呼ぶのも今回はあっさり言えた。急に下の名前で呼ばれたからかちょっと驚いていたが、とても嬉しそうだった。
「じゃあ付き合ってくれる?」
「もちろん」
そういった途端月嶋は俺を抱きしめた。
「…友里はさ、俺が友里のこと好きでも引かない?」
「え?なんで?」
「なんでって…男の俺が男のお前を好きなんだよ?」
「…そんなの関係ないじゃん、たまたま好きになったのが同性ってだけで…」
「……そっか、そうだよな」
「それに俺も燈也のこと好きなわけだし…」
「…それもそっか」
俺達は顔を合わせて笑う。幸せだな、まさかこんな事が起こるなんて思ってもいなかった。
「あ、もうこんな時間、どうする?まだちょっとだけ時間あるけど」
「…もうちょっとこうしてたい」
そんな俺の我儘に月嶋は黙って再び俺を優しく抱きしめる。屋上なんて誰も来ないから周りの目を心配する必要もない。
「友里大好き」
「俺も…ちょっといい?」
「ん?」
俺はつま先立ちで月嶋の頬にキスをする。とは言っても頬に優しく触れただけ。これはキスと呼べるのだろうか…そう思っていたら
「俺とキスしたかった?」
そう言って月嶋はあの日のように俺にキスをする。月嶋のキスはあの日と同じくすぐには離してくれない。
「んっ…」
「…そろそろ終わっちゃうね、戻ろっか」
「うん」
そして文化祭終了のチャイムが鳴り生徒の家族や他校の生徒は続々と帰っていき、他の生徒は自分の教室へと戻る。
教室では後片付けが嫌という空気が誰にでも伝わるほど漂っていた。まぁ、このクラスでやった事もあれだったしな…
でもそんな中、めんどくさい片付けにも表情を変えずにせっせと働く二人がいた
「佐野ちゃんっ、なんかいいことあったの?」
「え?い、いや…なにも」
「月嶋楽しそうだな」
「山本うるさい」
俺達がコソコソ話していると望月先生から「こらそこ、口だけじゃなく手も動かせよ〜」と怒られた。みんな「はーい」と返事してそれ以上は何も話さなかった。
月嶋の方をちらっと見ると目が合った。月嶋はこちらを見てニコッと微笑む。
それに俺もぎこちない笑みを返す。
後片付けも終わり、帰宅時間。山本と高橋は「用事ある」と言い先に帰ってしまった。
「ね、よければ俺ん家泊まらん?」
「へ?」
「さっきLIMEで母さん急用入ったから飯作れないって言われて、俺らでなんとかしろってさ」
「カップ麺とかある感じ?」
「いや、昨日見たとき一つしかなかったから…それに母さん以外料理できないし」
「そういうことなら…」
「ほんと!?」
「うん、ちょっとまってて」
俺は母さんにLIMEで「月嶋の家泊まります」と送った。そして一瞬で既読が付き、「がんばれ!」とスタンプを送ってきた。
「おまたせ、じゃあ行こっか」
「あ、着替えとかどうする?」
「あー…めんどくさいしいいや」
「ははっ、俺の服着たいだけとか?」
「そんなこと…あるかも」
「仕方ないなぁ」
学校祭も終わり、俺は燈矢と二人きりで家に帰る。とは言っても俺が向かう先は月嶋の家。お母さんが家にいなく、食べ物もないとのことで急遽泊まることになった。夜には帰るらしいが母親以外の家族全員大して家事が上手くないようだ。でも明日は振替休日で学校は休みなのでちょうどいい。
「ただいま〜」
「兄ちゃんおかえりー!」出迎えたのは蒼真くん。蒼真くんは兄が帰ってくるなり抱きつく。
「父さんは?」
「パパならまだ帰ってきてない」
「ふーん」
「…と友里じゃん」
「やっほー…」
「兄ちゃんがこいつのこと2回も家に呼ぶなんて珍しいじゃん、友里の家こっちじゃないだろうし」
「今日は友里に家事やってもらおっかなって」
「うん、よろしく…」
「……」蒼真くんは何も言わず俺を睨む。月嶋が「まぁそんな目で見てやんなって」となだめる。
「とりあえず上がって!」
「うん」月嶋に引かれ一旦家に上がるが相変わらず蒼真くんの視線が痛い…
「……」
「友里〜俺お腹空いた」
「あ、うん待ってて!」
「やったー」
「……」
「今日母さんいないんだから仕方ないだろ、蒼真」
「あ、ねぇねぇ、冷蔵庫に入ってるのって好きに使っていい?」
「ん?ああ、いいよ」
「リクエストとかある?」
「ハンバーグ!」
「オッケー、待ってて」そう言い、俺はキッチンへと向かった。
「あれ、パン粉が…」ハンバーグに必要な材料は一通りあったが、パン粉だけどこを探してもなかった。
「あ、でもこれがある!」
俺は戸棚からお麩を取り出す。お麩は味噌汁なんかにいれるあれだ。お麩を砕けばパン粉の代わりになるというのを聞いたことがある。それに、お麩は肉汁をよく吸うのでハンバーグがふっくらジューシーに仕上がるのだ。
やり方もとても簡単。ジップロックにお麩を入れ上か砕くだけ。
「こんなもんかな」そのままお麩粉?をまぶし焼く作業にかかる。その匂いにつられたのか燈也がキッチンへと入ってくる。
「うまそー」
「もうちょっとで終わるから」
「あ、親父の分も作ってくれてたの?」
「うん、お母さんの分も作ったほうがいい?」
「あー母さんなら飯食ってくるから大丈夫。」
「そっか」
「じゃ、頑張ってね」
「ありがと」
そのまま燈也はキッチンを出ていった。
「できたよ」
「すげー!ほんとに作ってくれたの?」
「お口に合うかわかんないけど…」
「絶対合う、いただきます」
「ふふっ、そう?」
「うめー!なんかいつもと違う?」
「あ、パン粉なかったからお麩を…」
「そうなん?それでこれって友里すげー!」
「この前テレビでやってて…」
「なるほどね~」
「そういえば燈也ってハンバーグ好きなの?」
「うん、大好き…子供っぽい?」
「そんなことない、俺も好きだし」
「あの肉汁がたまんないよな」
「それな!」
俺達が食べ進めていると蒼真くんが一口も手を付けていないのが目に入った。
「あれ、どうしたの?具合悪い?」俺がそう聞くもうんともすんとも言わない。
「蒼真?冷めないうちに食べな」
「…ない」
「?」
「いらない」そう言って蒼真くんは席を立つ。
「おい待て」燈也が慌てて腕を引く
「……」
「蒼真!!いい加減にしろ!!」普段あまり怒るイメージがない燈也が珍しく怒鳴った。
「蒼真、せっかく友里が作ってくれたんだから失礼だろ!!」
「まぁまぁ…」俺は燈也をなだめようと仲介に入ろうと試みる
「兄ちゃんのバカ!!」だが俺のそれも虚しく、燈也の腕を振り払い蒼真くんは走り出す。
「あ、待って!」
蒼真くんは玄関へと向かう。ちょうどそこに月嶋のお父さんが帰ってくる。2
「おお〜いいにおいする…ん?蒼真?」
蒼真くんはお父さんも無視して外へ出てしまった。俺もそれを追いかける。
「おお、佐野くん?」
「あ、どうも!」軽く挨拶をして、蒼真くんの後を追う。
「なぁ、何かあったのか」
「…さぁね」
「兄ちゃん…」
兄ちゃんが中学生の頃とか高1の頃はよく遊んだり勉強教えてくれたのに…高2になってから兄ちゃんは変わった。
遊んでくれるのは変わらないが明らかに回数が減った。それに、なにか考え事をしながら遊ぶようになった。
「兄ちゃん?」
「ああ、ごめん、何?」
「…なんでもない」
今までずっと一緒に遊んでいたのに急に変わってしまった。俺は悲しかった。
兄ちゃんは家に帰っても学校の話となると友里の話ばっかりだ
俺が一人さみしくブランコを漕いでいると横から「見つけた」という声が聞こえる
「え」
「探したんだから」
「…お前かよ」
「蒼真くんって俺のこと嫌い?」
「…はっきり言って嫌い。だってお前陰キャじゃん。」
「うっ…」
「なんでお前が…」
「…蒼真くんって燈也のこと好きだよね」
「そうだけど?」
「だよね、俺羨ましいな」
「何が?」
「だって家族なんだからいつも一緒にいれるじゃん」
「…でも家族だから結婚とかできないじゃん」
「あー…でも兄弟って特別な関係だよね」
「なんで?」
「そりゃあ血が繋がってるんだもん。結婚したとしても血が繋がるわけじゃないし、そっちのほうが特別感ない?」
「あっそ」
「って、あんま興味ない?」
「…まぁ、お前のも一理あるけど…」
「?けど?」
「ずっと一緒だったのに…お前が兄ちゃんを奪った」
「え、あ、ごめんね」
「…兄ちゃんいつもお前のことばっか考えてる」
「え?」
「お前ばっかりずるい…」俺の目からは涙が溢れてきた
「泣いてる!?大丈夫!?」
「…なんで俺のこと心配するの」
「え?なんでって?」
「俺お前のこと嫌いなんだよ?」
「…でもほっとけないから」
「は?」
「蒼真くんって燈也のこと好きでしょ?だから。」
「なんでそれでほっとけないんだよ」
「…でも燈也だって蒼真くんのこと大好きだと思うよ?だから一生べったりくっついてるままだと弟としか見られないから」
「…どゆこと?」
「簡単に言うと成長できたらもっと好きになってもらえるんじゃない?」
「成長?」
「いつまでもくっついてたって今までと変わらないなら燈也からの気持ちも変わらないんじゃない?ってこと」
「……」(つまり兄ちゃんから離れろってことか?やっぱこいつ兄ちゃんのこと狙って…!)
「燈也のこと大好きなのは伝わるけど、燈也のこと考えてあげてこそ好きでいれるんじゃない?」
「……!」
確かに思い返してみれば、俺は何をしてるんだろう。今までずっと我儘を聞いてもらってるだけで兄ちゃんは俺に我儘を言ってない。
俺だけが我儘を言って俺の願い通りにしてくれた。それは俺のことが好きだからと思っていたが、兄として、弟に尽くしてくれていただけなんだ。兄ちゃん別に俺のことなんて恋愛対象じゃなくただの弟として好きなのだ。俺は勘違いをしていた。俺が友里にしてきたこともかまってほしいという我儘に過ぎない。もしかしたら兄ちゃんがいつも友里の話をするからヤキモチを焼いていたのだろう。だからあんなことをしてしまった、そして兄ちゃんも我慢の限界だったんだろうな…
「…あの、ごめんなさい」
「なにが?」
「だって俺お前が作ったハンバーグいらないって…」
「ああ、なんだそんなこと?いいよ全然」
「え、なんで?なんで怒らないの?」友里は上を見ながら少し考えて口を開いた
「だって蒼真くんは燈也の大事な弟なんだから当然でしょ?」
「なんでそうなるの?」
「燈也だってあんなこと言っちゃった手前迎えにこれないだろうし」
「じゃあ父さんでいいじゃん」
「…でも俺蒼真くんのことももっと知りたかったなって」
「なんで?この前だって俺お前にいいことしてないじゃん」
「だからってほっとけないの、俺に嫌なことしてきても…燈也の大切な弟くんだから、仲良くしたいなって」
「…ねぇ、お前と兄ちゃんって付き合ってんの?」
「えっ!?」
「…いいよ」
「え?」
「お前なら兄ちゃんのこと好きにして」
「っ…いいの?」
「そう言ってんじゃん」
「俺…間違ってた。兄ちゃんがお前の事好きならそれ応援する」
「そっか」
「帰ろっ!友里兄ちゃん!」
「え?」
「友里兄ちゃん今までごめんね」
「いや全然…じゃあ燈也にも謝りに行こ」
「うん!」
兄ちゃんがこいつが好きな理由、なんとなくわかった気がする。そして俺も、ちょっと成長できた気がする!
「ごめんなさい…」
「…もうあんなことすんなよ」
「うん…」
「……」先程のことは解決したとはいえ気まずいようだ。そんな重い空気を晴らそうと月嶋のお父さんが口を開く。
「そういえばこのハンバーグ佐野くんが作ってくれたんだって?」
「あ、はい!お口に合わなかったですか?」
「いやぁ全然、すごく美味しいよ!」
「ありがとうございます」
「……」
あ…そういえばハンバーグで喧嘩したんだっけ…
そんな空気を察したのかお父さんは話題を変えた。
「そういえば佐野くんって彼女とかいんのかい?」燈矢と俺はその言葉に思わず吹き出す。
「えーっと…」
「そういう話はやめておこうぜ親父!」
「ん?そうかい」
ありがたいけどそれだと恋人がいない可愛そうなやつとか思われたりするんじゃないか…?
「てっきり佐野くんと燈也は付き合ってるもんかと」
「「え゙!?」」思わず二人で驚く。
「ん?どうした?」
「いやぁなんでも」
「別に…」俺らはぎこちなく返事をする。そんな話をしている間に蒼真くんはどうやら食べ終えたらしく食器を片付け始める。
「え、もう食べ終わったの?早いね」
「友里兄ちゃんのハンバーグ美味すぎたから」
「そっか、よかった」
「それより友里兄ちゃん!一緒にお風呂はいろ!」
「「え!?」」その言葉に驚いたのは俺だけでなく燈也もマジかよと言わんばかりに目を丸くする。
「だめ?」
「えぇ…だめというか、お皿洗わないと」
「終わったらでいいよ」
「な、なあ蒼真、兄ちゃんと入るか?」
「友里兄ちゃんと入る」
「そんな…」
「はは…でももう中学生でしょ?一人で入ってきなよ」
「ためになったねぇ〜」
「…そっち?」
「まぁ蒼真いつもは一人だもんな狭いし」
「でも友里兄ちゃんが言うなら先入ってくる!」
「いってらっしゃい」
「一緒に入りたくなったら入ってきてもいいぞ」
「ん、そう?」
「友里兄ちゃんだけね」
「そうか…」燈也はシュンとした顔で座り込む。それも気にせず蒼真くんは風呂場へと向かった。
「なんだお前らまだ喧嘩してんのか」お父さんもそう語りかけるがよほどショックだったのか燈也は黙ったままだ。
「そうみたいですね…」
「そうか…あ、それよりありがとうね何から何まで」
「全然良いですよ、したくてしてるんで」
「いやぁすまんね、前にもこんなことあったんだが僕達が料理したらキッチンが悲惨なことになって…」
「そうだったんですね」
「だからキッチン使用禁止令が出されて…まともにできるのは掃除だけなんだが妻はキレイ好きなもんで」
「掃除もさせてもらえないと…」
「そういうことだね」
「洗濯とかは?」
「洗剤使いすぎちゃうんだよね…」
「あー…」
「まぁ専業主婦はすごいよ…僕は普段仕事だから家事できないってのもあるけど」
「いつもお疲れ様です」
「お、嬉しいね他の家の子に褒められるって」
「どういたしまして…?」
「なぁなぁ、佐野くんは燈也のこと好きかい?」
「えっ?っと……」
「今なら聞こえんよ」
「はい…」
「羨ましいね燈也は」
「え?」
「いつでも泊まりに来ていいんだぞ」
「あ、はい」
「友里何話してんの」突然後ろから元気のない声で話しかけられた
「別に何も…家事の話?」
「ふーん…」
「じゃあ俺風呂入ってくるね」
「行ってらっしゃい」
燈也に見送られお風呂場へ向かおうと部屋を出ると突然玄関の扉が開いた
「ただいまー!心配で早めに帰ってき…ちゃった…?」
「あ……」
「え!嘘!佐野くん!?」
「どうも…」
「なんで!?」
「実は赫々然々で…」
「…なるほどね、まぁいいわ!佐野くんがいたなら安心!」
「あ、ごめんなさいおばさんの分のご飯作ってなくて」
「食べてきたからいいのよ、それよりあの子達は?」
「自分の部屋かと」
「今からお風呂?」
「あ、はい」
「着替えはどうするの?」
「それは…」
「俺の貸す」
「え〜でもこの前ダボダボだったじゃない」
「それでいいの」
「ほんとにいいの?」
「燈也がそれでいいなら」
「友里は俺の服着たいもんね」
「べっ!?別にそんなんじゃ…」
ちょっと着たかったかもなんて言えない…
「用意しとくから先入ってきな」
「う、うん」
燈也に促され俺はそそくさと風呂場へ向かう
「……」
『友里好きだ、俺と付き合お』
今思い返すとめちゃくちゃ恥ずかしい。
(でも、俺達付き合えたんだよな……あれ付き合ってる!?!?)
付き合い始めてすぐに家に泊まっているのか…めっちゃ大胆じゃん…
いや…でも付き合ってるんだしこういうことくらい普通なのかな…
今まで恋人なんてできたことないからわかんないな…というかいつか結婚とかもするのかな…って何考えてんだろ俺…
高校卒業したらどうしよ…同じ大学行けるなら行きたいけど…燈也が「東大行きたい」とか言ったらどうしよう…
俺も大して成績が悪い方ではないが東大となれば話は別だ。せめて京大とかなら…そんな事を考えていると外から声がかかる
「友里大丈夫?」
え?何が?俺、どんくらい入ってたのかな…なんだかくらくらするような…まあそろそろ上がるか…ふらつく足で扉を開けるが開けた途端目の前が真っ黒になった。
「友里!」
燈也の声…俺…呼んでる?どこ…?
暗闇の中懐かしい記憶が蘇る
「佐野!中学校ってどこいくの?東中?」そう問いかけてきたのは昔の燈也だった
「え、えっと…それが…」
「え!?引っ越す!?」
「うん…だから別の中学校…」
「っ…だったら俺も引っ越す!」
「え」
「それなら同じ中学に行けるよな」
「そうだけど…そう簡単に引っ越せるの?」
「それは…」
「一緒の中学校行けなくてごめんね」
「なんで謝るのさ」
「だって…俺も燈也と一緒がよかった…友達だし…」
「…いつ引っ越すの」
「再来週には…」
「…そっか」
「あ、そうだちょっと待ってて」
「?」
俺は机の上に置いていた小さなくまのぬいぐるみを手に取った
「これあげる」
「え」
「あ、いやだった?」
「そういうんじゃなくて、いいの?」
「うん、それなら離れてても一緒にいるみたいでしょ?」
「…ありがと」
「またいっしょに遊ぼ」
「おう…」
あれ…これってもしかして走馬灯…!?まだ死にたくない!
目が覚めるとそこは燈也の部屋だった。
「あれ…ここ…」
一旦整理しよう…ここは燈也の家で、泊まりに来てて、お風呂入ってたら声がかかって…あれ!?着替えてない!?じゃあ今スッポンポンでは!?
慌てて自分の姿を確認するがすでに服は着ていたようだ…いつの間に…
…ん?寝ている間に着替えれるわけないし…着替えさせられたのでは!?
俺が驚いているとちょうどそこに燈也が来た
「あ、起きた?」
「うん…でもなんで」
誰が着替えさせたのか、いつここに来たのか、疑問なことが多かった
「あ、俺がここまで運んできちゃった、それに裸じゃ風邪引くだろ?…あ、変なことしてないから」
聞くとすべて燈也がやってくれたようだ。ありのままの姿を見られたなんてとても恥ずかしい…燈矢の方を向いていられず、そっぽを向いた。するとちょっと薄汚れたくまのぬいぐるみがあった。
「…?あれって」
「え?あ…」
「これ、小学生の時にあげたやつ…持っててくれたの?」
「うん、友里がくれたの」
「ありがと」
「なにが?」
「もう5年くらい前なのに覚えててくれたんでしょ?嬉しいなって」
「だって好きな子からもらったものだし」
「…好き」
「俺も好きだよ」
「…ちゅーしていい?」
「いいよ」
俺はベッドの上から体を起こし、燈也の頬に唇を寄せる
「こっちでしてよ」
そう言い、燈也は自分の口を指差す
「…ほっぺでいいじゃん」
ただでさえ恥ずかしいのだ、勘弁してほしい…キスなんて慣れてないし
「そ、そっちからしてよ」
「えー、友里から口にちゅーしてほしい」
「…一回だけね」
「ふふっしてくれるんだ」
「い、一回だけだから!」
「はいはい…」
一回だけとは言ったもののやっぱり恥ずかしい…でも言った手前やっぱやめたはできない
俺は覚悟を決め燈也の口に向かってキスをした
「…これでいい?」
「やだ、足りない」
今度は燈也が俺の唇を奪う。
「んっ…」
「友里かわいい」
「む…」
「友里俺とキスするの嫌?」
「…嫌だったらしていいか聞かない」
「そだね」
そうだ、今あの話をしよう。忘れてしまう前に…
「ねえ、高校出たらどうする?」
「ん?そーだな…同棲でもする?」
「え?」
「ん?同棲。一緒に住むの。」
「あ、えと…そうじゃなくて…進路…」
「あー大学行きたいけど」
「どこ行くの?」
「友里が行きたいとこならどこでも」
「そう…」
「友里も俺と一緒のとこ行きたいでしょ?」
「うん」俺は即答した
「即答じゃん」
「…俺燈也より頭良くないから…東大は無理」
「友里ってテスト何位くらい?」
「35とかその辺」
「別に悪くないじゃん」
「あの学校生徒100人しかいないから微妙だよ、それに燈也たち成績トップ3じゃん」
「あーまぁそっか」
…というか同棲という言葉を忘れるところだった
「ど、同棲ってどんなとこ住むの?」
「一軒家とか」
「え!?それ高いんじゃ…」
「父さん大企業の社長だから」
「…え、マジ!?」
「マジマジ」
「そうだったんだ…」
「だから大丈夫」
「でも申し訳ないから…」
「後で返せば大丈夫よ」
「でも…」
「そんなに俺と同棲したくない?」
「いや、そうじゃなくて」
「だったらたまには甘えなよ、父さんも俺達のこと応援してるみたいだし…」
「え、言ったの?」
「いや、言ったというか…バレたというか…」
「な、なるほど…」
まぁ確かに俺も燈也のこと好きかって聞かれたしな…そんな話をしているうちにも俺の眠気はどんどん襲ってくる
「今日はもう寝よっか」その燈也の言葉に俺は頷く。
「おやすみ、友里」
「ん…」
俺はまたこの間のように抱き枕のように燈也の腕の中で寝た。羞恥心より今は睡魔が勝ってしまうが付き合えたのだからこういうのも慣れていかないとな…
「おー!佐野くん似合うねー!」
「そう?はは…」
もともとはクラスの女子からの提案で男子がメイド役をすることになるはずだったが男子は俺とネタに走るのが好きそうな五十嵐。その五十嵐の仕事は後半なので実質俺一人だ
「友里かわいい」
俺が恥ずかしそうに隅で丸まっていると月嶋が声をかけてくる。月嶋はタキシードビシッと決まっていてとてもかっこいい。
「ありがと…」
「もうすぐ始まるよだから…」月嶋がそう言いかけた途端
「え!?莉乃ちゃんメイドできないの!?」
先ほど俺のメイド姿を似合うと言ってくれた女子が驚く。
「うん…ちょっとお腹痛くて…」
「でも佐野くん一人じゃなぁ…誰かやってくれる人いない?」
その声に手を挙げる者はいない。
「私は受付だし…」そんなとき月嶋が手を挙げた
「じゃあ高橋は?」
「え゙」
「高橋くんやってくれる?」
「うーん…それは」
「高橋、今なら俺達4人一緒だぞ」
「んー…まぁ確かにそれなら…」
「ほんと!?ありがと!じゃあこれはい!」そう言って高橋にメイド服を渡す
「あ、はい…着替えてきます」
「急げよ〜」月嶋は高橋にそう言って自分の仕事の準備に戻る。俺も戻ろうとしたその時山本が声をかけてきた
「なぁ佐野、ちょっといいか?」
「ん?何?」
「後半さ、月嶋と二人きりで回ったらどう?」
「え?二人も一緒じゃないの?」
「お前も月嶋と二人のほうがいいだろ?俺らはいいからさ」
「…じゃあお言葉に甘えて」
「うん、じゃあ位置について」
「はっ、もうこんな時間!」
「ただいまー」高橋が戻ったと同時に開始のチャイムが鳴る
「じゃあみんな頑張ろー!」
「おー!」
「兄ちゃん来たよー!」
記念すべき最初のお客様…いやご主人様?は蒼真くんだった。
「蒼真じゃん久しぶり〜」
「隼人兄メイド服きてんの?似合うじゃん」
「そうか?あんま嬉しくねえな」
「蒼真一人で来たのか?」
「お母さんと来た」
「燈也ー!来たわよー!」
「げ…」
「お!もしかして月嶋くんのお母さんですか?受付お願いしまーす」
「そうなのよ〜燈也ったらこの前…」
「わ゙ー!席ご案内しますね」
「もー燈也ったら…って佐野くんと山本くん?」
「「ゲッ」」思わず声が揃ってしまう
「やだ〜二人ともかわいいじゃない」
「はは…どうも」
「…あ、ありがとう…ございます」
山本はタキシードだからまだいいが俺はメイド服だ。恥ずかしくてあまりうまく話せない。
「宏太兄かっけー!兄ちゃんの次くらいに」
「あっそ…ご注文は?」
「じゃあ俺オムライス!」
あ、俺には触れないのね…俺的にはいいんだけどなんかさみしいような
「お待たせしましたー」
(え!?はや!)
「サービスとしてメイドさんがケチャップでハート描いてくれまーす」山本はそう言って俺の方を見る。
「え!?俺!?」
「はいどうぞ」そう言いケチャップを握らせてきた
「友里描くの?」
「佐野くんが描いてくれるっていいじゃない」
「ふーん」蒼真くんがこちらを睨む
「ヒイッ」
「こら、そんな顔しないの」
「じ、じゃあ描かさせていただきます」
さっさと終わらせよう…ただでさえ恥ずかしいし…俺は心のなかでそう言いながらオムライスにハートを描いたその時
「続いてはおまじないをかけてもらいまーす」
「は!?」山本のその一言に思わず声が出る
「いいじゃんそのほうがメイド喫茶っぽいだろ」
「ええ…」
月嶋と高橋は他の人対応してるし…始まったばかりで客があまりいないのが救いだ。まぁ教室の外は観客ですごいけど…
「まだ〜?」
「はいただいま…って何するんですか」
「何って記念に撮っておきたくて…ダメだったかしら」
「全然オッケーですよ」そういったのはまたもや山本だった。
「なっ…」
「お詫びとしてチップ払っとくから!」
「う…お、美味しくなあれ萌え萌えキュン…」
「ありがと~!はいこれ」そう言って月嶋ママは俺にチップを握らせる
「お会計のときに…」
「あ、そうよねじゃあまた後でね」
「はい…」(なんとか終わった…)
「佐野、お客さん」
「はーい」俺が振り向くと入口には母さんが立っていた
「あら友里!随分とかわいい格好しちゃって」
「あ…」
終わった…こんな姿見られたくないランキングトップ2の二人に見られてしまった…ちなみにもう一人は月嶋ママ。好きな人の母親に見られるのもだいぶ気まずいっていうのにもっと気まずい自分の母親って…
「佐野、俺は蒼真んとこ行くから席案内してあげて」
「あ、はーい…」
(なんで自分の母さんを案内させられるんだ…!山本のバカ!)
これも仕事だ…仕方なく席を案内する。
「…席ご案内します」
「緊張しなくていいのよ〜」
(緊張というよりあんま見られたくないんだよ…!)
おしゃべり好きな母さんだからできるだけ月嶋ママたちからは離れた席に案内しようとしたのだが…
「こちらになります…」
残念なことに真隣しか空いていなかった。もし話されでもしたらいろんなことを全部吐き出してしまいそうだから不安だ。
そして案の定…
「あら?もしかして瑠那ちゃん?」
「ええ…ってもしかして優香!?」
「久しぶり〜」
(げ…知り合いだったのか…)
まあ、それもそうか小学校が一緒だったことを覚えてるくらいだし…ふと月嶋を見るとこの世の終わりのような顔をしていた。
月嶋が俺に向かってぼそっと「なああれ友里の母ちゃんだよな」と聞いてきた。俺は小さく頷く。
「俺の母さんあることないこと全部言ったりしそうだからさ…」
「そうなの?」
「ああ、この前なんて…」月嶋はそう言いかけたと思ったら「やっぱやめた」と言った。
「なにそれ気になるじゃん」
「それは…」月嶋がそう言いかけた瞬間
「え!?燈也くん彼女いなかったの!?」そういったのは俺の母さんだった
そして月嶋ママが「そうなのよ〜あの子ったらどうしてもゆ…」と言おうとした瞬間
「お話の途中すみません!ご注文お伺いします!」月嶋が声をかき消すかのように話しかける。
「あら燈也くん元気にしてた?」
「おかげさまで…」
「そう?よかった~、じゃあふわふわ天使パンケーキ?を一つくださいな」
「承知しましたお嬢様」
「やだお嬢様なんて〜」
「ははは…」
そして月嶋ママたちは母さんと一緒に回ることになったらしく3人で教室を出ていった。母さんたちが出た後もお客さんは絶えず数時間してやっと暇になった。
「はぁ…疲れた」
「ね、まさかあの人達が来るなんて…」
「お二人さん、もうそろ休憩だから先着替えて来な」
「え、いいの?」
「山本が後半の準備やんの?」
「高橋もいる、それにそこまで汚れてないから平気」
「というわけだからあとは俺らに任せて」そう言って高橋は俺らを廊下へ押し出す。それと同時にチャイムが鳴る。
「もうそんな時間か、着替えよっか」いつの間にか後半に切り替わる時間になっていたようだ。やっとこの姿から開放される…俺は急いで更衣室へ走る。そんなとき
「うわっ」今の俺は普段とは違いスカート、履き慣れていないスカートで走れば足を取られるのは当然と言ってもいい。
「友里!」俺が頭から着地しかけたところで月嶋が俺を引っ張る。
「大丈夫か?」
「うん、ありがと」
「そんな格好で走るんじゃねえよ」
「ごめんなさい…」
「…怪我ないならいいんだよ」
「うん……あ、着替えてくるから待ってて」
「うんわかった」
そうして俺は急いで着替えを終わらせ月嶋のもとへ向かうのであった。
着替え終わったと同時に後半開始のチャイムがなる。俺は急いで月嶋のもとへ向かう。
「おまたせ、待った?」
「全然」
「じゃあお店、回ろっか」
「うん」
高橋の提案で二人で回ることになった。二人きりなんて修学旅行以来。楽しみで思わず顔がニヤける。
「どこ行きたい?」
「んーそうだな…」
「俺はどこでもいいよ、友里がいれば。」
「じゃあここ行きたい」
「いいよ、行こ」
そして到着した先はフォトスポット。
「友里がこんなところ来たがるって珍しいね」
「月嶋と一緒に写真撮っておきたいから」
俺のその言葉に月嶋はただ「……そ」とだけ言いそっぽを向く
(そんなに嫌だった…?)
俺と写真を撮りたくないのかな、そんな事を考えていると…
「月嶋くん!一緒に写真撮らない?」
隣のクラスの女子が月嶋に話しかける。その子に続くように何人かの生徒が月嶋を誘う。
(月嶋も俺なんかより女子たちのほうがいいよね…)と思っていたら
「俺、先客いるからじゃあね」そう言って俺の手を引っ張る。
月嶋と写真を撮りたかったであろう女子たちからの視線が痛い
「いいよ、俺と撮りたくないんでしょ?」
「そんなことない。何枚でも撮るよ。」
「…ほんと?」
「うん、ほら撮ろ」
月嶋は俺の肩を抱いて器用に写真を撮る。ついでに俺も自分のスマホで写真を撮る。そして月嶋は満足したのかスマホをいじりだす。
「友里もインスタに上げよ」どうやらインスタに今取った写真を上げていたようだ
「あ、うん」
「友里顔写っちゃっても良い系?嫌なら鍵の方に上げるけど」
「鍵?」インスタには鍵があるのか?
「あー鍵垢ってこと。フォローしてる人しか見えないやつ。」
「あー…」
「今その垢高橋と山本しか入れてないから友里にも教えてあげる」
「あ、ありがと」
「これIDね」そう言って月嶋は2つのIDが書かれたメモを渡してきた。片方は鍵を開けている垢のようだ。
「どうやるの?」
「あーそこからか、検索マークあるだろ?それにID打ち込んで上に出てきたアカウントが俺のね」
「わかった」
そのまま月嶋の鍵垢とつながることになった。正直まだよくわかってない。
「次どこ行きたい?」
「それじゃあ……」次にどこに行こうか考えているとお腹が鳴った。
「お腹空いた?じゃあなにか食べに行こっか」
「う、うん」
「食べたいものとかある?」
「んーそうだな…」
食べ歩きできれば月嶋と一緒に色んなところを回れるし…マップを見ればちょうど3年生がお祭りの屋台のような展示をしているのが見えた。
「あ、3年生のお祭りのやつとか」
「あー…っと…いいよ」
「?いやだった?」
「そういうのじゃないから!」
「ならいいんだけど」
「友里は何食べたいの?」
「りんご飴とか食べたい」
「へぇ、じゃあ俺も食お」
「まぁないかもだけど」
「きっとあるだろ」
「そだね」
「3年教室2階だし混む前に行こ」
「うん」とその時だった
「あ、月嶋くん!ちょっと話したいことが…」他クラスの女子だった。慌てぶりとかを見るとなんとなく告白だとわかる。
「何?手短に頼むわ」
(え!?ここで言わすの!?)
「あ、ここじゃあれだし…人いないところで…」
普通そうだよな…告白なんて大勢の前でするもんじゃない。俺だってこんなところじゃしたくない。
「じゃあパス」
「えっ…」
「俺忙しいから、行くぞ友里」
「あ、うん」そう言って俺は月嶋に強制的に手を引かれ階段を降りる。後ろからものすごい視線を感じるけど…
「ねぇ、あれいいの?」
「あれって?」
「女子たち、あれ告白じゃ…」
「あー、俺ああいう空気読めないやつ無理。友里と話してたのにさ。」
「俺は別によかったのに」
「俺はよくないの」
「そ、そう」
「着いたよ友里」
「あ、ホントだ」
「お、りんご飴あるじゃんよかったね」
「うん!」
「そんなに好きなの?」
「えっ、あ…うん」ついはしゃぎすぎたか…恥ずかしい
「ふふっ、かわい」
「そんなこと…」
「友里はりんご飴と俺どっちが好き?」
「え」思ってもいなかった質問に驚く
「なーんてね、入ろっか」
「………」
「友里?」
「ああ、いや…なんでも」
「じゃあ行こ…」月嶋がそう言いかけたときだった
「あれー!?ツッキーだ!」
「ゲッ…」
「つ、つっきー?」
月嶋をツッキーと呼ぶ彼は月嶋よりもちょっと小さく、俺よりもちょっと大きい人だった。
「ん?この子ツッキーの彼ピ?」
「か!?」
「ちげぇから、まだ…」
彼ピ?は多分彼氏のことだろ…ん?月嶋今なんて…
「あーそう?お前がヤマピとかたかちゃんと一緒じゃないなんて珍しいからてっきり」
「というかこの人は?」
「ん、あー陸上部の先輩」
「ども~!高澤でーす!」
「え?そうだっけ…」
「あー、まあ今年辞めたし会ってなくて当然」
「そだね~」
「そうなんですね…」
「それよりこの子は?」
「あー、今年のマネっす」
「えー!この子が!?」
高澤先輩は目を丸くして俺を見つめてきた。
「陽輝ーちょっと手伝ってー」
「オッケー!じゃあね〜!」
「行っちゃった」
「…まぁ俺達も入るか」
「うん」
教室に入るとクオリティの高い提灯や屋台がずらりと並んでいた。
「教室そこまで広くないのにすご…」
「確かに…」
それはそうと月嶋が入った途端なんだかざわめき出した
「りんご飴食いに行くか」
「うん」
そして俺達は奥の方にある屋台へと向かった。
「りんご飴2つくださ…」
「お、さっきぶり!」
「げ…なんで」
「なんでって…俺のクラス来たくせに」
「月嶋と高澤先輩って仲悪いん?」
「そんなことないよ〜!な!ツッキー!」
月嶋はめんどくさそうに「そんな記憶ございません」と答えた。どこかのお偉いさんか?
「えー」
「それより早くくれません?」
「せっかち〜」
「うっさい、友里困ってるでしょ」
「いや俺は全然」
「大丈夫だってさ〜」
「あのねぇ…」
「…あ!もしかして……」
「?」
先輩は月嶋にだけ聞こえる声でなにか言ったようだった。
「は!?」
「ツッキー声でか〜い」
ふと隣を見ると月嶋の耳が少し赤くなっていた。なんの話してたんだろうか…
「頑張れよ!これ先輩からのプレゼント!」
「ありがとうございます…」俺は礼を言い、財布に手を伸ばした
「あ、お代はいらないよプレゼントだし」
「え、でも…」
「いいからいいから」
「お言葉に甘えようぜ」
「じゃ、じゃあ…ありがとうございます」
「おう!お幸せに!」
「…さっさと行こ」
「う、うん」
「ばいばーい」
俺はまた月嶋に手を引かれ外に出る。
「あ、写真撮ろ」
「いいよ、写メ撮ろ」
「写メ…?」
「写メール、とはいってもインスタに上げるだけだけど、やだ?」
「やじゃないけど」
「はいチーズ」
「ちょ、いきなり…」
俺の言葉も届かずスマホのシャッターが鳴る。
「もう一回撮りたい」
「いいよ」
さっきは急だったため少しぶれたからとりあえず俺のスマホで撮り直した
「ありがと」
「どういたしまして、それ後で送っといて」
「うん」
「じゃあこっち来て」
「え?ちょ…」俺がインスタに写真を投稿しようとしていたら急に腕を引っ張られた。せめてどこに行くか言ってくれ…
そして連れられた先はいつも昼食を食べる屋上。屋上に出し物はないはず…
「ねぇこんなところに何が…」俺がそう言いかけると月嶋が口を開いた。
「友里、話しておきたいことがあるんだけど」
「…?」何を言われるのだろう。もしかして俺と回るのが嫌だったとか…
だが月嶋の口から出た言葉は意外なものだった。
「友里好きだ、俺と付き合ってくれ」
「……え?」
突然のことに思わず声が出る
「ダメ?」
「え、ドッキリ?だって月嶋好きな人いるんじゃ」その言葉に月嶋は大きくため息をつく
「友里ってホント鈍感だよな、俺は好きな人以外にキスなんてしないよ」
…たしかに冷静に考えてみればそうだ。日本ではキスが挨拶というわけでもないし、最近距離が近いのも納得する。
俺は月嶋の言葉に安心したのかいつの間にかいつもより赤い頬に涙が伝う。
「…泣くほど嫌だった?」月嶋が悲しそうな声で問いかけてくる。
そんなわけがない。俺は自分で涙を拭った。
「違う…嬉しくて」
「…ほんと?」
「うん、俺も燈也大好き」
今までなんとなく抵抗があった下の名前で呼ぶのも今回はあっさり言えた。急に下の名前で呼ばれたからかちょっと驚いていたが、とても嬉しそうだった。
「じゃあ付き合ってくれる?」
「もちろん」
そういった途端月嶋は俺を抱きしめた。
「…友里はさ、俺が友里のこと好きでも引かない?」
「え?なんで?」
「なんでって…男の俺が男のお前を好きなんだよ?」
「…そんなの関係ないじゃん、たまたま好きになったのが同性ってだけで…」
「……そっか、そうだよな」
「それに俺も燈也のこと好きなわけだし…」
「…それもそっか」
俺達は顔を合わせて笑う。幸せだな、まさかこんな事が起こるなんて思ってもいなかった。
「あ、もうこんな時間、どうする?まだちょっとだけ時間あるけど」
「…もうちょっとこうしてたい」
そんな俺の我儘に月嶋は黙って再び俺を優しく抱きしめる。屋上なんて誰も来ないから周りの目を心配する必要もない。
「友里大好き」
「俺も…ちょっといい?」
「ん?」
俺はつま先立ちで月嶋の頬にキスをする。とは言っても頬に優しく触れただけ。これはキスと呼べるのだろうか…そう思っていたら
「俺とキスしたかった?」
そう言って月嶋はあの日のように俺にキスをする。月嶋のキスはあの日と同じくすぐには離してくれない。
「んっ…」
「…そろそろ終わっちゃうね、戻ろっか」
「うん」
そして文化祭終了のチャイムが鳴り生徒の家族や他校の生徒は続々と帰っていき、他の生徒は自分の教室へと戻る。
教室では後片付けが嫌という空気が誰にでも伝わるほど漂っていた。まぁ、このクラスでやった事もあれだったしな…
でもそんな中、めんどくさい片付けにも表情を変えずにせっせと働く二人がいた
「佐野ちゃんっ、なんかいいことあったの?」
「え?い、いや…なにも」
「月嶋楽しそうだな」
「山本うるさい」
俺達がコソコソ話していると望月先生から「こらそこ、口だけじゃなく手も動かせよ〜」と怒られた。みんな「はーい」と返事してそれ以上は何も話さなかった。
月嶋の方をちらっと見ると目が合った。月嶋はこちらを見てニコッと微笑む。
それに俺もぎこちない笑みを返す。
後片付けも終わり、帰宅時間。山本と高橋は「用事ある」と言い先に帰ってしまった。
「ね、よければ俺ん家泊まらん?」
「へ?」
「さっきLIMEで母さん急用入ったから飯作れないって言われて、俺らでなんとかしろってさ」
「カップ麺とかある感じ?」
「いや、昨日見たとき一つしかなかったから…それに母さん以外料理できないし」
「そういうことなら…」
「ほんと!?」
「うん、ちょっとまってて」
俺は母さんにLIMEで「月嶋の家泊まります」と送った。そして一瞬で既読が付き、「がんばれ!」とスタンプを送ってきた。
「おまたせ、じゃあ行こっか」
「あ、着替えとかどうする?」
「あー…めんどくさいしいいや」
「ははっ、俺の服着たいだけとか?」
「そんなこと…あるかも」
「仕方ないなぁ」
学校祭も終わり、俺は燈矢と二人きりで家に帰る。とは言っても俺が向かう先は月嶋の家。お母さんが家にいなく、食べ物もないとのことで急遽泊まることになった。夜には帰るらしいが母親以外の家族全員大して家事が上手くないようだ。でも明日は振替休日で学校は休みなのでちょうどいい。
「ただいま〜」
「兄ちゃんおかえりー!」出迎えたのは蒼真くん。蒼真くんは兄が帰ってくるなり抱きつく。
「父さんは?」
「パパならまだ帰ってきてない」
「ふーん」
「…と友里じゃん」
「やっほー…」
「兄ちゃんがこいつのこと2回も家に呼ぶなんて珍しいじゃん、友里の家こっちじゃないだろうし」
「今日は友里に家事やってもらおっかなって」
「うん、よろしく…」
「……」蒼真くんは何も言わず俺を睨む。月嶋が「まぁそんな目で見てやんなって」となだめる。
「とりあえず上がって!」
「うん」月嶋に引かれ一旦家に上がるが相変わらず蒼真くんの視線が痛い…
「……」
「友里〜俺お腹空いた」
「あ、うん待ってて!」
「やったー」
「……」
「今日母さんいないんだから仕方ないだろ、蒼真」
「あ、ねぇねぇ、冷蔵庫に入ってるのって好きに使っていい?」
「ん?ああ、いいよ」
「リクエストとかある?」
「ハンバーグ!」
「オッケー、待ってて」そう言い、俺はキッチンへと向かった。
「あれ、パン粉が…」ハンバーグに必要な材料は一通りあったが、パン粉だけどこを探してもなかった。
「あ、でもこれがある!」
俺は戸棚からお麩を取り出す。お麩は味噌汁なんかにいれるあれだ。お麩を砕けばパン粉の代わりになるというのを聞いたことがある。それに、お麩は肉汁をよく吸うのでハンバーグがふっくらジューシーに仕上がるのだ。
やり方もとても簡単。ジップロックにお麩を入れ上か砕くだけ。
「こんなもんかな」そのままお麩粉?をまぶし焼く作業にかかる。その匂いにつられたのか燈也がキッチンへと入ってくる。
「うまそー」
「もうちょっとで終わるから」
「あ、親父の分も作ってくれてたの?」
「うん、お母さんの分も作ったほうがいい?」
「あー母さんなら飯食ってくるから大丈夫。」
「そっか」
「じゃ、頑張ってね」
「ありがと」
そのまま燈也はキッチンを出ていった。
「できたよ」
「すげー!ほんとに作ってくれたの?」
「お口に合うかわかんないけど…」
「絶対合う、いただきます」
「ふふっ、そう?」
「うめー!なんかいつもと違う?」
「あ、パン粉なかったからお麩を…」
「そうなん?それでこれって友里すげー!」
「この前テレビでやってて…」
「なるほどね~」
「そういえば燈也ってハンバーグ好きなの?」
「うん、大好き…子供っぽい?」
「そんなことない、俺も好きだし」
「あの肉汁がたまんないよな」
「それな!」
俺達が食べ進めていると蒼真くんが一口も手を付けていないのが目に入った。
「あれ、どうしたの?具合悪い?」俺がそう聞くもうんともすんとも言わない。
「蒼真?冷めないうちに食べな」
「…ない」
「?」
「いらない」そう言って蒼真くんは席を立つ。
「おい待て」燈也が慌てて腕を引く
「……」
「蒼真!!いい加減にしろ!!」普段あまり怒るイメージがない燈也が珍しく怒鳴った。
「蒼真、せっかく友里が作ってくれたんだから失礼だろ!!」
「まぁまぁ…」俺は燈也をなだめようと仲介に入ろうと試みる
「兄ちゃんのバカ!!」だが俺のそれも虚しく、燈也の腕を振り払い蒼真くんは走り出す。
「あ、待って!」
蒼真くんは玄関へと向かう。ちょうどそこに月嶋のお父さんが帰ってくる。2
「おお〜いいにおいする…ん?蒼真?」
蒼真くんはお父さんも無視して外へ出てしまった。俺もそれを追いかける。
「おお、佐野くん?」
「あ、どうも!」軽く挨拶をして、蒼真くんの後を追う。
「なぁ、何かあったのか」
「…さぁね」
「兄ちゃん…」
兄ちゃんが中学生の頃とか高1の頃はよく遊んだり勉強教えてくれたのに…高2になってから兄ちゃんは変わった。
遊んでくれるのは変わらないが明らかに回数が減った。それに、なにか考え事をしながら遊ぶようになった。
「兄ちゃん?」
「ああ、ごめん、何?」
「…なんでもない」
今までずっと一緒に遊んでいたのに急に変わってしまった。俺は悲しかった。
兄ちゃんは家に帰っても学校の話となると友里の話ばっかりだ
俺が一人さみしくブランコを漕いでいると横から「見つけた」という声が聞こえる
「え」
「探したんだから」
「…お前かよ」
「蒼真くんって俺のこと嫌い?」
「…はっきり言って嫌い。だってお前陰キャじゃん。」
「うっ…」
「なんでお前が…」
「…蒼真くんって燈也のこと好きだよね」
「そうだけど?」
「だよね、俺羨ましいな」
「何が?」
「だって家族なんだからいつも一緒にいれるじゃん」
「…でも家族だから結婚とかできないじゃん」
「あー…でも兄弟って特別な関係だよね」
「なんで?」
「そりゃあ血が繋がってるんだもん。結婚したとしても血が繋がるわけじゃないし、そっちのほうが特別感ない?」
「あっそ」
「って、あんま興味ない?」
「…まぁ、お前のも一理あるけど…」
「?けど?」
「ずっと一緒だったのに…お前が兄ちゃんを奪った」
「え、あ、ごめんね」
「…兄ちゃんいつもお前のことばっか考えてる」
「え?」
「お前ばっかりずるい…」俺の目からは涙が溢れてきた
「泣いてる!?大丈夫!?」
「…なんで俺のこと心配するの」
「え?なんでって?」
「俺お前のこと嫌いなんだよ?」
「…でもほっとけないから」
「は?」
「蒼真くんって燈也のこと好きでしょ?だから。」
「なんでそれでほっとけないんだよ」
「…でも燈也だって蒼真くんのこと大好きだと思うよ?だから一生べったりくっついてるままだと弟としか見られないから」
「…どゆこと?」
「簡単に言うと成長できたらもっと好きになってもらえるんじゃない?」
「成長?」
「いつまでもくっついてたって今までと変わらないなら燈也からの気持ちも変わらないんじゃない?ってこと」
「……」(つまり兄ちゃんから離れろってことか?やっぱこいつ兄ちゃんのこと狙って…!)
「燈也のこと大好きなのは伝わるけど、燈也のこと考えてあげてこそ好きでいれるんじゃない?」
「……!」
確かに思い返してみれば、俺は何をしてるんだろう。今までずっと我儘を聞いてもらってるだけで兄ちゃんは俺に我儘を言ってない。
俺だけが我儘を言って俺の願い通りにしてくれた。それは俺のことが好きだからと思っていたが、兄として、弟に尽くしてくれていただけなんだ。兄ちゃん別に俺のことなんて恋愛対象じゃなくただの弟として好きなのだ。俺は勘違いをしていた。俺が友里にしてきたこともかまってほしいという我儘に過ぎない。もしかしたら兄ちゃんがいつも友里の話をするからヤキモチを焼いていたのだろう。だからあんなことをしてしまった、そして兄ちゃんも我慢の限界だったんだろうな…
「…あの、ごめんなさい」
「なにが?」
「だって俺お前が作ったハンバーグいらないって…」
「ああ、なんだそんなこと?いいよ全然」
「え、なんで?なんで怒らないの?」友里は上を見ながら少し考えて口を開いた
「だって蒼真くんは燈也の大事な弟なんだから当然でしょ?」
「なんでそうなるの?」
「燈也だってあんなこと言っちゃった手前迎えにこれないだろうし」
「じゃあ父さんでいいじゃん」
「…でも俺蒼真くんのことももっと知りたかったなって」
「なんで?この前だって俺お前にいいことしてないじゃん」
「だからってほっとけないの、俺に嫌なことしてきても…燈也の大切な弟くんだから、仲良くしたいなって」
「…ねぇ、お前と兄ちゃんって付き合ってんの?」
「えっ!?」
「…いいよ」
「え?」
「お前なら兄ちゃんのこと好きにして」
「っ…いいの?」
「そう言ってんじゃん」
「俺…間違ってた。兄ちゃんがお前の事好きならそれ応援する」
「そっか」
「帰ろっ!友里兄ちゃん!」
「え?」
「友里兄ちゃん今までごめんね」
「いや全然…じゃあ燈也にも謝りに行こ」
「うん!」
兄ちゃんがこいつが好きな理由、なんとなくわかった気がする。そして俺も、ちょっと成長できた気がする!
「ごめんなさい…」
「…もうあんなことすんなよ」
「うん…」
「……」先程のことは解決したとはいえ気まずいようだ。そんな重い空気を晴らそうと月嶋のお父さんが口を開く。
「そういえばこのハンバーグ佐野くんが作ってくれたんだって?」
「あ、はい!お口に合わなかったですか?」
「いやぁ全然、すごく美味しいよ!」
「ありがとうございます」
「……」
あ…そういえばハンバーグで喧嘩したんだっけ…
そんな空気を察したのかお父さんは話題を変えた。
「そういえば佐野くんって彼女とかいんのかい?」燈矢と俺はその言葉に思わず吹き出す。
「えーっと…」
「そういう話はやめておこうぜ親父!」
「ん?そうかい」
ありがたいけどそれだと恋人がいない可愛そうなやつとか思われたりするんじゃないか…?
「てっきり佐野くんと燈也は付き合ってるもんかと」
「「え゙!?」」思わず二人で驚く。
「ん?どうした?」
「いやぁなんでも」
「別に…」俺らはぎこちなく返事をする。そんな話をしている間に蒼真くんはどうやら食べ終えたらしく食器を片付け始める。
「え、もう食べ終わったの?早いね」
「友里兄ちゃんのハンバーグ美味すぎたから」
「そっか、よかった」
「それより友里兄ちゃん!一緒にお風呂はいろ!」
「「え!?」」その言葉に驚いたのは俺だけでなく燈也もマジかよと言わんばかりに目を丸くする。
「だめ?」
「えぇ…だめというか、お皿洗わないと」
「終わったらでいいよ」
「な、なあ蒼真、兄ちゃんと入るか?」
「友里兄ちゃんと入る」
「そんな…」
「はは…でももう中学生でしょ?一人で入ってきなよ」
「ためになったねぇ〜」
「…そっち?」
「まぁ蒼真いつもは一人だもんな狭いし」
「でも友里兄ちゃんが言うなら先入ってくる!」
「いってらっしゃい」
「一緒に入りたくなったら入ってきてもいいぞ」
「ん、そう?」
「友里兄ちゃんだけね」
「そうか…」燈也はシュンとした顔で座り込む。それも気にせず蒼真くんは風呂場へと向かった。
「なんだお前らまだ喧嘩してんのか」お父さんもそう語りかけるがよほどショックだったのか燈也は黙ったままだ。
「そうみたいですね…」
「そうか…あ、それよりありがとうね何から何まで」
「全然良いですよ、したくてしてるんで」
「いやぁすまんね、前にもこんなことあったんだが僕達が料理したらキッチンが悲惨なことになって…」
「そうだったんですね」
「だからキッチン使用禁止令が出されて…まともにできるのは掃除だけなんだが妻はキレイ好きなもんで」
「掃除もさせてもらえないと…」
「そういうことだね」
「洗濯とかは?」
「洗剤使いすぎちゃうんだよね…」
「あー…」
「まぁ専業主婦はすごいよ…僕は普段仕事だから家事できないってのもあるけど」
「いつもお疲れ様です」
「お、嬉しいね他の家の子に褒められるって」
「どういたしまして…?」
「なぁなぁ、佐野くんは燈也のこと好きかい?」
「えっ?っと……」
「今なら聞こえんよ」
「はい…」
「羨ましいね燈也は」
「え?」
「いつでも泊まりに来ていいんだぞ」
「あ、はい」
「友里何話してんの」突然後ろから元気のない声で話しかけられた
「別に何も…家事の話?」
「ふーん…」
「じゃあ俺風呂入ってくるね」
「行ってらっしゃい」
燈也に見送られお風呂場へ向かおうと部屋を出ると突然玄関の扉が開いた
「ただいまー!心配で早めに帰ってき…ちゃった…?」
「あ……」
「え!嘘!佐野くん!?」
「どうも…」
「なんで!?」
「実は赫々然々で…」
「…なるほどね、まぁいいわ!佐野くんがいたなら安心!」
「あ、ごめんなさいおばさんの分のご飯作ってなくて」
「食べてきたからいいのよ、それよりあの子達は?」
「自分の部屋かと」
「今からお風呂?」
「あ、はい」
「着替えはどうするの?」
「それは…」
「俺の貸す」
「え〜でもこの前ダボダボだったじゃない」
「それでいいの」
「ほんとにいいの?」
「燈也がそれでいいなら」
「友里は俺の服着たいもんね」
「べっ!?別にそんなんじゃ…」
ちょっと着たかったかもなんて言えない…
「用意しとくから先入ってきな」
「う、うん」
燈也に促され俺はそそくさと風呂場へ向かう
「……」
『友里好きだ、俺と付き合お』
今思い返すとめちゃくちゃ恥ずかしい。
(でも、俺達付き合えたんだよな……あれ付き合ってる!?!?)
付き合い始めてすぐに家に泊まっているのか…めっちゃ大胆じゃん…
いや…でも付き合ってるんだしこういうことくらい普通なのかな…
今まで恋人なんてできたことないからわかんないな…というかいつか結婚とかもするのかな…って何考えてんだろ俺…
高校卒業したらどうしよ…同じ大学行けるなら行きたいけど…燈也が「東大行きたい」とか言ったらどうしよう…
俺も大して成績が悪い方ではないが東大となれば話は別だ。せめて京大とかなら…そんな事を考えていると外から声がかかる
「友里大丈夫?」
え?何が?俺、どんくらい入ってたのかな…なんだかくらくらするような…まあそろそろ上がるか…ふらつく足で扉を開けるが開けた途端目の前が真っ黒になった。
「友里!」
燈也の声…俺…呼んでる?どこ…?
暗闇の中懐かしい記憶が蘇る
「佐野!中学校ってどこいくの?東中?」そう問いかけてきたのは昔の燈也だった
「え、えっと…それが…」
「え!?引っ越す!?」
「うん…だから別の中学校…」
「っ…だったら俺も引っ越す!」
「え」
「それなら同じ中学に行けるよな」
「そうだけど…そう簡単に引っ越せるの?」
「それは…」
「一緒の中学校行けなくてごめんね」
「なんで謝るのさ」
「だって…俺も燈也と一緒がよかった…友達だし…」
「…いつ引っ越すの」
「再来週には…」
「…そっか」
「あ、そうだちょっと待ってて」
「?」
俺は机の上に置いていた小さなくまのぬいぐるみを手に取った
「これあげる」
「え」
「あ、いやだった?」
「そういうんじゃなくて、いいの?」
「うん、それなら離れてても一緒にいるみたいでしょ?」
「…ありがと」
「またいっしょに遊ぼ」
「おう…」
あれ…これってもしかして走馬灯…!?まだ死にたくない!
目が覚めるとそこは燈也の部屋だった。
「あれ…ここ…」
一旦整理しよう…ここは燈也の家で、泊まりに来てて、お風呂入ってたら声がかかって…あれ!?着替えてない!?じゃあ今スッポンポンでは!?
慌てて自分の姿を確認するがすでに服は着ていたようだ…いつの間に…
…ん?寝ている間に着替えれるわけないし…着替えさせられたのでは!?
俺が驚いているとちょうどそこに燈也が来た
「あ、起きた?」
「うん…でもなんで」
誰が着替えさせたのか、いつここに来たのか、疑問なことが多かった
「あ、俺がここまで運んできちゃった、それに裸じゃ風邪引くだろ?…あ、変なことしてないから」
聞くとすべて燈也がやってくれたようだ。ありのままの姿を見られたなんてとても恥ずかしい…燈矢の方を向いていられず、そっぽを向いた。するとちょっと薄汚れたくまのぬいぐるみがあった。
「…?あれって」
「え?あ…」
「これ、小学生の時にあげたやつ…持っててくれたの?」
「うん、友里がくれたの」
「ありがと」
「なにが?」
「もう5年くらい前なのに覚えててくれたんでしょ?嬉しいなって」
「だって好きな子からもらったものだし」
「…好き」
「俺も好きだよ」
「…ちゅーしていい?」
「いいよ」
俺はベッドの上から体を起こし、燈也の頬に唇を寄せる
「こっちでしてよ」
そう言い、燈也は自分の口を指差す
「…ほっぺでいいじゃん」
ただでさえ恥ずかしいのだ、勘弁してほしい…キスなんて慣れてないし
「そ、そっちからしてよ」
「えー、友里から口にちゅーしてほしい」
「…一回だけね」
「ふふっしてくれるんだ」
「い、一回だけだから!」
「はいはい…」
一回だけとは言ったもののやっぱり恥ずかしい…でも言った手前やっぱやめたはできない
俺は覚悟を決め燈也の口に向かってキスをした
「…これでいい?」
「やだ、足りない」
今度は燈也が俺の唇を奪う。
「んっ…」
「友里かわいい」
「む…」
「友里俺とキスするの嫌?」
「…嫌だったらしていいか聞かない」
「そだね」
そうだ、今あの話をしよう。忘れてしまう前に…
「ねえ、高校出たらどうする?」
「ん?そーだな…同棲でもする?」
「え?」
「ん?同棲。一緒に住むの。」
「あ、えと…そうじゃなくて…進路…」
「あー大学行きたいけど」
「どこ行くの?」
「友里が行きたいとこならどこでも」
「そう…」
「友里も俺と一緒のとこ行きたいでしょ?」
「うん」俺は即答した
「即答じゃん」
「…俺燈也より頭良くないから…東大は無理」
「友里ってテスト何位くらい?」
「35とかその辺」
「別に悪くないじゃん」
「あの学校生徒100人しかいないから微妙だよ、それに燈也たち成績トップ3じゃん」
「あーまぁそっか」
…というか同棲という言葉を忘れるところだった
「ど、同棲ってどんなとこ住むの?」
「一軒家とか」
「え!?それ高いんじゃ…」
「父さん大企業の社長だから」
「…え、マジ!?」
「マジマジ」
「そうだったんだ…」
「だから大丈夫」
「でも申し訳ないから…」
「後で返せば大丈夫よ」
「でも…」
「そんなに俺と同棲したくない?」
「いや、そうじゃなくて」
「だったらたまには甘えなよ、父さんも俺達のこと応援してるみたいだし…」
「え、言ったの?」
「いや、言ったというか…バレたというか…」
「な、なるほど…」
まぁ確かに俺も燈也のこと好きかって聞かれたしな…そんな話をしているうちにも俺の眠気はどんどん襲ってくる
「今日はもう寝よっか」その燈也の言葉に俺は頷く。
「おやすみ、友里」
「ん…」
俺はまたこの間のように抱き枕のように燈也の腕の中で寝た。羞恥心より今は睡魔が勝ってしまうが付き合えたのだからこういうのも慣れていかないとな…