
「幸兄様朝なのです〜! 早く起きないと遅刻なのです〜」
朝7時、いつもと同じく妹に起こされた。
「今日はたまもか。おはよう」
「みんなで一緒に朝ご飯を食べるのです〜」
「今行くよ」
リビングに入ると他のみんなはテーブルについていた。
「幸兄遅いよ! ご飯冷めちゃうじゃん!」
「お兄ちゃんおはよーう!」
「おはよう幸近兄さん、はやく食べましょう」
「待たせて悪かったな……」
朝ご飯を食べていると夏鈴が怪訝なな顔で呟く。
「かりんたち明日から中間テストなんだー……」
「テンはいつも勉強してるから心配はないだろうが、夏鈴は大丈夫なのか?」
「もう全然だめ、テンに勉強教えてもらわないと……」
「私で良ければかまわないけど」
「ありがとう! そう言うお兄ちゃんは試験とかないの?」
「……」
幸近が無言で青ざめる。
「どしたのお兄ちゃん?」
「忘れてた……」
「え?」
「どうしよう夏鈴! 来週から試験なの忘れてたよ!」
「もう兄さんったらなんでそんな大事なことを忘れちゃうの?」
テンは呆れていた。
「幸兄はホントおっちょこちょいだよなー!」
「タケマル! 幸兄様はほんの少し抜けているだけなのです!」
「ははは……」
(たまもよ、それはフォローにはなっていないぞ……)
学校に着いてからも浮かない顔でいるとクリスタが話しかけてきた。
「はぁ? あんた今から勉強しても間に合うわけないでしょ!」
「だよなぁ……」
「まぁでもどうしてもって言うなら、わたしが勉強みてあげてもいいけど……」
「本当かクリスタ様〜!」
「そうよ! もっとわたしを崇め奉りなさい!」
「なぜか今だけはお前が神様のように神々しく見えるよ〜」
「そりゃそうよ、能力でそう見えるようにしてるんだから」
「そんなくだらない事に能力使うなよ」
「あ! あんた今くだらないっていったわね! そんなこと言ってると――」
「クリスタちゃん、あたしにもお願い……」
涙目のサーシャが話に割り込んできた。
「もうあんたまで……しょうがないわね」
「ソフィは勉強大丈夫なのか?」
隣ですまし顔の彼女にも尋ねてみた。
「当たり前でしょう? 私を誰だと思っているの? 学年主席様よ?」
「ソフィちゃん……助けて〜」
「もうサーシャったら……仕方ないわね」
「じゃあせっかくだから試験までの残り1週間、唯も誘ってみんなで勉強会なんてどう?」
と、クリスタが提案する。
「それはとてもありがたい話だが、場所はどうする?」
「そんなの決まってるじゃない、みんなで勉強できる所なんてあんたんち以外どこにあんのよ」
「そうね、テン達にも会いたいしちょうどいいわ」
ソフィもそれに続く。
「なんかパーティみたいで楽しそうだね〜! じゃああたしアニメのブルーレイ持っていくよ〜!」
「「それはやめなさい!!」」
珍しくソフィとクリスタの息が合った。
その日の放課後、皆が俺の家に集まった。
「もうお兄ちゃんったら、お姉ちゃん達が来るなら連絡してよね! なんの準備も出来なかったじゃない!」
「悪かったよ、突然決まってな……」
「ねぇこの写真に写ってるのってあんたの両親よね?」
クリスタがリビングに立て掛けてある写真を指差して言う。
「あぁそうだ」
「あんたの親って見たことないけど何してる人なの?」
「母さんは異能警察だったんだ。無能力者で初のグレイシスト7になった人で俺の憧れだ」
「へー、すごい人なのね」
「10年前、デニグレとの抗争で殉職しちゃったけどな」
「そうなのね……変なこと聞いちゃったかしら……」
「いや、そんな事はない。母さんは自分の仕事を全うして多くの命を救ったんだ。俺はそれを誇りに思ってる」
「じゃああなたが異能警察になりたいのも、お母さんに憧れての事だったのね」
と、ソフィ。
「あぁ。ガキの頃母さんにその夢の話をすると、とても喜んでくれたんだ。それで大人になったら同じ制服を着て一緒に写真を撮ろうって約束したんだ……」
少しの沈黙が流れたがすぐにそれはかき消された。
「その写真! みんなで撮りましょうよ!」
クリスタが思いついたように話す。
「それはいい考えだなクリスタ殿!」
「あたしたちが一緒に写ってもいいよね藤堂くん?」
「そうね、その為にはこの人を落第させないよう勉強しないとね」
「これは手厳しいですねソフィさん……。みんなありがとう、叶えたい夢がもう一つ増えたよ」
その時、隣にいた夏鈴が俺に向かって嬉しそうに小声で囁く。
「良かったね、お兄ちゃん」
「あぁ」
「ところで幸近のお父様は剣術の師範だと言っていたが、
どこに居られるのだろうか?」
「そう言えば山形には話していたな。俺の父さんはこの剣術道場の跡取りで、母さんとは門下生同士だったんだ」
「ご存命なのだろう?」
「生きてはいるんだが、母さんが亡くなった抗争に父さんも巻き込まれて目を悪くしてな……。それからは家を留守にする時間が増えて、今ではほとんど帰ってこないんだ」
「それは残念だ、是非ご挨拶したかったのだが……」
その後残りの弟妹も帰って来て、騒がしくなりつつも俺たちは勉強会を始めたのだった。
「あんた何回同じこと言わせるの! だからこれは刑法246条だってば!」
「そんな頭ごなしに怒鳴らなくても……。ソフィさん、クリスタが鬼教官すぎるんだが……」
「何度も同じ問題で間違えるあなたが悪いわ。サーシャ、そこ間違ってるわ、この問題は……」
「なるほどぉ、ソフィちゃん教えるの上手だねぇ」
ソフィが優しくサーシャに勉強を教える姿を見て幸近がクリスタの方を見る。
「なぁクリスタ、お前もああやって優しく教えてくれてもいいんじゃないか?」
「なによ……じゃああんたもソフィに教えて貰えばいいじゃない」
悔しそうな顔のクリスタを見てタケマルとたまもが茶々を入れる。
「あー! 幸兄がクリスタ姉をいじめてる!」
「幸兄様! 女の子をいじめちゃダメなのです!」
その言葉を聞いて幸近は慌てて弁明する。
「違うぞ! 決してそんなことはしていない! 俺はクリスタに勉強を教えてほしいんだ! お前じゃなきゃダメなんだ!」
「え?」
顔を赤らめて下を向くクリスタ。
「仕方ないわね……そこまで言うならもうちょっと優しく教えてあげるわよ……」
その時何故かソフィの肘が俺のみぞおちにクリーンヒットした。
「痛っ!!」
「ごめんなさい、肩が凝ったから腕を回そうとしたら偶然肘があなたのみぞおちに当たってしまったわ」
「ぐ、偶然って威力じゃなくないかコレ……」
「何を言っているの偶然よ。あなたレベルになるとこんなこと日常茶飯事でしょう?」
「どんなレベルなのかは知らんが、それは早く経験値周回しないと命の危険を感じる……」
「今は勉強に集中しなさいよ、落第候補生さん」
「なんか怒ってないか?」
「そんな訳ないじゃない」
勉強がひと段落ついたところで、夏鈴が声をかけてきた。
「みんな今日晩ご飯うちで食べていきなよ! かりんも勉強でご飯作れなかったからお兄ちゃんピザとろう! ピザ!」
「そうだな! みんな遠慮せず食べてってくれ」
その後皆で晩ご飯のピザを囲む賑やかな食卓の風景に、こんな日がいつまでも続けばいいと思う幸近だった。
第2部1話 また、始まる 完
《登場人物紹介》
名前:藤堂 真鈴
髪型:黒髪のセミロング
瞳の色:黒
身長:163cm
体重:49kg
誕生日:8月1日
年齢:享年33歳
血液型:B型
好きな食べ物:栗羊羹
嫌いな食べ物:生魚
ラグラス:なし

あれから俺は1週間の間、みっちりと勉強をした。
その甲斐あってなんとか赤点は避けられるだろうという程度の低い自信だけは持てるようになっていた。
「お兄ちゃん今日から試験だったよね?」
「とうとうこの日が来てしまったよ……」
「かりんたちはもう終わったから今は開放感でいっぱいだよねテン?」
「そうね、テストって初めて受けたけど結構緊張したから今はホッとしてるわ」
「お前も緊張とかするんだな」
「失礼ね兄さん! もう卵焼き食べてあげないからね!」
「え? お兄ちゃん、テンに卵焼き食べてもらってたの?」
「いや、それは……あの……2人ともごめんなさい!」
「「もう!!」」
「幸兄が怒られてる」
タケマルがニヤつきながらこちらを見ている。
「今のは幸兄様が悪いのです」
たまもも今回は助けてはくれなかった。
俺はその後の試験週間も乗り越え、クリスタ先生の地獄の特訓の成果もあり、自己採点の結果では赤点は免れたと感じていた。
――のだが、昼休み村上先生に呼ばれた。
「藤堂ちょっといいか?」
「はい」
「エマ校長からお前に話があると言われてるんだが、お前何かしたのか?」
「いえ、特段そのようなことは……試験も赤点ではないと思うんですが……」
「赤点ではないってお前……まぁとにかく放課後校長室に行ってくれ」
「分かりました……」
(一体なんの用件なんだ? まさか試験の結果が悪くて退学とか? いやまさかそんなことは……)
俺は考えるのを辞めた。そして放課後恐る恐る校長室の扉を開くと、そこには他に数人の生徒の姿もあった。その中にはよく見知ったいつもの4人の顔も並んでいる。
「これで全員揃ったようだな」
「エマ校長、これは一体?」
ソフィが尋ねる。
「いきなり呼び出してすまない。前々から話したいと思っていたのだが試験が近かった為、終わったこのタイミングで皆に来てもらったのだよ」
「それでご用件は何なのでしょうか?」
赤髪の、恐らく先輩の女性が口を開く。
「君達は近頃の異能犯罪についてどう思う?」
「犯人が検挙されている事件だけ数えても、年々増加傾向にあります」
黒髪で眼鏡をかけた、こちらも恐らく先輩であろう男性が答えた。
「その通りだ、そこで私は活発な異能犯罪に対してこの警察学校でも、近隣の住民を守るべく対応策を練るべきだと考えたのだ」
「どのような対策なのでしょう?」
「私の権限で学内から選抜隊を組織し、その者達には外部での異能使用の認可を与える事とする。そのメンバーがここに集まって貰った8名という訳だ」
「なぜ私達なのだろうか?」
山形が問う。
「君たち1年生5名の異能犯罪者の検挙率は入校1ヶ月程とは思えん素晴らしい成果だ。それを評価し選抜させて貰ったよ」
校長は先輩らしき生徒の方へ視線を移し続けた。
「そしてこの部隊には3名の優秀な2年生にも参加して貰う事とした。この部隊の隊長に任命したいのが、去年の学年主席であるセリーヌ君、後輩達に自己紹介を頼むよ」
校長がそう言うと先程の赤髪の女性が自己紹介を始めた。
「私は2年生のセリーヌ・フィラデルフィアだ。ラグラスは『氷華』。大気中や水場の水分を凍らせ操ることが出来る」
「そして副隊長にはマルコ君、頼む」
次に眼鏡の男性が話し始めた。
「僕は2年生のマルコ・ベル。ラグラスは『以心伝心』。離れている特定の相手と心の声で会話が出来る」
「そして残りの2年生の隊員として林君」
もう1人見覚えのない金髪で頭の上部に2つのお団子が印象的な女性がこちらを向いた。
「私は林玲だよ! よろしくね! ラグラスは『自己再生』。自分の傷を治すことが出来るの!」
玲はハッとしたような顔で幸近を見る。
「ってあれ? もしかして幸ちんじゃない?」
そう言われた瞬間ふと、この人と昔に会ったことがあるような気がした。
「もしかして玲姉ちゃん?」
「そうだよ! 久しぶりだねー!」
「玲、知り合いなのか?」
セリーヌが尋ねる。
「そうなの! 幸ちんとは同じ小学校でね、私が引っ越すまでは昔よく一緒に遊んだ幼馴染なんだー」
「本当にあなたって、3歩歩けば新しい女の子と出会うのね」
ソフィが怪訝な目を向けてくる。
「そんな言い方よせよ……幼馴染なんだから……」
そして校長が逸れた話を元に戻す。
「まぁあまり深く考えず、部活動のようなものと思ってくれれば良い」
「どんな活動なんでしょうか?」
「活動内容としては放課後に近所をパトロールしたり、近くで事件が起こった際には緊急の人員として派遣する事もあるだろう」
「願ってもない話だな」
「きっと早くから実践を積むいい経験となるはずだ。気が乗らない者は断って貰っても構わない」
もちろん任命された全員がこの話を受ける事となり、俺達8人は最初の任務として、自分達の選抜隊の名称を考えてくれと校長からの宿題が出された。そして自己紹介も兼ねて8人で集まり会議をすることになったのだ。
「では自己紹介も終わったところで、この部隊の名称を何にするか、良い案がある者はいるか?」
セリーヌ隊長が会議の指揮をとる。
「『ヒーロー戦隊マモルンジャー』なんてどうかしら?」
「おいクリスタ、今はふざける時間じゃないぞ」
「何言ってるの? 大真面目よ」
「……」
「他に案のある者はいないか?」
「『魔法少女隊サーシャーズ』はどう?」
「サーシャ……言いたい事はこれだけじゃないが、男もいるんだが……」
「えー? 可愛いと思うんだけどなぁ……」
「では『武士道一家』などいかがだろうか?」
「山形、お前の案がマシに思えてくるよ……」
「ぷはははは、幸ちんの友達は面白い子ばかりだねぇ」
玲が笑いを堪えられず吹き出してしまう。
結局その日は纏まらず、明日改めて皆で案を持ち寄る事となり解散となった。
夕飯の際、夏鈴とテンにその話をしてみた。
「何かいい案ないかな?」
「この前時代劇で見たのだけど『鬼面組』なんてどう?」
「テン……それは警察に捕まる側の名称だよ……」
「じゃあ『妹ラブ隊』にしなよ!」
「どんな羞恥プレイだよ!」
俺は自分で考える事にして、話をすり替えた。
「そう言えば、小学生の頃よく一緒に遊んでた玲姉ちゃんに学校で再会したんだ!」
「誰それ?」
「お前覚えてないのか? 玲姉ちゃんだよ!」
「かりんそんな人知らないよ?」
「まぁお前はまだ小さかったから覚えてなくても仕方ないか……」
その次の瞬間、タケマルが
「隙ありー!」と俺の皿から唐揚げを奪って頬張った。
「こら! タケマル! 兄さんのおかずとらないの!」
「幸兄様、わたしの唐揚げあげるです〜」
「たまもは自分の分食べていいんだぞ〜」
幸近はたまもの頭を撫でながら言う。
「おいタケマル、後で道場に来いよ、稽古つけてやる」
「幸兄が怒った! 助けてテン姉!」
「タケマルが悪いんだからちゃんと謝りなさい!」
本日の事件概要――窃盗一件。
容疑者、金土タケマル。被害者、藤堂幸近。
藤堂家の食卓は、本日も平和である。
第2部2話 校長の呼び出し 完
《登場人物紹介》
名前:セリーヌ・フィラデルフィア
髪型:赤髪ロングのストレート
瞳の色:紅
身長:171cm
体重:55kg
誕生日:3月30日
年齢:19歳
血液型:O型
好きな食べ物:シーフードパエリア、クロワッサン
嫌いな食べ物:フォアグラ
ラグラス:氷華
大気中や、水場の水分を凍らせ操ることが出来る

――放課後、皆で集まり持ち寄った案を出し合った。
だが、これという案が出ず残すはセリーヌ隊長の案だけとなり発表される。
「私の考えてきた案は『ラビットテイル』だ」
「直訳すると『ウサギの尻尾』ですよね? どういう意味なのですか?」
ソフィが尋ねる。
「私の故郷に伝わる昔話の題なのだが、あるところにウサギと狼がいた。
2匹はとても仲が良く、ある日協力してバターを作ろうという話になった。作ったバターをすぐに食べるのはもったいないから、冬の保存食とする為に森の木の下に埋め、この森には冬が来るまで近づかないようにしようと約束をするのだが、ウサギはその約束を破って1人で全部食べてしまうんだ。
結局それが狼にバレてしまい、ウサギは怒られて慌ててその場を逃げ出す。その時に人間の仕掛けた罠に引っ掛かり、自力では抜け出せなくなってしまった。
ウサギは狼に助けを求めるが、騙された狼はいい気がしない。だが狼はもう2度としないと誓うウサギの言葉を信じて助けてやるんだ。
その罠に引っかかった際にウサギの尻尾は千切れ、それ以降ウサギの尻尾は短くなってしまった――という話なんだ」
セリーヌは紅茶を一口啜り、さらに続けた。
「この話は嘘をつかれたのにそれを許し助ける狼の優しさと、嘘をつき罪を犯したウサギの業が私達の目指すものに近しいと感じるんだ。
罪を犯した者はそれを償わなければならない。だがその罪を許し、もう一度立ち上がることを応援する者が傍に居てやる事が大切なのではないか――とな。
そしてこのラビットテイルは植物の名にもなっている。
その植物の属名が『ラグラス』で、その花言葉は『感謝』だ。私たちにピッタリではないかと思ってな」
「………」
俺たちは隊長の説明に聞き入ってしまっていた。
「なんだかわたし達の案が幼稚に感じるほど筋が通っているわね」
クリスタが悔しがる。
「それにすっごくかわいいよぉ」
サーシャも乗り気だ。
「こんな名を思いつくとは流石は隊長殿だな!」
「俺もその案に賛成だ!」
こうして俺達学内選抜隊の名称は、『ラビットテイル』に決定したのだった。
それを校長に報告に行くと、「ほう、なるほど君たちらしい良い名だ……」と公認してくれ、翌日より活動が開始する事となった。
当面の間の活動は放課後、交代で2名ずつ選抜し近隣のパトロールに出ることだった。
そんな日々を続けていたある日、俺とクリスタがパトロールの当番になった。本来なら本日のお相手は山形だったのだが、なんでもクリスタは明日都合が悪いらしく交代して貰ったのだそうだ。
「今日も平和だなぁ……」
「ちょっとあんた! そんな気を抜いていたら凶悪犯を取り逃すかもしれないじゃない、真面目にやりなさいよ」
クリスタがそう言った瞬間、近くで叫び声が聞こえた。
「ひったくりよー! 誰か助けてー!」
声のする方を見ると女性が倒れながら助けを求めていた。
するとその女性が持っていたであろう鞄だけが宙に浮きながらこちらへ向かって来た。
「クリスタ気をつけろ! おそらく透明化のラグラスだ!」
「分かってるわ!」
クリスタはその鞄の進路を塞ぎこう叫ぶ。
「異能警察よ! 止まりなさい!」
その警告も虚しくその犯人の見えない攻撃により、クリスタは突き飛ばされてしまう。その突き飛ばされた方向が良くなく、クリスタは道路脇にあるドブに落ちてしまった。
「くそ! 止まれ!」
幸近の声にも耳を貸さず、逃走を続ける犯人の姿は見えないが、鞄を持つその手の位置だけは分かった為、強硬手段に出る。
「藤堂一刀流居合無刀『虚』!」
幸近に倒された犯人の透明化は解け、一件落着かと思われたが、クリスタの悲鳴が轟く。
「イヤァァアーーー!!」
なんとその犯人の男の透明化は自身の服までは効力が及ばないらしく、全裸だったのだ。うつ伏せに倒されながらもがく全裸の男の霰もない姿が、クリスタの位置から丸見えだった。クリスタはその犯人が連行されてからも、しばらくその場で縮こまり泣いていた。
「クリスタ、俺も悪かったよ……そろそろ機嫌なおしてくれよ……」
「あんたよくそんな事言えるわね……あんなもの見せられて、汚されて……わたしもう生きていけない!」
「そんな大袈裟な……」
「大袈裟じゃないわよ! せっかく今日は誕生日だったのに……この後ご飯とか行くの楽しみにしてたのに……」
「お前、今日誕生日だったのか?」
「そうよ……でももうどこにも行けない……」
考えるよりも先に口が動いていた。
「クリスタ、付き合ってくれ!」
「え? ちょ、ちょっとあんた、そういうのは順序とかタイミングとか、あ、あるでしょ……」
一気に赤面し動揺するクリスタ。
「あ、いや悪い、言い方が悪かった……この後ついて来てほしい場所がある」
辺りはすっかり暗くなり星も見えるようになってきた頃、俺は泥だらけのクリスタを連れて歩いていた。
「ちょっとどこに連れて行くつもりよ」
「いいから、もう少しなんだ」
人気のない薄暗い丘を登って行くと、少し開けた場所にでる。
「着いたぞ」
「こんなとこ連れてきて何をしようって――」
クリスタは吐き出した言葉を飲み込んだ。
そこはこの街を一望できる展望台で、キラキラと光る街の灯りと、星の瞬く夜空が悠然と広がっていた。
「綺麗……」
クリスタは幼少の頃を思い出しながらそう呟いた。
「どうだすごいだろ? これが俺の魔法だ」
「この街にこんな場所があったのね……」
「急だったからプレゼントは用意できないが、この魔法の景色を贈りたいと思ったんだ。来年はきっと、それなりの物を用意するよ」
「ねぇ……あんたの誕生日はいつなの?」
「1月10日だ」
「じゃあその頃には雪が降って、きっともっと綺麗に見えるわね……」
「冬にはあまり来た事はないが、そうだろうな」
「決めたわ」
「どうしたんだ?」
「この景色を私たちの"バター"にするの!」
「この前の隊長の昔話か?」
「そうよ。あんたの誕生日、きっとまたここに来ましょう? それまでこの魔法は、わたしの中で大切にしまっておくわ」
「約束を破っても、お前は助けてはくれなそうだな」
「当たり前よ。もし約束破ったら、尻尾だけじゃ済まさないから」
「クリスタ、誕生日おめでとう」
クリスタは泣いていた先ほどまでの表情とは一転して、この絶景とも甲乙つけ難い笑みを浮かべた。
「ありがとう、幸近……」
第2部3話 ラビットテイル 完
《登場人物紹介》
名前:マルコ・ベル
髪型:黒のミディアム
瞳の色:黒
身長:178cm
体重:72kg
誕生日:8月4日
年齢:19歳
血液型:B型
好きな食べ物:グラタン、ハム
嫌いな食べ物:ミミガー、馬肉
ラグラス:以心伝心
特定の相手と心の通話でやり取りが出来る
同時通話は10名ほどが限界
会話する条件は対象の顔と名前を知っていること

「幸近兄さん大変なの! ねぇ起きて!」
テンはベッドで横になっている幸近の腕を両手で掴み、体をゆすった。
「どうしたんだよ朝っぱらから……」
幸近が目を覚ますと、テンの顔が目の前にあった事に驚きつつ、その深刻な表情に眠気が吹き飛んだ。
「大変なのよ! 助けて……」
「どうしたテン……お前がそんなに慌てるなんて珍しいじゃないか」
「タケマルがね……学校に行きたくないって言うの……」
「熱でも出たのか?」
「ううん、平熱だし具合が悪そうでもないの……どうしよう兄さん……」
今にも泣きそうなテンを宥めると、俺はすぐにタケマルの部屋へと向かった。
扉を叩き、声をかける。
「タケマル! どうしたんだ? 学校で何かあったのか?」
「なんでもないよ! 今日は気分が乗らないんだ!」
「お前の気分で世界は回ってないんだぞ」
「知らねーよ! 今日は休む!」
「何があったか知らないが、今日だけだからな」
リビングに入るとテンが駆け寄って来た。
「タケマルどうだった……?」
「今日は仕方ないから休ませよう。放課後中学校に行って担任の先生に何があったのか聞いてくるよ」
「このままタケマルが引きこもっちゃったらどうしよう……。もしかしていじめられてるのかな……?」
「大丈夫、何があっても俺がなんとかする。それにタケマルももう小さな子供じゃないんだ、信じてやろうぜ」
「兄さん……」
「お前はいつも2人のお姉さんしてて偉いんだから、たまには兄貴にも面倒見させてくれよ」
テンは俺のTシャツの裾をギュッと掴み握りしめた。
「私……みんながちゃんと学校に行って真面目に生活しなきゃ、この家を出て行かないといけなくなるんじゃないかと思って、心配で……」
テンの目からは涙が溢れていた。
「テン……俺達はもう兄妹なんだ。血の繋がりなんてなかろうが、俺はお前達とずっと一緒に居たいと思ってるよ」
「にぃさぁん……」
日々溜め込んでいたものが爆発してしまったのだろう。初めてテンの大泣きする姿を見て、いつもはしっかり者のお姉さんだが、やはりまだ中学生の女の子なのだと実感した。
俺は放課後になると、タケマルの担任の先生に連絡をとって話を聞くことにした。
「学校で何かあったのでしょうか?」
「私の見ている限りタケマル君はクラスメイトとも仲良く過ごしていると思います」
「ではイジメなどはないと思って大丈夫ですか?」
「えぇ、むしろ彼はクラスのリーダー的な存在だと思います」
「そうですか……」
「でも心配ですね……もうすぐ授業参観もありますし」
「それはいつですか?」
「6月3日です。タケマル君からプリント預かってないですか?」
「すみません、忙しくて見れてなかったのかもしれません……」
家に帰ってからタケマルと2人で話をすることにした。
「タケマル、2人でラーメンでも食いに行くか」
「なんだよいきなり」
「たまには男だけで飯食うのも悪くないだろ」
「まぁいいけど……」
店に着いてから少し世間話をした。
「学校で友達は出来たか?」
「クラスのみんなとは仲良くなったよ。部活にもいっぱい誘われてるんだ!」
「すごいじゃないか、お前がやりたい事を選んでやればいいよ」
「でも……」
何かを言いたそうにするが、途中で口をつぐむ。
「遠慮せずに言ってみろよ。男同士、隠し事はなしだ!」
「……俺はみんなとは違うんだって、クラスのみんなを見てるといつも考えちまうんだ。みんなの普通はオレには分からない……。
幸兄、親がいないのっておかしいことなのか? みんなは授業参観に親が来るのは恥ずかしいから嫌だって言うんだ。でもオレは親がいないから、そんな気持ちにすらなれない。オレはやっぱりみんなとは違うのか?」
俺は、正直に言うと返答に困った。壮絶な過去を持ち、この年まで学校という社会に触れてこなかった少年に、どんな言葉をかけて良いのか。教師でも親でもない俺には分からなかった。でも兄として……何か伝えようと、俺は自分の人生を振り返り、今まで出会った人達の顔を思い浮かべながら口を開いた。
「誰だって人と違う部分を持ってるし、それについて悩んだり苦しむ事がある。その内容が違うだけで、お前が言うみんなだって、それぞれ苦しんでるんじゃないかな……」
「昔、おじちゃんが同じようなこと言ってた――」
タケマルは、カレルに引き取られた時の話を始めた。
――数年前。
見せ物小屋の檻の中で手足を繋がれ、鞭に打たれるタケマル。
「客の前に出たらもっと愛想良くせんか! 何度同じ事を言ったら分かるんだこのバケモノがっ!」
その男は罵声を浴びせながら、タケマルに暴行を続ける。
その男の背後に、カレルが突然現れた。
「そこまでにしなよ? 流石にやり過ぎじゃないかい?」
「お、お前は誰だ!? どこから忍び込んだ?」
「彼を引き取りに来た」
「な、何を言っている! そんな話聞いとらんぞ!」
「そりゃそうだよ。いま僕が決めたのだから……」
カレルは注射器を男の首に刺し、麻酔を打ち込んだ。
「おじちゃん……だれ……?」
ボロボロのタケマルが尋ねる。
「僕はカレル」
「おじちゃん、オレを殺してよ……?」
「なぜだい?」
「もう……疲れたんだ……生きてたって、痛いし、お腹は減るし、良い事ないんだ……」
「君、名前はあるかい?」
「タケマル……」
「いいかいタケマル。苦しむことから逃げちゃいけないよ? 人生はずっと苦しいんだ。そして苦しさを知ると、いつか苦しみに慣れてくる。これは君にとって大きな強さになるはずだ。その強さを手に入れた時、きっと君は人の痛みを分かってあげられる人間になれる」
「もう十分に痛みは知ってる……」
「そのようだね。その傷、痛むかい?」
「痛いよ。いつも夜が明けるとパンパンに腫れてるんだ」
「違う。僕が聞いたのは体の傷じゃなくて、心の傷の方だよ」
「……なんでそんなこと聞くの?」
「僕にはそっちの方が、よっぽど重症に見えたからね」
「痛い……。体の傷より、ずっと……」
タケマルは、たまらず泣き出した。
「僕のところには、君と同じように心に傷を持った子があと2人いる。人は誰でも、それぞれ少なからず悩みを抱えながら生きているんだ。若くしてその痛みを知った君達は、きっと人に優しくなれる」
「オレの……この傷、治るかな……?」
「体の傷と同じで、生きていれば治るさ」
「そっか……じゃあもうちょっとだけ、生きてみるよ」
とある10月9日、タケマルがこの世に生まれてから2つ目の苗字と、誕生日が与えられた――
オレはその話を聞いて複雑な心境だったが、タケマルにとってカレルは親同然だった。綺麗な思い出のまま、この少年の心に生きる糧となって残り続けてくれることを、静かに願った。
「お前はもう、その頃とは違うよな?」
「うん。今は……あの時より、ずっと楽しい」
「自分が人とは違うなんて、当たり前の事なんだよ。自分と同じ奴しかいない世の中なんて、つまんないだろ」
「オレ、明日から学校行くよ! みんなオレがいないと寂しがるだろうからさ!」
「あぁ、友達を大事にするのが、子供の仕事みたいなもんだ」
翌日からタケマルは、いつも通り元気に学校へ登校していった。
「兄さん……タケマルのこと、ありがとう」
「あいつはお前の弟でもあるが、俺の弟でもあるんだ。お礼を言われるような事は何もしていないよ」
「でも……」
テンが言葉を詰まらせる。
「それとな、お前だって俺の妹なんだから、この先お前自身の事で何か悩みが出来たなら、ちゃんと相談しないと怒るからな」
「私は……自分のことは自分でなんとかできるわ」
「あんなに泣いてたくせにか?」
「それを言うのは卑怯よ! 兄さんのいじわる!」
「なんとでも言えよ。お前に兄さんって呼んで貰えるなら、俺はなんだってできるんだ」
「何よそれ……」
「いつでも頼れってことだよ。妹1人救えない奴が、警察になんてなれねぇだろ」
「そんなこと言って、毎日泣きついてもいいの?」
「おぉ! それは最高のご褒美だな。あんなにかわいい泣き顔が毎日見られるだなんて」
「もう知らない! 兄さんのバカ! 私先に行くからね、行ってきます!」
「おう、行ってらっしゃい」
――タケマルの教室――
「では今日は授業参観だから、保護者の方が来られるけど、いつも通りに頑張ってね!」
教室の後ろには、ぞろぞろと保護者が集まってきた。
「うちの親来てるよ、超恥ずいわぁ」
「え? 翔太君の親どれー?」
「あれだよ、あの緑の――」
教室がざわざわと盛り上がる中、タケマルは後ろを振り返ることなく、ずっと前だけを見ていた。
「あっ! いた! タケマルくーん!」
「えっ?」
呼ばれるはずのない自分の名前が背後から聞こえた事に驚き、振り返る。
「サーシャ姉? なんでここに?」
「タケマル! しっかり授業受けるのよ!」
「タケマルの勇姿、しかと見届けに来たぞ!」
「クリスタ姉に、唯姉まで……」
「あなたがモタモタしてるから遅くなったじゃないの」
「お前が途中で道間違えるからだろ。タケマル、しっかりやれよ?」
「ソフィ姉、幸兄……なんで……」
「えー! あれ全員タケマル君の家族なの?」
「すごい沢山来てるじゃん! しかも美人な人ばっかり! いいなぁ!」
「ま、まぁな! 俺にはおせっかいな兄ちゃんと、綺麗で優しい姉ちゃんがたくさんいるんだぜ!」
タケマルは嬉しさと恥ずかしさが共存する感情を味わい、皆が言っていたのはこれの事かと、思い知ったのだった。
憂鬱でしかなかった授業参観だったが、この時からタケマルは自分1人の為に用意された舞台に立たされたような、そんな感覚を味わっていた。
「じゃあこの問題分かる人ー?」
「はーい!」
「すみません、保護者の方はちょっと……」
「クリスタ姉! 恥ずかしいからやめてくれよ!」
「何よ、じゃああんたが早く答えなさいよ!」
「タケマル君のお姉さんっておもしろい人だねー!」
教室中が笑いに包まれ、無事に授業参観は終わった。
俺たちは5人で中学校から出ると、校舎の方から大声で呼びかけられる。
「おーい! みんななんでここに居るのー? 学校はー?」
教室の窓から顔を出す、夏鈴とテンの姿が見えた。
その問いに対して俺達は大声でこう答えた。
「気分じゃないからサボったー!!」
第2部4話 サボりの美学 完
《登場人物紹介》
タケマルの担任の先生
名前:津田 松子
髪型:黒髪ショート
瞳の色:黒
身長:140cm
体重:35kg
誕生日:12月31日
年齢:26歳
血液型:A型
好きな食べ物:梅、無花果
座右の銘:環境より学ぶ意志があればいい
ラグラス:不眠
眠ることを必要としない
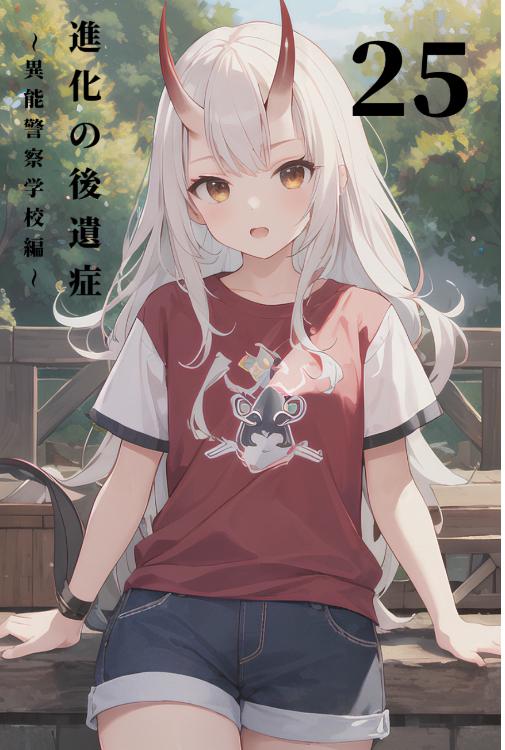
薄暗い部屋で、1人の男が部屋のあちこちに貼られている写真を見つめながら、誰かに電話をかけた。
「やぁ、君がジャッカルかい? 殺してほしい人間がいるのだが受けてくれるかい?」
「私の依頼金は高いが、用意できるのか?」
「僕を誰だと思っているんだい? その程度の金額掃いて捨てるほど擁しているさ」
「依頼金は指定の口座に前払いだ」
「分かっているよ、2人分振り込んでおく。君の事は信用しているがくれぐれも失敗などはよしてくれよ」
「私は依頼を失敗した事はない」
「そうだったね、ではよろしく頼むよ」
そう言って電話を切るともう一度壁の写真に目をやる。
「ソフィ、僕は必ず君を手に入れてみせるよ……」
その部屋に貼られていた写真の全てにソフィの姿が写っていたのだった。
――藤堂家道場。
「どうだテン? この新技!」
「どれも応用が効いて幸近兄さんと相性が良い技だと思うけど、最後のは……兄さんらしくなくて怖い」
「これが役に立つ日が来るかもしれないから、武器として持っておくのはいいと思うんだ」
「それでも……例え稽古でも私にはもう使わないで欲しい……」
「分かったよ。怖がらせて悪かったな」
「2人ともー! ご飯出来たよー!」
「今行く!」
居間に入るとたまもが駆け寄ってきた。
「幸兄様! 今日はわたしもお手伝いした餃子なのです〜」
「偉いじゃないかたまも〜、美味そうだ!」
「前回わたしだけ出番がなかったので、今回は頑張ってみたのです〜」
(前回とはなんの事か分からんが、たまもには今後重要な役割が待っているような……なんだかそんな気がする……)
「たまも、そういう事はオブラートに、いや餃子の皮くらいに包んだ言い方しないと……」
「幸兄様、それを言うなら春巻きの皮の方が良いのです〜。伏線は"張る"と言いますし、種を"蒔く"とも言うのです〜」
「こりゃ一本とられたな!」
「お兄ちゃん達なんの話してるの? 早くご飯食べよう?」
食事中テレビでニュースが流れ、割とこの近くで身元不明の遺体が発見され、その殺害現場の状況から犯人は世界的に有名な殺し屋『ジャッカル』の仕業ではないかという内容だった。
「最近また物騒な事件増えたよねー」
「この前の変態のひったくりも幸兄が捕まえたんだろ?」
「幸兄様がいれば安心なのです〜」
「でもお兄ちゃん、あんまり無茶はしないでね?」
「そうよ、兄さんはいつも無茶ばかりするんだから」
「分かってるよ、そこら辺のゴロツキならともかく、流石に殺し屋とやり合うなんてごめんだしな」
次の日学校に行くと村上先生から話があった。
「昨日ニュースで見た者もいるかもしれないが、殺し屋ジャッカルがこの国に潜伏している可能性がある。奴は一度依頼を受ければ一般人から国の要人まで構わず殺す。
その素性はジャッカルという通り名と男性である事以外ほとんど知られておらず、その理由は奴に狙われた者は1人残らず殺されてしまっているからだ」
「先生! そいつは一体どんな能力なのかしら?」
「数々の現場の痕跡から恐らく身体強化のラグラスではないかと言われているのだが、詳しくは解明されていない」
「じゃあそいつの強さは未知数ってことね……」
「フィールドの言うように奴は強く、そして実績がある。世界共通指名手配犯でありその星の数は4つ。
以前藤堂が大怪我を負わされたレッド・ビスクですら星3つの犯罪者であり、その昔レッドの兄貴分だったという噂もある」
(あの狼男より強いのかよ……)
「皆も常に複数人で行動するなど、充分に気を付けてくれ」
この話を受けて俺たち『ラビットテイル』の面々は、放課後に集まり緊急会議を行ったのだった。
「やはりパトロールの人員を増やした方が良いと思うのだが」
「僕もセリーヌの意見に賛成だ。さすがに奴は危険すぎる」
「2人が言うなら私も〜」
玲が気怠げに続く。
「それではしばらくの間2人1組を3チームに増やしてパトロールをするのはどうでしょうか?」
と、ソフィが提案する。
「そうだな! それがいい!」
山形もそれに賛成する。
「え〜、って事は1日に2人しか休めなくなるの〜?」
サーシャだけは沈んだ顔をしていた。
「殺し屋が捕まるまでの辛抱よサーシャ! なんなら私たちで捕まえちゃいましょう!」
「やる気十分なところ悪いがフィールド君、素性も能力も分からない相手をどうやって捕まえるんだい?」
(よくぞ言ってくれたマルコ先輩……)
「そ、それは……き、気合い……よね? 唯!」
「え? あぁ! もちろんだ!」
「では今日からパトロールを増員しよう。元々本日の担当だった藤堂とヨハネスの他に4人だが、やる気一杯のフィールドと山形、マルコと私で良いか?」
隊長の仕切りによって本日のパトロールメンバーが決定した。
そして会議が終わり、俺とソフィが世間話をしながらパトロールをしていた時のこと。
「そういえば隊長の名前ってどこかで聞いた事あるんだよなぁ……」
「あなたは本当に何も知らないのね、呆れるわ」
「なんだよ! 知ってる事があるなら教えろよ!」
「それが人に物を尋ねる態度かしら?」
「くっ……教えて下さいソフィさん」
「様よ」
「教えて下さいソフィ様ぁ〜」
「やけに棒読みに聞けえるけどまぁいいわ。隊長のお家は異能警察一家として名のある名家なの」
「お嬢様ってことか?」
「彼女の父は異能警察内に10人しかいない警視監の1人で、歳の離れた姉は現グレイシスト7のマライア・フィラデルフィアよ」
「それで隊長は学年主席って……とんでもないエリート一家じゃないか」
「そうね……でも優等生には優等生なりの悩みもあるんじゃないかしら……」
ソフィはその場で立ち止まり一方向を見つめた。その視線の先には2人の男の姿があった。
「ハインツ兄さん!」
「ん? ソフィじゃないか!」
ソフィはその男の元へと走り出した。
「兄さん、なんでここに?」
「それが例の事件で発見されたご遺体の身元が、私達の国の国民だったんだよ。その事件の捜査で急遽検死官として選ばれたティコと共にこの国に入ったんだ」
「やぁソフィ、久しぶりだね」
もう1人の男が言う。
「ティコさん、お久しぶりです」
「それでソフィ、隣の方はご友人かな?」
「初めまして、ソフィさんの友人の藤堂幸近です」
「こちらこそ初めまして、ソフィの兄のハインリッヒ・ヨハネスです。ソフィの母国で刑事をしているんだ。いつも妹と仲良くしてくれてありがとう。そしてこちらは医師で友人の……」
「ティコ・アンブロワーズです、よろしく」
「それにしてもソフィ、君が男性と歩いているなんて珍しいじゃないか! 将来は医者か弁護士と結婚すると、あんなに豪語していたのに、心変わりでもあったのかい?」
「ちょっと兄さん! この人はそんなんじゃないわ!」
兄と話すソフィはいつも俺達に見せている顔とはどこか違い、なんだか少し幼くなったように思えた。
第2部5話 殺し屋ジャッカル 完
《登場人物紹介》
名前:ハインリッヒ・ヨハネス
髪型:金髪ミディアム
瞳の色:ブラウン
身長:180cm
体重:75kg
誕生日:11月15日
年齢:25歳
血液型:O型
好きな食べ物:ザッハトルテ
嫌いな食べ物:辛いもの
ラグラス:危険察知
自らとその周囲に危険が降りかかる数秒前に察知することができる
この作家の他の作品
表紙を見る
ベースは主人公成長型の異世界転生ファンタジー。
の筈なのに、異世界で出会うダークマター製造機の王女、訳ありメイド、ケモ耳妹、ツンデレ騎士、ポンコツエルフ等のあるあるだけど魅力的なキャラクターと繰り広げるドタバタコメディが物語の進行を全力で邪魔してくる!そんな作者泣かせのキャラクター達を愛でるも良し、主人公の成長を応援するも良し、たまに訪れるバトルアクションに手に汗握るも良しの『愛情、努力、勝利』の王道異世界ファンタジー!
表紙を見る
とある繁華街にある雑居ビル葉戸メゾン。
このビルの2階にある『Bar Loiter』には客は来ないが、いつも事件が迷い込む!
このバーで働く女子大生の神谷氷見子と、社長の新田教助による謎解きエンターテイメント。
事件の鍵はいつも『カクテル言葉』にあり!?
気軽に読める1話完結型ミステリー!
表紙を見る
聖ヴィリアン暦1092年――桃色の花が咲く頃。
この日、勇者が死んだ――。
魔王を倒した翌朝、宿屋の一室で静かに息を引き取っていた勇者レイン。その信じられない状況に、パーティメンバーの3名は悲しみにくれていた。
そこへゆっくりと扉が開き、葬儀屋が現れる。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…





