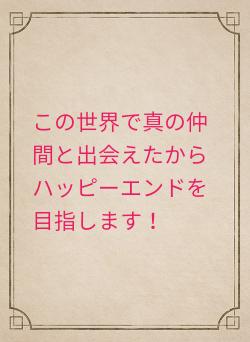ガルズさんに連れられた宿は宿屋ではなく館だった。
え? わたし、なにか聞き間違いした?
「あ、あの、ここは?」
「この一帯を治めているサンドラ男爵の館です」
男爵の館? な、なぜに? とは訊けず、そのままガルズさんのあとに続いて門を潜った。
館の前には馬車が何台も止まっており、騎士や兵士っぽい方々が荷物を積み込んでいた。
「なにかありまたしたか?」
なにか一から積み始めた感じがあった。それに、兵士っぽい方々が包帯をしている。
「ここに来る前に魔物に襲われましてね、二十日ほど足止めくらいまして、馬車の修理のために荷物をすべて降ろしたのです」
やはり旅って危険なのね。わたしも気をつけないと。
「さすが一人で旅をしているだけはありますね」
「はい?」
すみません。ちょっとなにを言ってるのかわかりません。聞き流しちゃいましたか?
「状況を見て、わたしの答えで納得できる。魔物と聞いても恐れることもない。男でも一人旅は心が折れるものですよ」
そうなんだ。まあ、旅と言う旅もしてないし、一日で心が折れたら精神惰弱と言うものだわ。
「──ガルズ様、お帰りなさいませ」
騎士様の一人がガルズ様に気がついて近寄って来た。
「バドル。今戻った。準備はどうだ?」
「申し訳ありませ。あまり捗ってません」
バドル様と言った騎士様も頭に包帯を巻いてある。魔物襲撃は相当のものだったようね。
「そうか。無理するなと言いたいが、さすがにこれ以上遅れるのは困る。なんとか頑張ってくれ」
なにか困ったことになっているようね。
「ガルズ様。お話し中申し訳ありませんが、よければわたしが回復魔法を施しましょうか?」
お世話になるんだし、回復魔法くらいしますよ。
「……回復魔法が使えるのですか……?」
「失くした四肢を治すほどではありませんけど、折れた骨くらいなら問題なく治せます」
回復する相手が少なかったので経験不足なんです。
「……あなたの言葉を疑うわけではありませんが、その、回復魔法を見せていただけませんか……」
「はい。では──」
と、騎士様の怪我を回復させる。
「……どう、なのだ……?」
戸惑いながら頭や体を触る騎士様。酷い傷じゃなかったから効果がわかるかしら?
「……な、治りました。しかも、視力もよくなりました……」
視力? まあ、回復魔法って体全体にかけるもの。不具合を起こしているところも治しちゃうのよね。おばあ様なら部分的に治しちゃうんだけど、未熟なわたしには無理だわ。
「シャーリー嬢は、聖女なのですか?」
「いえ、侍女ですよ」
少し前までは家事手伝いでしたけど。
「この程度の腕ですが、どうします?」
「是非、お願いします」
と言うので怪我をした方々を回復するべく館に入った。
「サンドラ男爵を呼べ! アリータもだ」
ガルズ様が自分の家のように指示を飛ばす。優しい人だと思ったけど、国の顔として外国にいく人は厳しい部分もあるのね。
「シャーリー嬢。荷物をお預かりします」
「え、あ、はい。お願いします」
なんて思わず騎士様に鞄を預けてしまったが、騎士様がすることではないんじゃないの?
「こちらへ」
と、ガルズ様に促されて反応することもできない。そのまま館の奥へと向かった。
男爵もいろいろあり、裕福な者もいればそうでない者いる。サンドラ男爵家は裕福なほうで、館の裏から出ると別棟があった。
別棟に入ると、なにかムッとする臭いが鼻腔に殴りかかって来た。
「せ、清浄! 清浄! 清浄!」
鼻を押さえながら清浄を連発する。臭いったりゃありゃしないわ!
なんとか清浄し終えたらベッドに寝ている怪我人を纏めて回復させる。
「ガルズ様。食事を与えてください。回復後はとてもお腹が空きますから」
わたしの回復魔法は完全な回復魔法ではなく、治癒魔法よりの回復魔法だ。なのでその人の魔力や生命力を使ってしまうので、食べないと逆に体を壊してしいかねないのよね。
「……領域回復……」
とは、広範囲で回復させる聖女級の回復魔法だ。
「わたしのは力技ですよ」
この程度で聖女扱いされたらたまったもんじゃないわ。恥ずかしいったりゃありゃしない。
「魔力は大丈夫ですか?」
「ええ。問題ありません。魔力があるだけが自慢ですから」
と言っておく。正直に言っても厄介ですからね。
「ガルズ様!」
と、恰幅のよい男性と三十くらいのご婦人が現れた。おそらく、男爵とガルズ様の奥様でしょう。
「いったいなにが?」
ベッドから起き出した方々を見て戸惑っているが、わたしが口出せることではないので黙ってます。
ガルズ様の説明にお二人がわたしに目を向けるが、紹介がまだなので静かに控えています。一応、侍女って立場ですので。
「シャーリー嬢。こちらがサンドラ男爵です」
「シャルロット・マルディックと申します」
「あ、ああ……」
控えめな反応にサンドラ男爵が戸惑い気味だ。
「旦那様。あとはわたしたちが」
すぐにガルズ様の奥様(の後ろには男爵の奥様らしきご婦人がいます)が間に入り、微妙な空気を吹き飛ばした。
「そうだな。シャーリー嬢に部屋を用意してやってくれ」
なにか目配せるガルズ様に、わかりましたとばかりに頷く奥様。なにか憧れる関係ね。
「はい。シャーリー嬢。こちらへ」
「はい」
素直に奥様に従い、その場をあとにした。
え? わたし、なにか聞き間違いした?
「あ、あの、ここは?」
「この一帯を治めているサンドラ男爵の館です」
男爵の館? な、なぜに? とは訊けず、そのままガルズさんのあとに続いて門を潜った。
館の前には馬車が何台も止まっており、騎士や兵士っぽい方々が荷物を積み込んでいた。
「なにかありまたしたか?」
なにか一から積み始めた感じがあった。それに、兵士っぽい方々が包帯をしている。
「ここに来る前に魔物に襲われましてね、二十日ほど足止めくらいまして、馬車の修理のために荷物をすべて降ろしたのです」
やはり旅って危険なのね。わたしも気をつけないと。
「さすが一人で旅をしているだけはありますね」
「はい?」
すみません。ちょっとなにを言ってるのかわかりません。聞き流しちゃいましたか?
「状況を見て、わたしの答えで納得できる。魔物と聞いても恐れることもない。男でも一人旅は心が折れるものですよ」
そうなんだ。まあ、旅と言う旅もしてないし、一日で心が折れたら精神惰弱と言うものだわ。
「──ガルズ様、お帰りなさいませ」
騎士様の一人がガルズ様に気がついて近寄って来た。
「バドル。今戻った。準備はどうだ?」
「申し訳ありませ。あまり捗ってません」
バドル様と言った騎士様も頭に包帯を巻いてある。魔物襲撃は相当のものだったようね。
「そうか。無理するなと言いたいが、さすがにこれ以上遅れるのは困る。なんとか頑張ってくれ」
なにか困ったことになっているようね。
「ガルズ様。お話し中申し訳ありませんが、よければわたしが回復魔法を施しましょうか?」
お世話になるんだし、回復魔法くらいしますよ。
「……回復魔法が使えるのですか……?」
「失くした四肢を治すほどではありませんけど、折れた骨くらいなら問題なく治せます」
回復する相手が少なかったので経験不足なんです。
「……あなたの言葉を疑うわけではありませんが、その、回復魔法を見せていただけませんか……」
「はい。では──」
と、騎士様の怪我を回復させる。
「……どう、なのだ……?」
戸惑いながら頭や体を触る騎士様。酷い傷じゃなかったから効果がわかるかしら?
「……な、治りました。しかも、視力もよくなりました……」
視力? まあ、回復魔法って体全体にかけるもの。不具合を起こしているところも治しちゃうのよね。おばあ様なら部分的に治しちゃうんだけど、未熟なわたしには無理だわ。
「シャーリー嬢は、聖女なのですか?」
「いえ、侍女ですよ」
少し前までは家事手伝いでしたけど。
「この程度の腕ですが、どうします?」
「是非、お願いします」
と言うので怪我をした方々を回復するべく館に入った。
「サンドラ男爵を呼べ! アリータもだ」
ガルズ様が自分の家のように指示を飛ばす。優しい人だと思ったけど、国の顔として外国にいく人は厳しい部分もあるのね。
「シャーリー嬢。荷物をお預かりします」
「え、あ、はい。お願いします」
なんて思わず騎士様に鞄を預けてしまったが、騎士様がすることではないんじゃないの?
「こちらへ」
と、ガルズ様に促されて反応することもできない。そのまま館の奥へと向かった。
男爵もいろいろあり、裕福な者もいればそうでない者いる。サンドラ男爵家は裕福なほうで、館の裏から出ると別棟があった。
別棟に入ると、なにかムッとする臭いが鼻腔に殴りかかって来た。
「せ、清浄! 清浄! 清浄!」
鼻を押さえながら清浄を連発する。臭いったりゃありゃしないわ!
なんとか清浄し終えたらベッドに寝ている怪我人を纏めて回復させる。
「ガルズ様。食事を与えてください。回復後はとてもお腹が空きますから」
わたしの回復魔法は完全な回復魔法ではなく、治癒魔法よりの回復魔法だ。なのでその人の魔力や生命力を使ってしまうので、食べないと逆に体を壊してしいかねないのよね。
「……領域回復……」
とは、広範囲で回復させる聖女級の回復魔法だ。
「わたしのは力技ですよ」
この程度で聖女扱いされたらたまったもんじゃないわ。恥ずかしいったりゃありゃしない。
「魔力は大丈夫ですか?」
「ええ。問題ありません。魔力があるだけが自慢ですから」
と言っておく。正直に言っても厄介ですからね。
「ガルズ様!」
と、恰幅のよい男性と三十くらいのご婦人が現れた。おそらく、男爵とガルズ様の奥様でしょう。
「いったいなにが?」
ベッドから起き出した方々を見て戸惑っているが、わたしが口出せることではないので黙ってます。
ガルズ様の説明にお二人がわたしに目を向けるが、紹介がまだなので静かに控えています。一応、侍女って立場ですので。
「シャーリー嬢。こちらがサンドラ男爵です」
「シャルロット・マルディックと申します」
「あ、ああ……」
控えめな反応にサンドラ男爵が戸惑い気味だ。
「旦那様。あとはわたしたちが」
すぐにガルズ様の奥様(の後ろには男爵の奥様らしきご婦人がいます)が間に入り、微妙な空気を吹き飛ばした。
「そうだな。シャーリー嬢に部屋を用意してやってくれ」
なにか目配せるガルズ様に、わかりましたとばかりに頷く奥様。なにか憧れる関係ね。
「はい。シャーリー嬢。こちらへ」
「はい」
素直に奥様に従い、その場をあとにした。