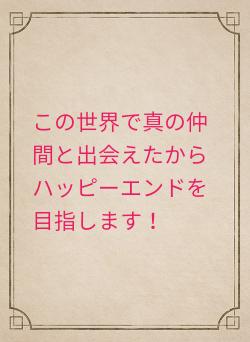異次元屋とは時間の流れが違うので、おば様の霊体はすぐに戻ってきた。
けど、その表情は何年もいっていたかのようにやつれている。人って霊体の疲れも肉体に影響を及ぼすのね。霊体回復の魔法がないか今度リューケンさんに尋ねてみようっと。
「……疲れたわ……」
侍女長様がすぐにお酒を出す。あそこまでいくと未来視ができるんじゃないかと思うわ……。
実際はおば様の行動や考えを理解しているのでしょうが、極めたら未来視と変わらないわね。
「労う言葉も見つかりません」
侍女としての立場であるわたしでも疲労感が凄まじいのに、被害者(としか表現できないわ)の立場ならその疲労は推し測ることもできないわ。
「久しぶりに胃が痛いわ」
胃の辺りを擦るおば様。責任感があると長生きできなさそうね。
「死者の石はすべて売却したわ」
「……一つ残らず、ですか?」
「あんな怖いもの一つたりとも残したくないわよ。もしかして、不味かったかしら?」
急に冷静になるおば様は、自分のしたことに不安になったようだ。
「いえ、不味いとは思いませんが、証拠を残しておいたほうはよかったとは思います」
なんなのかわからないものを残しておかないほうがいいとは思う。なにが仕掛けられてるかわかったもんじゃないしね。けど、だからと言ってすべてを手放してしまうのも違うと思う。
魔術結社との関係は良好でしょうが、情報を共有しているわけじゃない。世界レベルに合わせて情報を統制してるはずだ。つまり、わたしたちは魔術結社から見れば下の立場だと言うこと。情報をくださいと言っても簡単にはくれないでしょうね。
「……クッ。不味ったわね……」
侯爵夫人とは思えない悪態をつくおば様。さすがおばあ様と交流があった人よね。おば様が手玉に取られたわ。
そんなおば様に、わたしは小箱を卓に置いた。
「万が一のために少し残しておきました」
フフと、驚くおば様に笑ってみせた。
「……あなたは……」
手癖が悪いとは言わないでくださいね。主人の間違いを正すのも配下の役目ですしね。
「このことを知っているのはわたしと奥様、そして、侍女長様だけです」
その秘密をどうするかはおば様が決めること。わたしたちはタダ、口を閉じるだけである。
「ハァ~。あなたも悪いことを考えるようになってしまったのね……」
悪いことって、まあ、悪いことか。主に黙ってやったんだから。
わたしはまだ未熟な侍女。身を挺して、なんてまだできないわ。
「簡易な封印はしているようね」
「この世界に、聖なる魔法はありませんが、死人からして光系、闇系、回復系は効果があるはずです」
一つ、いいですかと目で問うと、理解したおば様は頷いた。
手に回復系魔法を纏わせながら死者の石をつかむと、煙を吹き出した。
「大丈夫だとは思いますが、安全のために吸わないでくださいね」
たぶん、回復煙──傷を修復するときに出る血の水蒸気だとは思うけど、未知なものは吸わないほうがいいでしょうよ。
ハンカチを出して口と鼻を覆い、おば様と侍女長様もそれに倣った。
完全に消えたら窓と戸を開けて換気をする。
「……回復魔法が効果あり、ですね。となれば死人も回復魔法で排除できそうですね」
まだ二十個近くある。対応策が練れるくらいには充分な量でしょう。
「そうね。もし、他の敷地にもあったら国が動くでしょうしね」
あ、そうか。ここだけに死者の石をばら蒔くはずがないか。他にもと考えるのは当然よね。
……タダ、ばら蒔けるほどの量になると秘密結社との繋がりは太く、計画が壮大ってことになるけどね……。
「こんなものを持っていたくないけど、収納魔法で仕舞っておくしかないわね」
魔法陣を描き、箱を異次元に仕舞った。
「シャーリー。あなたのことだから残りはないでしょうが、念のため、もう一度探してみてちょうだい」
「畏まりました。動きやすい服に着替えて隅々まで探してみます」
一応、侍女長様を見ると、やりなさいとばかりに小さく頷いた。
二人に一礼して部屋を出て自分の部屋へと向かった。
「……うん。確かにわたしは悪い娘よね……」
卓の上に置いていた死者の石をハンカチで包み、スカートの収納ポケットへと仕舞った。
おば様たちには申し訳ないけど、わたしも死者の石には興味がある。密かに調べさせていただきますわ。オホホ。
動きやすい服へと着替え、残りがあるかを探しに庭へと向かった。
けど、その表情は何年もいっていたかのようにやつれている。人って霊体の疲れも肉体に影響を及ぼすのね。霊体回復の魔法がないか今度リューケンさんに尋ねてみようっと。
「……疲れたわ……」
侍女長様がすぐにお酒を出す。あそこまでいくと未来視ができるんじゃないかと思うわ……。
実際はおば様の行動や考えを理解しているのでしょうが、極めたら未来視と変わらないわね。
「労う言葉も見つかりません」
侍女としての立場であるわたしでも疲労感が凄まじいのに、被害者(としか表現できないわ)の立場ならその疲労は推し測ることもできないわ。
「久しぶりに胃が痛いわ」
胃の辺りを擦るおば様。責任感があると長生きできなさそうね。
「死者の石はすべて売却したわ」
「……一つ残らず、ですか?」
「あんな怖いもの一つたりとも残したくないわよ。もしかして、不味かったかしら?」
急に冷静になるおば様は、自分のしたことに不安になったようだ。
「いえ、不味いとは思いませんが、証拠を残しておいたほうはよかったとは思います」
なんなのかわからないものを残しておかないほうがいいとは思う。なにが仕掛けられてるかわかったもんじゃないしね。けど、だからと言ってすべてを手放してしまうのも違うと思う。
魔術結社との関係は良好でしょうが、情報を共有しているわけじゃない。世界レベルに合わせて情報を統制してるはずだ。つまり、わたしたちは魔術結社から見れば下の立場だと言うこと。情報をくださいと言っても簡単にはくれないでしょうね。
「……クッ。不味ったわね……」
侯爵夫人とは思えない悪態をつくおば様。さすがおばあ様と交流があった人よね。おば様が手玉に取られたわ。
そんなおば様に、わたしは小箱を卓に置いた。
「万が一のために少し残しておきました」
フフと、驚くおば様に笑ってみせた。
「……あなたは……」
手癖が悪いとは言わないでくださいね。主人の間違いを正すのも配下の役目ですしね。
「このことを知っているのはわたしと奥様、そして、侍女長様だけです」
その秘密をどうするかはおば様が決めること。わたしたちはタダ、口を閉じるだけである。
「ハァ~。あなたも悪いことを考えるようになってしまったのね……」
悪いことって、まあ、悪いことか。主に黙ってやったんだから。
わたしはまだ未熟な侍女。身を挺して、なんてまだできないわ。
「簡易な封印はしているようね」
「この世界に、聖なる魔法はありませんが、死人からして光系、闇系、回復系は効果があるはずです」
一つ、いいですかと目で問うと、理解したおば様は頷いた。
手に回復系魔法を纏わせながら死者の石をつかむと、煙を吹き出した。
「大丈夫だとは思いますが、安全のために吸わないでくださいね」
たぶん、回復煙──傷を修復するときに出る血の水蒸気だとは思うけど、未知なものは吸わないほうがいいでしょうよ。
ハンカチを出して口と鼻を覆い、おば様と侍女長様もそれに倣った。
完全に消えたら窓と戸を開けて換気をする。
「……回復魔法が効果あり、ですね。となれば死人も回復魔法で排除できそうですね」
まだ二十個近くある。対応策が練れるくらいには充分な量でしょう。
「そうね。もし、他の敷地にもあったら国が動くでしょうしね」
あ、そうか。ここだけに死者の石をばら蒔くはずがないか。他にもと考えるのは当然よね。
……タダ、ばら蒔けるほどの量になると秘密結社との繋がりは太く、計画が壮大ってことになるけどね……。
「こんなものを持っていたくないけど、収納魔法で仕舞っておくしかないわね」
魔法陣を描き、箱を異次元に仕舞った。
「シャーリー。あなたのことだから残りはないでしょうが、念のため、もう一度探してみてちょうだい」
「畏まりました。動きやすい服に着替えて隅々まで探してみます」
一応、侍女長様を見ると、やりなさいとばかりに小さく頷いた。
二人に一礼して部屋を出て自分の部屋へと向かった。
「……うん。確かにわたしは悪い娘よね……」
卓の上に置いていた死者の石をハンカチで包み、スカートの収納ポケットへと仕舞った。
おば様たちには申し訳ないけど、わたしも死者の石には興味がある。密かに調べさせていただきますわ。オホホ。
動きやすい服へと着替え、残りがあるかを探しに庭へと向かった。