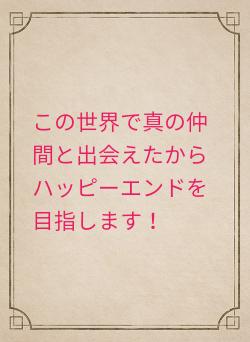ミア──お嬢様が蕾の会へお戻りになり、わたしの侍女生活に戻った。
と言ってもわたしに与えられた仕事は館の見回りだけどね。
もちろん、館を警備する兵もいて、常に巡回している。わたしがしなくてもいいと思うのだけれど、兵や黒衣がいても館に呪いを仕掛けられた。
侍女長様より庭も調べなさいと指示を出され、こうして見回りをしているのだ。
「ご苦労様です」
兵士さんたちに挨拶しながら庭を見回っていると、なにか不自然な石が落ちていた。
いきなり触るのは危険なので、枝で石を突っついてみる。
「……水晶、かしら……?」
無色透明な水晶など珍しくはないけど、館の庭に敷き詰められる石ではないと思う。
他にも探すと、結構な量の水晶が庭にあった。
「……理由はわからないけど、排除してたほうがいいわね……」
触るのはなにか危険なような感じがしたので、ゴミを拾う挟み板と取っ手のついた桶を借りてきて庭にある水晶を回収した。
「意外とあったわね」
集めたら二十キロ(異次元屋で買った体重計を使ってるから単位があちらになるのです)近くはあり、百個は超えていたわ。
「なにをなさっているので?」
桶に集めた水晶を見詰めていたら、若い兵士の男性に声をかけられてしまった。
まあ、侍女が桶の中を見詰めていたら不審がるわよね。
「いえ、なにか怪しい石があったので集めたのですが、どこに捨てようか考えてました」
穴を掘って埋めるのもなにか不味いような気がする。やはりどこかに捨ててくるしかないでしょうね。
「あ、怪しい石ですか?」
「わたしもなんの石かはわからないのですが、どうも危険な感じがするんですよね。あ、触らないでくださいね」
魔法的力は感じないけど、世の中には呪い石と言うものがある。まあ、誰かの呪いが籠められているとかではなく、体に悪い力が出ているのよ。
その力は目で見ることはできず、感じることもできない。特殊な方法じゃないと調べることもできないのよね。
「そ、そんなに危険なものなんですか!?」
「いえ、緊急性があるようなものではありません。ただ、触らないほうがいいのでは? と言ったくらいだと思います」
たぶん、触ってもすぐには反応しないでしょうけど、触らなくて済むなら触らないほうがいいでしょうね。
「す、すぐに隊長を呼んできます!」
と、若い兵士さんがどこかへと駆けていってしまいました。わたしも侍女長様を呼びたいんですが……。
生憎と侍女がくるような場所でもなく、下女もいないので、兵士さんを待つことにした。
しばらくして隊長さんと思われる方を連れて戻ってきた。
「危険な石があったのは本当ですか!?」
「どう危険かを説明するのは難しいですが、庭に置いておくのは止めたほうがいいものですね」
そんな説明で理解はしてくれないでしょう。わたしだって勘で言ってるんだからね。
「お、お待ちください。アルジャード様を呼んで参ります」
なにやら話が大きくなっていく。
「──なにがあった!?」
なんの説明もなく、いや、わたしが関係しているからか、アルジャードが慌ててやってきた。大変ね……。
「姫──ではなく、シャルロット、なにがあった?」
わたしのことは暗黙の了解になっているのでしょうけど、周りには建前を見せなくちゃならないんだから大変よね。
「庭に怪しい石があったので回収しました。ただ、どこに捨てるか悩んでいます」
「わかった。ロイヤード。第三種警戒体制を取れ。侯爵様にはわたしから伝える。ナターシャ。シャルロットについていろ」
アルジャードの指揮により兵士たちが慌ただしく動き出し、わたしは兵士の詰所みたいなところに連れていかれてしまった。
わたしにはどうすることもできずに佇むだけ。挟み板と桶を持っているわたし。周りから見たらさぞかし滑稽でしょうね……。
「シャルロット!」
と、侍女長様まできてしまった。
「お騒がせして申し訳ありません」
不本意ではあるけど、騒がしくしてしまったことには謝罪して起きましょう。
「いえ、いいのよ。わたしが指示したことですからね」
ただ、こうなることは予想できなかったとばかりに眉間にシワを作っていた。あとでマッサージしてあげましょう。将来、あなたのせいでシワが増えたわ、とか言われたくないしね。
「シャーリー!」
今度はおば様が現れた。こんなところにくるような身分ではないのにね。
「どう言うことなの?」
アルジャードにした説明をおば様にもした。今の段階でなんとも言えないからね。
「シャーリーでも知らないものなのね?」
「はい。知らないものです」
人よりは知識がある自負はあるけど、この世界のすべてを知っているわけじゃない。それどころか知らないことのほうが多いでしょうね。
「証拠として残せておける?」
「道具があれば一つくらいなら」
あまり残しておくのはお勧めできないけど、おば様の命令ならやるしかないわね。
「では、一つだけ封印して残してちょうだい。他はロブと相談しましょう」
と言うことで、おば様の命令で動き出した。
と言ってもわたしに与えられた仕事は館の見回りだけどね。
もちろん、館を警備する兵もいて、常に巡回している。わたしがしなくてもいいと思うのだけれど、兵や黒衣がいても館に呪いを仕掛けられた。
侍女長様より庭も調べなさいと指示を出され、こうして見回りをしているのだ。
「ご苦労様です」
兵士さんたちに挨拶しながら庭を見回っていると、なにか不自然な石が落ちていた。
いきなり触るのは危険なので、枝で石を突っついてみる。
「……水晶、かしら……?」
無色透明な水晶など珍しくはないけど、館の庭に敷き詰められる石ではないと思う。
他にも探すと、結構な量の水晶が庭にあった。
「……理由はわからないけど、排除してたほうがいいわね……」
触るのはなにか危険なような感じがしたので、ゴミを拾う挟み板と取っ手のついた桶を借りてきて庭にある水晶を回収した。
「意外とあったわね」
集めたら二十キロ(異次元屋で買った体重計を使ってるから単位があちらになるのです)近くはあり、百個は超えていたわ。
「なにをなさっているので?」
桶に集めた水晶を見詰めていたら、若い兵士の男性に声をかけられてしまった。
まあ、侍女が桶の中を見詰めていたら不審がるわよね。
「いえ、なにか怪しい石があったので集めたのですが、どこに捨てようか考えてました」
穴を掘って埋めるのもなにか不味いような気がする。やはりどこかに捨ててくるしかないでしょうね。
「あ、怪しい石ですか?」
「わたしもなんの石かはわからないのですが、どうも危険な感じがするんですよね。あ、触らないでくださいね」
魔法的力は感じないけど、世の中には呪い石と言うものがある。まあ、誰かの呪いが籠められているとかではなく、体に悪い力が出ているのよ。
その力は目で見ることはできず、感じることもできない。特殊な方法じゃないと調べることもできないのよね。
「そ、そんなに危険なものなんですか!?」
「いえ、緊急性があるようなものではありません。ただ、触らないほうがいいのでは? と言ったくらいだと思います」
たぶん、触ってもすぐには反応しないでしょうけど、触らなくて済むなら触らないほうがいいでしょうね。
「す、すぐに隊長を呼んできます!」
と、若い兵士さんがどこかへと駆けていってしまいました。わたしも侍女長様を呼びたいんですが……。
生憎と侍女がくるような場所でもなく、下女もいないので、兵士さんを待つことにした。
しばらくして隊長さんと思われる方を連れて戻ってきた。
「危険な石があったのは本当ですか!?」
「どう危険かを説明するのは難しいですが、庭に置いておくのは止めたほうがいいものですね」
そんな説明で理解はしてくれないでしょう。わたしだって勘で言ってるんだからね。
「お、お待ちください。アルジャード様を呼んで参ります」
なにやら話が大きくなっていく。
「──なにがあった!?」
なんの説明もなく、いや、わたしが関係しているからか、アルジャードが慌ててやってきた。大変ね……。
「姫──ではなく、シャルロット、なにがあった?」
わたしのことは暗黙の了解になっているのでしょうけど、周りには建前を見せなくちゃならないんだから大変よね。
「庭に怪しい石があったので回収しました。ただ、どこに捨てるか悩んでいます」
「わかった。ロイヤード。第三種警戒体制を取れ。侯爵様にはわたしから伝える。ナターシャ。シャルロットについていろ」
アルジャードの指揮により兵士たちが慌ただしく動き出し、わたしは兵士の詰所みたいなところに連れていかれてしまった。
わたしにはどうすることもできずに佇むだけ。挟み板と桶を持っているわたし。周りから見たらさぞかし滑稽でしょうね……。
「シャルロット!」
と、侍女長様まできてしまった。
「お騒がせして申し訳ありません」
不本意ではあるけど、騒がしくしてしまったことには謝罪して起きましょう。
「いえ、いいのよ。わたしが指示したことですからね」
ただ、こうなることは予想できなかったとばかりに眉間にシワを作っていた。あとでマッサージしてあげましょう。将来、あなたのせいでシワが増えたわ、とか言われたくないしね。
「シャーリー!」
今度はおば様が現れた。こんなところにくるような身分ではないのにね。
「どう言うことなの?」
アルジャードにした説明をおば様にもした。今の段階でなんとも言えないからね。
「シャーリーでも知らないものなのね?」
「はい。知らないものです」
人よりは知識がある自負はあるけど、この世界のすべてを知っているわけじゃない。それどころか知らないことのほうが多いでしょうね。
「証拠として残せておける?」
「道具があれば一つくらいなら」
あまり残しておくのはお勧めできないけど、おば様の命令ならやるしかないわね。
「では、一つだけ封印して残してちょうだい。他はロブと相談しましょう」
と言うことで、おば様の命令で動き出した。