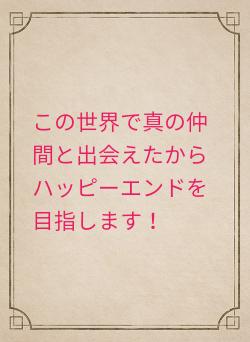──ドンドン!
「はひっ!?」
なにかの音にびっくりしてベッドから飛び起きた。
え? あ? へ? な、なんなの??
「いつまで寝てんだ! 延長料払ってもらうぞ!」
寝て? 延長料? ──あ! そうだった。わたし、宿屋に泊まったんだったわ!
「すっ、すみません。すぐに出ます!」
いけないいけない。疲れてたとは言え、油断しすぎたわ。城の外は危険だから油断するなとおばあ様が口酸っぱく言ってたじゃないのよ!
下着姿のまま眠ったので、すぐに異次元屋で買った服を着て靴を穿く。腰にホルスターベルトを回し、魔銃を入れる。
顔を洗いたいし髪も纏めたいけど、延長料のお金がないので鞄をつかんでそのまま部屋を出た。
「すみませんでした!」
宿屋の方に謝罪して外に出た。ふぅ~。
「さて。どうしましょうかね?」
おば様のところにいくのは決定──あっ、おば様に連絡しなくちゃならないか。
スマホを出しておば様に手紙を書く。
──侍女のお話、お受けします。ただ、問題があって一月くらいかかります。って。
おば様は侯爵夫人で王宮の奥を管理する人でもあるため、結構忙しいらしい。なので、通話するのは止めて手紙で報告したのだ。
なんて気遣いも無駄だったようで、すぐにおば様から通話が入った。暇なのかしら?
「はい。シャーリーです」
「シャーリー! どう言うことなの!」
スマホからおば様の金切り声。侯爵夫人にはあるまじき行為ですよ……。
「問題ってなんなの!?」
昨日のことを説明する。
……説明すると、これまでにない激動の一日だったと痛感させられるわね……。
「はぁ~。リンシャーじゃなにを言っても無駄ね」
おば様もリンシャーとは長い付き合いだ。文句を言うだけ無駄と知っている。
「さすがにわたしの力もサンビレス王国には届かないわ。なんとかカルビラス王国まで向かいなさい。アイドウス辺境伯には手紙を出しておくから」
「はい。ありがとうございます」
カルビラス王国の重鎮とは言え、辺境伯まで繋がりがあるんだ。さすがです。
「あなたなら大丈夫だとは思うけど、厄介事には首を突っ込まず、騒ぎを起こさず、大人しく来なさいね」
まるでわたしがもめ事を起こす前提のような口振りに聞こえるのですが……。
「他国ではどうしようもないけど、なにかあればカルビラス王国ザンバドリ侯爵の親族か侯爵家の侍女と名乗りなさい。多少なりとも信用はされるから」
「名乗って、大丈夫なんですか?」
貴族で名は命そのもの。親族でもないのに軽々しく名乗っていいものではない、と言うくらい貴族社会に疎いわたしでも知っていることだわ。
「ライラの娘はわたしの娘も同然。ザンバドリ侯爵があなたを全力で庇護するわ」
わたしも世間知らずの小娘ではない。おば様が心から言ってることもわかるし、打算があるのもわかる。わたしにはそれだけの価値があるのだから。
「ありがとうございます、おば様」
強かになれ。おばあ様がよく言っていた。
人は一人では生きられない。人の世界で生きるなら人を利用することも学べと。まあ、利用する者にはちゃんと利を与えるのも忘れるなとも言われてるけどね。
「お礼なんていいのよ。時間があるときでいいから連絡はちゃんとしてね」
「はい。一人のときに」
あ、今は路地裏に入って通話してます。あと、魔法で隠蔽してます。
「本当に気をつけてね」
「はい。ではまた」
と、長くなりそうだからこちらから通話を切った。
スマホをスカートのポケットに仕舞い、隠蔽を消して路地裏から出た。
「まずは朝食にしましょうか」
鞄から異次元屋特製のサンドイッチと飲み物を取り出した。
「うん。美味しい」
食べ歩きは行儀が悪いけど、食堂に入れるお金もなければ場所も知らないのだからごめん遊ばせ、である。
「オレンジジュースも美味しい」
こちらの世界の何百年も先をいった世界。果物一つ取ってもこちらの世界の果物と全然違う。いけないと思いつつも美味しさや品質に負けてあちらの世界のものを使っちゃうのよね。
お腹が満ちれば気持ちも落ち着く。周りにも目が向けれるようになった。
「……昨日も思ったけど、冒険者の町なのね……」
時間帯的に冒険者は仕事に出かけて姿は見えないけど、冒険者相手の露店が多かった。
「今から朝食なんだ」
露店の店主さんらがパンなどを食べてる姿がよく見られた。
町を回って情報収集していると、商店街っぽいところに出た。
「へ~。大きな店もあるんだ」
ここは、町の人を相手にしているようで、武器や防具をしてない人が多く、人の往来も多かった。
「すみません。少しよろしいでしょうか?」
往来する人の中から穏やかそうで、上品そうな中年男性に声をかけた。
「はい。どうかしましたか、お嬢さん?」
突然のことに警戒はしましたが、わたしの身なりと口調にすぐに口元を緩めた。
「買取りしてくださるお店を探しているのですが、お心当たりがあればお教えていただけませんでしょうか? 初めての町で困っておりますの」
なるべく上品そうな口調で困ったように尋ねた。女は演技ができなければいけないと、おば様に仕える侍女長さんに教えられました。
「買取りですか?」
「はい。恥ずかしながら旅費が心ともなくなりまして、指輪を売って足しにしようかと思いまして」
右手に嵌めている指輪を男性に見せた。
「……もしかして、魔法の指輪、ですか……?」
おや。一目見てわかるとか魔法師かしら? そんな風には見えないけど……。
「はい。水の指輪です」
指輪からチョロチョロと水を出して見せた。
これは、花壇に水をあげるための指輪で、大したものではない。けど、腐っても魔法の指輪。それなりに売れる、はず。
「それをお売りになると?」
「はい。旅費にできるものがないので」
ハンカチでは食事代くらいにしかならないだろうからね。
「では、我が商会で買取らせていただきます」
……はい?
「はひっ!?」
なにかの音にびっくりしてベッドから飛び起きた。
え? あ? へ? な、なんなの??
「いつまで寝てんだ! 延長料払ってもらうぞ!」
寝て? 延長料? ──あ! そうだった。わたし、宿屋に泊まったんだったわ!
「すっ、すみません。すぐに出ます!」
いけないいけない。疲れてたとは言え、油断しすぎたわ。城の外は危険だから油断するなとおばあ様が口酸っぱく言ってたじゃないのよ!
下着姿のまま眠ったので、すぐに異次元屋で買った服を着て靴を穿く。腰にホルスターベルトを回し、魔銃を入れる。
顔を洗いたいし髪も纏めたいけど、延長料のお金がないので鞄をつかんでそのまま部屋を出た。
「すみませんでした!」
宿屋の方に謝罪して外に出た。ふぅ~。
「さて。どうしましょうかね?」
おば様のところにいくのは決定──あっ、おば様に連絡しなくちゃならないか。
スマホを出しておば様に手紙を書く。
──侍女のお話、お受けします。ただ、問題があって一月くらいかかります。って。
おば様は侯爵夫人で王宮の奥を管理する人でもあるため、結構忙しいらしい。なので、通話するのは止めて手紙で報告したのだ。
なんて気遣いも無駄だったようで、すぐにおば様から通話が入った。暇なのかしら?
「はい。シャーリーです」
「シャーリー! どう言うことなの!」
スマホからおば様の金切り声。侯爵夫人にはあるまじき行為ですよ……。
「問題ってなんなの!?」
昨日のことを説明する。
……説明すると、これまでにない激動の一日だったと痛感させられるわね……。
「はぁ~。リンシャーじゃなにを言っても無駄ね」
おば様もリンシャーとは長い付き合いだ。文句を言うだけ無駄と知っている。
「さすがにわたしの力もサンビレス王国には届かないわ。なんとかカルビラス王国まで向かいなさい。アイドウス辺境伯には手紙を出しておくから」
「はい。ありがとうございます」
カルビラス王国の重鎮とは言え、辺境伯まで繋がりがあるんだ。さすがです。
「あなたなら大丈夫だとは思うけど、厄介事には首を突っ込まず、騒ぎを起こさず、大人しく来なさいね」
まるでわたしがもめ事を起こす前提のような口振りに聞こえるのですが……。
「他国ではどうしようもないけど、なにかあればカルビラス王国ザンバドリ侯爵の親族か侯爵家の侍女と名乗りなさい。多少なりとも信用はされるから」
「名乗って、大丈夫なんですか?」
貴族で名は命そのもの。親族でもないのに軽々しく名乗っていいものではない、と言うくらい貴族社会に疎いわたしでも知っていることだわ。
「ライラの娘はわたしの娘も同然。ザンバドリ侯爵があなたを全力で庇護するわ」
わたしも世間知らずの小娘ではない。おば様が心から言ってることもわかるし、打算があるのもわかる。わたしにはそれだけの価値があるのだから。
「ありがとうございます、おば様」
強かになれ。おばあ様がよく言っていた。
人は一人では生きられない。人の世界で生きるなら人を利用することも学べと。まあ、利用する者にはちゃんと利を与えるのも忘れるなとも言われてるけどね。
「お礼なんていいのよ。時間があるときでいいから連絡はちゃんとしてね」
「はい。一人のときに」
あ、今は路地裏に入って通話してます。あと、魔法で隠蔽してます。
「本当に気をつけてね」
「はい。ではまた」
と、長くなりそうだからこちらから通話を切った。
スマホをスカートのポケットに仕舞い、隠蔽を消して路地裏から出た。
「まずは朝食にしましょうか」
鞄から異次元屋特製のサンドイッチと飲み物を取り出した。
「うん。美味しい」
食べ歩きは行儀が悪いけど、食堂に入れるお金もなければ場所も知らないのだからごめん遊ばせ、である。
「オレンジジュースも美味しい」
こちらの世界の何百年も先をいった世界。果物一つ取ってもこちらの世界の果物と全然違う。いけないと思いつつも美味しさや品質に負けてあちらの世界のものを使っちゃうのよね。
お腹が満ちれば気持ちも落ち着く。周りにも目が向けれるようになった。
「……昨日も思ったけど、冒険者の町なのね……」
時間帯的に冒険者は仕事に出かけて姿は見えないけど、冒険者相手の露店が多かった。
「今から朝食なんだ」
露店の店主さんらがパンなどを食べてる姿がよく見られた。
町を回って情報収集していると、商店街っぽいところに出た。
「へ~。大きな店もあるんだ」
ここは、町の人を相手にしているようで、武器や防具をしてない人が多く、人の往来も多かった。
「すみません。少しよろしいでしょうか?」
往来する人の中から穏やかそうで、上品そうな中年男性に声をかけた。
「はい。どうかしましたか、お嬢さん?」
突然のことに警戒はしましたが、わたしの身なりと口調にすぐに口元を緩めた。
「買取りしてくださるお店を探しているのですが、お心当たりがあればお教えていただけませんでしょうか? 初めての町で困っておりますの」
なるべく上品そうな口調で困ったように尋ねた。女は演技ができなければいけないと、おば様に仕える侍女長さんに教えられました。
「買取りですか?」
「はい。恥ずかしながら旅費が心ともなくなりまして、指輪を売って足しにしようかと思いまして」
右手に嵌めている指輪を男性に見せた。
「……もしかして、魔法の指輪、ですか……?」
おや。一目見てわかるとか魔法師かしら? そんな風には見えないけど……。
「はい。水の指輪です」
指輪からチョロチョロと水を出して見せた。
これは、花壇に水をあげるための指輪で、大したものではない。けど、腐っても魔法の指輪。それなりに売れる、はず。
「それをお売りになると?」
「はい。旅費にできるものがないので」
ハンカチでは食事代くらいにしかならないだろうからね。
「では、我が商会で買取らせていただきます」
……はい?