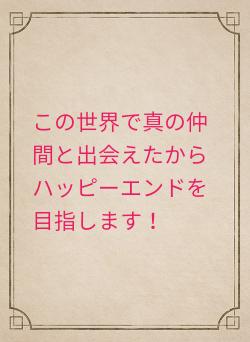明日からわたしは、シャルロット・マルディック男爵の娘でザンバドリ侯爵家の侍女だ。
割り当てられた部屋でそう気合いを入れた。
本来侍女は四人部屋らしいけど、ザンバドリ侯爵家でわたしの存在は特別であり、腫れ物のような立場だ(不本意だけど)。一般侍女に相手させるには酷と一人部屋を与えられてしまったのだ。
侍女の部屋か? と首を傾げてしまいそうな広さだが、割り当てられた部屋であり、これから過ごす部屋。快適にしようと異次元屋へと向かった。
「いらっしゃいませ。シャーリー様」
「ごきげんよう、リュージさん」
「今日はなにをお求めですか?」
「はい。部屋に置くものをいただきますね」
鏡やブラシ、小物類、部屋着、裁縫道具、タオルやバスタオル、暮らすとなると結構な物が必要になるのね。十二万ポイントも使ってしまったわ。
「そうだ。冷たいものを入れておく物ってありますか? こちらは、これから夏になるので飲み物を冷たくしておきたいので」
異世界には電気の力で動く冷蔵庫があり、夏でも冷たいものが食べられるそうだ。
まあ、こちらには魔法があるから似たようなことはできるけど、入れ物は真似できない。木箱だとすぐ冷気が逃げちゃうのよね。
「はい。クーラーボックスがありますよ。どのくらいのものがよろしいですか? 大きいものだと人が入るくらいまでありますよ」
人が入るくらいまであるの? 冷蔵庫があるのになにをそんなに入れるのかしらね?
「ワインが十本入るくらいのをお願いします」
その大きさなら部屋に置いても邪魔にならないでしょう。
「では、手頃なものを見繕っておきますね」
「はい。お願いします」
今日はこのくらいでいいでしょう。
異次元屋から出て、買ったものを召喚する。
「これがクーラーボックスか。なんの材質で作られてるのかしらね?」
文明が百年も離れていると技術がまったく違うと聞いたことあるけど、五百年くらい離れるともはや未知なるものよね。さっぱりだわ。
まあ、使う分には問題ないのだから構わないわね。
「これでアイスが作れるわ」
異次元屋で買うと高いしね。作れるものは作らないと。
買ったものを整理していると、ドアが叩かれた。
もう就寝の時間なのに誰かしら?
「ごめんなさい、シャーリー」
ドアを開けたらおば様──奥様がいた。
「どうかしましたか?」
「いえ、様子を見に来ただけよ。部屋はどう?」
中に入って来て部屋を見回した。
もう主従関係。主が侍女の部屋に来るなんてあり得ないんだけどな~。
廊下を見れば侍女長様がいて、わたしと目が合うとサッと視線を逸らされた。
……わたしは見てません。知りません、ってことですね。わかりました……。
「なに、この箱は? 異次元屋から買ったの?」
もしかして、異次元屋にいったことを見越してやって来たのかしら?
「クーラーボックスと言うもので冷たいものを入れるときように買ったんです。アイスを作ろうと思って」
「アイス、いいわね。食べたいわ。異次元屋のは高いからね」
まあ、おば様の魔力では一日千ポイント使えるかどうか。三百ポイントもするアイスは気軽には買えないわね。
「アイス、いいわよね」
期待の籠った目を向けられる。
「……食べます?」
「あら、いいの? ごめんなさいね、せがんだみたいで」
みたい、じゃなくておもいっきりせがんでましたけどね。
しょうがないのでスマホを出して異次元屋から通販する。
「ハールゲーツ、久しぶりだわ~」
アイスの中でも高級品で、わたしでも二日に一回しか食べれないものだ。
「美味しいわ~」
そりゃあ、他人の魔力で食べるアイスは美味しいでしょうよ。
「魔石があれば毎日食べれますよ。こちらの魔石は人気があるみたいですから」
「そうなの?」
「はい。結構なポイントになりました」
わたしも給金がもらえたらガルズ様のところに買いにいかないとね。
「魔石か。タダールン商会で扱ってたかしら?」
ハールゲーツを持ったまま部屋を出ていってしまった。
「行動力のあるおば様だこと」
それに付き合わされる周りはご苦労様。って、明日からわたしもその一人になるんだけどね。
「さて。明日から仕事だし、お風呂入って寝よう」
お湯玉を作り、今日の疲れを洗い流した。
割り当てられた部屋でそう気合いを入れた。
本来侍女は四人部屋らしいけど、ザンバドリ侯爵家でわたしの存在は特別であり、腫れ物のような立場だ(不本意だけど)。一般侍女に相手させるには酷と一人部屋を与えられてしまったのだ。
侍女の部屋か? と首を傾げてしまいそうな広さだが、割り当てられた部屋であり、これから過ごす部屋。快適にしようと異次元屋へと向かった。
「いらっしゃいませ。シャーリー様」
「ごきげんよう、リュージさん」
「今日はなにをお求めですか?」
「はい。部屋に置くものをいただきますね」
鏡やブラシ、小物類、部屋着、裁縫道具、タオルやバスタオル、暮らすとなると結構な物が必要になるのね。十二万ポイントも使ってしまったわ。
「そうだ。冷たいものを入れておく物ってありますか? こちらは、これから夏になるので飲み物を冷たくしておきたいので」
異世界には電気の力で動く冷蔵庫があり、夏でも冷たいものが食べられるそうだ。
まあ、こちらには魔法があるから似たようなことはできるけど、入れ物は真似できない。木箱だとすぐ冷気が逃げちゃうのよね。
「はい。クーラーボックスがありますよ。どのくらいのものがよろしいですか? 大きいものだと人が入るくらいまでありますよ」
人が入るくらいまであるの? 冷蔵庫があるのになにをそんなに入れるのかしらね?
「ワインが十本入るくらいのをお願いします」
その大きさなら部屋に置いても邪魔にならないでしょう。
「では、手頃なものを見繕っておきますね」
「はい。お願いします」
今日はこのくらいでいいでしょう。
異次元屋から出て、買ったものを召喚する。
「これがクーラーボックスか。なんの材質で作られてるのかしらね?」
文明が百年も離れていると技術がまったく違うと聞いたことあるけど、五百年くらい離れるともはや未知なるものよね。さっぱりだわ。
まあ、使う分には問題ないのだから構わないわね。
「これでアイスが作れるわ」
異次元屋で買うと高いしね。作れるものは作らないと。
買ったものを整理していると、ドアが叩かれた。
もう就寝の時間なのに誰かしら?
「ごめんなさい、シャーリー」
ドアを開けたらおば様──奥様がいた。
「どうかしましたか?」
「いえ、様子を見に来ただけよ。部屋はどう?」
中に入って来て部屋を見回した。
もう主従関係。主が侍女の部屋に来るなんてあり得ないんだけどな~。
廊下を見れば侍女長様がいて、わたしと目が合うとサッと視線を逸らされた。
……わたしは見てません。知りません、ってことですね。わかりました……。
「なに、この箱は? 異次元屋から買ったの?」
もしかして、異次元屋にいったことを見越してやって来たのかしら?
「クーラーボックスと言うもので冷たいものを入れるときように買ったんです。アイスを作ろうと思って」
「アイス、いいわね。食べたいわ。異次元屋のは高いからね」
まあ、おば様の魔力では一日千ポイント使えるかどうか。三百ポイントもするアイスは気軽には買えないわね。
「アイス、いいわよね」
期待の籠った目を向けられる。
「……食べます?」
「あら、いいの? ごめんなさいね、せがんだみたいで」
みたい、じゃなくておもいっきりせがんでましたけどね。
しょうがないのでスマホを出して異次元屋から通販する。
「ハールゲーツ、久しぶりだわ~」
アイスの中でも高級品で、わたしでも二日に一回しか食べれないものだ。
「美味しいわ~」
そりゃあ、他人の魔力で食べるアイスは美味しいでしょうよ。
「魔石があれば毎日食べれますよ。こちらの魔石は人気があるみたいですから」
「そうなの?」
「はい。結構なポイントになりました」
わたしも給金がもらえたらガルズ様のところに買いにいかないとね。
「魔石か。タダールン商会で扱ってたかしら?」
ハールゲーツを持ったまま部屋を出ていってしまった。
「行動力のあるおば様だこと」
それに付き合わされる周りはご苦労様。って、明日からわたしもその一人になるんだけどね。
「さて。明日から仕事だし、お風呂入って寝よう」
お湯玉を作り、今日の疲れを洗い流した。