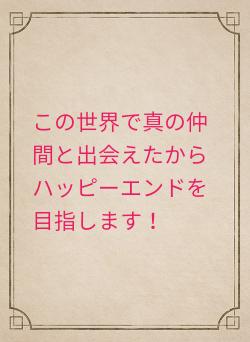旦那様が連れて来たシャルロット・マルディックと言う女性は不思議でしかなかった。
本人によれば隣国にも名を轟かすザンバドリ侯爵家の侍女で、男爵令嬢だと言う。なんの証拠も身分証もないのに旦那様は真実だと思っているようだ。
侍女として二十年務めているわたしの目からは侍女にも男爵令嬢にも見えなかった。では、どう見えたかと言われると……わからないとしか答えらない。これまで見たこともない女性なのだ。
貴族並みの教養と洗練された動き。庶民では身につかない態度。身分の高い男性を前にしても動じない肝の太さ。なによりわからないのはその清潔さだ。
わたしも奥様に仕え、髪や肌、衣服には心血を注いで来たが、旅の間にはどうしても限界がある。湯浴みも三日に一回。肌着は毎日洗いはしてるがドレスは晴れている日にしかできない。旅がこれほど大変だとは思わなかった。
シャーリー嬢ほどではないが、清浄の魔法を使える侍女はいるものの効果は小さく、一日二回が精々だ。とてもシャーリー嬢のような清潔さは保てない。いったいどうしているのか聞きたいくらいだ。
旦那様や奥様たちが集まり、シャーリー嬢は客人として扱うことが決まり、わたしが世話役としてつくようになりました。
部屋へと案内し、部下に見張りに立たせると、その部下がシャーリー嬢が買い物に出たいと伝えて来た。
すぐに旦那様や奥様に伝え、急いで護衛を組み、ライヤード商会に人を走らせ、わたしも同行してライヤード商会へと向かった。
「ナタリー。シャーリー嬢をよく観察しなさい」
と、出かける前に奥様から指令を受けてしまった。趣味嗜好からなにを買うか、事細かく見るようにと。
責任重大であるが、わたしもよくわからない者を旦那様や奥様に近づけることはしたくない。わたしを高く評価してくれ、重用してくれる主人のためにもシャーリー嬢を探ることを決意する。
ライヤード商会へは歩きでいくことになった。出発準備が忙しく、男爵家の方々も手伝ってくださってたので人を出せなかったのだ。
普通の男爵令嬢なら歩きなどしないし、言われたら取り止めるものだが、シャーリー嬢にそう告げたら「大変ですね」と言われて、歩きでいくことをなんら不思議ではないと思っている様子だった。
女一人で旅をしている言ってたので、歩きにはなんの抵抗もないのでしょうが、そもそも女一人で、それも侍女が国外に出ることが意味不明だわ。
ライヤード商会へは兵士一人が先頭に立ち、シャーリー嬢の横にルイドフィー様。その後ろにわたし。最後尾に兵士三人だ。
向かう途中のシャーリー嬢は自然体だ。戦いのことはわかりませんが、女一人で旅をしているのだから戦う術はあるのでしょう。今日は服が違うが、武器を持っていた。おそらく、魔法も使えるのでしょう。回復魔法が尋常ではないし。
それに、ルイドフィー様に一切目を向けないのが驚きだ。
ルイドフィー様は家柄的にも騎士としての働きでも女性受けするのに、さらに顔も女性受けする作りだ。わたしもあと十歳若ければ恋に落ちていただろう。
なのに、シャーリー嬢は無視だ。いや、それは言いすぎね。興味がないと言うべきか。美醜の区別ができないのかと疑うくらいだ。
ルイドフィー様はそんなシャーリー嬢に興味を示しているようだが、シャーリー嬢は軽く流している──どころか眼中にないって感じね。
……色男もシャーリー嬢の前では形無しね……。
ライヤード商会に着き、部屋に案内されたが、シャーリー嬢は背後に控えるわたしたちに眉をしかめた。
まあ、そうだろう。わたしも同じことされたら戸惑うばかり。恐れ多いと逃げ出すところだわ。
こちらがなにも言わないので、仕方がなく席に座った。堂々と。
……男爵令嬢かはわからないけど、上の立場として立ったことがあるなは間違いないわね……。
地方の支店長とは言え、ギャレーはライヤード商会でも重要な地。ダイグン男爵と繋がりを持つために優秀な者が送られる。
こちらがシャーリー嬢を理解するようにサナリオ様もシャーリー嬢を理解するために商会の商品を出して来た。
いろいろある中でシャーリー嬢が興味を示したのが魔石だ。
魔石は魔道具を動かすものに必要であるが、使うためには魔道具に合わせるために加工が必要で、そのままでは使えないし、魔石単体では安いものだ。
なのに、シャーリー嬢は買えるだけ買った。量の多さに驚いたものの、すべてを受け取った。
なにに使うかはわからないが、ライヤード商会としてはシャーリー嬢との繋がりが得たことに喜んでいることでしょう。聖印が刻まれた指輪を持つ者なんだから。
サナリオ様が呼んだ商人が来て、シャーリー嬢は気に入ったものを次々と買っていく。
それ、旅に必要なのか? と思うが、シャーリー嬢の趣味嗜好を探るには助かるが、ただ、謎が深まるばかりである。
……いったい何者なのよ……!?
何度叫びそうになったかわからないが、バンドゥーリ子爵家の侍女としての誇りを強く持ってシャーリー嬢の観察に集中した。
本人によれば隣国にも名を轟かすザンバドリ侯爵家の侍女で、男爵令嬢だと言う。なんの証拠も身分証もないのに旦那様は真実だと思っているようだ。
侍女として二十年務めているわたしの目からは侍女にも男爵令嬢にも見えなかった。では、どう見えたかと言われると……わからないとしか答えらない。これまで見たこともない女性なのだ。
貴族並みの教養と洗練された動き。庶民では身につかない態度。身分の高い男性を前にしても動じない肝の太さ。なによりわからないのはその清潔さだ。
わたしも奥様に仕え、髪や肌、衣服には心血を注いで来たが、旅の間にはどうしても限界がある。湯浴みも三日に一回。肌着は毎日洗いはしてるがドレスは晴れている日にしかできない。旅がこれほど大変だとは思わなかった。
シャーリー嬢ほどではないが、清浄の魔法を使える侍女はいるものの効果は小さく、一日二回が精々だ。とてもシャーリー嬢のような清潔さは保てない。いったいどうしているのか聞きたいくらいだ。
旦那様や奥様たちが集まり、シャーリー嬢は客人として扱うことが決まり、わたしが世話役としてつくようになりました。
部屋へと案内し、部下に見張りに立たせると、その部下がシャーリー嬢が買い物に出たいと伝えて来た。
すぐに旦那様や奥様に伝え、急いで護衛を組み、ライヤード商会に人を走らせ、わたしも同行してライヤード商会へと向かった。
「ナタリー。シャーリー嬢をよく観察しなさい」
と、出かける前に奥様から指令を受けてしまった。趣味嗜好からなにを買うか、事細かく見るようにと。
責任重大であるが、わたしもよくわからない者を旦那様や奥様に近づけることはしたくない。わたしを高く評価してくれ、重用してくれる主人のためにもシャーリー嬢を探ることを決意する。
ライヤード商会へは歩きでいくことになった。出発準備が忙しく、男爵家の方々も手伝ってくださってたので人を出せなかったのだ。
普通の男爵令嬢なら歩きなどしないし、言われたら取り止めるものだが、シャーリー嬢にそう告げたら「大変ですね」と言われて、歩きでいくことをなんら不思議ではないと思っている様子だった。
女一人で旅をしている言ってたので、歩きにはなんの抵抗もないのでしょうが、そもそも女一人で、それも侍女が国外に出ることが意味不明だわ。
ライヤード商会へは兵士一人が先頭に立ち、シャーリー嬢の横にルイドフィー様。その後ろにわたし。最後尾に兵士三人だ。
向かう途中のシャーリー嬢は自然体だ。戦いのことはわかりませんが、女一人で旅をしているのだから戦う術はあるのでしょう。今日は服が違うが、武器を持っていた。おそらく、魔法も使えるのでしょう。回復魔法が尋常ではないし。
それに、ルイドフィー様に一切目を向けないのが驚きだ。
ルイドフィー様は家柄的にも騎士としての働きでも女性受けするのに、さらに顔も女性受けする作りだ。わたしもあと十歳若ければ恋に落ちていただろう。
なのに、シャーリー嬢は無視だ。いや、それは言いすぎね。興味がないと言うべきか。美醜の区別ができないのかと疑うくらいだ。
ルイドフィー様はそんなシャーリー嬢に興味を示しているようだが、シャーリー嬢は軽く流している──どころか眼中にないって感じね。
……色男もシャーリー嬢の前では形無しね……。
ライヤード商会に着き、部屋に案内されたが、シャーリー嬢は背後に控えるわたしたちに眉をしかめた。
まあ、そうだろう。わたしも同じことされたら戸惑うばかり。恐れ多いと逃げ出すところだわ。
こちらがなにも言わないので、仕方がなく席に座った。堂々と。
……男爵令嬢かはわからないけど、上の立場として立ったことがあるなは間違いないわね……。
地方の支店長とは言え、ギャレーはライヤード商会でも重要な地。ダイグン男爵と繋がりを持つために優秀な者が送られる。
こちらがシャーリー嬢を理解するようにサナリオ様もシャーリー嬢を理解するために商会の商品を出して来た。
いろいろある中でシャーリー嬢が興味を示したのが魔石だ。
魔石は魔道具を動かすものに必要であるが、使うためには魔道具に合わせるために加工が必要で、そのままでは使えないし、魔石単体では安いものだ。
なのに、シャーリー嬢は買えるだけ買った。量の多さに驚いたものの、すべてを受け取った。
なにに使うかはわからないが、ライヤード商会としてはシャーリー嬢との繋がりが得たことに喜んでいることでしょう。聖印が刻まれた指輪を持つ者なんだから。
サナリオ様が呼んだ商人が来て、シャーリー嬢は気に入ったものを次々と買っていく。
それ、旅に必要なのか? と思うが、シャーリー嬢の趣味嗜好を探るには助かるが、ただ、謎が深まるばかりである。
……いったい何者なのよ……!?
何度叫びそうになったかわからないが、バンドゥーリ子爵家の侍女としての誇りを強く持ってシャーリー嬢の観察に集中した。