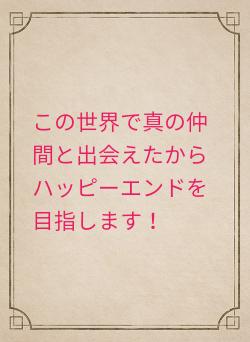侍女。
それは、高貴な人の身の回りを整える職業。
って言う知識くらいしかないわ。
なぜそんなことを言ったかと言えば、それは半年前まで遡る必要があるわね。
わたしに両親はおらず、祖母と一緒に山の中で暮らしていた。
山の中と言っても獣を狩ったり、田畑を耕したりはしてないわよ。立派な城で暮らしていたわ。
城のことはその内話すこととして、祖母が大往生でこの世を去ってしまった。
大好きな祖母が死んだことは凄く悲しかったけど、満足そうな死に顔を見てたらいつまでも悲しんでられないと気持ちを切り替えたわ。
十八年間、万能で魔法の才能があった祖母からいろんなことを叩き込まれ、便利な道具をたくさん引き継いだ。一人で生きていくには充分な力があるとね。
祖母──おばあ様は昔、国の重鎮で知り合いがたくさんいた、らしいけど、わたしが知るのはおば様──アリューナ様だけ。連絡が取れるのもアリューナ様だけだ。
スマホと言う魔法具でアリューナ様におばあ様の死を告げた。
おばあ様が死んだことに大変悲しみ、八日後に城へとやって来た。
「シャーリー。よく頑張ったわね」
会うなりわたしを抱き締め、励ましてくれた。
涙はもう出なくなっていたが、温もりを感じてしまったら自然と涙が溢れてしまった。
おば様の胸で大泣きしてしまったのち、おばあ様の部屋へと案内する。
「……眠っているみたいね……」
本来なら腐敗しているところだが、城にかけられた魔法によりおばあ様の体は死んだときのまま。知らない人が見れば寝ているとしか見えないでしょうね。
「おばあ様と城は繋がってますから、城が朽ちるまではこのままです」
この城は特別で特殊だ。国の軍隊が攻め込んで来ようが落ちることはない。小さい頃、黒竜が襲って来たことがあったけど、城を囲む結界に触れた瞬間に骨まで崩れ果てたわ。
「……そう。お葬式も上げることもできないのね……」
あ、お葬式か。考えもしなかったわ。でも、おばあ様はこの城を気に入っていたし、このままのほうがいいのかしら?
「……ミディ。あなたがいないのが寂しいわ……」
おばあ様とおば様は、親子のような関係だったり姉妹のような関係だったりもした。わたしも母のように慕ったり、姉のように慕ったりもした。家族と言ってもいいでしょう。
おばあ様の手に触れるおば様の横に移り、おば様の手の上にわたしの手を重ねた。
「シャーリー。これからどうするの?」
いつまでもおばあ様のもとにいてもおばあ様は生き返らない。十二分に冥福を祈ってから場所を移し、おば様にお茶を出したらそんなことを言われた。ん? どうするのとは?
「ここで一人で暮らすの?」
「……そう、ですね。いくあてもありませんから……」
生まれた場所は違うけど、記憶がある頃からここに住んでいるし、親戚もいない。誰かを頼る必要はないわ。
「わたしのところに来ない? まだ若いのだから外の世界を勉強しなさい。ミディもここに住むまでは外で暮らしてたんだから」
おばあ様は若い頃、いろんなところを旅をしたり王家に仕えたりしたとは聞いている。
「……外の世界……」
別に引きこもりではないので、おばあ様と一緒に旅行にいったことは何度でもある。町でお買い物をしたことだってあるわ。
けど、それは知っているとはなにか違う。ううん。まったく知らないと言っても過言ではないわ。
「すぐに答えを出すことはないわ。あなたの心が落ち着いてからでいいのだからね」
「……はい……」
外の世界に興味がない、と言えばウソになる。
ここでの暮らしは快適でなに不自由はない。ここほど住みやすい場所はないでしょう。けど、一人で暮らしていかなくちゃならないと考えたら、わたしは一人に堪えられるだろうか? 楽しいだろうか?
「なんなら働くのもいいかもね」
「働く?」
「そうよ。侯爵夫人のわたしが言うのもおかしなものだけど、働くのも社会勉強よ。ここでは経験できないことを経験できる。友達だってできるわ。もちろん、嫌なことや辛いこともある。気にくわない人と接しなくちゃならないときもあるわ。でもね、それが人よ。人の世界で生きると言うこと。孤独では決して味わえない人生なの」
「…………」
「あなたはまだ若い。この先、何十年と続くわ。しかも、あなたはミディの血を濃く受け継いでいる。このままここに閉じ籠れるとは思わない。きっと厄介事に巻き込まれるわ。ミディがそうだったから」
その話も聞いている。これは強大な力を持つ者の運命だと。
「あなた、マルディック男爵令嬢の身分はまだ持ってるわよね?」
おばあ様の孫では騒ぎになると、偽りの身分をいくつか持たされている。
確か、マルディック男爵令嬢の身分は、おば様のところに遊びにいったときのものだったはず。
「はい。消してはいないと思います」
まあ、どうやったかはおばあ様しか知らないけどね。
「なら、慣れるまでわたしのところで侍女をやってみない? わたしも近くにいてくれると安心だし、下働きなら町にもいけるわよ」
心が決まったら連絡してと、おば様は帰っていった。
「……どうしよう……」
いや、心は外の世界に傾いているけど、不安な気持ちが心を惑わせてい心が決まらないのだ。
「落ち着け、わたし。おば様は急ぐことはないって言ってたんだからゆっくり考えなさい」
両頬を叩き、しばらくやってなかった城の掃除に取りかかった。
それは、高貴な人の身の回りを整える職業。
って言う知識くらいしかないわ。
なぜそんなことを言ったかと言えば、それは半年前まで遡る必要があるわね。
わたしに両親はおらず、祖母と一緒に山の中で暮らしていた。
山の中と言っても獣を狩ったり、田畑を耕したりはしてないわよ。立派な城で暮らしていたわ。
城のことはその内話すこととして、祖母が大往生でこの世を去ってしまった。
大好きな祖母が死んだことは凄く悲しかったけど、満足そうな死に顔を見てたらいつまでも悲しんでられないと気持ちを切り替えたわ。
十八年間、万能で魔法の才能があった祖母からいろんなことを叩き込まれ、便利な道具をたくさん引き継いだ。一人で生きていくには充分な力があるとね。
祖母──おばあ様は昔、国の重鎮で知り合いがたくさんいた、らしいけど、わたしが知るのはおば様──アリューナ様だけ。連絡が取れるのもアリューナ様だけだ。
スマホと言う魔法具でアリューナ様におばあ様の死を告げた。
おばあ様が死んだことに大変悲しみ、八日後に城へとやって来た。
「シャーリー。よく頑張ったわね」
会うなりわたしを抱き締め、励ましてくれた。
涙はもう出なくなっていたが、温もりを感じてしまったら自然と涙が溢れてしまった。
おば様の胸で大泣きしてしまったのち、おばあ様の部屋へと案内する。
「……眠っているみたいね……」
本来なら腐敗しているところだが、城にかけられた魔法によりおばあ様の体は死んだときのまま。知らない人が見れば寝ているとしか見えないでしょうね。
「おばあ様と城は繋がってますから、城が朽ちるまではこのままです」
この城は特別で特殊だ。国の軍隊が攻め込んで来ようが落ちることはない。小さい頃、黒竜が襲って来たことがあったけど、城を囲む結界に触れた瞬間に骨まで崩れ果てたわ。
「……そう。お葬式も上げることもできないのね……」
あ、お葬式か。考えもしなかったわ。でも、おばあ様はこの城を気に入っていたし、このままのほうがいいのかしら?
「……ミディ。あなたがいないのが寂しいわ……」
おばあ様とおば様は、親子のような関係だったり姉妹のような関係だったりもした。わたしも母のように慕ったり、姉のように慕ったりもした。家族と言ってもいいでしょう。
おばあ様の手に触れるおば様の横に移り、おば様の手の上にわたしの手を重ねた。
「シャーリー。これからどうするの?」
いつまでもおばあ様のもとにいてもおばあ様は生き返らない。十二分に冥福を祈ってから場所を移し、おば様にお茶を出したらそんなことを言われた。ん? どうするのとは?
「ここで一人で暮らすの?」
「……そう、ですね。いくあてもありませんから……」
生まれた場所は違うけど、記憶がある頃からここに住んでいるし、親戚もいない。誰かを頼る必要はないわ。
「わたしのところに来ない? まだ若いのだから外の世界を勉強しなさい。ミディもここに住むまでは外で暮らしてたんだから」
おばあ様は若い頃、いろんなところを旅をしたり王家に仕えたりしたとは聞いている。
「……外の世界……」
別に引きこもりではないので、おばあ様と一緒に旅行にいったことは何度でもある。町でお買い物をしたことだってあるわ。
けど、それは知っているとはなにか違う。ううん。まったく知らないと言っても過言ではないわ。
「すぐに答えを出すことはないわ。あなたの心が落ち着いてからでいいのだからね」
「……はい……」
外の世界に興味がない、と言えばウソになる。
ここでの暮らしは快適でなに不自由はない。ここほど住みやすい場所はないでしょう。けど、一人で暮らしていかなくちゃならないと考えたら、わたしは一人に堪えられるだろうか? 楽しいだろうか?
「なんなら働くのもいいかもね」
「働く?」
「そうよ。侯爵夫人のわたしが言うのもおかしなものだけど、働くのも社会勉強よ。ここでは経験できないことを経験できる。友達だってできるわ。もちろん、嫌なことや辛いこともある。気にくわない人と接しなくちゃならないときもあるわ。でもね、それが人よ。人の世界で生きると言うこと。孤独では決して味わえない人生なの」
「…………」
「あなたはまだ若い。この先、何十年と続くわ。しかも、あなたはミディの血を濃く受け継いでいる。このままここに閉じ籠れるとは思わない。きっと厄介事に巻き込まれるわ。ミディがそうだったから」
その話も聞いている。これは強大な力を持つ者の運命だと。
「あなた、マルディック男爵令嬢の身分はまだ持ってるわよね?」
おばあ様の孫では騒ぎになると、偽りの身分をいくつか持たされている。
確か、マルディック男爵令嬢の身分は、おば様のところに遊びにいったときのものだったはず。
「はい。消してはいないと思います」
まあ、どうやったかはおばあ様しか知らないけどね。
「なら、慣れるまでわたしのところで侍女をやってみない? わたしも近くにいてくれると安心だし、下働きなら町にもいけるわよ」
心が決まったら連絡してと、おば様は帰っていった。
「……どうしよう……」
いや、心は外の世界に傾いているけど、不安な気持ちが心を惑わせてい心が決まらないのだ。
「落ち着け、わたし。おば様は急ぐことはないって言ってたんだからゆっくり考えなさい」
両頬を叩き、しばらくやってなかった城の掃除に取りかかった。